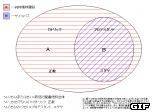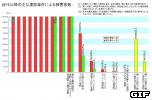俺によるこのありがたい仕置きによって、新旧約信仰者が辟易したり、四書五経への忌避感を抱いたりしたのなら、
それはそれでこちらの目論みにもかなっている。新旧約聖書やその信仰者であるおまえらを嫌悪している人間こそは
今の世界に溢れ返っており、おまえらが俺を嫌悪する分量すらその比ではないが、おまえらはあまりにも鈍感であるため、
少しもその嫌悪者たちの存在にすら気づこうともしない。それならばまず、おまえらを嫌悪している人々が、おまえらの
身勝手な振舞いによってどのような嫌悪感を抱いているのかを擬似的にでも思い知らせるのが得策であり、今おまえらが
俺や四書五経に対して抱いている嫌悪感こそは、おまえらや新旧約聖書を嫌悪している人々の嫌悪感とも同等のものだ。
こうして、教示を望んでいるわけでもない相手に布教を押し付けることは、新旧約聖書中では認められていることだとしても
四書五経中では忌まれていることであり、あくまで「去る者は追わず、来る者は拒まず(孟子)」というのが、真に正しい
教育姿勢でもある。自分たちからの一方的なドグマの押し付けなどが、それだけでも多大なる不快感を催させるものであり、
元来絶無であるべきもの。今の俺は、そのドグマの押し付けを罪とも思わないおまえらに合わせて、あえてその愚行をも
冒しているが、全くなければそれに越したこともないこと。俺も押し付けをやめて、おまえらも押し付けをやめる。
それでこそ人々にものを教える姿勢として過ちなく正しい姿であり、誰からも嫌悪を抱かれることもない。
「子貢、告朔の餼羊を去らんと欲す。子曰く、賜や、爾は其の羊を愛む、我は其の禮を愛む」
「子貢が、魯の国での告朔の礼が形骸化し、羊を生贄にする慣習ばかりしか残されていないのを見て、
その生贄もやめさせようとした。それを見て孔子は言われた。『賜(子貢)よ、おまえはその羊を惜しがって
いるようだが、私はその羊の生贄すらなくなることで、礼の風習が完全に途絶えてしまうことのほうが惜しい』」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・八佾第三・一七より)
返信する