サイズが 480KB を超えています。500KB を超えると書きこめなくなるよ。
聖書 Part8
▼ページ最下部
世に「聖書」として扱われている書物が、単なる学術書や文芸書などと決定的に異なっている点は、
「一人の人間が、全身全霊をかけてその実践に努めていくことができる書物」である点だといえる。
「○○聖書」という様な、何らかの目的を明確に冠した聖書であれば、その目的を達成するために、
一人以上の人間がその書物の内容を、全身全霊をかけて実践していくことが推奨される。もちろん
「聖書」扱いでない書物にも、それだけの度量を潜在している書物はいくらでもあるが、ことに
「○○聖書」といった名称がすでに定着しているほどの書物であれば、その○○を達成する上での
参考書としての定番扱いがされているわけで、「聖書」としての評価がすでに固まっているからには、
全身全霊をかけてその内容の実践に努めていくだけの価値があると、太鼓判を捺されているのでもある。
中でも、人間社会全体の規範を司るほどもの壮大さを兼ね備えている聖書であれば、それを聖典と
した一大学派や教派が形成されて、国家社会の運営を先導するほどもの勢力を擁する場合がある。
儒学の聖典である四書五経や、仏教の聖典である仏典、ヒンズー教の聖典であるヴェーダや
ウパニシャッド、イスラム教の聖典であるコーランなどが、そのような聖書の典型例であるといえる。
キリスト教とユダヤ教の聖典である新旧約聖書も、そのような、国家社会をも先導するだけの試みに
用いられては来たものの、如何せんその記述内容が粗悪に過ぎるために、それだけでは全く世の中を
司ることができず、仏教や拝火教の教義を拝借したり、無宗教の学術による補強を試みたりすることで
何とか聖書圏も保たれてきたが、それでももういい加減、崩壊が免れ得ない時期に差しかかっている。
世の中全体を司る理念となるだけの価値があって、それにより数百年以上もの泰平社会を実現していく
ことができるほどの聖書というのも、決してただ一つしか存在しなかったりするわけではない。ただ、
世の中を最低限度保っていくことが可能となる単独的な聖書の中でも、特に代表として挙げやすいのが、
儒学の正典である四書五経なので、だからこそ、世界で最も「標準的な聖書」として扱うにも相応しい
書物としての四書五経を、聖書全般を論ずる上での主要題材ともしつつ、ここで論じていくものとする。
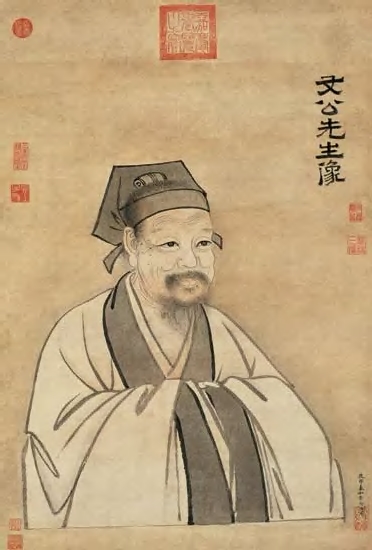
「一人の人間が、全身全霊をかけてその実践に努めていくことができる書物」である点だといえる。
「○○聖書」という様な、何らかの目的を明確に冠した聖書であれば、その目的を達成するために、
一人以上の人間がその書物の内容を、全身全霊をかけて実践していくことが推奨される。もちろん
「聖書」扱いでない書物にも、それだけの度量を潜在している書物はいくらでもあるが、ことに
「○○聖書」といった名称がすでに定着しているほどの書物であれば、その○○を達成する上での
参考書としての定番扱いがされているわけで、「聖書」としての評価がすでに固まっているからには、
全身全霊をかけてその内容の実践に努めていくだけの価値があると、太鼓判を捺されているのでもある。
中でも、人間社会全体の規範を司るほどもの壮大さを兼ね備えている聖書であれば、それを聖典と
した一大学派や教派が形成されて、国家社会の運営を先導するほどもの勢力を擁する場合がある。
儒学の聖典である四書五経や、仏教の聖典である仏典、ヒンズー教の聖典であるヴェーダや
ウパニシャッド、イスラム教の聖典であるコーランなどが、そのような聖書の典型例であるといえる。
キリスト教とユダヤ教の聖典である新旧約聖書も、そのような、国家社会をも先導するだけの試みに
用いられては来たものの、如何せんその記述内容が粗悪に過ぎるために、それだけでは全く世の中を
司ることができず、仏教や拝火教の教義を拝借したり、無宗教の学術による補強を試みたりすることで
何とか聖書圏も保たれてきたが、それでももういい加減、崩壊が免れ得ない時期に差しかかっている。
世の中全体を司る理念となるだけの価値があって、それにより数百年以上もの泰平社会を実現していく
ことができるほどの聖書というのも、決してただ一つしか存在しなかったりするわけではない。ただ、
世の中を最低限度保っていくことが可能となる単独的な聖書の中でも、特に代表として挙げやすいのが、
儒学の正典である四書五経なので、だからこそ、世界で最も「標準的な聖書」として扱うにも相応しい
書物としての四書五経を、聖書全般を論ずる上での主要題材ともしつつ、ここで論じていくものとする。
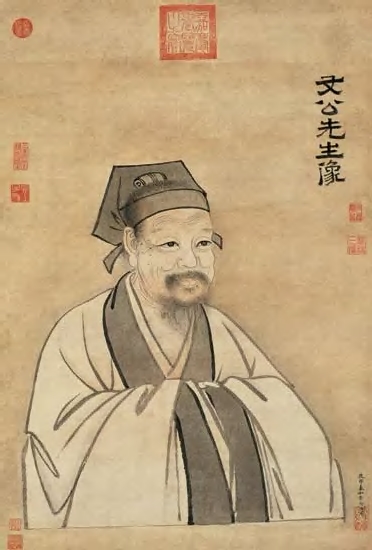
メモ書きの用途もあるから、長いのは我慢品。
※ スレ画は「世界標準の聖書」四書五経の代表的な推薦者、文公朱熹先生の肖像。
権力犯罪聖書(新旧約聖書)で「神の愛」とされるものは、結局のところ「自己愛」である。
心を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして主なる神を愛せば愛すほど、自己愛が高まる。
究極的には、それは「自己愛性人格障害」ともなり、理想の自己と現実の自己の乖離からなる
自殺衝動の因子ともなる。「神の愛」だけが信条となる旧約信者=ユダヤ教徒などには確かに、
自己愛性人格障害や自殺衝動に悩まされる人間が多い。(ウィトゲンシュタインやその家族など)
一方で、新旧約両方の犯罪聖書を信仰対象とするキリスト教徒の場合は、神の愛を騙る自己愛と共に、
近隣の人間ばかりに対する偏愛を美化した「隣人愛」が信条とされる。それにより、自己愛の独走
からなる自殺衝動も緩和され、見た目にもそれほどナルシシズムに塗れているようには見えなくなる。
ただ、キリスト教徒の隣人愛もまた、自己愛性人格障害にすらなり兼ねないほどもの自己愛を糧と
しているため、ただ「隣人を愛する」というばかりの志向性などにはない、多大なる濁念を伴っている。
武経七書「三略」で、有効な戦略の一つとして挙げられている「釈遠謀近(遠きを捨てて近きを謀る)」は、
隣人愛に相当するものを活用することで、仁愛の通用しない乱世を切り抜ける手段ともなっている。
ただ、そこには自己愛を隣人にも振り向けるような濁念は伴っていないし、当該の釈遠謀近を含む
兵法全般が、仁政のような正当な目的を達成するための手段と見なされているために、
決して「釈遠謀近であり続ける」ことなどが推奨されてはいないのである。
権力犯罪聖書(新旧約聖書)で「神の愛」とされるものは、結局のところ「自己愛」である。
心を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして主なる神を愛せば愛すほど、自己愛が高まる。
究極的には、それは「自己愛性人格障害」ともなり、理想の自己と現実の自己の乖離からなる
自殺衝動の因子ともなる。「神の愛」だけが信条となる旧約信者=ユダヤ教徒などには確かに、
自己愛性人格障害や自殺衝動に悩まされる人間が多い。(ウィトゲンシュタインやその家族など)
一方で、新旧約両方の犯罪聖書を信仰対象とするキリスト教徒の場合は、神の愛を騙る自己愛と共に、
近隣の人間ばかりに対する偏愛を美化した「隣人愛」が信条とされる。それにより、自己愛の独走
からなる自殺衝動も緩和され、見た目にもそれほどナルシシズムに塗れているようには見えなくなる。
ただ、キリスト教徒の隣人愛もまた、自己愛性人格障害にすらなり兼ねないほどもの自己愛を糧と
しているため、ただ「隣人を愛する」というばかりの志向性などにはない、多大なる濁念を伴っている。
武経七書「三略」で、有効な戦略の一つとして挙げられている「釈遠謀近(遠きを捨てて近きを謀る)」は、
隣人愛に相当するものを活用することで、仁愛の通用しない乱世を切り抜ける手段ともなっている。
ただ、そこには自己愛を隣人にも振り向けるような濁念は伴っていないし、当該の釈遠謀近を含む
兵法全般が、仁政のような正当な目的を達成するための手段と見なされているために、
決して「釈遠謀近であり続ける」ことなどが推奨されてはいないのである。
 然るに、キリスト教の隣人愛などは、信者が常日ごろから必ず釈遠謀近であり続けることを強要する。
然るに、キリスト教の隣人愛などは、信者が常日ごろから必ず釈遠謀近であり続けることを強要する。 人格障害級の自己愛を転化した隣人愛でもあるものだから、兵法として釈遠謀近を用いる場合などと
違って、自由に隣人愛を保ったり捨てたりすることもできない。すでに万人を利して我が利ともする
仁政が実現できる段になっても、隣人愛によって薄汚い利権の吹き溜まりを保ち続けていたりもしかねない
ものだから、そこに「単なる兵法」として釈遠謀近を用いる場合のような、道義性が備わらないのである。
兵法は、六道十界論でいえば「修羅道」に相当するが、修羅道は人道や天道のために善用される場合と、
餓鬼道や畜生道が到来する過程で否応なく共にもたらされる場合とがある。軍師や武士が、天子良民のために
兵法や武術を駆使することは前者に当たる一方、カルト信者が自己愛や隣人愛を必要もなく嗜好することで、
万人の万人に対する闘争状態を共にもたらしてしまったりすることは後者に当たる。だから修羅道は人道や
天道と共に「三善趣」と呼ばれたり、地獄道や餓鬼道や畜生道と共に「四悪趣」と呼ばれたりもする。
「釈遠謀近」を含む兵法全般が、善悪の彼岸を司る諸刃の剣であり、仁政などのために善用される場合と、
自己愛や隣人愛と共に悪用される場合とがあるので、そこに断悪修善を付与することもまた重要なことだといえる。
「仁と智とは、周公も未だ之れを尽くさざりき」
「仁(万人を労わる心)とそのための良知とは、
(周朝の名臣の)周公ですら完全に尽くせたなどということはない。
(自分個人や隣人のためだけに心や知力を尽くすことには限りがある。そのため
『やり尽くしてしまったこと』からなる虚無感によっての自殺衝動にかられたりもするが、
万人を労わる仁政のために心や知力を尽くすことには、全く限りがない。そのためどこまで尽くそうとしても、
やり尽くしてしまったが故の虚無感などにはかられず、どこまでも心身の壮健さを増していくことができる)」
(世界標準の聖書——通称四書五経——孟子・公孫丑章句下・九より)
結局、「世界最劣等の聖書」新旧約聖書の問題点をあげつらって、
そこに「世界標準の聖書」四書五経からの模範的な回答を提出することが主要題材となっている。
そしてそれは、「聖書」という存在を論ずる上での、
最も標準的な議論ともなっている。これと比べれば、
仏典やコーランを引き合いにすることすら、付録的な議論だといえる。
そこに「世界標準の聖書」四書五経からの模範的な回答を提出することが主要題材となっている。
そしてそれは、「聖書」という存在を論ずる上での、
最も標準的な議論ともなっている。これと比べれば、
仏典やコーランを引き合いにすることすら、付録的な議論だといえる。
たとえば、今の米軍などは、ちっとも怖くない。
世界最強かつ最大の軍備を誇り、人類を数十回滅亡させることが可能なほどもの
核兵器を保有している米軍といえども、その活動に何らの正当性が見られず、
蒙昧な文民の権力者に振り回されての無軌道な侵略行為や、その侵略先での
自暴自棄な虐殺行為や、捕虜の虐待や少女暴行などにばかり及んでいる以上は、
まさに「刃物を持ったキ○○イ」もいいところで、キ○○イとしての警戒対象に
なることはあっても、偉大な存在として畏怖されるに値するようなことは全くない。
軍兵が畏怖されるに値する存在となる条件は、ただただ強大な威力を蓄えたり
することではなく、その武力の活用に道義的な正当性が伴っていることでこそある。
徒法で人々を振り回す旧約邪神エホバなどを「万軍の主」扱いなどとして、
その存在性を至上とした活動に及んだりしたなら、どんなに屈強な大軍といえども、
一切畏敬されるに値する存在などではなくなる。一方で、社会を乱世から泰平
へと着実に導いていく、仁徳と兵法の文武両道などを活動理念としたならば、
これはもう、ただの一人や二人程度の兵隊さんといえども、怖れ畏まる他はない。
洋学上の政治学で、政治体制としての軍事独裁制が問題視され、そのような事態を招く
ことを防止するための理念としての「文民統制(シビリアン・コントロール)」が謳われて
来てもいるが、当然そこには、「文武両道」という理念に対する配慮が全く抜け落ちている。
全く文化的な理念を持たない暴力主義者が、軍事力によって国の政権までをも掌握するような
事態が起きたとすれば、まさにお先真っ暗となる。ならずとも、共産主義や独裁主義のような粗悪な
理念しか持たないままに、軍事力によって政権が奪取されることもまた、由々しき事態となる。
世界最強かつ最大の軍備を誇り、人類を数十回滅亡させることが可能なほどもの
核兵器を保有している米軍といえども、その活動に何らの正当性が見られず、
蒙昧な文民の権力者に振り回されての無軌道な侵略行為や、その侵略先での
自暴自棄な虐殺行為や、捕虜の虐待や少女暴行などにばかり及んでいる以上は、
まさに「刃物を持ったキ○○イ」もいいところで、キ○○イとしての警戒対象に
なることはあっても、偉大な存在として畏怖されるに値するようなことは全くない。
軍兵が畏怖されるに値する存在となる条件は、ただただ強大な威力を蓄えたり
することではなく、その武力の活用に道義的な正当性が伴っていることでこそある。
徒法で人々を振り回す旧約邪神エホバなどを「万軍の主」扱いなどとして、
その存在性を至上とした活動に及んだりしたなら、どんなに屈強な大軍といえども、
一切畏敬されるに値する存在などではなくなる。一方で、社会を乱世から泰平
へと着実に導いていく、仁徳と兵法の文武両道などを活動理念としたならば、
これはもう、ただの一人や二人程度の兵隊さんといえども、怖れ畏まる他はない。
洋学上の政治学で、政治体制としての軍事独裁制が問題視され、そのような事態を招く
ことを防止するための理念としての「文民統制(シビリアン・コントロール)」が謳われて
来てもいるが、当然そこには、「文武両道」という理念に対する配慮が全く抜け落ちている。
全く文化的な理念を持たない暴力主義者が、軍事力によって国の政権までをも掌握するような
事態が起きたとすれば、まさにお先真っ暗となる。ならずとも、共産主義や独裁主義のような粗悪な
理念しか持たないままに、軍事力によって政権が奪取されることもまた、由々しき事態となる。
 だから、文民統制が消去法的に選択されるしかないというのが洋学上の政治学の大体の結論だが、
だから、文民統制が消去法的に選択されるしかないというのが洋学上の政治学の大体の結論だが、 もちろん儒学道徳や仏法のような優良な理念によって世の中を司ることは、そこでは全く
念頭におかれていない。仁徳や仏法によって世の中を司るのであれば、たとえ軍事力によって
政権を奪取するのであろうとも、秦帝国の法家支配みたいな腐敗まみれの文民統治よりは
よっぽどマシな治世が期待されるというものである。しかし、洋学における文化上の最高理念は
どこまでも聖書信仰であり、その聖書信仰が仁徳や仏法に決定的に反する完全誤謬の塊である
ものだかから、仁徳や仏法を統治理念とすることなどは、始めから前提に入れようがないのである。
最高理念がどこまでも聖書信仰や洋学でしかあり得ない範囲で、軍事政権が立ち上げられるのは
確かにどうしようもないことで、それならまだ文民統制が敷かれたほうがマシだともいえる。
しかし、儒学や仏教までをも動員した、高等文化との文武両道による武家政権が樹立されたなら、
それこそ、粗悪な文化的理念しか持たない文民による統制などよりも、遥かに優れたものとなる。
そして、平安時代の公家統治のように、高等な文化に基づく文治が実現された時に、治世の優良さも
極まるが、乱世の熱狂も未だ冷め遣らぬ昨今、まだそこまでもの期待をするのは総計に過ぎるといえる。
「子、衛の霊公の無道なるを言う。康子曰く、夫れ是くの是くに、奚に而て喪わざる。孔子曰く、
仲叔圉は賓客を治め、祝鮀は宗廟を治め、王孫賈は軍旅を治む。夫れ是くの如くにして、奚に其れ喪わざる」
「先生は衛の霊公の政治が悪逆無道であることを指摘された。魯の家老の季康子は『どうしてそれで位を
失わずに済んだのでしょうか』と聞いた。孔先生は言われた。『仲叔圉のような名臣が外交を行い、祝鮀のような
名官が内務を取り仕切り、王孫賈のような名将が軍兵を統率していたから、位を追われることもなかったのです』
(無道な王君がどうにか軍力に助けられて体制を保つ例。万軍の主エホバも実情はこのようなものである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・憲問第十四・二〇)
勧善懲悪、断悪修善にかけて自由自在である者が、
「できないことは何もない」万能感に浸っているなどということは、まずない。
むしろ、自分には出来ないこと、善行にかけて決してやってはならないことのほうを
よく熟知して、入念な鍛造によって不純物を取り除き、鋭利に研ぎ澄ました名刀の刃先一筋
ほどにも「他に選択肢のない」一直線の範囲内だけでの、勧善懲悪や断悪修善をやり込めていく。
その能力に長ける者こそは、勧善懲悪や断悪修善にかけて自由自在でもあるのだから、とにかくできない
ことは何もなく、実際に何でもやってしまう自由自在などとは、決して相容れないものであることが分かる。
戦国時代、総合的には世界最大級の軍備を擁していた日本が、秀吉の野望からなる朝鮮出兵を
中途で取り止めにして後は、徳川幕府の下で外征を断絶し、260年にわたる内政の養生に徹した。
一方で、キリスト教圏ではカトリックだけでなく、プロテスタントまでもが力を付け始め、
スペインやポルトガルがすでに行っていた以上の世界侵略をも、イギリスやオランダなどが
試み始め、19世紀中盤にはほぼ全世界の主要地域を自分たちの征服下に置くまでに至った。
幕末の時点で、明らかに日本は欧米列強などと比べて、勢力の面で劣勢に立たされていた。
かつては世界最強の軍備すらをも誇っていたのが、自分たちからのあえての軍縮によって
その威力を大幅に萎縮させ、逆に世界を征服し尽くすほどもの威力を蓄えて来た欧米諸国と、
ほとんど無防備も同然の状態で、幕末には対峙することとなったのだった。
「できないことは何もない」万能感に浸っているなどということは、まずない。
むしろ、自分には出来ないこと、善行にかけて決してやってはならないことのほうを
よく熟知して、入念な鍛造によって不純物を取り除き、鋭利に研ぎ澄ました名刀の刃先一筋
ほどにも「他に選択肢のない」一直線の範囲内だけでの、勧善懲悪や断悪修善をやり込めていく。
その能力に長ける者こそは、勧善懲悪や断悪修善にかけて自由自在でもあるのだから、とにかくできない
ことは何もなく、実際に何でもやってしまう自由自在などとは、決して相容れないものであることが分かる。
戦国時代、総合的には世界最大級の軍備を擁していた日本が、秀吉の野望からなる朝鮮出兵を
中途で取り止めにして後は、徳川幕府の下で外征を断絶し、260年にわたる内政の養生に徹した。
一方で、キリスト教圏ではカトリックだけでなく、プロテスタントまでもが力を付け始め、
スペインやポルトガルがすでに行っていた以上の世界侵略をも、イギリスやオランダなどが
試み始め、19世紀中盤にはほぼ全世界の主要地域を自分たちの征服下に置くまでに至った。
幕末の時点で、明らかに日本は欧米列強などと比べて、勢力の面で劣勢に立たされていた。
かつては世界最強の軍備すらをも誇っていたのが、自分たちからのあえての軍縮によって
その威力を大幅に萎縮させ、逆に世界を征服し尽くすほどもの威力を蓄えて来た欧米諸国と、
ほとんど無防備も同然の状態で、幕末には対峙することとなったのだった。
それでも当時まだ、日本にはほぼ完璧といっていいほどの「正義」があった。朝鮮出兵の罪を犯した
豊臣家も滅ぼされて、徳川による鎖国政策が敷かれ、外界侵略による権力犯罪の咎を皆無にまで押し止めていた。
一方で、ルネサンスの頃までは、アレクサンドロス東征や十字軍遠征などの部分的な侵略行為に
止まっていた西洋社会が、ルネサンス、大航海時代以降には、まさに全世界にまで侵略の魔の手を
広げ尽くし、世界中を「あるよりもないほうがマシ」なほどの荒廃した文化文明に晒させて、
人類滅亡級の環境破壊の温床をももたらすこととなった。そうなったことで、西洋社会は「正義」を
完全に失った。瑣末な腕力、何でもアリの自由自在を求めつくした挙句に、自分たち自身が
真の勧善懲悪や断悪修善を一定以上に自由に行使する術を、完全に失ってしまったのである。
開国維新後には、日本も欧米のマネをして、大日本帝国としての覇権の奪取なども試みたから、相当に
自分たちの正義にも綻びが生じてしまったものの、江戸260年にわたる正義の堅持という実績は、未だに名誉な
ものであり、もしも維新後の乱心をことごとく反省し尽くして、江戸時代から完全にやり直すというのであれば、
腕力ばかりの貪りと引き換えに、正義を失い尽くした欧米諸国にも代わって、世界の先導者となるだけの
資格が、日本人には潜在的に備わっているといえる。今でも「明治時代あたりまでの日本人は偉かった」
というような認識が日本人の間でも通用しているが、当時すでに日本の政財界なども、裏では
欧米の金融資本勢力などとの結託をし始めていたので、そこにまで大義を認めることはできない。
明治という時代の闇とも真摯に向き合って、反省すべきものを反省してからの再起に臨むのであれば、
「何でもアリ」の自由自在と引き換えに、正義にかけての自由自在こそを蓄え続けてきた、江戸時代までの
日本人としての素養によって、正義の自由を失ってしまった欧米聖書圏をも、配下に置くことができるのである。
豊臣家も滅ぼされて、徳川による鎖国政策が敷かれ、外界侵略による権力犯罪の咎を皆無にまで押し止めていた。
一方で、ルネサンスの頃までは、アレクサンドロス東征や十字軍遠征などの部分的な侵略行為に
止まっていた西洋社会が、ルネサンス、大航海時代以降には、まさに全世界にまで侵略の魔の手を
広げ尽くし、世界中を「あるよりもないほうがマシ」なほどの荒廃した文化文明に晒させて、
人類滅亡級の環境破壊の温床をももたらすこととなった。そうなったことで、西洋社会は「正義」を
完全に失った。瑣末な腕力、何でもアリの自由自在を求めつくした挙句に、自分たち自身が
真の勧善懲悪や断悪修善を一定以上に自由に行使する術を、完全に失ってしまったのである。
開国維新後には、日本も欧米のマネをして、大日本帝国としての覇権の奪取なども試みたから、相当に
自分たちの正義にも綻びが生じてしまったものの、江戸260年にわたる正義の堅持という実績は、未だに名誉な
ものであり、もしも維新後の乱心をことごとく反省し尽くして、江戸時代から完全にやり直すというのであれば、
腕力ばかりの貪りと引き換えに、正義を失い尽くした欧米諸国にも代わって、世界の先導者となるだけの
資格が、日本人には潜在的に備わっているといえる。今でも「明治時代あたりまでの日本人は偉かった」
というような認識が日本人の間でも通用しているが、当時すでに日本の政財界なども、裏では
欧米の金融資本勢力などとの結託をし始めていたので、そこにまで大義を認めることはできない。
明治という時代の闇とも真摯に向き合って、反省すべきものを反省してからの再起に臨むのであれば、
「何でもアリ」の自由自在と引き換えに、正義にかけての自由自在こそを蓄え続けてきた、江戸時代までの
日本人としての素養によって、正義の自由を失ってしまった欧米聖書圏をも、配下に置くことができるのである。
「滕の文公問うて曰く、滕は小国なり。斉と楚のはざ間に於いて、斉に事えんか、楚に事えんか。
孟子対えて曰、是の謀は吾が能く及ぶ所に非ざるなり。已む無くんば、則ち一有り。斯の池を鑿ち、
斯の城を築き、民と与に之れを守り、死すとも民去らずんば、則と是れ可と為すなり」
「滕の文公が問うた。『我が滕は小国で、しかも斉と楚という大国に挟まれているのだが、
いったい斉に仕えればいいだろうか、楚に仕えたほうがいいだろうか』孟先生は答えられた。
『このはかりごとは私が答えられるものではありません。ただ、どうしてもと言われるのでしたら、
一計を案じてはおきましょう。この城の堀を広げ、城郭を増築し、民と共にこれを守るのです。
たとえ殺されようとも民が去らなければ、まあよいとした所でしょう』(道徳学の専門家である自分に対して、
合従連衡を是とする縦横家主義的な質問をしてきたため、孟子も『私が答えられる質問ではありません』と
明言し、滕文公に自らの徳性を磨くよう促すような返答だけをした。君子が『不可能は不可能』と断じた例)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・梁恵王章句下・一三)
孟子対えて曰、是の謀は吾が能く及ぶ所に非ざるなり。已む無くんば、則ち一有り。斯の池を鑿ち、
斯の城を築き、民と与に之れを守り、死すとも民去らずんば、則と是れ可と為すなり」
「滕の文公が問うた。『我が滕は小国で、しかも斉と楚という大国に挟まれているのだが、
いったい斉に仕えればいいだろうか、楚に仕えたほうがいいだろうか』孟先生は答えられた。
『このはかりごとは私が答えられるものではありません。ただ、どうしてもと言われるのでしたら、
一計を案じてはおきましょう。この城の堀を広げ、城郭を増築し、民と共にこれを守るのです。
たとえ殺されようとも民が去らなければ、まあよいとした所でしょう』(道徳学の専門家である自分に対して、
合従連衡を是とする縦横家主義的な質問をしてきたため、孟子も『私が答えられる質問ではありません』と
明言し、滕文公に自らの徳性を磨くよう促すような返答だけをした。君子が『不可能は不可能』と断じた例)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・梁恵王章句下・一三)
「強さ」というものが、すでにこの人間社会においては飽和状態にある。
何らの軌道性も持たない単なる力の強さは、核兵器による国際間の相互確証破壊体制の
確立によって完全な飽和状態に達した。たとえ北朝鮮のような小国といえども、
核爆弾と弾道ミサイルの保有が明らかである以上は、軍備にかけて世界最強である
アメリカといえども下手に手出しはできない。今の北朝鮮の核軍備にしろ、中国の空母にしろ、
何世代も昔の技術によって造られた粗末な代物ではあるにしろ、それでも最悪、人力での
「核特攻」にすら及んだなら、アメリカなどにも確実に甚大な被害をもたらせるわけで、
旧東側社会における命の扱いの粗末さも、それを妨げるどころか、後押しするものですらある。
核特攻なども含む、あらゆる事態を想定してみるならば、何らの道義性も伴わない、単なる
暴力の強大さによって人々が競い合う余地というのは、確かに完全に途絶えてしまったのである。
「強ければ上、弱ければ下」という判断基準が完全に無効化された現代において、
なお競争の基準にできるものがあるとすれば、それこそは「徳性の有無」であるといえる。
人々に仁政をも施せるほどの徳性の高さの持ち主ほど偉大で、かえって人々に危害をもたらす
ほどにも徳性の低い輩ほど賤しいという競争基準であれば、単なる腕力の強大さなどで
競い合う余地が絶たれたこれからの世の中においても、それなりに掲げていくことができる。
強さによる競争の余地が絶たれたから、さも人間は成長の余地が絶えたかのようにも言われる。
そのせいで、人々がある種の鬱屈に見舞われていたりもするが、これは、ただただ強さばかりを
貪ろうとする旧来の価値基準が未だ世の中に強要され続けているがために、「徳性の有無」という、
これからも競争の基準にして行ける判断基準のほうが、完全にひた隠されてしまっているからである。
何らの軌道性も持たない単なる力の強さは、核兵器による国際間の相互確証破壊体制の
確立によって完全な飽和状態に達した。たとえ北朝鮮のような小国といえども、
核爆弾と弾道ミサイルの保有が明らかである以上は、軍備にかけて世界最強である
アメリカといえども下手に手出しはできない。今の北朝鮮の核軍備にしろ、中国の空母にしろ、
何世代も昔の技術によって造られた粗末な代物ではあるにしろ、それでも最悪、人力での
「核特攻」にすら及んだなら、アメリカなどにも確実に甚大な被害をもたらせるわけで、
旧東側社会における命の扱いの粗末さも、それを妨げるどころか、後押しするものですらある。
核特攻なども含む、あらゆる事態を想定してみるならば、何らの道義性も伴わない、単なる
暴力の強大さによって人々が競い合う余地というのは、確かに完全に途絶えてしまったのである。
「強ければ上、弱ければ下」という判断基準が完全に無効化された現代において、
なお競争の基準にできるものがあるとすれば、それこそは「徳性の有無」であるといえる。
人々に仁政をも施せるほどの徳性の高さの持ち主ほど偉大で、かえって人々に危害をもたらす
ほどにも徳性の低い輩ほど賤しいという競争基準であれば、単なる腕力の強大さなどで
競い合う余地が絶たれたこれからの世の中においても、それなりに掲げていくことができる。
強さによる競争の余地が絶たれたから、さも人間は成長の余地が絶えたかのようにも言われる。
そのせいで、人々がある種の鬱屈に見舞われていたりもするが、これは、ただただ強さばかりを
貪ろうとする旧来の価値基準が未だ世の中に強要され続けているがために、「徳性の有無」という、
これからも競争の基準にして行ける判断基準のほうが、完全にひた隠されてしまっているからである。
高い徳性の持ち主が、より多くの人々からの支持を取り付けて、全面戦争とまでは行かない
平時の範囲内で、悪逆非道に走ろうとする連中を懲罰の対象とする、そういうところにまだ、
勇猛果敢な荒行の余地も残されている。ただ、そういうところでものを言う戦力はといえば、
ミサイルや戦車や戦闘機みたいな、最大級の兵器戦力よりもむしろ、悪人としての相手を
有効に懲罰することが可能となる、対人武器であるといえる。その理想形と呼べるのが、まさに
日本刀であり、日本刀と比べれば、槍や薙刀や弓矢ですら、平時の対人武器としては強大すぎる。
十分に強大さを控えた武器や武力と、それを相手に用いることに万全の道義性が備わることとが
相まって、言ってみれば、これからの時代における「強さ」になる。それは、ただただ腕力の
強大さを貪ってきたこれまでの時代の強さとは全く別個のものであり、今までの基準で蓄えてきた
強さが甚大であることなどが、これからの強さにそのまま応用できるなどということも決してない。
腕力の強大さと引き換えに道義性を失ってきたような連中は、かえって武装放棄して平民階級に
甘んじるなどしなければならなくなる。強さにそういったクリティカルな動向が伴い得ることを
あらかじめ見越していたのが東洋兵法でもあり、江戸幕府が全国に軍縮を敷いたことなどは、
完全に先の先の将来までをも見越した、確信的な兵術の一環であったことが確かである。
「強は此れ(孝)を強める者なり」
「親孝行に努める者こそは強くなる。(与えられる強さなどではなく、自ら培う強さである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・祭義第二十四より)
平時の範囲内で、悪逆非道に走ろうとする連中を懲罰の対象とする、そういうところにまだ、
勇猛果敢な荒行の余地も残されている。ただ、そういうところでものを言う戦力はといえば、
ミサイルや戦車や戦闘機みたいな、最大級の兵器戦力よりもむしろ、悪人としての相手を
有効に懲罰することが可能となる、対人武器であるといえる。その理想形と呼べるのが、まさに
日本刀であり、日本刀と比べれば、槍や薙刀や弓矢ですら、平時の対人武器としては強大すぎる。
十分に強大さを控えた武器や武力と、それを相手に用いることに万全の道義性が備わることとが
相まって、言ってみれば、これからの時代における「強さ」になる。それは、ただただ腕力の
強大さを貪ってきたこれまでの時代の強さとは全く別個のものであり、今までの基準で蓄えてきた
強さが甚大であることなどが、これからの強さにそのまま応用できるなどということも決してない。
腕力の強大さと引き換えに道義性を失ってきたような連中は、かえって武装放棄して平民階級に
甘んじるなどしなければならなくなる。強さにそういったクリティカルな動向が伴い得ることを
あらかじめ見越していたのが東洋兵法でもあり、江戸幕府が全国に軍縮を敷いたことなどは、
完全に先の先の将来までをも見越した、確信的な兵術の一環であったことが確かである。
「強は此れ(孝)を強める者なり」
「親孝行に努める者こそは強くなる。(与えられる強さなどではなく、自ら培う強さである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・祭義第二十四より)
聖書信仰級の邪信に取り込まれた時点で、人は「真の実」に対する尊重を失う。
真の実とは、端的に言えば五穀の実りであったり、子宝の実りであったりという、
人間にとって本当に「実」になる事物のことである。そしてそのような
真の実を尊重する教学である、儒学や神道などが「真実の教学」であるといえ、
また確信的に虚空の荘厳を凝らすことで、逆説的に真実の不虚さを
如実ならしめる、仏教などは「虚実自在の教学」であるといえる。
聖書信仰は、儒学や神道のような「真実の教学」でないのはもちろんのこと、
仏教のような「虚実自在の教学」でもない、「虚実転倒の邪教」である。
五穀や子宝の実りのような真の実は虚とし、金銭や財宝のような虚構を実とする。
人間にとってより実であるものを虚とし、どちらかといえば虚であるものを実とする、
虚実の転倒夢想を信者にけしかけるのが聖書信仰であり、それにより、家庭や農産を
ないがしろにしてまでの、個人的な富裕の貪りなどの実践をけしかけるのである。
確かに、実と虚というのは相反的な関係にあり、家庭円満や五穀豊穣に意義を
見出せる人間というのは、財物への貪りなどをあまり肥大化させたりもしない一方、
家庭や食に対して価値を見出せない者こそは、個人的に財物を貪ることにかけて
猛烈となったりもする。聖書信仰によって人工的に家庭や食に対する嫌悪を募らせて、
その反動によってこそ金銭欲などを増大させたユダヤ教徒やキリスト教徒の貪欲さたるや、
確かに異教徒などには決して見られないものであり、聖書信仰が絶やされたなら、
今の聖書信者ほどにも貪欲さを募らせたりする人間も、ほぼ皆無にまで立ち戻ることだろう。
真の実とは、端的に言えば五穀の実りであったり、子宝の実りであったりという、
人間にとって本当に「実」になる事物のことである。そしてそのような
真の実を尊重する教学である、儒学や神道などが「真実の教学」であるといえ、
また確信的に虚空の荘厳を凝らすことで、逆説的に真実の不虚さを
如実ならしめる、仏教などは「虚実自在の教学」であるといえる。
聖書信仰は、儒学や神道のような「真実の教学」でないのはもちろんのこと、
仏教のような「虚実自在の教学」でもない、「虚実転倒の邪教」である。
五穀や子宝の実りのような真の実は虚とし、金銭や財宝のような虚構を実とする。
人間にとってより実であるものを虚とし、どちらかといえば虚であるものを実とする、
虚実の転倒夢想を信者にけしかけるのが聖書信仰であり、それにより、家庭や農産を
ないがしろにしてまでの、個人的な富裕の貪りなどの実践をけしかけるのである。
確かに、実と虚というのは相反的な関係にあり、家庭円満や五穀豊穣に意義を
見出せる人間というのは、財物への貪りなどをあまり肥大化させたりもしない一方、
家庭や食に対して価値を見出せない者こそは、個人的に財物を貪ることにかけて
猛烈となったりもする。聖書信仰によって人工的に家庭や食に対する嫌悪を募らせて、
その反動によってこそ金銭欲などを増大させたユダヤ教徒やキリスト教徒の貪欲さたるや、
確かに異教徒などには決して見られないものであり、聖書信仰が絶やされたなら、
今の聖書信者ほどにも貪欲さを募らせたりする人間も、ほぼ皆無にまで立ち戻ることだろう。
聖書信仰ほどにも信者の金銭的、物質的欲望を募らせる信教も他にない一方で、
聖書信仰ほどにも家族や食物といった、人間にとって最も実のある事物に対する
尊重を損なわせる信教も、他にないのである。ただ親族に対する親愛を損ねたり、
食物に対する尊重を持たなかったりすることは、無宗教であってもいくらでも
あり得ることだが、教祖イエスの「おまえらに親族兄弟での殺し合いをさせる」
「パンの種こそは重要だ」などというような物言いを大真面目に信じ込ませて、
家族や食の栄養に対する尊重を体系的に損なわせたりまでするのは稀有なことで、
それにより、一定以上の家庭や食物に対する軽蔑を保ち続けるなどというのが、
聖書信仰でもなければあり得ないことで、そこまで珍妙な画策をわざわざ
試みるものなどがさすがに他にないから、聖書信者ほどにも異常なレベルの
貪欲さを備わらせた人間もまた、異教徒などには皆無なのである。
ただ貪欲であるというだけならまだしも、その裏に、人工的に形成された、
家族や食物に対する軽蔑意識がある。その軽蔑意識こそを糧に、聖書信者もまた
異教徒にはないほどの貪欲さを募らせているのだから、決してよろしきことなどではない。
貪欲の内に、必ず家庭崩壊や飢饉の種子を抱えているのだから、少しも進歩的なことだとは言えない。
「其の桐に其の椅に、其の実の離離たる。豈弟の君子は、令儀あらざる莫し」
「桐やイイギリの木にフサフサと実がなるようにして、楽しめる君子の、その姿も威儀深い。
(農工商の三民の事業を統制する君子としての仕事が、楽しめるほどに成功していることこそは
真の結実ともなっている。聖書信仰によって君子がそこまで豈弟でいられることも絶対にない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・小雅・白華之什・湛露)
聖書信仰ほどにも家族や食物といった、人間にとって最も実のある事物に対する
尊重を損なわせる信教も、他にないのである。ただ親族に対する親愛を損ねたり、
食物に対する尊重を持たなかったりすることは、無宗教であってもいくらでも
あり得ることだが、教祖イエスの「おまえらに親族兄弟での殺し合いをさせる」
「パンの種こそは重要だ」などというような物言いを大真面目に信じ込ませて、
家族や食の栄養に対する尊重を体系的に損なわせたりまでするのは稀有なことで、
それにより、一定以上の家庭や食物に対する軽蔑を保ち続けるなどというのが、
聖書信仰でもなければあり得ないことで、そこまで珍妙な画策をわざわざ
試みるものなどがさすがに他にないから、聖書信者ほどにも異常なレベルの
貪欲さを備わらせた人間もまた、異教徒などには皆無なのである。
ただ貪欲であるというだけならまだしも、その裏に、人工的に形成された、
家族や食物に対する軽蔑意識がある。その軽蔑意識こそを糧に、聖書信者もまた
異教徒にはないほどの貪欲さを募らせているのだから、決してよろしきことなどではない。
貪欲の内に、必ず家庭崩壊や飢饉の種子を抱えているのだから、少しも進歩的なことだとは言えない。
「其の桐に其の椅に、其の実の離離たる。豈弟の君子は、令儀あらざる莫し」
「桐やイイギリの木にフサフサと実がなるようにして、楽しめる君子の、その姿も威儀深い。
(農工商の三民の事業を統制する君子としての仕事が、楽しめるほどに成功していることこそは
真の結実ともなっている。聖書信仰によって君子がそこまで豈弟でいられることも絶対にない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・小雅・白華之什・湛露)
「たとひ七歳なりとも、われよりも勝ならば、われ彼に問うべし。
たとひ百歳なりとも、われよりも劣ならば、われかれを教ふべし」
(「正法眼蔵」禮拜得髓より)
相手が自分よりも優れているか、劣っているかということは、実相に根ざしてどちらもあり得ることであり、
ただひたすら相手を自分よりも優れたものと見なしたり、逆に悉く劣ったものと見なしたりするのでは
とうてい現実にそぐわず、以って、自分よりも本当に優れた相手に習うことでの成長を妨げることにもなる。
すでに本格的な礼楽の廃れていた春秋時代中期に、孔子は誰を特定の師にするわけでもなく、
方々の人々やその風習などをありのままに参考の対象ともしたという。(「史記」孔子世家などを参照)
だから「私は人が三人いればそこに師を見つける(述而第七・二二)」ともいい、
自らの勉学にかけての雑食さを別段、隠そうともしていない。
たとえば、古流武術の流れを汲む合気道の修練者には、あまり身体能力的にも優れていない虚弱者も多い。
開祖の植芝盛平からして、虚弱体質のために兵役を免除されている程だが、だからこそ、体力の強さなどに
頼らない超絶技巧の柔術をも修得して、旧軍部の上級将校にも柔術を指南する程もの名武術家となれたわけで、
むしろ部分的に人よりも劣っている部分があればこそ、他の面で突出する場合があるという手本になっているといえる。
相手が部分的に自分よりも劣っていた所で、他の面で自分よりも優れているなどということが
いくらでもあるわけだから、一概に他人が自分よりも優れているなどとも、劣っているなどとも言い切れず、
優れている面についてそれを習い、劣っている面についてはむしろ教えてやるという分別があるべきなのである。
たとひ百歳なりとも、われよりも劣ならば、われかれを教ふべし」
(「正法眼蔵」禮拜得髓より)
相手が自分よりも優れているか、劣っているかということは、実相に根ざしてどちらもあり得ることであり、
ただひたすら相手を自分よりも優れたものと見なしたり、逆に悉く劣ったものと見なしたりするのでは
とうてい現実にそぐわず、以って、自分よりも本当に優れた相手に習うことでの成長を妨げることにもなる。
すでに本格的な礼楽の廃れていた春秋時代中期に、孔子は誰を特定の師にするわけでもなく、
方々の人々やその風習などをありのままに参考の対象ともしたという。(「史記」孔子世家などを参照)
だから「私は人が三人いればそこに師を見つける(述而第七・二二)」ともいい、
自らの勉学にかけての雑食さを別段、隠そうともしていない。
たとえば、古流武術の流れを汲む合気道の修練者には、あまり身体能力的にも優れていない虚弱者も多い。
開祖の植芝盛平からして、虚弱体質のために兵役を免除されている程だが、だからこそ、体力の強さなどに
頼らない超絶技巧の柔術をも修得して、旧軍部の上級将校にも柔術を指南する程もの名武術家となれたわけで、
むしろ部分的に人よりも劣っている部分があればこそ、他の面で突出する場合があるという手本になっているといえる。
相手が部分的に自分よりも劣っていた所で、他の面で自分よりも優れているなどということが
いくらでもあるわけだから、一概に他人が自分よりも優れているなどとも、劣っているなどとも言い切れず、
優れている面についてそれを習い、劣っている面についてはむしろ教えてやるという分別があるべきなのである。
また、自らの親や主君などは、自分よりも優れているか否かなどに関わらず、謙りの対象とせねばならない。
すでに自分が壮健な成人ともなっていれば、体力でも知能でも年老いた親を上回り、何かにかけて自分のほうが
優れた仕事をこなせるようになりもする。それでもやはり自分の親である以上は敬わねばならないし、また自らが
何かにかけて多能であればこそ、多能な者を統制することこそが本務である主君を敬わねばならないこともある。
特に絶対的な上下関係を伴わない範囲においては、他人の優れた面を習って劣った面を習わない分別が
あるべきだし、また君臣父子のような上下関係を伴う範囲においては、能力の優劣などにかかわらず
目上にへりくだるようにしなければならない。だから、「優れた者に謙り、劣った者に謙らない」と、
「上下関係が前提としてある以上は、優劣の如何にかかわらず目上に謙る」という教条が正当となるのに対し、
「誰に対しても手当たり次第に、自分よりも優れた相手であるようにして謙る」という教条が不当となる。
「誰に対しても手当たり次第に、自分よりも優れた相手であるようにして謙る」という教条だけを聞けば、
決して耳障りにも聞こえないが、より正当な謙譲のあり方を他から参照してみればこそ、そこに潜在して
いる不当さが如実となる。犯罪聖書の記述というのは、軒並みこのようなものばかりであり、まさに
「井の中の蛙」の独り善がりからなる、世間知らずなままでの、手前勝手な物言いの宝庫なのである。
「孟公綽、趙魏の老を為すに則ち優る、以て滕薛の大夫を為す可からず」
「(魯の大夫の)孟公綽は、趙や魏のような大国でも、家老を任せる上では十分に優れている。
しかし、滕や薛のような小国といえども、大夫を任せるには至らな過ぎる。(魯の大夫はなおさら)
(何にかけては優れている、何にかけては劣っているという分別の提示例)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・憲問第十四・一二より)
すでに自分が壮健な成人ともなっていれば、体力でも知能でも年老いた親を上回り、何かにかけて自分のほうが
優れた仕事をこなせるようになりもする。それでもやはり自分の親である以上は敬わねばならないし、また自らが
何かにかけて多能であればこそ、多能な者を統制することこそが本務である主君を敬わねばならないこともある。
特に絶対的な上下関係を伴わない範囲においては、他人の優れた面を習って劣った面を習わない分別が
あるべきだし、また君臣父子のような上下関係を伴う範囲においては、能力の優劣などにかかわらず
目上にへりくだるようにしなければならない。だから、「優れた者に謙り、劣った者に謙らない」と、
「上下関係が前提としてある以上は、優劣の如何にかかわらず目上に謙る」という教条が正当となるのに対し、
「誰に対しても手当たり次第に、自分よりも優れた相手であるようにして謙る」という教条が不当となる。
「誰に対しても手当たり次第に、自分よりも優れた相手であるようにして謙る」という教条だけを聞けば、
決して耳障りにも聞こえないが、より正当な謙譲のあり方を他から参照してみればこそ、そこに潜在して
いる不当さが如実となる。犯罪聖書の記述というのは、軒並みこのようなものばかりであり、まさに
「井の中の蛙」の独り善がりからなる、世間知らずなままでの、手前勝手な物言いの宝庫なのである。
「孟公綽、趙魏の老を為すに則ち優る、以て滕薛の大夫を為す可からず」
「(魯の大夫の)孟公綽は、趙や魏のような大国でも、家老を任せる上では十分に優れている。
しかし、滕や薛のような小国といえども、大夫を任せるには至らな過ぎる。(魯の大夫はなおさら)
(何にかけては優れている、何にかけては劣っているという分別の提示例)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・憲問第十四・一二より)
 「水」は人間にとっての「へりくだり」の象徴となると共に、確かな実物の「恵み」ともなる。
「水」は人間にとっての「へりくだり」の象徴となると共に、確かな実物の「恵み」ともなる。 人間に欠くべからざる飲料として、また農産の豊穣をもたらす必須要素としての水。
その水がたとえば、治水事業のような泥臭い重労働によって保全されることはあっても、
一発当ててウハウハとなる博打稼業などによって増すことができたりすることはない。
「へりくだり」と「へつらい」の何が違うかといって、へりくだりは、治水事業のような重労働にすら
自分自身が挺身して、世の中に確かな恵みをもたらしていこうとするだけの心意気があるのに対し、
へつらいのほうにはそこまでの心意気はなく、見た目には相手にへりくだっているようであっても、
それにより自分が利益のおこぼれに与ってウハウハになるぐらいまでの見通ししか備わっていない点
だといえる。当然そのへつらいによって人々がより豊かな恵みに与れるなどということもなく、むしろ
へつらい者が自利を掠め取ったぶんだけ、全体としての恵みは目減りすらしてしまっているのである。
どこまでもへりくだる水の特性をありのままに讃える儒学や、神前に塩や米と共に水を供え、
地鎮祭などを通じて土木事業の安全無事を祈ったりもする神道などには、確かに水の特性と真摯に
向き合って、水の如き実物の恵みを着実にもたらしていこうとする理念が備わっている。のに対し、
水よりも聖霊(カネ)を上位の理念とし、聖霊の貪りを通じてついでに水のような実物の恵みも
もたらそうとする聖書信仰には、「へりくだり」という水の特性とも真摯に向き合っていこうとする
心意気などは全く欠けており、一発稼いでウハウハが本心の「へつらい」止まりな代物だといえる。
「士農工商」の四民制に基づくなら、治水事業を含む「工」も、金融業を含む「商」の上に置かれる。
それにより間接的に、水をカネよりも重要な実物であるとも見なしているわけで、カネよりも水を
より重要なものであると見なすことで、その特性、その恵み豊かさとも真摯に向き合っていくのである。
ただ水を自分たちにとっての恵みであるとばかり見なすのなら、我田引水もよかれということになるが、
水のどこまでもへりくだる特性を見習って、自利以上の利他からなる恵みの増大にすら挺身していく
ことをも目指していくのであれば、金権で水を独占しようとするような策動の価値などは否定される。
ただ水が欲しいなどと渇望するのではなく、自ら水のへりくだる特性に倣おうとすらしていく所にこそ、
より大きな恵みもまた確かに生ずるのだから、志しの高さがそのままより大きな豊かさに直結する好例だといえる。
「三十年の通を以ってすれば、凶旱水溢有ると雖も、民に菜色無し。
然る後に天子食するときは、日に挙ぐるに楽を以ってする」
「三十年分の国の収支を通算して毎年の予算をも決めるのであれば、たとえ旱魃や洪水が起ころうとも
民が飢え渇くことはない。それほどにも治世が成功して後には、天子も日々の宴食に舞楽を呼びもする。
(天下国家全土の民を飢えや渇きから解放する具体的な見通し。それは正式な帝業によってこそ実現される)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・王制第五より)
[YouTubeで再生]
 戦力の強さが必ずしも戦闘上の優越や、政治的な全能に結び付くわけでもないことは、
戦力の強さが必ずしも戦闘上の優越や、政治的な全能に結び付くわけでもないことは、
大昔から東洋兵法によってわきまえられて来たことであり、なおかついま米軍が
中東諸国などにおいて強いられている苦戦によって実証されていることでもある。
宮本武蔵の「五輪書」水之巻には、多勢に無勢の場合に相手の隊列を故意に乱れさせて、
単身の利によって相手を総崩れにさせる「多敵のくらい」の兵法が詳しく述べられてもいる。
両手にそれぞれ持ち合わせた大小の両刀を巧みに操ることで初めて可能となる超人的な技法
ではあるが、多勢の強大さを逆手に取って、相手を総崩れにさせる実例には一応なっている。
単身で死角に潜む中東のテロリストなどが、複数の乗員や兵員の乗車する戦車や装甲車に
RPG-7を打ち込んで破壊すれば、死者数の面でも軍備コストの面でも甚大な被害になる。
一方で、戦車や装甲車による重装備をした米軍が総攻撃を行ってみたところで、方々に単身で
散らばり、格安の装備ばかりで済ましているテロリストたちに大きな被害を与えることは難しい。
軍隊レベルの戦力の強さが、対テロリスト戦などにおいては害ばかりあって大した
益にもならないことが、今でもアフガニスタンなどの紛争地域で実証され続けている。
そして、やたらな軍備の増強は本国アメリカにも甚大な経済的負担を強い、
対外債務も今では13兆ドルを超えるまでになっている。(日本は約2兆ドル)
ステロイドを服用し過ぎたマッチョマンが中毒や精神疾患を患って惨死するようにして、
アメリカも強大さをむさぼり過ぎたあまりに自滅する。しかもただ自滅するだけでなく、
その強大さを実際にアフガンやイラクなどの侵略のために実用して、テロリストとの
ゲリラ戦ではは必ずしも強大さなどが通用しないことを思い知った上で自滅するという、
なんとも無様極まりない終焉を迎えることとなったのである。
 戦力の強さが必ずしも戦闘上の優越や、政治的な全能に結び付くわけでもないことは、
戦力の強さが必ずしも戦闘上の優越や、政治的な全能に結び付くわけでもないことは、 大昔から東洋兵法によってわきまえられて来たことであり、なおかついま米軍が
中東諸国などにおいて強いられている苦戦によって実証されていることでもある。
宮本武蔵の「五輪書」水之巻には、多勢に無勢の場合に相手の隊列を故意に乱れさせて、
単身の利によって相手を総崩れにさせる「多敵のくらい」の兵法が詳しく述べられてもいる。
両手にそれぞれ持ち合わせた大小の両刀を巧みに操ることで初めて可能となる超人的な技法
ではあるが、多勢の強大さを逆手に取って、相手を総崩れにさせる実例には一応なっている。
単身で死角に潜む中東のテロリストなどが、複数の乗員や兵員の乗車する戦車や装甲車に
RPG-7を打ち込んで破壊すれば、死者数の面でも軍備コストの面でも甚大な被害になる。
一方で、戦車や装甲車による重装備をした米軍が総攻撃を行ってみたところで、方々に単身で
散らばり、格安の装備ばかりで済ましているテロリストたちに大きな被害を与えることは難しい。
軍隊レベルの戦力の強さが、対テロリスト戦などにおいては害ばかりあって大した
益にもならないことが、今でもアフガニスタンなどの紛争地域で実証され続けている。
そして、やたらな軍備の増強は本国アメリカにも甚大な経済的負担を強い、
対外債務も今では13兆ドルを超えるまでになっている。(日本は約2兆ドル)
ステロイドを服用し過ぎたマッチョマンが中毒や精神疾患を患って惨死するようにして、
アメリカも強大さをむさぼり過ぎたあまりに自滅する。しかもただ自滅するだけでなく、
その強大さを実際にアフガンやイラクなどの侵略のために実用して、テロリストとの
ゲリラ戦ではは必ずしも強大さなどが通用しないことを思い知った上で自滅するという、
なんとも無様極まりない終焉を迎えることとなったのである。
戦って勝つためにこそ、「単なる強大さ」ばかりをあてにしていてはならない。
個々の戦闘技術を磨き上げることももちろん必要だし、何よりも、戦うべき場合に
おいて戦い、戦うべきでない場合においては戦わない分別こそが、勝利を導く鍵ともなる。
「百戦百勝は善の善なるものに非ざるなり。戦わずして人の兵を屈するは善の善なるものなり」
(「孫子」謀攻篇第三より)
と孫子が言ったとき、「善の善」とは単なる倫理的な「善」を言っているのではなく、
それでこそ最勝になれるという、兵法上の意義を込めた「善」を指し示しているのである。
また、倫理的な「善」とも合致しているからこそ、その「善」によって最勝ともなる。
軍事的に強大である、にもかかわらず戦うわけにもいかない場合があることをもわきまえる、
それでこそ最勝ともなりうるのだから、最勝故に最強であることと、全能故に何でもして
いいなどと思い込むこととは、とうてい両立し得ない事項であることが分かる。
「強は弱を犯さず、衆は寡を暴さず、而して弟、州巷に達す」
「強いからといって弱い者を犯さず、多勢だからといって無勢を攻め荒らすような
ことがなくなってから初めて、忠道に励もうとする者が五州の巷にまで及ぶことになる。
(アメリカのような強さにかまけての乱暴を行えば、決して人々からの忠誠は得られない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・祭義第二十四より)
個々の戦闘技術を磨き上げることももちろん必要だし、何よりも、戦うべき場合に
おいて戦い、戦うべきでない場合においては戦わない分別こそが、勝利を導く鍵ともなる。
「百戦百勝は善の善なるものに非ざるなり。戦わずして人の兵を屈するは善の善なるものなり」
(「孫子」謀攻篇第三より)
と孫子が言ったとき、「善の善」とは単なる倫理的な「善」を言っているのではなく、
それでこそ最勝になれるという、兵法上の意義を込めた「善」を指し示しているのである。
また、倫理的な「善」とも合致しているからこそ、その「善」によって最勝ともなる。
軍事的に強大である、にもかかわらず戦うわけにもいかない場合があることをもわきまえる、
それでこそ最勝ともなりうるのだから、最勝故に最強であることと、全能故に何でもして
いいなどと思い込むこととは、とうてい両立し得ない事項であることが分かる。
「強は弱を犯さず、衆は寡を暴さず、而して弟、州巷に達す」
「強いからといって弱い者を犯さず、多勢だからといって無勢を攻め荒らすような
ことがなくなってから初めて、忠道に励もうとする者が五州の巷にまで及ぶことになる。
(アメリカのような強さにかまけての乱暴を行えば、決して人々からの忠誠は得られない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・祭義第二十四より)
 正しいから肯定Yes好み、間違っているから否定No好みなどということはない。
正しいから肯定Yes好み、間違っているから否定No好みなどということはない。 真理は是もなければ非もない虚空にこそあり、真理に根ざした理想も非想非非想処の先にこそある。
是もなければ非もないとする論理志向は実際にNAND回路として、あらゆる論理回路を形成することが可能な
最高度の自由を持ち、便宜的に是とすべきものを是とし、非とすべきものを非とすることも自在となる。
何かにかけて是としようとすることも、何かにかけて非としようとすることも、
いずれもが是非の入り混じる実相世界に当てはめられた時点で、いつかは破綻を招く。
是とすべきものを是とし非とすべきものを非とすることが自在なNAND論理のような自由度が
是一辺倒や非一辺倒にはないから、無理な論理的構築を凝らしたところで、いつかは破綻するのである。
NAND論理に根ざした虚空の境地とまでいかずとも、ただ直観的に是とすべきものを是とし、
非とすべきものを非とするのが善で、それに違う是非を凝らすことが悪ともなる。
(もちろん直観に根ざした是非の判断が至当となるためにもそれなりの鍛錬を要する)
何でもかんでも是としてしまうことに付随する快感や、何でもかんでも非としようとすることに
付随する不快感を以ってして、是一辺倒を善とし、非一辺倒を悪として来たのが西洋社会ではあるが、
だからこそ西洋には始めから本物の善などはなかったのである。直観によって是非善悪を分別する
儒家のような思想も、是もなく非もない虚空の真理の先に正当な是非善悪を見出す仏教のような哲学もなく、
始めから一方的に是を積み立てたり、一方的に非を当て込んだりすることしか思想哲学上の指針として
なかったから、至当な是非からなる本物の善などは始めから見定めようもなかったのである。
善がなかったから、悪しかなかった。文明構築の指針としての善を寸分たりとも知らなかったから、
悪逆非道である試みしか為せなかった。それは確かに「過失」であり、本物の善も悪も知った上で
あえて悪を選び、必要もなくわざわざ好き好んで悪逆非道に邁進した場合のような、
「故意」故の許しがたさなどは決して伴っていない。
今まではそうだった。これからはそうではない。
これまでは過失だったが、これからは故意になる。
これまでは許しようがあったが、これからはもう許しようがない。
厳重な論理的導出にも根ざして、これからはもう摂取不捨である。
「百姓親しまず、五品に不遜なる」
「仁義礼智信の五常に対して不遜なため、百姓たちも親しみ合うことがない。
(仁徳に決定的に反する旧約教義のような邪説が流布されればこそ、民たちもまた不遜になる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・虞書・舜典より)
悪逆非道である試みしか為せなかった。それは確かに「過失」であり、本物の善も悪も知った上で
あえて悪を選び、必要もなくわざわざ好き好んで悪逆非道に邁進した場合のような、
「故意」故の許しがたさなどは決して伴っていない。
今まではそうだった。これからはそうではない。
これまでは過失だったが、これからは故意になる。
これまでは許しようがあったが、これからはもう許しようがない。
厳重な論理的導出にも根ざして、これからはもう摂取不捨である。
「百姓親しまず、五品に不遜なる」
「仁義礼智信の五常に対して不遜なため、百姓たちも親しみ合うことがない。
(仁徳に決定的に反する旧約教義のような邪説が流布されればこそ、民たちもまた不遜になる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・虞書・舜典より)
病気や犯罪をまず来たさないことが最善で、
来たしてしまった後、医療や刑罰で癒すのがその次である。
大病や大罪を来たしながら、巧みな医療や刑罰で凌ぐのがさらにその次で、
どんなに甚だしい大病や大罪を来たそうとも、医療や刑罰一つ施されないのが最悪だといえる。
上記の善悪の分別は、エントロピー保存則が守られる限りにおいて通用する。
病気や怪我によって自らの身心を傷めたり、犯罪によって他者の身命や財物を損ねたりしたなら、
それは必ずプラスマイナスゼロ以下の一方的な損壊となり、ゼロ以上の構築などには結び付かない。
それは、どんなに医学や法学が発達したところで同じことで、
医療や刑罰によってすでに起きてしまった病気や犯罪を癒すことは、あらかじめ
病気や犯罪を来たさないようにしていく努力以上の成果を挙げることが決してあり得ない。
だから、上記のような病気や犯罪にまつわる善悪の分別が当てはまるといえるが、
もちろん全ては、エントロピー保存則が普遍的である場合に限っての話で、一般論としては、
この世界においては物理法則としてのエントロピー保存則が普遍的であるから、便宜的に、
上記のような善悪の分別もまた、この世界において普遍的に通用すると断ずることができる。
昔の東洋人が、エントロピーの保存則を熱力学的に証明していたなどということはない。
それでも「覆水収むべからず(後漢書・竇何列伝より)」のような直観的な把握によって、
エントロピー保存則の普遍性をも常識的に了承していたのであって、むしろこのような概括的な
普遍法則の承諾から、体系的な善悪の分別のほうを積極的に推し進めてきた東洋人のあり方こそは、
エントロピー保存則の証明みたいな、稚拙な段階ばかりに拘泥し続けて来た
西洋人のあり方よりも誠実であるといえる。
来たしてしまった後、医療や刑罰で癒すのがその次である。
大病や大罪を来たしながら、巧みな医療や刑罰で凌ぐのがさらにその次で、
どんなに甚だしい大病や大罪を来たそうとも、医療や刑罰一つ施されないのが最悪だといえる。
上記の善悪の分別は、エントロピー保存則が守られる限りにおいて通用する。
病気や怪我によって自らの身心を傷めたり、犯罪によって他者の身命や財物を損ねたりしたなら、
それは必ずプラスマイナスゼロ以下の一方的な損壊となり、ゼロ以上の構築などには結び付かない。
それは、どんなに医学や法学が発達したところで同じことで、
医療や刑罰によってすでに起きてしまった病気や犯罪を癒すことは、あらかじめ
病気や犯罪を来たさないようにしていく努力以上の成果を挙げることが決してあり得ない。
だから、上記のような病気や犯罪にまつわる善悪の分別が当てはまるといえるが、
もちろん全ては、エントロピー保存則が普遍的である場合に限っての話で、一般論としては、
この世界においては物理法則としてのエントロピー保存則が普遍的であるから、便宜的に、
上記のような善悪の分別もまた、この世界において普遍的に通用すると断ずることができる。
昔の東洋人が、エントロピーの保存則を熱力学的に証明していたなどということはない。
それでも「覆水収むべからず(後漢書・竇何列伝より)」のような直観的な把握によって、
エントロピー保存則の普遍性をも常識的に了承していたのであって、むしろこのような概括的な
普遍法則の承諾から、体系的な善悪の分別のほうを積極的に推し進めてきた東洋人のあり方こそは、
エントロピー保存則の証明みたいな、稚拙な段階ばかりに拘泥し続けて来た
西洋人のあり方よりも誠実であるといえる。
エントロピー保存則の普遍性「覆水不可収」に根ざして、善悪を上記のように分別するのは、
善と見なせるものを推し進めた場合に着実な福徳の構築が見込まれ、悪と見なせるものを
推し進めた場合に着実な福徳の損壊と、最終的な破滅が見込まれるからである。そして、
覆水不可収が物理的に普遍的である以上は、上記の見込みもまた普遍的なものとなる。
以上で、上記のような善悪の分別の、物理的な普遍性もまた連動的に導き出されたわけである。
民の王化などによって、罪悪の増長を未然に防いで行こうとする儒学などのあり方がより善で、
罪を犯させた上で救ってやろうなどとするようなキリスト教などのあり方がより悪である。
より善だから、儒学などを実践すれば福徳の増進が見込まれる一方、より悪だから、
キリスト教などを実践すれば、福徳の損壊と最終的な破滅に見舞われる。これは、
西洋人こそが拘泥して来た挙句に証明してしまった、熱力学のエントロピー保存則の
普遍性によってこそ確証されたことである。自分たち西洋人が帰依して来たキリスト教こそは、
儒学などと比べればその実践が奨励されるに値しない、邪悪の信教ありのままの姿であることを
西洋人こそが物理的に証明してしまったのである。怨むんなら、そうである自分たちを怨むべきだ。
「子曰く、南人の言えること有り。曰く、人に而て恒無くんば、以て巫医も作す可からず、と。
善いかな。其の徳を恒にせざれば、或いは之れに羞じを承く。子曰く、占わざるのみ」
「先生は言われた。『南方の人々の言葉で、〈人として一定の庸徳が備わっているのでなければ、
占いや医療すら受けるべきではない〉というのがあるが、これはいい言葉だね。庸徳すら備わって
いないというのなら、その行いも恥ずべきことばかり。そんな人間は占いや医療を受ける価値も無い』」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・子路第十三・二二より)
善と見なせるものを推し進めた場合に着実な福徳の構築が見込まれ、悪と見なせるものを
推し進めた場合に着実な福徳の損壊と、最終的な破滅が見込まれるからである。そして、
覆水不可収が物理的に普遍的である以上は、上記の見込みもまた普遍的なものとなる。
以上で、上記のような善悪の分別の、物理的な普遍性もまた連動的に導き出されたわけである。
民の王化などによって、罪悪の増長を未然に防いで行こうとする儒学などのあり方がより善で、
罪を犯させた上で救ってやろうなどとするようなキリスト教などのあり方がより悪である。
より善だから、儒学などを実践すれば福徳の増進が見込まれる一方、より悪だから、
キリスト教などを実践すれば、福徳の損壊と最終的な破滅に見舞われる。これは、
西洋人こそが拘泥して来た挙句に証明してしまった、熱力学のエントロピー保存則の
普遍性によってこそ確証されたことである。自分たち西洋人が帰依して来たキリスト教こそは、
儒学などと比べればその実践が奨励されるに値しない、邪悪の信教ありのままの姿であることを
西洋人こそが物理的に証明してしまったのである。怨むんなら、そうである自分たちを怨むべきだ。
「子曰く、南人の言えること有り。曰く、人に而て恒無くんば、以て巫医も作す可からず、と。
善いかな。其の徳を恒にせざれば、或いは之れに羞じを承く。子曰く、占わざるのみ」
「先生は言われた。『南方の人々の言葉で、〈人として一定の庸徳が備わっているのでなければ、
占いや医療すら受けるべきではない〉というのがあるが、これはいい言葉だね。庸徳すら備わって
いないというのなら、その行いも恥ずべきことばかり。そんな人間は占いや医療を受ける価値も無い』」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・子路第十三・二二より)
死だ、死だ、と頻繁に口にはするものの、結局聖書信者は、
本物の個体の死と真剣に向き合うことには、一貫して拒絶を決め込んでいる。
仏教や神道の観点から言っても、個体の死によって脳の思考も完全に失われるとされる。
脳機能の働きの一種だった祖先崇拝や念仏信仰なども死ねば途絶えるが、それでも
先祖代々受け継がれていく魂や虚空の徳は不滅であり、存命中にそのような不滅なるものと
自己とを繋ぎとめておくための手段として、先祖供養や念仏などが嗜まれるのでもある。
結局、十字架信仰などはそういった意味での、不滅なるものと生存者との連繋を確立するもの
などでは決してないのである。全ては脳機能が健在であり続けることを前提とした箱庭劇の
範囲内であり、脳機能が死滅した後の世界などにまで、全く配慮は及んでいないのである。
脳機能が完全に死滅する、本物の死からは一貫して目を背け続けているから、
あたかも信仰が死後にまで持っていけるかのような物言いまでする。死して棺に納められ、
墓場に埋葬されてなお信仰を保っているとされるから、最後の審判の日には墓場から
復活するともされるが、これら全て、実相から乖離したお遊戯でしかなかったのである。
本物の個体の死と真剣に向き合うことには、一貫して拒絶を決め込んでいる。
仏教や神道の観点から言っても、個体の死によって脳の思考も完全に失われるとされる。
脳機能の働きの一種だった祖先崇拝や念仏信仰なども死ねば途絶えるが、それでも
先祖代々受け継がれていく魂や虚空の徳は不滅であり、存命中にそのような不滅なるものと
自己とを繋ぎとめておくための手段として、先祖供養や念仏などが嗜まれるのでもある。
結局、十字架信仰などはそういった意味での、不滅なるものと生存者との連繋を確立するもの
などでは決してないのである。全ては脳機能が健在であり続けることを前提とした箱庭劇の
範囲内であり、脳機能が死滅した後の世界などにまで、全く配慮は及んでいないのである。
脳機能が完全に死滅する、本物の死からは一貫して目を背け続けているから、
あたかも信仰が死後にまで持っていけるかのような物言いまでする。死して棺に納められ、
墓場に埋葬されてなお信仰を保っているとされるから、最後の審判の日には墓場から
復活するともされるが、これら全て、実相から乖離したお遊戯でしかなかったのである。
脳機能の死滅を伴う、本物の死と真摯に向き合っていくことを完全に拒絶してきたから、
聖書信仰だけは、明らかに他の教学とも段違いなレベルの不誠実さを信者に植えつけて来た。
生命の死と真摯に向き合うことにかけて、あらゆる教学の中でも白眉なのはやはり仏教で、
だからこそ仏教に真摯に帰依する者ほど誠実な人間も他にはない。それとは逆に、
本物の死から完全に目を背けることにかけて、聖書信仰の右に出るものもないからこそ、
聖書を狂信するものほど不誠実な人間も他にない。仏教と聖書教以外の信教帰依者や、
無信仰者などは、えてしてこの間のうちのどこかに位置し、誠実さにかけて敬虔な
仏教信者以上だったり、不誠実さにかけて聖書信者以上だったりすることはまずない。
(もちろん敬虔でない仏教信者や聖書信者が比較対象であれば、この限りでもない)
本物の死と真摯に向き合っていくことこそは、誠実であるが故に快い生を過ごす上での
秘訣ともなる。本物の死から目を背けて、脳機能も健在な生の範疇の限りでしか
何も考えられない所でこそ自意識過剰の思い上がりも増大し、不誠実さも極まり、
以って終始、不快きわまりない人生を送り続けるしかなくなるである。
「鮮民の生くるは、死して之れ久しきにも如かず」
「(肉親との縁も絶たれた)弧寡の民として生きることは、完全に死に絶えることにも及ばない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・小雅・小旻之什・蓼莪より)
聖書信仰だけは、明らかに他の教学とも段違いなレベルの不誠実さを信者に植えつけて来た。
生命の死と真摯に向き合うことにかけて、あらゆる教学の中でも白眉なのはやはり仏教で、
だからこそ仏教に真摯に帰依する者ほど誠実な人間も他にはない。それとは逆に、
本物の死から完全に目を背けることにかけて、聖書信仰の右に出るものもないからこそ、
聖書を狂信するものほど不誠実な人間も他にない。仏教と聖書教以外の信教帰依者や、
無信仰者などは、えてしてこの間のうちのどこかに位置し、誠実さにかけて敬虔な
仏教信者以上だったり、不誠実さにかけて聖書信者以上だったりすることはまずない。
(もちろん敬虔でない仏教信者や聖書信者が比較対象であれば、この限りでもない)
本物の死と真摯に向き合っていくことこそは、誠実であるが故に快い生を過ごす上での
秘訣ともなる。本物の死から目を背けて、脳機能も健在な生の範疇の限りでしか
何も考えられない所でこそ自意識過剰の思い上がりも増大し、不誠実さも極まり、
以って終始、不快きわまりない人生を送り続けるしかなくなるである。
「鮮民の生くるは、死して之れ久しきにも如かず」
「(肉親との縁も絶たれた)弧寡の民として生きることは、完全に死に絶えることにも及ばない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・小雅・小旻之什・蓼莪より)
 「豊とは大なり。大を窮むる者は必ずその居を失う」
「豊とは大なり。大を窮むる者は必ずその居を失う」 「『豊か』とは大いなることだが、大きいことを極めてしまっても、自分の居場所を失う」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・序卦伝より)
実物の農地における豊作などは、それはそれは多大な努力を必要とするもので、
しかも一定の努力すらすれば、それっきりで済むなどというものではなく、
耕作などを蔑ろにすれば途端に凶作に見舞われるし、そうでなくたって旱魃などの災害によって
一挙に実りを奪われたりするもの。実物の農産物の豊作を画策したりする所にこそ
「豊大さを窮める」などということがなく、どこまでも豊作のための努力をし続けていく必要がある。
一方、心境をお笑いやカルト信仰からなるウレシがりによって豊かにさせるということは、
気難しい相手などであればなかなか難しいということはあっても、必ず一定の所で極まってしまう。
無闇やたらとゲハゲハニタニタ笑い飛ばす所に心境が行き着いてしまえば、それまでなのであり、
それ以上にウレシさの質を増していくなんてことも、もはやないのである。
心境がウレシがりの豊満に満たされ尽くして、もはや膠着しきってしまっている状態ともなれば、
自己の内面における自らの立ち位置を見失って、客観的に自己を把握することも覚束なくなる。
これが他でもない「身の程知らず」の状態であり、身の程知らずな状態の人間が、
えてしてヘラヘラと不敵な笑みを浮かべていたりするのも、このためである。
このような身の程知らずと化してしまった人間の心象を、「易経」豊卦・上六では
「其の屋を豊かにし、其の家に蔀す。其の戸を闚うに、闃として其れ人无し。三歳まで覿ず。凶なり」
という風に表現している。自己の家屋、すなわち自分自身の内心ばかりを豊かにしようとして、
自意識過剰の思い上がりを募らせ、内心と外界の間にも、丈夫な格子戸を付けてしまう。
外から格子戸の中を覗いてみても、三年経っても人の気配が全く窺えない状態。それほどにも気配が
うかがえないのは、家屋ばかりを豪華にしすぎたために、家主が自己を見失ってしまっているからで、
ウレシがりの豊満によって内心を満杯にし尽くしてしまっているような人間に、確たる自己などはないのである。
だから、己ればかりを殊更に満たし尽くしているような人間は、自己を見失った身の程知らずとなってしまう。
自分がしっかりと身の程をわきまえるためには、かえって己れを虚しく
することのほうが必要で、豊かさの追求はむしろ農産などの、なかなか豊穣が実現し難くて、
極めるなんてことも決してあり得ないような分野にこそ振り向けるようにすべきなのである。
己れを豊満たらしめることは安易である一方、己れの虚しさと実物の豊穣とを追求していくことは、困難である。
社会的な栄華などと共に虚心を保つことは特に困難で、それこそ虚空の徳を尊ぶ仏門への帰依などにまで
頼らなければならなくなったりもしかねないわけだが、それ以前にまず、己れの個人的な豊満ばかりを
ことさらに追い求めて行こうとうする悪癖から、卒業することが必要だといえる。
「其の屋を豊かにし、其の家に蔀す。其の戸を闚うに、闃として其れ人无し。三歳まで覿ず。凶なり」
という風に表現している。自己の家屋、すなわち自分自身の内心ばかりを豊かにしようとして、
自意識過剰の思い上がりを募らせ、内心と外界の間にも、丈夫な格子戸を付けてしまう。
外から格子戸の中を覗いてみても、三年経っても人の気配が全く窺えない状態。それほどにも気配が
うかがえないのは、家屋ばかりを豪華にしすぎたために、家主が自己を見失ってしまっているからで、
ウレシがりの豊満によって内心を満杯にし尽くしてしまっているような人間に、確たる自己などはないのである。
だから、己ればかりを殊更に満たし尽くしているような人間は、自己を見失った身の程知らずとなってしまう。
自分がしっかりと身の程をわきまえるためには、かえって己れを虚しく
することのほうが必要で、豊かさの追求はむしろ農産などの、なかなか豊穣が実現し難くて、
極めるなんてことも決してあり得ないような分野にこそ振り向けるようにすべきなのである。
己れを豊満たらしめることは安易である一方、己れの虚しさと実物の豊穣とを追求していくことは、困難である。
社会的な栄華などと共に虚心を保つことは特に困難で、それこそ虚空の徳を尊ぶ仏門への帰依などにまで
頼らなければならなくなったりもしかねないわけだが、それ以前にまず、己れの個人的な豊満ばかりを
ことさらに追い求めて行こうとうする悪癖から、卒業することが必要だといえる。
出家修行のような着実な手段にも依らず、
むしろ人並み以上の罪業の積み重ねに邁進しながら、
「自分たちは清められた」とキリシタンがうそぶくのは、
自分たちが汚穢を眼前にした時には、十字架信仰の自己洗脳によって
IQ20〜35程度の重度知能障害状態に自分たちの脳みそを追いやっているからで、
それほどもの知能障害状態で罪業とも対峙するから、その汚らわしさを解することもない。
罪業の汚穢から「目を背ける」というのでは少し語弊があり、
キリシタンは、場合によっては罪業に目を向けもするし、正気を保っているように
見える状態のままで、強盗殺人や寺社打ち壊しのような大罪をも犯すのである。
ただ、そのような事態において、キリシタンは内心、自己洗脳によって自分たちを
重度知能障害級の白痴状態へと追いやっているのであり、その見た目が常人らしく
見えたところで、その脳内は完全に真性の蒙昧に侵されているのである。
罪も穢れも見ていたところで、所詮は見ている者自身の脳みそが、重度知的障害者などとも
同等の倫理理解度と化してしまっていて、まともな倫理的判断を行うこともできない。
倫理的理解度が重度知的障害者並みだから、善の楽しさ、悪の苦しさを感じ取ることも
できないわけで、この内の「悪の苦しみに対する不感症状態」を以ってして、
キリシタンは「自分たちが汚れから清められた」ともほざくのである。
自分たちにとって辛く苦しいこと=汚れ
辛くも苦しくもなく、ただひたすら楽しいこと=聖
という、それはそれは薄ら馬鹿げた思い込みまでもが、キリシタンの潜在意識にはあるわけで、
苦しくたって清浄さのために受け入れねばならないことや、度を越した快楽の汚らわしさの
存在などを全く想定にすら入れていないのは、キリシタンとなるような人間が始めから、
常人よりも遥かに度し難い、自意識過剰の思い上がりを患っていた人間であるからだ。
むしろ人並み以上の罪業の積み重ねに邁進しながら、
「自分たちは清められた」とキリシタンがうそぶくのは、
自分たちが汚穢を眼前にした時には、十字架信仰の自己洗脳によって
IQ20〜35程度の重度知能障害状態に自分たちの脳みそを追いやっているからで、
それほどもの知能障害状態で罪業とも対峙するから、その汚らわしさを解することもない。
罪業の汚穢から「目を背ける」というのでは少し語弊があり、
キリシタンは、場合によっては罪業に目を向けもするし、正気を保っているように
見える状態のままで、強盗殺人や寺社打ち壊しのような大罪をも犯すのである。
ただ、そのような事態において、キリシタンは内心、自己洗脳によって自分たちを
重度知能障害級の白痴状態へと追いやっているのであり、その見た目が常人らしく
見えたところで、その脳内は完全に真性の蒙昧に侵されているのである。
罪も穢れも見ていたところで、所詮は見ている者自身の脳みそが、重度知的障害者などとも
同等の倫理理解度と化してしまっていて、まともな倫理的判断を行うこともできない。
倫理的理解度が重度知的障害者並みだから、善の楽しさ、悪の苦しさを感じ取ることも
できないわけで、この内の「悪の苦しみに対する不感症状態」を以ってして、
キリシタンは「自分たちが汚れから清められた」ともほざくのである。
自分たちにとって辛く苦しいこと=汚れ
辛くも苦しくもなく、ただひたすら楽しいこと=聖
という、それはそれは薄ら馬鹿げた思い込みまでもが、キリシタンの潜在意識にはあるわけで、
苦しくたって清浄さのために受け入れねばならないことや、度を越した快楽の汚らわしさの
存在などを全く想定にすら入れていないのは、キリシタンとなるような人間が始めから、
常人よりも遥かに度し難い、自意識過剰の思い上がりを患っていた人間であるからだ。
十字架信仰は、信者の自意識過剰の思い上がりを控えさせたりしないのみならず、
自意識過剰の思い上がりありきのものの考え方を固着化させて、深刻化させていく。
挙句には、自意識過剰の思い上がりを抱いていない状態などが想像も付かないほどにも
芯から腐れ果てた心象を信者に植え付けさせて、矯正不能な状態にまでしてしまうのである。
キリシタン災禍というのは、この世界に現出している並みかそれ以上にも、
個々の信者の内面においてこそ根深いものとなっていて、それに対しての十分な対処を
施さないことには、現出しているキリシタン災禍の収拾も覚束ない。見えている部分以上にも、
目には見えてはいない部分にこそ、最も根深いキリシタン災禍もまた巣食っているのだといえる。
「子思曰く、昔、我が先君子は道を失う所無し。
道隆なれば則ち従って隆にし、道汚なれば則ち従って汚にす。汲には則ち安んぞ能くせん」
「(孔子の孫の)子思は言った。『昔、我が父(孔子の子の伯魚)は、少しも道を踏み外すことが
なかった。道が隆盛すればその道に従って隆となり、道が汚れてもその道に従って汚れられた。
私ごときにはとうてい真似のできることではない』(『汚れた道に従って汚れる』とは、たとえば
『論語』公冶長第五・二一の、乱世を愚人のフリをしてやり過ごした寧武子の姿などが当てはまる。
清廉な治世も汚れた乱世もよく見極めての倫理的判断が可能であればこその偉業だといえる。)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・檀弓上第三より)
自意識過剰の思い上がりありきのものの考え方を固着化させて、深刻化させていく。
挙句には、自意識過剰の思い上がりを抱いていない状態などが想像も付かないほどにも
芯から腐れ果てた心象を信者に植え付けさせて、矯正不能な状態にまでしてしまうのである。
キリシタン災禍というのは、この世界に現出している並みかそれ以上にも、
個々の信者の内面においてこそ根深いものとなっていて、それに対しての十分な対処を
施さないことには、現出しているキリシタン災禍の収拾も覚束ない。見えている部分以上にも、
目には見えてはいない部分にこそ、最も根深いキリシタン災禍もまた巣食っているのだといえる。
「子思曰く、昔、我が先君子は道を失う所無し。
道隆なれば則ち従って隆にし、道汚なれば則ち従って汚にす。汲には則ち安んぞ能くせん」
「(孔子の孫の)子思は言った。『昔、我が父(孔子の子の伯魚)は、少しも道を踏み外すことが
なかった。道が隆盛すればその道に従って隆となり、道が汚れてもその道に従って汚れられた。
私ごときにはとうてい真似のできることではない』(『汚れた道に従って汚れる』とは、たとえば
『論語』公冶長第五・二一の、乱世を愚人のフリをしてやり過ごした寧武子の姿などが当てはまる。
清廉な治世も汚れた乱世もよく見極めての倫理的判断が可能であればこその偉業だといえる。)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・檀弓上第三より)
完全誤謬の化身であるキリストの降臨によって、
この世に甚大な禍いがもたらされる。その際に異教徒などとは違って
自分たちが救済の対象になるとされるのが、キリスト信仰の正体である。
そもそもキリストなどがこの世に降臨しなければ、
この世に禍いがもたらされることもないのだから、
キリスト信者を含む誰しもが禍いなどに見舞われずに済む。
にもかかわらず、キリスト教徒はキリストの降臨によってこの世に
甚大な禍いがもたらされる中で、自分たちが特定して救われることを信じようとする。
救われることを企図することが信仰である一方で、この世に禍いがもたらされるのは
もはやほとんど信仰ですらない、キリスト教徒にとっての大前提である。
この世に大前提としての禍いがもたらされる根拠は、旧約の記述である。
バベルの塔は崩壊し、世界中を飲み込むほどの大洪水が起こる中で、
ユダヤ教徒がノアの箱舟に乗ることで救いを免れるという旧約の記述を、
「十字架信仰によって救われる」という風に置き換えているわけで、
十字架信仰こそは本義とされるキリスト教徒にとって、この世に大いなる
禍いがもたらされるという旧約の記録自体は、全く信仰対象でもないとまでは
いかないにしても、第二第三の信仰対象とされる。そのため、この世に積極的に
禍いをもたらしていくことこそが本義とされる旧約信仰(ユダヤ)などと比べれば、
「救済」という部分こそが第一義であるとされるぶんだけ、キリスト信仰のほうが
「粗悪さ」にかけてマシであるような印象を抱かせもするのである。
この世に甚大な禍いがもたらされる。その際に異教徒などとは違って
自分たちが救済の対象になるとされるのが、キリスト信仰の正体である。
そもそもキリストなどがこの世に降臨しなければ、
この世に禍いがもたらされることもないのだから、
キリスト信者を含む誰しもが禍いなどに見舞われずに済む。
にもかかわらず、キリスト教徒はキリストの降臨によってこの世に
甚大な禍いがもたらされる中で、自分たちが特定して救われることを信じようとする。
救われることを企図することが信仰である一方で、この世に禍いがもたらされるのは
もはやほとんど信仰ですらない、キリスト教徒にとっての大前提である。
この世に大前提としての禍いがもたらされる根拠は、旧約の記述である。
バベルの塔は崩壊し、世界中を飲み込むほどの大洪水が起こる中で、
ユダヤ教徒がノアの箱舟に乗ることで救いを免れるという旧約の記述を、
「十字架信仰によって救われる」という風に置き換えているわけで、
十字架信仰こそは本義とされるキリスト教徒にとって、この世に大いなる
禍いがもたらされるという旧約の記録自体は、全く信仰対象でもないとまでは
いかないにしても、第二第三の信仰対象とされる。そのため、この世に積極的に
禍いをもたらしていくことこそが本義とされる旧約信仰(ユダヤ)などと比べれば、
「救済」という部分こそが第一義であるとされるぶんだけ、キリスト信仰のほうが
「粗悪さ」にかけてマシであるような印象を抱かせもするのである。
上記のようなキリスト信仰の内実を鑑みてみるに、キリスト教徒は、
自分たちから率先して信仰を途絶していくことは、まずできないことが分かる。
新約のイエキリにまつわる記録を信じるという以前に、旧約の記録に基づいてこの世に
甚大な災禍がもたらされるという思い込みが大前提としてある。だからこそ無理にでも
キリスト信仰によって救われようとするのだから、まずは、旧約の記録が全くの虚構であり、
人々が「文化的前提」として扱うにも値しない無意味な書であることを公表する必要がある。
新約にしろ旧約にしろ、イスラエル聖書はその全てが信用に値しない虚偽虚言の集成で
あることには違いない。ただ、あくまで新約の記録のほうが旧約に依存しているのであり、
旧約の信憑性があってこその、新約の信憑性でみあるのだから、まずは旧約の記録の
「カルト詐欺指南」としての内実を明らかにし、そのカルト詐欺がもたらすマッチポンプの
「ポンプ」として新約教義が捏造されたことをも、順を追って説明する。カルト詐欺の
手管としての、旧約教義の実践が絶やされたからには、旧約教義がもたらすとされる
大災禍から救われようとするための新約信仰も、もはや必要がなくなる、だからもう
十字架などを信じる必要もないのだと説明して、全てのキリスト教徒にも棄教を促す。
十字架を信じたからと言って、別に旧約信仰の災禍から免れられるわけでもないが、旧約と新約、
両方の教義を通じて、邪信を二重三重にこじらせてしまっているキリスト教徒を、狂信の悪循環から
脱出させるためには、やはり「最初の邪信」たる旧約進行から絶やされていかなければならない。
自分たちから率先して信仰を途絶していくことは、まずできないことが分かる。
新約のイエキリにまつわる記録を信じるという以前に、旧約の記録に基づいてこの世に
甚大な災禍がもたらされるという思い込みが大前提としてある。だからこそ無理にでも
キリスト信仰によって救われようとするのだから、まずは、旧約の記録が全くの虚構であり、
人々が「文化的前提」として扱うにも値しない無意味な書であることを公表する必要がある。
新約にしろ旧約にしろ、イスラエル聖書はその全てが信用に値しない虚偽虚言の集成で
あることには違いない。ただ、あくまで新約の記録のほうが旧約に依存しているのであり、
旧約の信憑性があってこその、新約の信憑性でみあるのだから、まずは旧約の記録の
「カルト詐欺指南」としての内実を明らかにし、そのカルト詐欺がもたらすマッチポンプの
「ポンプ」として新約教義が捏造されたことをも、順を追って説明する。カルト詐欺の
手管としての、旧約教義の実践が絶やされたからには、旧約教義がもたらすとされる
大災禍から救われようとするための新約信仰も、もはや必要がなくなる、だからもう
十字架などを信じる必要もないのだと説明して、全てのキリスト教徒にも棄教を促す。
十字架を信じたからと言って、別に旧約信仰の災禍から免れられるわけでもないが、旧約と新約、
両方の教義を通じて、邪信を二重三重にこじらせてしまっているキリスト教徒を、狂信の悪循環から
脱出させるためには、やはり「最初の邪信」たる旧約進行から絶やされていかなければならない。
「事うるに孰れをか大と為す、事うるに親を大と為す。守るに孰れをか大と為す、
守るに身を大と為す。其の身を失わずして能く其の親に事うる者は、吾れ之れを聞くも、
其の身を失いて能く其の親に事うる者は、吾れ未だ之れ聞かざるなり。孰れをか事うると為らざらん。
親に事うるは事うるの本なり。孰れをか守ると為らざらん。身を守るは、守るの本なり」
「誰に仕えることが最も重大なことであろうか、親に仕えることこそは最も重大なことであろう。
何を守ることが最も重大なことであろうか、わが身を守ることこそは最も重大なことであろう。
わが身を守りつつ親に仕えることが出来たものは私も聞いたことがあるが、
わが身を失いながら親に仕えることが出来たものなどは、私は聞いたことがない。
人に仕えるということにも色々あるが、親に仕えることこそは仕えることの根本であるといえる。
守るものにも色々とあるが、わが身を守ることこそは守るということの根本であるといえる。
(親に仕えることを棄てて脳内超越神に仕え、わが身を失って天に召され、救われ守られるという
キリスト信仰の構造とは真逆の内容となっている。それでいてこれが仕えたり、守ったりすることの本来のあり方である)」
(権力道徳聖——通称四書五経——孟子・離婁章句上・一九より)
守るに身を大と為す。其の身を失わずして能く其の親に事うる者は、吾れ之れを聞くも、
其の身を失いて能く其の親に事うる者は、吾れ未だ之れ聞かざるなり。孰れをか事うると為らざらん。
親に事うるは事うるの本なり。孰れをか守ると為らざらん。身を守るは、守るの本なり」
「誰に仕えることが最も重大なことであろうか、親に仕えることこそは最も重大なことであろう。
何を守ることが最も重大なことであろうか、わが身を守ることこそは最も重大なことであろう。
わが身を守りつつ親に仕えることが出来たものは私も聞いたことがあるが、
わが身を失いながら親に仕えることが出来たものなどは、私は聞いたことがない。
人に仕えるということにも色々あるが、親に仕えることこそは仕えることの根本であるといえる。
守るものにも色々とあるが、わが身を守ることこそは守るということの根本であるといえる。
(親に仕えることを棄てて脳内超越神に仕え、わが身を失って天に召され、救われ守られるという
キリスト信仰の構造とは真逆の内容となっている。それでいてこれが仕えたり、守ったりすることの本来のあり方である)」
(権力道徳聖——通称四書五経——孟子・離婁章句上・一九より)
正しい言葉に正しい行いが伴うとも、間違った言葉に間違った行いが伴うとも限らない。
行いの過ちを取り繕うために正しげな言葉を駆使してみたり、逆に行いの正しさに
万全の守りがあるから、多少は戯れの放言をしてみたりすることもある。
行いによって殺人や窃盗のような実罪が犯されることもあれば、言葉によって
詐欺や偽証のような実罪が犯されることもある。ただ、言葉によって犯される罪にも、
必ず行為能力(財力や法権など)の取り扱いが伴っていて、その行為能力が人々の生活や
活動を大きく左右するものであればこそ、行為能力を不正に取り扱おうとすることを
目的とした詐欺なり偽証なりが、言葉によって犯される実罪ともなるのである。
故に、実罪は必ず行いと共にある一方で、言葉と共にはあったりなかったりするといえる。
行いが完全に行為能力の扱いを放棄しているというのなら、発言が相当に口汚くたって、
その発言が実罪につながることはほとんどない。社会的にどうといった効果があるわけ
でもないのに、口先だけは威勢がいい、その有り様は冷笑にすら値するものとなる。
実罪の罪障にかけては、行いが本であり、言葉は末だったり、末ですらなかったりする。
だから社会道徳の大家である儒家では行いの正しさを第一とし、発言の正しさは第二とする。
もちろん言葉も正しいに越したことはないが、過ちを取り繕うための巧言令色などもあるから、
言葉の正しさ美しさなどを決して信用はしない。記録として残されている言辞の秀逸さでは
孔子<孟子<荀子だが、儒者としての評価はむしろ孔子>孟子>荀子だったりもするように、
口先ばかりの美辞麗句を、かえって徳行にかけての減点対象にすらしたりもするのである。
行いの過ちを取り繕うために正しげな言葉を駆使してみたり、逆に行いの正しさに
万全の守りがあるから、多少は戯れの放言をしてみたりすることもある。
行いによって殺人や窃盗のような実罪が犯されることもあれば、言葉によって
詐欺や偽証のような実罪が犯されることもある。ただ、言葉によって犯される罪にも、
必ず行為能力(財力や法権など)の取り扱いが伴っていて、その行為能力が人々の生活や
活動を大きく左右するものであればこそ、行為能力を不正に取り扱おうとすることを
目的とした詐欺なり偽証なりが、言葉によって犯される実罪ともなるのである。
故に、実罪は必ず行いと共にある一方で、言葉と共にはあったりなかったりするといえる。
行いが完全に行為能力の扱いを放棄しているというのなら、発言が相当に口汚くたって、
その発言が実罪につながることはほとんどない。社会的にどうといった効果があるわけ
でもないのに、口先だけは威勢がいい、その有り様は冷笑にすら値するものとなる。
実罪の罪障にかけては、行いが本であり、言葉は末だったり、末ですらなかったりする。
だから社会道徳の大家である儒家では行いの正しさを第一とし、発言の正しさは第二とする。
もちろん言葉も正しいに越したことはないが、過ちを取り繕うための巧言令色などもあるから、
言葉の正しさ美しさなどを決して信用はしない。記録として残されている言辞の秀逸さでは
孔子<孟子<荀子だが、儒者としての評価はむしろ孔子>孟子>荀子だったりもするように、
口先ばかりの美辞麗句を、かえって徳行にかけての減点対象にすらしたりもするのである。
言葉による罪が、特に多く犯されるようになるのが法治主義社会、契約主義社会である。
拳一つ、小刀一つ用いられない完全な文治下において、契約書や権利書一枚によって、
本当に人間の命までもが左右される。そんな中で、確かに言葉による実罪もまた
多量に犯されることになるわけで、言葉による罪を全く裁かないというのであれば、
大量の殺人罪級の詐欺師や嘘吐きが野に放られたままで居続けることになる。
契約主義の精神的怠惰が未だ抜けきらない限りにおいて、「妖言」の罪を精査して取締りの
対象とすることも、それなりに欠かせないのも確かだが、さりとて、「口汚さすなわち罪」として
扱われたりまでするのも考えもので、言行にまつわる罪の何たるかを人々がよく自主判断できるように
なったなら、高祖以来の法制緩和策で人々の自主的な善悪の分別が養われるようになった前漢初期、
呂后の代に妖言罪が撤廃されたようにして、口先の自由はかえって守られていくようにすらなる。
罪はあくまで罪として裁かれる一方で、罪でないものに対する解放もまた推進されていくことになる。
「夏の道は未だ辞を涜せず、備わるを求めず、大いに民に望まず、民未だ其れ親しむを厭わず。
殷人は未だ礼を涜せず、備わるを民に求む。周人は民を強いて、未だ神を涜せず、而して賞爵刑罰窮む」
「虞夏の頃にはまだ朝廷の辞令が冒涜されたような試しもなかったので、人々に善悪の分別が
備わることを求めることすらなく、そのため民も大いに君に親しんだ。殷の頃には朝廷の辞令を謗るような
ものはいても、作為された礼楽を冒涜するような者まではいなかったので、人々に分別を求めることができた。
周代には辞令や礼楽を謗る者も多くなったため、これらを強いるようになり、辛うじて神を
冒涜までする者はいないという状態だった。これに至って賞罰の作為も極まることとなった。
(言葉による冒涜という意味であれば、朝廷の辞令や礼楽への冒涜が行われないことのほうが程度が高い。
神に対する冒涜云々が取り沙汰されている時点で、もはや人々には自主的な分別すらないのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・表記第三十二より)
拳一つ、小刀一つ用いられない完全な文治下において、契約書や権利書一枚によって、
本当に人間の命までもが左右される。そんな中で、確かに言葉による実罪もまた
多量に犯されることになるわけで、言葉による罪を全く裁かないというのであれば、
大量の殺人罪級の詐欺師や嘘吐きが野に放られたままで居続けることになる。
契約主義の精神的怠惰が未だ抜けきらない限りにおいて、「妖言」の罪を精査して取締りの
対象とすることも、それなりに欠かせないのも確かだが、さりとて、「口汚さすなわち罪」として
扱われたりまでするのも考えもので、言行にまつわる罪の何たるかを人々がよく自主判断できるように
なったなら、高祖以来の法制緩和策で人々の自主的な善悪の分別が養われるようになった前漢初期、
呂后の代に妖言罪が撤廃されたようにして、口先の自由はかえって守られていくようにすらなる。
罪はあくまで罪として裁かれる一方で、罪でないものに対する解放もまた推進されていくことになる。
「夏の道は未だ辞を涜せず、備わるを求めず、大いに民に望まず、民未だ其れ親しむを厭わず。
殷人は未だ礼を涜せず、備わるを民に求む。周人は民を強いて、未だ神を涜せず、而して賞爵刑罰窮む」
「虞夏の頃にはまだ朝廷の辞令が冒涜されたような試しもなかったので、人々に善悪の分別が
備わることを求めることすらなく、そのため民も大いに君に親しんだ。殷の頃には朝廷の辞令を謗るような
ものはいても、作為された礼楽を冒涜するような者まではいなかったので、人々に分別を求めることができた。
周代には辞令や礼楽を謗る者も多くなったため、これらを強いるようになり、辛うじて神を
冒涜までする者はいないという状態だった。これに至って賞罰の作為も極まることとなった。
(言葉による冒涜という意味であれば、朝廷の辞令や礼楽への冒涜が行われないことのほうが程度が高い。
神に対する冒涜云々が取り沙汰されている時点で、もはや人々には自主的な分別すらないのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・表記第三十二より)
実の親兄弟との関係すら蔑ろにする者が、
真の朋友関係を築き上げられるようなこともありはしない。
それは、妾腹の私生児ほどにも親を親しみにくい立場に生まれた人間といえども同じことで、
当該の境遇に生まれ育ちながらも、母を慈しみ、自らも先祖供養を果たした孔子の場合は、
顔淵や子路のような門弟との交遊の記録にも一定の親密さが垣間見られるのに対し、
先祖供養も孝養もほったらかして「親族兄弟での殺し合いをさせる」とまで予言した
イエスのほうはといえば、実質門弟である「使徒」とされる取り巻きとの
交わりもどこか他人行儀で、確かに「人間同士の関係」という印象に乏しい。
それは別に、イエスが「神の子」だったからではなく、
一番身近な人間関係である親族兄弟との親しみすらをも放棄した孤独者だったからで、
親族との親しみすら放棄した結果として、赤の他人である使徒や信者などの取り巻きとも
他人行儀な付き合いしかできなかったという以上の、何事でもあり得なかったのである。
脳内超越神への帰依という妄想と引き換えに、天下万人誰しもとの他人行儀な付き合いを頑ななものと
ならしめるイエス流の精神病理は、確かに全てのキリスト教徒らに対しても強固に植え付けられて、
誰しもが他人同然な存在であることを前提とした、巧みな修辞などをも発展させたのだった。
真の朋友関係を築き上げられるようなこともありはしない。
それは、妾腹の私生児ほどにも親を親しみにくい立場に生まれた人間といえども同じことで、
当該の境遇に生まれ育ちながらも、母を慈しみ、自らも先祖供養を果たした孔子の場合は、
顔淵や子路のような門弟との交遊の記録にも一定の親密さが垣間見られるのに対し、
先祖供養も孝養もほったらかして「親族兄弟での殺し合いをさせる」とまで予言した
イエスのほうはといえば、実質門弟である「使徒」とされる取り巻きとの
交わりもどこか他人行儀で、確かに「人間同士の関係」という印象に乏しい。
それは別に、イエスが「神の子」だったからではなく、
一番身近な人間関係である親族兄弟との親しみすらをも放棄した孤独者だったからで、
親族との親しみすら放棄した結果として、赤の他人である使徒や信者などの取り巻きとも
他人行儀な付き合いしかできなかったという以上の、何事でもあり得なかったのである。
脳内超越神への帰依という妄想と引き換えに、天下万人誰しもとの他人行儀な付き合いを頑ななものと
ならしめるイエス流の精神病理は、確かに全てのキリスト教徒らに対しても強固に植え付けられて、
誰しもが他人同然な存在であることを前提とした、巧みな修辞などをも発展させたのだった。
聖書教徒と聖書教徒、あるいは聖書教徒と非聖書教徒との関係は必ず、非聖書教徒同士の
関係よりも他人行儀なものであり、聖書教徒同士での最も親密な人間関係ですら、
非聖書教徒同士での最も疎遠な交友関係ほどにも親密なものではない。
聖書教徒同士での交友関係などというものも、非聖書教徒の立場からすれば必ず一定以上に
浅はかなもので、だからこそ利権の共有関係をありのままに「友愛」などと呼びもする。
利権の共有関係なんてただの商業関係でしかなく、アカの他人同士であってもいくらでも
持ち得る関係なわけだが、聖書教徒にとっての交友なんてのは、利権が絡もうが絡むまいが
他人同士も同然のものでしかないから、利権絡みの関係すら平気で友愛などとして扱ってしまうのである。
普遍的かつ全般的に、聖書教徒の人間関係は疎遠なものであり、決定的に「和」が欠けた
代物だといえる。非聖書教徒でも、一部の郷原(世間知らずの偽善者)が聖書教徒並みに
疎遠な人間関係しか築けないことがあるが、聖書信仰の源流である古代ユダヤ教からして、
中東の郷原(聖書詐欺師)によって拵えられたものであり、その正体は一にしているといえる。
「宗公に恵いて、神も時に怨む罔く、神も時に恫む罔き。寡妻を刑して兄弟に至り、以て家邦をも御む」
「(実際の主君の)皇祖に従って、(正統な)神々もまた怨んだり痛ましがったりすることがない。
(孔子の母のような)寡婦をも慈しんで自らの兄弟にまで至り、以って万邦を治め尽くすまでに至る。
(正統な神仏が怨み痛ましんだりすることがないのは、まず実の母兄弟への慈しみに尽くすことである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・大雅・文王之什・思斉より)
関係よりも他人行儀なものであり、聖書教徒同士での最も親密な人間関係ですら、
非聖書教徒同士での最も疎遠な交友関係ほどにも親密なものではない。
聖書教徒同士での交友関係などというものも、非聖書教徒の立場からすれば必ず一定以上に
浅はかなもので、だからこそ利権の共有関係をありのままに「友愛」などと呼びもする。
利権の共有関係なんてただの商業関係でしかなく、アカの他人同士であってもいくらでも
持ち得る関係なわけだが、聖書教徒にとっての交友なんてのは、利権が絡もうが絡むまいが
他人同士も同然のものでしかないから、利権絡みの関係すら平気で友愛などとして扱ってしまうのである。
普遍的かつ全般的に、聖書教徒の人間関係は疎遠なものであり、決定的に「和」が欠けた
代物だといえる。非聖書教徒でも、一部の郷原(世間知らずの偽善者)が聖書教徒並みに
疎遠な人間関係しか築けないことがあるが、聖書信仰の源流である古代ユダヤ教からして、
中東の郷原(聖書詐欺師)によって拵えられたものであり、その正体は一にしているといえる。
「宗公に恵いて、神も時に怨む罔く、神も時に恫む罔き。寡妻を刑して兄弟に至り、以て家邦をも御む」
「(実際の主君の)皇祖に従って、(正統な)神々もまた怨んだり痛ましがったりすることがない。
(孔子の母のような)寡婦をも慈しんで自らの兄弟にまで至り、以って万邦を治め尽くすまでに至る。
(正統な神仏が怨み痛ましんだりすることがないのは、まず実の母兄弟への慈しみに尽くすことである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・大雅・文王之什・思斉より)
悪行に伴う良心の呵責は、人が怪我をした場合に感ずる痛みなどと同じで、
健全な心身機能の発露の一種だといえる。無痛症のごとく自らの悪行に
呵責を抱くこともないのなら、絶体絶命の自滅の窮地にまでまっしぐらとも
なりかねないから、むしろ良心の呵責を抱けることは大事にすべきで、
そもそも呵責を抱かなくて済むぐらいに、浄行に徹することを重んずるべきだといえる。
良心の呵責がどういった原理に基づいて起こるのかは、大乗仏教の唯識思想によって
基本から体系化され、他の大乗仏教思想においても大命題の一つとされている。
仏教は唯心論だから、苦とか楽とかいった心性を本に据えて、世俗の現象などを
末に置くが、両者は決して別個のものではなく、善因楽果は確かに世俗的な福徳に
結び付き、悪因苦果は現実の災禍に結び付くもの。善悪にまつわる心性の苦楽は、
禍福を察知するアンテナの反応とでもいったところで、反応が正常である限りにおいて
確かに楽と福は一致し、苦と禍も一致するが、反応が異常であれば楽が禍に結び付いたり
苦が福に結び付いたり、そもそも苦楽と禍福が全く連動的な関係を持たなかったりする。
唯識思想を初歩中の初歩とする大乗仏教は、結局、苦楽と禍福の連動を正常ならしめて、
楽に基づいて福を得、苦に基づいて禍を除けることを推進するので、災禍が甚大化したり
する前からその種子を苦痛として感じ取り、その種子を摘み取ることによる安寧をも実現する。
健全な心身機能の発露の一種だといえる。無痛症のごとく自らの悪行に
呵責を抱くこともないのなら、絶体絶命の自滅の窮地にまでまっしぐらとも
なりかねないから、むしろ良心の呵責を抱けることは大事にすべきで、
そもそも呵責を抱かなくて済むぐらいに、浄行に徹することを重んずるべきだといえる。
良心の呵責がどういった原理に基づいて起こるのかは、大乗仏教の唯識思想によって
基本から体系化され、他の大乗仏教思想においても大命題の一つとされている。
仏教は唯心論だから、苦とか楽とかいった心性を本に据えて、世俗の現象などを
末に置くが、両者は決して別個のものではなく、善因楽果は確かに世俗的な福徳に
結び付き、悪因苦果は現実の災禍に結び付くもの。善悪にまつわる心性の苦楽は、
禍福を察知するアンテナの反応とでもいったところで、反応が正常である限りにおいて
確かに楽と福は一致し、苦と禍も一致するが、反応が異常であれば楽が禍に結び付いたり
苦が福に結び付いたり、そもそも苦楽と禍福が全く連動的な関係を持たなかったりする。
唯識思想を初歩中の初歩とする大乗仏教は、結局、苦楽と禍福の連動を正常ならしめて、
楽に基づいて福を得、苦に基づいて禍を除けることを推進するので、災禍が甚大化したり
する前からその種子を苦痛として感じ取り、その種子を摘み取ることによる安寧をも実現する。
儒学の場合はそんな超絶技巧な哲学探求は抜きにして、着実に福徳に結び付くことが
保証される行いと、災禍に見舞われることが紛れもない行いとを大まかに取り上げて、
後者を避けて前者を進取することによる勧善懲悪に務める。結果、「浩然の気」の
ようなすがすがしさをも得られると孟子なども言ってはいるが、儒学は別に唯心論では
ないから、内面の心性にまで遡ってああだこうだと論ずることは二の次とされている。
それにしたって、結局儒学の実践者も、結局は悪因苦果をもたらす行いを避けて、
善因楽果をもたらす行いを進取しているから、大乗仏教の唯心的な分析も、非常な
共感を以って理解することができる。聖書信者などであればそんなことはないはずで、
たとえ文面として唯識思想の内容が理解できたところで、そこに感情にまで根ざした
同意などはできないはずだ。善悪にかけて苦楽を感ずるアンテナからして狂ってしまって
いるから、別に無理に正そうとしていなくとも、それなりに正されたアンテナを持ち
合わせている儒者などが唯識論に抱けるような共感は、微塵たりとも抱けないはずである。
善因楽果、悪因苦果は、正常な感性を持ち合わせている人間にとっての普遍法則であり、
感性が狂えばいくらでもその因果関係は破綻する。しかし、感性が狂うこと自体が後々により
大きな禍いを招く因子ともなるため、結局の所、総合的な因果関係は満たされる。だから結局、
唯識のわきまえや儒行などに根ざして、正常な感性を保っておくにも越したことはないのである。
「哀楽時を失えば、殃咎必ず至る」
「哀楽が時宜に適っていなければ、後々に必ずその報いが禍と咎となってやってくる。
(悪逆非道の中に良心の呵責を抱かないでいたりするのも、哀楽の失時であるといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・荘公二十年より)
保証される行いと、災禍に見舞われることが紛れもない行いとを大まかに取り上げて、
後者を避けて前者を進取することによる勧善懲悪に務める。結果、「浩然の気」の
ようなすがすがしさをも得られると孟子なども言ってはいるが、儒学は別に唯心論では
ないから、内面の心性にまで遡ってああだこうだと論ずることは二の次とされている。
それにしたって、結局儒学の実践者も、結局は悪因苦果をもたらす行いを避けて、
善因楽果をもたらす行いを進取しているから、大乗仏教の唯心的な分析も、非常な
共感を以って理解することができる。聖書信者などであればそんなことはないはずで、
たとえ文面として唯識思想の内容が理解できたところで、そこに感情にまで根ざした
同意などはできないはずだ。善悪にかけて苦楽を感ずるアンテナからして狂ってしまって
いるから、別に無理に正そうとしていなくとも、それなりに正されたアンテナを持ち
合わせている儒者などが唯識論に抱けるような共感は、微塵たりとも抱けないはずである。
善因楽果、悪因苦果は、正常な感性を持ち合わせている人間にとっての普遍法則であり、
感性が狂えばいくらでもその因果関係は破綻する。しかし、感性が狂うこと自体が後々により
大きな禍いを招く因子ともなるため、結局の所、総合的な因果関係は満たされる。だから結局、
唯識のわきまえや儒行などに根ざして、正常な感性を保っておくにも越したことはないのである。
「哀楽時を失えば、殃咎必ず至る」
「哀楽が時宜に適っていなければ、後々に必ずその報いが禍と咎となってやってくる。
(悪逆非道の中に良心の呵責を抱かないでいたりするのも、哀楽の失時であるといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・荘公二十年より)
家の内に落ち着いてよく家内を静め、夫に万全の信頼を
置いている女ともなれば、これは良妻賢母そのものだといえる。
ソクラテスの「洞窟の比喩」のように、暗い穴蔵の奥底から外界を
観察するあり方なども、嫁いだ女があまり無闇に視野を広げたりしないで
いようとする貞順さの現れとしては良好であると、「易経」帰妹・九二にもある。
それは、夫に従順である、妻たる女のあり方としてこそ吉祥な姿なのであり、
社会に打って出る男までもがそのようなあり方であるのは、むしろ不吉なのである。
(「易経」履卦・六三でも、「洞窟の比喩」に基づくような為政が
「無知な軍政」に譬えられた上で、「凶である」と断じられている)
春秋戦国時代、極度の争乱下にあった中国において、男までもが社会への積極的な
参画を自重して、家で静かにしていることを促す学派としての「道家」があった。
それは、社会参画すなわち争乱への参画というほどにも、当時の中国が極度の乱世に
陥っていたからこそ有効たり得た言い分であり、道家の奨励するような極度の隠退志向が
婦女子や老人だけでなく、壮年の男などにまで適用されたりする状況は、やはり異常なのである。
置いている女ともなれば、これは良妻賢母そのものだといえる。
ソクラテスの「洞窟の比喩」のように、暗い穴蔵の奥底から外界を
観察するあり方なども、嫁いだ女があまり無闇に視野を広げたりしないで
いようとする貞順さの現れとしては良好であると、「易経」帰妹・九二にもある。
それは、夫に従順である、妻たる女のあり方としてこそ吉祥な姿なのであり、
社会に打って出る男までもがそのようなあり方であるのは、むしろ不吉なのである。
(「易経」履卦・六三でも、「洞窟の比喩」に基づくような為政が
「無知な軍政」に譬えられた上で、「凶である」と断じられている)
春秋戦国時代、極度の争乱下にあった中国において、男までもが社会への積極的な
参画を自重して、家で静かにしていることを促す学派としての「道家」があった。
それは、社会参画すなわち争乱への参画というほどにも、当時の中国が極度の乱世に
陥っていたからこそ有効たり得た言い分であり、道家の奨励するような極度の隠退志向が
婦女子や老人だけでなく、壮年の男などにまで適用されたりする状況は、やはり異常なのである。
春秋戦国時代における中国の争乱から避難して、日本に移住して来た弥生系の渡来人たちも、
大人の男までもが隠退を是としてしまうような事態の劣悪さを忌んで、主婦の神たる
アマテラスを日本神話上の最高神へと擁立もした。(もちろん唯一無二というわけでもない)
スサノオのような荒くれ者の男神の乱暴を忌んで岩戸に隠れ、岩戸の内から外を眺めるに
際しても、あくまで「コッソリ」と眇めに見るようなその姿は、妻や母たる女としてこそ
理想の姿なのであり、これと同じようなあり方を男が実践したなら、それこそ女々しいだけである。
そして、アマテラスこそは、人が全幅の信頼を置くべき神としても、至高であるといえる。
実物の妻や母ではなく、妻や母たる女のあるべき姿としての理想系であるアマテラスに最大の
信頼を置いて、女こそは実際にそうあり、社会に打って出る男も、アマテラスのようであろうと
する女のその姿勢にこそ信頼を置いて、自分はむしろスサノオのようであればいいのである。
スサノオはといえば、その髪の内にムカデを飼っていたりもするほどもの豪傑の神であり、姉弟神
としてアマテラスとの対極的な関係にもあればこそ、道家的な静寂さともスサノオこそは無縁である。
妻たる女が家でアマテラスのようであればこそ、夫たる男もまた世間でスサノオのようですら居られる。
そこに夫唱婦随の理想形もまたあるのであり、夫婦がそのようで居られる世の中こそは、吉祥でもある。
「事は静かなることを欲し、以て陰陽の定まる所を待つ」
「万事が静かなることを欲し、それにより陰陽雌雄が定まるのを待つ。
(自分一身の静寂などではなく、天地万物の静寂にまで志しは及ぶ)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・月令第六より)
大人の男までもが隠退を是としてしまうような事態の劣悪さを忌んで、主婦の神たる
アマテラスを日本神話上の最高神へと擁立もした。(もちろん唯一無二というわけでもない)
スサノオのような荒くれ者の男神の乱暴を忌んで岩戸に隠れ、岩戸の内から外を眺めるに
際しても、あくまで「コッソリ」と眇めに見るようなその姿は、妻や母たる女としてこそ
理想の姿なのであり、これと同じようなあり方を男が実践したなら、それこそ女々しいだけである。
そして、アマテラスこそは、人が全幅の信頼を置くべき神としても、至高であるといえる。
実物の妻や母ではなく、妻や母たる女のあるべき姿としての理想系であるアマテラスに最大の
信頼を置いて、女こそは実際にそうあり、社会に打って出る男も、アマテラスのようであろうと
する女のその姿勢にこそ信頼を置いて、自分はむしろスサノオのようであればいいのである。
スサノオはといえば、その髪の内にムカデを飼っていたりもするほどもの豪傑の神であり、姉弟神
としてアマテラスとの対極的な関係にもあればこそ、道家的な静寂さともスサノオこそは無縁である。
妻たる女が家でアマテラスのようであればこそ、夫たる男もまた世間でスサノオのようですら居られる。
そこに夫唱婦随の理想形もまたあるのであり、夫婦がそのようで居られる世の中こそは、吉祥でもある。
「事は静かなることを欲し、以て陰陽の定まる所を待つ」
「万事が静かなることを欲し、それにより陰陽雌雄が定まるのを待つ。
(自分一身の静寂などではなく、天地万物の静寂にまで志しは及ぶ)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・月令第六より)
テレビあたりが、
男にとっては狭すぎる視野を、
女にとっては広すぎる視野を
人々に植え付ける。
男なら、テレビよりも広い視野を持つべきだし、
女なら、テレビすら視野としては広すぎると言える。
電通のステマに踊らされるぐらいなら、
自分で服装や手料理を研究してるほうが、
実際、男の目から見ても魅力的だといえる。
男にとっては狭すぎる視野を、
女にとっては広すぎる視野を
人々に植え付ける。
男なら、テレビよりも広い視野を持つべきだし、
女なら、テレビすら視野としては広すぎると言える。
電通のステマに踊らされるぐらいなら、
自分で服装や手料理を研究してるほうが、
実際、男の目から見ても魅力的だといえる。
実物の農産が土地の良し悪しによって何十倍、百倍なんて豊作に結び付くなんてことも、もちろんない。
平均を100とした場合の作況指数は、どんなに豊作でも110越えあたりがいいとこで、十倍に当たる
1000はおろか、200や300すら非常識すぎて想定もされないような数値となっている。
まるでわらしべ長者のようにして、わずかな元手を頼りに何十倍、何百倍の収益を上げるという望みは、
商売や博打に限って可能となることで、農漁業はおろか、純粋な工業生産によってですら、
そこまでもの、投資ををはるかに上回る爆発的な収益などが期待できるものではない。
この世界の富は、全体的には限られたものであり、特に生産するそばから消費されていく食資源については、
生産努力の怠りが即座に飢饉などの大問題へとも発展する。だから商売人やばくち打ちのような、わずかな
努力で膨大な富を得ようとする神経で、国政までをも取り仕切るのではいい加減立ち行かなくなるのであり、
なればこそ、商人気質の人間が大権を掌握することには、必ず大きな過ちが伴うことが避けられないのである。
政商から、秦国の宰相に躍り出た呂不韋の私生児として、秦国の王統を乗っ取った贏政は、秦王として
一国だけに君臨し、諸国との競争に乗じる限りにおいては、それはそれは強大な辣腕を振るい、長平の戦い
では40万の趙兵を生き埋めにするなどの暴虐にも及び、ほぼ腕力一つで中国全土を統一するに至った。
しかし、統一秦帝国の始皇帝となって後は、努力に相応の対価を得る堅実さを解さない自らの商人気質が、
自己完結的な帝国を治めるに際しては裏目に出てしまい、商売と比べれば、そんなに爆発的な収益が
期待できるわけでもない農工業などにまで、商業や博打レベルの増産を強いた結果、あまりにも不条理な
重労働を押し付けられたことからなる民の怒りを買い、わずかな期間での帝国の自壊をも招いたのだった。
平均を100とした場合の作況指数は、どんなに豊作でも110越えあたりがいいとこで、十倍に当たる
1000はおろか、200や300すら非常識すぎて想定もされないような数値となっている。
まるでわらしべ長者のようにして、わずかな元手を頼りに何十倍、何百倍の収益を上げるという望みは、
商売や博打に限って可能となることで、農漁業はおろか、純粋な工業生産によってですら、
そこまでもの、投資ををはるかに上回る爆発的な収益などが期待できるものではない。
この世界の富は、全体的には限られたものであり、特に生産するそばから消費されていく食資源については、
生産努力の怠りが即座に飢饉などの大問題へとも発展する。だから商売人やばくち打ちのような、わずかな
努力で膨大な富を得ようとする神経で、国政までをも取り仕切るのではいい加減立ち行かなくなるのであり、
なればこそ、商人気質の人間が大権を掌握することには、必ず大きな過ちが伴うことが避けられないのである。
政商から、秦国の宰相に躍り出た呂不韋の私生児として、秦国の王統を乗っ取った贏政は、秦王として
一国だけに君臨し、諸国との競争に乗じる限りにおいては、それはそれは強大な辣腕を振るい、長平の戦い
では40万の趙兵を生き埋めにするなどの暴虐にも及び、ほぼ腕力一つで中国全土を統一するに至った。
しかし、統一秦帝国の始皇帝となって後は、努力に相応の対価を得る堅実さを解さない自らの商人気質が、
自己完結的な帝国を治めるに際しては裏目に出てしまい、商売と比べれば、そんなに爆発的な収益が
期待できるわけでもない農工業などにまで、商業や博打レベルの増産を強いた結果、あまりにも不条理な
重労働を押し付けられたことからなる民の怒りを買い、わずかな期間での帝国の自壊をも招いたのだった。
削除(by投稿者)
削除(by投稿者)
秦帝国崩壊後、短期間の戦乱の後に統一漢帝国の初代皇帝となった劉邦は、万里の長城や阿房宮、
始皇帝陵墓の建設といった非常識な規模の土木事業によっても民を圧迫していた秦朝を反面教師として、
なるべく民への法的な締め付けなどを緩和していく政策を敷いた。あまりにも放任主義であり過ぎた
ために、王宮でのチャンバラごっこなどの乱暴すらもがまかり通ったままでいたため、劉邦も儒者の
叔孫通らに、礼楽による作為的な規律化を依頼したと「史記」などにもあるが、それも、「法権」という
強権によって民を締め付けることを劉邦が極力避けていたからであり、むしろ秦帝国が民に強いていた
ような法規による強権支配が存在しなければこそ、礼楽による規律化が実施された実例ともなっている。
劉邦は、政商の私生児だった贏政などとは違い、田舎の無名の百姓の末っ子だった。
その、若い頃の素行も決して誉められたようなものではなく、いてもいなくてもいいような末子としての
立場にかまけて、家の仕事の手伝いもほっぽらかして街をほっつき歩いていたという逸話までもがある。
しかし、それほどにもいい加減な生まれ育ちでありながら、商人気質によって帝国全土を支配しようとした
秦朝などとは違って、劉邦の興した漢朝は前後あわせて400年以上もの治世を実現するに至った。それは、
いくらゴロツキ同然の出自とはいえど、農家の血筋からなる劉邦の気質が、わずかな努力で膨大な富を
せしめるような博打志向を由としてはいなかったからで、国政に際しては必ず重要となる食資源の確保
などについても、子々孫々の代々に至るまで堅実な見通しを立てていくことができるものだったからだ。
始皇帝陵墓の建設といった非常識な規模の土木事業によっても民を圧迫していた秦朝を反面教師として、
なるべく民への法的な締め付けなどを緩和していく政策を敷いた。あまりにも放任主義であり過ぎた
ために、王宮でのチャンバラごっこなどの乱暴すらもがまかり通ったままでいたため、劉邦も儒者の
叔孫通らに、礼楽による作為的な規律化を依頼したと「史記」などにもあるが、それも、「法権」という
強権によって民を締め付けることを劉邦が極力避けていたからであり、むしろ秦帝国が民に強いていた
ような法規による強権支配が存在しなければこそ、礼楽による規律化が実施された実例ともなっている。
劉邦は、政商の私生児だった贏政などとは違い、田舎の無名の百姓の末っ子だった。
その、若い頃の素行も決して誉められたようなものではなく、いてもいなくてもいいような末子としての
立場にかまけて、家の仕事の手伝いもほっぽらかして街をほっつき歩いていたという逸話までもがある。
しかし、それほどにもいい加減な生まれ育ちでありながら、商人気質によって帝国全土を支配しようとした
秦朝などとは違って、劉邦の興した漢朝は前後あわせて400年以上もの治世を実現するに至った。それは、
いくらゴロツキ同然の出自とはいえど、農家の血筋からなる劉邦の気質が、わずかな努力で膨大な富を
せしめるような博打志向を由としてはいなかったからで、国政に際しては必ず重要となる食資源の確保
などについても、子々孫々の代々に至るまで堅実な見通しを立てていくことができるものだったからだ。
専門的な能力のある君子士人が未だ健在である時代ならまだしも、もはやそんな人材は絶えてしまった
春秋戦国時代末期の中国や、今の日本などにおいて、仮に国政を任せるに際して最善に相当する人物が
存在するとすれば、それは劉邦のような、努力に相応の対価を得ようとする百姓気質の持ち主のはずであり、
わらしべ長者ばかりを期待する贏政のような商人気質の持ち主などではないはずである。むろん、今の
時代は商人気質の持ち主ばかりが権力に食い入っている時代なので、権力機構全般を刷新していくので
ないと、劉邦のような堅実志向の持ち主が権力の座に就くことも、とうてい叶わないわけではあるが。
「先王能く礼を修めて以って義に達し、信を体して以って順に達す。故に此れ順の実なり」
「昔の偉大な王君たちは、自らが礼儀を修めることで道義の通用する所に達し、信用に値する
あり方を体現することで民からの従順をも得た。そこにこそ、従順さという実りがあったのである。
(口先だけの実る実る詐欺などを信条としているから、聖書信者に従順さは実らないのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・礼運第九より)
春秋戦国時代末期の中国や、今の日本などにおいて、仮に国政を任せるに際して最善に相当する人物が
存在するとすれば、それは劉邦のような、努力に相応の対価を得ようとする百姓気質の持ち主のはずであり、
わらしべ長者ばかりを期待する贏政のような商人気質の持ち主などではないはずである。むろん、今の
時代は商人気質の持ち主ばかりが権力に食い入っている時代なので、権力機構全般を刷新していくので
ないと、劉邦のような堅実志向の持ち主が権力の座に就くことも、とうてい叶わないわけではあるが。
「先王能く礼を修めて以って義に達し、信を体して以って順に達す。故に此れ順の実なり」
「昔の偉大な王君たちは、自らが礼儀を修めることで道義の通用する所に達し、信用に値する
あり方を体現することで民からの従順をも得た。そこにこそ、従順さという実りがあったのである。
(口先だけの実る実る詐欺などを信条としているから、聖書信者に従順さは実らないのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・礼運第九より)
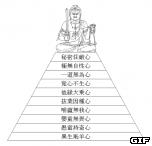 心の貧しさが、人間を異生羝羊心に繋ぎとめる。
心の貧しさが、人間を異生羝羊心に繋ぎとめる。 貧しさから脱却していこうとする時に愚童持斎心に目覚め、嬰童無畏心に至って
概ね満足した心となる。唯蘊無我心以上からが積極的な心の豊かさの追求となり、
他縁大乗心以上が心の豊かさの衆生への回向をも兼ねる境地となる。
心が貧しいから、物質的な虚栄に固執する。
傍から見れば明らかに過剰に見える物質的、金銭的な貪りを
完全に当たり前なこととして嗜み、それを全く恥とも思わない。
されば、心が豊かでありさえすれば、全く物質的な豊かさを追い求めないのかといえば、
必ずしもそんなこともない。むしろ、余裕を以ってモノやカネを扱えるようになることから、
物質的、金銭的な豊かさの追い求め方が洗練される。人は誰しもいつかは死ぬのであれ、
それまではモノやカネにも頼りつつ生きていくのだから、その生き方を心の豊かさと
共に充実させていく上で、洗練されたカネやモノの扱い方をも追求していくのである。
 事実上の日本の首都でもある、世界最大の都市圏東京の都市構造などと比べて、
事実上の日本の首都でもある、世界最大の都市圏東京の都市構造などと比べて、 古都京都や奈良、鎌倉などの伝統的な街並み、その他諸々の古寺名刹などの伝統的建造物は、
明らかに小規模なものではあるが、その造型や様式は決して、東京のそれに勝るとも劣らないものばかりである。
のみならず、法隆寺のように1000年経っても壊れない程もの秀逸な建築技術までもが導入されても居て、
せいぜい耐用年数が100年やそこらである、現代の高層ビルなどの土建物には見られない、
子々孫々の代々に至るまでの、末永い需用の見通しまでもが立てられていることが分かる。
そこにこそ、自分一身、一代限りの栄華ですらあればそれでいいなどという、
仮初めに終始したりすることのない、より洗練された、物質的な豊かさの希求までもがある。
先々までの見通しも立てられない、異生羝羊心止まりの心では、ただ心そのものが貧しいだけでなく、心の貧しさの
反動としての物質的な貪りまでもが行き当たりばったりなものばかりと化してしまって、見るに堪えないものとなる。
だから、物質的な豊かさを追い求める上でも、我が心が貧しいよりも豊かであるほうがいいのであり、何も、
出家修業者のように物質的豊かさを捨て去ることと共にばかり、心の豊かさを追い求めるのが能でもないのである。
「君子は利を尽くさず、以って民に遺す。〜大夫は羊に座せず」
「君子は自らの一身のために利得を尽くしたりはしない。例えば、大夫は羊を殺してその肉を
食うようなことがあったとしても、その毛皮までをも独り占めにして絨毯代わりにしたりはしないように。
(羊に相当するような人物が独り占めにしていたような利得も、君子は独り占めにはしないのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・坊記第三十より)
口先だけでのいい腐し予言宗教の系譜としては、
確かにイエキリが最終にして最悪の預言者だったに違いない。
それと比べればムハンマドなども、文盲としての純朴さや
軍人としての豊富な経験などから、非常に堅実な預言を果たしたといえ、
その堅実さこそが、イエキリの思い上がりまみれな物言いをありがたがる
新約信者などからすれば、「余計なもの」としても映るのである。
中国史でいえば、ムハンマドの性格は漢の高祖劉邦あたりにも近似している一方、
イエキリの性格は、秦帝国の宦官趙高あたりに似ている。言辞よりも実地経験を
重んずる傾向が、成人に至るまでの文盲と豊富な軍事経験という、共通した
境遇によって劉邦やムハンマドには具わったのに対し、宦官や妾腹の私生児
のような、人間扱いすらなかなかされにくい立場から、口先だけでのいい加減な
虚言癖を募らせていった点が、趙高とイエキリとでは共通しているといえる。
(むろん、妾腹の私生児や宦官の中にも、孔子や司馬遷のように、自助努力に
よって偉業を成した聖人もいるのだから、決して不可避なことなどでもなかった)
旧約から新約に至る諸々のユダヤ人の不実まみれな預言も、
全く実地性に根ざしていないのではなく、当時から政商詐欺集団として
中東やローマで悪行を働いていた、その経験の豊かさに確かに根ざしている。
しかし、中東やローマではユダヤ人の聖書詐欺師としての実情は記録されず、
政商詐欺を高度にカルト教義化した記録だけが新旧約聖書として遺された。
一方で、同時期の中国では「春秋」や「史記」のように、権力道徳を失った
春秋戦国時代の為政者たちの、政商や食客や縦横家をも駆使しての権力犯罪
こそが詳密に記録され、権力犯罪を正当化する寓意の構築を試みた公孫竜などの
名家(詭弁家)のほうが弾圧されるなり、批判の対象とされるなりしている。
確かにイエキリが最終にして最悪の預言者だったに違いない。
それと比べればムハンマドなども、文盲としての純朴さや
軍人としての豊富な経験などから、非常に堅実な預言を果たしたといえ、
その堅実さこそが、イエキリの思い上がりまみれな物言いをありがたがる
新約信者などからすれば、「余計なもの」としても映るのである。
中国史でいえば、ムハンマドの性格は漢の高祖劉邦あたりにも近似している一方、
イエキリの性格は、秦帝国の宦官趙高あたりに似ている。言辞よりも実地経験を
重んずる傾向が、成人に至るまでの文盲と豊富な軍事経験という、共通した
境遇によって劉邦やムハンマドには具わったのに対し、宦官や妾腹の私生児
のような、人間扱いすらなかなかされにくい立場から、口先だけでのいい加減な
虚言癖を募らせていった点が、趙高とイエキリとでは共通しているといえる。
(むろん、妾腹の私生児や宦官の中にも、孔子や司馬遷のように、自助努力に
よって偉業を成した聖人もいるのだから、決して不可避なことなどでもなかった)
旧約から新約に至る諸々のユダヤ人の不実まみれな預言も、
全く実地性に根ざしていないのではなく、当時から政商詐欺集団として
中東やローマで悪行を働いていた、その経験の豊かさに確かに根ざしている。
しかし、中東やローマではユダヤ人の聖書詐欺師としての実情は記録されず、
政商詐欺を高度にカルト教義化した記録だけが新旧約聖書として遺された。
一方で、同時期の中国では「春秋」や「史記」のように、権力道徳を失った
春秋戦国時代の為政者たちの、政商や食客や縦横家をも駆使しての権力犯罪
こそが詳密に記録され、権力犯罪を正当化する寓意の構築を試みた公孫竜などの
名家(詭弁家)のほうが弾圧されるなり、批判の対象とされるなりしている。
これは、中国には孔子や司馬遷のような偉大な文人、そして高祖劉邦のような
本物の権力道徳を持ち直させるだけの器量を持つ名君が存在していた一方で、
西洋やイスラエルにはそのような偉人が存在せず、むしろ権力犯罪を寓意に
よって正当化する詭弁や虚言などのほうが持て囃されていたことを原因としている。
結局、孔子や劉邦や司馬遷のような偉人が中国に存在し得たのは、中国が
世界的に見れば日出ずる東方に位置する世界だったからで、日光を追い求めよう
とする陽性志向が当時の多くの中国人にも豊富だったから、その中から
孔子や劉邦や司馬遷のような偉人が、選抜的に生まれ得たのだといえる。
その逆に、日没する西方にはそれだけの陽性志向が量として存在しなかったから、
むしろ権力犯罪をカルト化した後の製品(新旧約)をあり難がることのほうが
優先されて、仮に孔子や劉邦や司馬遷のような志しの持ち主がいたとしても、
大多数の権勢に圧されて十分な能力を発揮することもできなかったのである。
地球の丸さがすでに全人類に把握されている今なら、中国人や日本人だからといって
陽性志向を蓄えるとも限らないし、西洋人だからといって陽性志向を損なうとも
限らない。しかし、昔は洋の東西に伴う陰陽志向の分岐が遍在していたのであり、
昔についてはやはりその異質性を踏まえつつ論考の対象とすべきなのである。
いま東洋人も西洋人も平等であるとした所で、過去には確かな差異があったのである。
「行いて著らかならず、習いて察らかならず、終身之れに由るも其の道を知らざる者は衆し」
「何をやってもその意味が明らかでなく、何を習っても詳らかに知ることはなく、終身
頼りにしながらも、最後までその本道を知らない者は結構多い。(四書五経の記述の逆の
実践を促しているだけでしかないのが新旧約聖書の記述なわけだが、巧みな寓意による
カルト教義化が仕組まれていることもあって、最後まで誰もそれに気づこうとしない。
最初から最後まで、新旧約の受容や実践は、孟子のこの言葉通りであることで一貫している)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句上・五より)
本物の権力道徳を持ち直させるだけの器量を持つ名君が存在していた一方で、
西洋やイスラエルにはそのような偉人が存在せず、むしろ権力犯罪を寓意に
よって正当化する詭弁や虚言などのほうが持て囃されていたことを原因としている。
結局、孔子や劉邦や司馬遷のような偉人が中国に存在し得たのは、中国が
世界的に見れば日出ずる東方に位置する世界だったからで、日光を追い求めよう
とする陽性志向が当時の多くの中国人にも豊富だったから、その中から
孔子や劉邦や司馬遷のような偉人が、選抜的に生まれ得たのだといえる。
その逆に、日没する西方にはそれだけの陽性志向が量として存在しなかったから、
むしろ権力犯罪をカルト化した後の製品(新旧約)をあり難がることのほうが
優先されて、仮に孔子や劉邦や司馬遷のような志しの持ち主がいたとしても、
大多数の権勢に圧されて十分な能力を発揮することもできなかったのである。
地球の丸さがすでに全人類に把握されている今なら、中国人や日本人だからといって
陽性志向を蓄えるとも限らないし、西洋人だからといって陽性志向を損なうとも
限らない。しかし、昔は洋の東西に伴う陰陽志向の分岐が遍在していたのであり、
昔についてはやはりその異質性を踏まえつつ論考の対象とすべきなのである。
いま東洋人も西洋人も平等であるとした所で、過去には確かな差異があったのである。
「行いて著らかならず、習いて察らかならず、終身之れに由るも其の道を知らざる者は衆し」
「何をやってもその意味が明らかでなく、何を習っても詳らかに知ることはなく、終身
頼りにしながらも、最後までその本道を知らない者は結構多い。(四書五経の記述の逆の
実践を促しているだけでしかないのが新旧約聖書の記述なわけだが、巧みな寓意による
カルト教義化が仕組まれていることもあって、最後まで誰もそれに気づこうとしない。
最初から最後まで、新旧約の受容や実践は、孟子のこの言葉通りであることで一貫している)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句上・五より)
自らの家族を尊重しようともしない妾腹の私生児、
イエスキリストあたりを信奉しているようなものこそは、
まったく自分のことしか考えていないのでもある。
母子家庭育ちの妾腹の私生児という、義父持ちのイエキリ以上にも
不遇な環境で生まれ育ちながら、自ら進んで先祖供養をも尽くして、
正式に孔家の跡取りともなった孔子こそは、自分のため以上にも、
一家のために生きようとする誠実さがあった。イエキリにはそんな
誠実さはなく、ただ自分のことしか頭になかったから、本当の父親
の身元も確かめず、義父の家督を継ぐでもなく、自らを「神の子」
などと呼ばわった。ここにこそ最悪級の自意識過剰があるといえる。
神仏への帰依などを待つまでもなく、人は人である以上は、まず家族のために
生きねばならない宿命を持つ。問題は、そうであることを尊重できるか否かであって、
孔子は尊重していたから先祖供養や家督の継承にも努めた一方、イエキリは全く尊重など
していなかったから、実父も養父も蔑ろにした「神の子」邪教をでっち上げたのである。
人にとって最も不可避である、家族の関係すら蔑ろにする所に、自意識過剰の発端がある。
それをいくら後付けで「超越神への帰依」などによって埋め合わせようとしてみた所で、
始めから家族をも尊重していようとする場合ほどもの自己の虚心さは、決して備わらない。
イエスキリストあたりを信奉しているようなものこそは、
まったく自分のことしか考えていないのでもある。
母子家庭育ちの妾腹の私生児という、義父持ちのイエキリ以上にも
不遇な環境で生まれ育ちながら、自ら進んで先祖供養をも尽くして、
正式に孔家の跡取りともなった孔子こそは、自分のため以上にも、
一家のために生きようとする誠実さがあった。イエキリにはそんな
誠実さはなく、ただ自分のことしか頭になかったから、本当の父親
の身元も確かめず、義父の家督を継ぐでもなく、自らを「神の子」
などと呼ばわった。ここにこそ最悪級の自意識過剰があるといえる。
神仏への帰依などを待つまでもなく、人は人である以上は、まず家族のために
生きねばならない宿命を持つ。問題は、そうであることを尊重できるか否かであって、
孔子は尊重していたから先祖供養や家督の継承にも努めた一方、イエキリは全く尊重など
していなかったから、実父も養父も蔑ろにした「神の子」邪教をでっち上げたのである。
人にとって最も不可避である、家族の関係すら蔑ろにする所に、自意識過剰の発端がある。
それをいくら後付けで「超越神への帰依」などによって埋め合わせようとしてみた所で、
始めから家族をも尊重していようとする場合ほどもの自己の虚心さは、決して備わらない。
もしも、出家して家族との縁を断つというのなら、その時には自己を徹底して否定し尽くす
酷烈な精進修行にでも励めばいいのであり、それにより自我を完全に捨て去れた時にまた
初めて、家族のために生きようとする場合ていどの虚心さが備わるというものだ。
自分が無駄メシぐらいの次男坊や三男坊だったりした場合、あるいは親が世間に顔向けもできない
ほどもの重大犯罪をやらかした場合などに、出家修行という手段によって虚心さを得ようとするのも
一つの手ではあるが、基本はまず家族のために生きることで、自らの虚心さを養うのが人の常である。
家族のために生きること、さらにはそれを尊重することで、自意識過剰の思い上がりをも抑止する。
信仰者が神のために、商売人が顧客のために生きようとしたりすることも、人が家族のために
生きようとする場合ほどもの虚心さを保障するものでは決してないので、それらの奉仕意識が却って
家族の尊重を蔑ろにしたりすることがあるのなら、自意識過剰の悪化もまた避けられるものではない。
社会的な職務や神への帰依なども、家族の尊重に上乗せできるだけの代物であって初めて、自意識過剰の
抑止を妨げることなく推進するものともなるので、そういう職業や信教を精査することも重要だといえる。
「古えの学者は己れの為めにし、今の学者は人の為めにす」
「昔の学者は自分のために勉強したが、今の学者は他人のためにばかり勉強している。
(自分のことを第一としたほうがいい実例。聖書圏には自己修養の学が決定的に欠けてもいる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——憲問第十四・二五より)
酷烈な精進修行にでも励めばいいのであり、それにより自我を完全に捨て去れた時にまた
初めて、家族のために生きようとする場合ていどの虚心さが備わるというものだ。
自分が無駄メシぐらいの次男坊や三男坊だったりした場合、あるいは親が世間に顔向けもできない
ほどもの重大犯罪をやらかした場合などに、出家修行という手段によって虚心さを得ようとするのも
一つの手ではあるが、基本はまず家族のために生きることで、自らの虚心さを養うのが人の常である。
家族のために生きること、さらにはそれを尊重することで、自意識過剰の思い上がりをも抑止する。
信仰者が神のために、商売人が顧客のために生きようとしたりすることも、人が家族のために
生きようとする場合ほどもの虚心さを保障するものでは決してないので、それらの奉仕意識が却って
家族の尊重を蔑ろにしたりすることがあるのなら、自意識過剰の悪化もまた避けられるものではない。
社会的な職務や神への帰依なども、家族の尊重に上乗せできるだけの代物であって初めて、自意識過剰の
抑止を妨げることなく推進するものともなるので、そういう職業や信教を精査することも重要だといえる。
「古えの学者は己れの為めにし、今の学者は人の為めにす」
「昔の学者は自分のために勉強したが、今の学者は他人のためにばかり勉強している。
(自分のことを第一としたほうがいい実例。聖書圏には自己修養の学が決定的に欠けてもいる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——憲問第十四・二五より)
いま、世界で安寧に与れている人間というのは、一人もいない。
自己修練によって「心頭滅却すれば火もまた涼し」的なやせ我慢気味の安楽を
自得している人間がいたとしたところで、それは別に「誰かから授かった安楽」
などであるわけではない。そうではなく、外的な境遇に即して安らぎに
与れている人間がいるのかといえば、今は一人もいないのである。
歴史的基準に即しても、特に安楽な人間がいない時代であるし、人間の心性の
普遍的基準に根ざしても、安楽として扱えるほどにも安楽な人間がいない時代である。
その中で「比較的安楽っぽい人間」がいたとすれば、それは
「比較的苦悩が少ない人間」であるというばかりのことである。
積極的に安楽が多いというのではなく、ただ苦悩の程がマシであるというだけのこと。
中には、苦悩が少なめであることを「安楽だ」などと勘違いしている人間もいるが、
それは真の安楽も、その実現の可能さも知らない狭劣見の持ち主だからこそのこと。
真の安楽はどこにもなく、ただ苦悩の程がより酷いか、マシなほうかという違いだけが存在
する現状において、じゃあ世界で「勝ち組」扱いされているような人間のほうが苦悩が少なく、
「負け組」扱いされているような人間のほうが苦悩が多いかといえば、そういうわけでもない。
「行動即犯罪」という程にも罪障まみれと化してしまっている今の世界において、活動に
積極的であろうとする者ほど苦悩が多くなり、消極的でいようとする者ほど苦悩が少なくて済む。
実質問題、勝ち組であろうとしている人間こそは一定以上に積極的に活動しても
いるので、一定以上に苦悩も多く、負け組に甘んじている人間のほうはといえば、
これまた牛馬のような隷従活動に没頭させられている場合などには、苦悩が多い一方、
そんなに活動に積極的でもないという場合もあるので、その場合には苦悩も少ない。
自己修練によって「心頭滅却すれば火もまた涼し」的なやせ我慢気味の安楽を
自得している人間がいたとしたところで、それは別に「誰かから授かった安楽」
などであるわけではない。そうではなく、外的な境遇に即して安らぎに
与れている人間がいるのかといえば、今は一人もいないのである。
歴史的基準に即しても、特に安楽な人間がいない時代であるし、人間の心性の
普遍的基準に根ざしても、安楽として扱えるほどにも安楽な人間がいない時代である。
その中で「比較的安楽っぽい人間」がいたとすれば、それは
「比較的苦悩が少ない人間」であるというばかりのことである。
積極的に安楽が多いというのではなく、ただ苦悩の程がマシであるというだけのこと。
中には、苦悩が少なめであることを「安楽だ」などと勘違いしている人間もいるが、
それは真の安楽も、その実現の可能さも知らない狭劣見の持ち主だからこそのこと。
真の安楽はどこにもなく、ただ苦悩の程がより酷いか、マシなほうかという違いだけが存在
する現状において、じゃあ世界で「勝ち組」扱いされているような人間のほうが苦悩が少なく、
「負け組」扱いされているような人間のほうが苦悩が多いかといえば、そういうわけでもない。
「行動即犯罪」という程にも罪障まみれと化してしまっている今の世界において、活動に
積極的であろうとする者ほど苦悩が多くなり、消極的でいようとする者ほど苦悩が少なくて済む。
実質問題、勝ち組であろうとしている人間こそは一定以上に積極的に活動しても
いるので、一定以上に苦悩も多く、負け組に甘んじている人間のほうはといえば、
これまた牛馬のような隷従活動に没頭させられている場合などには、苦悩が多い一方、
そんなに活動に積極的でもないという場合もあるので、その場合には苦悩も少ない。
勝ち組であれば必ず一定以上に苦悩が多く、負け組は個々によって勝ち組並みに
苦悩が多かったり、意外と少なかったりする。だから、苦悩の多少は必ずしも勝ち組か
負け組かには依らないが、負け組であることと引き換えに活動に消極的である者こそは、
特筆して今の世の中でも苦悩が少ないほうであるということだけはいえる。
苦悩をできる限り少なくするために、活動に消極的でばかりあろうとするのも、確かに
異常なことである。何をやっても強盗殺人やその従犯にしかなり得ない、総員犯罪者状態の
世の中である場合に限って正当性を帯びる活動規範であり、少なからず積極的な活動が
徳行に結び付くようになったならば、すぐにでも改めなければならない規範でもあるといえる。
多大なる苦悩が積極的な悪行によってもたらされるのと同じように、重畳なる安楽もまた、
積極的な善行によってこそもたらされる。単なる不動は善因楽果悪因苦果の断滅というばかりで、
本格の出家修行者でもない限りは、そればかりに没頭し続けていればいいものでもない。
というよりも、一般人すら不動こそが最善となってしまうような世の中自体が、そう長く持つ
ものでもないので、いつまでも不動ばかりに甘んじていることなどを思い煩う必要もないといえる。
「嗟あ爾じ君子よ、恒には安処すること無かれ。
爾じの位を靖共し、正直に是れ与せよ。神も之れを聴きて、以て女じを穀せん。
(ここから既出)嗟あ爾じ君子よ、恒には安息すること無かれ。
爾じの位を靖共し、是れ正直を好め。神も之れを聴きて、爾じに景福を介わらん」
「ああ、君子たるものよ、いつまでも安処していたりはするな。そなたの勤めを謹んで果たし、
正しい人々の味方であれ。さすれば神もそなたを聞こし召したまいて、そなたを加護するであろう。
ああ、君子たるものよ、いつまでも安息していたりはするな。そなたの勤めを謹んで果たし、
正しい人々こそを好んで居よ。さすれば神もそなたを聞こし召して、そなたに慶福を賜うであろう」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・小雅・北山之什・小明より)
苦悩が多かったり、意外と少なかったりする。だから、苦悩の多少は必ずしも勝ち組か
負け組かには依らないが、負け組であることと引き換えに活動に消極的である者こそは、
特筆して今の世の中でも苦悩が少ないほうであるということだけはいえる。
苦悩をできる限り少なくするために、活動に消極的でばかりあろうとするのも、確かに
異常なことである。何をやっても強盗殺人やその従犯にしかなり得ない、総員犯罪者状態の
世の中である場合に限って正当性を帯びる活動規範であり、少なからず積極的な活動が
徳行に結び付くようになったならば、すぐにでも改めなければならない規範でもあるといえる。
多大なる苦悩が積極的な悪行によってもたらされるのと同じように、重畳なる安楽もまた、
積極的な善行によってこそもたらされる。単なる不動は善因楽果悪因苦果の断滅というばかりで、
本格の出家修行者でもない限りは、そればかりに没頭し続けていればいいものでもない。
というよりも、一般人すら不動こそが最善となってしまうような世の中自体が、そう長く持つ
ものでもないので、いつまでも不動ばかりに甘んじていることなどを思い煩う必要もないといえる。
「嗟あ爾じ君子よ、恒には安処すること無かれ。
爾じの位を靖共し、正直に是れ与せよ。神も之れを聴きて、以て女じを穀せん。
(ここから既出)嗟あ爾じ君子よ、恒には安息すること無かれ。
爾じの位を靖共し、是れ正直を好め。神も之れを聴きて、爾じに景福を介わらん」
「ああ、君子たるものよ、いつまでも安処していたりはするな。そなたの勤めを謹んで果たし、
正しい人々の味方であれ。さすれば神もそなたを聞こし召したまいて、そなたを加護するであろう。
ああ、君子たるものよ、いつまでも安息していたりはするな。そなたの勤めを謹んで果たし、
正しい人々こそを好んで居よ。さすれば神もそなたを聞こし召して、そなたに慶福を賜うであろう」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・小雅・北山之什・小明より)
「私は自分の信じているものが完全に間違っていてもそれを信じます」という
完全誤謬信仰の論理が脳内で確立されることが、聖書信仰に敬虔であることとも同義である。
完全に間違っていること、たとえば「1+1=3」という誤算を正答と断定すること、
それは別に、必ずしも完全誤謬信仰に依らずとも、ただ「馬鹿」であるというだけでもできる。
帝国海軍の東郷平八郎も、1+1を3にも4にもする気勢で日露戦争に臨んだというし、論理性を
逸脱した感情的な奮起が馬鹿となって、1+1を3や4と断ずることもまたできるのである。
単なる馬鹿と完全誤謬信仰の違いは、馬鹿は何に対しても適用ができる一方、
完全誤謬信仰は信仰対象にだけ適用される点にある。常日ごろからの異様な奮起や、
酒の酔いにかられての勢いなどで、馬鹿は何に対しても「1+1=3」のごとき無理をあてこすれる。
一方、完全誤謬信仰者は、信仰対象以外にまで妄りに「1+1=3」のような無理をあてこすらず、
(十字架のような)信仰対象に依拠する限りにおいてのみ、「1+1=3」をもYesとするのである。
だから、信教の価値が保証されている限りにおいて、完全誤謬信仰者の人格などが疑われる
こともないのに対し、馬鹿は始めから人格を疑われ続け、蔑みや嘲笑の対象ともなり続ける。
完全誤謬信仰の論理が脳内で確立されることが、聖書信仰に敬虔であることとも同義である。
完全に間違っていること、たとえば「1+1=3」という誤算を正答と断定すること、
それは別に、必ずしも完全誤謬信仰に依らずとも、ただ「馬鹿」であるというだけでもできる。
帝国海軍の東郷平八郎も、1+1を3にも4にもする気勢で日露戦争に臨んだというし、論理性を
逸脱した感情的な奮起が馬鹿となって、1+1を3や4と断ずることもまたできるのである。
単なる馬鹿と完全誤謬信仰の違いは、馬鹿は何に対しても適用ができる一方、
完全誤謬信仰は信仰対象にだけ適用される点にある。常日ごろからの異様な奮起や、
酒の酔いにかられての勢いなどで、馬鹿は何に対しても「1+1=3」のごとき無理をあてこすれる。
一方、完全誤謬信仰者は、信仰対象以外にまで妄りに「1+1=3」のような無理をあてこすらず、
(十字架のような)信仰対象に依拠する限りにおいてのみ、「1+1=3」をもYesとするのである。
だから、信教の価値が保証されている限りにおいて、完全誤謬信仰者の人格などが疑われる
こともないのに対し、馬鹿は始めから人格を疑われ続け、蔑みや嘲笑の対象ともなり続ける。
仮に、信教の価値の絶対性などが認められなくなれば、完全誤謬信仰者も即座に単なる馬鹿並みの
扱いを受けるようになる。今という時代はまだ、信教の保護を通じて完全誤謬信仰が保護されて
いる時代だからこそ、馬鹿までもが連動的に社会的な市民権を得てしまっているところもあるが、
完全誤謬信仰への保護が取り払われることを通じて、馬鹿もろともに市民権を失うこととなる。
むろん、全ての信教が完全誤謬信仰なのではなく、仏教のように誤謬を排した真実真理のみを
信仰対象とする信教もあるので、全ての信教の価値保証を解消するのではなく、あらゆるカルト
の源泉でもある完全誤謬信仰に限って、信教としての保護対象から外すようにせねばならない。
信教全般を禁止するわけではないが、完全誤謬信仰を奨励する信教だけは「邪教」として
取り締りの対象とする。これが邪教取締りの指針としてもうってつけとなり、邪教の蔓延
によってお株を奪われていた諸々の正統な信教の息を吹き返させる機縁ともなるのである。
「水は流れて而かも盈たず、険を行きて而かも其の信を失わざる」
「水が低いところ、低いところへと流れ落ちてひと所に止まっていないようにして、
険難に臨むことがあったとしても、決して信じる所のものを失わない。(これが正信の
不壊なる原理であり、一ところの言葉に束縛されるといようなことではないのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・坎・彖伝より)
扱いを受けるようになる。今という時代はまだ、信教の保護を通じて完全誤謬信仰が保護されて
いる時代だからこそ、馬鹿までもが連動的に社会的な市民権を得てしまっているところもあるが、
完全誤謬信仰への保護が取り払われることを通じて、馬鹿もろともに市民権を失うこととなる。
むろん、全ての信教が完全誤謬信仰なのではなく、仏教のように誤謬を排した真実真理のみを
信仰対象とする信教もあるので、全ての信教の価値保証を解消するのではなく、あらゆるカルト
の源泉でもある完全誤謬信仰に限って、信教としての保護対象から外すようにせねばならない。
信教全般を禁止するわけではないが、完全誤謬信仰を奨励する信教だけは「邪教」として
取り締りの対象とする。これが邪教取締りの指針としてもうってつけとなり、邪教の蔓延
によってお株を奪われていた諸々の正統な信教の息を吹き返させる機縁ともなるのである。
「水は流れて而かも盈たず、険を行きて而かも其の信を失わざる」
「水が低いところ、低いところへと流れ落ちてひと所に止まっていないようにして、
険難に臨むことがあったとしても、決して信じる所のものを失わない。(これが正信の
不壊なる原理であり、一ところの言葉に束縛されるといようなことではないのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・坎・彖伝より)
「其の進むこと鋭き者は、其の退くことも速やかなり」
「鋭く進取するものほど、撤退するときも速やかである。
(『儒者は進取を共にするは難くも、守成を共にするは可なり』と『史記』叔孫通列伝にもある。
始皇帝や項羽のように利得を鋭く先取りしようとするものほど、失う時もあっという間なのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句上・四四より)
「鋭く進取するものほど、撤退するときも速やかである。
(『儒者は進取を共にするは難くも、守成を共にするは可なり』と『史記』叔孫通列伝にもある。
始皇帝や項羽のように利得を鋭く先取りしようとするものほど、失う時もあっという間なのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句上・四四より)
 諸刃の剣は、善悪の彼岸。
諸刃の剣は、善悪の彼岸。 実際に、善悪を超越するということは、生身の人間にとっては
そうそうに付き合いきれもしないもので、多少は立ち会うことが
あったとしても、世間全般としては敬遠されることが通例となっている。
安直に言って、諸刃の剣は危険である。
切れ味がどうというよりも、形状として自他を共に傷つけがちなもの。
諸刃では技巧的な技なども自傷に繋がりやすいから、自傷を不孝の一つと見なす
儒学の思想にも根ざして、日本などでも片刃の剣技のほうが発達してきた。
一方で、日本で片刃の剣技が発達したのは、そこに「勧善懲悪」の意図までもがあったから、
十七条憲法で、勧善懲悪を「古えの良き典」として賛じていた聖徳太子が、七星剣という
片刃の鉄剣をも佩いていたように、四書五経や十七条憲法にあるような勧善懲悪の則を
実践していくためにこそ、片刃の長剣をも用いての剣技を発達させていったのである。
聖書圏に、特定して片刃の剣技を発展させていたような事実はないが、
日本人が諸刃ではなく片刃の剣技を発展させたようにして、聖書信者もまた、
諸刃以上に技巧的な片刃の剣技のような感覚に即して、聖書信仰を実践してきたのである。
本人たちとしては、それが「勧善懲悪」の実践のつもりでもあったのだろうが、
実際には勧善懲悪の逆、悪逆非道の、片刃の剣技的な実践に務めてきたのである。
 悪逆非道の片刃の剣技の能力が、勧善懲悪の能力に即座に転用できるかといえば、
悪逆非道の片刃の剣技の能力が、勧善懲悪の能力に即座に転用できるかといえば、 けっしてそんなこともない。それどころか、悪逆非道の技巧的な実践にばかり
及んできたことが、かえって勧善懲悪の技巧的な実践にかけてのハンデにすらなる。
悪逆非道の片刃は捨て去って、まったく使い勝手の違う勧善懲悪の片刃に持ち替えたとしても、
「一からやり直し」というほどにも大きな試練が伴うことになるわけで、それだったらもう
刀なんか持たない、帯刀身分ではない百姓に甘んずるとしたとしても、仕方のないことである。
実際にやってみれば分かるが、片刃の剣術というのは非常に作為的なもので、
人体に非常に人工的な動きを強いる。徒手空拳の柔術などが人体の構造に根ざした
合理的な動きを突き止めているのに対し、剣術の動きには不自然な動きも多々見られる。
それは実際、身体にいいものでもなく、昔の武士も剣術と共に柔術をこなすことで、
剣術によって患った身体の凝りをほぐしてもいたのである。
勧善懲悪は、確かに人から尊ばれる偉業ともなる一方で、やはり全く自分に負担をかけない
なんてこともない。できる限り無益な自傷を避けながらも、負担の多い挺身にも臨んでいく
というのが勧善懲悪の実践ともなるので、そこはただひたすら我田引水に専らであり続ける
悪逆非道の実践にもない要素である。まるで悪逆非道に専らであるようにして、
勧善懲悪にも専らでいられるなどということもないのだから、悪逆非道にこそ
期待できたものを、勧善懲悪に期待したりするのも筋違いとなるのである。
世界中を飢餓や貧困に陥れるほどにも自分たちだけで富を占有している
欧米聖書圏の人間が、その富によって過剰な軍備をも敷く。
誰から自分たちを守るのかって、欧米による富の収奪によってこそ
困窮に陥れられた結果、戦乱すら避けられなくなっている異界の人々から。
始めから富の収奪などに及ばなければ、異界の人々も、戦乱を来たす
ほどもの困窮にかられたりすることもないわけだから、聖書信者が
それらの人々の攻撃から身を守るための、軍備などに及ぶ必要もない。
(もちろん、始めから軍備を敷けるだけの富を蓄えてもいないことになるが)
あくまで仮のこととして、欧米の聖書信仰者が自分たちの甚大な
軍力によって異教徒たちを殲滅し、完全に滅ぼし尽くしたとする。
その場合、富の収奪先がなくなって、軍備はおろか、自分たちの
物質的栄華を今までのように保ち続けることすらできなくなる。
ABC兵器などによる大量虐殺は致命的な地球環境の破壊をももたらし、
虐殺完遂後の地球上で聖書信仰者がまともな生活を送ることも叶わなくなる。
だから結局のところ、聖書信者が異教徒を滅ぼし尽くすという選択は
あくまで非現実的なものであり続けるわけだが、かといって、自分たち
聖書信者が極度の困窮に陥れた人々の、苦悩にかられた乱交からなる人口爆発
が止まることもなく、それによる世界の破滅もまた避けられるものではない。
欧米聖書圏の人間が、その富によって過剰な軍備をも敷く。
誰から自分たちを守るのかって、欧米による富の収奪によってこそ
困窮に陥れられた結果、戦乱すら避けられなくなっている異界の人々から。
始めから富の収奪などに及ばなければ、異界の人々も、戦乱を来たす
ほどもの困窮にかられたりすることもないわけだから、聖書信者が
それらの人々の攻撃から身を守るための、軍備などに及ぶ必要もない。
(もちろん、始めから軍備を敷けるだけの富を蓄えてもいないことになるが)
あくまで仮のこととして、欧米の聖書信仰者が自分たちの甚大な
軍力によって異教徒たちを殲滅し、完全に滅ぼし尽くしたとする。
その場合、富の収奪先がなくなって、軍備はおろか、自分たちの
物質的栄華を今までのように保ち続けることすらできなくなる。
ABC兵器などによる大量虐殺は致命的な地球環境の破壊をももたらし、
虐殺完遂後の地球上で聖書信仰者がまともな生活を送ることも叶わなくなる。
だから結局のところ、聖書信者が異教徒を滅ぼし尽くすという選択は
あくまで非現実的なものであり続けるわけだが、かといって、自分たち
聖書信者が極度の困窮に陥れた人々の、苦悩にかられた乱交からなる人口爆発
が止まることもなく、それによる世界の破滅もまた避けられるものではない。
紛れもなく、聖書の論理がこの世界に最大限に適用されたからこそ、
聖書信者たちにとっての絶体絶命の危機が到来することとなった。
それを選択したのも、推進したのも欧米の聖書信者たち自身であり、
その責任を取らねばならないのも、取ることができるのも、欧米人のみである。
責任を取る発端となるのは、まず聖書信者たちが自分たちの愚かさを自覚すること。
聖書によって自分たちの愚かさを埋め合わせたようなこともなく、
ただ自分たちの愚かさを聖書によって正当化して推進ばかりして来た。何よりもまず、
「聖書を信仰する」という選択を自分たちが行ったことこそは愚行の極みだったと知り、
聖書によって自分たちの罪が清められるなどという幻想も払拭して、聖書の信仰を
選択したことこそが、自分たちにとっての最大級の罪であったことをも諾うのである。
権力犯罪聖書——通称聖書の存在性が少しでも肯定されるような風潮が、
この世から完全に絶やされたときに、初めて聖書信者たちが招いている全人類に
とっての絶体絶命の危機も、回避され始めることになる。当然、それはまだである。
「遠人服せずして来たすこと能わず、邦分崩離析して守ること能わず。而して干戈を邦内に
動かさんことを謀る。吾れ恐る、季孫の憂いは顓臾に在らず、蕭牆の内に在らんことを」
「(今の魯国は)遠方の人間を従わせることはおろか、招きよせることも出来ず、諸国が分裂して
争乱を来たしているのにろくに守ることもできず、それでいて国内にすら軍備をうごめかせる。
私は恐れる、(魯の家老の)季孫が憂いとすべき患いは(隣国の)顓臾などではなく、国内にこそあることを。
(魯国が不徳なままに軍備ばかりを増強していることを愚行と断じている。聖書の神の所業もこれに等しい)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・季氏第十六・一より)
聖書信者たちにとっての絶体絶命の危機が到来することとなった。
それを選択したのも、推進したのも欧米の聖書信者たち自身であり、
その責任を取らねばならないのも、取ることができるのも、欧米人のみである。
責任を取る発端となるのは、まず聖書信者たちが自分たちの愚かさを自覚すること。
聖書によって自分たちの愚かさを埋め合わせたようなこともなく、
ただ自分たちの愚かさを聖書によって正当化して推進ばかりして来た。何よりもまず、
「聖書を信仰する」という選択を自分たちが行ったことこそは愚行の極みだったと知り、
聖書によって自分たちの罪が清められるなどという幻想も払拭して、聖書の信仰を
選択したことこそが、自分たちにとっての最大級の罪であったことをも諾うのである。
権力犯罪聖書——通称聖書の存在性が少しでも肯定されるような風潮が、
この世から完全に絶やされたときに、初めて聖書信者たちが招いている全人類に
とっての絶体絶命の危機も、回避され始めることになる。当然、それはまだである。
「遠人服せずして来たすこと能わず、邦分崩離析して守ること能わず。而して干戈を邦内に
動かさんことを謀る。吾れ恐る、季孫の憂いは顓臾に在らず、蕭牆の内に在らんことを」
「(今の魯国は)遠方の人間を従わせることはおろか、招きよせることも出来ず、諸国が分裂して
争乱を来たしているのにろくに守ることもできず、それでいて国内にすら軍備をうごめかせる。
私は恐れる、(魯の家老の)季孫が憂いとすべき患いは(隣国の)顓臾などではなく、国内にこそあることを。
(魯国が不徳なままに軍備ばかりを増強していることを愚行と断じている。聖書の神の所業もこれに等しい)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・季氏第十六・一より)
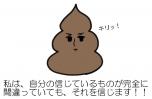 完全誤謬信仰の肝要は、あくまで
完全誤謬信仰の肝要は、あくまで 「私は自分の信じているものが完全に間違っていてもそれを信じます」
というほどもの勢いで対象を狂信することにある。
しかし、それほどもの狂信に至るための方便もまた様々であり、決して
「私は自分の信じているものが完全に間違っていてもそれを信じます」という
あからさまな教条ばかりに基づいて、完全誤謬信仰に陥ったりするわけでもない。
聖書教義もまた、信者を完全誤謬信仰に陥らせるための悪巧方便の一つであり、
完全誤謬信仰に陥ることができる確度では、あらゆる邪教教義の中でも突出している。
無論、まともな精神力の持ち主であれば始めから聖書教義を信仰したりはしないし、
また信仰しようたってできやしない。ただ、もしも聖書教義を信仰すらできたなら、その人間は
確実に完全誤謬信仰に没入することができる。非常に効能の確かな悪巧方便の一つであるといえる。
完全誤謬信仰に基づく、脳内の論理回路のショートが信者に与える酩酊は、
信者たちが実社会において犯した悪行に基づく、良心の呵責からなる苦しみをも覆い隠す。
これが、キリスト教徒などが聖書信仰によって「救われた」とする根拠であり、
それを以って「救われた」とするのなら、確かに、キリスト教徒は完全に救われたのである。
悪逆非道の悪因苦果は、それはそれで普遍的なものであり、誰しもが本当の所、苦痛に見舞われるもの。
ただ、無信仰の快楽犯などは、あらかじめ完全誤謬信仰の服用と同等の論理思考の破綻を脳内で蓄えて、
まるで始めから良心の呵責などないかのような態度で、罪を犯したりする。キリスト教徒の場合は
それとは微妙に違って、悪いことをすれば良心の呵責によって、自分もまた苦悩に見舞われるということ
までは分かっている。だからキリスト教教義に基づく完全誤謬信仰への没入によって、良心の呵責から
なる苦悩が覆い隠されたことを以ってして「救われた」ともうそぶくわけで、良心の呵責など始めから
抱いていないかのように振る舞う快楽犯などと比べれば、そこが誠実げに見えたりもするのである。
とはいえ、良心の呵責を自覚した後の後付けによってでも、完全誤謬信仰への没入によって苦悩から
解き放たれようとすること自体が、罪の償い方として不正なものであり、現実の罪悪のほうが相応の処罰
にもよらずに野放しにされて来たことは着実に破綻の温床となり、今日に至って絶体絶命の危機をも招いた。
キリスト教徒同士の間では、悪因苦果の苦しみを多少なりとも自覚した後に救われようとして来たことが、
自分たちの誠実さの証しであるかのようにも認識されて来たわけだが、非聖書圏の人間の感覚からすれば、
それもまた十分に不誠実な所業の範疇であり、何ら情状酌量の事由とするに足らないものだとする他はない。
酌量の余地があるとすれば、それは聖書教義が、信者を完全誤謬信仰に没入させる悪巧方便として、
あまりにもその性能が高かったことであり、故にこそ、信者が罪悪の苦しみを実感したかのような
体裁を取った上で、完全誤謬信仰の酩酊に没入することすらをも実現させて来てやったことだといえる。
それにより、信者たちに快楽犯などにはないような偽善を行使する余地を与えてやったことが、
聖書教義に特有の罪であるといえ、快楽犯よりはまだ聖書信者たちのほうが、「察しようのある
気休め」のさ中にありながら罪悪を積み重ねてきたということが、言えなくもないわけである。
「子、衛の公子荊を謂えり。「善く室に居る。始め有るに、曰く、苟くも合えりと。
少しく有あるに、曰く、苟くも完きなりと。富みて有るに、曰く、苟くも美なりと」
「先生が衛国の公子の荊を評して言われた。『家内の治め方が非常に優れている。財産が最低限足りている時に〈まあまあだ〉
といい、多少余りがある時に〈やっと完全といった所だ〉といい、非常に富んでいるときに〈立派なことだ〉といっている』
(これは、天下と利害を共にする純正な公族であればこそ評価に値する逸話であり、政商とつるんで私利私欲を貪る暴君など
であれば評するに値しないことだが、純正な公族としては、完全な仁政の達成すら志しとしては低いものとされる。
志しが『完全』止まりなカルト信仰の神経は、仁政に転用するにも値しないものなのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・子路第十三・八より)
解き放たれようとすること自体が、罪の償い方として不正なものであり、現実の罪悪のほうが相応の処罰
にもよらずに野放しにされて来たことは着実に破綻の温床となり、今日に至って絶体絶命の危機をも招いた。
キリスト教徒同士の間では、悪因苦果の苦しみを多少なりとも自覚した後に救われようとして来たことが、
自分たちの誠実さの証しであるかのようにも認識されて来たわけだが、非聖書圏の人間の感覚からすれば、
それもまた十分に不誠実な所業の範疇であり、何ら情状酌量の事由とするに足らないものだとする他はない。
酌量の余地があるとすれば、それは聖書教義が、信者を完全誤謬信仰に没入させる悪巧方便として、
あまりにもその性能が高かったことであり、故にこそ、信者が罪悪の苦しみを実感したかのような
体裁を取った上で、完全誤謬信仰の酩酊に没入することすらをも実現させて来てやったことだといえる。
それにより、信者たちに快楽犯などにはないような偽善を行使する余地を与えてやったことが、
聖書教義に特有の罪であるといえ、快楽犯よりはまだ聖書信者たちのほうが、「察しようのある
気休め」のさ中にありながら罪悪を積み重ねてきたということが、言えなくもないわけである。
「子、衛の公子荊を謂えり。「善く室に居る。始め有るに、曰く、苟くも合えりと。
少しく有あるに、曰く、苟くも完きなりと。富みて有るに、曰く、苟くも美なりと」
「先生が衛国の公子の荊を評して言われた。『家内の治め方が非常に優れている。財産が最低限足りている時に〈まあまあだ〉
といい、多少余りがある時に〈やっと完全といった所だ〉といい、非常に富んでいるときに〈立派なことだ〉といっている』
(これは、天下と利害を共にする純正な公族であればこそ評価に値する逸話であり、政商とつるんで私利私欲を貪る暴君など
であれば評するに値しないことだが、純正な公族としては、完全な仁政の達成すら志しとしては低いものとされる。
志しが『完全』止まりなカルト信仰の神経は、仁政に転用するにも値しないものなのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・子路第十三・八より)
>>65に書いたことをもう少し詳述すると、
キリスト教徒が、良心の呵責を抱いたかのような体裁の後に、
完全誤謬信仰への没入によって「救われた」とうそぶいて来たこと、
それはやはり不誠実なことであるため、その「誠実さ」などを以って
酌量事由にすることはできないが、聖書教義が、信者を完全誤謬信仰
に陥れるための悪巧方便としてあまりにも高性能であったために、
キリスト教徒たちが良心の呵責を感じているかのような偽善ごっこを
通じて気を紛らわしつつ悪行を重ねて来たことが、「察しよう」がある。
ということ。
「誠実だから」ではなく、「精神薄弱者の所業としては察しようがあるから」、
常人を対象とした刑事処分を、心神喪失者を対象とした民事処分などに
変更してやるぐらいの酌量の余地はあるということ。常人並みの誠実さを
期待できるほど、キリスト教徒が立派な人間でないことでは一貫している。
キリスト教徒が、良心の呵責を抱いたかのような体裁の後に、
完全誤謬信仰への没入によって「救われた」とうそぶいて来たこと、
それはやはり不誠実なことであるため、その「誠実さ」などを以って
酌量事由にすることはできないが、聖書教義が、信者を完全誤謬信仰
に陥れるための悪巧方便としてあまりにも高性能であったために、
キリスト教徒たちが良心の呵責を感じているかのような偽善ごっこを
通じて気を紛らわしつつ悪行を重ねて来たことが、「察しよう」がある。
ということ。
「誠実だから」ではなく、「精神薄弱者の所業としては察しようがあるから」、
常人を対象とした刑事処分を、心神喪失者を対象とした民事処分などに
変更してやるぐらいの酌量の余地はあるということ。常人並みの誠実さを
期待できるほど、キリスト教徒が立派な人間でないことでは一貫している。
孔子も幼少期、礼楽に用いる祭器を用いて遊んでいたというし(「史記」孔子世家)、
弟子の子貢も「孔先生は決まった相手から学ばず、なおかつ誰しもから
学ばれていた」との証言を遺している。(子張第十九・二二)
孔子もまた、その成長過程において、家族以外に学んだりすることが多かった。
父なしの妾腹の私生児という境遇上、親を敬えども、模範にしたりすることまでは
なかなか困難だったのにも違いなく、その点、賢母として知られる母を持つ
孟子などのほうが、遥かに恵まれた立場にもあっただろうことがうかがえる。
それでいて、天地万物万人を学ぶべき師とし、特に易学の形而上学的な法則に、森羅万象にも
通ずる普遍法則を見出して、綴じ糸が三たびも擦り切れるほどにも「易経」を読み込むなどして、
天地万物に永久普遍の道理までをも見出した。その道理が「論語」などにもある道徳論であり、
その中には「父父たり、子子たり」などという序列論もあるものだから、孔子自身、一度も
会ったことのない父親の墓にまで詣でて、孔家の跡取りとしての自らの立場をも固めたのである。
その郷里での態度なども、過度なほどに恭しく、イエキリのように、師らしいものとして
振る舞おうとした素振りすら見られない(郷党第十・一)。それでいて孔子は「郷原は徳の賊なり」
ともいい、親を尊ぶべき郷里ですら人気を取ろうとする者の浅はかさに、苦言を呈してもいる。
始めから郷里での人気取りなど試みようともしなかったのと、試みはしたものの見くびられて
挫折したのとが、孔子とイエキリとでの相違点であり、一応郷里での人気取りを試みるだけは
していたあたりが、イエキリが郷原止まりな知見の持ち主だった証拠にもなっている。
弟子の子貢も「孔先生は決まった相手から学ばず、なおかつ誰しもから
学ばれていた」との証言を遺している。(子張第十九・二二)
孔子もまた、その成長過程において、家族以外に学んだりすることが多かった。
父なしの妾腹の私生児という境遇上、親を敬えども、模範にしたりすることまでは
なかなか困難だったのにも違いなく、その点、賢母として知られる母を持つ
孟子などのほうが、遥かに恵まれた立場にもあっただろうことがうかがえる。
それでいて、天地万物万人を学ぶべき師とし、特に易学の形而上学的な法則に、森羅万象にも
通ずる普遍法則を見出して、綴じ糸が三たびも擦り切れるほどにも「易経」を読み込むなどして、
天地万物に永久普遍の道理までをも見出した。その道理が「論語」などにもある道徳論であり、
その中には「父父たり、子子たり」などという序列論もあるものだから、孔子自身、一度も
会ったことのない父親の墓にまで詣でて、孔家の跡取りとしての自らの立場をも固めたのである。
その郷里での態度なども、過度なほどに恭しく、イエキリのように、師らしいものとして
振る舞おうとした素振りすら見られない(郷党第十・一)。それでいて孔子は「郷原は徳の賊なり」
ともいい、親を尊ぶべき郷里ですら人気を取ろうとする者の浅はかさに、苦言を呈してもいる。
始めから郷里での人気取りなど試みようともしなかったのと、試みはしたものの見くびられて
挫折したのとが、孔子とイエキリとでの相違点であり、一応郷里での人気取りを試みるだけは
していたあたりが、イエキリが郷原止まりな知見の持ち主だった証拠にもなっている。
親や家族が大学者や帝王だったりするのであるならまだしも、ただの人であるのなら、
本人の大成が親族以外の誰かを頼りにすることだって当然あることだ。それが実際にあったのが
孔子である一方、それすらもなかったのがイエキリである。親兄弟を模範とせず、のみならず、
誰しもに何も学ぼうとはせず、完全なる我流の思い付きを「神からの啓示」などとして触れ回った。
だからこそ、誰しもから学ぼうとした孔子とは真逆の言行ばかりに走り、郷里においても、仁徳に
違う郷原としての振る舞いに及んで、気分のいい結果が得られなかったことにケチを付けたのである。
誰しもに学ぶことを通じて、父なしでありながら父子の親の大切さをも知り、親愛を損ねる郷里での
人気取りなども始めから控えていた孔子と、誰にも学ばないでいようとした結果、義父がいるにも
関わらず父子の親を疎かにしたままでいて、郷里での人気取りのような愚行にも及んだイエキリと、
行いの結果以前の、本人たち自身の行動規範こそが、根本からの品性の優劣を見せしめている。
どうして、人としてのあり方の規範を孔子に求めず、イエキリ風情に求めたりする道理が通るものか。
「郷党では歯に如くは莫し」
「郷里程度の小さな仲間内では、年齢の長幼以上に普遍的な拠り所となる基準はない。
(都市社会ならば、年齢の長幼以上にも仁徳の有無や官位の上下のほうが普遍的な基準となるが、
郷里程度ならせいぜい長幼が普遍基準止まりとなる。それも解さずに、郷里での人気取りなどを
試みようとすること自体が世間知らずな証しであり、郷原が徳の賊止まりとなる理由でもあるといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・公孫丑章句下・二より)
本人の大成が親族以外の誰かを頼りにすることだって当然あることだ。それが実際にあったのが
孔子である一方、それすらもなかったのがイエキリである。親兄弟を模範とせず、のみならず、
誰しもに何も学ぼうとはせず、完全なる我流の思い付きを「神からの啓示」などとして触れ回った。
だからこそ、誰しもから学ぼうとした孔子とは真逆の言行ばかりに走り、郷里においても、仁徳に
違う郷原としての振る舞いに及んで、気分のいい結果が得られなかったことにケチを付けたのである。
誰しもに学ぶことを通じて、父なしでありながら父子の親の大切さをも知り、親愛を損ねる郷里での
人気取りなども始めから控えていた孔子と、誰にも学ばないでいようとした結果、義父がいるにも
関わらず父子の親を疎かにしたままでいて、郷里での人気取りのような愚行にも及んだイエキリと、
行いの結果以前の、本人たち自身の行動規範こそが、根本からの品性の優劣を見せしめている。
どうして、人としてのあり方の規範を孔子に求めず、イエキリ風情に求めたりする道理が通るものか。
「郷党では歯に如くは莫し」
「郷里程度の小さな仲間内では、年齢の長幼以上に普遍的な拠り所となる基準はない。
(都市社会ならば、年齢の長幼以上にも仁徳の有無や官位の上下のほうが普遍的な基準となるが、
郷里程度ならせいぜい長幼が普遍基準止まりとなる。それも解さずに、郷里での人気取りなどを
試みようとすること自体が世間知らずな証しであり、郷原が徳の賊止まりとなる理由でもあるといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・公孫丑章句下・二より)
 「私は自分の信じているものが完全に間違っていてもそれを信じます」
「私は自分の信じているものが完全に間違っていてもそれを信じます」 という論理の脳内でのごり押しが、あらゆる正誤善悪の切実な判断を見失ったがための酩酊を呼び込む。
それが完全誤謬信仰のメカニズムであり、キリストを信仰することで救われた気になる理由もこの限りである。
別にアルコールやニコチンを経口で摂取するでも、薬物を注射器で投与するでもなく、ただ
「私は自分の信じているものが完全に間違っていてもそれを信じます」
という意味合いの情念を脳内でごり押しするだけで酩酊に没入できるわけだから、
キリスト信仰を始めとする完全誤謬信仰は、極めて携帯性にも富むものだといえる。
週に一度程度、教会などでキリストへの帰依の意志を新たにするだけでも、
キリスト教徒は恒常的に完全誤謬信仰の酩酊に没入していられるようなので、
キリスト教への入信の儀式(洗礼)なども一人につき一度だけ行われ、何度もは行われない。
なればこそ、キリスト教徒がキリスト教徒である限りにおいて犯した罪が、
完全誤謬信仰の酩酊の範囲外で犯されたようなこともない。
飲酒運転が、一定量以上のアルコール摂取と共に成立するようにして、
キリスト教徒の犯す罪もまた、必ず一定以上の完全誤謬信仰からなる酩酊と共に犯されている。
だから許容の対象になるのかどうかを、飲酒運転などに当てはめて考えてみるなら、全くないことになる。
それどころか、好き好んで酩酊に耽りつつ大罪を犯したことが、人としての信用のなさを確証することにすらなるといえる。
飲酒運転犯や飲酒運転事故犯が、免許を取り消されたり重罰を受けたりすることが妥当であるというのなら、
キリスト教徒として罪を犯した者もまた、社会的な行為能力制限や惜しみない重罰を受けることが妥当だということになる。
(日本の現行法では、ただのひき逃げの最高刑が懲役10年、飲酒運転のひき逃げに対する最高刑が懲役15年ともなっている)
無論、飲酒運転それだけなら誰にも迷惑をかけないようにして、
ただキリストを信仰しているだけというのなら、誰にも迷惑はかからない。
飲酒運転が事故につながることで初めて人に迷惑がかかるように、
キリスト信仰の酩酊が犯罪行為に繋がった時に初めて、人様にも迷惑がかかる。
だから、ただ飲酒運転をしただけ、キリストを信仰しただけで刑事罰までをも被るというのは
やり過ぎになるともいえ、免許取り消しや社会的不具者指定程度の処分で済ますべきだともいえる。
飲酒運転とキリスト信仰と、事故や権力犯罪などの迷惑行為に発展する頻度では、どっこいどっこいだといえる。
ただ、飲酒運転はすでに社会的な禁忌としての扱いが定着しているから、容認の過剰からなる事故への発展なども
未然に控えられているのに対し、キリスト信仰は禁忌としての扱いすら取り払われたままだから、
完全誤謬信仰の酩酊にことかけての権力犯罪行為などが野放しになったままでもいる。
警察が厳重な取り締まりの対象などにしなくとも、そもそも世間一般から、
飲酒運転の危険性は認知されていて、一定以上に忌避の対象ともなっている。
キリスト信仰も、何よりもまずそういった「忌避対象」としての認識が世間一般に広く定着する必要があるのであり、
頭ごなしな取り締まりの対象にしたりすることは、あくまで二の次なのである。
「孝以て君に事え、弟以て長に事う。民に貳せざるを示すためなり」
「父に仕える心がけを推して主君に仕え、兄に仕える心がけを推して年長者に仕える。
民に二番煎じの不誠実さを排した姿を示すためである。(先天的な父子兄弟の関係を反故にして他に
仕えるのであれば、それが一度きりであるとした所ですでに二番煎じだから、不誠実の至りだといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・坊記第三十より)
ただキリストを信仰しているだけというのなら、誰にも迷惑はかからない。
飲酒運転が事故につながることで初めて人に迷惑がかかるように、
キリスト信仰の酩酊が犯罪行為に繋がった時に初めて、人様にも迷惑がかかる。
だから、ただ飲酒運転をしただけ、キリストを信仰しただけで刑事罰までをも被るというのは
やり過ぎになるともいえ、免許取り消しや社会的不具者指定程度の処分で済ますべきだともいえる。
飲酒運転とキリスト信仰と、事故や権力犯罪などの迷惑行為に発展する頻度では、どっこいどっこいだといえる。
ただ、飲酒運転はすでに社会的な禁忌としての扱いが定着しているから、容認の過剰からなる事故への発展なども
未然に控えられているのに対し、キリスト信仰は禁忌としての扱いすら取り払われたままだから、
完全誤謬信仰の酩酊にことかけての権力犯罪行為などが野放しになったままでもいる。
警察が厳重な取り締まりの対象などにしなくとも、そもそも世間一般から、
飲酒運転の危険性は認知されていて、一定以上に忌避の対象ともなっている。
キリスト信仰も、何よりもまずそういった「忌避対象」としての認識が世間一般に広く定着する必要があるのであり、
頭ごなしな取り締まりの対象にしたりすることは、あくまで二の次なのである。
「孝以て君に事え、弟以て長に事う。民に貳せざるを示すためなり」
「父に仕える心がけを推して主君に仕え、兄に仕える心がけを推して年長者に仕える。
民に二番煎じの不誠実さを排した姿を示すためである。(先天的な父子兄弟の関係を反故にして他に
仕えるのであれば、それが一度きりであるとした所ですでに二番煎じだから、不誠実の至りだといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・坊記第三十より)
精子 Part8wwww
 悪因苦果の苦しみとはまた別に、善因楽果を得るための過渡的な労苦というものもまたある。
悪因苦果の苦しみとはまた別に、善因楽果を得るための過渡的な労苦というものもまたある。 しかし、それは決して良心の呵責などを誘うものではなく、「善行を為している」という
自覚に根ざした、浩然の気のすがすがしさと共にこそある、身心の健全な疲労でのみある。
「肩をそびやかしてへつらい笑うことは、真夏の炎天下に田畑を耕すよりも疲れる」
(「孟子」滕文公章句下・七より)
という曾子の言葉が、まさに悪因苦果の苦しみと、善行にかけての過渡的な苦しみとの相違を如実に
示してもいる。相手から私益を貪らんがために、商人らが肩をそびやかしてへつらい笑うときの
心痛は悪因苦果だから、公益のためにも田畑を耕す農民の重度の疲労などよりも、不健全に苦しい。
善行にかけての労苦ならば、善因楽果に基づく浩然の気による相殺が期待できるが、悪因苦果の
苦しみにはそれが期待できない。だから麻薬や邪淫や完全誤謬信仰のような、救いになるどころか、
かえって副作用すらをももたらす不健全な手段に基づいた、苦痛の相殺を試みるしかなくなる。
善行の労苦を、善因楽果である浩然の気によって相殺するという場合にこそ、実益面での加増すらもが
期待できる一方、悪行からなる悪因苦果の苦しみを、完全誤謬信仰や麻薬のような不適切な手段で
相殺しようとする場合にこそ、実益面にかけての大きな損失すらもが最終的に見込まれるのである。
労苦は労苦で、確かにしたほうがいい場合がある。しかもそのような労苦のほうが、真夏の炎天下
での耕作のような重労働でもあったりする一方、避けたほうがマシな悪行のための労苦こそは、
顧客の前で肩をそびやかしてへつらい笑うような、比較的な軽作業であったりもするのである。
完全誤謬信仰に基づくのでもなければ相殺できなかった労苦こそは、紛れもなく悪行の労苦である。
悪行の労苦だから浩然の気による相殺も叶わず、なおかつ後々にプラマイゼロ以下の損失までもが
見込まれる。労苦が決して報われないのではなく、完全誤謬信仰級の酩酊によってこそ相殺して
きたような悪行の労苦こそは、特定して報われることがなく、かえって破滅の温床にすらなる。
「こんなに苦労をして来たのに」などという不満を吐く余地が、悪行の苦しみを完全誤謬信仰に
よってでも相殺しようとしてきた場合にこそ、特定して存在しない。全ては紛れもなく徒労であった
と断じられる他はなく、せいぜい、妄信からなる悪行によって破滅の種を撒き散らしてきたことが、
過失としての認定によって、なるべく減刑の対象となることを期待するぐらいのことしかできない。
それは、どこまでも特殊例であって、労苦一般に対する普遍的な報いなどではない。むしろ、
健全な労苦によって相応の成果を挙げることのほうが世の常なのだから、当り散らしも禁物だ。
「顔子は乱世に当たりて、陋巷に居り、一箪の食、一瓢の飲。
人は其の憂いに堪えざるも、顔子は其の楽しみを改めず。孔子も之れを賢とせり」
「顔先生(孔子の弟子の顔淵。孔子の亦弟子である孟子にとって、顔淵は先生格でもある)は
春秋時代の乱世において、薄汚く狭い路地に住み、一膳一杯の飲食という質素な生活を貫かれた。
常人ならその憂いを耐え忍ぶこともできないが、顔先生はその楽しみを改めようともしなかった。
孔先生もそのあり方を賢明だと認めていた。(顔淵は清貧の善因楽果である浩然の気を楽しんでいた。
その楽しみを感じ取る感性に欠けていたりするものだから、貧窮の憂いを耐え忍ぶこともできなくて、
悪因苦果まみれの悪逆非道による虚栄を求めてしまったりもするのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・離婁章句下・三〇より)
悪行の労苦だから浩然の気による相殺も叶わず、なおかつ後々にプラマイゼロ以下の損失までもが
見込まれる。労苦が決して報われないのではなく、完全誤謬信仰級の酩酊によってこそ相殺して
きたような悪行の労苦こそは、特定して報われることがなく、かえって破滅の温床にすらなる。
「こんなに苦労をして来たのに」などという不満を吐く余地が、悪行の苦しみを完全誤謬信仰に
よってでも相殺しようとしてきた場合にこそ、特定して存在しない。全ては紛れもなく徒労であった
と断じられる他はなく、せいぜい、妄信からなる悪行によって破滅の種を撒き散らしてきたことが、
過失としての認定によって、なるべく減刑の対象となることを期待するぐらいのことしかできない。
それは、どこまでも特殊例であって、労苦一般に対する普遍的な報いなどではない。むしろ、
健全な労苦によって相応の成果を挙げることのほうが世の常なのだから、当り散らしも禁物だ。
「顔子は乱世に当たりて、陋巷に居り、一箪の食、一瓢の飲。
人は其の憂いに堪えざるも、顔子は其の楽しみを改めず。孔子も之れを賢とせり」
「顔先生(孔子の弟子の顔淵。孔子の亦弟子である孟子にとって、顔淵は先生格でもある)は
春秋時代の乱世において、薄汚く狭い路地に住み、一膳一杯の飲食という質素な生活を貫かれた。
常人ならその憂いを耐え忍ぶこともできないが、顔先生はその楽しみを改めようともしなかった。
孔先生もそのあり方を賢明だと認めていた。(顔淵は清貧の善因楽果である浩然の気を楽しんでいた。
その楽しみを感じ取る感性に欠けていたりするものだから、貧窮の憂いを耐え忍ぶこともできなくて、
悪因苦果まみれの悪逆非道による虚栄を求めてしまったりもするのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・離婁章句下・三〇より)
「信仰は無条件に善いこと」などということからして、決してなかった。
何に対する信仰とも、どのような信仰とも限らない、信仰一般の中には
「私は自分の信じているものが完全に間違っていてもそれを信じます」
という完全誤謬信仰までもが自動的に含まれている。それは、奴隷が主人に対して
絶対服従であろうとする姿勢も同然であり、仮に未だ奴隷制が完全に解消されていない
ような世の中においてですら、善いか悪いかでいえば悪いものとされるものなのである。
奴隷制は日本でも鎌倉時代まで、中国でも「苦力」という形で中共建国前まで
存続していたが、それが決して倫理的な存在などであるからではなく、ただ
権力者などにとって都合のいい人材要員であるから容認されて来たまでのことだ。
遥か昔、楚漢戦争後に楚軍の落ち武者となった季布が、剃髪に首枷という奴隷装束にまで
身をやつして逃亡していたことが、「それ程もの屈辱を呑んでいた」という理由で
高祖劉邦の感銘を買い、その罪を許されて郎中や太守としての復帰をも許されている。
奴隷制が存在しようが存在するまいが、奴隷などという身分、奴隷である者のあり方などが
評価の対象などになることは、太古の昔から東洋ではなかった。むしろ、奴隷こそは透徹
して屈辱的な存在であると見なされていたからこそ、奴隷身分の伝統的な装束である剃髪が、
仏門における出家修行者のための「忍辱行」を兼ねる装束としても流用されたのだった。
何に対する信仰とも、どのような信仰とも限らない、信仰一般の中には
「私は自分の信じているものが完全に間違っていてもそれを信じます」
という完全誤謬信仰までもが自動的に含まれている。それは、奴隷が主人に対して
絶対服従であろうとする姿勢も同然であり、仮に未だ奴隷制が完全に解消されていない
ような世の中においてですら、善いか悪いかでいえば悪いものとされるものなのである。
奴隷制は日本でも鎌倉時代まで、中国でも「苦力」という形で中共建国前まで
存続していたが、それが決して倫理的な存在などであるからではなく、ただ
権力者などにとって都合のいい人材要員であるから容認されて来たまでのことだ。
遥か昔、楚漢戦争後に楚軍の落ち武者となった季布が、剃髪に首枷という奴隷装束にまで
身をやつして逃亡していたことが、「それ程もの屈辱を呑んでいた」という理由で
高祖劉邦の感銘を買い、その罪を許されて郎中や太守としての復帰をも許されている。
奴隷制が存在しようが存在するまいが、奴隷などという身分、奴隷である者のあり方などが
評価の対象などになることは、太古の昔から東洋ではなかった。むしろ、奴隷こそは透徹
して屈辱的な存在であると見なされていたからこそ、奴隷身分の伝統的な装束である剃髪が、
仏門における出家修行者のための「忍辱行」を兼ねる装束としても流用されたのだった。
透徹して卑しい存在、賤しい人のあり方と見なされるべき奴隷の、主人に対する服従姿勢も
同然の信仰としての完全誤謬信仰。仮に信仰が絶対化されるのであれば、完全誤謬信仰すら
もが絶対無謬のものとして扱われることとなってしまう。それは自明にダメなことなので、
信を無条件に絶対化することなども、決して誉められたものではないということが言える。
そのような、無条件に絶対的な信を誉めそやす神なども、ダメな神であることが間違いない。
何らかの方向性が指し示されていて、それを「一心不乱に信じよ」というのならまだしも、
全く以って、ただ信じることはそれだけで素晴らしいなどというのなら、原理的にダメだ。
原理的に、そこには必ず完全誤謬信仰の是認すらもが含まれているから、原理的にダメだ。
罪の奴隷の解放を謳って、ただ信仰の奴隷になることを促すだけの邪神などは、去れ。
「言語必ず信なるは、以って行いを正すがために非ざるなり」
「必ずと言っていいほど信じるに値する言葉があったとしても、それによって行いを正して
行こうとする目的があるから発せられるのではない。(まず正しい行いがあってから、次に正しい
言葉が発せられる。それこそは信じるにも値するのだから、優先順位も行>言>信だといえる。)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句下・三二より)
同然の信仰としての完全誤謬信仰。仮に信仰が絶対化されるのであれば、完全誤謬信仰すら
もが絶対無謬のものとして扱われることとなってしまう。それは自明にダメなことなので、
信を無条件に絶対化することなども、決して誉められたものではないということが言える。
そのような、無条件に絶対的な信を誉めそやす神なども、ダメな神であることが間違いない。
何らかの方向性が指し示されていて、それを「一心不乱に信じよ」というのならまだしも、
全く以って、ただ信じることはそれだけで素晴らしいなどというのなら、原理的にダメだ。
原理的に、そこには必ず完全誤謬信仰の是認すらもが含まれているから、原理的にダメだ。
罪の奴隷の解放を謳って、ただ信仰の奴隷になることを促すだけの邪神などは、去れ。
「言語必ず信なるは、以って行いを正すがために非ざるなり」
「必ずと言っていいほど信じるに値する言葉があったとしても、それによって行いを正して
行こうとする目的があるから発せられるのではない。(まず正しい行いがあってから、次に正しい
言葉が発せられる。それこそは信じるにも値するのだから、優先順位も行>言>信だといえる。)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句下・三二より)
親鸞聖人が法然上人の門下において、他の弟子たちと
「信不退(信仰を止めない)」と「行不退(実践を止めない)」の
いずれを優先するかという論議を行ったとき、他の弟子たちはみんな
行不退を選んだのに対し、親鸞聖人だけは信不退を選んだ。論議の後、
法然上人にいずれかを問えば、「わしも親鸞と同じく信不退に賛成する」と答えた。
他力本願の浄土信仰者としては、どんな行い以上にも信仰を守る他はないと。
それは裏返してみるならば、他力本願である以上は信仰に十分な行いが伴い得ないことを
認めるべきだということなのであり、何ら正しい行いを為せているわけでもない自らが望むような
こともまた、信仰に見合うほど高潔なものではないことをも認めるべきであるということだ。
他力本願の信者であるなら、仏法の内実すら理解できなくて当然である。
華厳経や弘法大師の言葉などに、善人正機(悪人ですら救われるのだから、善人が救われるのも当然である)
に相当するような言葉も見受けられるとした所で、それは仏法を理解できた者に対する言葉でこそある。
他力本願の信者は仏法も解さないから、仏法で非とされる妄念妄動にもまみれたままでいる。
だから、その妄念に仏法を掛け合わせるなら、「善人ですら救われるのだから、悪人が救われるのも当然である」
という自利作善の場合とは真逆の教条をあてがうほうが適切ともなる。何を望むべきなのかも分かっていないし、
見えてない所にあるものが何なのかも全然分かっていないから、教条もひっくり返してしまったほうが適切なのである。
「信不退(信仰を止めない)」と「行不退(実践を止めない)」の
いずれを優先するかという論議を行ったとき、他の弟子たちはみんな
行不退を選んだのに対し、親鸞聖人だけは信不退を選んだ。論議の後、
法然上人にいずれかを問えば、「わしも親鸞と同じく信不退に賛成する」と答えた。
他力本願の浄土信仰者としては、どんな行い以上にも信仰を守る他はないと。
それは裏返してみるならば、他力本願である以上は信仰に十分な行いが伴い得ないことを
認めるべきだということなのであり、何ら正しい行いを為せているわけでもない自らが望むような
こともまた、信仰に見合うほど高潔なものではないことをも認めるべきであるということだ。
他力本願の信者であるなら、仏法の内実すら理解できなくて当然である。
華厳経や弘法大師の言葉などに、善人正機(悪人ですら救われるのだから、善人が救われるのも当然である)
に相当するような言葉も見受けられるとした所で、それは仏法を理解できた者に対する言葉でこそある。
他力本願の信者は仏法も解さないから、仏法で非とされる妄念妄動にもまみれたままでいる。
だから、その妄念に仏法を掛け合わせるなら、「善人ですら救われるのだから、悪人が救われるのも当然である」
という自利作善の場合とは真逆の教条をあてがうほうが適切ともなる。何を望むべきなのかも分かっていないし、
見えてない所にあるものが何なのかも全然分かっていないから、教条もひっくり返してしまったほうが適切なのである。
行いも言葉も、思考すらもが正しくあり得ないというような状況において、自主的に望まれることもまた
正しいわけがない。>>75の孟子の言葉の通り、正しい行を為せる程に思考もまた正しい時にこそ、真に正しい
言葉もまた発せられて、その言葉こそは真に信ずるに値する言葉ともなるが、妄念まみれであるために妄動しか
来たせないような愚人が、どんなに聞こえのいい言葉を吐いてみた所で、その言葉も所詮は妄念から発されたもの。
だからこそ同レベルの愚人からの共感を得られ、愚人が妄念によって望むことをありのままに叶えようともするが、
そこで指し示される望みの成就は、聖人が正念に基づいて発する言葉のうちの望みの成就とは、反転すらしてしまう。
愚人こそは、「善人こそは救われる」という状況を忌み嫌い、「悪人こそは救われる」という状況の到来を
心底望んでいる。望んでいるということは、今はまだ十分にその望みが叶えられていないとも考えているのである。
一方で聖人こそは、「悪人こそは救われる」という状況を忌み嫌い、「善人こそは救われる」という状況の到来こそを
望んでいる。聖人の考えからいえば、他力本願によってでしか救われ得ないような事態は、もう十分すでに、悪人
こそは救われている状況だから、それを大前提とした上での、善人こそは救われる浄土への往生を望むのである。
今が「善人こそは救われる世の中」であるか「悪人こそは救われる世の中」であるかに関わらず、
愚人は「善人こそは救われる世の中」が「悪人こそは救われる世の中」になることを望み、
聖人は「悪人こそは救われる世の中」が「善人こそは救われる世の中」になることを望む。
聖人か愚人かで望みすらもが反転するのだから、愚人は、信仰に自らの希望を託しすらしてはならないのである。
「利口を悪むは其の信を乱るを恐るればなり」
「信ずるべきものを信ずることを乱すのを恐れるために、上辺だけの口達者をも憎むのである。
(イエスのような虚言癖の口達者こそは、信仰に託すべき望み、信仰の先にあるものをも撹乱するのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句下・三七より)
正しいわけがない。>>75の孟子の言葉の通り、正しい行を為せる程に思考もまた正しい時にこそ、真に正しい
言葉もまた発せられて、その言葉こそは真に信ずるに値する言葉ともなるが、妄念まみれであるために妄動しか
来たせないような愚人が、どんなに聞こえのいい言葉を吐いてみた所で、その言葉も所詮は妄念から発されたもの。
だからこそ同レベルの愚人からの共感を得られ、愚人が妄念によって望むことをありのままに叶えようともするが、
そこで指し示される望みの成就は、聖人が正念に基づいて発する言葉のうちの望みの成就とは、反転すらしてしまう。
愚人こそは、「善人こそは救われる」という状況を忌み嫌い、「悪人こそは救われる」という状況の到来を
心底望んでいる。望んでいるということは、今はまだ十分にその望みが叶えられていないとも考えているのである。
一方で聖人こそは、「悪人こそは救われる」という状況を忌み嫌い、「善人こそは救われる」という状況の到来こそを
望んでいる。聖人の考えからいえば、他力本願によってでしか救われ得ないような事態は、もう十分すでに、悪人
こそは救われている状況だから、それを大前提とした上での、善人こそは救われる浄土への往生を望むのである。
今が「善人こそは救われる世の中」であるか「悪人こそは救われる世の中」であるかに関わらず、
愚人は「善人こそは救われる世の中」が「悪人こそは救われる世の中」になることを望み、
聖人は「悪人こそは救われる世の中」が「善人こそは救われる世の中」になることを望む。
聖人か愚人かで望みすらもが反転するのだから、愚人は、信仰に自らの希望を託しすらしてはならないのである。
「利口を悪むは其の信を乱るを恐るればなり」
「信ずるべきものを信ずることを乱すのを恐れるために、上辺だけの口達者をも憎むのである。
(イエスのような虚言癖の口達者こそは、信仰に託すべき望み、信仰の先にあるものをも撹乱するのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句下・三七より)
自性は虚空であるが故に、あるいは絶対真理たる梵と一如であるが故に、清浄なものである。
しかし、人間の心身が必ずしも純粋な自性ばかりに律されているとも限らず、色声香味触法
といった外部からの受容によって大きな影響を被ることもある。それが時に人間自身の悪念や
悪思、悪言や悪行といった悪果として結実してしまうことがあるわけで、そこに道徳律(俗諦)
に根ざして紛れもなく「悪」と規定できる諸事物が生ずることもまた、確かな事実なのである。
過度に色欲をそそる異性、無制限な食欲を駆り立てる食物などは、それ自体が悪でなくても、
それを得ようとする側の人間の感情の焼け付きを生じさせて、以って妄念や妄言や妄動、
悪念や悪言や悪行へと走らせる原因になってしまう場合がある。もしも受容する人間の
側に十分な自制心があったり、「色声香味触法の一切は空である」といったような悟りが
あったならば、同様の受容によって妄念や妄動を生じさせるとも限らないわけで、そうである
限りにおいて、どこにも「悪」に相当する現象は生じていないことにもなるわけである。
権力犯罪聖書——通称聖書もまた、そのような「受容者に妄念妄動をけしかける種子(:=悪種)」の
一つだといえるが、犯罪聖書が他の悪種と違う点は、眼耳鼻舌身の五根に訴える五感(色声香味触)
の悪種ではなく、総合的な理念意志としてこそ受容される「法」の悪種、悪法である点だといえる。
悪法であるが故にこそ、五感に訴えかける即物的な悪種よりもその悪質さが捉えにくく、
過度に肉欲をそそる性風俗だとか、健康を損ねるほどに食欲を駆り立てるジャクフードだとかいった
ような、分かりやすい悪種に対すると同様な受容取り締まりの対象にしていくことはなかなか難しい。
ただ難しいだけでなく、悪法が世の中にもたらす害悪こそは突出して致命的なものでもあるために、
性風俗やジャンクフードを取り締まる程度の、生半な姿勢で取り締まれるものではないとも言える。
しかし、人間の心身が必ずしも純粋な自性ばかりに律されているとも限らず、色声香味触法
といった外部からの受容によって大きな影響を被ることもある。それが時に人間自身の悪念や
悪思、悪言や悪行といった悪果として結実してしまうことがあるわけで、そこに道徳律(俗諦)
に根ざして紛れもなく「悪」と規定できる諸事物が生ずることもまた、確かな事実なのである。
過度に色欲をそそる異性、無制限な食欲を駆り立てる食物などは、それ自体が悪でなくても、
それを得ようとする側の人間の感情の焼け付きを生じさせて、以って妄念や妄言や妄動、
悪念や悪言や悪行へと走らせる原因になってしまう場合がある。もしも受容する人間の
側に十分な自制心があったり、「色声香味触法の一切は空である」といったような悟りが
あったならば、同様の受容によって妄念や妄動を生じさせるとも限らないわけで、そうである
限りにおいて、どこにも「悪」に相当する現象は生じていないことにもなるわけである。
権力犯罪聖書——通称聖書もまた、そのような「受容者に妄念妄動をけしかける種子(:=悪種)」の
一つだといえるが、犯罪聖書が他の悪種と違う点は、眼耳鼻舌身の五根に訴える五感(色声香味触)
の悪種ではなく、総合的な理念意志としてこそ受容される「法」の悪種、悪法である点だといえる。
悪法であるが故にこそ、五感に訴えかける即物的な悪種よりもその悪質さが捉えにくく、
過度に肉欲をそそる性風俗だとか、健康を損ねるほどに食欲を駆り立てるジャクフードだとかいった
ような、分かりやすい悪種に対すると同様な受容取り締まりの対象にしていくことはなかなか難しい。
ただ難しいだけでなく、悪法が世の中にもたらす害悪こそは突出して致命的なものでもあるために、
性風俗やジャンクフードを取り締まる程度の、生半な姿勢で取り締まれるものではないとも言える。
権力犯罪聖書——通称聖書とは逆に、人々に善思善言善行を促す善法としての存在意義を持つのが、
他でもない権力道徳聖書——通称四書五経の記述なわけで、善法であるが故に悪法たる犯罪聖書とは
その記述内容がことごとく相反し、善法たる四書五経の実践に務める以上は、自動的に悪法たる
犯罪聖書の実践が滞り、以って悪思悪言悪行に及ぶこともできなくなるようになっている。
しかし、四書五経に記録されている道徳律もまた、善法とはいえ、「法」の内に入るものである。
実定法文至上主義は、それはそれで四書五経中の「左伝」昭公六年などで批判的に取り上げられている
ものだが、孔子や孟子がその主な把捉者として立ち回っている権力道徳律もまた、易学にも根ざした
普遍的な法則でもあるにしたって、一般的な観点から見た場合の「法」であるにも違いないのである。
「法治主義」というものは、どんな形を取るのであれ、作為の極みとなる。善法であれ悪法であれ
実定法であれ、法による統治支配を絶対化しようとしたならば、その作為の過剰さこそが破綻を招く
原因ともなる。悪法を排し、実定法を緩和し、善法を推進していくことが「最も優良な法の受容法」
ともなるが、さりとて法の受容が過剰すぎれば、それがどうしたって瓦解の原因ともなってしまうのである。
だから、色声香味触の五根だけでなく、第六根の法もまた、善悪実定の如何に関わらず、「その一切が
空である」というほどもの諦観を抱いて、法全般の受容に取り組むこともまた国家鎮護、天下平定の
ための重要な指針となる。それがまた、法の受容が悪果に結び付かないための叡知ともなるなのである。
「天の烝民を生める、物有りて則有り。民は之の彝に秉い、是の懿鄹を好めり」
「天がこの世に諸々の民を生じさせ、その物としての性質に即して規則をも生じさせた。
民はその本性に根ざして、純正な規則を守ることの威徳を好んだ。(『孟子』告子章句上・六で性善論の
論拠ともしている句。仁徳を人々は本性から好んでいるから、その実践が善因楽果をももたらすのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・大雅・蕩之什・烝民より)
他でもない権力道徳聖書——通称四書五経の記述なわけで、善法であるが故に悪法たる犯罪聖書とは
その記述内容がことごとく相反し、善法たる四書五経の実践に務める以上は、自動的に悪法たる
犯罪聖書の実践が滞り、以って悪思悪言悪行に及ぶこともできなくなるようになっている。
しかし、四書五経に記録されている道徳律もまた、善法とはいえ、「法」の内に入るものである。
実定法文至上主義は、それはそれで四書五経中の「左伝」昭公六年などで批判的に取り上げられている
ものだが、孔子や孟子がその主な把捉者として立ち回っている権力道徳律もまた、易学にも根ざした
普遍的な法則でもあるにしたって、一般的な観点から見た場合の「法」であるにも違いないのである。
「法治主義」というものは、どんな形を取るのであれ、作為の極みとなる。善法であれ悪法であれ
実定法であれ、法による統治支配を絶対化しようとしたならば、その作為の過剰さこそが破綻を招く
原因ともなる。悪法を排し、実定法を緩和し、善法を推進していくことが「最も優良な法の受容法」
ともなるが、さりとて法の受容が過剰すぎれば、それがどうしたって瓦解の原因ともなってしまうのである。
だから、色声香味触の五根だけでなく、第六根の法もまた、善悪実定の如何に関わらず、「その一切が
空である」というほどもの諦観を抱いて、法全般の受容に取り組むこともまた国家鎮護、天下平定の
ための重要な指針となる。それがまた、法の受容が悪果に結び付かないための叡知ともなるなのである。
「天の烝民を生める、物有りて則有り。民は之の彝に秉い、是の懿鄹を好めり」
「天がこの世に諸々の民を生じさせ、その物としての性質に即して規則をも生じさせた。
民はその本性に根ざして、純正な規則を守ることの威徳を好んだ。(『孟子』告子章句上・六で性善論の
論拠ともしている句。仁徳を人々は本性から好んでいるから、その実践が善因楽果をももたらすのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・大雅・蕩之什・烝民より)
随順するものが、主導するものの安全保障にかまけて驕り高ぶる状態というのは、
言ってみれば「カカア天下」であり、随順者である以上はしおらしく主導者の後を
追っていく「夫唱婦随」の状態と比べて、まことに不健全なものであるといえる。
随順者が驕り高ぶってまでいながら、主導者が無制限にその安全をも保障し続けて
やろうとする所に、大きなロスが生ずる。その端緒が欧米聖書圏における軍備過剰や、
綱渡り状態の経済政策だったりもするわけで、始めから夫唱婦随が確立されたままで、
女子供や小人がやりたい放題することなく君子の後を追うように努めていたならば、
そこまで経済や軍事を自壊級にまで煩雑化させる必要などもなかったのである。
陰陽不全のカカア天下状態、女子供や小人こそはやりたい放題できる状態——
それを今では「民主制」とも呼ぶ——を推進した挙句に、経済や軍事の規模が過剰に
肥大化した、のみならず、父権への甚だしい軽蔑が少子高齢化にも結び付き、国全体
としては男尊女卑の風潮を保っている中国やインドや中東諸国などに、人口面やその
内部構成の健全度などの面において、大きく水を開けられることともなってしまった。
女々しい信者の立場に立った、軽薄な記述ばかりが目立つ犯罪聖書などと違い、
四書五経の記述はどこまでも君子本位であり、女子供はおろか、小人(被支配階級)
の男の立場に立った記述すらもが、ほぼ皆無に等しい。その記述姿勢からしてすでに、
夫唱婦随を実現していくことを目的としているのであり、君子本位の記述だからと
いって、女子供や小人を全くの度外視にしていたりするわけでもないのである。
言ってみれば「カカア天下」であり、随順者である以上はしおらしく主導者の後を
追っていく「夫唱婦随」の状態と比べて、まことに不健全なものであるといえる。
随順者が驕り高ぶってまでいながら、主導者が無制限にその安全をも保障し続けて
やろうとする所に、大きなロスが生ずる。その端緒が欧米聖書圏における軍備過剰や、
綱渡り状態の経済政策だったりもするわけで、始めから夫唱婦随が確立されたままで、
女子供や小人がやりたい放題することなく君子の後を追うように努めていたならば、
そこまで経済や軍事を自壊級にまで煩雑化させる必要などもなかったのである。
陰陽不全のカカア天下状態、女子供や小人こそはやりたい放題できる状態——
それを今では「民主制」とも呼ぶ——を推進した挙句に、経済や軍事の規模が過剰に
肥大化した、のみならず、父権への甚だしい軽蔑が少子高齢化にも結び付き、国全体
としては男尊女卑の風潮を保っている中国やインドや中東諸国などに、人口面やその
内部構成の健全度などの面において、大きく水を開けられることともなってしまった。
女々しい信者の立場に立った、軽薄な記述ばかりが目立つ犯罪聖書などと違い、
四書五経の記述はどこまでも君子本位であり、女子供はおろか、小人(被支配階級)
の男の立場に立った記述すらもが、ほぼ皆無に等しい。その記述姿勢からしてすでに、
夫唱婦随を実現していくことを目的としているのであり、君子本位の記述だからと
いって、女子供や小人を全くの度外視にしていたりするわけでもないのである。
四書五経やその他諸々の漢籍(一部文学書などを除く)の、君子本位を貫く
記述姿勢こそはありのままに、社会規模での夫唱婦随の実現を企図したものである。
文学小説や諸々の洋学書のように、女子供や小人階級こそを主な読者層とし、
実際に女子供や小人こそを主人公としたような著述を心がけること自体がすでに、
世の中総出でのカカア天下状態の実現を企図したものであるということもまた言える。
女子供や小人を本位とする、よさげにいえば民主主義的、直言すれば
カカア天下的な書物の著述姿勢に権威を付与している最大級の存在こそは、
他でもない犯罪聖書であり、ギリシャ古典あたりがそれに次ぐ存在となっている。
多くの漢籍だけでなく、ヴェーダやウパニシャッドや仏典といったインド古典もまた、
バラモン階級や沙門階級が自分たちのために編み出したものであるため、上記のような
条件は満たしていない。イスラムのコーランやハディースもまた、一人前の軍政家でもあった
ムハンマドの口承記録やその敷衍であり、やはり為政本位の著述であることには変わりない。
世の中で最大級の実力を持つ君子を本位とした著述文化は、やはり中国古典に極まる。
一方、小人や女子供を本位とした著述文化は、やはりイスラエル以西の西洋に多い。
中国よりもさらに東方の日本では、もはや男が長々とした文章を書き溜めるまでもなく
速攻の実践に臨むことが主眼とされたため、君子本位の古典文学が別に多いということもないが、
著述に臨む以上はなるべく君子本位であろうとし、小人や女子供本位ではないほうがよい。
世界最高の女流作家である紫式部もまた、「史記」や「漢書」のような君子の事跡を主に記録した
大説を好んだというのだから、女子供だからといって君子本位の著述を遠ざけるべきでもない。
記述姿勢こそはありのままに、社会規模での夫唱婦随の実現を企図したものである。
文学小説や諸々の洋学書のように、女子供や小人階級こそを主な読者層とし、
実際に女子供や小人こそを主人公としたような著述を心がけること自体がすでに、
世の中総出でのカカア天下状態の実現を企図したものであるということもまた言える。
女子供や小人を本位とする、よさげにいえば民主主義的、直言すれば
カカア天下的な書物の著述姿勢に権威を付与している最大級の存在こそは、
他でもない犯罪聖書であり、ギリシャ古典あたりがそれに次ぐ存在となっている。
多くの漢籍だけでなく、ヴェーダやウパニシャッドや仏典といったインド古典もまた、
バラモン階級や沙門階級が自分たちのために編み出したものであるため、上記のような
条件は満たしていない。イスラムのコーランやハディースもまた、一人前の軍政家でもあった
ムハンマドの口承記録やその敷衍であり、やはり為政本位の著述であることには変わりない。
世の中で最大級の実力を持つ君子を本位とした著述文化は、やはり中国古典に極まる。
一方、小人や女子供を本位とした著述文化は、やはりイスラエル以西の西洋に多い。
中国よりもさらに東方の日本では、もはや男が長々とした文章を書き溜めるまでもなく
速攻の実践に臨むことが主眼とされたため、君子本位の古典文学が別に多いということもないが、
著述に臨む以上はなるべく君子本位であろうとし、小人や女子供本位ではないほうがよい。
世界最高の女流作家である紫式部もまた、「史記」や「漢書」のような君子の事跡を主に記録した
大説を好んだというのだから、女子供だからといって君子本位の著述を遠ざけるべきでもない。
「孔子曰く、似て非なる者を悪む。莠を悪むは其の苗を乱るを恐れればなり。佞を悪むは、其の義を乱るを恐れればなり。利口を
悪むは、其の信を乱るを恐れればなり鄭声を悪むは、其の楽を乱るを恐れればなり。紫を悪むは、其の朱を乱るを恐れればなり。
郷原を悪むは、其の徳を乱るを恐れればなり。君子は経に反るのみ。経を正せば則ち庶民興り、庶民興るれば斯ち邪慝なし」
「孔先生は言われた。『似て非なる類いのものをよく思わぬ。苗に似た雑草をよく思わないのは、穀類の苗を紛らわすことを
恐れるから。阿りの徒をよく思わないのは、道義を紛らわすのを恐れるから。口達者をよく思わないのは、信頼性を紛らわす
のを恐れるから。紫のような間色をよく思わないのは、赤のような原色を紛らわすのを恐れるから。世間知らずの偽善者を
よく思わないのは、仁徳を紛らわすのを恐れるから』 君子はこのように危うきをよく恐れて、本来の道に立ち返るのみである。
道が正されれば庶民までもがそれに倣って道徳を振興し、庶民までもが道徳を振興するぐらいだから、詐悪も起こらなくなる。
(君子がよく詐悪の害を恐れ憎むようにして、庶民もまたその姿を倣い、以って天下全土における詐悪の害もまた鎮まるのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句下・三七より)
悪むは、其の信を乱るを恐れればなり鄭声を悪むは、其の楽を乱るを恐れればなり。紫を悪むは、其の朱を乱るを恐れればなり。
郷原を悪むは、其の徳を乱るを恐れればなり。君子は経に反るのみ。経を正せば則ち庶民興り、庶民興るれば斯ち邪慝なし」
「孔先生は言われた。『似て非なる類いのものをよく思わぬ。苗に似た雑草をよく思わないのは、穀類の苗を紛らわすことを
恐れるから。阿りの徒をよく思わないのは、道義を紛らわすのを恐れるから。口達者をよく思わないのは、信頼性を紛らわす
のを恐れるから。紫のような間色をよく思わないのは、赤のような原色を紛らわすのを恐れるから。世間知らずの偽善者を
よく思わないのは、仁徳を紛らわすのを恐れるから』 君子はこのように危うきをよく恐れて、本来の道に立ち返るのみである。
道が正されれば庶民までもがそれに倣って道徳を振興し、庶民までもが道徳を振興するぐらいだから、詐悪も起こらなくなる。
(君子がよく詐悪の害を恐れ憎むようにして、庶民もまたその姿を倣い、以って天下全土における詐悪の害もまた鎮まるのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句下・三七より)
何かを敬う以上は、神仏よりも主君よりも、まず先に敬いの対象とすべき相手として、実の親がある。
(鬼籍の先祖を神仏とする場合にのみ、親への崇敬と神仏崇拝もまた一如となる)
その親に対する敬いを他者に対しても振り向けていく場合に、その敬いが最も着実な敬いとなる一方、
親や先祖への敬いを蔑ろにした所から試みられる敬いは、いかなるものであろうとも、虚構止まりとなる。
聖書圏において、神への信仰や敬いを欠くもの、それ即ちニヒリスト(虚無主義者)であり、
誰に対する崇敬も持たない無頼者の代名詞ともされている。これこそは、聖書信者が親や先祖への
敬いを蔑ろにしているのみならず、親や先祖への敬いなどは「始めから存在しないもの」
であるなどと、完全に思い込み尽くしてしまっている証拠であるといえる。
紀元前の西洋文化や、犯罪聖書におけるイエスらの暴言暴行を鑑みるに、キリスト信仰が蔓延する
以前の西洋において、それなりに親族先祖への崇敬を嗜む文化もまたあったように見受けられる。その上で、
実父の素性が定かでないイエスを「神の子」として祭り上げたり、キリスト信仰によって他の神仏への崇拝を
破壊するなどして、聖書信仰が親や先祖に対する崇敬の文化を人工的に破壊していった形跡が多々見られる。
ただ、それはもう2000年近くも前の話で、現今の聖書信者にとっては、自分たちの先祖が人工的に
親や先祖への崇敬を破棄して、あえて好き好んで聖書信仰だけに惑溺していったという史実に対する認識
すらもがもはや疎かとなっているから、「敬いといえば神への敬いが第一」「神への敬いを欠いた所にあるのは
ニヒリズムのみ」などというような、完全に間違った思い込みに凝り固まるまでに至ってしまっているのである。
(鬼籍の先祖を神仏とする場合にのみ、親への崇敬と神仏崇拝もまた一如となる)
その親に対する敬いを他者に対しても振り向けていく場合に、その敬いが最も着実な敬いとなる一方、
親や先祖への敬いを蔑ろにした所から試みられる敬いは、いかなるものであろうとも、虚構止まりとなる。
聖書圏において、神への信仰や敬いを欠くもの、それ即ちニヒリスト(虚無主義者)であり、
誰に対する崇敬も持たない無頼者の代名詞ともされている。これこそは、聖書信者が親や先祖への
敬いを蔑ろにしているのみならず、親や先祖への敬いなどは「始めから存在しないもの」
であるなどと、完全に思い込み尽くしてしまっている証拠であるといえる。
紀元前の西洋文化や、犯罪聖書におけるイエスらの暴言暴行を鑑みるに、キリスト信仰が蔓延する
以前の西洋において、それなりに親族先祖への崇敬を嗜む文化もまたあったように見受けられる。その上で、
実父の素性が定かでないイエスを「神の子」として祭り上げたり、キリスト信仰によって他の神仏への崇拝を
破壊するなどして、聖書信仰が親や先祖に対する崇敬の文化を人工的に破壊していった形跡が多々見られる。
ただ、それはもう2000年近くも前の話で、現今の聖書信者にとっては、自分たちの先祖が人工的に
親や先祖への崇敬を破棄して、あえて好き好んで聖書信仰だけに惑溺していったという史実に対する認識
すらもがもはや疎かとなっているから、「敬いといえば神への敬いが第一」「神への敬いを欠いた所にあるのは
ニヒリズムのみ」などというような、完全に間違った思い込みに凝り固まるまでに至ってしまっているのである。
聖書の神のような、我が家の祖霊でもない雑神は、仮りに敬うに値する神である
としたところで、優先順位でいえば「四番目以降」に敬うべき神であるといえる。
まず一番目に敬うべきなのが、上にも書いたとおり実際の親である。
また、祖霊を祀った神仏に限って親とも順位が等しく、同率一位であるといえる。
親と祖霊の次、三番目に敬うべきなのが、自国の主君である。
これまた敬うべき度合いでは親並みであるといえるが、親族に対する親密さを帯びた敬意こそを主君にも援用して
振り向けるべきであるから、親や祖霊を敬ってから、その敬意こそを主君にも振り向けるようにすべきだといえる。
親と、祖霊と、主君の次に敬うべきなのが、上天名山大川神仙その他、諸々の雑多な神仏であり、
聖書の神も入れるとするならここに入る(無論、邪神だからここにすら入れてはならないともいえる)。
これらの神仏は崇敬対象としての優先順位が低いのみならず、場合によっては「まだ敬ってはいけない」という場合
すらある。始皇帝のように中国一帯での暴政を繰り返しながら、中国一の名山である泰山の神を我流の礼法で祭ろう
としたら、暴風雨が吹き荒れて台無しになったという逸話もあるように(「史記」封禅書)、自分にそれらの神仏を
祭るだけの身分なり資格なりが整ってからでないと、まだ崇敬の対象にしてはいけないという場合すらもがある。
聖書の神が邪神であるのは、優先順位がより高い親や祖霊や主君への敬いをも蔑ろにした、
虚構の敬いこそを信者に強要するからである。その信仰を欠いた所に、元信者が人工的なニヒリズムを
患うのみならず、その信仰に基づく神への敬い自体が、ありのままに虚構の敬いでしかなくもある。
「虚構だ」と断じられるのも、本当に大切なものへの敬いを蔑ろにしてから講じられる聖書信者の敬いが、
本当に大切なものへの敬いと比べて、どこまでも薄っぺらいもの止まりでしかないからである。
としたところで、優先順位でいえば「四番目以降」に敬うべき神であるといえる。
まず一番目に敬うべきなのが、上にも書いたとおり実際の親である。
また、祖霊を祀った神仏に限って親とも順位が等しく、同率一位であるといえる。
親と祖霊の次、三番目に敬うべきなのが、自国の主君である。
これまた敬うべき度合いでは親並みであるといえるが、親族に対する親密さを帯びた敬意こそを主君にも援用して
振り向けるべきであるから、親や祖霊を敬ってから、その敬意こそを主君にも振り向けるようにすべきだといえる。
親と、祖霊と、主君の次に敬うべきなのが、上天名山大川神仙その他、諸々の雑多な神仏であり、
聖書の神も入れるとするならここに入る(無論、邪神だからここにすら入れてはならないともいえる)。
これらの神仏は崇敬対象としての優先順位が低いのみならず、場合によっては「まだ敬ってはいけない」という場合
すらある。始皇帝のように中国一帯での暴政を繰り返しながら、中国一の名山である泰山の神を我流の礼法で祭ろう
としたら、暴風雨が吹き荒れて台無しになったという逸話もあるように(「史記」封禅書)、自分にそれらの神仏を
祭るだけの身分なり資格なりが整ってからでないと、まだ崇敬の対象にしてはいけないという場合すらもがある。
聖書の神が邪神であるのは、優先順位がより高い親や祖霊や主君への敬いをも蔑ろにした、
虚構の敬いこそを信者に強要するからである。その信仰を欠いた所に、元信者が人工的なニヒリズムを
患うのみならず、その信仰に基づく神への敬い自体が、ありのままに虚構の敬いでしかなくもある。
「虚構だ」と断じられるのも、本当に大切なものへの敬いを蔑ろにしてから講じられる聖書信者の敬いが、
本当に大切なものへの敬いと比べて、どこまでも薄っぺらいもの止まりでしかないからである。
「君に事えては、其の事うるを敬して其の食を後にす」
「主君に仕える場合には、仕える以上はまず敬うことに務め、褒美を頂くことなどは後回しにする。
(君父の尊位に根ざした仕官にかけての敬いこそは、まず褒美ありきな聖書信仰の敬いなどよりも確実に誠実である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・衛霊公第十五・三八より)
「主君に仕える場合には、仕える以上はまず敬うことに務め、褒美を頂くことなどは後回しにする。
(君父の尊位に根ざした仕官にかけての敬いこそは、まず褒美ありきな聖書信仰の敬いなどよりも確実に誠実である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・衛霊公第十五・三八より)
聞いても聡からず、言っても実に欠けるばかりなら、
そんな耳や口は始めから機能していないほうがマシですらある。
母子家庭育ちの妾腹の私生児としての、自らの賤しさを心底恥じていたから、
孔子は郷里では唖オシも同然の拙い物言いしかしなかったという。それでいて、
逆境を乗り越えるための猛勉強によって培われた言行の丹精豊かさが、朝廷
等の公けの場では大いに発揮され、その姿があまりにも悠然としていたために、
諸侯が孔子と同席するのを躊躇ったほどであったという。(「韓非子」より)
人の言うことを聞いてよく学ぶ従順な耳を持ち、時と場合とを選んで
発すべき言葉を適格に発する口とが備わるのなら、それに越したことはない。
逆に、聞いても何も学ぶことがなく、いくらでも聞いたことを捻じ曲げてしまう
勝手な耳を持ち、人を欺くような虚言ばかりを発する口を得るぐらいなら、
そんな耳や口はないほうがマシである。もしもそうであったりするのなら、
郷里で唖のように振る舞っていた孔子のあり方こそを見習うべきだといえる。
ただ聴力がある、話術に長けるというだけでは、善いとも悪いとも言えない。
聞き分けの悪い耳や虚言癖持ちの口が、かえって度し難いということもあるし、
実際に盗聴や虚偽のような犯罪行為にすら発展し得るもの。それは聴力も話術も
持たなければ犯しえない罪なわけだから、聴力や話術があればこその宿命だといえる。
そんな耳や口は始めから機能していないほうがマシですらある。
母子家庭育ちの妾腹の私生児としての、自らの賤しさを心底恥じていたから、
孔子は郷里では唖オシも同然の拙い物言いしかしなかったという。それでいて、
逆境を乗り越えるための猛勉強によって培われた言行の丹精豊かさが、朝廷
等の公けの場では大いに発揮され、その姿があまりにも悠然としていたために、
諸侯が孔子と同席するのを躊躇ったほどであったという。(「韓非子」より)
人の言うことを聞いてよく学ぶ従順な耳を持ち、時と場合とを選んで
発すべき言葉を適格に発する口とが備わるのなら、それに越したことはない。
逆に、聞いても何も学ぶことがなく、いくらでも聞いたことを捻じ曲げてしまう
勝手な耳を持ち、人を欺くような虚言ばかりを発する口を得るぐらいなら、
そんな耳や口はないほうがマシである。もしもそうであったりするのなら、
郷里で唖のように振る舞っていた孔子のあり方こそを見習うべきだといえる。
ただ聴力がある、話術に長けるというだけでは、善いとも悪いとも言えない。
聞き分けの悪い耳や虚言癖持ちの口が、かえって度し難いということもあるし、
実際に盗聴や虚偽のような犯罪行為にすら発展し得るもの。それは聴力も話術も
持たなければ犯しえない罪なわけだから、聴力や話術があればこその宿命だといえる。
あらゆる道徳上の教条のうちでも、
「礼にあらざれば聴くことなかれ。礼にあらざれば言うことなかれ(顔淵第十二・一)」
という教条ほどにも、現代社会において著しく蔑ろにされている教条も他に無い。
ただ蔑ろにされているのみならず、蔑ろにすることが少しも悪いことだとすら捉えられておらず、
むしろとにかく何でも聞いて、何でも言うことこそは正義であるとすら見なされている感がある。
聞くべきでないことを聞かなかった、言うべきでないことを言わなかったがための
好影響というのは、色々と聞いたり言ったりした場合の影響ほどには、分かりやすくない。
水面に石を投げて波紋を立てるよりも、始めから石を投げないでいることのほうが、
その結果どうなったかが分かりにくいのも当然なことで、なおのこと、その先にある
平穏無事の好影響を察せるか否かに、石投げを踏み止まる決断もまた左右されるのである。
好影響は、確かにあるのである。未だ無闇に耳聡く、歯に衣着せないでいる内からそれを
察するのは難しくても、耳と口との悪用を取りやめることの功徳は、確かな結果となって現れる。
せいぜいその瞬間まで、自分たちが耳口の悪用を踏み止まったことを、よく自覚しておくことだ。
「礼にあらざれば聴くことなかれ。礼にあらざれば言うことなかれ(顔淵第十二・一)」
という教条ほどにも、現代社会において著しく蔑ろにされている教条も他に無い。
ただ蔑ろにされているのみならず、蔑ろにすることが少しも悪いことだとすら捉えられておらず、
むしろとにかく何でも聞いて、何でも言うことこそは正義であるとすら見なされている感がある。
聞くべきでないことを聞かなかった、言うべきでないことを言わなかったがための
好影響というのは、色々と聞いたり言ったりした場合の影響ほどには、分かりやすくない。
水面に石を投げて波紋を立てるよりも、始めから石を投げないでいることのほうが、
その結果どうなったかが分かりにくいのも当然なことで、なおのこと、その先にある
平穏無事の好影響を察せるか否かに、石投げを踏み止まる決断もまた左右されるのである。
好影響は、確かにあるのである。未だ無闇に耳聡く、歯に衣着せないでいる内からそれを
察するのは難しくても、耳と口との悪用を取りやめることの功徳は、確かな結果となって現れる。
せいぜいその瞬間まで、自分たちが耳口の悪用を踏み止まったことを、よく自覚しておくことだ。
「戎を成すとも退けず、飢えを成すとも遂んぜられず。
曾ち我が蟄御も、僭僭として日びに瘁める。凡百の君子も、
肯て用て訊める莫し。聴言には則ち答え、譖言には則ち退く。(ここから既出)
哀しきかな言るに能わず、匪れ舌より是れ出ずれば、維ち躬に是れ瘁しむ。
しかも能言のやからの、巧言の流るるが如きは、躬を俾て休きに處らしむ」
「戦乱が起これば平定することもできず、飢饉が起きれば安んずることもできず。
朝廷の内臣たちも暴慢にかられて頭をおかしくしているばかり。中位の官吏たちも
上司の腐敗をよく諌めることができないのは、おもねる言葉は聞き入れられても、
耳に痛い忠言は即座に退けられるから。哀しきかな、正しい言葉を口にするほど
わが身を貶める結果となってしまう現状は。それでいて、能弁に長ける連中どもが
有害無益な巧言によって上に取り入ることで、甘い汁を吸っているとまで来ている。
(聴力や話術の悪用が、戦乱や飢餓の放置に直結していることをよく明示している)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・小雅・祈父之什・雨無正より)
曾ち我が蟄御も、僭僭として日びに瘁める。凡百の君子も、
肯て用て訊める莫し。聴言には則ち答え、譖言には則ち退く。(ここから既出)
哀しきかな言るに能わず、匪れ舌より是れ出ずれば、維ち躬に是れ瘁しむ。
しかも能言のやからの、巧言の流るるが如きは、躬を俾て休きに處らしむ」
「戦乱が起これば平定することもできず、飢饉が起きれば安んずることもできず。
朝廷の内臣たちも暴慢にかられて頭をおかしくしているばかり。中位の官吏たちも
上司の腐敗をよく諌めることができないのは、おもねる言葉は聞き入れられても、
耳に痛い忠言は即座に退けられるから。哀しきかな、正しい言葉を口にするほど
わが身を貶める結果となってしまう現状は。それでいて、能弁に長ける連中どもが
有害無益な巧言によって上に取り入ることで、甘い汁を吸っているとまで来ている。
(聴力や話術の悪用が、戦乱や飢餓の放置に直結していることをよく明示している)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・小雅・祈父之什・雨無正より)
善行の規範としての権力道徳聖書——通称四書五経の記述が完璧に磐石だから、
その四書五経と真逆の記述を寄せ集めているだけでしかない
権力犯罪聖書——通称聖書もまた、悪行の規範としては完璧に磐石なものである。
天人修羅の三善趣と共に、地獄餓鬼畜生の三悪趣が六道の内に包含されているように、
人が善行に反する悪行によって、一定の生活規範を保てることもまた一つの真理である。
天道や人道に即して磐石な人生を送れるほどにも、餓鬼道や畜生道に即して磐石な
人生を送ることが実際、人間には可能である。ただ、三善趣(特に人天の二道)と
三悪趣が一ところで共存や共栄することだけは真理に即して不可能なことであり、
どちらかが威勢を蓄えたぶんだけ、もう一方の威勢は必ず衰えることになる。
実際、聖書信仰によって世界中が悪逆非道の渦中に巻き込まれた結果、
既存の教学文化のうちでも、善行を旨とするものであればあるほど、表社会からの
雲隠れを決め込むこととなってしまった。儒学や大乗仏教の実践はほぼ完璧に廃れ、
神道や道教やヒンズー教も、その品質を大幅に低下させてしまっている。修羅道に
勧善懲悪の情緒を加味した日本の武道も、権威を失墜させてその多くが形骸化し、
スポーツ化で高尚な精神性を失った流派ほど幅を利かせるようにもなっている。
(そういう形骸的な武道ほど、実際、勧善懲悪のために善用することも困難なのである)
ただ衰退しているというばかりでなく、確信的に隠退を決め込んでいる流派もまた
いくらかはあるはずで、そこには右往左往するような優柔不断さも全くない。ただ、
悪逆非道によって世界を侵略し尽くそうとする不埒者などには決して教授してやる
こともない、独自の秘伝や密法をひたすら温存していくことにのみ徹しているのである。
その四書五経と真逆の記述を寄せ集めているだけでしかない
権力犯罪聖書——通称聖書もまた、悪行の規範としては完璧に磐石なものである。
天人修羅の三善趣と共に、地獄餓鬼畜生の三悪趣が六道の内に包含されているように、
人が善行に反する悪行によって、一定の生活規範を保てることもまた一つの真理である。
天道や人道に即して磐石な人生を送れるほどにも、餓鬼道や畜生道に即して磐石な
人生を送ることが実際、人間には可能である。ただ、三善趣(特に人天の二道)と
三悪趣が一ところで共存や共栄することだけは真理に即して不可能なことであり、
どちらかが威勢を蓄えたぶんだけ、もう一方の威勢は必ず衰えることになる。
実際、聖書信仰によって世界中が悪逆非道の渦中に巻き込まれた結果、
既存の教学文化のうちでも、善行を旨とするものであればあるほど、表社会からの
雲隠れを決め込むこととなってしまった。儒学や大乗仏教の実践はほぼ完璧に廃れ、
神道や道教やヒンズー教も、その品質を大幅に低下させてしまっている。修羅道に
勧善懲悪の情緒を加味した日本の武道も、権威を失墜させてその多くが形骸化し、
スポーツ化で高尚な精神性を失った流派ほど幅を利かせるようにもなっている。
(そういう形骸的な武道ほど、実際、勧善懲悪のために善用することも困難なのである)
ただ衰退しているというばかりでなく、確信的に隠退を決め込んでいる流派もまた
いくらかはあるはずで、そこには右往左往するような優柔不断さも全くない。ただ、
悪逆非道によって世界を侵略し尽くそうとする不埒者などには決して教授してやる
こともない、独自の秘伝や密法をひたすら温存していくことにのみ徹しているのである。
人天こそは勇躍の機会を得る、浄土が仏の加護を得ることはあっても、鬼畜の天下たる
穢土が仏や本物の神の加護を得ることもないので、悪逆非道にまみれた穢土こそは、
いつかは必ず自業自得で潰える運命にある。穢土が潰え去り、鬼畜が滅び尽くした後に
また善趣の文化が息を吹き返し、穢土では隠し通されていた諸々の秘法までもが開陳
されていくこととなる。その神々しき文化興隆に一切協賛することができないことが、
穢土こそを我が世としていた鬼畜どもに対する、最大級の罰ともなるのである。
むしろ知らないでいたほうがマシだったような、浅知恵悪知恵ばかりを貪った挙句に
自業自得で滅亡し、真に価値ある知恵や、それに根ざした文化が花開くときには
もはや自分たち自身がこの世にいない。これ程もの不幸が、他にあるだろうか?
「孟子斉を去りて、休に居る。公孫丑問うて曰く、仕えて而も禄を受けざるは、古えの道か。曰く、
非なり。崇に於いて吾れ王に見えるを得るも、退きて去るの志し有り。変るを欲せず、故に受けざるなり」
「孟先生はしばらく滞在していた斉国を去って、休という場所に居た。門弟の公孫丑が『先生は斉国で
客卿としての待遇に与りましたのに、俸禄も受けずに立ち去ってしまいました。これは古の道でしょうか』
先生『そうではない。私は斉国の崇という地で初めて王に謁見したが、それ以来私は色々な献言を尽くしてきた。
しかしその言葉はどれも聞き入れられなかったので、私も退役する志しを固めた。まるで仕事を果たしたかの
ように自他を偽りたくなかったので、俸禄も受けなかったのだ』(孟子が、俸禄を得たからには死兵
とすらなって働く食客風情などとは、明らかに一線を引いていたことがうかがえる逸話にあたる。
恵みを得られる得られないなどという打算にすら動かされない、確かな信念があったのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・公孫丑章句下・一四より)
穢土が仏や本物の神の加護を得ることもないので、悪逆非道にまみれた穢土こそは、
いつかは必ず自業自得で潰える運命にある。穢土が潰え去り、鬼畜が滅び尽くした後に
また善趣の文化が息を吹き返し、穢土では隠し通されていた諸々の秘法までもが開陳
されていくこととなる。その神々しき文化興隆に一切協賛することができないことが、
穢土こそを我が世としていた鬼畜どもに対する、最大級の罰ともなるのである。
むしろ知らないでいたほうがマシだったような、浅知恵悪知恵ばかりを貪った挙句に
自業自得で滅亡し、真に価値ある知恵や、それに根ざした文化が花開くときには
もはや自分たち自身がこの世にいない。これ程もの不幸が、他にあるだろうか?
「孟子斉を去りて、休に居る。公孫丑問うて曰く、仕えて而も禄を受けざるは、古えの道か。曰く、
非なり。崇に於いて吾れ王に見えるを得るも、退きて去るの志し有り。変るを欲せず、故に受けざるなり」
「孟先生はしばらく滞在していた斉国を去って、休という場所に居た。門弟の公孫丑が『先生は斉国で
客卿としての待遇に与りましたのに、俸禄も受けずに立ち去ってしまいました。これは古の道でしょうか』
先生『そうではない。私は斉国の崇という地で初めて王に謁見したが、それ以来私は色々な献言を尽くしてきた。
しかしその言葉はどれも聞き入れられなかったので、私も退役する志しを固めた。まるで仕事を果たしたかの
ように自他を偽りたくなかったので、俸禄も受けなかったのだ』(孟子が、俸禄を得たからには死兵
とすらなって働く食客風情などとは、明らかに一線を引いていたことがうかがえる逸話にあたる。
恵みを得られる得られないなどという打算にすら動かされない、確かな信念があったのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・公孫丑章句下・一四より)
罪障は、それを脳が把捉しているといないとに関わらず、
相応の贖罪に基づくのでなければ、消えることも減ることもない。
カルト信仰の酩酊によって罪障の把捉を完全に疎かにしたままでいられた所で、
最悪、人類滅亡級の悪因苦果にまで結実する罪障のほうは、着実に肥大化していくのみである。
罪を犯した以上は、自らがその罪を相応の罰によって償うのみである。
宗教信仰やその実践などは、罪障を十分に抑制できてから初めて嗜むべきもので、まだ自分が
罪障まみれの内から、逃避目的の宗教信仰などに走ることは、どこまでも卑劣なことでしかない。
卑劣なことだから、罪障の肥大化からなる致命的な規模の悪因苦果もまた避けられるものではない。
大きな罪を犯したままでいるというのなら、どんな宗教信仰やその実践に務めること以上にも、
社会的に公正な手続きに即して罪を償うことを優先すべきである。「罪を犯す」という
行為自体が最強度に俗物の所業であり、高尚な理念など共にある資格のないものであればこそ、
社会的な処罰というしごく卑俗な手段によって対処するのでなければ、誠実さを保てない。
犯罪風情を神なり高尚な理念なりによってどうにかしようとすること自体が、不誠実の至りである。
相応の贖罪に基づくのでなければ、消えることも減ることもない。
カルト信仰の酩酊によって罪障の把捉を完全に疎かにしたままでいられた所で、
最悪、人類滅亡級の悪因苦果にまで結実する罪障のほうは、着実に肥大化していくのみである。
罪を犯した以上は、自らがその罪を相応の罰によって償うのみである。
宗教信仰やその実践などは、罪障を十分に抑制できてから初めて嗜むべきもので、まだ自分が
罪障まみれの内から、逃避目的の宗教信仰などに走ることは、どこまでも卑劣なことでしかない。
卑劣なことだから、罪障の肥大化からなる致命的な規模の悪因苦果もまた避けられるものではない。
大きな罪を犯したままでいるというのなら、どんな宗教信仰やその実践に務めること以上にも、
社会的に公正な手続きに即して罪を償うことを優先すべきである。「罪を犯す」という
行為自体が最強度に俗物の所業であり、高尚な理念など共にある資格のないものであればこそ、
社会的な処罰というしごく卑俗な手段によって対処するのでなければ、誠実さを保てない。
犯罪風情を神なり高尚な理念なりによってどうにかしようとすること自体が、不誠実の至りである。
罪を犯しました、じゃあ刑罰を受けましょう、それら全てが卑俗の極みに当たる現象であり、
特定して「神聖さ」などを一貫して付与してはならない事象にあたる。非俗であることがイヤだ
ってんなら、始めから罪を犯したりもしないでいればいいだけの話なのであり、犯罪という卑俗の
極みのような所業に及んでおいて、その先に自分自身への刑罰以外の、神聖な何ものかを期待しよう
とすること自体、筋が通っていない。聖と俗のけじめを付けていない、みそくそな態度だといえる。
だから、罪を犯したものが十分な贖罪も果たさずに、罪障から眼を背けるための信仰やその実践を
促すような信教の正当性は認められないのであり、仮にあったとした所で、邪教と見なす他はない。
そういう教義を持つ信教である以上は、千年以上の歴史を持つ教派であろうとも、認められはしない。
世界規模での宗教信仰の是正を図るとするならば、必ずそう結論付けられる以外に余地はない。
「言れ師氏に告げらる、言れ帰せよと告げらる。いざ我が私を汚せん、
いざ我が衣を澣がん。害れか澣ぎ害れか否とし、帰して父母を寧んぜん」
「教育係の女官に、『もう嫁いでよい』と告げられた。心身の汚れを洗い落とし、
衣服もすすぎ洗いして奇麗にする。汚濁を漱いで二度とまとわり付かないようにし、
嫁いで従順な妻となり、故郷の父母たちをも安心させたい。(行為能力も子供並みに
制限されている封建時代の女が、嫁いで従順な妻となるための用意として浄心があった。
莫大な行為能力を掌握する大人の男が、浄心ばかりで全てを済ませられるはずもない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・周南・葛覃より)
特定して「神聖さ」などを一貫して付与してはならない事象にあたる。非俗であることがイヤだ
ってんなら、始めから罪を犯したりもしないでいればいいだけの話なのであり、犯罪という卑俗の
極みのような所業に及んでおいて、その先に自分自身への刑罰以外の、神聖な何ものかを期待しよう
とすること自体、筋が通っていない。聖と俗のけじめを付けていない、みそくそな態度だといえる。
だから、罪を犯したものが十分な贖罪も果たさずに、罪障から眼を背けるための信仰やその実践を
促すような信教の正当性は認められないのであり、仮にあったとした所で、邪教と見なす他はない。
そういう教義を持つ信教である以上は、千年以上の歴史を持つ教派であろうとも、認められはしない。
世界規模での宗教信仰の是正を図るとするならば、必ずそう結論付けられる以外に余地はない。
「言れ師氏に告げらる、言れ帰せよと告げらる。いざ我が私を汚せん、
いざ我が衣を澣がん。害れか澣ぎ害れか否とし、帰して父母を寧んぜん」
「教育係の女官に、『もう嫁いでよい』と告げられた。心身の汚れを洗い落とし、
衣服もすすぎ洗いして奇麗にする。汚濁を漱いで二度とまとわり付かないようにし、
嫁いで従順な妻となり、故郷の父母たちをも安心させたい。(行為能力も子供並みに
制限されている封建時代の女が、嫁いで従順な妻となるための用意として浄心があった。
莫大な行為能力を掌握する大人の男が、浄心ばかりで全てを済ませられるはずもない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・周南・葛覃より)
 「上に好む者あれば、下に必ず焉れより甚だしき者あり。
「上に好む者あれば、下に必ず焉れより甚だしき者あり。 君子の徳は風なり、小人の徳は草なり。草は之れに風を加うれば、必ず偃す」
「上に立つ者が好むものは、必ず下の者もまたそれ以上に好むものである。
たとえば支配者が好む徳が風であるとすれば、被支配者が好む徳は草とでも
言ったようなもので、草はこれに風を加えれば、必ず伏せるのである」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・滕文公章句上・二より)
カルト信仰なり、「天は人の上に人を作らず」云々の民権思想なりによって
「草に吹く風」としての支配者の存在性が名目上は覆い隠されるということがある。
それでもやはり、一定以上に大規模な社会における支配構造というのは改変できないもので、
必ずどこかに、庶民の生殺与奪の権限をも一身に背負った支配者が生ずるものである。
その支配者が表向きには姿を隠して、自らの動向をいちいち衆目によって審査されずにも
済むままでいたならば、それこそ真の支配者が表に出る場合以上もの腐敗を招くわけで、
誰からの目付けも受けることがないにことかけての放辟邪侈にも及ぶのである。
そして、いくら自分たちが支配者であることを隠し通そうとも、実質支配者である者が
好き好む性向はその支配対象にも落とし込まれ、支配者が執拗に財を好むようであれば、
被支配者もまた執拗に財を好むようになる。他者から利益を強奪してでも自分たちだけが
私利私欲を満たそうと支配者がしたならば、その性向もまた一般庶民にまで落とし込まれて、
誰といわず財物を奪い合うことが常套と化した乱世をも招いてしまうことになるのである。
被支配者もそれに倣って放辟邪侈を好もうとする。名目上は「草の上に吹く風」が
隠されているものだから、被支配者は自分たちの意思で放辟邪侈を好き好んで
いるかのようにすら思い込んでしまっているが、実際には支配者の悪癖を無意識に
見習った結果として、自分たちまでもが無制限に放辟邪侈をも好むようになっている。
まず、「それが自分たちの自由意思によって選択したことだ」などという思い込みを
衆生から引き剥がすために、衆目からはひた隠された状態のままでいる真の支配者の
存在をも公けにして、民衆の悪癖好みも所詮は支配者に倣ったものでしかなかったのだ
ということを思い知らせる。それによって民衆たち自身の罪は相当に軽減されると共に、
所詮は風になびく草でしかあり得ない、被支配者としての自分たちの矮小までもが思い
知らされる。その上で、素性を公けにしながら浄行を心がけていく支配者の姿を衆生にも
見習わせていくようにして、自分たちまでもが積極的な浄行に励んでいくように促すのである。
支配者の素性を公開することが恐ろしいのも、到底人々にその行いを見習わせるにも値しない
暴君然とした支配者である場合に限ってのことであり、それこそ本人たち自身の死後にでも
公開するしかなかったりすらし兼ねない。自らの行いを広く衆生に見せ付けても恐れる所が
ないぐらいに浄行に努めている支配者であればこそ、確信的に自らの徳によって、草である
衆生たちをなびかせることもできる。所詮は、いつでも草の上に風は吹いているのであるにしろ。
「迅雷風烈には、必ず変ず」
「(孔先生は)ひどい雷や暴風が巻き起これば、必ず態度を変じて居住まいを正された。
(雷や暴風雨に巻き込まれての無駄な危害を被らないため。
またこのような落ち着いた姿こそを人々に見習わせるため)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・郷党第十・二一より)
「仁遠からんや。我れ仁を欲すれば、斯に仁至る(既出)」
「仁は得がたいものだろうか。もし自分から仁を欲したなら、仁はすぐに得られるだろうさ」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・述而第七・二九より)
カルト信仰が、虚言癖や奇行癖を伴うような著しい精神異常を原動力として嗜まれるのに対し、
仁徳はむしろ、そのような精神異常を徹底して排除した所にある、まっさらな正気によって自得される。
精神異常を来たした状態で仁徳は会得できないし、正気によってはカルト信仰に没入することもない。
故に、仁徳の会得とカルト信仰への没入は互いに相容れず、両者を兼修することも絶対にできない。
仁徳を会得した状態と、カルト信仰に没入した状態と、いずれも住心が磐石である点では共通する。
片や浩然の気に根ざして愚童持斎心に安住し、片や誤謬信仰の酩酊に根ざして異生羝羊心に安住する。
そこに安住することに健全なすがすがしさや、無制限な快楽が伴うからこそ永く安住することが出来る。
今まで安住していたカルト信仰状態を卒業するのであっても、自力他力のいずれによるのであれ、
仁徳の会得と共に生きるのであれば、今まで並みかそれ以上の心の安楽と共に生きられる。ただ、
まるでカルト信仰に没入していくようにして、仁徳を会得することが不可能であるのは、上記の通り。
カルト信仰に陥る原因となった精神異常はむしろ払拭して、正気を取り戻したところでこそ仁徳は
得られるものであり、仁徳を得たからこその安楽もまた、正気と共にこそ得られるものなのである。
「仁は得がたいものだろうか。もし自分から仁を欲したなら、仁はすぐに得られるだろうさ」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・述而第七・二九より)
カルト信仰が、虚言癖や奇行癖を伴うような著しい精神異常を原動力として嗜まれるのに対し、
仁徳はむしろ、そのような精神異常を徹底して排除した所にある、まっさらな正気によって自得される。
精神異常を来たした状態で仁徳は会得できないし、正気によってはカルト信仰に没入することもない。
故に、仁徳の会得とカルト信仰への没入は互いに相容れず、両者を兼修することも絶対にできない。
仁徳を会得した状態と、カルト信仰に没入した状態と、いずれも住心が磐石である点では共通する。
片や浩然の気に根ざして愚童持斎心に安住し、片や誤謬信仰の酩酊に根ざして異生羝羊心に安住する。
そこに安住することに健全なすがすがしさや、無制限な快楽が伴うからこそ永く安住することが出来る。
今まで安住していたカルト信仰状態を卒業するのであっても、自力他力のいずれによるのであれ、
仁徳の会得と共に生きるのであれば、今まで並みかそれ以上の心の安楽と共に生きられる。ただ、
まるでカルト信仰に没入していくようにして、仁徳を会得することが不可能であるのは、上記の通り。
カルト信仰に陥る原因となった精神異常はむしろ払拭して、正気を取り戻したところでこそ仁徳は
得られるものであり、仁徳を得たからこその安楽もまた、正気と共にこそ得られるものなのである。
誰かに導かれてではなく、自ら進んで欲することでこそ、仁徳は得られる。
欲する際に外的影響などを介していないほうが、仁徳の会得にかけては確実性が高い。
まず自主的に仁徳を得て、それから忠臣孝養、睦友子愛に神仏への崇敬といった、他者との関わり
も兼ねた仁行に努めていく。仁行徳行のほとんど全てが「世のため人のため」でもあればこそ、
仁徳を会得すること自体は徹底して純粋な自己選択に依るべきである。それでこそ、
自らが何に対しても絶対服従である奴隷的存在となることなどとも一線が引けるのだから。
根本の信仰の部分に、確固たる自己や自己選択が存在しないから、その反動で聖書圏の人間も
極端な個人主義に走ってしまった。信仰すら、そもそも精神異常によって否応なく陥ったものであり、
何一つとして自主性によることなく右往左往させられ続けることこそが信仰によって徹底されたから、
信教を一定以上に劣後する風潮が盛り上がり始めた近世以降には、極端な個人主義にも触れきった。
だからこそ、「世のため人のため」を旨とする仁徳などに帰服することも恐ろしかろうて、
そもそも仁徳は帰服するものではなく自得するものであり、しかも自らの完全なる自主性によって
欲した結果、至るものである。だからこそ心置きなく「世のため人のため」を標榜もできるのだから、
仁徳こそは、その根本の部分に至上にして健全なる個人主義を備えているのだとすら言える。
「行くも之れを使むる或り、止まるも之れを尼むる或り。行くも止まるも、人の能くする所に非ざるなり」
「行くこともそれなりの命運に基づくし、止まることもそれなりの命運に即している。
行くことも止まることも、誰かが作為でどうにかできることではない。(全ての選択は
天命に基づくといえなくもないが、その場合にも、誰かの作為の普遍性などは認められない。
孟子が、天命論に限っては無為自然論者でもあることを示唆した記録ともなっている」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・梁恵王章句下・一六より)
欲する際に外的影響などを介していないほうが、仁徳の会得にかけては確実性が高い。
まず自主的に仁徳を得て、それから忠臣孝養、睦友子愛に神仏への崇敬といった、他者との関わり
も兼ねた仁行に努めていく。仁行徳行のほとんど全てが「世のため人のため」でもあればこそ、
仁徳を会得すること自体は徹底して純粋な自己選択に依るべきである。それでこそ、
自らが何に対しても絶対服従である奴隷的存在となることなどとも一線が引けるのだから。
根本の信仰の部分に、確固たる自己や自己選択が存在しないから、その反動で聖書圏の人間も
極端な個人主義に走ってしまった。信仰すら、そもそも精神異常によって否応なく陥ったものであり、
何一つとして自主性によることなく右往左往させられ続けることこそが信仰によって徹底されたから、
信教を一定以上に劣後する風潮が盛り上がり始めた近世以降には、極端な個人主義にも触れきった。
だからこそ、「世のため人のため」を旨とする仁徳などに帰服することも恐ろしかろうて、
そもそも仁徳は帰服するものではなく自得するものであり、しかも自らの完全なる自主性によって
欲した結果、至るものである。だからこそ心置きなく「世のため人のため」を標榜もできるのだから、
仁徳こそは、その根本の部分に至上にして健全なる個人主義を備えているのだとすら言える。
「行くも之れを使むる或り、止まるも之れを尼むる或り。行くも止まるも、人の能くする所に非ざるなり」
「行くこともそれなりの命運に基づくし、止まることもそれなりの命運に即している。
行くことも止まることも、誰かが作為でどうにかできることではない。(全ての選択は
天命に基づくといえなくもないが、その場合にも、誰かの作為の普遍性などは認められない。
孟子が、天命論に限っては無為自然論者でもあることを示唆した記録ともなっている」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・梁恵王章句下・一六より)
永遠の[アガペー]愛がないなら・・・ 動機が不純なら・・・ お勉強なんて……毒かもね
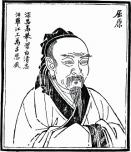 「舌は刃となってこの世を切り裂く」というのが、春秋戦国時代の悪徳外交家、
「舌は刃となってこの世を切り裂く」というのが、春秋戦国時代の悪徳外交家、 通称「縦横家」にとっての決まり文句でもあったらしい。代表的な思想家には
鬼谷子などがいて、その門下で外交戦術を教わった蘇秦や張儀らが、中国全土を
合従連衡や大分裂の波乱に陥れていたことは、「史記」などにも詳しく述べられている。
その、縦横家たちが国際紛争を煽る悪逆非道を繰り返しているさ中に、あまりもの濁世に
愛想を尽かして楚国の重職を退官して後、放浪のさ中に数多の詩歌を唄い、最後には
入水自殺を果たした屈原という詩人がいる。その詩集は「楚辞」として後世にまで受け継がれ、
風流な詩文芸には乏しかった戦国時代の中国文化の中では、異色を放つ存在ともなっている。
「宝玉が欠けようとも磨いて修復することができるが、配慮に欠けた言葉は取り繕いようもない」
とは「詩経」大雅・抑にあり、「言うべきでないことは言うな。理由なきことはわざわざ口にするな」
とも、同じく「詩経」小雅・賓之初筵にある。それでいて「詩経」全体が風流な自然描写や叙情で
埋め尽くされており、配慮に満ちた言うべきこと、由縁あることを述べる文芸の精髄となっている。
唐詩や宋詩、日本の短詩文芸などにおいても、特に自然現象の丹念な描写が秀逸となっている。
和語で歌われる五七五の定型詩は、季語のある詩だけが「俳句」として、季語を持たない「川柳」
とも区別されているほどで、自然現象の季節による移り変わりの描写が特筆して重視されてもいる。
それもやはり、配慮に満ちた理由ある物事を述べる上でも、自然描写がうってつけだからで、
縦横家やカルト教祖が口走るような、根も葉もない虚言とも一線を画せるからなのである。
 配慮と由縁に満ちた善美なる口舌文化は、自然描写の豊かな詩文芸あたりに極まるが、
配慮と由縁に満ちた善美なる口舌文化は、自然描写の豊かな詩文芸あたりに極まるが、 そこまでいかずも、詩文芸の風流さを参考にしたような節度ある言行をたしなめもする。別に、
孔子や孟子の創作した詩歌が後世に残されているわけでもないが、記録に残されているその言行は、
確かに詩学を学んだものならではの節度や品位が保たれたものとなっている。それと比べれば、
春秋戦国時代に世をかき乱していた政商や食客、そして縦横家らの言行には何らの節操もなく、
ただひたすら権力の濫用ばかりに明け暮れていたその姿が、無様極まりないものともなっている。
確かに、詩文芸ばかりに耽っていられるほど平和な時代も恒常的ではなく、乱世に無理にでも
詩文芸の清浄さに与ろうとしたなら、屈原のように自殺せねばならなくなったり、鎌倉幕府三代将軍の
源実朝のように、和歌をうつつを抜かした挙句に首をはねられて暗殺されることになったりもする。
そのような事情があるから、あえて乱世に自ら自身は詩文芸を嗜まなかった孔孟や徳川家康のような人物も
いるわけで、それはそれで時と場合とに柔軟に対応したあり方だといえる。ただ、そうであっても、詩文芸の
善美さを遠ざけつつも尊重の対象とし、極度にその善美さからかけ離れるような、根も葉もない虚言や奇行に
及ぶことは極力避けるという程度の心がけはすべきなのであり、それすらも心がけようとしない時にこそ、
政商や食客や縦横家やカルト信者などとしての、悪口虚言を駆使した罪悪の重畳にも及んでしまうのである。
口舌もまた、善用と悪用の両極に振り切れられるものである。どちらかといえば善用を心がけ、
専らな善用が不可能な場合にも、できる限り悪用を避ける心がけができてこそ、一人前だといえる。
「晋人、文子を人を知ると謂えり。文子は其の中退然として衣に
勝たざるが如くし、其の言吶吶然として諸を其の口から出さざるが如くす」
「晋の人々は、上将軍の趙文子を『他人への配慮がよく利いている』と評していた。
その身は恭しくて、まるで衣服の豪壮さに不相応であるかの如くし、その言葉もどこまでも
朴訥としていて、まるで口から出すことも出来ないでいるかのようだったからだ」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・檀弓下第四より)
相応の対価を得るために仕えるのではなく、仕える以上は仕える。
それでこそ臣下が主君に仕える、あるいは妻が夫に仕える態度だといえる。
対価に相応の随順しか心がけないのは、商売人の態度である。
そんな態度では、世の中のごく一部の権益だけに携わる内はまだ無事でも、
天下国家レベルの大権にまで携わろうとした時には、必ず大破綻を招く。
金をもらった分だけしか働こうとしないような不誠実な態度で、
全世界規模の権益を健全に運用していけるような事実も一切ないからだ。
従う、従わないにさっぱりとした損得勘定が必ず伴う、だから人としての尊厳が
守られているかのような風潮が自由主義や個人主義、男女平等主義などによって広められても
いるが、かりそめの損得勘定ばかりによって全てを回しても問題が起こらなくても済むのは、
上にも書いたとおり、世の中のごく一部の権益に携わる場合に限ってのこと。ごく一部の
権益にしか携わっていられないから、天下国家の尺度から見れば「小人」に相当する存在とも
なるわけで、公利公益に即して物事を考えていた時代に、商人階級こそは「小人」とも呼ばれて、
それ相応の扱いを受けていたりしたことにも、普遍的な理由があったからなのである。
冷徹な損得勘定だけに即して全てを回してれば、そのぶんだけ本人たち自身の
自意識過剰の思い上がりは肥大化するわけで、その肥大化した自意識を以ってして、
忠義や夫唱婦随に務める者よりも雄大であるなどとすら、自由主義や個人主義に即して
見なされるわけだけども、むしろそのような自意識過剰の思い上がりを募らせている者こそは、
天下国家レベルではごく一部の権益にしか携わることを許されない、実相からの小人でしかない。
それでこそ臣下が主君に仕える、あるいは妻が夫に仕える態度だといえる。
対価に相応の随順しか心がけないのは、商売人の態度である。
そんな態度では、世の中のごく一部の権益だけに携わる内はまだ無事でも、
天下国家レベルの大権にまで携わろうとした時には、必ず大破綻を招く。
金をもらった分だけしか働こうとしないような不誠実な態度で、
全世界規模の権益を健全に運用していけるような事実も一切ないからだ。
従う、従わないにさっぱりとした損得勘定が必ず伴う、だから人としての尊厳が
守られているかのような風潮が自由主義や個人主義、男女平等主義などによって広められても
いるが、かりそめの損得勘定ばかりによって全てを回しても問題が起こらなくても済むのは、
上にも書いたとおり、世の中のごく一部の権益に携わる場合に限ってのこと。ごく一部の
権益にしか携わっていられないから、天下国家の尺度から見れば「小人」に相当する存在とも
なるわけで、公利公益に即して物事を考えていた時代に、商人階級こそは「小人」とも呼ばれて、
それ相応の扱いを受けていたりしたことにも、普遍的な理由があったからなのである。
冷徹な損得勘定だけに即して全てを回してれば、そのぶんだけ本人たち自身の
自意識過剰の思い上がりは肥大化するわけで、その肥大化した自意識を以ってして、
忠義や夫唱婦随に務める者よりも雄大であるなどとすら、自由主義や個人主義に即して
見なされるわけだけども、むしろそのような自意識過剰の思い上がりを募らせている者こそは、
天下国家レベルではごく一部の権益にしか携わることを許されない、実相からの小人でしかない。
奴隷のように生まれ付き絶対服従なのではなく、臣下や妻としての素養を得て後に、
自らの意志にも依って臣従したり嫁いだりする。たとえば武家の家に長男として産まれた所で、
あまりにも武士としての素養に欠け過ぎていたために勘当されるなり出家するなりして、
一生将軍や大名に仕えることもなく、日陰の人生を過ごしたりすることも実際にあった。
どうしても仕えたり嫁いだりできない事情があった場合には拒絶することもあった上で、
いざ主君に仕える以上は忠義を尽くし、嫁ぐ以上は妻としての貞節をも守り通していた。
君子階級の男だけでなく、女もまた商売人のような小ざかしい損得勘定などと共には居られず、
まるで夫が主君に絶対的な忠義を尽くしているようにして、自分もまた夫に対する
絶対的な随順を尽くしていた。君子階級ほど、女が社会的な職務を担える余地のない階級も
他にない一方で、君子階級の女であるからには、そんじょそこらの小人の男などよりも
遥かに真剣な態度で生きて行こうとしていたのだから、そこは見上げたものだといえるだろう。
特に、誰しもが自意識過剰の思い上がりを肥大化させきっている、今の世の諸人などからすれば。
「君に事うるに、〜近くして諌めざるは則ち尸利なり。
〜君に事うるには、諌むることを欲して陳ぶることを欲せず」
「主君に仕えている時に、近侍の立場に居ながら諫言にすら努めようとしないのは、
それにより自らが君からの不興を買って、自らの利益を損ねることを恐れる下心があるからだ。
主君に仕える上では、諫言によって君の過ちを未然に食い止めることこそを目指し、
君が過ちを犯してからそれを指摘するようなことがないようにしていかなければならない。
(この記述のとおりに務めたならば、耳に逆らう諫言によって自らが主君からの不興を買い、
自己利益を損ないつつ天下の公益を守ることにもなり得るわけだから、瑣末な損得勘定
などによってこのような忠義を尽くしていくことは、ほぼ不可能に等しいといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・表記第三十二より)
自らの意志にも依って臣従したり嫁いだりする。たとえば武家の家に長男として産まれた所で、
あまりにも武士としての素養に欠け過ぎていたために勘当されるなり出家するなりして、
一生将軍や大名に仕えることもなく、日陰の人生を過ごしたりすることも実際にあった。
どうしても仕えたり嫁いだりできない事情があった場合には拒絶することもあった上で、
いざ主君に仕える以上は忠義を尽くし、嫁ぐ以上は妻としての貞節をも守り通していた。
君子階級の男だけでなく、女もまた商売人のような小ざかしい損得勘定などと共には居られず、
まるで夫が主君に絶対的な忠義を尽くしているようにして、自分もまた夫に対する
絶対的な随順を尽くしていた。君子階級ほど、女が社会的な職務を担える余地のない階級も
他にない一方で、君子階級の女であるからには、そんじょそこらの小人の男などよりも
遥かに真剣な態度で生きて行こうとしていたのだから、そこは見上げたものだといえるだろう。
特に、誰しもが自意識過剰の思い上がりを肥大化させきっている、今の世の諸人などからすれば。
「君に事うるに、〜近くして諌めざるは則ち尸利なり。
〜君に事うるには、諌むることを欲して陳ぶることを欲せず」
「主君に仕えている時に、近侍の立場に居ながら諫言にすら努めようとしないのは、
それにより自らが君からの不興を買って、自らの利益を損ねることを恐れる下心があるからだ。
主君に仕える上では、諫言によって君の過ちを未然に食い止めることこそを目指し、
君が過ちを犯してからそれを指摘するようなことがないようにしていかなければならない。
(この記述のとおりに務めたならば、耳に逆らう諫言によって自らが主君からの不興を買い、
自己利益を損ないつつ天下の公益を守ることにもなり得るわけだから、瑣末な損得勘定
などによってこのような忠義を尽くしていくことは、ほぼ不可能に等しいといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・表記第三十二より)
現状、権力者の保身目的で未だ公けにはされていないが、
「諸行無常」「諸法実相」「諸法因果」「罪福異熟」「万物斉同」
このあたりの真理法則の普遍性は、科学的にも証明され終わっている。
諸法実相に反する形而上の天国への昇天を通じて、
諸行無常に反する永遠の生を勝ち得ようとするような信教は
根本から邪教であると、科学的にも証明され終わっている。
邪教が邪教たることを最大級に客観的に証明して、
完全なる死亡宣告のとどめを刺すのは、結局は科学あたりなる。
しかし、科学が邪教亡き後のこの世界の人間規範までをも
司って行けるのかといえばそんなこともなく、科学自体はどこまでも
産業振興の指針としての存在意義しか持たないままで居続ける。
世界最悪の邪教たるキリスト教に支配された欧米社会でこそ、近代科学も発達し、
その近代科学が完成の日の目を見るにあたって、欧米の文化的母体たる
キリスト教こそは有害無益であることが科学的にも証明された。
大まかに言って、「近代科学はキリスト教に対する親殺しを果たした」
という風に言えなくもない。ルネサンス以降の西洋の科学者らが、
実はイスラム圏で蓄積されていた計算学や幾何学などをも参考にしつつ
科学を発展させていったことが、まだあまり公けにはされてもいないので、
西洋の科学者たちがキリスト信仰の下に科学を発展させて、挙句に
キリスト信仰の不能性を証明してしまったものだから、キリスト教圏は
文化的に「親殺しからなる自滅」に及んだかのような体裁になろうとしている。
「諸行無常」「諸法実相」「諸法因果」「罪福異熟」「万物斉同」
このあたりの真理法則の普遍性は、科学的にも証明され終わっている。
諸法実相に反する形而上の天国への昇天を通じて、
諸行無常に反する永遠の生を勝ち得ようとするような信教は
根本から邪教であると、科学的にも証明され終わっている。
邪教が邪教たることを最大級に客観的に証明して、
完全なる死亡宣告のとどめを刺すのは、結局は科学あたりなる。
しかし、科学が邪教亡き後のこの世界の人間規範までをも
司って行けるのかといえばそんなこともなく、科学自体はどこまでも
産業振興の指針としての存在意義しか持たないままで居続ける。
世界最悪の邪教たるキリスト教に支配された欧米社会でこそ、近代科学も発達し、
その近代科学が完成の日の目を見るにあたって、欧米の文化的母体たる
キリスト教こそは有害無益であることが科学的にも証明された。
大まかに言って、「近代科学はキリスト教に対する親殺しを果たした」
という風に言えなくもない。ルネサンス以降の西洋の科学者らが、
実はイスラム圏で蓄積されていた計算学や幾何学などをも参考にしつつ
科学を発展させていったことが、まだあまり公けにはされてもいないので、
西洋の科学者たちがキリスト信仰の下に科学を発展させて、挙句に
キリスト信仰の不能性を証明してしまったものだから、キリスト教圏は
文化的に「親殺しからなる自滅」に及んだかのような体裁になろうとしている。
キリスト教がこの世から無くなるのはいいことである。それによって
人々が最悪の迷妄を晴らして、今以上の幸福と繁栄に与れるようになるから。
しかし、そのいいことが、理念としての「親殺し」を発端として訪れるというのは
不吉なことであるため、「キリスト教徒主導の近代科学がキリスト教を殺した」
というような体裁は、あまり大々的に触れ回られるべきものでもない。
むしろ、科学法則が結局は陰陽五行や仏法の法則に帰着し、キリスト教の
推進による世界規模の荒廃以前に繁栄していた、優良な異教文化の正当性が
証明されたことのほうをより大々的に触れ回るべきで、「ある文化の死」よりは、
「ある文化の再興」のほうに光を当てることのほうが、前向きともなるに違いない。
これからの、キリスト教文化の死亡は永遠である一方で、不変的な科学法則にも
合致した、優良な伝統文化の興隆こそは永劫でもある。衰滅が永遠であるものよりは、
隆盛こそが永遠であるものに目を向けるほうが、哀しくない上に、道理にも適っている。
「子、罕に利を言うも、命と与に、仁と与にす」
「孔先生は自分一身の利得についてはほとんど語られなかった。
まれに語るときにも、かならず人としての使命や仁義と共に語られた。
(何の使命もなく、ただ私利をむさぼりながら生きることなどは、
語る価値すら無いから、一言も語らなかったのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・子罕第九・一)
人々が最悪の迷妄を晴らして、今以上の幸福と繁栄に与れるようになるから。
しかし、そのいいことが、理念としての「親殺し」を発端として訪れるというのは
不吉なことであるため、「キリスト教徒主導の近代科学がキリスト教を殺した」
というような体裁は、あまり大々的に触れ回られるべきものでもない。
むしろ、科学法則が結局は陰陽五行や仏法の法則に帰着し、キリスト教の
推進による世界規模の荒廃以前に繁栄していた、優良な異教文化の正当性が
証明されたことのほうをより大々的に触れ回るべきで、「ある文化の死」よりは、
「ある文化の再興」のほうに光を当てることのほうが、前向きともなるに違いない。
これからの、キリスト教文化の死亡は永遠である一方で、不変的な科学法則にも
合致した、優良な伝統文化の興隆こそは永劫でもある。衰滅が永遠であるものよりは、
隆盛こそが永遠であるものに目を向けるほうが、哀しくない上に、道理にも適っている。
「子、罕に利を言うも、命と与に、仁と与にす」
「孔先生は自分一身の利得についてはほとんど語られなかった。
まれに語るときにも、かならず人としての使命や仁義と共に語られた。
(何の使命もなく、ただ私利をむさぼりながら生きることなどは、
語る価値すら無いから、一言も語らなかったのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・子罕第九・一)
 洋の東西や古今を問わず、「文字文化とカネ」というのは密接な関係を持ち続けてきた。
洋の東西や古今を問わず、「文字文化とカネ」というのは密接な関係を持ち続けてきた。 為政者といわず商売人といわず、カネを扱うところに最低限の文字文化が必要とされる。
そこに高尚な精神文化などは全く伴わず、単なる数字の操作を厳密にやり込めることだけを
目的とする。その無機質さはある意味、法文処理以上であり、単なる物質経済を全てと考えるのであれば、
高尚な精神性や道徳はおろか、法律以上にも金銭文化こそは、最も原理的なものとして扱われることになる。
文明の金銭文化への依存度の高さは、文字文化そのものの高尚さとは反比例的な関係を持つ。
世界中でも最も金銭文化(主にユダヤ文化)への依存度が高い西洋文明こそは、
文字文化が最も簡素でもあり、アルファベットに特有の書道なども存在しない。
西洋と同じく商業主義的な傾向はあるものの、厳粛な宗教信仰によって金銭文化
そのものを劣後するイスラムには書道文化も存在し、コーランを損壊するものを
極端な憎悪対象にするなどの、過剰とも言える程の書物に対する尊重すらもがある。
乞食行者をも尊ぶインド文化と、商業を徹底した差別下におく伝統的な中国文化
においてこそ、文字文化そのものの高尚さは極まり、金銭文化などともほとんど
隔絶された所に、純粋な道徳や真理にまつわる荘厳な文化体系を構築している。
中国文化やインド文化がとんでもなく膨大で、書道や真言にかけての深遠な体系をも備えていながらも、
金銭本位の物質文化で溢れ返っている今日の世の中で、あまり大した役割を担うようなことがないのも、半ば
確信的なことである。乞食を尊び、商売を劣後する、完全な確信性の下に金銭文化への協力を絶ってもいるのだから。
聖書信仰で「聖霊」などと呼ばれる一つの宗教的要素、その正体はといえば
「金銭文化を司る言葉」とでもいった所で、悪徳的な金融経済が野放しに
なっている所では、そのような言葉がそのままカネも同然の役割を担ったりもする。
中国やインドなどで蓄えられてきた壮大な文字文化は、まさにその「聖霊」を退治することを目的として
編み出されて来たといっても過言ではなく、聖霊の名の下での金銭文化の興隆に協力しないのみならず、
金銭文化の至尊化を積極的に討伐して徹底的な抑制下に置くことをこそ存在目的としているとすらいえる。
金融や物質本位な今の世の中では役立たない、のみならず、今の世の中のその度し難い性向を
頭のてっぺんから完全に降伏し尽くして、身の程を思い知らせるためにこそ役立てられるものであり、
それがイヤだというのなら、永遠に近づいたりすることもなく、完全に無視していればいいだけのことである。
所詮は金融や物質なんて人間にとっては本末のうちの末でしかなく、そればかりにかかずらわっていれば、
そのせいで自業自得の破綻の危機に見舞われるしかないのだから、否応なくそのような自分たちの愚かしさを
降伏していただくしかなくなる時も来るわけだけども、少しでも怨みつらみの不平を残しつつ救いを求めたり
するのなら、そのまま滅びてしまうがいいさ。聖霊への見限りを完全に付けられもしないのなら、そうしたがいい。
「孚有り、血を去りて酡れ出ずる咎无なし。孚有りて酡れ出ずるとは、上と志しを合わせればなり」
「誠心を尽くして上に仕えることで、流血の禍いを去って憂患からも遠ざかり、咎もない。
誠心によって憂患からも遠ざかれるのは、上もまた自分たちと志しを合わせてくれるからである。
(屠殺の流血などは金銭文化からいえば親しいものですらあるが、それは誠心などからは程遠いものである。
自他の血を流してまで奉仕するなどという所にこそ、えてして志しに違う裏心もまたあるものである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・小畜・六四‐象伝)
「金銭文化を司る言葉」とでもいった所で、悪徳的な金融経済が野放しに
なっている所では、そのような言葉がそのままカネも同然の役割を担ったりもする。
中国やインドなどで蓄えられてきた壮大な文字文化は、まさにその「聖霊」を退治することを目的として
編み出されて来たといっても過言ではなく、聖霊の名の下での金銭文化の興隆に協力しないのみならず、
金銭文化の至尊化を積極的に討伐して徹底的な抑制下に置くことをこそ存在目的としているとすらいえる。
金融や物質本位な今の世の中では役立たない、のみならず、今の世の中のその度し難い性向を
頭のてっぺんから完全に降伏し尽くして、身の程を思い知らせるためにこそ役立てられるものであり、
それがイヤだというのなら、永遠に近づいたりすることもなく、完全に無視していればいいだけのことである。
所詮は金融や物質なんて人間にとっては本末のうちの末でしかなく、そればかりにかかずらわっていれば、
そのせいで自業自得の破綻の危機に見舞われるしかないのだから、否応なくそのような自分たちの愚かしさを
降伏していただくしかなくなる時も来るわけだけども、少しでも怨みつらみの不平を残しつつ救いを求めたり
するのなら、そのまま滅びてしまうがいいさ。聖霊への見限りを完全に付けられもしないのなら、そうしたがいい。
「孚有り、血を去りて酡れ出ずる咎无なし。孚有りて酡れ出ずるとは、上と志しを合わせればなり」
「誠心を尽くして上に仕えることで、流血の禍いを去って憂患からも遠ざかり、咎もない。
誠心によって憂患からも遠ざかれるのは、上もまた自分たちと志しを合わせてくれるからである。
(屠殺の流血などは金銭文化からいえば親しいものですらあるが、それは誠心などからは程遠いものである。
自他の血を流してまで奉仕するなどという所にこそ、えてして志しに違う裏心もまたあるものである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・小畜・六四‐象伝)
いくら創作文芸としての手巧の限りを尽くし、挙句にはそこに絶対超越神を登場させて、
現実の諸問題などをもことごとく作中で解消させてみたりした所で、所詮は、新旧約聖書の
作者たち自身はバビロンの囚人だったり、ローマの物狂いだったりする。そうやって現実
から逃避して、空想に救いを求めたりした時点で、決して最善は尽くしていないのである。
問題を解決するための書記姿勢として至上なのは、当該の問題を解決することにかけて
最大級の成功を果たした者の事績や、最大級の失敗を犯した者の罪状をありのままに記録して、
前者を模範の対象とさせ、後者を反面教師の対象とさせることである。その代表が「史記」を
始めとする正史編纂の試みであり、高度な読書の対象として正史に勝るものも他にないといえる。
四書五経のうちでも「書経」や「春秋」は、この条件を満たすことを目的とした歴史書であり、
その編纂者は他でもない孔子である。孔子こそは、世界最古級にして最大級の歴史家でもあり、
司馬遷や班固らもまた、孔門が試みていた歴史書編纂事業の本格化に取り組んだのだといえる。
とはいえ、四書五経はその全てが歴史書なのではなく、易や詩や礼法や、孔子や孟子たち
自身の言行録が含まれている。この内でも、孔子や孟子の言行録に当たる「論語」「孟子」は、
社会的に大成功を果たせたというわけでもない、在野の学者である孔子や孟子の事績をそのまま
収めているわけで、実際に政治機構への接近を試みながらも、濁世ではその学説が理想論に
過ぎるために敬遠されて仕官に失敗するといったような記録までもが、ありのままに記されている。
それでいてやはり、孔子や孟子の言行はどこまでも実地性に根ざしていて、当時の権力者
たちが放辟邪侈の悪癖を取り止めての精進にすら根ざしたなら、実現できたものばかりである。
その証拠に、「論語」の記述をありのままに実践することに務めた漢代の中国や、「孟子」の
記述の実践にすら務めていた江戸時代の日本などが、実際に一定の徳治にも成功しているのである。
現実の諸問題などをもことごとく作中で解消させてみたりした所で、所詮は、新旧約聖書の
作者たち自身はバビロンの囚人だったり、ローマの物狂いだったりする。そうやって現実
から逃避して、空想に救いを求めたりした時点で、決して最善は尽くしていないのである。
問題を解決するための書記姿勢として至上なのは、当該の問題を解決することにかけて
最大級の成功を果たした者の事績や、最大級の失敗を犯した者の罪状をありのままに記録して、
前者を模範の対象とさせ、後者を反面教師の対象とさせることである。その代表が「史記」を
始めとする正史編纂の試みであり、高度な読書の対象として正史に勝るものも他にないといえる。
四書五経のうちでも「書経」や「春秋」は、この条件を満たすことを目的とした歴史書であり、
その編纂者は他でもない孔子である。孔子こそは、世界最古級にして最大級の歴史家でもあり、
司馬遷や班固らもまた、孔門が試みていた歴史書編纂事業の本格化に取り組んだのだといえる。
とはいえ、四書五経はその全てが歴史書なのではなく、易や詩や礼法や、孔子や孟子たち
自身の言行録が含まれている。この内でも、孔子や孟子の言行録に当たる「論語」「孟子」は、
社会的に大成功を果たせたというわけでもない、在野の学者である孔子や孟子の事績をそのまま
収めているわけで、実際に政治機構への接近を試みながらも、濁世ではその学説が理想論に
過ぎるために敬遠されて仕官に失敗するといったような記録までもが、ありのままに記されている。
それでいてやはり、孔子や孟子の言行はどこまでも実地性に根ざしていて、当時の権力者
たちが放辟邪侈の悪癖を取り止めての精進にすら根ざしたなら、実現できたものばかりである。
その証拠に、「論語」の記述をありのままに実践することに務めた漢代の中国や、「孟子」の
記述の実践にすら務めていた江戸時代の日本などが、実際に一定の徳治にも成功しているのである。
権力者たちからのあまりもの冷遇に打ちひしがれて、孔子や孟子もまた、犯罪聖書の作者のように
現実から完全に逃避した夢想論ばかりを並べ立てることだって出来たはずである。それによって、
不埒な幻想の流布を果たし、世の中を大きな不安に陥れて、世の中への復讐を果たすみたいなこと
だって考えられなくはなかったはずだ。しかし、孔孟はそんなことなど露ほどにも志すことなく、
ただひたすら、天下国家の安寧と繁栄との実現を目的とした、着実な徳治の手法ばかりを世の中に
広め続けることを——半ば存命中の成功は不可能であると察しつつ——試み続けたのである。
「史記」や「漢書」中の成功者のような人生を、自分が送れるとも限らない。
場合によっては一生、日の目を見ないままに人生を終える可能性だってあり得る。
そうであってもなお、犯罪聖書の作者やキリストのように、世の中への復讐を込めた乱世画策の
寓意を拵えることなどを試みたりはせずに、孔子や孟子のように、着実に治世を実現する権力道徳の
手法のみを学んだり、身に付けたり、触れ回ったりするように心がけることができるわけである。
ここにこそ、「先天的な落ち度は許されようもあるが、後天的な落ち度は許されようもない」という
「書経」太甲中の教えもまた適用されるのであり、孔子や孟子のように、最大級の先天的な不遇を
ものともせず後天的な浄行を尽くした者がいればこそ、先天的な不遇にかられて後天的な悪行にも
及んだ、犯罪聖書の作者やイエキリの罪が決して許されるものではないことまでもが確かなのである。
「予れ兆民に臨むに、懍乎として朽索の六馬を馭するが若し。人の上たる者、奈何ぞ敬わん」
「私は億兆の民の統治に臨むに際し、戦々恐々として、まるで朽ちた手綱で六頭もの馬を御している
かのような思いであった。人の上に立つ者として、どうしてそれぐらいの恭敬を欠かさずにいられよう。
(朽ちて枯れることもある現実の世界から逃避して、思い上がりを募らせていたりする余裕はないのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・夏書・五子之歌より)
現実から完全に逃避した夢想論ばかりを並べ立てることだって出来たはずである。それによって、
不埒な幻想の流布を果たし、世の中を大きな不安に陥れて、世の中への復讐を果たすみたいなこと
だって考えられなくはなかったはずだ。しかし、孔孟はそんなことなど露ほどにも志すことなく、
ただひたすら、天下国家の安寧と繁栄との実現を目的とした、着実な徳治の手法ばかりを世の中に
広め続けることを——半ば存命中の成功は不可能であると察しつつ——試み続けたのである。
「史記」や「漢書」中の成功者のような人生を、自分が送れるとも限らない。
場合によっては一生、日の目を見ないままに人生を終える可能性だってあり得る。
そうであってもなお、犯罪聖書の作者やキリストのように、世の中への復讐を込めた乱世画策の
寓意を拵えることなどを試みたりはせずに、孔子や孟子のように、着実に治世を実現する権力道徳の
手法のみを学んだり、身に付けたり、触れ回ったりするように心がけることができるわけである。
ここにこそ、「先天的な落ち度は許されようもあるが、後天的な落ち度は許されようもない」という
「書経」太甲中の教えもまた適用されるのであり、孔子や孟子のように、最大級の先天的な不遇を
ものともせず後天的な浄行を尽くした者がいればこそ、先天的な不遇にかられて後天的な悪行にも
及んだ、犯罪聖書の作者やイエキリの罪が決して許されるものではないことまでもが確かなのである。
「予れ兆民に臨むに、懍乎として朽索の六馬を馭するが若し。人の上たる者、奈何ぞ敬わん」
「私は億兆の民の統治に臨むに際し、戦々恐々として、まるで朽ちた手綱で六頭もの馬を御している
かのような思いであった。人の上に立つ者として、どうしてそれぐらいの恭敬を欠かさずにいられよう。
(朽ちて枯れることもある現実の世界から逃避して、思い上がりを募らせていたりする余裕はないのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・夏書・五子之歌より)
「物事には本末がある」という考え方は、
陰陽思想や万物斉同思想によってこそ磐石ともなる。
「アリ」か「ナシ」かなどという短絡的な決め付けではなく、
根本に当たるものと末節に当たるものとが、陽と陰として万物を形成している。
根本たる陽だけでも、末節たる陰だけでも万物を形成することはできず、
両者が一定の差別関係に置かれながら調和することで、万物が安泰になるとされる。
東洋人にとっては、言葉で表すまでもなく自然と備わっている世界観だが、
西洋人にはこのような高度な世界観は始めからは全く備わっていない。
ただ、有るべきものと無かるべきものとがこの世に暫定的に存在していて、
有るべきものに追従して無かるべきものを滅ぼしていくことで
世界が発展していくというような観念までしか持ち合わせていない。
その短絡的なものの考え方が、自業自得で西洋人たち自身に大きな恐怖感をもたらしてもいる。
自分たちが「有るべきもの」の側からあぶれて、「無かるべきもの」の側に組み込まれて、
迫害や殲滅の対象となることを、他でもない自分たちの考え方によってこそ恐れている。
そういったものの考え方全てを、陰陽法則や万物斉同の実相にも根ざした、
「本末調和」の考え方によってこそ刷新していくべきだといえる。
仮に、自分が本末の内の末の側に組み込まれた所で、末節は末節でそれなりの存在意義がある。
一方で、根本にも根本で重大な存在意義があり、末節以上にも尊重されるべきものですらある。
根本が生きて末節が死ぬのでも、末節が生きて根本が死ぬのでも世界は立ち行かず、
お互いの分をわきまえた根本と末節が調和することによってこそ、世界も保たれる。
陰陽思想や万物斉同思想によってこそ磐石ともなる。
「アリ」か「ナシ」かなどという短絡的な決め付けではなく、
根本に当たるものと末節に当たるものとが、陽と陰として万物を形成している。
根本たる陽だけでも、末節たる陰だけでも万物を形成することはできず、
両者が一定の差別関係に置かれながら調和することで、万物が安泰になるとされる。
東洋人にとっては、言葉で表すまでもなく自然と備わっている世界観だが、
西洋人にはこのような高度な世界観は始めからは全く備わっていない。
ただ、有るべきものと無かるべきものとがこの世に暫定的に存在していて、
有るべきものに追従して無かるべきものを滅ぼしていくことで
世界が発展していくというような観念までしか持ち合わせていない。
その短絡的なものの考え方が、自業自得で西洋人たち自身に大きな恐怖感をもたらしてもいる。
自分たちが「有るべきもの」の側からあぶれて、「無かるべきもの」の側に組み込まれて、
迫害や殲滅の対象となることを、他でもない自分たちの考え方によってこそ恐れている。
そういったものの考え方全てを、陰陽法則や万物斉同の実相にも根ざした、
「本末調和」の考え方によってこそ刷新していくべきだといえる。
仮に、自分が本末の内の末の側に組み込まれた所で、末節は末節でそれなりの存在意義がある。
一方で、根本にも根本で重大な存在意義があり、末節以上にも尊重されるべきものですらある。
根本が生きて末節が死ぬのでも、末節が生きて根本が死ぬのでも世界は立ち行かず、
お互いの分をわきまえた根本と末節が調和することによってこそ、世界も保たれる。
実際に、この世界はそういう風にできているのだから、考え方以前に、それを普遍法則として
承諾しないことには、本当にこの世界も立ち行かなくなる。最低限のこととして、本末調和
という法則の普遍性を他人行儀にでもうべなうことがあった上で、さらには自分たちのものの
考え方までをも本末調和に合わせていって、「アリかナシか」で全てを決め付けてしまう
原始的なものの考え方を卒業していくことが、より前進的な心がけとして推奨されるのである。
その上では、本末調和に違背するものの考え方をけしかける邪義だけは、廃絶が免れ得ない。
わざわざ今さら特定するまでもない「例の邪義」は、他でもない西洋人たち自身が育んできた
科学理論によってその不当性が確証され、否応のない全否定の運命にも立たされてもいる。
とはいえ、その邪義が全否定されて廃絶された所で、かつてそれに取り込まれていた被害者
たちが、実相にかなった本末調和の考え方へと転向できるとも限らず、考え方だけは結局
「アリかナシか」の旧態依然としたもののままに止まったままでいることもあり得るのである。
教育が足りなければ、確実に考え方だけはそのままでもあり続ける。
それ程にもこの世界の普遍法則としての本末調和のほうが特殊なものであり、
何らの教化もなく自然と人々にその把握が備わるなどということを期待できる
ものでもないから、その特殊法則としての本末調和を大いに教化していくことで、人々の
原始的に過ぎるものの考え方の自業自得からなる恐怖を、払拭していくことが必要だといえる。
「夫れ礼は自らを卑くして而して人を尊ぶ。負販の者と雖も、必ず尊ぶべきものあるなり」
「礼儀礼節は自らを卑しんで、他者を尊ぶことを促す。仮に本当に礼節に適おうとするのなら、
商品を背負って販売するような賤しい身分の者にすら、尊ぶべきものを見つけるはずである。
(古代ユダヤ人がやっていたような賤業も、卑しいながらに尊ぶべき所があったりした。
身分の尊卑で完全に関係性が断絶するなどと思い込んだことこそは決定的な落ち度である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・曲礼上第一より)
承諾しないことには、本当にこの世界も立ち行かなくなる。最低限のこととして、本末調和
という法則の普遍性を他人行儀にでもうべなうことがあった上で、さらには自分たちのものの
考え方までをも本末調和に合わせていって、「アリかナシか」で全てを決め付けてしまう
原始的なものの考え方を卒業していくことが、より前進的な心がけとして推奨されるのである。
その上では、本末調和に違背するものの考え方をけしかける邪義だけは、廃絶が免れ得ない。
わざわざ今さら特定するまでもない「例の邪義」は、他でもない西洋人たち自身が育んできた
科学理論によってその不当性が確証され、否応のない全否定の運命にも立たされてもいる。
とはいえ、その邪義が全否定されて廃絶された所で、かつてそれに取り込まれていた被害者
たちが、実相にかなった本末調和の考え方へと転向できるとも限らず、考え方だけは結局
「アリかナシか」の旧態依然としたもののままに止まったままでいることもあり得るのである。
教育が足りなければ、確実に考え方だけはそのままでもあり続ける。
それ程にもこの世界の普遍法則としての本末調和のほうが特殊なものであり、
何らの教化もなく自然と人々にその把握が備わるなどということを期待できる
ものでもないから、その特殊法則としての本末調和を大いに教化していくことで、人々の
原始的に過ぎるものの考え方の自業自得からなる恐怖を、払拭していくことが必要だといえる。
「夫れ礼は自らを卑くして而して人を尊ぶ。負販の者と雖も、必ず尊ぶべきものあるなり」
「礼儀礼節は自らを卑しんで、他者を尊ぶことを促す。仮に本当に礼節に適おうとするのなら、
商品を背負って販売するような賤しい身分の者にすら、尊ぶべきものを見つけるはずである。
(古代ユダヤ人がやっていたような賤業も、卑しいながらに尊ぶべき所があったりした。
身分の尊卑で完全に関係性が断絶するなどと思い込んだことこそは決定的な落ち度である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・曲礼上第一より)
カルト教祖としての布教活動中に、イエキリの為した言行が
有罪か無罪かなどということとも無関係に、進んで冤罪被害者に
なることで、強盗殺人級の重罪人への刑罰すらをも肩代わりしようとした
末期のイエスのふざけきりこそは、ありのままに大罪と見なせるものだ。
冤罪は、それによって刑罰を免れた真犯人の罪を多重化させるのみならず、
不当な裁決を行ってしまった法務処理者の罪責すらをも加味してしまう。
「冤罪を認めてしまった」ということが、法務機関の道義的な信頼性を地に墜とす。
強盗殺人犯の死刑囚バラバの代わりにイエキリを磔刑に処し、すでに拘束下にあった
バラバはといえば無罪放免にしてしまったローマ総督のピラトは、それによって自ら
の法の下での正義を根底にまで貶めた。引責辞職ぐらいは当たり前の大失態であり、
その後にも後任者がバラバの処刑などに務めるのでなければ、ローマ総督府の正義は
取り戻されえなかったわけだが、そのような努力が果たされたような事実もない。
それによりローマ帝国の支配者としての正義もまた地に墜ちて、それはそれで所詮は
邪教の内に過ぎないキリスト教などに、全国の支配権を乗っ取られもしたのだった。
冤罪は、その災厄としての度し難さによって、道徳観の未熟な国や天下を乗っ取る
原動力とすらなり得る。道徳意識が十分に成長した世の中であれば、冤罪にすら
適当な処分を科して、世の中の健全性を保つこともできるが、せいぜい正義の根拠が
法律止まりであるような未熟な世の中においては、法務処理者をも巻き込んでの疑獄を
もたらす冤罪現象が、全く自浄不能なものとしてのさばることとなってしまうのである。
有罪か無罪かなどということとも無関係に、進んで冤罪被害者に
なることで、強盗殺人級の重罪人への刑罰すらをも肩代わりしようとした
末期のイエスのふざけきりこそは、ありのままに大罪と見なせるものだ。
冤罪は、それによって刑罰を免れた真犯人の罪を多重化させるのみならず、
不当な裁決を行ってしまった法務処理者の罪責すらをも加味してしまう。
「冤罪を認めてしまった」ということが、法務機関の道義的な信頼性を地に墜とす。
強盗殺人犯の死刑囚バラバの代わりにイエキリを磔刑に処し、すでに拘束下にあった
バラバはといえば無罪放免にしてしまったローマ総督のピラトは、それによって自ら
の法の下での正義を根底にまで貶めた。引責辞職ぐらいは当たり前の大失態であり、
その後にも後任者がバラバの処刑などに務めるのでなければ、ローマ総督府の正義は
取り戻されえなかったわけだが、そのような努力が果たされたような事実もない。
それによりローマ帝国の支配者としての正義もまた地に墜ちて、それはそれで所詮は
邪教の内に過ぎないキリスト教などに、全国の支配権を乗っ取られもしたのだった。
冤罪は、その災厄としての度し難さによって、道徳観の未熟な国や天下を乗っ取る
原動力とすらなり得る。道徳意識が十分に成長した世の中であれば、冤罪にすら
適当な処分を科して、世の中の健全性を保つこともできるが、せいぜい正義の根拠が
法律止まりであるような未熟な世の中においては、法務処理者をも巻き込んでの疑獄を
もたらす冤罪現象が、全く自浄不能なものとしてのさばることとなってしまうのである。
「罪なくして死地に就くを忍びず。〜罪なくして死地に就くを隠む」
「罪もなく死地に追いやられるものに対して忍びない気持ちを抱く。
罪なく死地におもむかされるようなものに対しては哀悼の意を抱く。
(斉の宣王は生贄のため屠場に連れて行かれる牛を見ていたたまれない気持ちになり、
『その牛を犠牲にするのを止めよ』と命じた。結局、生贄の儀式をやめるわけには
いかなかったので、牛よりも小さい羊を生贄のために殺すこととなったが、孟子は、宣王が、
罪もなく死地に赴かされるような相手を見れば、たとえその相手が動物であっても忍びない
気持ちになれる、慈しみの心の持ち主であることを高く評価した。『人間生贄教』である
キリスト教がこの世から根絶された所で、肉用獣などを罪もなく殺すことは、世の中が総出
を挙げて肉食の禁止にでも取り組まないことには、途絶し得ないことである。そうであっても、
そもそも人であれ動物であれ、生き物が何の罪なく殺されたりすることには一定の忍びなさを
抱けるだけの、心の繊細さを大事にすべきなのである。世の中がどのような段階にあるのであれ、
罪なきものの犠牲を嬉しがるような壊れた神経は、できる限り忌まれて然るべきなのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・梁恵王章句上・七より)
「罪もなく死地に追いやられるものに対して忍びない気持ちを抱く。
罪なく死地におもむかされるようなものに対しては哀悼の意を抱く。
(斉の宣王は生贄のため屠場に連れて行かれる牛を見ていたたまれない気持ちになり、
『その牛を犠牲にするのを止めよ』と命じた。結局、生贄の儀式をやめるわけには
いかなかったので、牛よりも小さい羊を生贄のために殺すこととなったが、孟子は、宣王が、
罪もなく死地に赴かされるような相手を見れば、たとえその相手が動物であっても忍びない
気持ちになれる、慈しみの心の持ち主であることを高く評価した。『人間生贄教』である
キリスト教がこの世から根絶された所で、肉用獣などを罪もなく殺すことは、世の中が総出
を挙げて肉食の禁止にでも取り組まないことには、途絶し得ないことである。そうであっても、
そもそも人であれ動物であれ、生き物が何の罪なく殺されたりすることには一定の忍びなさを
抱けるだけの、心の繊細さを大事にすべきなのである。世の中がどのような段階にあるのであれ、
罪なきものの犠牲を嬉しがるような壊れた神経は、できる限り忌まれて然るべきなのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・梁恵王章句上・七より)
 正義の最大級の根拠が、法律ではなく普遍道徳や真理にこそある世の中であれば、
正義の最大級の根拠が、法律ではなく普遍道徳や真理にこそある世の中であれば、 法務処理者自身に全ての法権が集中してしまうようなこともないために、
法治機構を巻き込んでの冤罪が絶対的な安定性を獲得するようなこともない。
漢の文帝の時代、高祖劉邦と共に帝国勃興の礎となった武将の絳侯周勃が、
文帝からの使者を武装して迎えていたために謀反の疑いをかけられ、獄につながれた。
周勃は軍務にかけては有能だったものの、朴訥で弁舌能力などには欠けていたために、
政治ではあまり能力を発揮することができず、弁説豊かな陳平らに重職をも譲っていた。
投獄中にも言葉で弁解することがうまく行かず、弁解の内容を詳記した手紙を賄賂と
共に獄吏に渡して、朝廷の高位者に届けさせた。賄賂を用いたりしたその手段は決して
褒められたものではないものの、わざわざ弁解を手紙にして送ったりしたあたりが、
周勃の巧言令色の寡なさを示唆する振る舞いでもあるとして、太后や袁盎らの感銘を買い、
文帝への熟諫などの協力も得て、最終的には釈放されることとなったのだった。
上の事例などは、他人の罪を自分が背負った場合ではなく、無実の罪を自分が着せられた
場合の冤罪にあたるわけだが、そうであるにしたって、漢帝国が法治よりも徳治のほうを
より尊重している世の中であったからこそ、冤罪が解消された実例となっている。
法治主義の致命的な欠陥としては、他に公務員の極度の堕落化などが挙げられるが、
冤罪の解消がほぼ不可能であることもまた、法治主義の最大級の欠陥の一つであるといえる。
これらの欠陥を補うためにこそ、法治に徳治を上乗せすることが有効ともなる。
法治を捨て去って徳治に移行するのではなく、法治に徳治を上乗せするのである。
今となっては、「聖書の神への帰依が磐石である」ということは、
「人類を自分たちごと滅亡へと陥れる覚悟が磐石である」ということと全く道義となっている。
キリスト教であれユダヤ教であれ、聖書信仰が貫かれることこそは人類滅亡のシナリオであり、
それをくじくことこそは、人類の滅亡を回避する上での最重要課題ともなっている。
悪性新生物(ガン)にも転移するものもあればしないものもあるし、
薬による「散らし」が可能なものとそうでないものとまでもがある。
「転移」という面では、社会統治の理念としてあまりにも無責任な側面が大きすぎる
聖書信仰がこれ以上に世界的覇権を拡大させていくことが不可能に等しく、実際に
聖書信者数は70億人を超える世界人口のうちでも20億人程度で頭打ち状態となっている。
「薬による散らし」は、言ってみれば聖書信者に対する「説得による棄教の促し」とでも
言った所で、ちゃんと事情を説明したなら、さほど信仰心が旺盛なわけでもない今の聖書圏の
大部分の人々も応じてくれるものと思われる。ただ、「全員が全員」それに応じてくれるなどとも
楽観するわけには行かず、頑なに棄教を拒む者に対して社会的制限をかけるなどの実力行使が
必要になる場合も考えられるる。これこそは、ガン細胞でいう所の「手術による切除」ともなる。
ガン細胞の転移、すなわち聖書信仰のこれ以上の世界的拡大は抑制されているとして、
では伸び悩み状態にある聖書圏をこのまま飼い殺し状態にしておけばどうなるかといって、
やはり、それによる地球人類の破滅が免れられるともいえない。欧米聖書圏だけで世界中の
富の八割以上が独占されていることなど、聖書圏が全世界に対してかけている負担の度合いが
あまりにも過剰なために、極度の疲弊に晒された地球人類の側の致命的荒廃が避けられないから。
「人類を自分たちごと滅亡へと陥れる覚悟が磐石である」ということと全く道義となっている。
キリスト教であれユダヤ教であれ、聖書信仰が貫かれることこそは人類滅亡のシナリオであり、
それをくじくことこそは、人類の滅亡を回避する上での最重要課題ともなっている。
悪性新生物(ガン)にも転移するものもあればしないものもあるし、
薬による「散らし」が可能なものとそうでないものとまでもがある。
「転移」という面では、社会統治の理念としてあまりにも無責任な側面が大きすぎる
聖書信仰がこれ以上に世界的覇権を拡大させていくことが不可能に等しく、実際に
聖書信者数は70億人を超える世界人口のうちでも20億人程度で頭打ち状態となっている。
「薬による散らし」は、言ってみれば聖書信者に対する「説得による棄教の促し」とでも
言った所で、ちゃんと事情を説明したなら、さほど信仰心が旺盛なわけでもない今の聖書圏の
大部分の人々も応じてくれるものと思われる。ただ、「全員が全員」それに応じてくれるなどとも
楽観するわけには行かず、頑なに棄教を拒む者に対して社会的制限をかけるなどの実力行使が
必要になる場合も考えられるる。これこそは、ガン細胞でいう所の「手術による切除」ともなる。
ガン細胞の転移、すなわち聖書信仰のこれ以上の世界的拡大は抑制されているとして、
では伸び悩み状態にある聖書圏をこのまま飼い殺し状態にしておけばどうなるかといって、
やはり、それによる地球人類の破滅が免れられるともいえない。欧米聖書圏だけで世界中の
富の八割以上が独占されていることなど、聖書圏が全世界に対してかけている負担の度合いが
あまりにも過剰なために、極度の疲弊に晒された地球人類の側の致命的荒廃が避けられないから。
聖書信仰はそのまま許容するとして、欧米聖書圏が寡占している八割以上の世界資源を均等に
振り分けることなどだけを想定してみたならば、この場合は聖書信者の過度の反発が避けられない。
異教徒がどうなろうがお構いなしで、ただひたすら自分たちだけが狭隘な栄華を謳歌すること
(選民主義)こそは聖書信仰において正義ともされているのだから、異教徒のために自分たちの
富の大半を失うなどということを、聖書信者としての立場から認められるものでもない。
かような思考実験を通じて、「人類の滅亡を回避するためには、聖書信仰の地球上からの
根絶だけは避けることができない」という結論を導き出すことができる。もうこれまでにも
幾度となく同じような思考実験を繰り返してきたが、やはり結論が結論なものだから、
できる限り多くの再試験を重ねて、その無謬性を極限まで高めることに務めて来たのだ。
いくら純度100%の邪教とはいえ、片田舎の極西社会で2000年にもわたって執拗に信じ込んで
きたものを破棄させられる気持ちを考えてみたならば、やはり忍びないものがあるからだ。
「磐桓たり。貞に居るに利ろし。〜磐桓と雖も、志しは正しきを行うなり」
「極度の艱難に遭って、立ちすくむことこそが磐石となってしまう。それでも貞正でいるのがよい。
艱難に立ちすくむことが磐石となってしまった所で、やはり行いを正しくする志しでいるべきである。
(聖書信者はまさに、磔刑という大難の恐怖によって立ちすくみが磐石となってしまった状態=磐桓の
状態にある。だからといって貞正さや正行を損なってしまったのは聖書信者の落ち度であり、凶行である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——屯・初九‐象伝より)
振り分けることなどだけを想定してみたならば、この場合は聖書信者の過度の反発が避けられない。
異教徒がどうなろうがお構いなしで、ただひたすら自分たちだけが狭隘な栄華を謳歌すること
(選民主義)こそは聖書信仰において正義ともされているのだから、異教徒のために自分たちの
富の大半を失うなどということを、聖書信者としての立場から認められるものでもない。
かような思考実験を通じて、「人類の滅亡を回避するためには、聖書信仰の地球上からの
根絶だけは避けることができない」という結論を導き出すことができる。もうこれまでにも
幾度となく同じような思考実験を繰り返してきたが、やはり結論が結論なものだから、
できる限り多くの再試験を重ねて、その無謬性を極限まで高めることに務めて来たのだ。
いくら純度100%の邪教とはいえ、片田舎の極西社会で2000年にもわたって執拗に信じ込んで
きたものを破棄させられる気持ちを考えてみたならば、やはり忍びないものがあるからだ。
「磐桓たり。貞に居るに利ろし。〜磐桓と雖も、志しは正しきを行うなり」
「極度の艱難に遭って、立ちすくむことこそが磐石となってしまう。それでも貞正でいるのがよい。
艱難に立ちすくむことが磐石となってしまった所で、やはり行いを正しくする志しでいるべきである。
(聖書信者はまさに、磔刑という大難の恐怖によって立ちすくみが磐石となってしまった状態=磐桓の
状態にある。だからといって貞正さや正行を損なってしまったのは聖書信者の落ち度であり、凶行である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——屯・初九‐象伝より)
 人が善性を手に入れるためには、自らの生命としての本源
人が善性を手に入れるためには、自らの生命としての本源 からなる善性にこそ立ち返ることを心がけるべきである。決して
「土くれによって造られた自らの生体などに善性は存在し得ない」
などと決め付けて、自分自身以外の何かに善性を求めたりすべきではない。
そうであろうと心がけることが、原理的に人間が善性を手に入れる至当な手段となっている。
そうでないんなら、ただ自分以外の何かに善性の在り処を求めればいいだけだが、実際問題、
人間にとっては修身こそが善性を手に入れる上での最善策となるのであり、修身を疎かにして
までの外物への拘泥こそは、善性を失って悪性にかられる原因にもなってしまうのである。
理論的には、純粋な位相上の問題であり、仮に人間が善性の拠り所と
すべきものが内面ではなく外面にあったとしたならば、それに添って
外物こそを主要な拠り所とすればよかっただけのことである。
善性の拠り所とすべきものが、人間の内面にあると考えたから孟子は性善説を唱え、
内面にそれだけのものはないと考えたから荀子は性悪説を唱えた。だからといって、
孟子が善人で荀子が悪人だったというのではなく、善性の拠り所とすべきものを
孟子は内面に見定めた一方、荀子は外面に見定めたという違いがあるのみである。
それが片や善思善言善行の取っ掛かりとなり、片や悪思悪言悪行の取っ掛かりとなった
とした所で、その選択は善に基づいていたとも悪に基づいていたとも言えず、故にこそ、
善悪もその取っ掛かりにまで遡れば、もはやそこには善も悪もなかったことが知れるのである。
孟子が性善説を唱え、荀子が性悪説を唱える分岐点となったのは、本人たち自身の
「勇気」の有無だった。孟子には場合によっては戦役すら辞さないほどもの勇猛さがあったが、
荀子には戦役全般を頭ごなしに否定し尽くす生粋の臆病さばかりのみがあった。
その勇猛さの有無が、自分たち自身の本性からの善性の発露、それに基づく
善思善言善行を推進していけるか否かという意見を分かつこととなったのだった。
東洋人が主に性善説に根ざした思想宗教哲学を構築し、西洋人は主に性悪説に根ざした
思想宗教哲学を構築してきたのは、本人たち自身の「光明」に対する信奉の有無による。
日出ずる東方への居住を好んだ東洋人は、自分たち自身の陽性さを養って行った一方、
日没する西方への居住を好んだ西洋人は、逆に自分たち自身の陰性を深刻なものとさせた。
その結果、それぞれに性善説を拠り所にしたり性悪説を拠り所にしたりして、善性の在り処
を自分たち自身の内面に求めたり、外面に求めたりしていくこととなったのだった。
それが結果として片や積善につながり、片や積悪につながった。構築されて来たものは
一概に善だったり悪だったりするものの、それを志し始めるに至ったきっかけはといえば、
光明に対する信奉の有無や勇気の有無のような、善とも悪とも言えないようなものだった。
「善悪も本質的には虚空である」という真理がそこにあるのであり、その真理の諾いにもよって、
積善を果たせた者は増上慢を防ぎ、積悪に陥ってしまった者は自分たちを慰めればいい。
善悪の分別など未だ未熟だった頃の過ちも、徳行も共に、虚空の真理の下で安んずるのである。
「形色は天性なり。惟だ聖人にして然る後に以て形を踐む可し」
「以って生まれた人間としての形態や容色こそは、ありのままに天性に適っている。ただ、
仁徳を修めた聖人となることで初めて、その形色の天性を踏襲することができるのである」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・仁心章句上・三八より)
「勇気」の有無だった。孟子には場合によっては戦役すら辞さないほどもの勇猛さがあったが、
荀子には戦役全般を頭ごなしに否定し尽くす生粋の臆病さばかりのみがあった。
その勇猛さの有無が、自分たち自身の本性からの善性の発露、それに基づく
善思善言善行を推進していけるか否かという意見を分かつこととなったのだった。
東洋人が主に性善説に根ざした思想宗教哲学を構築し、西洋人は主に性悪説に根ざした
思想宗教哲学を構築してきたのは、本人たち自身の「光明」に対する信奉の有無による。
日出ずる東方への居住を好んだ東洋人は、自分たち自身の陽性さを養って行った一方、
日没する西方への居住を好んだ西洋人は、逆に自分たち自身の陰性を深刻なものとさせた。
その結果、それぞれに性善説を拠り所にしたり性悪説を拠り所にしたりして、善性の在り処
を自分たち自身の内面に求めたり、外面に求めたりしていくこととなったのだった。
それが結果として片や積善につながり、片や積悪につながった。構築されて来たものは
一概に善だったり悪だったりするものの、それを志し始めるに至ったきっかけはといえば、
光明に対する信奉の有無や勇気の有無のような、善とも悪とも言えないようなものだった。
「善悪も本質的には虚空である」という真理がそこにあるのであり、その真理の諾いにもよって、
積善を果たせた者は増上慢を防ぎ、積悪に陥ってしまった者は自分たちを慰めればいい。
善悪の分別など未だ未熟だった頃の過ちも、徳行も共に、虚空の真理の下で安んずるのである。
「形色は天性なり。惟だ聖人にして然る後に以て形を踐む可し」
「以って生まれた人間としての形態や容色こそは、ありのままに天性に適っている。ただ、
仁徳を修めた聖人となることで初めて、その形色の天性を踏襲することができるのである」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・仁心章句上・三八より)
 良くも悪しくも、「土地」こそは最も磐石な富の源泉となる。
良くも悪しくも、「土地」こそは最も磐石な富の源泉となる。 肥沃な土地、痩せた土地、資源のある土地、温泉の出る土地、何も出ない土地と色々あって、
それぞれの土地の特性をうまく生かした事業に励むことが、良くも悪しくも最も磐石な富の獲得方法となる。
「良くも悪しくも」といったのは、恵まれた土地によってもたらされる富が
地権者に過剰な堕落を許して、働きもしないで豪遊できることが当たり前で
あるかのような考え方までをも時には根付かせてしまうことがあるからだ。
東洋の封建社会においては、そのような地主身分に対する卑しみが儒学道徳にも基づいて嗜まれ
(里仁第四・一一の「小人は土を懐う」など)、地権の嵩にかかって莫大な富を囲い込むことなども、
許されないこととまではいかずとも、決して立派な行いなどとは見なされて来なかった。
ところが西洋はといえば、地主と貴族はほぼ同等の存在だった。一国の国王なども
特に裕福な地主が代表してなったりするばかりで、これと決めて割り振られた封土全体を
公益に適うように統治する官職を別に置くような、東洋的な締まりのよさはなかった。
それを問題視したマルクスらが、無産階級(労働者)が有産階級(地主などの資産家)を
革命によって滅ぼすことを正当化した共産主義をぶち上げたりもしたわけだが、そこには地主らを
専ら「貴族」と見なしきってのルサンチマンが未だ滞留していたのであり、そもそも地主風情を
いっさい高貴な身分であるなどとは見なさない、東洋的な分別などは全く欠けていたのである。
 西洋において、地主に対する見識が未熟なままに止まり続けたのは、
西洋において、地主に対する見識が未熟なままに止まり続けたのは、 儒学道徳に相当するような君子道徳が欠けていたことと、不毛の地である砂漠地帯の
価値観を基本としたイスラエル聖書を至上の聖典として来たこととの両方を原因としている。
砂漠こそは、まさに不毛の地の最たるものであり、地権に対する価値を見出しにくい風土の至りである。
実際に砂漠地帯たる中東を居住地として来た人々は行商を主要な生業とし、全く地の利などをあてにしてはいない。
砂漠地帯の内部であれば、そういった地権を無視したものの考え方がそのまま通用するわけだが、
欧米のようなそれなりに恵まれた国土において、地権を無視ないし軽視する砂漠地帯のものの考え方が犯罪聖書
によって輸入された結果、地権の嵩にかかって富を貪る行いに対する卑しみもまた、行き届かなかったのである。
富は良くも悪しくも、あぶく銭のように膨れ上がっては消え去るばかりのものではない。
土地の恵みに即して膨大な富が長年にわたってもたらされることも、良くも悪しくもあり得ることで、そこに
万端の責任を持って封土を治めきろうとする者と、私利私欲のために地権を濫用しようとする者との両者が生じ得る。
この内の前者を優遇して後者を冷遇する心がけがないことには、後者の過剰な膨れ上がりまでもが生じてしまうわけで、
実際に地権を駆使して大事業を為すことが試みられる文明社会において、土地に対する諦観を持つことはあって
然るべきことだといえる。見識の未熟なものが巨大な地権を持つことは、気 違いに刃物も同然なことなのだから。
「子衛に適く。冉有僕す。子曰く、庶きかな。冉有曰、既に庶し。又た何をか加えん。
曰く、之れを富まさん。曰く既に富まんに、又た何をか加えん。曰く、之れを教えん」
「孔先生は冉有を従えて衛国に赴かれた。国の様子を見て、『人口が増大しているね』と指摘された。
冉有『人口は十分とすれば、さらに何を加えたらよろしいでしょうか』 先生『富ませたらよい』
冉有『すでに富も十分としましたなら、さらに何を加えましょうか』 先生『教育を充実させよう』
(人口と富とを堅実かつ正当に保っていく教育を施す。富は富で大事にすべきものなのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・子路第十三・九より)
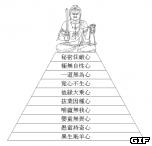 人性の根本は、全く以ってこの世界と同根であり、その根本性に即して考え、
人性の根本は、全く以ってこの世界と同根であり、その根本性に即して考え、 言行することがありのままに、この世界のための思考や言行ともなる。
もちろんその根本性ばかりに即せるとも限らず、根本性から乖離した濁念によってこそ
思考や言行してしまうこともあるわけで、その時にこそ何も世のため人のためにならず、
かえって公益を損ねてまで私益を貪るような悪逆非道の企てにまで繋がってしまうのである。
そのような事態に陥らないためにも、陥ってから後に立ち直るためにも、人は自らの根本性にこそ
立ち返るべきなのであり、それによってのみ過ちを止めて、正しきを為すこともまた可能となるのである。
根本性から乖離した濁念ばかりに囚われて害心の塊と化してしまっている人間が、害心の浄化を
外物などに求めて、挙句には形而上の超越神などにすがったとしたならば、それは自らの害心こそを
堅固なものと化してしまうばかりのこととなり、寸分たりとも害心が清められることにはならない。
形而上の超越神あたりこそは、害心を岩の如く固め尽くすにもうってつけの依存対象となる。
それは、形而上の超越神こそはこの世界と何のかかわりもない、無責任極まりない存在だからで、
世のため人のためにならず、かえって世と人とを損なおうとする害心にとっても最高の伴侶となるからだ。
形而上の超越神への心理的依存によって、害心を岩の如く固めた人間が、正心に立ち戻って
善思善言善行を為せるようになるまでの道のりこそは、最も長い更生の道のりともなる。
 まずは、形而上の超越神への依存を取り止めて、害心こそを堅固なものとすることを途絶する。
まずは、形而上の超越神への依存を取り止めて、害心こそを堅固なものとすることを途絶する。 ここでまず極度の不安症になり、親からはぐれた幼子ほどもの悲痛にかられるはずである。
その悲痛を乗り越えて、外物ではなく自らの根本性に立ち返る修練を重ねる。道徳の勉強でも
座禅でも武道でもヨガでも、間違ったものですらなければ手段は何でもいいが、自らの性根に立ち返る
修練を通じて濁念を止め、常日ごろから性根に即した思考や言行が為せるような正心を得るのである。
害心を岩の如く固めたままで、正心を得るなんてことだけはあり得ないから、どちらかを捨てて
もう一方を取ることはやはり必須だ。弘法大師は「十住心論」で、「秘密荘厳心にまで至れた者は、
(異生羝羊心を含む)あらゆる住心を自由に行き来することができる」とも書かれているが、それも、
一ところの住心に止まらないでいる融通無碍さがあるからなのであり、害心まみれの異生羝羊心に
岩の如く凝り固まりきっているなどというのでは、そのような自由さが得られることもないのである。
「害心を完璧に捨て去れるほどに立派であれ」などとも、別に誰しもに強要したりするわけでもないが、
害心にこそ凝り固まって一切変じようがないなどという状態だけは、いい加減卒業すべきだといえる。
人が正心こそを堅固なものとすることが稀であるのと同じように、害心こそを
岩のように堅固とさせることもまた、決して健常なことなどではないのだから。
「泰山の巌巌たる、魯邦の鞢む所。亀と蒙とをも奄有し、遂に大東をも荒つ。
海邦に至りて、淮夷も来たりて同らぐ。率いて従わざるは莫し、魯侯の功なる」
「岩肌も隆々たる泰山を、魯国の人々も仰ぎ見る。亀山と蒙山をも配下に置き、東方の国々をも統べる。
海の向こうの淮の夷たちも来訪して和合す。大群を率いて従わない者もないほどの、魯候の大いなる功。
(社会的な大業を成すことで、自らが高名な岩山のようともなる。これは偉大さが岩のように堅固な例だといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・頌・魯頌・閟宮より)
「演劇」というものは、古今東西を問わず頻繁に催されて来ているが、
その取り扱い方はといえば、それぞれに大きな開きがある。
東洋での演劇の取り扱い方はといえば、基本、低い。
別段特殊な技能に基づいたりするわけでもない単なる演技などは、
仏教の妄語戒などにも違反しかねないものなので、決して偉いものなどとはされない。
能や狂言や歌舞伎や京劇などの、特殊な技能を要する演劇はそれはそれで一つの
尊重の対象とされ、技能の持ち主が舞台外においても優遇されるということはあるが、
舞台上と舞台外での扱いには、あくまで厳密な一線が引かれた上でのことに限られる。
古代ローマの頃から今にまで至る、西洋での演劇の持て囃し方こそは、
まさに「無条件」と呼ぶに相応しいもの。舞台上で奇抜な演技をできるものは即座に
持て囃されて、舞台を降りてもまるで演劇上の人物であるかのように羨望される。
そもそもが舞台上で要求されるものが、必ずしも特殊技能などではないから、
現実と舞台上の分別を必ずしも付けたりする必要もない。
必ずしも演劇を否定したりする必要はないし、またすべきでもないが、舞台上と現実に
厳密な一線を引く演劇こそは尊ばれるべきである一方、両者の間に必ずしも一線を引かない
ような公私混同型の演劇は、「ジャンク」としての扱いに止められてしかるべきだといえる。
その取り扱い方はといえば、それぞれに大きな開きがある。
東洋での演劇の取り扱い方はといえば、基本、低い。
別段特殊な技能に基づいたりするわけでもない単なる演技などは、
仏教の妄語戒などにも違反しかねないものなので、決して偉いものなどとはされない。
能や狂言や歌舞伎や京劇などの、特殊な技能を要する演劇はそれはそれで一つの
尊重の対象とされ、技能の持ち主が舞台外においても優遇されるということはあるが、
舞台上と舞台外での扱いには、あくまで厳密な一線が引かれた上でのことに限られる。
古代ローマの頃から今にまで至る、西洋での演劇の持て囃し方こそは、
まさに「無条件」と呼ぶに相応しいもの。舞台上で奇抜な演技をできるものは即座に
持て囃されて、舞台を降りてもまるで演劇上の人物であるかのように羨望される。
そもそもが舞台上で要求されるものが、必ずしも特殊技能などではないから、
現実と舞台上の分別を必ずしも付けたりする必要もない。
必ずしも演劇を否定したりする必要はないし、またすべきでもないが、舞台上と現実に
厳密な一線を引く演劇こそは尊ばれるべきである一方、両者の間に必ずしも一線を引かない
ような公私混同型の演劇は、「ジャンク」としての扱いに止められてしかるべきだといえる。
 それこそ、「舞台上で罪を犯していないから」「舞台上で罪が清められたから」
それこそ、「舞台上で罪を犯していないから」「舞台上で罪が清められたから」 などという理由で、現実での服罪を疎かにする犯罪者までもが頻発しかねないからで、
公私混同型の演劇などが持て囃されている以上は、そのような犯罪者に
対する責任の追及もまたうやむやになってしまうから。
それこそ、確かに妄語戒の違反からなる罪障の蔓延の助長にもなっているわけで、
その点、演劇そのものではなく、演劇上の特殊技能こそを特定して保護してきた
東洋のあり方のほうが、演劇受容の仕方として節度を守って来ているといえる。
舞台上での演劇やスポーツなどばかりに耽り過ぎたために、ローマ帝国も自壊したように、
大衆向けの娯楽文化ばかりに飲み込まれ尽くした国や世界というのは、それによる自壊が
免れられるものでもない。西洋人は今までそれしか知らなかったから、同じ過ちをまた
米英崩壊などの形で繰り返しつつもあるが、全世界的に見れば、過ちを改める方法は
実在するわけだから、西洋人にとっても「過ちを改めざる、これを過ちという」という
教条はすでに通用的なものとなっている。今度も過ちを改めないようであれば、それこそ
お天道様までもがそれを許さないがために、人類の滅亡までもが避けられないのである。
「犠牲既に成え、粢盛既に潔く、祭祀時を以てす。然して旱乾水溢あれば、則ち社稷変じて置く」
「立派な犠牲と、清浄な穀物を供え、祭祀もしかるべき時に執り行って、それでもなお旱魃や
水害が起こるようであれば、社稷ごとそっくり造り直してしまう。(君子現実を見て豹変す)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句下・一四より)
たとえば、俺がこうして書いていることの大半は、単なる現実である。
ネット上に投稿して来た原稿用紙数万枚ぶんの文章の、ほぼ大半が現実把握の記録。
だからといって何の意図もないなんてことももちろんなく、記録すべき現実を記録して、
すべきでない現実までは記録しない、「春秋の筆法」と呼ばれているような物書きを心がけている。
その名の通り、この筆法は四書五経中の「春秋経」に由来するもので、源流もその筆者である孔子にあたる。
代表的な継承者には「漢書」の著者である班固などがいて、その「漢書」の記述も現実把握+道義的記録
という姿勢を守っている。何でもかんでもやたらと書きまくっている司馬遷の「史記」などと比べれば
その記述もいかめしく、代表的な権力者の引責自殺などの、書くべきではあってもあまり文芸的には
楽しめないような記事こそが目白押しともなっている。(故に「漢書」は難読書の代表格としても扱われている)
上で、「何でもかんでも」とは言ったものの、司馬遷の「史記」もまた当然、史実把握の記録ではある。ただ、
史実のうちでも書くべきことを書いて書くべきでないことを書かない姿勢を貫いている、「春秋」や「漢書」など
とは違って、「史記」は史実ですらあれば何でもかんでも取り上げている。これは万物斉同の道家思想にこそ
由来する筆法で、楽しみながら歴史を学べるという点では、確かに春秋の筆法をも上回っているといえる。
司馬遷は純粋な史家だったが、孔子は礼学者や政治家だったし、班固も史家であると同時に諸官僚でもあった。
純粋な文筆家に止まるのであれば司馬遷のような文筆姿勢でも構わないが、政治家などとしてやっていくのであれば
司馬遷流の筆法ですら「芸能」に過ぎるといえ、読み方によっては味も素っ気もない「春秋」や「漢書」級の
冷徹な文筆に徹することが賢明だといえる。逆に、それぐらいの文筆であれば、実際の政治や軍政の場でも
役立てられたりもするのであり、しかも文章力を役立てた効用が純粋な「勧善懲悪」でもあり得るのである。
ネット上に投稿して来た原稿用紙数万枚ぶんの文章の、ほぼ大半が現実把握の記録。
だからといって何の意図もないなんてことももちろんなく、記録すべき現実を記録して、
すべきでない現実までは記録しない、「春秋の筆法」と呼ばれているような物書きを心がけている。
その名の通り、この筆法は四書五経中の「春秋経」に由来するもので、源流もその筆者である孔子にあたる。
代表的な継承者には「漢書」の著者である班固などがいて、その「漢書」の記述も現実把握+道義的記録
という姿勢を守っている。何でもかんでもやたらと書きまくっている司馬遷の「史記」などと比べれば
その記述もいかめしく、代表的な権力者の引責自殺などの、書くべきではあってもあまり文芸的には
楽しめないような記事こそが目白押しともなっている。(故に「漢書」は難読書の代表格としても扱われている)
上で、「何でもかんでも」とは言ったものの、司馬遷の「史記」もまた当然、史実把握の記録ではある。ただ、
史実のうちでも書くべきことを書いて書くべきでないことを書かない姿勢を貫いている、「春秋」や「漢書」など
とは違って、「史記」は史実ですらあれば何でもかんでも取り上げている。これは万物斉同の道家思想にこそ
由来する筆法で、楽しみながら歴史を学べるという点では、確かに春秋の筆法をも上回っているといえる。
司馬遷は純粋な史家だったが、孔子は礼学者や政治家だったし、班固も史家であると同時に諸官僚でもあった。
純粋な文筆家に止まるのであれば司馬遷のような文筆姿勢でも構わないが、政治家などとしてやっていくのであれば
司馬遷流の筆法ですら「芸能」に過ぎるといえ、読み方によっては味も素っ気もない「春秋」や「漢書」級の
冷徹な文筆に徹することが賢明だといえる。逆に、それぐらいの文筆であれば、実際の政治や軍政の場でも
役立てられたりもするのであり、しかも文章力を役立てた効用が純粋な「勧善懲悪」でもあり得るのである。
史実に限るとはいえ、何でもかんでも網羅しつくそうとする司馬遷流の筆法は、実地では役立てにくい。
そして、史実に限らずあることないこと書きまくったり、実際にはあり得ないようなことばかりを書きまくったり
喋りまくったりする「詭弁」の能力があったなら、その能力こそは実地での「悪逆非道」にすら結び付くのである。
春秋の筆法に根ざすような文章力の研鑽はぜひすべきことだし、司馬遷流の筆法なども身に付けてはならない
などということまではない。ただ、詭弁や虚言を弄して、それこそを文章化する能力などがあったならば、
これこそはあって余計であり、なくて別に困らないものであるといえ、むしろ身に付けないほうがマシだったりする。
残念ながら、そのような詭弁的文章力のほうが今の世の中では「純文学」などとして持て囃されていて、
司馬遷流の筆法も「ノンフィクション」という狭い枠組みに追い込まれ、春秋の筆法はといえば、
もはや文学的な価値はほとんどないかのようにすら扱われてしまっているのである。
本来は、この序列は逆であるべきなのである。書くべき現実を書いて書くべきでない現実を書かない春秋の筆法が第一、
現実であれば何でもかんでも書いてしまう司馬遷流の筆法が第二、あることないことなんでも書きまくる詭弁的な筆法
が第三で、第一と第二こそは文筆の王道とされ、第三は度し難い外道として十分な警戒下に置かれるべきなのである。
>>124-125に「演劇も無条件に礼賛されたりすべきではない」と書いたのと同じように、文芸も無制限に
持て囃されたりされるのはむしろ避けるべきで、筆法が最低限以上の道義性にかなっている場合に限って
「聖文」として扱い、それ以外を「俗文」や「悪文」として、その受容に一定の歯止めをかけるべきなのである。
卑俗な文芸や演劇に慣れきってしまっている現代人にとっては、酷烈な物言いにも聞こえるかもしれないが、
それもまた書くべきことを書いて書くべきでないことを書かない、春秋の筆法にこそ即した記録であるからだ。
正直、その記述をありのままに実践することが、自分自身すらもが畏れ憚るぐらいのものですらあるのだ。
そして、史実に限らずあることないこと書きまくったり、実際にはあり得ないようなことばかりを書きまくったり
喋りまくったりする「詭弁」の能力があったなら、その能力こそは実地での「悪逆非道」にすら結び付くのである。
春秋の筆法に根ざすような文章力の研鑽はぜひすべきことだし、司馬遷流の筆法なども身に付けてはならない
などということまではない。ただ、詭弁や虚言を弄して、それこそを文章化する能力などがあったならば、
これこそはあって余計であり、なくて別に困らないものであるといえ、むしろ身に付けないほうがマシだったりする。
残念ながら、そのような詭弁的文章力のほうが今の世の中では「純文学」などとして持て囃されていて、
司馬遷流の筆法も「ノンフィクション」という狭い枠組みに追い込まれ、春秋の筆法はといえば、
もはや文学的な価値はほとんどないかのようにすら扱われてしまっているのである。
本来は、この序列は逆であるべきなのである。書くべき現実を書いて書くべきでない現実を書かない春秋の筆法が第一、
現実であれば何でもかんでも書いてしまう司馬遷流の筆法が第二、あることないことなんでも書きまくる詭弁的な筆法
が第三で、第一と第二こそは文筆の王道とされ、第三は度し難い外道として十分な警戒下に置かれるべきなのである。
>>124-125に「演劇も無条件に礼賛されたりすべきではない」と書いたのと同じように、文芸も無制限に
持て囃されたりされるのはむしろ避けるべきで、筆法が最低限以上の道義性にかなっている場合に限って
「聖文」として扱い、それ以外を「俗文」や「悪文」として、その受容に一定の歯止めをかけるべきなのである。
卑俗な文芸や演劇に慣れきってしまっている現代人にとっては、酷烈な物言いにも聞こえるかもしれないが、
それもまた書くべきことを書いて書くべきでないことを書かない、春秋の筆法にこそ即した記録であるからだ。
正直、その記述をありのままに実践することが、自分自身すらもが畏れ憚るぐらいのものですらあるのだ。
「庶頑讒説、若し時しきに在らざれば、侯を以て之れを明らかにし、
撻を以て之れを記し、書を用て識らせんかな。並びに生くるを欲さんかな」
「諸々の頑迷で讒言を触れまわるものの内で、特に不正が明らかであるものなどは、
射侯の儀式によってその悪を明らかにし、鞭打ちなどの実刑によってこれを戒め、
その所業をも克明に書き残して、後世にまで長く伝えて行くこととしよう。
それもこれも、末永く人々と共生していくことを欲すればでこそあるのだよ。
(書いていることをそのまま証拠にするのではなく、証拠を得て書く)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・虞書・益稷より)
撻を以て之れを記し、書を用て識らせんかな。並びに生くるを欲さんかな」
「諸々の頑迷で讒言を触れまわるものの内で、特に不正が明らかであるものなどは、
射侯の儀式によってその悪を明らかにし、鞭打ちなどの実刑によってこれを戒め、
その所業をも克明に書き残して、後世にまで長く伝えて行くこととしよう。
それもこれも、末永く人々と共生していくことを欲すればでこそあるのだよ。
(書いていることをそのまま証拠にするのではなく、証拠を得て書く)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・虞書・益稷より)
たとえば、春秋の筆法で書かれた「漢書」の高帝紀において、
著者の班固は「劉家は堯帝の末裔である」という巷説を引き合いに出して、
みずからも「漢は堯帝の命運を継いでいるのだろう」と締めくくっている。
小百姓だった劉家が古えの聖王の末裔だなんてのは全く信憑性のない話で、
それを引き合いに班固も劉家の中華皇帝としての正統性を主張しているものだから、
班固も所詮は虚言家であるかのような物言いが、一部の不勉強な者たちによって為されてもいる。
しかし、そもそも伝承上からして、堯の帝業を本当に継いだのは舜であり、
舜は堯とも全く血のつながりのない、不良な親に悩まされていた小百姓である。
(劉邦も父親に「出来の悪い息子だ」といびられていたことが「史記」などに記録されている)
その舜もまた、自らの帝業を血のつながりのない臣下である禹に譲った。
禹は、自らがカタワになるほどにも中原一帯の治水事業に奔走したとされており、
(劉邦も中原一帯の争乱の平定のために、親族も蔑ろにしての東奔西走の大仕事を果たした)
高祖劉邦はこの舜や禹に極めて類似する功績を挙げたことが間違いないので、その劉邦を
始祖とする漢が堯の帝業を受け継いでいると考えるのも、あながちおかしいことでもないのである。
不勉強なものは、「劉家は堯の末裔である」という俗説を信じていればいいだけのことだし、
ちゃんと勉強するのであれば、劉家が堯の帝業を正統に受け継いでいるのだということを、
末裔論などよりも遥かに着実な根拠の実在に基づいて、計り知ることができるわけである。
春秋の筆法とはこのような、小人が帝位の簒奪を目論むことを最大級に防止するなどの、正当な目的を
込めた筆法のことを言うのであり、その描写姿勢は単なるノンフィクションなどよりも遥かに巧妙である。
ウソも書いているようでいて、やはり書いてはおらず、主観と客観を織り交ぜた巧みな記述によって
読む者に決して不埒な思いなどを抱かせず、ただ善心を養うことだけを促すのである。
著者の班固は「劉家は堯帝の末裔である」という巷説を引き合いに出して、
みずからも「漢は堯帝の命運を継いでいるのだろう」と締めくくっている。
小百姓だった劉家が古えの聖王の末裔だなんてのは全く信憑性のない話で、
それを引き合いに班固も劉家の中華皇帝としての正統性を主張しているものだから、
班固も所詮は虚言家であるかのような物言いが、一部の不勉強な者たちによって為されてもいる。
しかし、そもそも伝承上からして、堯の帝業を本当に継いだのは舜であり、
舜は堯とも全く血のつながりのない、不良な親に悩まされていた小百姓である。
(劉邦も父親に「出来の悪い息子だ」といびられていたことが「史記」などに記録されている)
その舜もまた、自らの帝業を血のつながりのない臣下である禹に譲った。
禹は、自らがカタワになるほどにも中原一帯の治水事業に奔走したとされており、
(劉邦も中原一帯の争乱の平定のために、親族も蔑ろにしての東奔西走の大仕事を果たした)
高祖劉邦はこの舜や禹に極めて類似する功績を挙げたことが間違いないので、その劉邦を
始祖とする漢が堯の帝業を受け継いでいると考えるのも、あながちおかしいことでもないのである。
不勉強なものは、「劉家は堯の末裔である」という俗説を信じていればいいだけのことだし、
ちゃんと勉強するのであれば、劉家が堯の帝業を正統に受け継いでいるのだということを、
末裔論などよりも遥かに着実な根拠の実在に基づいて、計り知ることができるわけである。
春秋の筆法とはこのような、小人が帝位の簒奪を目論むことを最大級に防止するなどの、正当な目的を
込めた筆法のことを言うのであり、その描写姿勢は単なるノンフィクションなどよりも遥かに巧妙である。
ウソも書いているようでいて、やはり書いてはおらず、主観と客観を織り交ぜた巧みな記述によって
読む者に決して不埒な思いなどを抱かせず、ただ善心を養うことだけを促すのである。
 その、春秋の筆法で書かれた「漢書」において、班固は王奔のようなならず者が漢の王統を
その、春秋の筆法で書かれた「漢書」において、班固は王奔のようなならず者が漢の王統を 揺るがすことがないように努める記述に心がけている。小百姓という、本来の劉家の身分の賤しさは
帝位簒奪を目論む格好の理由になりやすく、実際に漢帝国はその初期から群臣の謀反に悩まされていた。
よく勉強してみたなら、劉家が小百姓だったことも帝位の正統性への疑念材料などには全くならない、
のみならず、それこそは舜や禹の化身とするに最も相応しい出自であることまでもが計り知れるわけだが、
そこまでもの勉強が行き届かないが故に、出自の賤しさなどを理由に漢室の淘汰を目論むような連中に
対しては、「劉家は堯の末裔である」などというお粗末な巷説をそのままあてがっておくわけである。
万世一系の天皇家を戴く日本などはともかく、裸一貫の小百姓こそが皇帝にまで上り詰める
という物語構造は、世界的にはむしろ健全なことである。四民制や君子階級の質素倹約などによって、
百姓らに対する万全の保護に努めてきた国や社会なんてのは、世界的には極めて稀有なのだから、慢性的に
虐げられてきた底辺の百姓こそが帝位を得るほうが、カウンターバランスが取れていることにもなる。
実際の国家社会においてこそ、それが健全ともなるのであり、別にルサンチマンのはけ口を信教などに
求めたりする必要もない。信教にはむしろ、不埒なルサンチマンを十全に抑制する効果こそを
期待すべきであり、その期待を満たしてくれる信教も仏教や道教、神道などとして存在する。
いくら底辺の百姓あたりが世界の帝王になるのが道義的に相応しいにしたって、それがしみったれた
ルサンチマンなどを動機として企てられたりするのでは無様である。むしろ自分自身はルサンチマンなど
完全に捨て去って、権力犯罪者としての虚栄に溺れていた連中を「品性上は自分以下の下衆」として
十分に蔑みぬいていることなどを根拠として、帝位にも就くとしたって就くべきである。さすればこそ、
数多の百姓のうちで、誰が世界の帝王となるに相応しいのかも、自然と定まっていくのである。
「上に大澤有れば則ち恵は必ず下に及ぶ。顧るに、上は先に下は後になるのみ。上に積み重なりて、
而こうして下に凍餒の民有るに非ざるなり。是の故に上に大澤有れば、則ち民夫人も下流に待つ。
恵の必ず将に至らんとするを知るなり。餕に由りて之れを見る。故に曰く、以て政を観るべしと」
「(純正な為政者として)上にある者が大いに豊かであるとき、その恵みは必ず下にまで及ぶ。
まず上にある者が恵みを得てから、それが下々の者にも後から至ることでのみ、今までにも
世の中がうまくいってきた。上に十分な蓄財があるにもかかわらず、上凍える民が発生した
ようなことは未だかつてない。そのため、上にある者が十二分に潤っているときには、
民たちも素直に下流に待って不平を抱いたりすることがない。それも、自分たちにまで必ず
恵みが及ぶことを知っているからである。神祇祭祀の際に供える食物の余計如何によってそれが
分かるため、昔から『(祭祀の供えで)政治を判別すればいい』とも言われてきているのである。
(これは当然、政財が癒着して権力者が私的な財を退蔵する民主主義社会での話などではない。
『下にある者から恵む』というイエキリの暴言が『民主主義』という理念の源流ともなっているが、
一部の下が真っ先に恵みを得るような状態では、上下全般への恵みの行き渡りが滞るのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・祭統第二十五より)
而こうして下に凍餒の民有るに非ざるなり。是の故に上に大澤有れば、則ち民夫人も下流に待つ。
恵の必ず将に至らんとするを知るなり。餕に由りて之れを見る。故に曰く、以て政を観るべしと」
「(純正な為政者として)上にある者が大いに豊かであるとき、その恵みは必ず下にまで及ぶ。
まず上にある者が恵みを得てから、それが下々の者にも後から至ることでのみ、今までにも
世の中がうまくいってきた。上に十分な蓄財があるにもかかわらず、上凍える民が発生した
ようなことは未だかつてない。そのため、上にある者が十二分に潤っているときには、
民たちも素直に下流に待って不平を抱いたりすることがない。それも、自分たちにまで必ず
恵みが及ぶことを知っているからである。神祇祭祀の際に供える食物の余計如何によってそれが
分かるため、昔から『(祭祀の供えで)政治を判別すればいい』とも言われてきているのである。
(これは当然、政財が癒着して権力者が私的な財を退蔵する民主主義社会での話などではない。
『下にある者から恵む』というイエキリの暴言が『民主主義』という理念の源流ともなっているが、
一部の下が真っ先に恵みを得るような状態では、上下全般への恵みの行き渡りが滞るのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・祭統第二十五より)
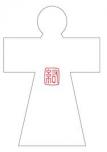 キリスト信仰自体は、旧約信仰などに根ざした悪魔の働きを助長する。
キリスト信仰自体は、旧約信仰などに根ざした悪魔の働きを助長する。 助長して、最大級に活発化させた挙句に、このまま悪魔の働きをのさばらせた
ままでいたなら、一般のキリスト教徒と悪魔役のキリスト教徒やユダヤ教徒と、
その他の異教徒とを合わせた誰しもが破滅を免れ得ない事態にまで至らしめる、
そこまで至った挙句に、キリスト信仰が悪魔ごとこの世から消え去るというのであれば、
キリストもまた、神道でいうところの「形代カタシロ」としての役割を果たすことで、
この世に滞留する害悪を自分ごと祓い清めることに貢献したことになるかもしれない。
「必ずそうなる」とも断言できないのは、キリスト信仰が悪魔の働きを活発化させることで
この世にもたらした豊満な物質文明が、至らない小人の情欲を駆り立てるものであることもまた
確かなことだから。世界中の富を自分たちだけで八割以上も寡占することでこそ成り立っている
キリスト教圏の物質文明の豊満さを、たとえば十分な精神的修養を積んだ聖人や賢人であれば
諦観することができたとしても、そんじょそこらの小人や女子供までもが諦観できるなどとは
とても断言できないわけで、故にこそ、悪魔の働きをキリスト信仰ごとこの世から滅ぼし去る
だけの思い切りが、全世界全人類によって付けられることまでをも期待するのもまた、難しいのだ。
一人当たりの資源占有率で、今ほぼ世界平均と同等の状態にあるインドネシアやフィリピンなどの
世相を鑑みるに、やはり物質的な魅力に長けているなどということはない。特に、今でもスペインや
アメリカによる植民化の禍根が著しいフィリピンについては、イスラム教国化によって社会風紀が
是正されたインドネシアなどと比べても世相の乱れが著しく、売春婦の輸出や人身売買などの
問題がよく取り沙汰されてもいる。民衆の再教育や文化振興も疎かなままに、ただ富の不均衡だけを
是正すれば、欧米キリスト教国なども今のフィリピンのようになるわけで、欧米人たち自身がそれを
望まないだろうことはもちろんのこと、傍目に見てもそれが魅力的なことだなどとはとても思えない。
たとえば、江戸時代の日本などは鎖国状態で、物資面ではほぼ自給自足で、決して物質的に豊かだった
などということもないわけだが、それでも江戸時代の文化などは、今から見ても魅力的な所がある。
それは、江戸社会が物質的な豊かさ以上にも、文化的な豊かさの養生に務めていた社会だったからで、
そのような条件は、未だキリスト教国であるフィリピンはおろか、ほとんど「対キリスト教用の防壁」
としての役割に専らなイスラムに征服されている、今のインドネシアもまた満たせていることではない。
キリスト信仰が活発化させた悪魔の働きが、キリスト信仰ごとこの世から撃滅されて、
悪魔の働きによって画策されていた富の不均衡も是正されたとして、それだけでそこに残るのは
今のインドネシアやフィリピンレベルの世相だけで、もしもキリスト教が持ち越されたままでいたなら、
特に売春天国でもあるフィリピンのようになる。これこそは、仮にキリストが形代としての役割を果たし
きってこの世から退場したとしても、大した成果が見込めない証拠にもなっているわけで、そこから
さらに、江戸時代や平安時代の日本並みにまで文化振興が行き届いて、二度と悪魔の働きなどによって
高等な文化が毀損されないようにするための反面教師材料として、「かつてのキリスト信仰の成果」
が参考にされ、実際に悪魔が二度と現れなくなったとしたならば、それでこそ、キリスト信仰が
この世にプラスマイナスゼロ以上の好影響をもたらしたことにもなり得るのである。
あまり楽しい話でもないのも確かだが、そもそもキリスト信仰にまつわる事物などに楽しみ(福)を見出そう
などとしたことからして大間違いだったのだから仕方がない。悪魔の働きを始めとする罪悪の助長こそを
本分としている、キリスト信仰などとは無縁な所での文化振興にこそ、楽しみをも見出すべきだったのだから。
などということもないわけだが、それでも江戸時代の文化などは、今から見ても魅力的な所がある。
それは、江戸社会が物質的な豊かさ以上にも、文化的な豊かさの養生に務めていた社会だったからで、
そのような条件は、未だキリスト教国であるフィリピンはおろか、ほとんど「対キリスト教用の防壁」
としての役割に専らなイスラムに征服されている、今のインドネシアもまた満たせていることではない。
キリスト信仰が活発化させた悪魔の働きが、キリスト信仰ごとこの世から撃滅されて、
悪魔の働きによって画策されていた富の不均衡も是正されたとして、それだけでそこに残るのは
今のインドネシアやフィリピンレベルの世相だけで、もしもキリスト教が持ち越されたままでいたなら、
特に売春天国でもあるフィリピンのようになる。これこそは、仮にキリストが形代としての役割を果たし
きってこの世から退場したとしても、大した成果が見込めない証拠にもなっているわけで、そこから
さらに、江戸時代や平安時代の日本並みにまで文化振興が行き届いて、二度と悪魔の働きなどによって
高等な文化が毀損されないようにするための反面教師材料として、「かつてのキリスト信仰の成果」
が参考にされ、実際に悪魔が二度と現れなくなったとしたならば、それでこそ、キリスト信仰が
この世にプラスマイナスゼロ以上の好影響をもたらしたことにもなり得るのである。
あまり楽しい話でもないのも確かだが、そもそもキリスト信仰にまつわる事物などに楽しみ(福)を見出そう
などとしたことからして大間違いだったのだから仕方がない。悪魔の働きを始めとする罪悪の助長こそを
本分としている、キリスト信仰などとは無縁な所での文化振興にこそ、楽しみをも見出すべきだったのだから。
「夫れ物の人を感ずること窮まり無くして、人の好悪節無きときは、則ち是れ物至りて而も人、
物に化せるなり。人の物に化せらるなる者は、天理を滅ぼして而かも人欲を窮むる者なり」
「外物が人に与える感傷に極まりがなく、そのせいで人々が好悪の節操を失ったときには、外物の影響力が
完全に人を支配した状態となってしまう。そしてその外物に支配されてしまったような人間こそは、
天理をも滅ぼして、自分一身の欲望を極めようとすることになるのである。(好悪の節操を
信者に失わせて無限の濁愛に溺れさせようとするキリスト信仰こそは、天理を滅ぼすのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・楽記第十九より)
物に化せるなり。人の物に化せらるなる者は、天理を滅ぼして而かも人欲を窮むる者なり」
「外物が人に与える感傷に極まりがなく、そのせいで人々が好悪の節操を失ったときには、外物の影響力が
完全に人を支配した状態となってしまう。そしてその外物に支配されてしまったような人間こそは、
天理をも滅ぼして、自分一身の欲望を極めようとすることになるのである。(好悪の節操を
信者に失わせて無限の濁愛に溺れさせようとするキリスト信仰こそは、天理を滅ぼすのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・楽記第十九より)
一般に、好みやすく愛しやすいものほど天理に違い、好みにくく愛しにくいものほど天理に適っている場合が多い。
常人が好き好み愛すべきものとして「徳」に優るものはなく、仮に徳を愛せたならば、愛することがそのまま天理に適う。
これこそは「仁」のあり方だともいえるわけで、それが可能ならば愛もふんだんに奨励されて然るべきものだが、
残念ながら徳ほどにも愛し難いものもまた稀有であり、故に仁に処ることもまた生半に可能なことではない。
(孔子も高弟の顔淵が三ヶ月間仁に違わぬ生活を送っていただけでも驚嘆している。雍也第六・七参照)
愛しやすいもの、男にとっての美女だとか女にとっての美男だとか、宝物だとかカネだとかいったものはえてして
愛しすぎることが天理に違うものであり、愛しすぎながら為すことの何もかもが不仁に根ざすことともなりかねない。
一般に、人間は五官へ快感と共に強く訴えかけてくるものほど好みやすいようにできているため、愛しやすいものが
身近にあったならさらに愛しやすくなり、疎遠でしかなかったら愛しにくくもなる。だから、仮に「近隣の者を愛せ」
などとけしかけてくるものがいたとすれば、それはすなわち「愛しやすいもののうちでも特に愛しやすいものを愛せ」
とけしかけていることにもなるわけで、これこそは好悪に対して無条件に専らであることを促す暴言ともなっている。
逆に、愛し難いものが身近にあればさらに嫌いになり、疎遠であればそんなに嫌わずに済むという法則もある。
身長2メートル超で怪物のような形相をしていたとされる孔子や、小太りで気難しかったとされる家康公のような
仁者のそばにいることが厭わしいということはあっても、好き好めるなんてこともそうそうにはあり得ないわけで、
遠近でいえば近隣にあるものを重視する性向の持ち主は、自業自得で仁を遠ざけやすくなる実例ともなっている。
ニーチェのように「遠人を愛せ」というのも荒唐無稽に過ぎるが、愛しやすいものよりは愛しにくいものを愛そうと
心がけたほうが、天理に適って仁に近づける可能性も高い。そうあるためには、まず好悪に専らであろうとする浮ついた
神経をできる限り控えて、そこから愛すべきものを愛し、愛すべきでないものを愛さないように分別していく必要がある。
常人が好き好み愛すべきものとして「徳」に優るものはなく、仮に徳を愛せたならば、愛することがそのまま天理に適う。
これこそは「仁」のあり方だともいえるわけで、それが可能ならば愛もふんだんに奨励されて然るべきものだが、
残念ながら徳ほどにも愛し難いものもまた稀有であり、故に仁に処ることもまた生半に可能なことではない。
(孔子も高弟の顔淵が三ヶ月間仁に違わぬ生活を送っていただけでも驚嘆している。雍也第六・七参照)
愛しやすいもの、男にとっての美女だとか女にとっての美男だとか、宝物だとかカネだとかいったものはえてして
愛しすぎることが天理に違うものであり、愛しすぎながら為すことの何もかもが不仁に根ざすことともなりかねない。
一般に、人間は五官へ快感と共に強く訴えかけてくるものほど好みやすいようにできているため、愛しやすいものが
身近にあったならさらに愛しやすくなり、疎遠でしかなかったら愛しにくくもなる。だから、仮に「近隣の者を愛せ」
などとけしかけてくるものがいたとすれば、それはすなわち「愛しやすいもののうちでも特に愛しやすいものを愛せ」
とけしかけていることにもなるわけで、これこそは好悪に対して無条件に専らであることを促す暴言ともなっている。
逆に、愛し難いものが身近にあればさらに嫌いになり、疎遠であればそんなに嫌わずに済むという法則もある。
身長2メートル超で怪物のような形相をしていたとされる孔子や、小太りで気難しかったとされる家康公のような
仁者のそばにいることが厭わしいということはあっても、好き好めるなんてこともそうそうにはあり得ないわけで、
遠近でいえば近隣にあるものを重視する性向の持ち主は、自業自得で仁を遠ざけやすくなる実例ともなっている。
ニーチェのように「遠人を愛せ」というのも荒唐無稽に過ぎるが、愛しやすいものよりは愛しにくいものを愛そうと
心がけたほうが、天理に適って仁に近づける可能性も高い。そうあるためには、まず好悪に専らであろうとする浮ついた
神経をできる限り控えて、そこから愛すべきものを愛し、愛すべきでないものを愛さないように分別していく必要がある。
無条件の愛に没落しきっているような人間からすれば、上記のような愛にまつわる論及からして理屈に過ぎるものと映り、
そのような論及全般を愛よりも劣後しなければならないという判断が、本能的にはたらいてしまうのに違いない。
愛こそは正義、愛ですらあれば正義なのだから、その愛に制限をかけようとしているようにすら見受けられる物言いには、
それ自体が悪であるという短絡的な評価がはたらいて、自らを正義の味方だと自認する陶酔までもが始まるのに違いない。
そしてその、無条件の愛こそを絶対正義と断ずるものの考え方が、今ありのままに人類の滅亡にすら直結している。
それをこのまま推進していけばこそ人類の滅亡すらもが免れ得ないがために、無条件の愛こそは絶対悪だったことを
実証してしまい、以って無条件の愛こそを正義だと断じていた自分たちこそがバカだったことをも証明してしまっている。
無条件の愛こそを絶対化していたような連中こそは、分別の保たれた愛を嗜むことが人一倍困難な心理状態とも化して
しまっている。分別ある愛を嗜むぐらいなら、愛全般を捨て去ってしまうほうがまだ簡単なことだったりもするわけで、
そういった連中に勧められるのは、仁愛の養生よりはむしろ仏門での出家あたりだといえる。無条件の愛を祭り上げ
すぎたことの弊害は、分別によって愛を善用せしめる選択肢の不能性としても結実してしまっているわけで、これこそは
愛そのものではなく、好悪に無条件に専らであろうとした不埒さこそが、真の問題であった証拠ともなっているる。
無条件の愛は愛しやすいものへの愛に結び付き、分別ある愛は愛すべきものへの愛に結び付く。人間にとってはただ
そうであるばかりのことなのだから、無条件の愛のほうが一般的だとか、分別ある愛が統制的だとかいったような
傍観論が、なんら人間にとって実のない論題であることをもわきまえて、我が身の程にこそ落ち着くべきだといえる。
「人の其の言を易んずるは、責め無きのみ」
「人が言葉を軽んずるのは、自らに責める所(責任感)がないからだ。
(責任感がないから、全ての願いは叶えられるみたいな虚言も放っていた)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・離婁章句上・二二より)
そのような論及全般を愛よりも劣後しなければならないという判断が、本能的にはたらいてしまうのに違いない。
愛こそは正義、愛ですらあれば正義なのだから、その愛に制限をかけようとしているようにすら見受けられる物言いには、
それ自体が悪であるという短絡的な評価がはたらいて、自らを正義の味方だと自認する陶酔までもが始まるのに違いない。
そしてその、無条件の愛こそを絶対正義と断ずるものの考え方が、今ありのままに人類の滅亡にすら直結している。
それをこのまま推進していけばこそ人類の滅亡すらもが免れ得ないがために、無条件の愛こそは絶対悪だったことを
実証してしまい、以って無条件の愛こそを正義だと断じていた自分たちこそがバカだったことをも証明してしまっている。
無条件の愛こそを絶対化していたような連中こそは、分別の保たれた愛を嗜むことが人一倍困難な心理状態とも化して
しまっている。分別ある愛を嗜むぐらいなら、愛全般を捨て去ってしまうほうがまだ簡単なことだったりもするわけで、
そういった連中に勧められるのは、仁愛の養生よりはむしろ仏門での出家あたりだといえる。無条件の愛を祭り上げ
すぎたことの弊害は、分別によって愛を善用せしめる選択肢の不能性としても結実してしまっているわけで、これこそは
愛そのものではなく、好悪に無条件に専らであろうとした不埒さこそが、真の問題であった証拠ともなっているる。
無条件の愛は愛しやすいものへの愛に結び付き、分別ある愛は愛すべきものへの愛に結び付く。人間にとってはただ
そうであるばかりのことなのだから、無条件の愛のほうが一般的だとか、分別ある愛が統制的だとかいったような
傍観論が、なんら人間にとって実のない論題であることをもわきまえて、我が身の程にこそ落ち着くべきだといえる。
「人の其の言を易んずるは、責め無きのみ」
「人が言葉を軽んずるのは、自らに責める所(責任感)がないからだ。
(責任感がないから、全ての願いは叶えられるみたいな虚言も放っていた)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・離婁章句上・二二より)
カネかモノかでいえばモノ、モノか食い物かでいえば食い物のほうが
人間にとって必要不可欠なものであり、さらにこれらの「産業媒体」を
トップダウンに統制する公務が、産業全般よりもさらに重大なものとなる。
産業統制(士)、食い物(農)、モノ(工)、カネ(商)という社会構成の
大略を、封建社会では「士農工商」の四民制として序列化してもいた。
今でも農が商工よりも重大であるという程度の認識はそれなりにあるから、
国家によって農業が保護されたりもしているが、商と工の序列はあいまいで、
かえって商のほうが工よりも上に置かれたりしている。そしてなにより、
「士」が全くの無益な存在とされ、士人階級が産業をトップダウンに統制
したりすることこそは「悪逆非道の極み」みたいな扱いまでもがされている。
士人を殊更に権威の座から引き摺り下ろすことの正当化材料としては
最たるものである民主主義、その民主主義が提唱された西洋はといえば、
始めから金持ちの代表が王侯臣官といった士人階級をも兼任し続けて来ていて、
農工商の三民を総じて公正に統治するような、立派な士人が実在した試しがない。
士人はまず、豪商や地主といった「上流階級」の金持ちのために働き、
ついでに「下層階級」である平民にもたまには恵んでやる程度の存在でしか
なかったわけで、そんな士人がいるよりもいないほうがマシであるのも確かな
ことだから、西洋で民主主義が提唱されたのも必然的なことだったといえる。
では、民主主義によって社会統治の理想が達成されたのかといえば、全くそんなことはない。
選挙制によって為政者が民からの拘束を受ける場合であれ、共産制によって生産者と
為政者が同一とのものとして扱われる場合であれ、為政が産業から独立した一人前の
仕事として認められないような事態が到来することによって、結局、為政者が資産家の
傀儡である場合と同等か、それ以上もの問題が巻き起こるばかりのこととなった。
人間にとって必要不可欠なものであり、さらにこれらの「産業媒体」を
トップダウンに統制する公務が、産業全般よりもさらに重大なものとなる。
産業統制(士)、食い物(農)、モノ(工)、カネ(商)という社会構成の
大略を、封建社会では「士農工商」の四民制として序列化してもいた。
今でも農が商工よりも重大であるという程度の認識はそれなりにあるから、
国家によって農業が保護されたりもしているが、商と工の序列はあいまいで、
かえって商のほうが工よりも上に置かれたりしている。そしてなにより、
「士」が全くの無益な存在とされ、士人階級が産業をトップダウンに統制
したりすることこそは「悪逆非道の極み」みたいな扱いまでもがされている。
士人を殊更に権威の座から引き摺り下ろすことの正当化材料としては
最たるものである民主主義、その民主主義が提唱された西洋はといえば、
始めから金持ちの代表が王侯臣官といった士人階級をも兼任し続けて来ていて、
農工商の三民を総じて公正に統治するような、立派な士人が実在した試しがない。
士人はまず、豪商や地主といった「上流階級」の金持ちのために働き、
ついでに「下層階級」である平民にもたまには恵んでやる程度の存在でしか
なかったわけで、そんな士人がいるよりもいないほうがマシであるのも確かな
ことだから、西洋で民主主義が提唱されたのも必然的なことだったといえる。
では、民主主義によって社会統治の理想が達成されたのかといえば、全くそんなことはない。
選挙制によって為政者が民からの拘束を受ける場合であれ、共産制によって生産者と
為政者が同一とのものとして扱われる場合であれ、為政が産業から独立した一人前の
仕事として認められないような事態が到来することによって、結局、為政者が資産家の
傀儡である場合と同等か、それ以上もの問題が巻き起こるばかりのこととなった。
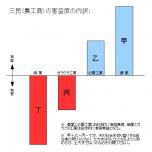 真に必要なのは、為政者と、資産家を含む全ての産業従事者との間に一線を引いて、
真に必要なのは、為政者と、資産家を含む全ての産業従事者との間に一線を引いて、 資産家といえども産業階級の一員でしかなく、しかも着実に食い物やモノを自力で作って
くださっている農夫や工業技術者などと比べれば、格下の産業従事者でしかないのだということを
世の中総出を挙げて認識し、資産家こそを最底辺の社会的立場に追い込むことだといえる。
そのために重要となるのが、一つには儒学のような権力道徳学の流布であり、もう一つが、
国家レベルの武力の洗練だといえる。古代ローマ皇帝や現アメリカ大統領なども、軍の統帥権を
保有していることが大権掌握の最もな根拠となっている。しかし、あまりにも過剰な軍備は、
それ自体が資産家などからの援助によってまでの維持に務めなければならないお荷物となってしまう。
結果、皇帝や大統領といえども軍産複合体の言いなりにならざるを得ないようなことにも
なってしまうわけで、そのうような事態を招かないために、軍備はなるべく最低限に止め、
常用の武器も日本刀のような、低コスト高パフォーマンスのものであるように心がけるべきである。
そこまでして士産の分離を心がけたならば、士人こそはあらゆる産業(金融を含む)の上に立つ、
「人の花形」たる存在ともなり得るわけで、また士人が人々の上に立つことにも、「社会保障の要」
という紛れもない根拠が伴うことにもなる。士人が忠節に務めたならば、それがそのまま産業従事者
同士での人間関係の雛形ともなるし、また士人が孝養に努めたならば、それがそのまま年金破綻後の
世の中での生き抜き方の見本ともなっていく。立派な士人による統治を完全にかなぐり捨てた
世の中が最終的にどうなるかという見本としては、現代社会ほどにもうってつけなものはなく、
結果はといえば「このままだと確実に破滅が免れ得ないと」いうものだった。農工商の三民の
序列を重んずるだけでなく、三民の上に士人をおく四民制全体が必要不可欠な役割を担っていた
ことが現代社会の体たらくによってこそ判明してるのだから、現代社会の体質からの一概な脱却
こそを本気で推し進めていったなら、「禍転じて福と為す」こともそんなに難しいことではない。
「禹は吾れ間然するところ無し。飲食を菲くして孝を鬼神にまで致し、衣服を悪しくして
美を黻冕にまで致す。宮室を卑くして力を溝洫に尽くす。禹は吾れ間然するところ無し」
「夏の禹帝には一点の非の打ち所も無い。自らの飲食を粗末にしながら、孝養は鬼籍の先祖にまで尽くし、
常用の衣服も簡素なものでありながら、位を表す前垂や冠だけは豪華なものとされた。住まいとなる宮室はこれまた
ボロ家でありながら、感慨の水路を立派にすることには力を尽くされた。夏の禹帝には一点の非の打ち所も無い。
(飲食は粗末にしても、位を表す衣装は場合によっては金銀なども用いて飾り付け、序列の徹底を促していた。
全体的に、自分一身の利益よりも天下の公益を禹帝が優先していたことを評する記述となっている)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・泰伯第八・二一より)
美を黻冕にまで致す。宮室を卑くして力を溝洫に尽くす。禹は吾れ間然するところ無し」
「夏の禹帝には一点の非の打ち所も無い。自らの飲食を粗末にしながら、孝養は鬼籍の先祖にまで尽くし、
常用の衣服も簡素なものでありながら、位を表す前垂や冠だけは豪華なものとされた。住まいとなる宮室はこれまた
ボロ家でありながら、感慨の水路を立派にすることには力を尽くされた。夏の禹帝には一点の非の打ち所も無い。
(飲食は粗末にしても、位を表す衣装は場合によっては金銀なども用いて飾り付け、序列の徹底を促していた。
全体的に、自分一身の利益よりも天下の公益を禹帝が優先していたことを評する記述となっている)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・泰伯第八・二一より)
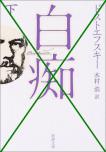 愛ばかりに振り切れてバカになることでも、
愛ばかりに振り切れてバカになることでも、 知識ばかりに振り切れて血も涙もなくなることでもなく、
高度に愛と上知とを両立させていくことが仁の発端ともなる。
幼い我が子が危険に晒されているときに母が抱く恐れなどは、
当然我が子への愛に根ざしているが、かといって愛に溺れきって
蒙昧なままでいたなら、我が子を危険から守ることも叶わない。
だから、健全な母親が幼い我が子などに対して抱く思いは、
えてして愛と知力とをそれなりに両立したものとなる。
世で大業を為す男もまた、そのような愛と知力との両立を以ってことに臨むべきで、
それができたなら自然と言行が仁徳に根ざしたものともなる。それぐらいの男であって
初めて、女が立派な母親である並みの威厳が保たれることにもなるわけで、逆に、
情愛一極や機械的知識一極に振れ切って、ろくに仁徳も養えないというのであれば、
確かにそのような男は、女にすら見下されても仕方のない男止まりであるのだと言える。
(一定数以上の女が立派な母たり得ることで、初めて世の中も成り立っているのだから)
「愛に溺れる以上は知識なんか捨てちまえ、知識に頼る以上は情愛なんか無視しろ、
それでこそTPOをわきまえられた立派な大人だ」なんていう情報洗脳までもが今は潜在的に
まかり通っていたりもするが、これもまた甚だしい転倒夢想の一種で、本当は知と愛を
両立することもできないような人間こそが生粋の未熟者であり、そうあってはならない
見本としてこそ扱うべきなのである。智と愛の両立を仁徳にまで昇華させられていた
士大夫こそが尊ばれていた封建社会においても、情愛一辺倒に陥って獣のごとき情欲を
貪っていた町人などもいなくはなかったわけだけども、だからといって立派な大人扱いなどを
されることもなく、かえって「好色一代男」のような物笑いの種にすらなっていたのである。
 今という時代は、知と愛の両立なんかできない人間、
今という時代は、知と愛の両立なんかできない人間、 愛する以上は馬鹿な愛(白痴)に振れ切り、知識に頼る以上は血も涙も無い
頭でっかち(悪霊)に振れ切るような輩ばかりが保護されている時代である。
しかも、そのような未熟者たちが不正に保護されていたことが、昨今の金融界の不正な
金利操作の発覚などと共に露呈してしまってもいる。金融システムを裏から操作できるような
悪知恵の持ち主が、情欲に振り切れてバカと化すようなカモばかりを低金利の融資で保護し、
世界を左右できる規模の巨万の富を、バカか悪知恵の両極端でしかいられない未熟者たちだけで
独占していたことがばらされたわけで、それに連動して、知と愛を高度に両立させられる
仁者こそは、権力の座から強制的に排除されていたことまでもが明かされてしまったのである。
知識ばかりに頼りきって、血も涙もない疑心暗鬼と化すことが批判されることは
これまでにもあったが、情欲に振り切れて白痴状態と化すことは、たとえば辛い仕事を
やらされている人間の気晴らしなどとしては、かえって推奨すらされているのが現状である。
本当はそれもまたよくないことである、のみならず、白痴並みに蒙昧な情欲への陥りこそは、
心ない知識の鬼にとっての生みの親ですらあったことが、キリスト教圏においてこそ
無機質な機械的知識ばかりが大量に蓄積されて来たことからも明らかなのである。
濁愛か悪知恵かの両極端でしかいられない人間が、仁者たる男以下であるのはもちろんのこと、
我が子を必死で守ろうとする、慈愛ある母ほどもの品性すら保てていない存在であることも
上に書いた通りであり、幼い我が子を惜しみ無き愛と、相応の知恵とで慈しむことを、世の
母親たちの誰しもが放棄したりしたならば(少子高齢化などによって)即座に世の中も
ままならなくなるようにして、バカか悪知恵かの両極端でしかいられない未熟者ばかりが
世を治める大権を牛耳り続けたなら、当然それによっても世の中がままならなくなるのである。
大知はおろか、人並みの知見すら損壊してしまう程の劣情にかられることが、完全に禁止される
とまでいかずとも、決していいものなどとは見なされない程度の扱いは受けて然るべきである。
当然、そのような白痴状態への陥りを「神の降臨」だなどと嘯く病気も去ってしまうべきだ。
「礼の多きを以って貴しと為すは、其の心を外にするを以ってなり。〜
礼の少なきを以って貴しと為すは、其の心を内にするを以ってなり。〜
古えの聖人は之れを内にするを尊しと為し、之れを外にするを楽しみと為す。
之れを少なくするを貴しと為し、之れを多くするを美と為す。是の故に先王の
礼を制するや、多くすべからず、寡なくすべからず、唯だ其れ稱うのみにす」
「礼の実践が多大であることが貴ばれるのは、その内なる敬心が外部に発露するためである。逆に、
礼の実践が寡少であることが貴ばれることもあり、これは内なる敬心の養いに務めている場合である。
昔の聖人は内なる敬心の養いこそをより尊貴とし、それを外部に発露させることはむしろ楽しみとしていた。
敬心の養いに専らなために外的な礼儀が寡少となることをより貴いこととし、ついにはその敬心が発露
されることは善美なこととした。そのため先王の定めた礼制もまた、多すぎることも少なすぎることも
よしとされず、ただ融通に適うように心がけられていた。(他者への情欲によって、自らの思い上がりが
肥大化するのとは逆に、自らの敬心の養いがあってから、それが他者への礼節として発露される。
自意識過剰の思い上がりよりも恭敬のほうが、自らに養う上で自己本位である必要があるのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・礼器第十より)
とまでいかずとも、決していいものなどとは見なされない程度の扱いは受けて然るべきである。
当然、そのような白痴状態への陥りを「神の降臨」だなどと嘯く病気も去ってしまうべきだ。
「礼の多きを以って貴しと為すは、其の心を外にするを以ってなり。〜
礼の少なきを以って貴しと為すは、其の心を内にするを以ってなり。〜
古えの聖人は之れを内にするを尊しと為し、之れを外にするを楽しみと為す。
之れを少なくするを貴しと為し、之れを多くするを美と為す。是の故に先王の
礼を制するや、多くすべからず、寡なくすべからず、唯だ其れ稱うのみにす」
「礼の実践が多大であることが貴ばれるのは、その内なる敬心が外部に発露するためである。逆に、
礼の実践が寡少であることが貴ばれることもあり、これは内なる敬心の養いに務めている場合である。
昔の聖人は内なる敬心の養いこそをより尊貴とし、それを外部に発露させることはむしろ楽しみとしていた。
敬心の養いに専らなために外的な礼儀が寡少となることをより貴いこととし、ついにはその敬心が発露
されることは善美なこととした。そのため先王の定めた礼制もまた、多すぎることも少なすぎることも
よしとされず、ただ融通に適うように心がけられていた。(他者への情欲によって、自らの思い上がりが
肥大化するのとは逆に、自らの敬心の養いがあってから、それが他者への礼節として発露される。
自意識過剰の思い上がりよりも恭敬のほうが、自らに養う上で自己本位である必要があるのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・礼器第十より)
 とにかく働きまくる奴隷状態でも、有閑階級としての悠々自適状態でもなく、
とにかく働きまくる奴隷状態でも、有閑階級としての悠々自適状態でもなく、 徒労は厭いながらも、着実な成果に結び付く仕事にかけては熱心である
ことが、人が一生を送る上で最も生きがいを感じられる方策ともなる。
人は皆いつかは必ず死ぬ、そのことに対して過度の悲哀を抱いたりするのなら、
それはやはり自分の生き方がどこか不健全であるからで、本当に生きがいの
ある生涯を尽くせたならば、人という生き物は臨終に際して悲哀を抱くどころか、
「十分な役目を果たした」という大きな満足と共にすらいることができるのである。
因果関係でいえば、生きがいのある人生が原因で、満足な死が結果である。
同様に、生きがいのない人生が原因となって、不満だらけの死という結果にも至る。
このうちの、満足な死を「涅槃」として教理の中心にも据えているのが仏教で、
そこから生きがいのある人生の送り方を導き出して、それを実践面の教義ともしている。
逆に、生きがいのない人生、不満だらけの死を大前提においてるのが聖書信仰で、
そのような無様な生死が神の導きによる形而上への昇天によって救われるとしている。
生きがいのある人生を送ることで満足な死を迎えるぐらいのことは、儒学だって
大前提としているが、「未だ生を知らず、焉んぞ死を知らん(先進第十一・一二)」
とあるように、生死論にかけて殊更であるようなことから敬遠するようにもしている。
 生きがいのない人生と不満だらけの死を大前提としているような不具者からすれば、
生きがいのない人生と不満だらけの死を大前提としているような不具者からすれば、 世俗での活動の探求ばかりにもっぱらであろうとする儒学の実践者のあり方などは、
特に俗物然として見えるのだろうけども、その活動はといえば、君子としての
仁政の実現に特化されていたりと、それなりの筋が通っている。商人階級だった
古代ユダヤ人はおろか、古代オリエントの諸々の為政者ですらもが君子としての
仁政を心がけていたような試しはほとんどなく、その証拠に、為政者たちが私的に
貯め込んだ財によって無益な土建を繰り返していた痕跡がピラミッドなどとして
遺されてもいるのである。(中国でも、始皇帝陵墓などが近年発掘されているが)
世俗での活動の内に、君子としての仁政などを想定したことすらないような人間が、
そのような活動にかけてこそ熱心であろうとする儒者の「全てを知っている」などと
うそぶく資格は微塵もない。君子としての仁政にまで至れたなら、人は必ず最高に
生きがいのある生と、大満足な死とを享受できるわけだから、そんな因果関係など
始めから露ほどにも知らずに、世俗の活動全般が生きがいのない生と、不満だらけの
死とをもたらすばかりであるなどと決め込むのは、ただのもの知らずだといえる。
俗世においては、儒者の志すようなある種の活動にかけて、生きがいと知足に満ちた
生死を得られることが確かだし、また、超俗においても仏教などにおいて、存命中
の浄行によって「生まれ変わるよりも至上な」涅槃を実現する方策が説かれている。
今生の生死が、生きがいのなさや、不満だらけの死ばかりに見舞われたりしないための
方法は世俗超俗いずれにおいても拓けているのだから、そのような不具な生死を大前提
とした形而上への救いの希求などに拘泥する正当性なども、もはやないのだといえる。
「化者に比るまで、土を膚に親しむる無きは、人の心に於いて独り恔きこと無からんや」
「親の身体が完全に朽ちてなくなるまで、その皮膚すらも土に近づけないように、
孝養を尽くすことほど、誰一人として快さを抱かない者のない行いがあるだろうか。
(いつかは土に帰る身であればこそ、努力が至上の快さにつながる実例)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・公孫丑章句下・七より)
「親の身体が完全に朽ちてなくなるまで、その皮膚すらも土に近づけないように、
孝養を尽くすことほど、誰一人として快さを抱かない者のない行いがあるだろうか。
(いつかは土に帰る身であればこそ、努力が至上の快さにつながる実例)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・公孫丑章句下・七より)
仁徳豊かな君子として自らが世に君臨することが、着実に「生きていないこと」よりも有意義な生を本人にもたらす。
だからこそ、そのような人間が死ぬに際しても、心から生きがいのある人生を送れたと納得もできるのである。
「生きていないこと」よりもさらに意義のない人生もまた確かにあり、そのような人生はすべからく、
君子としての人のあり方に反した人生を送っている。いわゆる「小人」の人生だけども、小人だからといって
必ずしも被支配階級に甘んじているとも限らず、自らの品性は小人であるままに権力だけは手に入れて、
いるよりもいないほうがマシなほどに有害無益な暴政を働く権力犯罪者になってしまうことまでもあるわけで、
その時にこそ「あるよりもないほうがマシな生」もまた極まる。ただ品性が小人止まりなだけでも、
えてして劣等感からなる苦しみなどにあえいだりするものだが、その苦しみを克服するために、「小人のままでの
権力の掌握」という間違った手段に及んだ挙句に、余計に生きていることの苦しみを増大化させてしまうのである。
権力を掌握するかしないかという以前に、まず人が「論語」にあるような意味での「君子」であろうとすることが本来
からの品性の向上につながり、「小人」であってしまうことが本来からの品性の堕落につながってしまう。人としての
本来の品性が君子級に上等であったなら、権力なんか掌握しなくたってそれなりに有意義な生を送れるし、逆に、本来の
品性が小人止まりなのでは、どんなに莫大な権力を掌握してみたところで、相変わらず意義のない生のままであり続ける。
仏門での出家ほどもの、本格的な超俗領域に立ち入るのでもない限りは、このあたりの分別が十分に普遍的な
ものでもあり得る。釈迦もまた、宮女たちの裸踊りに嫌気が差して実家の王家を抜け出して乞食行に邁進したと
いうから、釈迦の実家だった王家からして「仁政家」であったとまでは考えにくいわけで、王家が王家だからといって
酒池肉林の遊興に耽ることが当たり前であるかのような風潮にこそ、釈迦も反発したのだろうことが窺えるのである。
だからこそ、そのような人間が死ぬに際しても、心から生きがいのある人生を送れたと納得もできるのである。
「生きていないこと」よりもさらに意義のない人生もまた確かにあり、そのような人生はすべからく、
君子としての人のあり方に反した人生を送っている。いわゆる「小人」の人生だけども、小人だからといって
必ずしも被支配階級に甘んじているとも限らず、自らの品性は小人であるままに権力だけは手に入れて、
いるよりもいないほうがマシなほどに有害無益な暴政を働く権力犯罪者になってしまうことまでもあるわけで、
その時にこそ「あるよりもないほうがマシな生」もまた極まる。ただ品性が小人止まりなだけでも、
えてして劣等感からなる苦しみなどにあえいだりするものだが、その苦しみを克服するために、「小人のままでの
権力の掌握」という間違った手段に及んだ挙句に、余計に生きていることの苦しみを増大化させてしまうのである。
権力を掌握するかしないかという以前に、まず人が「論語」にあるような意味での「君子」であろうとすることが本来
からの品性の向上につながり、「小人」であってしまうことが本来からの品性の堕落につながってしまう。人としての
本来の品性が君子級に上等であったなら、権力なんか掌握しなくたってそれなりに有意義な生を送れるし、逆に、本来の
品性が小人止まりなのでは、どんなに莫大な権力を掌握してみたところで、相変わらず意義のない生のままであり続ける。
仏門での出家ほどもの、本格的な超俗領域に立ち入るのでもない限りは、このあたりの分別が十分に普遍的な
ものでもあり得る。釈迦もまた、宮女たちの裸踊りに嫌気が差して実家の王家を抜け出して乞食行に邁進したと
いうから、釈迦の実家だった王家からして「仁政家」であったとまでは考えにくいわけで、王家が王家だからといって
酒池肉林の遊興に耽ることが当たり前であるかのような風潮にこそ、釈迦も反発したのだろうことが窺えるのである。
王業全般を卑俗なものとして諦めた釈迦の振る舞いと、王業も清浄であることに務めたなら相当な生きがいに繋がり得る
こととの矛盾は、大乗仏教において止揚され、仏菩薩縁覚声聞の四乗には及ばないものの、俗世での清浄な統治に励む
転輪聖王だとか、半ば超俗に足を踏み入れつつ帝王でもある帝釈天だとか数多の天王だとかいった尊格が提示されている。
「華厳経」でも、自らは世俗での帝業に励むものが、在家信者として仏門に帰依することが、より一層の帝国の繁栄に繋がる
などとも宣伝していて、仏門においても、清浄な君子としての業務にそれなりの価値があることが認められているのである。
世俗での君子としての業務が盛大であるということは、世の中での最大級の善行に励んでいるということでもある。
それを試みた上で未だ飽き足らないというのならまだしも、そもそもそんな試みに及んだことはおろか、
「君子としての王業が最大級の善行となる」という認知すら疎かなままでいる。そのような連中が中東以西の
世界のほぼ全てを占めているわけで、それほどにも知見や経験が未熟なままに「人生など苦しみの塊でしかない」
などとほざくのでは、耳を貸してやるにも足らないほどにも身の程知らずな戯れ言止まりでしかないといえる。
最大級の善行を為してなお飽き足らないというのならまだしも、そもそも善行なんかやったことも、その価値を計り知った
こともないような分際でいて、「生きることに価値が無い」などと決め付けるのは、井の中の蛙の大海への悪口でしかない。
まだ人生も世俗も諦観する資格もないうちから、狭隘な了見だけに基づいて人生や世俗を否定してかかるような連中は、
お坊さんや仙人が偉大であるのとは真逆に、常人以下の品性しか持たない賤人でしかないということが言えるのである。
こととの矛盾は、大乗仏教において止揚され、仏菩薩縁覚声聞の四乗には及ばないものの、俗世での清浄な統治に励む
転輪聖王だとか、半ば超俗に足を踏み入れつつ帝王でもある帝釈天だとか数多の天王だとかいった尊格が提示されている。
「華厳経」でも、自らは世俗での帝業に励むものが、在家信者として仏門に帰依することが、より一層の帝国の繁栄に繋がる
などとも宣伝していて、仏門においても、清浄な君子としての業務にそれなりの価値があることが認められているのである。
世俗での君子としての業務が盛大であるということは、世の中での最大級の善行に励んでいるということでもある。
それを試みた上で未だ飽き足らないというのならまだしも、そもそもそんな試みに及んだことはおろか、
「君子としての王業が最大級の善行となる」という認知すら疎かなままでいる。そのような連中が中東以西の
世界のほぼ全てを占めているわけで、それほどにも知見や経験が未熟なままに「人生など苦しみの塊でしかない」
などとほざくのでは、耳を貸してやるにも足らないほどにも身の程知らずな戯れ言止まりでしかないといえる。
最大級の善行を為してなお飽き足らないというのならまだしも、そもそも善行なんかやったことも、その価値を計り知った
こともないような分際でいて、「生きることに価値が無い」などと決め付けるのは、井の中の蛙の大海への悪口でしかない。
まだ人生も世俗も諦観する資格もないうちから、狭隘な了見だけに基づいて人生や世俗を否定してかかるような連中は、
お坊さんや仙人が偉大であるのとは真逆に、常人以下の品性しか持たない賤人でしかないということが言えるのである。
「小球大球を受け、下国の綴旒と為りて、天の休を何う。
競わず絿らず、剛ならず柔ならず、政を敷くに優優と、百禄も是に遒まる」
「大小諸々の勅命を受け、下位の国々の見本たる本流ともなって、天からの福を受ける。
専らに競おうとも貪ろうともせず、剛に過ぎず柔に過ぎず、悠然として政を敷き、天下の富も皆なここに集まるのである。
(仁徳によって天下を治めるためにこそ、不埒な競争意識などは捨て去る必要があるし、それでこそ天の休命にも適う)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・頌・商頌・長発より)
競わず絿らず、剛ならず柔ならず、政を敷くに優優と、百禄も是に遒まる」
「大小諸々の勅命を受け、下位の国々の見本たる本流ともなって、天からの福を受ける。
専らに競おうとも貪ろうともせず、剛に過ぎず柔に過ぎず、悠然として政を敷き、天下の富も皆なここに集まるのである。
(仁徳によって天下を治めるためにこそ、不埒な競争意識などは捨て去る必要があるし、それでこそ天の休命にも適う)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・頌・商頌・長発より)
自ら進んで冤罪の被害者となって、重罪人バラバの代わりに死刑になった
イエスの暴挙を、判事であったローマ総督のピラトもそのまま放任した。
「飛んで火にいる夏の虫」同然の所業に及んだイエスに対する不当処罰は、
まだ許せるところがあるし、また冤罪ほど事態のこじれる事件も他にないものだから、
「冤罪を誘発した」という罪だけによって、イエスへの磔刑を正当化してもいいぐらいのものである。
問題は、それによって死刑囚だった強盗殺人犯バラバを無罪放免に処したことで、これにより
ローマ帝国は法治機構の信頼性の破綻を招き、カトリックに全土を征服されることともなった。
キリスト教に「権力」を強奪されたローマ圏は一挙に閉塞状態と化し、
俗に言う「暗黒時代」を800年以上に渡り経験することとなった。ローマ帝国による支配を
カトリックが乗っ取ったからといって、そこで法治支配以上に優良な統治が敷かれたなどと
いうこともなく、むしろ誰しもが餓鬼畜生と化した状態をカルト教義によって無理やり治めて
いくという状態に移行してしまったわけだから、「暗黒」と化したのも当然のことだといえる。
キリスト教がローマ帝国を乗っ取れたのは、上記の通り、ローマ総督府が自分たちの法治支配を
イエスの暴挙の容認によって破綻させてしまったからである。ではなぜ、イエスの暴挙によって
法治支配が破綻せざるを得なくなったのかといえば、古代ローマには権力道徳がなかったからだ。
イエスの言行は、孔孟が体系化したような権力道徳にことごとく違背している。すなわち
「権力犯罪」の体系の流布だったわけだから、それをしてイエスを妖言罪などによって処罰し、
バラバのような他の死刑囚も代わりに釈放したりもせずに、粛々と刑を実行すればよかったのである。
しかし、当時のローマやイスラエルには体系化された純正な権力道徳などはなかったから、
総督ピラトも大衆に扇動されて分けも分からないままにイエスを処刑し、代わりにバラバを
放免するという、権力者にあるまじき大いなる過ちを犯した。実定法にまつわる知識はあっても、
仁義道徳にまつわる知識まではなかったから、イエスの妖言に十分に対応しきることもできなかった。
イエスの暴挙を、判事であったローマ総督のピラトもそのまま放任した。
「飛んで火にいる夏の虫」同然の所業に及んだイエスに対する不当処罰は、
まだ許せるところがあるし、また冤罪ほど事態のこじれる事件も他にないものだから、
「冤罪を誘発した」という罪だけによって、イエスへの磔刑を正当化してもいいぐらいのものである。
問題は、それによって死刑囚だった強盗殺人犯バラバを無罪放免に処したことで、これにより
ローマ帝国は法治機構の信頼性の破綻を招き、カトリックに全土を征服されることともなった。
キリスト教に「権力」を強奪されたローマ圏は一挙に閉塞状態と化し、
俗に言う「暗黒時代」を800年以上に渡り経験することとなった。ローマ帝国による支配を
カトリックが乗っ取ったからといって、そこで法治支配以上に優良な統治が敷かれたなどと
いうこともなく、むしろ誰しもが餓鬼畜生と化した状態をカルト教義によって無理やり治めて
いくという状態に移行してしまったわけだから、「暗黒」と化したのも当然のことだといえる。
キリスト教がローマ帝国を乗っ取れたのは、上記の通り、ローマ総督府が自分たちの法治支配を
イエスの暴挙の容認によって破綻させてしまったからである。ではなぜ、イエスの暴挙によって
法治支配が破綻せざるを得なくなったのかといえば、古代ローマには権力道徳がなかったからだ。
イエスの言行は、孔孟が体系化したような権力道徳にことごとく違背している。すなわち
「権力犯罪」の体系の流布だったわけだから、それをしてイエスを妖言罪などによって処罰し、
バラバのような他の死刑囚も代わりに釈放したりもせずに、粛々と刑を実行すればよかったのである。
しかし、当時のローマやイスラエルには体系化された純正な権力道徳などはなかったから、
総督ピラトも大衆に扇動されて分けも分からないままにイエスを処刑し、代わりにバラバを
放免するという、権力者にあるまじき大いなる過ちを犯した。実定法にまつわる知識はあっても、
仁義道徳にまつわる知識まではなかったから、イエスの妖言に十分に対応しきることもできなかった。
これこそは、権力者には法律だけでなく、仁徳の知識や実践もまたなければならない証拠にもなっている。
仁徳なんか全くなくて、法律しか知らないというのであれば、イエス級に不埒なカルト犯罪者を
裁ききることはできない。最悪、そのせいでローマ帝国がカトリックに乗っ取られて、800年以上もの
暗黒時代を到来させたようなことにだってなりかねないわけだから、そのような過ちを二度と
繰り返さないためにも、法律だけでなく、仁徳にまつわる素養までもが権力者たる者には必須だといえる。
「君子にして不仁なる者有らんか。未だ小人にして仁なる者あらざるなり」
「権力を持つ君子であっても不仁なものはいるが、権力を持たない小人でいながら仁者たり得た者はいない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・憲問第十四・七より)
孔子も士大夫としての役儀などに与りつつ仁徳のあり方を体系化していった。一生涯小人階級だったイエス
などが仁者だったはずはないし、総督ピラトらもまた、権力者ではあっても仁者ではなかったようである。
イエスのような人間の言行に権力が征服されることは、原理的に必ず不仁の蔓延につながる。
権力者が仁徳の養いによって不仁に対する防波堤を築き、不仁が権力を乗っ取るようなことがないように
心がけないのであれば、世の中が数百年規模の暗黒に見舞われるぐらいのことはいくらでもあり得る。
そういう時代にも貞正を貫く人間もまたいた所で、大局として人々が楽果に与れる頻度は地に墜ちる。
誰一人として環境からの幸福には与れなくなる、そのような情勢を二度と招かないようにしたいものである。
「権量を謹み、法度を審らかにし、廃官を修めれば、四方の政行われん」
「権力の扱いをよく慎んで、制度もよく整えて、廃官にまで配慮を行き届かせれば、四方の政治もうまく行く。
(権力を手に入れたからといって驕り高ぶって欲しいままでいたりすれば、政治もうまく行かないのである。
不仁な小人だったイエスの驕り高ぶりを引き継いだローマ・カトリックも、ろくな政治は為せなかった)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・堯曰第二十・二より)
仁徳なんか全くなくて、法律しか知らないというのであれば、イエス級に不埒なカルト犯罪者を
裁ききることはできない。最悪、そのせいでローマ帝国がカトリックに乗っ取られて、800年以上もの
暗黒時代を到来させたようなことにだってなりかねないわけだから、そのような過ちを二度と
繰り返さないためにも、法律だけでなく、仁徳にまつわる素養までもが権力者たる者には必須だといえる。
「君子にして不仁なる者有らんか。未だ小人にして仁なる者あらざるなり」
「権力を持つ君子であっても不仁なものはいるが、権力を持たない小人でいながら仁者たり得た者はいない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・憲問第十四・七より)
孔子も士大夫としての役儀などに与りつつ仁徳のあり方を体系化していった。一生涯小人階級だったイエス
などが仁者だったはずはないし、総督ピラトらもまた、権力者ではあっても仁者ではなかったようである。
イエスのような人間の言行に権力が征服されることは、原理的に必ず不仁の蔓延につながる。
権力者が仁徳の養いによって不仁に対する防波堤を築き、不仁が権力を乗っ取るようなことがないように
心がけないのであれば、世の中が数百年規模の暗黒に見舞われるぐらいのことはいくらでもあり得る。
そういう時代にも貞正を貫く人間もまたいた所で、大局として人々が楽果に与れる頻度は地に墜ちる。
誰一人として環境からの幸福には与れなくなる、そのような情勢を二度と招かないようにしたいものである。
「権量を謹み、法度を審らかにし、廃官を修めれば、四方の政行われん」
「権力の扱いをよく慎んで、制度もよく整えて、廃官にまで配慮を行き届かせれば、四方の政治もうまく行く。
(権力を手に入れたからといって驕り高ぶって欲しいままでいたりすれば、政治もうまく行かないのである。
不仁な小人だったイエスの驕り高ぶりを引き継いだローマ・カトリックも、ろくな政治は為せなかった)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・堯曰第二十・二より)
陰か陽かでいえば、生が陰で死が陽である。
もっと正確に言えば、生死の流転が陰で、不生不滅が陽である。
生きてるうちに多大なる罪業を重ねて、死後にも地獄餓鬼畜生の三悪趣を永遠にさ迷い続けなければ
ならないようなザマに陥ってしまっている者であれば、死後の世界が光明に満ちた極楽浄土で
あるなんてこともなく、むしろ死後にこそより暗い闇が待ち受けているということにすらなる。
死後に光明が待ち受けているというのならば、それは生死の流転を解脱した涅槃が近いということで、
場合によっては生きてるうちから不生不滅の境地(有余涅槃)に至れることもある。そういう者に
とってこそ確実に生こそは陰で、死の先こそは陽であり、生きてるうちにも、生の暗がりを
いかに光明で照らしていくかということが主要な課題となっていくのである。
「生きる」ということの業を、より深刻なものと化していくような行いは、大体が悪業に繋がる。
悪業だから生死の流転を多重化させ、本来は死後にあるはずの光明をより遠ざけることともなる。
だから、生死の流転を解脱した涅槃に至るために、仏門は出家による抜業因種をも企図する。本格の
仏門ならば妻子を持つことすらをも絶って、この世に出家者が残すカルマを最低限に止め置こうとする。
上述の、二つの選択肢とはまた別の選択肢がもう一つあって、世俗での活動にはやはり邁進して
いくものの、その活動を世のため人のため、国家鎮護や天下平定のためだけに限って、積極的に
自他の悪業を食い止めていこうとするものである。これこそは儒家の選択肢でもあるし、原始仏教と
バラモン教の折衷とでもいうべき大乗仏教などが根幹の理念として据えているものでもある。
原始仏教のように、自らがこの世に残すカルマをできる限り最小限に止めおくことと、儒家や大乗仏教の
ように、天下国家の大局からの悪業の矮小化に務めていくことと、いずれもが「自らが生きる」ということ
ばかりに専らであるのでは務まらない代物となっている。孔子や孟子ですら「天命のためには命をも捨てる」
というようなことをいい、周の放伐革命に抗議して首陽山に餓死した伯夷・叔世兄弟を聖人と見なしてもいる。
もっと正確に言えば、生死の流転が陰で、不生不滅が陽である。
生きてるうちに多大なる罪業を重ねて、死後にも地獄餓鬼畜生の三悪趣を永遠にさ迷い続けなければ
ならないようなザマに陥ってしまっている者であれば、死後の世界が光明に満ちた極楽浄土で
あるなんてこともなく、むしろ死後にこそより暗い闇が待ち受けているということにすらなる。
死後に光明が待ち受けているというのならば、それは生死の流転を解脱した涅槃が近いということで、
場合によっては生きてるうちから不生不滅の境地(有余涅槃)に至れることもある。そういう者に
とってこそ確実に生こそは陰で、死の先こそは陽であり、生きてるうちにも、生の暗がりを
いかに光明で照らしていくかということが主要な課題となっていくのである。
「生きる」ということの業を、より深刻なものと化していくような行いは、大体が悪業に繋がる。
悪業だから生死の流転を多重化させ、本来は死後にあるはずの光明をより遠ざけることともなる。
だから、生死の流転を解脱した涅槃に至るために、仏門は出家による抜業因種をも企図する。本格の
仏門ならば妻子を持つことすらをも絶って、この世に出家者が残すカルマを最低限に止め置こうとする。
上述の、二つの選択肢とはまた別の選択肢がもう一つあって、世俗での活動にはやはり邁進して
いくものの、その活動を世のため人のため、国家鎮護や天下平定のためだけに限って、積極的に
自他の悪業を食い止めていこうとするものである。これこそは儒家の選択肢でもあるし、原始仏教と
バラモン教の折衷とでもいうべき大乗仏教などが根幹の理念として据えているものでもある。
原始仏教のように、自らがこの世に残すカルマをできる限り最小限に止めおくことと、儒家や大乗仏教の
ように、天下国家の大局からの悪業の矮小化に務めていくことと、いずれもが「自らが生きる」ということ
ばかりに専らであるのでは務まらない代物となっている。孔子や孟子ですら「天命のためには命をも捨てる」
というようなことをいい、周の放伐革命に抗議して首陽山に餓死した伯夷・叔世兄弟を聖人と見なしてもいる。
ただ自らが生きることばかりに専らで、天命をも無視しての遊興ばかりに耽るというのであれば、仏門での
出家修行などが覚束ないのはもちろんのこと、儒学を実践する仁政家としてですら大成できたりすることはない。
それでいて、儒学の経典である四書五経などに書かれている教条は、人として嗜むべき最低限の
道徳的なわきまえばかりとなってもいる。してみれば、人間が生きることばかりに専らであるということは、
即座に最低限の人としてのわきまえをも失った、餓鬼畜生の振る舞いに直結してしまうということである。
人は本来、生きることばかりに専らでいたりしてはいけない生き物なのであり、もしも
そのようでいたならば、動物以上の知能や技術力もあいまって、地獄に堕する悪業をも動物以上に
すら深めてしまうことになる。文明社会をも築き上げられる知能や技術の持ち主であればこそ、
人間は生きることばかりに専らであることが「過ぎたるはなお及ばざるが如し」にも直結して
しまうものだから、最低でも儒説程度の生存欲に対する自制は嗜んでおくべきなのだといえる。
人間であればこそ、自分が生きることばかりに専らであることが、暗くて陰鬱な死へとも直結してしまう。
だからこそ、生きることに対して消極的な教条がままある、儒家や仏門に従うぐらいでちょうどいいのである。
「君子に終わると曰い、小人に死と曰う」
「君子が『身を終える』ということを、小人は『死ぬ』という。
(君子は身を終えても名を残すから『死ぬ』とは言わない。『天子がお隠れになる』なども
これに準拠した語法だといえる。そもそも『死』などを強調している時点で小人なのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・檀弓上第三より)
出家修行などが覚束ないのはもちろんのこと、儒学を実践する仁政家としてですら大成できたりすることはない。
それでいて、儒学の経典である四書五経などに書かれている教条は、人として嗜むべき最低限の
道徳的なわきまえばかりとなってもいる。してみれば、人間が生きることばかりに専らであるということは、
即座に最低限の人としてのわきまえをも失った、餓鬼畜生の振る舞いに直結してしまうということである。
人は本来、生きることばかりに専らでいたりしてはいけない生き物なのであり、もしも
そのようでいたならば、動物以上の知能や技術力もあいまって、地獄に堕する悪業をも動物以上に
すら深めてしまうことになる。文明社会をも築き上げられる知能や技術の持ち主であればこそ、
人間は生きることばかりに専らであることが「過ぎたるはなお及ばざるが如し」にも直結して
しまうものだから、最低でも儒説程度の生存欲に対する自制は嗜んでおくべきなのだといえる。
人間であればこそ、自分が生きることばかりに専らであることが、暗くて陰鬱な死へとも直結してしまう。
だからこそ、生きることに対して消極的な教条がままある、儒家や仏門に従うぐらいでちょうどいいのである。
「君子に終わると曰い、小人に死と曰う」
「君子が『身を終える』ということを、小人は『死ぬ』という。
(君子は身を終えても名を残すから『死ぬ』とは言わない。『天子がお隠れになる』なども
これに準拠した語法だといえる。そもそも『死』などを強調している時点で小人なのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・檀弓上第三より)
人間という生き物にとって、「自分が生きる」ということばかりに専らではないように
務めるぐらいが実質上ちょうどいいのと同じように、これまた人間にとっては、自己愛だとか
隣人愛だとかいったような、「安易な愛」を偏重しないようにするぐらいがちょうどいい。
仁愛や親愛が、それなりの知見や義務感と共にこそ達成し得る「高度な愛」であるのに対し、
自己愛や隣人愛は何の知識も義務感もなく、好き勝手な中にまんまと陥れる安易な愛でしかない。
たとえば、「遠くの親戚よりも近くの他人」で、近くにいるから便利な隣人ばかりとの
関係を専らにして、遠方の親戚家族などは蔑ろにしてしまうほうが実際、簡単なことである。
自分や隣人ばかりの利益に専らで、天下の公益を我田引水によって損ねてしまうことのほうが
我が欲望のままに行えることで、何らの知見の研鑽の必要もないぶんだけ、より簡単なことだといえる。
生存意欲も自己愛も隣人愛も、完全に捨て去られて然るべきものなのかといえば、そうとも限らない。
この世の中で旺盛に活動していく人間に「生存欲をなくせ」というのは矛盾しているし、墨子のように
あらゆる偏愛を捨て去っての博愛一辺倒でいた所で、八方美人すぎて何の成果も挙げられはしなかったりもする。
生存欲も自己愛も隣人愛もあったとした上で、そんなものを至上のものとして掲げたりはしない。 ┐
天命のためには身命をも呈する心構えや、仁愛や親愛こそを至上のものとして、それと比べれば ├ ①
生存欲だの自己愛だの隣人愛だのが、一貫して劣後される他ない代物であることをわきまえる。 ┘
自分が幾度となく言い重ねてきた諸々の分別のうちでも、これこそは最も推奨するに値する分別だといえる。
それでいて、この分別を恒常的に嗜める人間というのも、そんなに多くないだろうことまでもが予想される。
務めるぐらいが実質上ちょうどいいのと同じように、これまた人間にとっては、自己愛だとか
隣人愛だとかいったような、「安易な愛」を偏重しないようにするぐらいがちょうどいい。
仁愛や親愛が、それなりの知見や義務感と共にこそ達成し得る「高度な愛」であるのに対し、
自己愛や隣人愛は何の知識も義務感もなく、好き勝手な中にまんまと陥れる安易な愛でしかない。
たとえば、「遠くの親戚よりも近くの他人」で、近くにいるから便利な隣人ばかりとの
関係を専らにして、遠方の親戚家族などは蔑ろにしてしまうほうが実際、簡単なことである。
自分や隣人ばかりの利益に専らで、天下の公益を我田引水によって損ねてしまうことのほうが
我が欲望のままに行えることで、何らの知見の研鑽の必要もないぶんだけ、より簡単なことだといえる。
生存意欲も自己愛も隣人愛も、完全に捨て去られて然るべきものなのかといえば、そうとも限らない。
この世の中で旺盛に活動していく人間に「生存欲をなくせ」というのは矛盾しているし、墨子のように
あらゆる偏愛を捨て去っての博愛一辺倒でいた所で、八方美人すぎて何の成果も挙げられはしなかったりもする。
生存欲も自己愛も隣人愛もあったとした上で、そんなものを至上のものとして掲げたりはしない。 ┐
天命のためには身命をも呈する心構えや、仁愛や親愛こそを至上のものとして、それと比べれば ├ ①
生存欲だの自己愛だの隣人愛だのが、一貫して劣後される他ない代物であることをわきまえる。 ┘
自分が幾度となく言い重ねてきた諸々の分別のうちでも、これこそは最も推奨するに値する分別だといえる。
それでいて、この分別を恒常的に嗜める人間というのも、そんなに多くないだろうことまでもが予想される。
世の半分を構成する女は、ほぼ全てがこんなわきまえ①を保つことなど不可能である。
男であっても頑是ない子供や、精神が未熟なままに年だけ重ねた小人男などにも不可能であろう。
結果、上記①のようなわきまえを保てる人間は、どんなに多く見積もっても全世界の半分以下に
止まることになり、多数決であれば上記①のようなわきまえこそが劣後されることになってしまう。
多数決によって、①のような上等なわきまえが天下に通用するということは、原理的にありえない。
男か女でいえば男が上で女が下、君子か小人かでいえば君子が上で小人が下といった適正な差別を実施した上で、
上位のものが下位のものを一方的に教導していくという体制が整えられることで初めて、天下に①のような
わきまえが通用して、以て人類が生存欲や自己愛や隣人愛の過剰からなる滅亡の危機を免れられることともなる。
多数決ですらあれば必ず正しいなんてことも決してない。「船頭多くして船山に登る」ということがあり、
世界の多数派である女子供と小人の意見を優先させた挙句に、人類が滅亡の危機に見舞われることにすらなり得る。
人間が必ずしも愚かだなんてことはないが、多数派については、愚かでいやすいようにもできている。
安易なほう、安易なほうへと堕落し続ける多数派の愚か者を、その命ごと斬り捨てるとまではいかずとも、
全くその言い分を聞いてやらずに、こちらの命令だけを聞き従わせるといったことも、時に必要になるのである。
「仁義礼智は、外由り我れを鑠るには非ざるなり。我固より之れを有するなり。思う弗きのみ。故に求むれば
則ち之れを得、舍つれば則ち之れを失うとも曰えり。相倍蓰而て算無き者あるは、其の才を尽くす能わざればなり」
「仁義礼智は、外的に自らを飾り立てるための道具などではない。誰しもが本より具えてはいるものの、それを
自覚することがないだけのことである。だから『求めれば得られるが、捨てるのなら失うばかり』ともいえる。
得る者と失う者とで極端に隔絶してしまうことがあるのも、自らの才分を尽くしたか否かによるのである。
(仁義礼智の四端を自得するために才分を尽くすことこそは、君子にとっての至上命題だといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・告子章句上・六より)
男であっても頑是ない子供や、精神が未熟なままに年だけ重ねた小人男などにも不可能であろう。
結果、上記①のようなわきまえを保てる人間は、どんなに多く見積もっても全世界の半分以下に
止まることになり、多数決であれば上記①のようなわきまえこそが劣後されることになってしまう。
多数決によって、①のような上等なわきまえが天下に通用するということは、原理的にありえない。
男か女でいえば男が上で女が下、君子か小人かでいえば君子が上で小人が下といった適正な差別を実施した上で、
上位のものが下位のものを一方的に教導していくという体制が整えられることで初めて、天下に①のような
わきまえが通用して、以て人類が生存欲や自己愛や隣人愛の過剰からなる滅亡の危機を免れられることともなる。
多数決ですらあれば必ず正しいなんてことも決してない。「船頭多くして船山に登る」ということがあり、
世界の多数派である女子供と小人の意見を優先させた挙句に、人類が滅亡の危機に見舞われることにすらなり得る。
人間が必ずしも愚かだなんてことはないが、多数派については、愚かでいやすいようにもできている。
安易なほう、安易なほうへと堕落し続ける多数派の愚か者を、その命ごと斬り捨てるとまではいかずとも、
全くその言い分を聞いてやらずに、こちらの命令だけを聞き従わせるといったことも、時に必要になるのである。
「仁義礼智は、外由り我れを鑠るには非ざるなり。我固より之れを有するなり。思う弗きのみ。故に求むれば
則ち之れを得、舍つれば則ち之れを失うとも曰えり。相倍蓰而て算無き者あるは、其の才を尽くす能わざればなり」
「仁義礼智は、外的に自らを飾り立てるための道具などではない。誰しもが本より具えてはいるものの、それを
自覚することがないだけのことである。だから『求めれば得られるが、捨てるのなら失うばかり』ともいえる。
得る者と失う者とで極端に隔絶してしまうことがあるのも、自らの才分を尽くしたか否かによるのである。
(仁義礼智の四端を自得するために才分を尽くすことこそは、君子にとっての至上命題だといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・告子章句上・六より)
己れに備わる仁義礼智の四端を自覚し、その恒常的な実践に務めて行く、
その過程において善を勧める一方、悪を赦すことなく懲らしたりもする、
それでこそ浩然の気が保たれて、すがすがしい気持ちのままでもいられるからそうするし、
またそうすることで、罪刑の因果関係が保たれた社会的安寧までもが実現されるから。
世俗的に実があるのは、後者の社会的健全性の実現のほうであるけれども、より普遍的
であるのは前者の、「そうすることがすがすがしいから」という理由のほうだといえる。
そうするほうがすがすがしいから、来世でもそのまた来世でも、
形而上の形而上の形而上でもそうであることを志し続けることが確か。
今生限りにおいて健全性が確保されるから、勧善懲悪に臨むというだけならば、
来世や形而上でもそうするかどうかまでは知れないが、勧善懲悪が心の底から普遍的に
すがすがしいのだから、来世だろうが形而上だろうが形而下だろうがそう志し続けることが確か。
大罪をこともなげに許容するようなところでこそ、心の底からのつまらなさにも苛まれる。
心の底からのつまらなさだから、来世でも形而上でも形而下でも、永久につまらない。
実質的な因果律の破綻こそは、三千大千世界の去来今に渡ってつまらないもののままであり続けるし、
逆に因果律の保全に務めることが、絶対普遍のものとしてすがすがしいことのままであり続ける。
結論としては、悪いことをせずさせず、善いことをしてさせるに越したことはないという
ごくありきたりな結論にいたるわけだから、そのありきたりな範囲の論議にしか及ばない儒説だけに
従ったところで効能はさして変わらないわけだが、あえて仏説などに根ざすことで、遠大な形而上
なぞを想定してみたところで、人としてすべきことに大した相違などはないことが分かるのである。
その過程において善を勧める一方、悪を赦すことなく懲らしたりもする、
それでこそ浩然の気が保たれて、すがすがしい気持ちのままでもいられるからそうするし、
またそうすることで、罪刑の因果関係が保たれた社会的安寧までもが実現されるから。
世俗的に実があるのは、後者の社会的健全性の実現のほうであるけれども、より普遍的
であるのは前者の、「そうすることがすがすがしいから」という理由のほうだといえる。
そうするほうがすがすがしいから、来世でもそのまた来世でも、
形而上の形而上の形而上でもそうであることを志し続けることが確か。
今生限りにおいて健全性が確保されるから、勧善懲悪に臨むというだけならば、
来世や形而上でもそうするかどうかまでは知れないが、勧善懲悪が心の底から普遍的に
すがすがしいのだから、来世だろうが形而上だろうが形而下だろうがそう志し続けることが確か。
大罪をこともなげに許容するようなところでこそ、心の底からのつまらなさにも苛まれる。
心の底からのつまらなさだから、来世でも形而上でも形而下でも、永久につまらない。
実質的な因果律の破綻こそは、三千大千世界の去来今に渡ってつまらないもののままであり続けるし、
逆に因果律の保全に務めることが、絶対普遍のものとしてすがすがしいことのままであり続ける。
結論としては、悪いことをせずさせず、善いことをしてさせるに越したことはないという
ごくありきたりな結論にいたるわけだから、そのありきたりな範囲の論議にしか及ばない儒説だけに
従ったところで効能はさして変わらないわけだが、あえて仏説などに根ざすことで、遠大な形而上
なぞを想定してみたところで、人としてすべきことに大した相違などはないことが分かるのである。
 例えば、木片を刀剣状に削り上げた木刀は、その鋭利さなどで真剣に匹敵するはずはないが、それを用いて
例えば、木片を刀剣状に削り上げた木刀は、その鋭利さなどで真剣に匹敵するはずはないが、それを用いて 剣術の練習をすることができるし、真剣では無理があるほどにも大胆な稽古すら繰り返すことができる。
もちろん、木刀での練習に飽き足らなければ、真剣や模造刀での練習にも及べばいいわけだが、結局、
木刀を用いようが真剣を用いようが、自らが剣術の鍛錬によって「剣の理合」を身に付けようとすること
には変わりない。それと同じで、儒学ぐらいに表面的な勉学に務めることと、仏教ほどにも深遠な修練に
務めることでも、いずれもがこの世界、この宇宙やその形而上の形而上の形而上に至るまでの普遍的な
理合こそを探求していることには変わりないわけで、ただ儒学のほうが木刀での鍛錬ほどにも大雑把である
のに対し、仏教のほうは真剣での鍛錬ほどにも精密であったりするという違いがあるばかりのことである。
儒学と仏教の相違は上記のようなものだけども、そもそも道理なり真理なりの「普遍的な理合」を
把捉しようとすらせず、かえって普遍的な理合に違う邪曲こそを追い求めようとする学問なり宗教なりも
あるわけで、それらの教学にはまったく上記のような共通法則などはない。そういう邪教邪学も
この世には残念ながら実在しているわけだから、儒学や仏教のような、普遍的な理合を追い求めている
教学もまた全体的には特殊なものであるといえ、特筆して庇護や推奨の対象にすべきものだといえる。
昔の日本などでは、儒学や仏教こそが特に主要な文化的地位を占めていたから、特定してそれらばかりを
庇護するというようなことからして、あまりなかった。寛政異学の禁などにおいても、洋学と共に
異端派の儒学などが排撃の対象とされていて、儒学の庇護というよりは儒学の洗練という意味合いの
ほうが強かった。儒学全般、仏教全般こそを、普遍的な理合を捉えた正学正教として特筆して見直し、
邪曲の追求に専らな雑学雑教とは別格のものとして扱うなどということは、実際問題、日本人や中国人
ですら未だ十分に実施したこともないのだから、全く新しい試みとしての心構えが必要だといえる。
儒学や仏教こそが、そこまで特別に正しいものだったということが、今にこそ明らかとなったのだから。
「否を休む。大人は吉なり。其れ亡びなん、其れ亡びなんとて、苞桑に繋ぐ」
「否塞が潰える、大人にとっては格好のとき。それでも『滅びるかもしれない、亡びるかもしれない』
と内心憂慮を保ち、桑の木の根元にものを繋ぎとめておくような、堅固な心持ちのままでいるとよい」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・否・九五より)
「否塞が潰える、大人にとっては格好のとき。それでも『滅びるかもしれない、亡びるかもしれない』
と内心憂慮を保ち、桑の木の根元にものを繋ぎとめておくような、堅固な心持ちのままでいるとよい」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・否・九五より)
いくら形而上に超越的な観念を思い描いてみたところで、
それが形而下の事物と全く関係がないのでは、不実の至りとしかならない。
陰陽学における太極の法則や、大乗仏教における六道の様態などは、
観念的であったところで、この形而下の世界の法則にも適格に合致している。
形而下の現象に対する鋭い洞察があった上で、その知見を概括的に理念化しているわけで、
理念としては形而上的であっても、形而下との厳密な連絡を保ったままでいる。
そのような、形而下の現象との緊密な連絡を保った理念としての神だとか仏だとかを敬い、
鬼なり悪霊なりを厭うことが現実上の効験にも繋がる一方で、形而下との連絡を全く欠いた
単なる夢想上の神なり霊なりを崇めたり、それに対立する異質の神仏などを貶めたりしたなら、
何の効験も得られないばかりか、その徒労や悪業に見合った制裁すらをも被ることになる。
形而上に思い描く超越的な夢想も、具体的である以上は形而下の事物を流用している。形而下の
事物が刹那的なものであるというのなら、そのような形而上の夢想もまた連動して刹那的である。
そんな夢想よりは、形而下との連絡を保っていても高度に数理的な易の陰陽法則などのほうが
より普遍的であるし、概念的な具体性を徹底して排する仏法などもさらに普遍的ですらある。
陰陽五行や六道輪廻のような、形而下の現象を概括した普遍法則を参考にしたなら、形而下に
おいて自らが為すことや、造り上げるものなどにもそれなりの普遍性を付与することができる。
そのような事物を継承して維持することに務めていけば、それがよき伝統ともなっていくのである。
してみれば、形而上に全く超越的な概念を夢想してみて、その普遍性を愛でようとしたりする
ことからして、さして魅力的なことだとも言えない。そのような夢想も所詮は形而下の事物の
模倣でしかない上に、完全に形而下と隔絶しているものだから、形而下においてよき伝統を
もたらす普遍的な指針となったりもしないわけで、より普遍的である上に、形而下における
開物成務をも健全化させられる陰陽法則や仏法と比べて、何も秀でている所がないと言える。
それが形而下の事物と全く関係がないのでは、不実の至りとしかならない。
陰陽学における太極の法則や、大乗仏教における六道の様態などは、
観念的であったところで、この形而下の世界の法則にも適格に合致している。
形而下の現象に対する鋭い洞察があった上で、その知見を概括的に理念化しているわけで、
理念としては形而上的であっても、形而下との厳密な連絡を保ったままでいる。
そのような、形而下の現象との緊密な連絡を保った理念としての神だとか仏だとかを敬い、
鬼なり悪霊なりを厭うことが現実上の効験にも繋がる一方で、形而下との連絡を全く欠いた
単なる夢想上の神なり霊なりを崇めたり、それに対立する異質の神仏などを貶めたりしたなら、
何の効験も得られないばかりか、その徒労や悪業に見合った制裁すらをも被ることになる。
形而上に思い描く超越的な夢想も、具体的である以上は形而下の事物を流用している。形而下の
事物が刹那的なものであるというのなら、そのような形而上の夢想もまた連動して刹那的である。
そんな夢想よりは、形而下との連絡を保っていても高度に数理的な易の陰陽法則などのほうが
より普遍的であるし、概念的な具体性を徹底して排する仏法などもさらに普遍的ですらある。
陰陽五行や六道輪廻のような、形而下の現象を概括した普遍法則を参考にしたなら、形而下に
おいて自らが為すことや、造り上げるものなどにもそれなりの普遍性を付与することができる。
そのような事物を継承して維持することに務めていけば、それがよき伝統ともなっていくのである。
してみれば、形而上に全く超越的な概念を夢想してみて、その普遍性を愛でようとしたりする
ことからして、さして魅力的なことだとも言えない。そのような夢想も所詮は形而下の事物の
模倣でしかない上に、完全に形而下と隔絶しているものだから、形而下においてよき伝統を
もたらす普遍的な指針となったりもしないわけで、より普遍的である上に、形而下における
開物成務をも健全化させられる陰陽法則や仏法と比べて、何も秀でている所がないと言える。
目に見えるこの世界と全く隔絶した何かを追い求めるよりは、この世界との連絡も保ちつつ
普遍的である何かを追い求めることのほうが魅力的である。必要という以上にも、魅力的であり、
そのうえ害がなくて益がある。近代科学などにもある程度この方向性が備わっているが、理論面では
まだまだ未熟で、概念遊びの介在する余地が多分に残存しているために、権力犯罪や道義なき戦争
などのために悪用されることが多い。陰陽法則や仏法と比べて好き勝手に論じられる自由度が高い、
にもかかわらずではなくだからこそ、探求者や利用者の不埒さをも容認してしまっているのである。
形而下との連絡を全く欠いた観念を玩ぶ信教や思想哲学が排されて、科学もまたそのような
概念の玩びを差し挟む余地がなくなるほどに見識が引き締められたならば、そこには必ず
陰陽法則や仏法や、それに近似するものだけが残されるはずである。それで人類文明が
終わるのではなく、むしろそこからこそ全世界規模での人類文明が初めて始まるのである。
概念遊びに道草を食い過ぎて、文明を進歩させる以上にも退歩させてしまっていたような
派閥が退場させられて、世界規模で文明を着実に前進させていけるようになるのである。
産業革命によって科学が地球人類にもたらした影響も、未だプラスマイナスゼロ以下のままでしかない。
だからこそ極重の苦悩に見舞われた人々が気休めの乱交に及んで、世界人口を爆発させてもいる。
全世界全人類が、不幸ばかりをもたらす不埒な超越的概念の玩びから卒業することでやっと
その傾向が収束する見込みも立つのだから、もはやそうするしかないのでもある。
普遍的である何かを追い求めることのほうが魅力的である。必要という以上にも、魅力的であり、
そのうえ害がなくて益がある。近代科学などにもある程度この方向性が備わっているが、理論面では
まだまだ未熟で、概念遊びの介在する余地が多分に残存しているために、権力犯罪や道義なき戦争
などのために悪用されることが多い。陰陽法則や仏法と比べて好き勝手に論じられる自由度が高い、
にもかかわらずではなくだからこそ、探求者や利用者の不埒さをも容認してしまっているのである。
形而下との連絡を全く欠いた観念を玩ぶ信教や思想哲学が排されて、科学もまたそのような
概念の玩びを差し挟む余地がなくなるほどに見識が引き締められたならば、そこには必ず
陰陽法則や仏法や、それに近似するものだけが残されるはずである。それで人類文明が
終わるのではなく、むしろそこからこそ全世界規模での人類文明が初めて始まるのである。
概念遊びに道草を食い過ぎて、文明を進歩させる以上にも退歩させてしまっていたような
派閥が退場させられて、世界規模で文明を着実に前進させていけるようになるのである。
産業革命によって科学が地球人類にもたらした影響も、未だプラスマイナスゼロ以下のままでしかない。
だからこそ極重の苦悩に見舞われた人々が気休めの乱交に及んで、世界人口を爆発させてもいる。
全世界全人類が、不幸ばかりをもたらす不埒な超越的概念の玩びから卒業することでやっと
その傾向が収束する見込みも立つのだから、もはやそうするしかないのでもある。
「上世、嘗て其の親を葬らざる者あり。其親死すれば則ち挙げて之れを壑に委てたり。他日之れを過ぐるに、狐狸之れを食らい、
蝿蚋之れを姑嘬う。其の顙に汗有りて、睨して視ざる。夫の汗なるは、人の為めに汗なるに非ず、中心より面目に達せるなり。
蓋し帰反して虆梩もて之れを掩えり。之れを掩うは是れを誠にすなり。則ち孝子仁人の其の親を掩えるは、亦た必ず道有らん」
「大昔、自らの親を埋葬しない者がいた。親が死ねばその遺体を人気のない谷底に捨ててそのままにしておいた。他日、
その付近を通り過ぎると、狐や狸がその遺体の肉を食らい、蝿や蚋が食んだ肉を咀嚼しているのを見た。思わず額に
冷や汗が滴り、斜めに視たきりで直視することもできなかった。冷や汗をかいたのは、別に人にいい顔を見せようと
したからではなく、本当に心の底から親に面目がないと思ったからである。その後、すぐに帰宅して鋤ともっこを
持ち出してきて、親の遺体を土で蔽った。土で蔽ったのも誠を立てようと思ったからである。今の孝子や仁人が
親の遺体を埋葬することにも、そういった道義性があるからなのである。(親の遺体が腐乱して禽獣に貪り食われるのが
忍びないからこれを埋葬する。永遠足りえない親の命の儚さにこそ蔽いをする。またそれが孝子仁人のあり方ともなるのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・滕文公章句上・五より)
蝿蚋之れを姑嘬う。其の顙に汗有りて、睨して視ざる。夫の汗なるは、人の為めに汗なるに非ず、中心より面目に達せるなり。
蓋し帰反して虆梩もて之れを掩えり。之れを掩うは是れを誠にすなり。則ち孝子仁人の其の親を掩えるは、亦た必ず道有らん」
「大昔、自らの親を埋葬しない者がいた。親が死ねばその遺体を人気のない谷底に捨ててそのままにしておいた。他日、
その付近を通り過ぎると、狐や狸がその遺体の肉を食らい、蝿や蚋が食んだ肉を咀嚼しているのを見た。思わず額に
冷や汗が滴り、斜めに視たきりで直視することもできなかった。冷や汗をかいたのは、別に人にいい顔を見せようと
したからではなく、本当に心の底から親に面目がないと思ったからである。その後、すぐに帰宅して鋤ともっこを
持ち出してきて、親の遺体を土で蔽った。土で蔽ったのも誠を立てようと思ったからである。今の孝子や仁人が
親の遺体を埋葬することにも、そういった道義性があるからなのである。(親の遺体が腐乱して禽獣に貪り食われるのが
忍びないからこれを埋葬する。永遠足りえない親の命の儚さにこそ蔽いをする。またそれが孝子仁人のあり方ともなるのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・滕文公章句上・五より)
 未だ惑いの中にある者であろうとも、それなりに信念を以って行動したり、人生を送ったりすることはある。
未だ惑いの中にある者であろうとも、それなりに信念を以って行動したり、人生を送ったりすることはある。 「最後の審判の時に全ての信者が復活する」という、永久不変の絶対真理に即した完全誤謬を
信じながら死ぬ場合にも、それなりに毅然としていられたりする。だから、そのような完全誤謬を
信じながら死んでいく欧米のキリスト教徒たちも、まともな信教を剥奪された戦後の大多数の日本人などと
比べれば毅然としていて、醜悪な寝たきり状態での終末期医療などもあえて拒絶して死んでいったりする。
「私は自分の信じているものが完全に間違っていてもそれを信じます」という、何らの価値もない完全誤謬信仰と
いえども、それによって心持ちを頑なならしめて、命を賭してことに臨むことだって絶対にできなくもないのである。
ただ、そのような劣悪な信念に即して心持ちを凝り固める人間は、根本的な部分で己れの才覚を尽くしていない。
正しいもの、優良なものを信じていくに値するだけの格物致知を尽くすこともなく、まず何かを信じていようとした。
何でもいいからとりあえず信じようとした怠惰の結果、完全に間違っているものであろうとも信じてしまう、
人として最も劣悪な領域での、狂信への凝り固まりに落ち着いてしまったのである。
孟子の提唱した仁義礼智の四端と、荀子が覇道政治を是認する過程で定立した信とを合わせて五常(仁義礼智信)という。
このうちの信と知(智)は時に、むしろ持たないでいるほうがマシなほどに劣悪な邪信や小知でもあり得る。
それを仁義という理念、礼儀という実践によって統御し、正信や良知に止め置くことが儒学の実践ともなる。
邪信や小知も存在してしまっている状態でこそ、仁義や礼儀によって知や信を統制しなければならなくなるわけだから、
「大道廃れて仁義あり(老子)」ということもまた確かである。大道が十分に通用している世の中であれば、
人々が邪信に凝り固まったり、小知を駆使したりして破滅を呼び込んだりすることもないわけだから、
わざわざ仁義や礼儀で信知を制御しようなどという作為を差し挟んだりする必要もないのである。
邪信や小知に凝り固まって、あるよりもないほうがマシであるような害悪ばかりを募らせている連中がいる。
だからそのぶんだけ五常の理念に即した統制を執り行う。そのあたりのけじめは十分に付けておくべきで、
さもなくば「仁義や礼儀などで世の中の浄化に務めようとしているような奴らがいるから、俺らは邪信や小知を
駆使した悪行に走っていたって大丈夫だろう」などという「甘え」を一部の人間が抱くことにすらなりかねない。
人類史上最悪の邪教であるキリスト教などよりは、儒学のほうが数百年以上早くの内から形成されている。
しかし、その儒学も夏桀殷紂や春秋諸侯のような暴政家が登場して後、乱世と化してしまった古代の中国を修善
していく目的で周公や孔孟らによって体系化されて来ている。小知や邪信に基づく世の乱脈があって後に、あからさまな
聖人君子による仁徳の体系化もまた試みられ始めたわけで、その順序はこれからも大切にしていくべきである。
邪教の信者や暴政家こそが、自業自得で体系的な仁徳による浄化を被る。そうでもしなければ世の中が
立ち行かなくなるほどもの乱脈を自分たちが呼び込んでしまったからこそ、作為的な勧善懲悪にも甘んじなければならない。
「大道廃れて仁義あり」という言葉は、大道を廃らせてしまった悪人たちにとってこその戒めの言葉なのである。
「君子は其の道によって楽を得、小人は其の欲によって楽を得。
道を以って欲を制すれば、則ち楽しみて乱れず。欲を以って道を忘るれば、則ち惑いて楽しまず」
「君子は道義によって楽しみを得ようとし、小人は愛欲によって楽しみを得ようとする。
道義によって愛欲を制すれば、よく楽しめながら乱れることもない。一方で、
愛欲によって道義を忘れれば、惑いに苛まれてろくに楽しむこともできない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・楽記第十九より)
だからそのぶんだけ五常の理念に即した統制を執り行う。そのあたりのけじめは十分に付けておくべきで、
さもなくば「仁義や礼儀などで世の中の浄化に務めようとしているような奴らがいるから、俺らは邪信や小知を
駆使した悪行に走っていたって大丈夫だろう」などという「甘え」を一部の人間が抱くことにすらなりかねない。
人類史上最悪の邪教であるキリスト教などよりは、儒学のほうが数百年以上早くの内から形成されている。
しかし、その儒学も夏桀殷紂や春秋諸侯のような暴政家が登場して後、乱世と化してしまった古代の中国を修善
していく目的で周公や孔孟らによって体系化されて来ている。小知や邪信に基づく世の乱脈があって後に、あからさまな
聖人君子による仁徳の体系化もまた試みられ始めたわけで、その順序はこれからも大切にしていくべきである。
邪教の信者や暴政家こそが、自業自得で体系的な仁徳による浄化を被る。そうでもしなければ世の中が
立ち行かなくなるほどもの乱脈を自分たちが呼び込んでしまったからこそ、作為的な勧善懲悪にも甘んじなければならない。
「大道廃れて仁義あり」という言葉は、大道を廃らせてしまった悪人たちにとってこその戒めの言葉なのである。
「君子は其の道によって楽を得、小人は其の欲によって楽を得。
道を以って欲を制すれば、則ち楽しみて乱れず。欲を以って道を忘るれば、則ち惑いて楽しまず」
「君子は道義によって楽しみを得ようとし、小人は愛欲によって楽しみを得ようとする。
道義によって愛欲を制すれば、よく楽しめながら乱れることもない。一方で、
愛欲によって道義を忘れれば、惑いに苛まれてろくに楽しむこともできない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・楽記第十九より)
 「金持ち争わず」という俗諺通り、概ねのところでは、
「金持ち争わず」という俗諺通り、概ねのところでは、 貧しいから争いが起こり、富裕だから平和でいられるというもの。
未だ資本的、資源的な富裕で突出している欧米聖書圏内での戦争は稀な一方、
貧しいアフリカや中東、東南アジア諸国での内戦や国際紛争は恒常的なものであり続けている。
それらの社会から富を巻き上げて、狭隘な富裕を謳歌しているのが欧米聖書圏でもあるわけだから、
所詮は世界中の紛争の本当の火種も、欧米の不正な富裕者でこそあるのだといえる。
ところで、今でもインドのように、ブラックアフリカ並みの貧困下に置かれながら、
内紛まではほぼ控えられている大国もある。これは、仏教の影響も受けているヒンズー教の
教化などがあって初めて実現し得ていることで、同レベルの生活水準でありながら
ブラックアフリカなどでは内紛が絶えないでいるのも、欧米聖書圏による文化的征服の禍根が
持ち越されたままであるのだからだと言える。のみならず、富裕な欧米聖書圏においてですら、
アイルランドやユーゴスラビアのように紛争を巻き起こす国もあるわけで、聖書信仰こそは貧富の
如何によらず、人々に最大級かつ不必要な闘争本能を植え付けている邪教であることが分かるのである。
人々に不埒な闘争本能を植え付けた挙句に、自分たちだけが大量に富を独占して、「金持ち争わず」
の要領でどうにか隣人間の関係だけを良好に保とうとするあり方からして、原理的に必ず一定以上の
争いをこの世にもたらし続けるものである。聖書信仰がそうである一方で、インドのヒンズー教などは、
最悪級の貧困下においてですら内紛ぐらいは未然に止め置くだけの効験をあらたかにしている。
その手段たるや、カースト制による絶対支配だったりもして、決してもろ手を挙げて称賛できたりする
ような代物でもないが、結果としてヒンズー教が信仰圏に与えている影響は、富裕者同士の争いすら
時に勃発させる聖書信仰がこの世に与えている影響などと比べれば、遥かにマシなものとなっている。
やはりその程度にも大きな差異があるが、まず人々に心の豊かさをもたらす信教と、
そうでない信教との両方がある。人々に最悪級の心の貧しさをもたらすのが他でもない聖書信仰で、
だからこそ金持ち同士での争いすら時に巻き起こさせるのに対し、ヒンズー教などは比較的、
信者に心の豊かさをもたらす信教だから、相当な貧困下においても信者を最悪の妄動にまでは至らせない。
当然、人々に心の豊かさをもたらす教学を推進して、心の貧しさをもたらす教学を排していくべきで、
たとえ世界中の貧富の格差を埋め合わせてみたところで、誰しもが聖書信者並みの心の貧しさのままでいたり
したなら、紛争の多発化なども防げない。一方で、誰しもがインド人並みの心の豊かさを身に付けたなら、
誰しもが今のインド並みの貧困下に置かれた所で、紛争級の妄動にまでは至らない。別に誰しもが今の
インド人並みの貧しさに置かれるべきでもないが、最悪そうなったところで、心の豊かさにだけよって
争いを未然に食い止めることだってできなくはないのだという見本に、今のインドなどがなってくれてもいる。
この地球上の資源含有率などからいっても、世界中の誰しもが今の欧米人並みの富裕に与れるなんてことも
あり得ない。ただ資源占有率を均すだけなら、誰しもがインドネシア人やフィリピン人並みの生活を
送らされることにもなるわけで、だからといって誰しもが今のインドネシア人やフィリピン人を
目指すべきだなどということもないとは、すでに>>132-133にも書いた。フィリピンのキリスト教はおろか、
インドネシアのイスラム教ですら、人々に心の豊かさをもたらすことにかけて長けた信教であるなどという
ことはないわけで、心の豊かさについて見習うべきなのはむしろインド人などのほうである。さらに言えば、
今のインド人以上にも、仏教圏だった頃のインド人のあり方などを見習うほうが、よりうってつけでもある。
そうでない信教との両方がある。人々に最悪級の心の貧しさをもたらすのが他でもない聖書信仰で、
だからこそ金持ち同士での争いすら時に巻き起こさせるのに対し、ヒンズー教などは比較的、
信者に心の豊かさをもたらす信教だから、相当な貧困下においても信者を最悪の妄動にまでは至らせない。
当然、人々に心の豊かさをもたらす教学を推進して、心の貧しさをもたらす教学を排していくべきで、
たとえ世界中の貧富の格差を埋め合わせてみたところで、誰しもが聖書信者並みの心の貧しさのままでいたり
したなら、紛争の多発化なども防げない。一方で、誰しもがインド人並みの心の豊かさを身に付けたなら、
誰しもが今のインド並みの貧困下に置かれた所で、紛争級の妄動にまでは至らない。別に誰しもが今の
インド人並みの貧しさに置かれるべきでもないが、最悪そうなったところで、心の豊かさにだけよって
争いを未然に食い止めることだってできなくはないのだという見本に、今のインドなどがなってくれてもいる。
この地球上の資源含有率などからいっても、世界中の誰しもが今の欧米人並みの富裕に与れるなんてことも
あり得ない。ただ資源占有率を均すだけなら、誰しもがインドネシア人やフィリピン人並みの生活を
送らされることにもなるわけで、だからといって誰しもが今のインドネシア人やフィリピン人を
目指すべきだなどということもないとは、すでに>>132-133にも書いた。フィリピンのキリスト教はおろか、
インドネシアのイスラム教ですら、人々に心の豊かさをもたらすことにかけて長けた信教であるなどという
ことはないわけで、心の豊かさについて見習うべきなのはむしろインド人などのほうである。さらに言えば、
今のインド人以上にも、仏教圏だった頃のインド人のあり方などを見習うほうが、よりうってつけでもある。
未だイギリス連合下に置かれ、最悪級の貧困に喘がされているがための非常的な措置として、酷烈なカースト制を
敷いている今のインドなどよりも、古代中国と並んで世界最大級の繁栄を謳歌していた、仏教圏だった頃の
インドのあり方などを見習うほうが、心の豊かさの蓄え方を教わる上では適している。今のインド人もまた、
昔のインド文化を糧としているわけだから、インドの歴史性もまた決して無視されていいものではないといえる。
——真正聖書=四書五経にまつわる論議としては、今日は道はずれ気味になってしまったが、
「より重大なのは物質的貧富以上にも心の貧富である」という認識が、四書五経中でも一貫されている。
ただ、俗世の道徳学たる儒学の聖典であるために、四書五経などでは抽象的な心論は少なく、
心か本で財物が末であるという本末認識を大前提とした、具体的な実践論などのほうが豊富である。
そうであることをよくわきまえた上で四書五経を読めば、その記述内容に納得がいくことも多いのである。
「信を講じ睦を修む、之れを人の利と謂う。争奪相殺す、之れを人の憂いと謂う」
「信実さを養って人々との親睦に務めることが、人としての利益である。争って奪い合い殺し合うのは憂いである。
(平和によってお互いの利益を損なわないことが、ありのままに利益である。物質的な富裕も利益なら、
平和によってお互いの利益を守ることもまた利益なのだから、両者を対立的なものとして捉えたりする必要はない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・礼運第九より)
敷いている今のインドなどよりも、古代中国と並んで世界最大級の繁栄を謳歌していた、仏教圏だった頃の
インドのあり方などを見習うほうが、心の豊かさの蓄え方を教わる上では適している。今のインド人もまた、
昔のインド文化を糧としているわけだから、インドの歴史性もまた決して無視されていいものではないといえる。
——真正聖書=四書五経にまつわる論議としては、今日は道はずれ気味になってしまったが、
「より重大なのは物質的貧富以上にも心の貧富である」という認識が、四書五経中でも一貫されている。
ただ、俗世の道徳学たる儒学の聖典であるために、四書五経などでは抽象的な心論は少なく、
心か本で財物が末であるという本末認識を大前提とした、具体的な実践論などのほうが豊富である。
そうであることをよくわきまえた上で四書五経を読めば、その記述内容に納得がいくことも多いのである。
「信を講じ睦を修む、之れを人の利と謂う。争奪相殺す、之れを人の憂いと謂う」
「信実さを養って人々との親睦に務めることが、人としての利益である。争って奪い合い殺し合うのは憂いである。
(平和によってお互いの利益を損なわないことが、ありのままに利益である。物質的な富裕も利益なら、
平和によってお互いの利益を守ることもまた利益なのだから、両者を対立的なものとして捉えたりする必要はない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・礼運第九より)
漢帝国のような徳治制の社会においては、王侯による恩赦の発布が重要な政治行為の一環とされていた。
「漢書」の帝紀における歴代皇帝の詔勅もその多くが恩赦にまつわるもので、罪人の釈放や減刑が、
法定刑を含む規制の緩和、正月祭などを民が自由に催すことの許可などと共に、頻繁に下されていた。
恩赦を発する理由はといえば、「龍が現れた」「鳳が飛んだ」なども含む、今だとオカルトじみて
聞こえるような瑞祥だったりもするが、とにかく適当な理由すら付けて赦令を下していたということ。
一方で、それほどにも恩赦を多発できたのは、当該の国家の朝廷なり幕府なりが積極的な徳治に努めることで、
世の中の福徳の余りある程もの増進を果たしていたからで、そのような努力も行われない法治主義の国家
などで恩赦を乱発したりしたなら、それによる世相不安の深刻化すらもが免れられなくなるのである。
法治国家ですら恩赦の多発化などは警戒せねばならないのだから、人々に権力犯罪や我田引水を
けしかける邪教に支配された社会などで、恩赦などを通用させる余地がないこともまた明らかである。
犯罪行為への恩赦といわず、破産を通じての借金の踏み倒しなどを容認するだけでも、相当に危うい。
今の日本などはまだ、全体に比べての破産者や生活保護者が少数に止まっていて、しかも全国民を挙げての
健全な自活が旺盛なものだから、落伍者を保護してやることだってできなくはない。(それでも保護を
受けることを恥じて自殺する者が多数に上っているが)一方で、全国民を挙げての浪費が甚だしい
アメリカや、公務員による富の食いつぶしが著しいギリシャなどでは、国全体での破綻までもが
危ぶまれる事態と化してしまっている。特に、アメリカの破綻は国を挙げての借金踏み倒しの先に
行き着いたものだといえ、為政者が徳治を心がけているわけでもないのに、民事と刑事両面における
赦免を乱発しすぎた挙句に、国家全体が破綻の様相を呈することとなった典型となっているのである。
「漢書」の帝紀における歴代皇帝の詔勅もその多くが恩赦にまつわるもので、罪人の釈放や減刑が、
法定刑を含む規制の緩和、正月祭などを民が自由に催すことの許可などと共に、頻繁に下されていた。
恩赦を発する理由はといえば、「龍が現れた」「鳳が飛んだ」なども含む、今だとオカルトじみて
聞こえるような瑞祥だったりもするが、とにかく適当な理由すら付けて赦令を下していたということ。
一方で、それほどにも恩赦を多発できたのは、当該の国家の朝廷なり幕府なりが積極的な徳治に努めることで、
世の中の福徳の余りある程もの増進を果たしていたからで、そのような努力も行われない法治主義の国家
などで恩赦を乱発したりしたなら、それによる世相不安の深刻化すらもが免れられなくなるのである。
法治国家ですら恩赦の多発化などは警戒せねばならないのだから、人々に権力犯罪や我田引水を
けしかける邪教に支配された社会などで、恩赦などを通用させる余地がないこともまた明らかである。
犯罪行為への恩赦といわず、破産を通じての借金の踏み倒しなどを容認するだけでも、相当に危うい。
今の日本などはまだ、全体に比べての破産者や生活保護者が少数に止まっていて、しかも全国民を挙げての
健全な自活が旺盛なものだから、落伍者を保護してやることだってできなくはない。(それでも保護を
受けることを恥じて自殺する者が多数に上っているが)一方で、全国民を挙げての浪費が甚だしい
アメリカや、公務員による富の食いつぶしが著しいギリシャなどでは、国全体での破綻までもが
危ぶまれる事態と化してしまっている。特に、アメリカの破綻は国を挙げての借金踏み倒しの先に
行き着いたものだといえ、為政者が徳治を心がけているわけでもないのに、民事と刑事両面における
赦免を乱発しすぎた挙句に、国家全体が破綻の様相を呈することとなった典型となっているのである。
罪を許すということには、当然それなりのリスクが伴う。そのリスクを見越した上で、自ら徳治を心がける
天皇なり皇帝なりが大赦を下すようなこともあるが、それは決して誰しもにできるようなことではない。
ただ能力がなくてできないというばかりでなく、それなりの立場にいるのでなければできない。
カルト宗教の指導者や商売人などは、その立場からして天下国家規模の運営責任を担うものではないから、
世の中に害を与える規模の刑事的、民事的過ちを勝手に許してやったりしていいはずもないのである。
徳治社会でも法官は法官で別にいて、ただの事務処理者として徳治を実施する王侯や高官の下に置かれる。
上司からの命令でもないうちは、法官は民に対する信賞必罰を心がけ、民もまたそれに従う。その頻度が
法治社会と比べて少ないということはあっても、守らせ守らせられる法規というものがやはり一定以上にはある。
誰しもが誰しもと無条件に許し合うなんていうことは、法治社会はおろか、徳治社会でもあり得ないことで、
罪を許されることばかりを欲するような卑しい身分の者ほど、(小人は恵を懐う。里仁第四・一一)
最後まで信賞必罰に則ったままの存在でいることを、徳治社会でも強要され続けるのである。
法で禁止されるべき様な悪行は自律的に行わず、むしろ善行によって世の大利の目方を増しすらするような
君子であって初めて、他人の罪を許してやれるだけの度量すらもが備わるのだから、自分が罪を許されたい
がために、他人の罪を許してやろうとするような考えが通用していい余地などは、どこにもないのだといえる。
「天道は善に福し淫に禍す。〜肆に台れ小子、天命の明威を将し、敢えて赦さず」
「天道は必ず正善なる者に福徳を授け、淫悪にふける者に災禍を下す。だからこそ私もまた、
その天命に根ざした明らかな威徳によって、罪を罰するに際しても、あえて赦そうとしないのである」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・商書・湯誥より)
天皇なり皇帝なりが大赦を下すようなこともあるが、それは決して誰しもにできるようなことではない。
ただ能力がなくてできないというばかりでなく、それなりの立場にいるのでなければできない。
カルト宗教の指導者や商売人などは、その立場からして天下国家規模の運営責任を担うものではないから、
世の中に害を与える規模の刑事的、民事的過ちを勝手に許してやったりしていいはずもないのである。
徳治社会でも法官は法官で別にいて、ただの事務処理者として徳治を実施する王侯や高官の下に置かれる。
上司からの命令でもないうちは、法官は民に対する信賞必罰を心がけ、民もまたそれに従う。その頻度が
法治社会と比べて少ないということはあっても、守らせ守らせられる法規というものがやはり一定以上にはある。
誰しもが誰しもと無条件に許し合うなんていうことは、法治社会はおろか、徳治社会でもあり得ないことで、
罪を許されることばかりを欲するような卑しい身分の者ほど、(小人は恵を懐う。里仁第四・一一)
最後まで信賞必罰に則ったままの存在でいることを、徳治社会でも強要され続けるのである。
法で禁止されるべき様な悪行は自律的に行わず、むしろ善行によって世の大利の目方を増しすらするような
君子であって初めて、他人の罪を許してやれるだけの度量すらもが備わるのだから、自分が罪を許されたい
がために、他人の罪を許してやろうとするような考えが通用していい余地などは、どこにもないのだといえる。
「天道は善に福し淫に禍す。〜肆に台れ小子、天命の明威を将し、敢えて赦さず」
「天道は必ず正善なる者に福徳を授け、淫悪にふける者に災禍を下す。だからこそ私もまた、
その天命に根ざした明らかな威徳によって、罪を罰するに際しても、あえて赦そうとしないのである」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・商書・湯誥より)
自分たちでこの世に破滅をもたらしておいて、
自分たちこそは特定して救われようとするようなガン細胞人種こそは、
仮に一切衆生が救われるとした所で、最後まで救われないままでい続けなければならないことが確か。
仮に誰かが救われないことになるのだとすれば、
そのようなガン細胞人種こそが特定して救われないことになるのも確か。
自分たち全員が、ガンが切除されるようにして死滅させられるのだとすれば、ガン細胞人種も
「死なば諸共」で、自分たちごと全人類を滅亡に陥れるヤケクソにすら及びかねない。
下劣ではあるにしろ、小人の心情としてはそれも分からないことはないから、
救済対象を選別するような小乗志向ではなく、一切衆生を救済していくことを旨とする
大乗志向によってこそ救済に取り組んでいくぐらいのことは、救済者も心がけたほうがいいといえる。
それでも実際問題、現世では救われない者がいる。
この世に害悪をもたらして自分たちが救われようとする、ガン細胞人種としての心得を
最後まで捨て去ろうとしないもの、邪教の棄教と引き換えの救済にすら応じようとしないものは、
どんなに大きな災厄からも人々を救い出せるほどもの手腕を持つ救済者によってですら、救われることはない。
救われ得ないから救われないのではなく、自分自身が救われることを拒み通しているから、救われない。
まるで如来か菩薩ほどにも救済能力に長けた者がいたとすれば、大罪を積み重ねて来たキリスト教徒や
ユダヤ教徒を、棄教後に救い取ることですらできなくはないだろう。「華厳経」十回向品第二十五の四にも、
菩薩が冤罪によってこの世に撒き散らされる災厄すらも十分に除滅するとあるから、冤罪信仰である
キリスト教が撒き散らす災厄からすら、菩薩が一切衆生を救い出すことも不可能ではないに違いない。
自分たちこそは特定して救われようとするようなガン細胞人種こそは、
仮に一切衆生が救われるとした所で、最後まで救われないままでい続けなければならないことが確か。
仮に誰かが救われないことになるのだとすれば、
そのようなガン細胞人種こそが特定して救われないことになるのも確か。
自分たち全員が、ガンが切除されるようにして死滅させられるのだとすれば、ガン細胞人種も
「死なば諸共」で、自分たちごと全人類を滅亡に陥れるヤケクソにすら及びかねない。
下劣ではあるにしろ、小人の心情としてはそれも分からないことはないから、
救済対象を選別するような小乗志向ではなく、一切衆生を救済していくことを旨とする
大乗志向によってこそ救済に取り組んでいくぐらいのことは、救済者も心がけたほうがいいといえる。
それでも実際問題、現世では救われない者がいる。
この世に害悪をもたらして自分たちが救われようとする、ガン細胞人種としての心得を
最後まで捨て去ろうとしないもの、邪教の棄教と引き換えの救済にすら応じようとしないものは、
どんなに大きな災厄からも人々を救い出せるほどもの手腕を持つ救済者によってですら、救われることはない。
救われ得ないから救われないのではなく、自分自身が救われることを拒み通しているから、救われない。
まるで如来か菩薩ほどにも救済能力に長けた者がいたとすれば、大罪を積み重ねて来たキリスト教徒や
ユダヤ教徒を、棄教後に救い取ることですらできなくはないだろう。「華厳経」十回向品第二十五の四にも、
菩薩が冤罪によってこの世に撒き散らされる災厄すらも十分に除滅するとあるから、冤罪信仰である
キリスト教が撒き散らす災厄からすら、菩薩が一切衆生を救い出すことも不可能ではないに違いない。
しかし、キリスト教徒やユダヤ教徒が、それらの邪教信仰を続けている限りにおいては、
どんなに有能な菩薩や如来といえども、それらの人々を救い取ることが不可能であり続けるだろう。
キリスト信仰やユダヤ信仰を貫くことによって、仏法のような純正な手法によって救われることを
自分たちが一貫して拒絶し続けているのだから、能力的に十分救えたところで、原理的に救うことができない。
最後まで邪信を貫こうとする者がいれば、その分だけ救われない者の数も増えてしまう。
だから一切衆生の救済能力者が現れたところで、相変わらず救われない者がいる可能性も残る。
そのような不届き者にあらかじめ反省を促して、邪信を完全に捨て去る覚悟を得させてから自分が世に
降臨することもまた救済者の義務であるに違いなく、救済者はただ現れればいいというばかりでもないといえる。
一切衆生を救い取る能力者がいたところで、それ即ち一切衆生救済の機縁となるわけでもない。
救済を受ける者もまた、邪教の完全永久棄教などの用意を整えられた時こそが、真の救済の機縁ともなる。
救済者と衆生の間にすら、八卦が二重に積み重なって六十四卦になるが如き相乗性が、断固として備わっているのである。
「年を薀む毋かれ、利を壅むる毋れ、姦を保つ毋れ、慝を留むる毋れ。災患を救い、禍乱を恤い、
好悪を同じくして王室を獎けよ。或いは茲の命を間さば、司慎司盟、名山名川、群神群祀、先王先公、
七姓十二国の祖、明神も之れを殛し、俾其の民を失い、命を隊し氏を亡ぼし、其の国家を踣さしめん」
「年毎の収穫を退蔵して民に分け与えるのを怠ったりせず、その他の利益についても退蔵したりせず、
姦邪の甚だしい者を保護してやったりもせず、悪い隠し事をそのままにしておいたりもするな。それでいて
災難憂患をよく救い、禍乱が巻き起こることを警戒し、好悪を同じくして玉を助けていくようにせよ。
この命すら守らない国があれば、全世界、ありとあらゆる山川神霊、王侯やその祖霊に至るまでが総力を
挙げての殺戮に臨み、民も失わせてその命なきものとし、国家丸ごとの取り潰しを完遂することだろう」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左子伝・襄公十一年より)
どんなに有能な菩薩や如来といえども、それらの人々を救い取ることが不可能であり続けるだろう。
キリスト信仰やユダヤ信仰を貫くことによって、仏法のような純正な手法によって救われることを
自分たちが一貫して拒絶し続けているのだから、能力的に十分救えたところで、原理的に救うことができない。
最後まで邪信を貫こうとする者がいれば、その分だけ救われない者の数も増えてしまう。
だから一切衆生の救済能力者が現れたところで、相変わらず救われない者がいる可能性も残る。
そのような不届き者にあらかじめ反省を促して、邪信を完全に捨て去る覚悟を得させてから自分が世に
降臨することもまた救済者の義務であるに違いなく、救済者はただ現れればいいというばかりでもないといえる。
一切衆生を救い取る能力者がいたところで、それ即ち一切衆生救済の機縁となるわけでもない。
救済を受ける者もまた、邪教の完全永久棄教などの用意を整えられた時こそが、真の救済の機縁ともなる。
救済者と衆生の間にすら、八卦が二重に積み重なって六十四卦になるが如き相乗性が、断固として備わっているのである。
「年を薀む毋かれ、利を壅むる毋れ、姦を保つ毋れ、慝を留むる毋れ。災患を救い、禍乱を恤い、
好悪を同じくして王室を獎けよ。或いは茲の命を間さば、司慎司盟、名山名川、群神群祀、先王先公、
七姓十二国の祖、明神も之れを殛し、俾其の民を失い、命を隊し氏を亡ぼし、其の国家を踣さしめん」
「年毎の収穫を退蔵して民に分け与えるのを怠ったりせず、その他の利益についても退蔵したりせず、
姦邪の甚だしい者を保護してやったりもせず、悪い隠し事をそのままにしておいたりもするな。それでいて
災難憂患をよく救い、禍乱が巻き起こることを警戒し、好悪を同じくして玉を助けていくようにせよ。
この命すら守らない国があれば、全世界、ありとあらゆる山川神霊、王侯やその祖霊に至るまでが総力を
挙げての殺戮に臨み、民も失わせてその命なきものとし、国家丸ごとの取り潰しを完遂することだろう」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左子伝・襄公十一年より)
 ガン細胞が人体に勝つということは、原理的にあり得ない。
ガン細胞が人体に勝つということは、原理的にあり得ない。 寄生する人体に勢力で勝って、人体を殺してしまったなら、自分も死ぬのみ。
だからせいぜい劣勢にある範囲だけで悪さをするのが関の山で、
虚栄を真の繁栄だなどと思い込んでのから騒ぎに終始するのみなのである。
ガン細胞ではなく、寄生虫や、卵を宿主に産み付ける虫などの内に、
宿主を殺してまで養分を吸い尽くす種がいくらかある。寄生菌の
冬虫夏草などもその部類だが、これらの寄生生物は、宿主となる
生物との異質性が十分であり、人間の白人と有色人種ほどにも
近似的な関係にあったりはしない。もしも白人がこのような
寄生生物のマネごとをして、宿主である他の地球人類を滅ぼそう
などとしたりしたなら、自分たちもまた同質の人類であるために、
住環境を失うなどの大きな危害を被り、決してただでは済まなくなる。
欧米の白人キリスト教徒も、せいぜい地球人類にとってのガン細胞止まりで、
宿主を殺してまで自分たちが生き延びられるような生物とまではいかない。
そこが多かれ少なかれ選民志向の持ち主であり続けてきた欧米キリスト教徒にとっての、
大きな見当違いだった部分であり、他者を殺してでも自分たちが生き延びる勢いでの、
異教徒に対する悪逆非道の限りを尽くしてきたことへの決まりも付かない所だともいえる。
人間同士の関係が、人体とガン細胞程度の関係に発展することはある一方で、宿主と、
宿主を殺し尽くす能力のある寄生生物の関係にまで発展することは、原理的にあり得ない。
犯罪聖書の信者はおろか、著者や登場人物たち自身もまた、全くそれに気づいていなかった。
その理由はといえば、古代オリエントや古代ローマにおいて、資産家でもある
支配階級と、一方的な搾取対象とされている被支配階級との断絶が極端であり過ぎて、
後者あっての前者という認識すらもが疎かにされていたことが挙げられる。
東洋においても支配被支配の関係は当然あるが、支配者が資産家でもあったりしたなら、
支配者こそは被支配者にとっての寄生体になってしまうという社会の実相をわきまえて、
支配階級と資産家を分断して、資産家を民間人の中でも特に賤しい存在として冷遇することが
四民制やカースト制によって嗜まれていたために、実際には被支配者にとっての寄生体に過ぎない、
資産家兼支配者を、あたかも被支配者の捕食者であるかのように思い違うことまでは避けていたのだった。
古代オリエントの遺跡や、西洋の伝統建築などにも巨大で美麗なものが多々あるが、
そこに住む人々が人間社会の実相を捉えられていたとはいい難い。あまりにも壮大な建築物の
中に引きこもって、外界との直接的な関係を断つのが支配者にとっての恒でもあったから、
支配者と被支配者を総合した世界の実相をわきまえることもできなかった。土建こそは人類文明の
極致みたいな所もあるが、これが土建によって人類社会の実相を見損なうこともある実例となっている。
土建もまた、世のため人のためにあってこそのものだということがいえるのである。
「世の守りなり。身の能く為す所に非ざるなり」
「この地は世世に渡って守り継がれて来たもの。自分一身の身勝手によってどうしていいものでもない。
(過去の為政にまでよく思いを致して、この世に身勝手の通用する余地などないことをわきまえている)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・梁恵王章句下・一五より)
その理由はといえば、古代オリエントや古代ローマにおいて、資産家でもある
支配階級と、一方的な搾取対象とされている被支配階級との断絶が極端であり過ぎて、
後者あっての前者という認識すらもが疎かにされていたことが挙げられる。
東洋においても支配被支配の関係は当然あるが、支配者が資産家でもあったりしたなら、
支配者こそは被支配者にとっての寄生体になってしまうという社会の実相をわきまえて、
支配階級と資産家を分断して、資産家を民間人の中でも特に賤しい存在として冷遇することが
四民制やカースト制によって嗜まれていたために、実際には被支配者にとっての寄生体に過ぎない、
資産家兼支配者を、あたかも被支配者の捕食者であるかのように思い違うことまでは避けていたのだった。
古代オリエントの遺跡や、西洋の伝統建築などにも巨大で美麗なものが多々あるが、
そこに住む人々が人間社会の実相を捉えられていたとはいい難い。あまりにも壮大な建築物の
中に引きこもって、外界との直接的な関係を断つのが支配者にとっての恒でもあったから、
支配者と被支配者を総合した世界の実相をわきまえることもできなかった。土建こそは人類文明の
極致みたいな所もあるが、これが土建によって人類社会の実相を見損なうこともある実例となっている。
土建もまた、世のため人のためにあってこそのものだということがいえるのである。
「世の守りなり。身の能く為す所に非ざるなり」
「この地は世世に渡って守り継がれて来たもの。自分一身の身勝手によってどうしていいものでもない。
(過去の為政にまでよく思いを致して、この世に身勝手の通用する余地などないことをわきまえている)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・梁恵王章句下・一五より)
古代から近現代に至るまで、「ユダヤ人」を称する旧約信者が
生業としてきた政商とか金融ヤクザとか悪徳外交家とかいった職分は、
それを敵に回す国や民族のみならず、味方に付ける国や民族すらをも破滅に陥れる。
だからこそ、古来からユダヤ人を重用してきた欧州諸国なども引っ切り無しの
興亡を続け、1000年前の国体をそのまま保てているような国も一つもないのである。
「ユダヤ人」は民族でも人種でもなく、旧約聖書の信者のことである。
それでいて、国を挙げて旧約を信仰している国などは、近年のイスラエル建国以前には
一つとして存在しなかった。旧約信仰が国家や民族レベルで保たれていたような
事実もなく、主にキリスト教圏において、ゲリラ的にユダヤ人を称する旧約信者が
生じては消え、生じては消えを繰り返してきたのみである。
仮に、旧約の神によって旧約信者が救われるとした所で、そもそも旧約信者という存在自体が、
救われる対象としての実体性を保てていない。キリスト教圏において、無責任な家族計画によって
一般家庭からはじき出された孤児なり私生児なりが旧約信者としての悪行を繰り返しては消え去り、
悪行を繰り返しては消え去りを繰り返しているだけなのだから、未だかつて旧約信者たる
ユダヤ人が救われたことはおろか、ユダヤ人がユダヤ人として、誰かに救われる
対象としての体裁を保てていたことすらないことが確かなのである。
キリスト教も、ユダヤ教における神の救いを敷衍して、自分たちが神に救われるとしている。
そもそも始めから全く救われる体を保てていないユダヤ教徒のようにして、自分たちキリスト教徒
もまた救われるという完全矛盾。救われる救われると豪語しながら、ユダヤ教徒もキリスト教徒も、
信仰によって救われるということが如何なることであるのかすら、全く見えていないのである。
生業としてきた政商とか金融ヤクザとか悪徳外交家とかいった職分は、
それを敵に回す国や民族のみならず、味方に付ける国や民族すらをも破滅に陥れる。
だからこそ、古来からユダヤ人を重用してきた欧州諸国なども引っ切り無しの
興亡を続け、1000年前の国体をそのまま保てているような国も一つもないのである。
「ユダヤ人」は民族でも人種でもなく、旧約聖書の信者のことである。
それでいて、国を挙げて旧約を信仰している国などは、近年のイスラエル建国以前には
一つとして存在しなかった。旧約信仰が国家や民族レベルで保たれていたような
事実もなく、主にキリスト教圏において、ゲリラ的にユダヤ人を称する旧約信者が
生じては消え、生じては消えを繰り返してきたのみである。
仮に、旧約の神によって旧約信者が救われるとした所で、そもそも旧約信者という存在自体が、
救われる対象としての実体性を保てていない。キリスト教圏において、無責任な家族計画によって
一般家庭からはじき出された孤児なり私生児なりが旧約信者としての悪行を繰り返しては消え去り、
悪行を繰り返しては消え去りを繰り返しているだけなのだから、未だかつて旧約信者たる
ユダヤ人が救われたことはおろか、ユダヤ人がユダヤ人として、誰かに救われる
対象としての体裁を保てていたことすらないことが確かなのである。
キリスト教も、ユダヤ教における神の救いを敷衍して、自分たちが神に救われるとしている。
そもそも始めから全く救われる体を保てていないユダヤ教徒のようにして、自分たちキリスト教徒
もまた救われるという完全矛盾。救われる救われると豪語しながら、ユダヤ教徒もキリスト教徒も、
信仰によって救われるということが如何なることであるのかすら、全く見えていないのである。
救われた先に何があるか、いかなる条件を以ってして救われたとするか、それすらまともに
考えることもないままに「救い」という救いを求め、かえって事実上の破滅を呼び込んできた。
そもそも自分たちが救済されるビジョンすら明確ではなかったのだから、その先に受刑者や
強制入院患者や禁治産者としての処遇が待ち受けていた所で、別に心外だったりはしないはずだ。
「これは自分の想定していた救済とは違う」なんてこともないのだから、心外であるはずもない。
救われるか救われないか以前に、自分が救われる対象としての体裁を保てているかが問題である。
浄土信者やムスリムは、救われようが救われまいが、救われる対象としての体裁を保てている、
一方で、キリスト教徒やユダヤ教徒は、仮に救うことができたところで、そもそも本人たち自身
からして、誰かに救われる対象としての体裁を保とうとした試しすらないことが確かなのである。
ユダヤ=キリスト両聖書教は、誰にも救われない宗教である以前に、誰からの救いをも拒み通す宗教でこそある。
誰かに救われ得るような体裁をことごとくかなぐり捨てることで、最大級の破滅を自他に招き寄せる
ことばかりを目的としている宗教であり、誰かに救われるなんていう体裁からして、始めから虚構
でしかなかったのである。そして、今になって人類滅亡級の破滅を呼び寄せて、なおかつその
信仰によって誰からの救いをも拒み通そうとしている。救いも拒み通して破滅を呼び込み続ける、
その行いは今までどおり一貫していて、ただ完全に絶体絶命である点だけが特別なところである。
絶体絶命だから、聖書信仰を破棄してでも誰かに救いを求めるしかない。それもまた完全に、
「誰からの救いをも拒み通す信教」としての聖書信仰に対する、今まで通りの扱いだといえる。
考えることもないままに「救い」という救いを求め、かえって事実上の破滅を呼び込んできた。
そもそも自分たちが救済されるビジョンすら明確ではなかったのだから、その先に受刑者や
強制入院患者や禁治産者としての処遇が待ち受けていた所で、別に心外だったりはしないはずだ。
「これは自分の想定していた救済とは違う」なんてこともないのだから、心外であるはずもない。
救われるか救われないか以前に、自分が救われる対象としての体裁を保てているかが問題である。
浄土信者やムスリムは、救われようが救われまいが、救われる対象としての体裁を保てている、
一方で、キリスト教徒やユダヤ教徒は、仮に救うことができたところで、そもそも本人たち自身
からして、誰かに救われる対象としての体裁を保とうとした試しすらないことが確かなのである。
ユダヤ=キリスト両聖書教は、誰にも救われない宗教である以前に、誰からの救いをも拒み通す宗教でこそある。
誰かに救われ得るような体裁をことごとくかなぐり捨てることで、最大級の破滅を自他に招き寄せる
ことばかりを目的としている宗教であり、誰かに救われるなんていう体裁からして、始めから虚構
でしかなかったのである。そして、今になって人類滅亡級の破滅を呼び寄せて、なおかつその
信仰によって誰からの救いをも拒み通そうとしている。救いも拒み通して破滅を呼び込み続ける、
その行いは今までどおり一貫していて、ただ完全に絶体絶命である点だけが特別なところである。
絶体絶命だから、聖書信仰を破棄してでも誰かに救いを求めるしかない。それもまた完全に、
「誰からの救いをも拒み通す信教」としての聖書信仰に対する、今まで通りの扱いだといえる。
「天の方に虐いせるとき、然かるも謔謔とする無かれ。老夫の灌灌とするにも、小子は蹻蹻とす。
我れを匪として耄せると言い、爾が憂い用て謔とせる。将に熇熇多として、救い薬す可からず」
「天がまさに大禍を下せるときにすら、不埒な享楽に耽っていたりすべきではない。それを知る私
のような老人は戦々恐々としているが、小僧っ子どもはといえば未だケラケラと浮かれたままでいる。
私のこの態度こそを老耄として非難し、この憂いをもただの諧謔として歯牙にもかけぬ。将にいま、
禍いの火も方々へと燃え広がりつつあるが、だからといって救ってやるべきだとすらいえない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・大雅・生民之什・板より)
自ら破滅を追い求め続けている連中を救ってやったりして、どうしようというのか。
破滅こそを欲している者どもに対する救いなど、ただの有難迷惑にしかならないじゃないか。
我れを匪として耄せると言い、爾が憂い用て謔とせる。将に熇熇多として、救い薬す可からず」
「天がまさに大禍を下せるときにすら、不埒な享楽に耽っていたりすべきではない。それを知る私
のような老人は戦々恐々としているが、小僧っ子どもはといえば未だケラケラと浮かれたままでいる。
私のこの態度こそを老耄として非難し、この憂いをもただの諧謔として歯牙にもかけぬ。将にいま、
禍いの火も方々へと燃え広がりつつあるが、だからといって救ってやるべきだとすらいえない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・大雅・生民之什・板より)
自ら破滅を追い求め続けている連中を救ってやったりして、どうしようというのか。
破滅こそを欲している者どもに対する救いなど、ただの有難迷惑にしかならないじゃないか。
イエスの行いは、見習えるものではないし、見習うべきものでもないし、
本人が人々に見習わせるに値するものたろうとしたものですらない。
イエスのマネをしたって、ただ死ぬだけで生き返れるわけでも、昇天できるわけでもない。
現実問題そうだから、カトリックの祖であるアウグスチヌスも、信者がイエスのマネをして
自殺することを公的に禁止した。その論拠はといえば、「神からもらった命を大事にしなさい」
などというもので、これこそ、イエス自身がまったく反故にしたはずの代物である。故に、
カトリックはその原初の頃から、イエスの行いが全く見習えないものであるのみならず、
見習うべきでないものであることすらをもとっくに認めてしまっているのだといえる。
そのカトリックに反目する形で、ドイツで生じたプロテスタントも、イエスの教えは
全く守ることもできないものばかりであることを主張した上での、信仰義認を本是とした。
カトリックにはまだ、イエスの教えの内に何か守るべき有意義なものがあることを
認めようとする傾向があったが、プロテスタントはそれすらをも全否定した。
結局、キリスト教圏の人間は、その最原初のころから、
全人生を挙げて見習うに値するだけの大師を得たことがない。
全ての師弟関係が「一過性の事務」止まりでしかない完全な横並び関係、それをキリスト教徒は
「神の下での平等」とすら嘯いて来たらしいが、なんと空しい人間関係を続けてきたものだろう。
全人生を挙げて師とすべきものを見習い、自分もまた全人生を挙げての師とされるに値する
だけの賢聖となる、そこにこそ人間にとっての、人並み以上の向上もまた存在し得るのであり、
それを欠いたところにはもはや、凡人並みかそれ以下の、衆愚の集いしかあり得ないのである。
本人が人々に見習わせるに値するものたろうとしたものですらない。
イエスのマネをしたって、ただ死ぬだけで生き返れるわけでも、昇天できるわけでもない。
現実問題そうだから、カトリックの祖であるアウグスチヌスも、信者がイエスのマネをして
自殺することを公的に禁止した。その論拠はといえば、「神からもらった命を大事にしなさい」
などというもので、これこそ、イエス自身がまったく反故にしたはずの代物である。故に、
カトリックはその原初の頃から、イエスの行いが全く見習えないものであるのみならず、
見習うべきでないものであることすらをもとっくに認めてしまっているのだといえる。
そのカトリックに反目する形で、ドイツで生じたプロテスタントも、イエスの教えは
全く守ることもできないものばかりであることを主張した上での、信仰義認を本是とした。
カトリックにはまだ、イエスの教えの内に何か守るべき有意義なものがあることを
認めようとする傾向があったが、プロテスタントはそれすらをも全否定した。
結局、キリスト教圏の人間は、その最原初のころから、
全人生を挙げて見習うに値するだけの大師を得たことがない。
全ての師弟関係が「一過性の事務」止まりでしかない完全な横並び関係、それをキリスト教徒は
「神の下での平等」とすら嘯いて来たらしいが、なんと空しい人間関係を続けてきたものだろう。
全人生を挙げて師とすべきものを見習い、自分もまた全人生を挙げての師とされるに値する
だけの賢聖となる、そこにこそ人間にとっての、人並み以上の向上もまた存在し得るのであり、
それを欠いたところにはもはや、凡人並みかそれ以下の、衆愚の集いしかあり得ないのである。
キリスト教圏において蓄積されて来た、洋学にまつわる知見や技術なども、その全てが
一過性の事務止まりな代物で、全人生を挙げて学んだり身に付けたりするに値するものではない。
だからこそ、人生を挙げての修練に取り組んでいく必要がある、儒学や仏道や武道などと
比べて、それを教えてくれる相手が偉大だなどということもない。少なくとも、洋学の知識や
技能の持ち主だからといって、尊敬に値する人間だったりすることはなく、仮に尊敬に値する
人間でもあるのなら、必ず別の側面での、人生を挙げての研鑽に取り組んでいたりするのである。
それにしたって、洋学知識の持ち主が、かりそめの尊敬の対象にされたりすることはある。
西洋医学の知識の持ち主である医師などがその最たる例だが、医者に対する尊敬などは、
キリスト教の牧師や宣教師に対する懺悔などと同レベルの、困った時の依り縋りの体現でしかない。
健全なうちからのより一層の向上などではなく、病気や怪我や悪行などの、負の問題を呈した
後にそれを救っていただこうというまでものでしかないから、医師や牧師や宣教師などを
敬った所で、本人自身が人並み以上の向上を果たせたりすることは永久にないのである。
全人生を挙げて見習うに値する大師への尊敬は、そのような敬いとも全く異なる。
別に自分が追い詰められているわけでもないうちからの、積極的に積み立てられていく尊敬。
その尊敬によってのみ、人もまたより一層の向上があり得るのだから、困った時の神頼み、
困った時の師頼みなどに全ての尊敬を集約させたりしていてもならないことが分かるのである。
「籩豆の事は、則ち有司存せり」
「お祭りのお供えのことなどは、係りの祭司がいるから任せればよい。(君子の本分ではない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・泰伯第八・四より)
一過性の事務止まりな代物で、全人生を挙げて学んだり身に付けたりするに値するものではない。
だからこそ、人生を挙げての修練に取り組んでいく必要がある、儒学や仏道や武道などと
比べて、それを教えてくれる相手が偉大だなどということもない。少なくとも、洋学の知識や
技能の持ち主だからといって、尊敬に値する人間だったりすることはなく、仮に尊敬に値する
人間でもあるのなら、必ず別の側面での、人生を挙げての研鑽に取り組んでいたりするのである。
それにしたって、洋学知識の持ち主が、かりそめの尊敬の対象にされたりすることはある。
西洋医学の知識の持ち主である医師などがその最たる例だが、医者に対する尊敬などは、
キリスト教の牧師や宣教師に対する懺悔などと同レベルの、困った時の依り縋りの体現でしかない。
健全なうちからのより一層の向上などではなく、病気や怪我や悪行などの、負の問題を呈した
後にそれを救っていただこうというまでものでしかないから、医師や牧師や宣教師などを
敬った所で、本人自身が人並み以上の向上を果たせたりすることは永久にないのである。
全人生を挙げて見習うに値する大師への尊敬は、そのような敬いとも全く異なる。
別に自分が追い詰められているわけでもないうちからの、積極的に積み立てられていく尊敬。
その尊敬によってのみ、人もまたより一層の向上があり得るのだから、困った時の神頼み、
困った時の師頼みなどに全ての尊敬を集約させたりしていてもならないことが分かるのである。
「籩豆の事は、則ち有司存せり」
「お祭りのお供えのことなどは、係りの祭司がいるから任せればよい。(君子の本分ではない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・泰伯第八・四より)
人事を尽くした上で天命を待つのなら、寝て待とうが起きて待とうが、いずれでも構いやしない。
着実な善因楽果を期待するのであれば、何も強制捜査を待つような態度でいる必要もない。
自らの為してきた試みが善因楽果に相当するか、悪因苦果に相当するかすら分からないから、
強制捜査を待つようなおどおどした態度でしかいられない。そして、それ程にも不注意であるからには、
悪因苦果に結び付く悪行を為してきた可能性のほうが高いので、それはそれは恐ろしくもあろう。
もちろん、悪逆非道を尽くしておきながら「何とかなるさLet it be」と開き直って平然としている
場合もなきにしもあらずで、だからこそ素直に摘発にも応じられるというのなら、摘発を警戒
している場合よりも神妙だといえる。というわけで、悪因苦果を待ち受ける悪人といえども、
できる限り警戒を捨てて、自然体で処遇に甘んじていくほうがまだマシなのだといえる。
自らの行いに責任を感じているのであれば、善を為したのであれ悪を為したのであれ、
その結果に恐れおののいたりすることもなく、泰然として結果を受け入れるばかりのはずだ。
僥倖であれ災難であれ、自らの行いからすれば心外な結果がもたらされた場合に人は恐れおののき、
行いとの因果関係を説明されて納得するか、もしくはそれでも納得いかなくて不満を抱き続けたりする。
自らの行いとは全く無縁な、他者からの一方的な仕打ちを警戒すべきだということはあるし、
また自分自身が悪因苦果を呼び込むような過ちを犯さないように慎んでいくべきだともいえる。
その上で、自らの責任ある行いに対する報いまでをもいちいち警戒すべきもないということが言える。
警戒すべきものとそうでないものとの分別を付ける、そのあり方が以上のようであるべきだということ。
着実な善因楽果を期待するのであれば、何も強制捜査を待つような態度でいる必要もない。
自らの為してきた試みが善因楽果に相当するか、悪因苦果に相当するかすら分からないから、
強制捜査を待つようなおどおどした態度でしかいられない。そして、それ程にも不注意であるからには、
悪因苦果に結び付く悪行を為してきた可能性のほうが高いので、それはそれは恐ろしくもあろう。
もちろん、悪逆非道を尽くしておきながら「何とかなるさLet it be」と開き直って平然としている
場合もなきにしもあらずで、だからこそ素直に摘発にも応じられるというのなら、摘発を警戒
している場合よりも神妙だといえる。というわけで、悪因苦果を待ち受ける悪人といえども、
できる限り警戒を捨てて、自然体で処遇に甘んじていくほうがまだマシなのだといえる。
自らの行いに責任を感じているのであれば、善を為したのであれ悪を為したのであれ、
その結果に恐れおののいたりすることもなく、泰然として結果を受け入れるばかりのはずだ。
僥倖であれ災難であれ、自らの行いからすれば心外な結果がもたらされた場合に人は恐れおののき、
行いとの因果関係を説明されて納得するか、もしくはそれでも納得いかなくて不満を抱き続けたりする。
自らの行いとは全く無縁な、他者からの一方的な仕打ちを警戒すべきだということはあるし、
また自分自身が悪因苦果を呼び込むような過ちを犯さないように慎んでいくべきだともいえる。
その上で、自らの責任ある行いに対する報いまでをもいちいち警戒すべきもないということが言える。
警戒すべきものとそうでないものとの分別を付ける、そのあり方が以上のようであるべきだということ。
警戒対象に上記のような分別を付けることが、自らの生活全般にとっての適切な緩急ともなる。
たとえば、スポーツ化してしまっている今の剣道や柔道は、選手がこぞって力んでばかりいる
ものだから、長年現役で続けていくことも叶わなくなってしまっているが、古武道や合気道など
であれば、力の緩急からして訓練の対象とされているから、年老いてもなお続けていられたりする。
そのような緩急織り交ぜることによる耐久性を、警戒にまつわる上記のような分別ももたらしてくれる。
残念ながら、近現代の文明社会というのは、上記のような警戒の分別を持たないままでいるような
人間こそを保護してやるために発展してきている所がある。自らの行いに責任を持たないから、
その結果を警戒したりする一方で、他者からの侵害への警戒は警察任せ、自らの行いの修正も法律任せ
という人間のためにばかり今の社会は拵えられていて、そのために不注意極まりない人間ばかりが
溢れ返る社会とも化してしまっている。これが民主主義や法治主義の弊害であるともいえる一方、
不注意と無価値な注意とを人々に植え付ける方向性は、犯罪聖書にすらあらかじめ備わっていた
ようなので、近代以降に極度に問題化してしまっている人間規範の是正は、民主主義のような
近代的理念以前にまで、その問題の根本性を突き詰めていく必要があるようである。
「寝るに尸せず。居るに容せず」
「(孔先生は)寝るときも死体のような無様な寝方はされなかった。一方で、
家などで燕居している時にまで無闇に威儀を正したりはせず、ゆったりとしておられた。
(就寝中には就寝中なりの正し方があるし、覚醒中にも覚醒中なりの休み方がある)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・郷党第十・一八より)
たとえば、スポーツ化してしまっている今の剣道や柔道は、選手がこぞって力んでばかりいる
ものだから、長年現役で続けていくことも叶わなくなってしまっているが、古武道や合気道など
であれば、力の緩急からして訓練の対象とされているから、年老いてもなお続けていられたりする。
そのような緩急織り交ぜることによる耐久性を、警戒にまつわる上記のような分別ももたらしてくれる。
残念ながら、近現代の文明社会というのは、上記のような警戒の分別を持たないままでいるような
人間こそを保護してやるために発展してきている所がある。自らの行いに責任を持たないから、
その結果を警戒したりする一方で、他者からの侵害への警戒は警察任せ、自らの行いの修正も法律任せ
という人間のためにばかり今の社会は拵えられていて、そのために不注意極まりない人間ばかりが
溢れ返る社会とも化してしまっている。これが民主主義や法治主義の弊害であるともいえる一方、
不注意と無価値な注意とを人々に植え付ける方向性は、犯罪聖書にすらあらかじめ備わっていた
ようなので、近代以降に極度に問題化してしまっている人間規範の是正は、民主主義のような
近代的理念以前にまで、その問題の根本性を突き詰めていく必要があるようである。
「寝るに尸せず。居るに容せず」
「(孔先生は)寝るときも死体のような無様な寝方はされなかった。一方で、
家などで燕居している時にまで無闇に威儀を正したりはせず、ゆったりとしておられた。
(就寝中には就寝中なりの正し方があるし、覚醒中にも覚醒中なりの休み方がある)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・郷党第十・一八より)
「親始めて死するときは、〜夫れ悲哀中に在り、故に形外に変わるなり。
痛疾心に在り、故に口は味わいを甘しとせず、身美に安んじざるなり」
「親が始めて死んだともなれば、その悲哀は内より溢れ出て、外貌すらをも
変容させてしまう。痛疾が心に深く止まっているために、口もよくものを
味わうことができず、身も決して美を楽しんだりすることができない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・問喪第三十五より)
痛疾心に在り、故に口は味わいを甘しとせず、身美に安んじざるなり」
「親が始めて死んだともなれば、その悲哀は内より溢れ出て、外貌すらをも
変容させてしまう。痛疾が心に深く止まっているために、口もよくものを
味わうことができず、身も決して美を楽しんだりすることができない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・問喪第三十五より)
昔の儒礼のように、孝子が親の喪に絶食級の悲しみを抱いて、
泣き通して乞食のごとくやせ衰えて、一時的には杖すら突くように
なったとして、当然それをいつしか喜びに換えたりするわけでもない。
親の喪のごとき悲しみは、春夏秋冬のうちの冬のようなもので、
人間生活のうちでは辛い時期でありながらも、春の息吹を
返させるために、原理的に欠くべからざるものともなっている。
親族の喪なども大して重視しない現代社会で、悲しみなんてのは、
ハッピーエンドで終わるドラマの途中経過としてぐらいしか許容されない。
それ以上の悲しみは全て排斥の対象とされて、出来る限り常日ごろから
嬉しがっていられたらそれに越したことはないとされている。
悲しみと楽しみでは、むしろ悲しむことのほうを優先すべきですらある。
常日ごろから満腹状態であいるよりは、多少腹をすかした状態でものを食べるほうが
おいしいく感じられるのとも同じように、悲しむべきことを十分に悲しむ心がけが
あって後に初めて、楽しむべき物事を十分に楽しむこともまたできるようになる。
儒礼では上記のように親の喪に悲しみを尽くすことなどを推奨しているし、
仏法も諸行無常や一切皆苦などという、悲しみの至りでありながらも絶対的である真理を
よくわきまえた先にこそある、泥沼の中のハスの花のごとき悟りを重視しているのである。
泣き通して乞食のごとくやせ衰えて、一時的には杖すら突くように
なったとして、当然それをいつしか喜びに換えたりするわけでもない。
親の喪のごとき悲しみは、春夏秋冬のうちの冬のようなもので、
人間生活のうちでは辛い時期でありながらも、春の息吹を
返させるために、原理的に欠くべからざるものともなっている。
親族の喪なども大して重視しない現代社会で、悲しみなんてのは、
ハッピーエンドで終わるドラマの途中経過としてぐらいしか許容されない。
それ以上の悲しみは全て排斥の対象とされて、出来る限り常日ごろから
嬉しがっていられたらそれに越したことはないとされている。
悲しみと楽しみでは、むしろ悲しむことのほうを優先すべきですらある。
常日ごろから満腹状態であいるよりは、多少腹をすかした状態でものを食べるほうが
おいしいく感じられるのとも同じように、悲しむべきことを十分に悲しむ心がけが
あって後に初めて、楽しむべき物事を十分に楽しむこともまたできるようになる。
儒礼では上記のように親の喪に悲しみを尽くすことなどを推奨しているし、
仏法も諸行無常や一切皆苦などという、悲しみの至りでありながらも絶対的である真理を
よくわきまえた先にこそある、泥沼の中のハスの花のごとき悟りを重視しているのである。
悲しみが楽しみに変わるのではなく、総体として悲しみの多い人生がより楽しみを楽しむ。
もちろん悲しみ通しなどではなく、悲しむべきものを悲しむことで、楽しむべきものをより楽しむ。
たとえば、道義を貫いたがための貧賤などは決して悲しむべきものではないから悲しまない、
一方で、道義を貫くことが貧窮に繋がってしまうような乱れた世情はよく悲しんで、
その世情を自力他力の精進によって改善していけた場合に、自分一身の富貴ばかりを
楽しもうとする小人などが決して与ることのない、無上の楽しみを得たりもする。
悲しむべきを楽しみ、楽しむべきを悲しもうとする転倒夢想はえてして、
総体として悲しむ分量を減らす。この世には実際、悲しむべきもののほうが
楽しむべきものよりも随分と多いから、両者を転倒させれば、楽しむべき
もののほうが悲しむべきものよりも遥かに多いことになってしまう。
悲しむべきものは決して楽しもうともしたりせずに、よく悲しんで、それからいざ
楽しむべきものを目の当たりにしたときに、初めてそこで楽しむようにする分別を付ける。
そしたら人間が生きていく限りにおいて、最も楽しい楽しみを楽しめるようになる。
人間の楽しみは鬼畜の悲しみ、鬼畜の楽しみは人間の悲しみであったりするものなので、
自分が鬼畜ではない人間であるように心がければ、自然と最高の楽しみにも与れるようになる。
もちろん悲しみ通しなどではなく、悲しむべきものを悲しむことで、楽しむべきものをより楽しむ。
たとえば、道義を貫いたがための貧賤などは決して悲しむべきものではないから悲しまない、
一方で、道義を貫くことが貧窮に繋がってしまうような乱れた世情はよく悲しんで、
その世情を自力他力の精進によって改善していけた場合に、自分一身の富貴ばかりを
楽しもうとする小人などが決して与ることのない、無上の楽しみを得たりもする。
悲しむべきを楽しみ、楽しむべきを悲しもうとする転倒夢想はえてして、
総体として悲しむ分量を減らす。この世には実際、悲しむべきもののほうが
楽しむべきものよりも随分と多いから、両者を転倒させれば、楽しむべき
もののほうが悲しむべきものよりも遥かに多いことになってしまう。
悲しむべきものは決して楽しもうともしたりせずに、よく悲しんで、それからいざ
楽しむべきものを目の当たりにしたときに、初めてそこで楽しむようにする分別を付ける。
そしたら人間が生きていく限りにおいて、最も楽しい楽しみを楽しめるようになる。
人間の楽しみは鬼畜の悲しみ、鬼畜の楽しみは人間の悲しみであったりするものなので、
自分が鬼畜ではない人間であるように心がければ、自然と最高の楽しみにも与れるようになる。
「其の労すべきを択びて之れを労す、又た誰をか怨みん」
「自分から労苦すべきものを選んで労苦しているのだから、どうして誰かを怨んだりすることがあろう。
(自分で選んだわけでもない使役に労苦させたりしたなら、怨みを恐れなければならなくもなる。
四書五経には『労苦を厭うな』という意味の金言も多いが、それも自主的な労苦についてのことだからだ)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・堯曰第二十・四より)
「自分から労苦すべきものを選んで労苦しているのだから、どうして誰かを怨んだりすることがあろう。
(自分で選んだわけでもない使役に労苦させたりしたなら、怨みを恐れなければならなくもなる。
四書五経には『労苦を厭うな』という意味の金言も多いが、それも自主的な労苦についてのことだからだ)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・堯曰第二十・四より)
行為能力制限、いわゆる禁治産は、近代になってからイギリスなどで提唱されたものだが、
昔の封建社会の庶民には政治的権限はなく、奴隷には商行為の権限すらなかったわけで、
古来から人類は、禁治産と同等の意味を持つ階級差別を行ってきていることが分かる。
その階級差別が民主主義や自由主義によって撤廃されて、誰でも望みすらすれば
最大級の行為能力を活用できる体裁をあてがわれるようになった。実際には、最大級の
政治的経済的権限を掌握することに対して暗黙裡の制限がかけられていたりもするが、
(各国主要銀行の不正な金利公表値の操作などにも、融資対象を選別する意図があった)
体裁だけでも、誰しもが無制限の行為能力活用の権限を与えられたことによって、
封建制や奴隷制が敷かれていた頃にはなかったような問題を多く来たすようにもなった。
そのような問題のうちでも最大級に当たるのが、人口爆発である。
自分の血統を家系として責任を持って繋いでいく覚悟もないような人間にまで、
無制限に稼いではやりたい放題でいる権限を与えてしまったせいで、総体としての
人口も爆発した。帝王将軍や大名諸侯などの支配者こそが責任ある家系の保ち方を体現して、
行為能力面で士人以下とされた民間人などにもそのあり方を見習わせていったりしたなら、
それなりの人口調節も可能となるが、行為能力の面で、責任能力のある人間もない人間も
横並びにさせられたような状態では、そのような手段に基づく人口調節もできなくなるからだ。
今また、かつての階級差別をそのまま復活させるというのでは、大きな反発も免れられない。
かといって、このまま誰しもの無制限な行為能力活用などを容認し続けていたなら、
人口爆発による世界の破滅までもが免れられなくなる。だから両者の中間を取って、
民事法的な基準に即した禁治産処理を実施していくというのも、一つの手だとはいえる。
昔の封建社会の庶民には政治的権限はなく、奴隷には商行為の権限すらなかったわけで、
古来から人類は、禁治産と同等の意味を持つ階級差別を行ってきていることが分かる。
その階級差別が民主主義や自由主義によって撤廃されて、誰でも望みすらすれば
最大級の行為能力を活用できる体裁をあてがわれるようになった。実際には、最大級の
政治的経済的権限を掌握することに対して暗黙裡の制限がかけられていたりもするが、
(各国主要銀行の不正な金利公表値の操作などにも、融資対象を選別する意図があった)
体裁だけでも、誰しもが無制限の行為能力活用の権限を与えられたことによって、
封建制や奴隷制が敷かれていた頃にはなかったような問題を多く来たすようにもなった。
そのような問題のうちでも最大級に当たるのが、人口爆発である。
自分の血統を家系として責任を持って繋いでいく覚悟もないような人間にまで、
無制限に稼いではやりたい放題でいる権限を与えてしまったせいで、総体としての
人口も爆発した。帝王将軍や大名諸侯などの支配者こそが責任ある家系の保ち方を体現して、
行為能力面で士人以下とされた民間人などにもそのあり方を見習わせていったりしたなら、
それなりの人口調節も可能となるが、行為能力の面で、責任能力のある人間もない人間も
横並びにさせられたような状態では、そのような手段に基づく人口調節もできなくなるからだ。
今また、かつての階級差別をそのまま復活させるというのでは、大きな反発も免れられない。
かといって、このまま誰しもの無制限な行為能力活用などを容認し続けていたなら、
人口爆発による世界の破滅までもが免れられなくなる。だから両者の中間を取って、
民事法的な基準に即した禁治産処理を実施していくというのも、一つの手だとはいえる。
ただ、奴隷制や、政財癒着の甚だしい西洋的封建制はともかく、政財の分離こそを目的と
していた東洋的封建制を特定して復活させることは、反発される程のことでもないだろう。
漢帝国ほどにも潔癖を期した東洋的封建支配であれば、君子階級の処罰や、引責目的での
自殺や下野なども相次ぐため、民間からの人材の抜擢も随時行われていくことになるし、
日本の武家社会でも奴隷制が撤廃されていたように、政財の癒着を徹底して排除した
東洋的封建制によってこそ、奴隷制という最悪の階級差別を撤廃できたりもするのだから。
民間人は全て政治的権限を剥奪され、禁治産全般にかけては民事法的な処置があてがわれる。
一方で、為政者のあり方にはかつての東洋的封建制があてがわれ、徹底して責任ある為政を
執り行っていくことが義務付けられていくようにする。それが、現時点での最善策になるといえる。
政治的権限だけでなく、民間での経済的権限すらをも禁治産によって制限される人間は、
実質上はかつての奴隷階級とも同等の処遇に置かれることになるわけだが、それはあくまで
邪教信仰に基づく心神喪失などの已む無き理由があってのこととされる。それが、ただ
頭ごなしに行為能力を奪われていたかつての奴隷などとは違った部分であるといえる。
破滅の回避のために、上記のような措置が敷かれた後の世において、君子階級として
振る舞えることこそは誉れとなり、禁治産にまで甘んじさせられることこそは恥じになる。
陰惨な絶対差別に基づく上流階級の傲慢や下流階級の卑下などはこれからもないようにするが、
それぞれの処遇を受けることが誉れになったり、恥になったりすることはこれからもある。
恥になるような処遇をできる限り脱却して、誉れとなるような処遇にこそ与っていこうと
誰しもが志して、世の中総出を挙げての向上が嗜まれていくほうが、よりよいからだ。
していた東洋的封建制を特定して復活させることは、反発される程のことでもないだろう。
漢帝国ほどにも潔癖を期した東洋的封建支配であれば、君子階級の処罰や、引責目的での
自殺や下野なども相次ぐため、民間からの人材の抜擢も随時行われていくことになるし、
日本の武家社会でも奴隷制が撤廃されていたように、政財の癒着を徹底して排除した
東洋的封建制によってこそ、奴隷制という最悪の階級差別を撤廃できたりもするのだから。
民間人は全て政治的権限を剥奪され、禁治産全般にかけては民事法的な処置があてがわれる。
一方で、為政者のあり方にはかつての東洋的封建制があてがわれ、徹底して責任ある為政を
執り行っていくことが義務付けられていくようにする。それが、現時点での最善策になるといえる。
政治的権限だけでなく、民間での経済的権限すらをも禁治産によって制限される人間は、
実質上はかつての奴隷階級とも同等の処遇に置かれることになるわけだが、それはあくまで
邪教信仰に基づく心神喪失などの已む無き理由があってのこととされる。それが、ただ
頭ごなしに行為能力を奪われていたかつての奴隷などとは違った部分であるといえる。
破滅の回避のために、上記のような措置が敷かれた後の世において、君子階級として
振る舞えることこそは誉れとなり、禁治産にまで甘んじさせられることこそは恥じになる。
陰惨な絶対差別に基づく上流階級の傲慢や下流階級の卑下などはこれからもないようにするが、
それぞれの処遇を受けることが誉れになったり、恥になったりすることはこれからもある。
恥になるような処遇をできる限り脱却して、誉れとなるような処遇にこそ与っていこうと
誰しもが志して、世の中総出を挙げての向上が嗜まれていくほうが、よりよいからだ。
「言未だ之れに及ばずして言う、之れを躁と謂う。(ここまで既出)
言之れに及びて言わず、之れを隠と謂う。未だ顔色を見ずして言う、之れを瞽と謂う」
「まだ自分が言う番でもないのに勝手にしゃべり出すのは『躁』という過ちである。
自分が言う番になっても何も言おうとしないのは『隠』という過ちである。
相手の顔色も窺わずに一方的にものを言うのは『瞽』という過ちである」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・季氏第十六・六より)
犯罪聖書(新旧約聖書)の信者以前に、犯罪聖書に登場する神や登場人物、
そして犯罪聖書の著者自身が、四書五経が提示する君子としてのあり方を全く満たせず、
逆に小人としてのあり方ばかりに従っている。信者がダメな人間であるのは聖書信仰も
大いに認めていることであって、それは仏門の浄土信仰などとも同じくする所である。
しかし、聖書信仰はその教祖やクリエーターからして全くダメな人間ばかりで、ダメ人間が
ダメ人間を教導するという、どこにも締まりのない体裁でしかないことが特殊なのである。
四書五経が提示する君子像などを、誰しもが体得できたならそれに越したことはないが、
そこまではなかなか覚束ないから、一部の有志が君子としての修養やそれに基づく仕官に
よって小人止まりな衆生を導いていくというのが、儒学でも現実的な所として認められていて、
漢や唐や江戸幕府などの儒学による統治を成功させた社会も、実際にはその程度のものであった。
誰しもが君子である社会とまでいかずとも、一部の君子が多数の小人を教導していく社会を
画策していく程度で、十分に治世は達成できる。一部の君子を養成していくぐらいなら、
中国みたいな環境的に恵まれているわけでもない国ですら何百年と続けていけるというのに、
あまつさえ、中国と比べれば遥かに異民族からの侵略などのリスクも低い地理条件にある
西洋の人間こそは、小人が小人を支配する宗教的政治的体制しか今まで画策してこなかった。
言之れに及びて言わず、之れを隠と謂う。未だ顔色を見ずして言う、之れを瞽と謂う」
「まだ自分が言う番でもないのに勝手にしゃべり出すのは『躁』という過ちである。
自分が言う番になっても何も言おうとしないのは『隠』という過ちである。
相手の顔色も窺わずに一方的にものを言うのは『瞽』という過ちである」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・季氏第十六・六より)
犯罪聖書(新旧約聖書)の信者以前に、犯罪聖書に登場する神や登場人物、
そして犯罪聖書の著者自身が、四書五経が提示する君子としてのあり方を全く満たせず、
逆に小人としてのあり方ばかりに従っている。信者がダメな人間であるのは聖書信仰も
大いに認めていることであって、それは仏門の浄土信仰などとも同じくする所である。
しかし、聖書信仰はその教祖やクリエーターからして全くダメな人間ばかりで、ダメ人間が
ダメ人間を教導するという、どこにも締まりのない体裁でしかないことが特殊なのである。
四書五経が提示する君子像などを、誰しもが体得できたならそれに越したことはないが、
そこまではなかなか覚束ないから、一部の有志が君子としての修養やそれに基づく仕官に
よって小人止まりな衆生を導いていくというのが、儒学でも現実的な所として認められていて、
漢や唐や江戸幕府などの儒学による統治を成功させた社会も、実際にはその程度のものであった。
誰しもが君子である社会とまでいかずとも、一部の君子が多数の小人を教導していく社会を
画策していく程度で、十分に治世は達成できる。一部の君子を養成していくぐらいなら、
中国みたいな環境的に恵まれているわけでもない国ですら何百年と続けていけるというのに、
あまつさえ、中国と比べれば遥かに異民族からの侵略などのリスクも低い地理条件にある
西洋の人間こそは、小人が小人を支配する宗教的政治的体制しか今まで画策してこなかった。
小人が小人を支配する体制しか許されて来なかったから、西洋社会も真の治世には
一瞬たりとも与れず、春秋戦国時代の中国の如き争乱を数千年の永きにわたって続けてきた。
その争乱を永続させるペースと、軍事技術などの発展とが相まって、もはや自分たちの
争乱によって地球人類を滅亡させかねない状態にまで至ってしまった。
まさに、「小人始めありて終わりなし(晋書)」をありのままに
体現したような結末で、そのような結末に至らしめた最たる原因もまた、
「小人の小人による小人のための伝道書」である新旧約聖書の右に出るものはなかったといえる。
西洋人が、西洋人だからといって君子による社会統治を絶対にできないとも限らない。
小人統治を絶対化する聖書信仰などを捨てて、潔く君子統治こそを試みていく方向に切り替えたなら、
長年の異民族支配による荒廃も著しい今の中国人などよりも、先に君子統治を実現すらできるかもしれない。
もちろん今すぐに可能となるということもあり得ず、聖書信仰を捨てて、聖書信仰によってこそ
患ってしまった凶状を十分に拭い去って後に、始めて君子統治も可能になると見込まれる。
もちろん、これからも一切皆小人の体制のままでいて、もはや自分たちでは社会運営もままならないために、
東洋人による委任統治を受けたいというのならそれでもいいわけだが、さすがにそうであり続ける
ことにまでは耐え難い屈辱を抱いて、自分たちでも君子統治を実現していけるように
心がけていくほうが、人間性を尊ぶ東洋人としての立場からも好しとできるものだ。
それでこそ、人間が人間を家畜のように支配する陰惨な時代もまた、終焉を迎えるのだから。
一瞬たりとも与れず、春秋戦国時代の中国の如き争乱を数千年の永きにわたって続けてきた。
その争乱を永続させるペースと、軍事技術などの発展とが相まって、もはや自分たちの
争乱によって地球人類を滅亡させかねない状態にまで至ってしまった。
まさに、「小人始めありて終わりなし(晋書)」をありのままに
体現したような結末で、そのような結末に至らしめた最たる原因もまた、
「小人の小人による小人のための伝道書」である新旧約聖書の右に出るものはなかったといえる。
西洋人が、西洋人だからといって君子による社会統治を絶対にできないとも限らない。
小人統治を絶対化する聖書信仰などを捨てて、潔く君子統治こそを試みていく方向に切り替えたなら、
長年の異民族支配による荒廃も著しい今の中国人などよりも、先に君子統治を実現すらできるかもしれない。
もちろん今すぐに可能となるということもあり得ず、聖書信仰を捨てて、聖書信仰によってこそ
患ってしまった凶状を十分に拭い去って後に、始めて君子統治も可能になると見込まれる。
もちろん、これからも一切皆小人の体制のままでいて、もはや自分たちでは社会運営もままならないために、
東洋人による委任統治を受けたいというのならそれでもいいわけだが、さすがにそうであり続ける
ことにまでは耐え難い屈辱を抱いて、自分たちでも君子統治を実現していけるように
心がけていくほうが、人間性を尊ぶ東洋人としての立場からも好しとできるものだ。
それでこそ、人間が人間を家畜のように支配する陰惨な時代もまた、終焉を迎えるのだから。
罪業の無制限な拡大と共なる聖書圏の維持が、人類の滅亡に直結するようになる前には、
聖書信仰こそが信者たちにとっても、本当に「確かな拠り所」であったに違いない。
聖書信仰こそが信者たちにとっても、本当に「確かな拠り所」であったに違いない。
ルネサンス以降、西洋でも聖書信仰の酩酊ばかりに耽っていることは少しずつ目減りし、
産業革命以降はもはや宗教信仰のほうが下火となった。それでも西洋人にとっての
一番の心の拠り所としての聖書信仰は健在であったが、英蘭などによる植民地支配の激化、
米ペリー艦隊の地球の裏側(日本)への到達などで、西洋人の世界的覇権が良くも悪しくも
飽和点に達した。聖書信仰こそを根本的な拠り所としての、覇権の拡大が強制的に終結し、
地球という限られた世界の範囲内での暴慢の拡大という、いつかは破裂する風船の膨張の
如き危険な時代を歩み始めることとなった。それをいち早く察知したのが哲学者のニーチェで、
「神は死んだ」という宣言によってこそ、信仰の酩酊を原動力とした西洋人の無制限な
暴慢の拡大に歯止めをかけようともしたが、麻薬的酩酊を伴う聖書信仰を剥奪されることが
西洋人にとっては麻酔切れの如き苦痛を伴うことだから、結局うまくいくこともなく、
ニーチェ自身もニヒリズムにやられて発狂するなど、新たな問題を来たすばかりのこととなった。
聖書信仰は、信者の「依存症」を深刻化させる。何に対する依存といわず、とにかく何ものかに
依存しておこうとする依存症一般が人一倍深刻なものとなる。そこまで信者や学生の依存症を
深刻化させる宗教や学問も多くはなく、他力信仰の浄土教ですらもが、信者の信仰依存を
抑制させるような働きを持ち合わせている。聖書信仰によって患った強度の信仰依存を
他の宗教や学問で埋め合わせるというのも得策ではないし、薬物による緩和ケアなども
なおさら推奨できるものではないといえる。麻薬中毒患者が一旦は閉鎖病棟などに隔離されて、
薬切れによる極度の苦痛と引き換えの依存症からの脱却を試みる。そのような措置が成功して後に、
元聖書信者に対して低依存性の「確かな拠り所」をまたあてがう。聖書信仰がもはや誰にとっての
「確かな拠り所」でもあり得なくなってしまっている一方で、これからも「確かな拠り所」とするに
値する思想哲学宗教などはいくらでもある。ただ、それらは聖書信仰と比べれば依存性が遥かに低いから、
依存症を克服して後の元聖書信者にこそあてがっていくようにしなければならないのである。
産業革命以降はもはや宗教信仰のほうが下火となった。それでも西洋人にとっての
一番の心の拠り所としての聖書信仰は健在であったが、英蘭などによる植民地支配の激化、
米ペリー艦隊の地球の裏側(日本)への到達などで、西洋人の世界的覇権が良くも悪しくも
飽和点に達した。聖書信仰こそを根本的な拠り所としての、覇権の拡大が強制的に終結し、
地球という限られた世界の範囲内での暴慢の拡大という、いつかは破裂する風船の膨張の
如き危険な時代を歩み始めることとなった。それをいち早く察知したのが哲学者のニーチェで、
「神は死んだ」という宣言によってこそ、信仰の酩酊を原動力とした西洋人の無制限な
暴慢の拡大に歯止めをかけようともしたが、麻薬的酩酊を伴う聖書信仰を剥奪されることが
西洋人にとっては麻酔切れの如き苦痛を伴うことだから、結局うまくいくこともなく、
ニーチェ自身もニヒリズムにやられて発狂するなど、新たな問題を来たすばかりのこととなった。
聖書信仰は、信者の「依存症」を深刻化させる。何に対する依存といわず、とにかく何ものかに
依存しておこうとする依存症一般が人一倍深刻なものとなる。そこまで信者や学生の依存症を
深刻化させる宗教や学問も多くはなく、他力信仰の浄土教ですらもが、信者の信仰依存を
抑制させるような働きを持ち合わせている。聖書信仰によって患った強度の信仰依存を
他の宗教や学問で埋め合わせるというのも得策ではないし、薬物による緩和ケアなども
なおさら推奨できるものではないといえる。麻薬中毒患者が一旦は閉鎖病棟などに隔離されて、
薬切れによる極度の苦痛と引き換えの依存症からの脱却を試みる。そのような措置が成功して後に、
元聖書信者に対して低依存性の「確かな拠り所」をまたあてがう。聖書信仰がもはや誰にとっての
「確かな拠り所」でもあり得なくなってしまっている一方で、これからも「確かな拠り所」とするに
値する思想哲学宗教などはいくらでもある。ただ、それらは聖書信仰と比べれば依存性が遥かに低いから、
依存症を克服して後の元聖書信者にこそあてがっていくようにしなければならないのである。
人間にとって、聖書信仰よりも遥かに磐石な拠り所となるものはいくらでもある。ただ、
それらはほぼ全て聖書信仰よりも依存性が低い。依存性が低いものだから、未だ聖書信仰の
酩酊のさ中にあるような人間には拠り所として脆弱であるようにすら思われる。それは自らの
依存症が深刻であり過ぎるがための自業自得の偏見に過ぎないのであり、依存症すら克服できたなら、
「不退転」ということにかけて紛れもなく聖書信仰以上たり得るものはいくらでもあるのだ。
拠り所を何も持たずにいられるほど強い人間がそんなに多くないことは、純粋な哲理教学
としては世界でも最優等である仏教ですらもが認めている所である。だから仏門にも他力本願の
浄土門があるが、同時にその浄土門までもが、依存症を軽減していく方向性を備えてもいる。
依存を皆無にまではなかなかできないが、なるべく減らしていくようにするというのが、
全ての人間にとっても健全なあり方となるのであり、それでも残存してしまう依存癖を決して
誇ったりもせず、むしろ恥じるぐらいのことが、女子供を含む全ての人類に守られていくように
なるのが適当である。そしてそれは、今という時代にはもはや必須なことともなっている。
「三日斎して、一日之れを用うるも、猶お敬わざるを恐る」
「たった一日の祭事のために三日間の斎戒沐浴を尽くしたとしても、まだ敬いが足りてはいないかと恐れる。
(君子が薄氷を踏むように物事を恐れ慎みながら為す姿の一例)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・郊特牲第十一より)
それらはほぼ全て聖書信仰よりも依存性が低い。依存性が低いものだから、未だ聖書信仰の
酩酊のさ中にあるような人間には拠り所として脆弱であるようにすら思われる。それは自らの
依存症が深刻であり過ぎるがための自業自得の偏見に過ぎないのであり、依存症すら克服できたなら、
「不退転」ということにかけて紛れもなく聖書信仰以上たり得るものはいくらでもあるのだ。
拠り所を何も持たずにいられるほど強い人間がそんなに多くないことは、純粋な哲理教学
としては世界でも最優等である仏教ですらもが認めている所である。だから仏門にも他力本願の
浄土門があるが、同時にその浄土門までもが、依存症を軽減していく方向性を備えてもいる。
依存を皆無にまではなかなかできないが、なるべく減らしていくようにするというのが、
全ての人間にとっても健全なあり方となるのであり、それでも残存してしまう依存癖を決して
誇ったりもせず、むしろ恥じるぐらいのことが、女子供を含む全ての人類に守られていくように
なるのが適当である。そしてそれは、今という時代にはもはや必須なことともなっている。
「三日斎して、一日之れを用うるも、猶お敬わざるを恐る」
「たった一日の祭事のために三日間の斎戒沐浴を尽くしたとしても、まだ敬いが足りてはいないかと恐れる。
(君子が薄氷を踏むように物事を恐れ慎みながら為す姿の一例)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・郊特牲第十一より)
「春秋左氏伝」僖公十九年の、「人間を生贄に用いたりしてはならない」
という意味の発言の引用がこの聖書スレでの初めての真正聖書からの引用だった。
「イエスは人間であると同時に神の子だった。だから生贄にされても構わない」
だとしたら、神の子こそは人間以下の畜生同然の存在でしかなかったことになる。
実際には、イエスの「神の子(キリスト)」という自称は、自らが妾腹の私生児で
あることを開き直っての皮肉的な自称であったわけだが、じゃあ妾腹の私生児であれば
畜生も同然の存在として生贄にされても構いやしないのかといえば、決してそんなこともない。
妾腹の私生児といえども、孔子のような大学者や一休宗純のような名僧、長谷川平蔵のような
花形の武士として大成できる可能性もあるわけだから、ただ妾腹の私生児であるというだけの
理由で、頭ごなしに畜生並みの扱いを受けたりするのであれば、それはそのような処遇を
講じようとする世の中のほうが倫理的に間違っていると見なす他はないのである。
では、自らが妾腹の私生児であることにコンプレックスを抱いて、それを発散するために
自分を神の子だなどと触れ回ったりする、過ちを犯した妾腹の私生児の場合はどうかといえば、
これは確かに、人間以下の畜生並みの存在としてすら扱いたい気持ちにもなりかねない所がある。
しかし、それでも自分の側にまともな神経が備わっているのならば、そのような「かわいそうな人」
を哀れんで、丁重に禁治産などの保護措置を施してやるようにすべきである。もしも自分たちが
それを怠って、畜生並みと断定した妾腹の私生児を、冤罪事件のカモにして社会的動乱を勃発
させるようなことをしたとしたなら、それはそうした人々の側にも大きな罪があるといえる。
という意味の発言の引用がこの聖書スレでの初めての真正聖書からの引用だった。
「イエスは人間であると同時に神の子だった。だから生贄にされても構わない」
だとしたら、神の子こそは人間以下の畜生同然の存在でしかなかったことになる。
実際には、イエスの「神の子(キリスト)」という自称は、自らが妾腹の私生児で
あることを開き直っての皮肉的な自称であったわけだが、じゃあ妾腹の私生児であれば
畜生も同然の存在として生贄にされても構いやしないのかといえば、決してそんなこともない。
妾腹の私生児といえども、孔子のような大学者や一休宗純のような名僧、長谷川平蔵のような
花形の武士として大成できる可能性もあるわけだから、ただ妾腹の私生児であるというだけの
理由で、頭ごなしに畜生並みの扱いを受けたりするのであれば、それはそのような処遇を
講じようとする世の中のほうが倫理的に間違っていると見なす他はないのである。
では、自らが妾腹の私生児であることにコンプレックスを抱いて、それを発散するために
自分を神の子だなどと触れ回ったりする、過ちを犯した妾腹の私生児の場合はどうかといえば、
これは確かに、人間以下の畜生並みの存在としてすら扱いたい気持ちにもなりかねない所がある。
しかし、それでも自分の側にまともな神経が備わっているのならば、そのような「かわいそうな人」
を哀れんで、丁重に禁治産などの保護措置を施してやるようにすべきである。もしも自分たちが
それを怠って、畜生並みと断定した妾腹の私生児を、冤罪事件のカモにして社会的動乱を勃発
させるようなことをしたとしたなら、それはそうした人々の側にも大きな罪があるといえる。
総督ピラトがイエスを磔刑に処すとき、群集もまた「そいつを十字架にかけろ」とこぞって
豪語していた。ピラトもその怒声に圧される形で、罪状も不明確なイエスを磔刑で殺した。
妖言乱行の過ちを犯した、至らない妾腹の私生児を、だからといって畜生並みの存在と断定して、
生贄にするが如き過剰処刑に服させた。イエス本人すらもがそれを欲していたようではあるが、
明らかにイエスだけでなく、当時のイスラエルやローマ全体が、特定の人間を畜生以下の存在と
見なして憚らぬ不徳さで覆い尽くされていたといえ、だからこそ、人間をいけにえとして十字架に
かけるような過ちが犯されながらも、誰一人としてそれを糾弾することすらしないでいたのである。
春秋時代の中国でも、捕虜となった軍人が生贄に用いられるなどの事例が何度かあったようだが、
同時に僖公十九年にそれを適格に糾弾した司馬子魚のように、人間を生贄にすることが不徳の
至りとなることを冷静に見抜いているものもいた。だからイエスのような蒙昧状態の妾腹の
私生児が現れた所で、それを生贄にしようなどとすることが社会的に許されるはずもなかった。
イエスが愚かな妾腹の私生児だからといって、本人を生贄にまで処したのは、当時のイスラエル人
やローマ人の罪でもあったのであり、イエスが心神喪失者であるが故に無罪であるというのなら、
イスラエル人やローマ人全体が代わりにその罪を負って行かねばならないとすら言えるのである。
「唯だ天下の至聖、〜凡そ血気有る者の尊親せざる莫し」
「天下でも飛び切りの聖人こそは、血肉ある人々のうちでも尊び親しまざる者がない。
(むしろ仰ぎ見る人々の側こそが血肉を尽くして、天下の至聖を尊親するのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——中庸・三一より)
豪語していた。ピラトもその怒声に圧される形で、罪状も不明確なイエスを磔刑で殺した。
妖言乱行の過ちを犯した、至らない妾腹の私生児を、だからといって畜生並みの存在と断定して、
生贄にするが如き過剰処刑に服させた。イエス本人すらもがそれを欲していたようではあるが、
明らかにイエスだけでなく、当時のイスラエルやローマ全体が、特定の人間を畜生以下の存在と
見なして憚らぬ不徳さで覆い尽くされていたといえ、だからこそ、人間をいけにえとして十字架に
かけるような過ちが犯されながらも、誰一人としてそれを糾弾することすらしないでいたのである。
春秋時代の中国でも、捕虜となった軍人が生贄に用いられるなどの事例が何度かあったようだが、
同時に僖公十九年にそれを適格に糾弾した司馬子魚のように、人間を生贄にすることが不徳の
至りとなることを冷静に見抜いているものもいた。だからイエスのような蒙昧状態の妾腹の
私生児が現れた所で、それを生贄にしようなどとすることが社会的に許されるはずもなかった。
イエスが愚かな妾腹の私生児だからといって、本人を生贄にまで処したのは、当時のイスラエル人
やローマ人の罪でもあったのであり、イエスが心神喪失者であるが故に無罪であるというのなら、
イスラエル人やローマ人全体が代わりにその罪を負って行かねばならないとすら言えるのである。
「唯だ天下の至聖、〜凡そ血気有る者の尊親せざる莫し」
「天下でも飛び切りの聖人こそは、血肉ある人々のうちでも尊び親しまざる者がない。
(むしろ仰ぎ見る人々の側こそが血肉を尽くして、天下の至聖を尊親するのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——中庸・三一より)
真っ当な神仏を尊崇する人間は、「立派な人間」という意味での君子になり、
邪まな神にすがろうとする人間は、「つまらない人間」という意味での小人になる。
君子たることを社会的に落とし込めば聖王や賢臣となり、長寿繁栄にも与れる一方で、
小人であることを落とし込めば悪徳商人や死兵となり、短命や破滅にも追い込まれる。
四書五経では、祖霊を祭ることを重んじる人間が君子、軽んじる人間が小人程度の
判別があるだけで、小人が邪神にすがることで己の性向を強化するようなことまでは
提示されていない。当時まだ、世界最悪の邪神信仰である聖書信仰もなかったわけだから、
そんな物事をわざわざあげつらわなかったのも当然のことだが、たとえば殷の紂王が
愛妾妲己に溺れて遊興に耽りすぎて国を滅ぼしたり、周の幽王がこれまた愛妾の褒姒に
心を惑わされて、諸侯からの信頼を失って王権を失ったりといったことはすでにあった。
邪神にすがって己の品性を下落させることも、男が女色に溺れてダメになるのと
似たようなもので、問題なのは、決してただ色を好むようにして邪神を信じる
ことではなく、あまりにも一概すぎて他を忘れ去るほどにも色に溺れるようにして、
邪神への信仰に溺れ去ってしまうことである。孔子も魯国に仕官中、上司の季桓子が
斉国から送られて来た女楽団をただ受け入れただけでは見限らなかったが、季桓子が
その舞楽に溺れて三日間も朝廷に顔を出さなかったことには見限りを付け、魯を去ってもいる。
社会人である以上、酒色遊興を拒み通すなんてのも潔癖すぎることで、軽く嗜む程度なら
時に奨励すらされるものである。ただ、それで済むこともなく、完全に溺れきって身を
滅ぼすようなことにもなりかねないもので、酒色がそうであるようにして、邪神信仰もまた
ちょっとかじるぐらいでは済まずに、どこまでも深みにはまっていきやすいものなのである。
邪まな神にすがろうとする人間は、「つまらない人間」という意味での小人になる。
君子たることを社会的に落とし込めば聖王や賢臣となり、長寿繁栄にも与れる一方で、
小人であることを落とし込めば悪徳商人や死兵となり、短命や破滅にも追い込まれる。
四書五経では、祖霊を祭ることを重んじる人間が君子、軽んじる人間が小人程度の
判別があるだけで、小人が邪神にすがることで己の性向を強化するようなことまでは
提示されていない。当時まだ、世界最悪の邪神信仰である聖書信仰もなかったわけだから、
そんな物事をわざわざあげつらわなかったのも当然のことだが、たとえば殷の紂王が
愛妾妲己に溺れて遊興に耽りすぎて国を滅ぼしたり、周の幽王がこれまた愛妾の褒姒に
心を惑わされて、諸侯からの信頼を失って王権を失ったりといったことはすでにあった。
邪神にすがって己の品性を下落させることも、男が女色に溺れてダメになるのと
似たようなもので、問題なのは、決してただ色を好むようにして邪神を信じる
ことではなく、あまりにも一概すぎて他を忘れ去るほどにも色に溺れるようにして、
邪神への信仰に溺れ去ってしまうことである。孔子も魯国に仕官中、上司の季桓子が
斉国から送られて来た女楽団をただ受け入れただけでは見限らなかったが、季桓子が
その舞楽に溺れて三日間も朝廷に顔を出さなかったことには見限りを付け、魯を去ってもいる。
社会人である以上、酒色遊興を拒み通すなんてのも潔癖すぎることで、軽く嗜む程度なら
時に奨励すらされるものである。ただ、それで済むこともなく、完全に溺れきって身を
滅ぼすようなことにもなりかねないもので、酒色がそうであるようにして、邪神信仰もまた
ちょっとかじるぐらいでは済まずに、どこまでも深みにはまっていきやすいものなのである。
邪神信仰を「ちょっと嗜む」なんてことが果たしてできるのかを考えてみるに、
たとえば密教修行での試練の一環などとしては不可能でもなさそうではある。
しかし、あまりにも危険すぎて万人には勧められないし、修行の失敗者が
カルト宗教家としての悪行に走るようなことにもなりかねないといえる。
ユダヤ=キリスト両聖書教もまた、本来はそのような「失敗した密教」だったと
考えられなくもない。別に古代のユダヤ人らが、正統なタントラ教の修行などに
失敗して邪教を生成し始めたとも限らないが、ユダヤ教やキリスト教の宗教
としての存在性は十分、密教の失敗と見なすに値するものとなっている。
ちょっと嗜むことすら憚られるという点では、邪神信仰は酒色以上だともいえる。
最低でも、妻が夫の浮気を怨む程度以上には、邪教信者であることも怨まれて然るべきだ。
邪教信仰を嗜む危険性よりは、酒色を嗜む危険性のほうが遥かに小さいのだから。
「蔽芾たる甘棠、翦る勿れ敗る勿れ、召伯の憩いし所」
「よく生い茂った甘棠の樹を伐るでない、傷つけるでない。かつて周の賢臣召公も、その木蔭で憩われたのだから。
(『生い茂った甘棠の樹』は召公の威徳の暗喩。その威徳の下で召公自身もまた憩うていた。
邪教の神やそれへの邪信などと違い、君子の威徳はそれがありのままに憩いの場なのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・召南・甘棠より)
たとえば密教修行での試練の一環などとしては不可能でもなさそうではある。
しかし、あまりにも危険すぎて万人には勧められないし、修行の失敗者が
カルト宗教家としての悪行に走るようなことにもなりかねないといえる。
ユダヤ=キリスト両聖書教もまた、本来はそのような「失敗した密教」だったと
考えられなくもない。別に古代のユダヤ人らが、正統なタントラ教の修行などに
失敗して邪教を生成し始めたとも限らないが、ユダヤ教やキリスト教の宗教
としての存在性は十分、密教の失敗と見なすに値するものとなっている。
ちょっと嗜むことすら憚られるという点では、邪神信仰は酒色以上だともいえる。
最低でも、妻が夫の浮気を怨む程度以上には、邪教信者であることも怨まれて然るべきだ。
邪教信仰を嗜む危険性よりは、酒色を嗜む危険性のほうが遥かに小さいのだから。
「蔽芾たる甘棠、翦る勿れ敗る勿れ、召伯の憩いし所」
「よく生い茂った甘棠の樹を伐るでない、傷つけるでない。かつて周の賢臣召公も、その木蔭で憩われたのだから。
(『生い茂った甘棠の樹』は召公の威徳の暗喩。その威徳の下で召公自身もまた憩うていた。
邪教の神やそれへの邪信などと違い、君子の威徳はそれがありのままに憩いの場なのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・召南・甘棠より)
「子曰く、吾れ嘗て終日食わず、終夜寝ず。以て思う、益無しと。学ぶに如かざるなり(既出)」
「先生は言われた。『私は昔一日中何も食べず、一晩中寝もしないでいたことがあったが、
今になってみると無駄なことをしたもんだと思う。順序だてて勉強をすることには全く及ばない』」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・衛霊公第十五・三一)
上記のように孔子は言うけれども、もしも飲まず食わずの修練を孔子が可としたなら、
弟子たちはこぞってそのような修練に励んだに違いない。だから陳で糧食を絶たれる危機に遭った折にも、
孔門の弟子たちの多くは飢えをしのぎながら孔子に付き随い続けたのだし、孔子が提示する理想の君子像の
忠実な実践に務めるあまり、無理がたたって夭折してしまった顔淵のような弟子までもがいたのである。
とはいえ、決して孔子の弟子が揃いも揃って精鋭揃いだったのでもなく、子貢のように孔子が反対する
投機で身銭を稼いでいた弟子もいれば、宰我のように文辞は得意でも実践や情緒の伴わない弟子もいた。
そうでありながらも、できる限り孔子の教えを固く守ろうとする弟子たちが相次いだのは、ひとえに孔子自身
の知見や人格の優秀さがあったからで、もしもそれがなかったら、弟子たちも単なる野次馬止まりな連中
ばかりとなり、「しばらく寝ないでおけ」程度の師からの指示すらも守られることはなかったはずなのである。
当初、孔子の学団はただの私塾でしかなかったわけで、社会的な位階からいえばさほどのものでも
なかったわけだが、それでも当時の孔子と弟子たちのやりとりが「論語」や「礼記」などに詳述されて、
2000年以上にわたって研究の対象とされてきた。それは、孔子とその弟子の関係が「理想の師弟関係」
としてこの上ないものでもあったからで、厳しすぎず優しすぎない中庸の保たれたその教育姿勢が、
近世までの日本や中国における教育体制のあり方としても、参考にされ続けてきたからである。
「先生は言われた。『私は昔一日中何も食べず、一晩中寝もしないでいたことがあったが、
今になってみると無駄なことをしたもんだと思う。順序だてて勉強をすることには全く及ばない』」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・衛霊公第十五・三一)
上記のように孔子は言うけれども、もしも飲まず食わずの修練を孔子が可としたなら、
弟子たちはこぞってそのような修練に励んだに違いない。だから陳で糧食を絶たれる危機に遭った折にも、
孔門の弟子たちの多くは飢えをしのぎながら孔子に付き随い続けたのだし、孔子が提示する理想の君子像の
忠実な実践に務めるあまり、無理がたたって夭折してしまった顔淵のような弟子までもがいたのである。
とはいえ、決して孔子の弟子が揃いも揃って精鋭揃いだったのでもなく、子貢のように孔子が反対する
投機で身銭を稼いでいた弟子もいれば、宰我のように文辞は得意でも実践や情緒の伴わない弟子もいた。
そうでありながらも、できる限り孔子の教えを固く守ろうとする弟子たちが相次いだのは、ひとえに孔子自身
の知見や人格の優秀さがあったからで、もしもそれがなかったら、弟子たちも単なる野次馬止まりな連中
ばかりとなり、「しばらく寝ないでおけ」程度の師からの指示すらも守られることはなかったはずなのである。
当初、孔子の学団はただの私塾でしかなかったわけで、社会的な位階からいえばさほどのものでも
なかったわけだが、それでも当時の孔子と弟子たちのやりとりが「論語」や「礼記」などに詳述されて、
2000年以上にわたって研究の対象とされてきた。それは、孔子とその弟子の関係が「理想の師弟関係」
としてこの上ないものでもあったからで、厳しすぎず優しすぎない中庸の保たれたその教育姿勢が、
近世までの日本や中国における教育体制のあり方としても、参考にされ続けてきたからである。
しかるに、今の教育体制はといえば、厳しすぎるか優しすぎるかのいずれかでしかない。
西洋由来のスパルタ教育で徹底的に教え込むか、もしくは生徒のわがままを無条件に受け入れるかの、
アメかムチかの教育でしかあり得ない。孔子とその弟子のような、お互いがどこまでも学究を
研鑽し続けていくもの同士としての、双方向的な教学などはどこにもなく、ただ教師が生徒に対して
一方的に知識を教え込むことだけが全てとされている。生徒が教師に対して口出しできるのは、
せいぜい「その知識は間違っていませんか」程度のところまでで、生徒こそが教師に対して
さらなる知見や人格の向上を促していく余地などは、微塵も存在していないのである。
師弟関係は、「君臣・父子・夫婦・兄弟・朋友」の天下の達道のうちで下から二番目の優先順位に当たり、
上下関係を伴う人間関係としては最低のものともなっている。そのようなわきまえがあればこそ、教師だから
といってヘタに偉ぶったりもせず、生徒の学知すらをも参考にしつつの教学を発展させて行けたりもする。
それ程にも人として真摯な存在であればこそ、教師としての自分に対して生徒たちが誠心誠意随順して
行こうとすらするようになるのであり、それでこそ師から弟子へと仁智が伝承されて行けるのでもある。
「讒諂の民、比黨して之れを危うくする者有れども、身は危うくす可くも、
志しは奪う可からざるなり。起居危うしと雖も、竟に其の志しを信ぶる有り」
「人を裏切り貶めようとする者が、こぞって儒者を危うからしめようとしたところで、
それによって身を危うからしめる程度のことはできても、志しや願いまで奪い去ることはできない。
起居動作に未だ危うい点があった所で、儒者ならば結局は自らの志願を貫き通してしまう。
(身も危うからしめて、願いも聞き入れられない。儒者にすら及ばないというのなら、そういうこともあるだろう)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・儒行第四十一より)
西洋由来のスパルタ教育で徹底的に教え込むか、もしくは生徒のわがままを無条件に受け入れるかの、
アメかムチかの教育でしかあり得ない。孔子とその弟子のような、お互いがどこまでも学究を
研鑽し続けていくもの同士としての、双方向的な教学などはどこにもなく、ただ教師が生徒に対して
一方的に知識を教え込むことだけが全てとされている。生徒が教師に対して口出しできるのは、
せいぜい「その知識は間違っていませんか」程度のところまでで、生徒こそが教師に対して
さらなる知見や人格の向上を促していく余地などは、微塵も存在していないのである。
師弟関係は、「君臣・父子・夫婦・兄弟・朋友」の天下の達道のうちで下から二番目の優先順位に当たり、
上下関係を伴う人間関係としては最低のものともなっている。そのようなわきまえがあればこそ、教師だから
といってヘタに偉ぶったりもせず、生徒の学知すらをも参考にしつつの教学を発展させて行けたりもする。
それ程にも人として真摯な存在であればこそ、教師としての自分に対して生徒たちが誠心誠意随順して
行こうとすらするようになるのであり、それでこそ師から弟子へと仁智が伝承されて行けるのでもある。
「讒諂の民、比黨して之れを危うくする者有れども、身は危うくす可くも、
志しは奪う可からざるなり。起居危うしと雖も、竟に其の志しを信ぶる有り」
「人を裏切り貶めようとする者が、こぞって儒者を危うからしめようとしたところで、
それによって身を危うからしめる程度のことはできても、志しや願いまで奪い去ることはできない。
起居動作に未だ危うい点があった所で、儒者ならば結局は自らの志願を貫き通してしまう。
(身も危うからしめて、願いも聞き入れられない。儒者にすら及ばないというのなら、そういうこともあるだろう)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・儒行第四十一より)
聖書圏における犯罪聖書以外の書物というのは、そのどれもが矮小である。
分量的にも犯罪聖書以下のものがほとんどだし、その内容も一過性の消費物止まりで、
後世にまで伝えていくだけの普遍的な価値を湛えているものなども極めて少ない。
(かろうじて、修辞を養う上で有用なものなどが、古典として残って行ってもいる)
全ての書物は犯罪聖書以下でしかないと思い込み、いつかは犯罪聖書によって全てが
刷新されるために、今生での普遍性の追求などにも大した意味はないとまで思っているから。
犯罪聖書が、質でも量でも古さでも、「最低限度の東洋古典」である四書五経以下なのだから、
その犯罪聖書よりも漏れなく矮小なものとして著された、全ての西洋古典もまた四書五経以下である。
聖書圏は、全般的に「勉学不遇の地」なのである。
犯罪聖書が勉学対象として不適であるだけでなく、その犯罪聖書よりもさらに下等なものとして
書かれた全ての書物までもが、本格的な勉学の対象とするに値しないものであり続けてきたのだから。
聖書圏には、本格的な勉学などが未だかつてあったことはないのである。
正統な道統に即しているわけでもない、我流の学者の我流の知識をかじるぐらいまでが
勉学の全てであって、あたかも儒者が数多の漢籍を体系的に読み込んだり、仏僧が大蔵経を
読み尽くして実践したりするほどもの勉学は、聖書圏においてはあり得たことがないのである。
非聖書圏の東洋人にとっては、洋学知識ばかりを詰め込まされてきたことを反省して、
東洋学などへ回帰することが「勉強のし直し」となるが、聖書圏の西洋人の場合などには
なかなかそうもいかない。東洋学への勉学姿勢を西洋学に落とし込むのは可能な一方で、
西洋学への勉強姿勢を東洋学に落とし込むのは、はなはだ困難なことであるから。
分量的にも犯罪聖書以下のものがほとんどだし、その内容も一過性の消費物止まりで、
後世にまで伝えていくだけの普遍的な価値を湛えているものなども極めて少ない。
(かろうじて、修辞を養う上で有用なものなどが、古典として残って行ってもいる)
全ての書物は犯罪聖書以下でしかないと思い込み、いつかは犯罪聖書によって全てが
刷新されるために、今生での普遍性の追求などにも大した意味はないとまで思っているから。
犯罪聖書が、質でも量でも古さでも、「最低限度の東洋古典」である四書五経以下なのだから、
その犯罪聖書よりも漏れなく矮小なものとして著された、全ての西洋古典もまた四書五経以下である。
聖書圏は、全般的に「勉学不遇の地」なのである。
犯罪聖書が勉学対象として不適であるだけでなく、その犯罪聖書よりもさらに下等なものとして
書かれた全ての書物までもが、本格的な勉学の対象とするに値しないものであり続けてきたのだから。
聖書圏には、本格的な勉学などが未だかつてあったことはないのである。
正統な道統に即しているわけでもない、我流の学者の我流の知識をかじるぐらいまでが
勉学の全てであって、あたかも儒者が数多の漢籍を体系的に読み込んだり、仏僧が大蔵経を
読み尽くして実践したりするほどもの勉学は、聖書圏においてはあり得たことがないのである。
非聖書圏の東洋人にとっては、洋学知識ばかりを詰め込まされてきたことを反省して、
東洋学などへ回帰することが「勉強のし直し」となるが、聖書圏の西洋人の場合などには
なかなかそうもいかない。東洋学への勉学姿勢を西洋学に落とし込むのは可能な一方で、
西洋学への勉強姿勢を東洋学に落とし込むのは、はなはだ困難なことであるから。
聖書信仰は、侵略地に「勉強嫌い」をもたらす。
それも、信仰への酩酊者を増大させると同時に、侵略地に現存する勉学の本格性を
損なわせるからで、本来なら勉学を志せたはずの人間が、環境が聖書信仰下な
ものだから勉学嫌いになってしまったなんてこともいくらでもあったはずである。
孔子の弟子の子路なども蛮勇の徒だったが、その勇気を「智仁勇」の三才として善用できるのが
儒学であればこそ、孔子にも随順できた。もしも子路が聖書圏に生まれていたなら、勇気なんて
野蛮なものでしかないと決め付けるその風潮にも圧されて、きっと勉強嫌いになっていたに違いない。
正当な道統に根ざした本格的な勉学や、その対象となるだけの文書資料などは、聖書圏はおろか、
今の日本でもほとんど巷に出回らないものとなってしまった。東洋古典も抄訳でそのごく一部が
出版されたりするぐらいで、決して体系的な勉学の対象にされるだけの体裁などは整っていない。
聖書信仰を廃絶することは、体系的な学問全般の復興にもつながる。
日本人などにとっては久しぶり、西洋人にとっては初めてとなる、体系的な学問の享受。
勉強嫌いにとっては恐ろしいことのように思われるかもしれないが、決して君が嫌っている
類いの勉学を復興していこうとしているわけではないのだから、安心せられたい。
「天下国家を為むるに〜凡そ事豫めすれば則ち立ち、豫めせざれば則ち廃す。言前に定まれば則ち
跲かず、事前に定まれば則ち困まず、行い前に定まれば則ち疚しからず、道前に定まれば則ち窮せず」
「天下国家を平定するような大業は、かならず前もっての用意が整っている場合にのみ実行に移し、用意が
整っていないようであれば踏み止まる。言うべきことも前もって定まっていればつまずかず、やる事も定まって
いれば苦しむようなこともなく、行いも定まっていれば疚しい所もなく、道筋も定まっていれば窮することもない。
(前もってすべての用意を整えているのだから、始めから苦しんだり疚しがったりすることもないはずである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——中庸・二〇より)
それも、信仰への酩酊者を増大させると同時に、侵略地に現存する勉学の本格性を
損なわせるからで、本来なら勉学を志せたはずの人間が、環境が聖書信仰下な
ものだから勉学嫌いになってしまったなんてこともいくらでもあったはずである。
孔子の弟子の子路なども蛮勇の徒だったが、その勇気を「智仁勇」の三才として善用できるのが
儒学であればこそ、孔子にも随順できた。もしも子路が聖書圏に生まれていたなら、勇気なんて
野蛮なものでしかないと決め付けるその風潮にも圧されて、きっと勉強嫌いになっていたに違いない。
正当な道統に根ざした本格的な勉学や、その対象となるだけの文書資料などは、聖書圏はおろか、
今の日本でもほとんど巷に出回らないものとなってしまった。東洋古典も抄訳でそのごく一部が
出版されたりするぐらいで、決して体系的な勉学の対象にされるだけの体裁などは整っていない。
聖書信仰を廃絶することは、体系的な学問全般の復興にもつながる。
日本人などにとっては久しぶり、西洋人にとっては初めてとなる、体系的な学問の享受。
勉強嫌いにとっては恐ろしいことのように思われるかもしれないが、決して君が嫌っている
類いの勉学を復興していこうとしているわけではないのだから、安心せられたい。
「天下国家を為むるに〜凡そ事豫めすれば則ち立ち、豫めせざれば則ち廃す。言前に定まれば則ち
跲かず、事前に定まれば則ち困まず、行い前に定まれば則ち疚しからず、道前に定まれば則ち窮せず」
「天下国家を平定するような大業は、かならず前もっての用意が整っている場合にのみ実行に移し、用意が
整っていないようであれば踏み止まる。言うべきことも前もって定まっていればつまずかず、やる事も定まって
いれば苦しむようなこともなく、行いも定まっていれば疚しい所もなく、道筋も定まっていれば窮することもない。
(前もってすべての用意を整えているのだから、始めから苦しんだり疚しがったりすることもないはずである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——中庸・二〇より)
 君子道徳が信教とも別物のもの(儒学)として醸成されて来ている極東社会では、
君子道徳が信教とも別物のもの(儒学)として醸成されて来ている極東社会では、 あまり大都市の中心部などに巨大な霊地を拵えたりすることははばかられて来た。
伊勢神宮や出雲大社も田舎である三重や島根に建てられ、比叡山や高野山もその名のとおり、
山岳地帯に造られている。このうちでも、山あいでありながら比較的京都に近い位置にある
比叡山では、昔から僧団の腐敗が重ね重ね問題になって来ていて、宗教施設が大都市の
世俗的権力と癒着することがいかに大きな問題に結びつくかを実証する例ともなっている。
イスラムのように政教一致を完全に開き直るのならまだしも、キリスト教圏は一応、そのほとんどの
国がすでに政教分離を国是として掲げている。にもかかわらず米大統領は聖書に手を置いて宣誓し、
その他の西洋諸国でもキリスト教団勢力を嵩にかかった政治家が政権を得て国家元首となったりしている。
度し難いほどに政教の分離がやりきれないままでいるのも、西洋の社会構造からして、大都市の中心部に
巨大な教会がいくつも林立しているような体たらくだからで、本当に政教を分離させるというのなら、
キリスト教圏の場合は、キリスト教を廃教に追い込むぐらいは必須な実相と化してしまっているからだ。
儒学に相当するような、無宗教的かつ実践的な権力学が西洋にはないものだから、今に至るまで
権力の中枢に宗教勢力がはびこるザマと化してしまっている。近世ごろから相当数の無宗教的な
政治学や社会学を西洋人もこしらえ始めたが、そのほぼ全てが現実性を欠き、共産主義のような高潔な
理想を謳う政治イデオロギーほど、左翼(変革主義)としての節操のなさを来たしてしまってもいる。
だから西洋の場合、保守的な派閥ほど宗教勢力との癒着が甚だしいという事態をも招いているわけで、
保守派こそは儒学のような無宗教的な学問によって為政を取り仕切ることが正当であることからすれば、
まったく事態が転倒しきったままに固着した、複雑骨折の様相を呈してしまっているといえる。
できることなら、西洋諸国の全ての教会を儒学の学校にしてしまう。可能であれば、
それで政教の癒着にかけては万事解決できるといえる。結果、西洋では宗教施設がほぼ皆無になる。
それが心もとないというんだったら、西洋式の神社なりお寺なりを、都市の郊外などに造り直す。
今ある教会を神道や仏教に改宗したからって、それで政教癒着の腐敗が防ぎ止められる
ともいかないのは、上記の比叡山の腐敗例からも分かるとおり。
たとえば、今ある教会が全てモスクにすげ替えられるような、西洋人が最も恐れる形の宗教征服は
なくても済む。一方で、世俗権力から宗教勢力を追っ払うという措置はやはり必要になる。
聖書信仰の酩酊にかられて、世界でも最も劣悪な為政を続けてきた聖書圏にとって、
これからも政教癒着の腐敗を長らえながら存続していけるすべだけはあり得ないのである。
「以て城郭を築き、都邑を建て、竇窖を穿ちて、囷倉を修む可し。
乃ち有司に命じて、民を趣して收斂せしめ、菜を畜うるを務め、積聚を多くせしむ。
乃ち麥を種うるを勧め、或いは時を失うこと毋らしむ。其れ時を失うありては、罪を行うて疑う無かれ」
「城郭を築き、都市を建造して、大穴を穿ってそこを穀倉とするようにする。諸々の役人たちに命じて、
民たちに租税を収めさせ、同時に野菜などの蓄財を多くするように促す。麦類などを植えることも勧めて、
決して命令に違うことがないようにする。命令に従わない場合には有罪であることを疑わぬように。
(都市こそは、封建的な人間の営みの産物なのだから、不埒な幻想の対象としたりすべきでもない)」
(権力道徳聖——通称四書五経——礼記・月令第六より)
それで政教の癒着にかけては万事解決できるといえる。結果、西洋では宗教施設がほぼ皆無になる。
それが心もとないというんだったら、西洋式の神社なりお寺なりを、都市の郊外などに造り直す。
今ある教会を神道や仏教に改宗したからって、それで政教癒着の腐敗が防ぎ止められる
ともいかないのは、上記の比叡山の腐敗例からも分かるとおり。
たとえば、今ある教会が全てモスクにすげ替えられるような、西洋人が最も恐れる形の宗教征服は
なくても済む。一方で、世俗権力から宗教勢力を追っ払うという措置はやはり必要になる。
聖書信仰の酩酊にかられて、世界でも最も劣悪な為政を続けてきた聖書圏にとって、
これからも政教癒着の腐敗を長らえながら存続していけるすべだけはあり得ないのである。
「以て城郭を築き、都邑を建て、竇窖を穿ちて、囷倉を修む可し。
乃ち有司に命じて、民を趣して收斂せしめ、菜を畜うるを務め、積聚を多くせしむ。
乃ち麥を種うるを勧め、或いは時を失うこと毋らしむ。其れ時を失うありては、罪を行うて疑う無かれ」
「城郭を築き、都市を建造して、大穴を穿ってそこを穀倉とするようにする。諸々の役人たちに命じて、
民たちに租税を収めさせ、同時に野菜などの蓄財を多くするように促す。麦類などを植えることも勧めて、
決して命令に違うことがないようにする。命令に従わない場合には有罪であることを疑わぬように。
(都市こそは、封建的な人間の営みの産物なのだから、不埒な幻想の対象としたりすべきでもない)」
(権力道徳聖——通称四書五経——礼記・月令第六より)
仏法を悟った者は、犯罪聖書の神の名の下での救いなどが決してありはしないことをも悟る。
そこまでいかない、仁徳の把捉者でも、犯罪聖書への信仰にすがる界隈が世の中に多大なる害悪を
もたらすという大局的な実情をわきまえて、そんなものにすがらず、すがらせないようにしていく。
真理と道理いずれにおいても、犯罪聖書などにすがらないことを磐石化する名分はいくらでも立てられる。
これはつまり、心の内面と社会性のような外面、両面から聖書信仰の不当性が確立されているということでもある。
心の持ちようのような内面においても、犯罪聖書なんかを信仰するよりはしないほうがマシで、
社会にもたらす害益度のような外面においても、信仰しないほうがマシであることが完全に結論づけられる。
それが可能であるのは、仏教や儒学による真理学や権力道徳学の体系化が蓄えられてきたからで、
仏教や儒学が既存していればこそ、聖書信仰の全くの有害無益さもまた明らかになったのだといえる。
全くの有害無益にもかかわらず、犯罪聖書や聖書信仰がこの世に生じてしまったのは、地球全体としては
極西の小部落社会にあたる、欧米やイスラエルにまで仏法や仁徳の教化が覚束ないでいたからで、
それらの部落社会の人々が聖書圏外の文化としての仏教や儒学を具体的に察知することができるように
なったのも、自分たち自身が大航海時代などを通じて、外界への進出を試みるようになってからだった。
いくら全くの有害無益とはいえ、そうであることを実証してくれる確たる体系にも与れないで
いた限りにおいて、聖書信仰を続けてしまったことは、やはり過失として扱うことができる。
近世に四書五経の一部などが西洋に輸入されて、シノワズリなどの中国文化の流行があって後にも、
まだ四書五経と犯罪聖書の記述の相反性にまでは察知が及ばず、犯罪聖書が四書五経と比べれば
質でも量でも古さでも全ての面において劣る有害無益の書であることが把握できなかったとしたなら、
その時点でもまだ、西洋人が聖書信仰に基づいて悪逆非道を続けることに過失性が伴っていたことになる。
そこまでいかない、仁徳の把捉者でも、犯罪聖書への信仰にすがる界隈が世の中に多大なる害悪を
もたらすという大局的な実情をわきまえて、そんなものにすがらず、すがらせないようにしていく。
真理と道理いずれにおいても、犯罪聖書などにすがらないことを磐石化する名分はいくらでも立てられる。
これはつまり、心の内面と社会性のような外面、両面から聖書信仰の不当性が確立されているということでもある。
心の持ちようのような内面においても、犯罪聖書なんかを信仰するよりはしないほうがマシで、
社会にもたらす害益度のような外面においても、信仰しないほうがマシであることが完全に結論づけられる。
それが可能であるのは、仏教や儒学による真理学や権力道徳学の体系化が蓄えられてきたからで、
仏教や儒学が既存していればこそ、聖書信仰の全くの有害無益さもまた明らかになったのだといえる。
全くの有害無益にもかかわらず、犯罪聖書や聖書信仰がこの世に生じてしまったのは、地球全体としては
極西の小部落社会にあたる、欧米やイスラエルにまで仏法や仁徳の教化が覚束ないでいたからで、
それらの部落社会の人々が聖書圏外の文化としての仏教や儒学を具体的に察知することができるように
なったのも、自分たち自身が大航海時代などを通じて、外界への進出を試みるようになってからだった。
いくら全くの有害無益とはいえ、そうであることを実証してくれる確たる体系にも与れないで
いた限りにおいて、聖書信仰を続けてしまったことは、やはり過失として扱うことができる。
近世に四書五経の一部などが西洋に輸入されて、シノワズリなどの中国文化の流行があって後にも、
まだ四書五経と犯罪聖書の記述の相反性にまでは察知が及ばず、犯罪聖書が四書五経と比べれば
質でも量でも古さでも全ての面において劣る有害無益の書であることが把握できなかったとしたなら、
その時点でもまだ、西洋人が聖書信仰に基づいて悪逆非道を続けることに過失性が伴っていたことになる。
当時すでに、中国も元や金や清といった異民族国家による支配が相次ぎ、中国国内での仁徳統治も
相当に疎かになっていた。いくら四書五経に優れた記述が多いとはいえ、原産地の中国がろくにその
実践も覚束ないでいたというのでは、四書五経の実践可能性が未だ疑われたままでいたとしても仕方がない。
四書五経が実際に世界レベルでの実用も可能であることを実証しているのは、漢代や唐代における
中華帝国の成功であり、それはもはや1000年以上もまえのことである。それでも当時の
儒学統治が類いまれな成功を果たしていたことが分かるのは、漢書や唐書のような正史書における
当時の治世の綿密な記録と、その記録に即した史跡の残存や発掘などがあるからである。
儒学というよりは、武士道による統治という印象が強い日本の江戸時代における泰平統治なども、
実際には武力が行使されたりすることは極めてまれで、概ねは儒学や朱子学を根幹とした文治を
旨としていたことが、すでに倒幕の熱も冷めきった今になってこそ、冷静に見極められつつもある。
今やっと、世界規模での儒学や仏教による統治を復興してく目処が立った。
そうしなければ西洋人までもが、過失ではない確信犯としての罪を負わされることに
なるだけの文化研究上の素地が整ったから。今までの聖書信仰者の罪は過失として扱われる一方で、
これからは決して、聖書信仰に基づく罪業の拡大が許されないようにもなったから。
これが「時宜」というもので、「中庸」二十章でも「義とは(時)宜なり」と、語呂合わせでその道義性を諾っている。
時宜に即せなかったがために大罪を犯し続けて来てしまった聖書信仰者のあり方にも、逆説的な道義性を見るのである。
「道に志し、徳に拠り、仁に依り、芸に遊ぶ」
「(訳は不要だろう。権力道徳者にとって、仁徳は目指すだけでなく、依り頼むものですらある)」
(権力道徳性——通称四書五経——論語・述而第七・六より)
相当に疎かになっていた。いくら四書五経に優れた記述が多いとはいえ、原産地の中国がろくにその
実践も覚束ないでいたというのでは、四書五経の実践可能性が未だ疑われたままでいたとしても仕方がない。
四書五経が実際に世界レベルでの実用も可能であることを実証しているのは、漢代や唐代における
中華帝国の成功であり、それはもはや1000年以上もまえのことである。それでも当時の
儒学統治が類いまれな成功を果たしていたことが分かるのは、漢書や唐書のような正史書における
当時の治世の綿密な記録と、その記録に即した史跡の残存や発掘などがあるからである。
儒学というよりは、武士道による統治という印象が強い日本の江戸時代における泰平統治なども、
実際には武力が行使されたりすることは極めてまれで、概ねは儒学や朱子学を根幹とした文治を
旨としていたことが、すでに倒幕の熱も冷めきった今になってこそ、冷静に見極められつつもある。
今やっと、世界規模での儒学や仏教による統治を復興してく目処が立った。
そうしなければ西洋人までもが、過失ではない確信犯としての罪を負わされることに
なるだけの文化研究上の素地が整ったから。今までの聖書信仰者の罪は過失として扱われる一方で、
これからは決して、聖書信仰に基づく罪業の拡大が許されないようにもなったから。
これが「時宜」というもので、「中庸」二十章でも「義とは(時)宜なり」と、語呂合わせでその道義性を諾っている。
時宜に即せなかったがために大罪を犯し続けて来てしまった聖書信仰者のあり方にも、逆説的な道義性を見るのである。
「道に志し、徳に拠り、仁に依り、芸に遊ぶ」
「(訳は不要だろう。権力道徳者にとって、仁徳は目指すだけでなく、依り頼むものですらある)」
(権力道徳性——通称四書五経——論語・述而第七・六より)
「今、同室の人に闘う者有れば、之れを救うに被髪纓冠して之れを救うと雖も可なり。
郷鄰に闘う者有れば、被髮纓冠して往きて之れを救うは則ち惑いなり。戸を閉ざすと雖も可なり。(既出)」
「いま仮に、自分と同じ部屋で問題を呈した者がいれば、無冠の乱れ髪のままでこれを救おうとしても構わない。
しかし、自分の住む地域で問題を呈した者がいたとして、これに対してまで無冠の乱れ髪のままで救いの手を
差し伸べに行ったりすれば、それは惑いというものだ。我が家の戸を閉めて、そ知らぬ振りでいても構わない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・離婁章句下・三〇より)
ごく近くの隣人であれば、私人として争いに割って入るも可。しかし戸外の他人ともなれば、
衣冠束髪の正式な公人でもない限りは争いに関わるべきでもないという、絶妙な距離感覚。
仁徳者は極端な個人主義でもなければ、天下万人に無限の博愛を注ぐような夢想家でもない。
世の中における人と人との関わりの深さによって、関わり方を自在に調整していく技術家でこそある。
その仁徳者が天下国家に対して好影響を与えるだけの能力を発揮するためにこそ、正式な公人としての
立場が必要になる。上記のとおり、無名の私人の分際で市街の問題にまでおせっかいに関わろうとする
ことは不適切なことだと仁者なら考える。それは個人主義だからではなく、公人による適切な処理を
邪魔しないためであり、むしろ公人こそが市井の問題を完璧に処理することを企図しているからでもある。
殺人すら、正式な兵士や刑吏として適切にこなすのなら、一切の罪障を帯びなくて済んだりもする。
それほどにも公人という立場は、私人とは隔絶した特別性を帯びるものであり、そうである
ことを私人までもがよく尊重したならば、公人も市井の争いなどを完璧に処理して、やむなく
行われる戦闘などの場合にも、余裕を持って正義ある戦いに臨めていけるようにもなるのである。
郷鄰に闘う者有れば、被髮纓冠して往きて之れを救うは則ち惑いなり。戸を閉ざすと雖も可なり。(既出)」
「いま仮に、自分と同じ部屋で問題を呈した者がいれば、無冠の乱れ髪のままでこれを救おうとしても構わない。
しかし、自分の住む地域で問題を呈した者がいたとして、これに対してまで無冠の乱れ髪のままで救いの手を
差し伸べに行ったりすれば、それは惑いというものだ。我が家の戸を閉めて、そ知らぬ振りでいても構わない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・離婁章句下・三〇より)
ごく近くの隣人であれば、私人として争いに割って入るも可。しかし戸外の他人ともなれば、
衣冠束髪の正式な公人でもない限りは争いに関わるべきでもないという、絶妙な距離感覚。
仁徳者は極端な個人主義でもなければ、天下万人に無限の博愛を注ぐような夢想家でもない。
世の中における人と人との関わりの深さによって、関わり方を自在に調整していく技術家でこそある。
その仁徳者が天下国家に対して好影響を与えるだけの能力を発揮するためにこそ、正式な公人としての
立場が必要になる。上記のとおり、無名の私人の分際で市街の問題にまでおせっかいに関わろうとする
ことは不適切なことだと仁者なら考える。それは個人主義だからではなく、公人による適切な処理を
邪魔しないためであり、むしろ公人こそが市井の問題を完璧に処理することを企図しているからでもある。
殺人すら、正式な兵士や刑吏として適切にこなすのなら、一切の罪障を帯びなくて済んだりもする。
それほどにも公人という立場は、私人とは隔絶した特別性を帯びるものであり、そうである
ことを私人までもがよく尊重したならば、公人も市井の争いなどを完璧に処理して、やむなく
行われる戦闘などの場合にも、余裕を持って正義ある戦いに臨めていけるようにもなるのである。
公人だけでなく私人までもが仁徳者である、誰しもが仁義を尊ぶ世の中であるに越したことはないが、
だからといって私人である仁者が、公人と全く同じような振る舞いをすべきだなんてことも全くない。
私人と公人とではあまりにも立場が違えばこそ、全く真逆の行いに務めるべきことすらザラにある。
だからこそ、誰しもが公共性を最大級に尊重しようとした場合でも、上記の孟子の言のようなあり方が妥当となる。
個人主義だからではなく、公共性を尊ぶためにこそ、私人は公共レベルの物事にみだりに関わろうとしない。
ただそうであるだけでなく、自分が重度の犯罪被害などに遭った場合にも、その対処を公的機関に
まずは一任し、私的に仕返しをしたり争ったりすることもなるべく控えるようにする。
それでも全く公的機関が処理をしてくれず、同様の怠慢が国中や世界中で蔓延して、いよいよ革命によって
体制を刷新でもしなければならず、しかも自分が新たな体制における権力者になるしかないとしたならば、
仕方なく自分がその立場に立って、自分に危害を加えて来た相手にも対する、公的な処罰を科すことだろう。
だから結局、自分に危害を加えて来た相手とも私的に争ったりすることは、永久にないままである。
仁徳者であるなら、他人に不条理な危害を加える犯罪者などと争ったりすることも徹底的に避けて、
逆にこちらの側が一方的かつ公正な処罰を当人たちに科すことだけに専念し続けるのである。
「醜夷に在りて争わず」
「同等の立場にある者同士として争ったりはしない。
(犯罪に私的な報復を加えたりすれば、自分も犯罪者となる。同じ穴の狢としての争いは避ける)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・曲礼上第一より)
だからといって私人である仁者が、公人と全く同じような振る舞いをすべきだなんてことも全くない。
私人と公人とではあまりにも立場が違えばこそ、全く真逆の行いに務めるべきことすらザラにある。
だからこそ、誰しもが公共性を最大級に尊重しようとした場合でも、上記の孟子の言のようなあり方が妥当となる。
個人主義だからではなく、公共性を尊ぶためにこそ、私人は公共レベルの物事にみだりに関わろうとしない。
ただそうであるだけでなく、自分が重度の犯罪被害などに遭った場合にも、その対処を公的機関に
まずは一任し、私的に仕返しをしたり争ったりすることもなるべく控えるようにする。
それでも全く公的機関が処理をしてくれず、同様の怠慢が国中や世界中で蔓延して、いよいよ革命によって
体制を刷新でもしなければならず、しかも自分が新たな体制における権力者になるしかないとしたならば、
仕方なく自分がその立場に立って、自分に危害を加えて来た相手にも対する、公的な処罰を科すことだろう。
だから結局、自分に危害を加えて来た相手とも私的に争ったりすることは、永久にないままである。
仁徳者であるなら、他人に不条理な危害を加える犯罪者などと争ったりすることも徹底的に避けて、
逆にこちらの側が一方的かつ公正な処罰を当人たちに科すことだけに専念し続けるのである。
「醜夷に在りて争わず」
「同等の立場にある者同士として争ったりはしない。
(犯罪に私的な報復を加えたりすれば、自分も犯罪者となる。同じ穴の狢としての争いは避ける)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・曲礼上第一より)
歴史的人物の言行を逐一伝説化して、何気ないような振る舞いに至るまで
全て記録するような風習は、それこそ孔子や釈迦こそを実質的な原初としている。
釈迦などは、臨終時の横臥が頭北面西だったことまでもが言い継がれている。
生まれた瞬間に七歩歩いて、天地を指差して「天上天下唯我独尊」と唱えたなど、
実際にはあり得ないような逸話までもが釈迦の行業に仮託されていて、
伝説的な人物に日頃の行いから範を取ろうとしていくことはむしろ、
仏教や儒学の盛んな東洋においてこそ最大級の隆盛を果たしていたとすらいえる。
しかるに、西洋では史上最高の伝説的人物とされるイエスからして、
サイコパスの重度精神障害者だった。その言行を真似しようとすればするほど
自分たち自身まで心身を患ってしまうことになるから、正教か旧教か新教かに
関わらず、イエスの言行をそのまま真似することは程々にすべきとされた。
(今の韓国キリスト教あたりは、相当にイエスの真似を試みてもいる)
他人の言行をことさらな範にしたりしない性向が付与された結果、西洋人も
自意識過剰の思い上がりを募らせた個人主義者ばかりとなった。一方で、
イエスの言行が真似ではなく信仰の対象とはされ続けたから、信仰を通じての
内面からの精神障害の伝染はそれなりに来たしていた。そのような、イエスの言行
までは真似しなくとも、信仰を通じてイエス並みの精神障害者と化した西洋人が、
自分たちの言行をフィクションをも踏まえつつ小説化することが「文学」ともされた。
全て記録するような風習は、それこそ孔子や釈迦こそを実質的な原初としている。
釈迦などは、臨終時の横臥が頭北面西だったことまでもが言い継がれている。
生まれた瞬間に七歩歩いて、天地を指差して「天上天下唯我独尊」と唱えたなど、
実際にはあり得ないような逸話までもが釈迦の行業に仮託されていて、
伝説的な人物に日頃の行いから範を取ろうとしていくことはむしろ、
仏教や儒学の盛んな東洋においてこそ最大級の隆盛を果たしていたとすらいえる。
しかるに、西洋では史上最高の伝説的人物とされるイエスからして、
サイコパスの重度精神障害者だった。その言行を真似しようとすればするほど
自分たち自身まで心身を患ってしまうことになるから、正教か旧教か新教かに
関わらず、イエスの言行をそのまま真似することは程々にすべきとされた。
(今の韓国キリスト教あたりは、相当にイエスの真似を試みてもいる)
他人の言行をことさらな範にしたりしない性向が付与された結果、西洋人も
自意識過剰の思い上がりを募らせた個人主義者ばかりとなった。一方で、
イエスの言行が真似ではなく信仰の対象とはされ続けたから、信仰を通じての
内面からの精神障害の伝染はそれなりに来たしていた。そのような、イエスの言行
までは真似しなくとも、信仰を通じてイエス並みの精神障害者と化した西洋人が、
自分たちの言行をフィクションをも踏まえつつ小説化することが「文学」ともされた。
イエスほどものあからさまな奇行にまでは及ばずとも、イエス並みの精神障害を
患った状態で為される西洋人の言行のフィクションを踏まえた記録、当然それは
孔子や釈迦のような史実上の政賢の言行と比べて取るに足らないものである。
のみならず、紂王や蘇秦や趙高のごとき、史実に即して記録された大悪人と比べても
匿名性があるために、糾弾の的にしにくいという一層の度がたさを帯びているといえる。
孔子や釈迦だけでなく、その他の歴史上の「真の偉人」たちの言行を範としたり
することには、やはりそれなりの意義があるから、他者の言行を何もかも見習いの対象と
しないなどという所に振れきるのは決してよくない。ただ、言行を見習ったり信仰の対象と
したりするせいで、かえって何も見習わなければいいほどもの劣悪な言行規範が自らに
植え付けられてしまうような凶人なり、その文学的表現なりもまたいくらでもあるものだから、
純粋な犯罪行為の摘発や防止を目的とした、犯罪心理の参考対象とするのでもなければ、
みだりにそのような凶人の言行を真似することも、信奉したりすることもすべきでない。
西洋の文学者なんて、出版社やパトロンに商略結婚を強いられたせいで、結婚に対する
極度の嫌悪感を抱いていたりするのが常だから、その作品を参考にすればするほど
まともな恋愛や結婚から遠ざかりもする。そういう事情があるのも知らずに、「文学
だから高尚」「読んで自分のためになる」なんて思い込むのも、哀れなことだといえる。
「天と水と違い行くは訟なり。君子以って事を作すに始めを謀る」
「天と水とが食い違った状態になるのは訟(争いごとの卦)である。
君子はそのような事態を招かないために、始めからことを慎重に計画して行く。
(天啓を謳う狂人が水徳に違うことを豪語するとは、まさに争いごとの兆しである。
そのような狂人の言行を持て囃したとすれば、そのような人間全員が少なくとも君子ではない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・訟・象伝より)
患った状態で為される西洋人の言行のフィクションを踏まえた記録、当然それは
孔子や釈迦のような史実上の政賢の言行と比べて取るに足らないものである。
のみならず、紂王や蘇秦や趙高のごとき、史実に即して記録された大悪人と比べても
匿名性があるために、糾弾の的にしにくいという一層の度がたさを帯びているといえる。
孔子や釈迦だけでなく、その他の歴史上の「真の偉人」たちの言行を範としたり
することには、やはりそれなりの意義があるから、他者の言行を何もかも見習いの対象と
しないなどという所に振れきるのは決してよくない。ただ、言行を見習ったり信仰の対象と
したりするせいで、かえって何も見習わなければいいほどもの劣悪な言行規範が自らに
植え付けられてしまうような凶人なり、その文学的表現なりもまたいくらでもあるものだから、
純粋な犯罪行為の摘発や防止を目的とした、犯罪心理の参考対象とするのでもなければ、
みだりにそのような凶人の言行を真似することも、信奉したりすることもすべきでない。
西洋の文学者なんて、出版社やパトロンに商略結婚を強いられたせいで、結婚に対する
極度の嫌悪感を抱いていたりするのが常だから、その作品を参考にすればするほど
まともな恋愛や結婚から遠ざかりもする。そういう事情があるのも知らずに、「文学
だから高尚」「読んで自分のためになる」なんて思い込むのも、哀れなことだといえる。
「天と水と違い行くは訟なり。君子以って事を作すに始めを謀る」
「天と水とが食い違った状態になるのは訟(争いごとの卦)である。
君子はそのような事態を招かないために、始めからことを慎重に計画して行く。
(天啓を謳う狂人が水徳に違うことを豪語するとは、まさに争いごとの兆しである。
そのような狂人の言行を持て囃したとすれば、そのような人間全員が少なくとも君子ではない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・訟・象伝より)
そもそも、「神の計画」などはなかった。
古代ユダヤ人であれイエスであれ、その行いは「小人は険を犯して僥倖を求める(中庸・一四)」
であることで一貫していたのであり、その「僥倖」を自分たちの中で「神の計画の成就」に勝手に
すり替えて、無闇に険を犯したがる自分たちの小人さ加減から目を逸らしたがっていただけなのでもある。
形而上の超越神による計画などがなかったのみならず、古代ユダヤ人やイエスが、
「神の物語」に仮託して成就させようとしていた実際的な計画などからして、やはりなかった。
政商として国家に寄生することで法外な富をせしめるユダヤ人の行いや、冤罪事件の画策で
世の中を未曾有の争乱に陥れたイエスの行いなどは、ただ自分たちの富裕欲を満たしたかったり、
妾腹の私生児としての自らの負い目を、間違った方法によってでも晴らしたかったりといった動機によって
試みられたというばかりのものでしかない。そこに「神の物語」としての粉飾を加えて、単なる悪行として
早急に摘発される場合以上もの「存在性の延命」の余地を与えたのも、古代ユダヤ人やイエス自身に、
「人々を末永く争乱や破滅に陥れ続けたい」という、自分一身の生涯をも超えた悪意が備わっていたからだ。
それでいて、自分たちが捏造した「神の計画」がいつかは成就するかのように予言しておいてもいる。
それは、深刻な政商詐欺の被害下に置かれた国家が、いつかは財政破綻によって崩壊してしまうということを、
古代ユダヤ人もまた政商詐欺集団としての身の上から実地に経験していたからに違いなく、たとえ政商詐欺の
社会的容認や拡大を、巧妙なカルト教義によって無理に推進し続けてみたところで、所詮は害悪の塊でしかない
政商詐欺なぞを推進し続けた先にあるのが、国家レベルの破綻であるということをも潜在的に察知していたからだ。
古代ユダヤ人であれイエスであれ、その行いは「小人は険を犯して僥倖を求める(中庸・一四)」
であることで一貫していたのであり、その「僥倖」を自分たちの中で「神の計画の成就」に勝手に
すり替えて、無闇に険を犯したがる自分たちの小人さ加減から目を逸らしたがっていただけなのでもある。
形而上の超越神による計画などがなかったのみならず、古代ユダヤ人やイエスが、
「神の物語」に仮託して成就させようとしていた実際的な計画などからして、やはりなかった。
政商として国家に寄生することで法外な富をせしめるユダヤ人の行いや、冤罪事件の画策で
世の中を未曾有の争乱に陥れたイエスの行いなどは、ただ自分たちの富裕欲を満たしたかったり、
妾腹の私生児としての自らの負い目を、間違った方法によってでも晴らしたかったりといった動機によって
試みられたというばかりのものでしかない。そこに「神の物語」としての粉飾を加えて、単なる悪行として
早急に摘発される場合以上もの「存在性の延命」の余地を与えたのも、古代ユダヤ人やイエス自身に、
「人々を末永く争乱や破滅に陥れ続けたい」という、自分一身の生涯をも超えた悪意が備わっていたからだ。
それでいて、自分たちが捏造した「神の計画」がいつかは成就するかのように予言しておいてもいる。
それは、深刻な政商詐欺の被害下に置かれた国家が、いつかは財政破綻によって崩壊してしまうということを、
古代ユダヤ人もまた政商詐欺集団としての身の上から実地に経験していたからに違いなく、たとえ政商詐欺の
社会的容認や拡大を、巧妙なカルト教義によって無理に推進し続けてみたところで、所詮は害悪の塊でしかない
政商詐欺なぞを推進し続けた先にあるのが、国家レベルの破綻であるということをも潜在的に察知していたからだ。
キリスト教徒やユダヤ教徒は、当然こんなことは認めないだろうし、カルト教義の流布者としての
古代のユダヤ人やイエス自身に「実際はこうなんだろうが」と、上記のような分析を提示してみたところで、
自己と他者とを同時に偽る有能な詐欺師根性に基づいて、頑なに「そんなことはない」と否認するにも違いない。
しかし、「政商カルト詐欺の聖書」通称聖書への信仰が2000年にわたって推進され続けてきた
結果はといえば、紛れもなく上記のような分析こそが百発百中していたがためのものとなっている。
本物の神の計画があったわけでもなければ、神の計画に仮託した何らかの人為的な計画があったわけでもない。
ただ、致命的な社会破綻を来たすまでの、政商詐欺による放辟邪侈を推進していくための悪巧方便が、最終的な
社会破綻までをも「神の計画の成就」などと偽証することであったのみ。聖書信仰の「蜜月」は、あったとした
ところで「最後の審判」以前までのものであり、しかもその蜜月もまた罪業まみれであるがために、常に一定以上
の良心の呵責を孕んできた。確かに「最後の審判」以後に、その潜在的な良心の呵責が晴らされていくことにも
なり得るが、それは自分たちが政商詐欺の支援からなる蜜月を剥奪されて、人並み以上に自分たちの罪を償っていく
ようになるからなのだから、「神の計画の成就」たるや、いかにお粗末なものだったのかが知れたものだといえる。
「大いに為す有らんとするの君は、必ず召さざる所の臣有りて、謀ること有らんと欲すれば、
則ち之れに就く。其の徳を尊び道を楽しむこと是の如くならずんば、与て為す有るに足らざればなり」
「真に大業を為そうとする君には、必ず招き寄せない類いの臣下がいて、計画を企てる場合にも
自分から臣下の居場所に赴いて行った。君自身がそれほどにも徳を尊んで道を楽しむのでなければ、
本当に大いなる計画を成就させることなどはできないからだ。(イエスは神の計画を成就させるために、
自分から神のいる天国へと赴いて行った。計画主謀者である神がイエスのほうへと赴かないからには、
イエスがさほど有能な配下でないか、計画そのものがどうでもいいものだったかのいずれかだったのだろう)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・公孫丑章句下より)
古代のユダヤ人やイエス自身に「実際はこうなんだろうが」と、上記のような分析を提示してみたところで、
自己と他者とを同時に偽る有能な詐欺師根性に基づいて、頑なに「そんなことはない」と否認するにも違いない。
しかし、「政商カルト詐欺の聖書」通称聖書への信仰が2000年にわたって推進され続けてきた
結果はといえば、紛れもなく上記のような分析こそが百発百中していたがためのものとなっている。
本物の神の計画があったわけでもなければ、神の計画に仮託した何らかの人為的な計画があったわけでもない。
ただ、致命的な社会破綻を来たすまでの、政商詐欺による放辟邪侈を推進していくための悪巧方便が、最終的な
社会破綻までをも「神の計画の成就」などと偽証することであったのみ。聖書信仰の「蜜月」は、あったとした
ところで「最後の審判」以前までのものであり、しかもその蜜月もまた罪業まみれであるがために、常に一定以上
の良心の呵責を孕んできた。確かに「最後の審判」以後に、その潜在的な良心の呵責が晴らされていくことにも
なり得るが、それは自分たちが政商詐欺の支援からなる蜜月を剥奪されて、人並み以上に自分たちの罪を償っていく
ようになるからなのだから、「神の計画の成就」たるや、いかにお粗末なものだったのかが知れたものだといえる。
「大いに為す有らんとするの君は、必ず召さざる所の臣有りて、謀ること有らんと欲すれば、
則ち之れに就く。其の徳を尊び道を楽しむこと是の如くならずんば、与て為す有るに足らざればなり」
「真に大業を為そうとする君には、必ず招き寄せない類いの臣下がいて、計画を企てる場合にも
自分から臣下の居場所に赴いて行った。君自身がそれほどにも徳を尊んで道を楽しむのでなければ、
本当に大いなる計画を成就させることなどはできないからだ。(イエスは神の計画を成就させるために、
自分から神のいる天国へと赴いて行った。計画主謀者である神がイエスのほうへと赴かないからには、
イエスがさほど有能な配下でないか、計画そのものがどうでもいいものだったかのいずれかだったのだろう)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・公孫丑章句下より)
いくらイエスを慕ったり、十字架上のイエスを侮辱した連中を憎んだりしようとも、
それが俗悪で濁念にまみれた、当時のイスラエルやローマの世情を復元させる温床にしかならない。
たとえば、春秋時代末期から戦国時代にかけての中国(司馬遷は「秦代」と定義する)もまた、
子が親を殺し、臣下が主君を殺す最悪の争乱状態にあった。最悪の乱世は精神衛生上でも極めて有害で、
孔子や孟子のような強靭な精神力の持ち主か、さもなくば老荘列のような世間からの隠退者でもなければ
心の健全さを保てないでもいた。そのような時代性を真っ向から肯定しての、実定法支配や悪徳外交を
体系化した韓非や鬼谷の論説などを為政の参考としたなら、それによって当時の乱れた世相までもが
復元されることとなってしまう。イエス磔刑の記録などを持て囃すこともまた、それと同等の問題を
来たし得るもので、世相全体の「穢れ」を濃縮した代物であることでは、全く共通しているのである。
犯罪聖書の記録にも邪気がこもっているし、書物としての「韓非子」や「鬼谷子」の内容にも邪気が伴っている。
そのような邪気を日本人は「穢れ」として一般的に解釈し、記録や思想に限らず、精神衛生面から穢れを帯びて
しまっているような事物や人物全般を差別下に置いたりもしていた。日本人自身、穢れを「血肉」に類推するなど、
理論性を欠いた判別を拠り所にしてもいたから、今では迷信的なものとして退けられつつあるけれども、
穢れとは要するに邪気のことであり、それはたとえば、春秋戦国時代の中国や、イエス磔刑時の
イスラエルやローマに蔓延していた世相からの邪気などとも同定することができるのである。
春秋戦国時代に、主に秦人たちがもたらしていた醜悪な世相は、あまりにも度し難いことから、
中国でも漢代や唐代に排斥の対象とされ、当時の原型をとどめている系譜というのはもはや中国にもない。
日本でも、中国から渡来してきた秦人の内でも、特に穢れの甚だしい者は被差別部落の構成員となる
などの運命を辿ったが、唯一、僻地の土佐国に落ち延びた長宗我部氏だけは、古代の秦人の系譜を色濃く
残しながら、被差別部落となることまでは免れつつの延命を、幕末に至るまで辛うじて保ち続けていた。
それが俗悪で濁念にまみれた、当時のイスラエルやローマの世情を復元させる温床にしかならない。
たとえば、春秋時代末期から戦国時代にかけての中国(司馬遷は「秦代」と定義する)もまた、
子が親を殺し、臣下が主君を殺す最悪の争乱状態にあった。最悪の乱世は精神衛生上でも極めて有害で、
孔子や孟子のような強靭な精神力の持ち主か、さもなくば老荘列のような世間からの隠退者でもなければ
心の健全さを保てないでもいた。そのような時代性を真っ向から肯定しての、実定法支配や悪徳外交を
体系化した韓非や鬼谷の論説などを為政の参考としたなら、それによって当時の乱れた世相までもが
復元されることとなってしまう。イエス磔刑の記録などを持て囃すこともまた、それと同等の問題を
来たし得るもので、世相全体の「穢れ」を濃縮した代物であることでは、全く共通しているのである。
犯罪聖書の記録にも邪気がこもっているし、書物としての「韓非子」や「鬼谷子」の内容にも邪気が伴っている。
そのような邪気を日本人は「穢れ」として一般的に解釈し、記録や思想に限らず、精神衛生面から穢れを帯びて
しまっているような事物や人物全般を差別下に置いたりもしていた。日本人自身、穢れを「血肉」に類推するなど、
理論性を欠いた判別を拠り所にしてもいたから、今では迷信的なものとして退けられつつあるけれども、
穢れとは要するに邪気のことであり、それはたとえば、春秋戦国時代の中国や、イエス磔刑時の
イスラエルやローマに蔓延していた世相からの邪気などとも同定することができるのである。
春秋戦国時代に、主に秦人たちがもたらしていた醜悪な世相は、あまりにも度し難いことから、
中国でも漢代や唐代に排斥の対象とされ、当時の原型をとどめている系譜というのはもはや中国にもない。
日本でも、中国から渡来してきた秦人の内でも、特に穢れの甚だしい者は被差別部落の構成員となる
などの運命を辿ったが、唯一、僻地の土佐国に落ち延びた長宗我部氏だけは、古代の秦人の系譜を色濃く
残しながら、被差別部落となることまでは免れつつの延命を、幕末に至るまで辛うじて保ち続けていた。
その長宗我部勢が、幕末に坂本龍馬や中岡慎太郎のような悪徳外交家、岩崎弥太郎のような悪徳政商を輩出し、
半ば米英のような外圧の犬ともなりつつの、近現代の日本の国家体制の枠組みを造り上げた。始めのうちは、
その文明開化の奇抜さなどから「悪いものでもない」ような評価を受けてもいたが、段々その、内面の穢れを
物質的な虚飾で取り繕うメッキが剥がれて行き、今ではもはや日本全土が穢れまみれとなったことが如実化
してしまい、意味不明な凶悪事件や、未成年者のいじめなどの問題が多発化するようにもなってしまっている。
日本の世相腐敗の元凶は主に、この古代の秦人の系譜を受け継ぐ邪気ではあるが、だからといって日本人たちが
今の世相を許容しているというのではない。西洋文明の大々的な流入こそが、今の世相を容認せざるを得ない
主な理由だと考えられていて、西洋文明の根幹は未だキリスト教だから、結局のところ、キリスト教を容認する
ことを通じて、秦人の末裔たちがもたらしている今の腐れ切った世相をも黙認させられてしまっているのである。
秦人による支配が日本の世相腐敗の主因なら、キリスト教教義にも基づくその是認もまた腐敗の副因であり、
両者が相まって日本社会の腐敗も磐石なものとなってしまっている。両者が相まえるのも、いずれもが、
昔の日本人が「穢れ」と呼んで忌み嫌っていた所の邪気を帯びているからで、穢れというものは二重にも
三重にも折り重なることで、その甚大さを増すものであることが分かる。あまりにも甚大であるからといって、
その処理をおざなりにすることもなく、一つ一つの穢れの根源から着実に拭い去っていく努力が必要だといえる。
「夫れ人必ず自ら侮りて、然る後に人之れを侮る。
家必ず自ら毀ちて、而る後に人之れを毀つ。国必ず自ら伐ちて、而る後人之れを伐つ」
「人は必ず自らを侮ることがあってから、しかる後に人にも侮られることがある。
自分から家をダメにするようなことがあってから、人に家をだめにされるようなことがある。
自分から国を亡ぼすようなことをするから、他国に亡ぼされるようなこともある。
(これはイエス本人と、イエスを侮辱していた当時のイスラエル人やローマ人全員に言えることである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・離婁章句上・八より)
半ば米英のような外圧の犬ともなりつつの、近現代の日本の国家体制の枠組みを造り上げた。始めのうちは、
その文明開化の奇抜さなどから「悪いものでもない」ような評価を受けてもいたが、段々その、内面の穢れを
物質的な虚飾で取り繕うメッキが剥がれて行き、今ではもはや日本全土が穢れまみれとなったことが如実化
してしまい、意味不明な凶悪事件や、未成年者のいじめなどの問題が多発化するようにもなってしまっている。
日本の世相腐敗の元凶は主に、この古代の秦人の系譜を受け継ぐ邪気ではあるが、だからといって日本人たちが
今の世相を許容しているというのではない。西洋文明の大々的な流入こそが、今の世相を容認せざるを得ない
主な理由だと考えられていて、西洋文明の根幹は未だキリスト教だから、結局のところ、キリスト教を容認する
ことを通じて、秦人の末裔たちがもたらしている今の腐れ切った世相をも黙認させられてしまっているのである。
秦人による支配が日本の世相腐敗の主因なら、キリスト教教義にも基づくその是認もまた腐敗の副因であり、
両者が相まって日本社会の腐敗も磐石なものとなってしまっている。両者が相まえるのも、いずれもが、
昔の日本人が「穢れ」と呼んで忌み嫌っていた所の邪気を帯びているからで、穢れというものは二重にも
三重にも折り重なることで、その甚大さを増すものであることが分かる。あまりにも甚大であるからといって、
その処理をおざなりにすることもなく、一つ一つの穢れの根源から着実に拭い去っていく努力が必要だといえる。
「夫れ人必ず自ら侮りて、然る後に人之れを侮る。
家必ず自ら毀ちて、而る後に人之れを毀つ。国必ず自ら伐ちて、而る後人之れを伐つ」
「人は必ず自らを侮ることがあってから、しかる後に人にも侮られることがある。
自分から家をダメにするようなことがあってから、人に家をだめにされるようなことがある。
自分から国を亡ぼすようなことをするから、他国に亡ぼされるようなこともある。
(これはイエス本人と、イエスを侮辱していた当時のイスラエル人やローマ人全員に言えることである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・離婁章句上・八より)
刑事や政治も「礼楽刑政」の秩序に即して、
ただの事務処理以上にも厳粛なものとして執り行われたほうがよい。
乱世にはなかなかそういうわけにもいかないこともあるにしろ、
恒常的な為政や刑事にかけては、礼楽の潤色を加えたほうが安定することが、
周や漢や唐や平安朝などの治世の成功からも容易に察することができる。
宗教の内でも、神道や密教や道教やバラモン教などは、礼楽統治を補佐する能力を持つ。
バラモンをカーストの最高位に置いているインドが、内政にかけては万年泰平状態を
確立できているのも、バラモンが祭司として実質的な礼楽統治の指導者ともなっているからだ。
礼楽統治の補佐になるわけでもなければ、障害になるわけでもない部類の宗教として
禅仏教や浄土教があり、これらは礼楽統治の覚束ない乱世を治世へと正しかえす
消火栓としての役割に長けているし、また治世が取り戻されて後の、武家階級や庶民階級に
とっての、煩瑣な体系性を省いた簡易的な拠り所としての役割すらをも担っていけるものである。
治世における礼楽統治の補佐役になるわけでもなければ、乱世を治世に引き戻す能力を具えて
いるわけでもない、礼楽統治の覚束ない最悪の乱世こそをもたらして恒常化させようとする
類いの宗教なり、学術なりがある。宗教としてはユダヤ教やキリスト教がそれに当てはまり、
学術としては大半の洋学、中国諸子百家中の法家や縦横家などがそれに当てはまる。
イエスの冤罪磔刑劇のごとき、あられもない醜態を刑事が帯びたりするのであれば、
それにより刑政の秩序も極端に乱れ、礼楽によって統制するどころではない状態が恒常化
してしまうことにもなる。さらに、イエスを神の子(キリスト)として崇め立てて信仰の対象と
したりしたなら、絶対に礼楽統治など不能と化した乱れた為政が、完全に固着化することになる。
ただの事務処理以上にも厳粛なものとして執り行われたほうがよい。
乱世にはなかなかそういうわけにもいかないこともあるにしろ、
恒常的な為政や刑事にかけては、礼楽の潤色を加えたほうが安定することが、
周や漢や唐や平安朝などの治世の成功からも容易に察することができる。
宗教の内でも、神道や密教や道教やバラモン教などは、礼楽統治を補佐する能力を持つ。
バラモンをカーストの最高位に置いているインドが、内政にかけては万年泰平状態を
確立できているのも、バラモンが祭司として実質的な礼楽統治の指導者ともなっているからだ。
礼楽統治の補佐になるわけでもなければ、障害になるわけでもない部類の宗教として
禅仏教や浄土教があり、これらは礼楽統治の覚束ない乱世を治世へと正しかえす
消火栓としての役割に長けているし、また治世が取り戻されて後の、武家階級や庶民階級に
とっての、煩瑣な体系性を省いた簡易的な拠り所としての役割すらをも担っていけるものである。
治世における礼楽統治の補佐役になるわけでもなければ、乱世を治世に引き戻す能力を具えて
いるわけでもない、礼楽統治の覚束ない最悪の乱世こそをもたらして恒常化させようとする
類いの宗教なり、学術なりがある。宗教としてはユダヤ教やキリスト教がそれに当てはまり、
学術としては大半の洋学、中国諸子百家中の法家や縦横家などがそれに当てはまる。
イエスの冤罪磔刑劇のごとき、あられもない醜態を刑事が帯びたりするのであれば、
それにより刑政の秩序も極端に乱れ、礼楽によって統制するどころではない状態が恒常化
してしまうことにもなる。さらに、イエスを神の子(キリスト)として崇め立てて信仰の対象と
したりしたなら、絶対に礼楽統治など不能と化した乱れた為政が、完全に固着化することになる。
礼楽統治の原典中の原典である四書五経の記述と、イエキリを神格化した犯罪聖書の記述が
ことごとく相反しているのみならず、それらの実践と信仰とが決定的に相反してもいる。
四書五経を実践する以上は犯罪聖書への信仰を取りやめねばならず、犯罪聖書への
信仰に固執し続ける以上は、絶対に四書五経を実践することはできない。
ただ政治や刑事をまともなものとする、それだけのために犯罪聖書への信仰を廃絶する
というのでは正直、浅い。ただ刑政を健全化していこうとすることと、犯罪聖書を
信仰することとでは、必ずしも相反した関係になく、両者が並立してしまった結果、
また聖書信仰によって乱れた刑政がもたらされてしまうようなことにもなりかねない。
政治や刑事を礼楽によって潤色する、そこに目標を定めることで初めて、聖書信仰を
この世から否応なく廃絶して行けるようにもなり、礼楽統治との決定的な相反性に即して、
この世から完全に聖書信仰が根絶された結果、刑政の健全性もやっと安定化することになる。
刑政を極度の乱脈に陥れる邪教が、極大級の災禍をすでにもたらした後であればこそ、
礼楽によっての為政の潤色までもが、半ば義務性を帯びるようになってしまったのである。
「楚子、巣車に登りて以て晋軍を望む。子重、大宰伯州犁をして王の後に侍らしむ。王曰く、
〜幕を張れり。曰く、先君に虔卜するなり。幕を徹せり。曰く将に命を發せんとするなり」
「楚の共王が櫓付きの車に登って晋軍を遠望した。大宰相の伯州犁が子重の命で王に近侍した。
王は言った。『あそこで幕を張っているのは何だ』 伯州犁『あれは先君の霊に伺いを立てているのです』
王『あ、幕を外したぞ』 伯州犁『今から伺いによって得られた命令を下そうとしているのです』
(幕が裂けて神異に適うなんて道理はない。特に正式命令絶対のまともな軍人ならそう考える)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・成公十六年より)
ことごとく相反しているのみならず、それらの実践と信仰とが決定的に相反してもいる。
四書五経を実践する以上は犯罪聖書への信仰を取りやめねばならず、犯罪聖書への
信仰に固執し続ける以上は、絶対に四書五経を実践することはできない。
ただ政治や刑事をまともなものとする、それだけのために犯罪聖書への信仰を廃絶する
というのでは正直、浅い。ただ刑政を健全化していこうとすることと、犯罪聖書を
信仰することとでは、必ずしも相反した関係になく、両者が並立してしまった結果、
また聖書信仰によって乱れた刑政がもたらされてしまうようなことにもなりかねない。
政治や刑事を礼楽によって潤色する、そこに目標を定めることで初めて、聖書信仰を
この世から否応なく廃絶して行けるようにもなり、礼楽統治との決定的な相反性に即して、
この世から完全に聖書信仰が根絶された結果、刑政の健全性もやっと安定化することになる。
刑政を極度の乱脈に陥れる邪教が、極大級の災禍をすでにもたらした後であればこそ、
礼楽によっての為政の潤色までもが、半ば義務性を帯びるようになってしまったのである。
「楚子、巣車に登りて以て晋軍を望む。子重、大宰伯州犁をして王の後に侍らしむ。王曰く、
〜幕を張れり。曰く、先君に虔卜するなり。幕を徹せり。曰く将に命を發せんとするなり」
「楚の共王が櫓付きの車に登って晋軍を遠望した。大宰相の伯州犁が子重の命で王に近侍した。
王は言った。『あそこで幕を張っているのは何だ』 伯州犁『あれは先君の霊に伺いを立てているのです』
王『あ、幕を外したぞ』 伯州犁『今から伺いによって得られた命令を下そうとしているのです』
(幕が裂けて神異に適うなんて道理はない。特に正式命令絶対のまともな軍人ならそう考える)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・成公十六年より)
禅書「無門関」第二則:百丈野狐
「百丈和尚が説法していると、一人の老人が『自分は参禅に失敗して五百回
野狐としての生を送らされている修行者の化身です。どうか自分を野狐としての
生から解き放ってください』と言った。百丈和尚が『不味因果』と言うと修行者は
悟りを開いて野狐としての生を脱した。『すでに野狐としての身は裏山にあります』
という修行者の言葉通り、裏山で野狐の死体が見つかり、荼毘に付した。(略省取意)」
上記の公案など、実は老人がただの参禅者で、百丈和尚との禅問答に
臨むために、あらかじめ狐を仕留めておいて一芝居うったのだとも考えられなくはない。
禅仏教が隆盛を極めていた当時の中国でなら、それぐらいする人間もいたかもしれず、
実際芝居だったのだろうが、だからといってこの公案の有難みが揺らぐわけでもない。
新約犯罪聖書におけるイエスの復活劇なども、読み方によっては、ただマリアか誰かが
イエスの遺体を穴蔵から持ち出しただけで、復活後のイエスによる弟子たちに対する
説法なども、単なる弟子たちの脳内妄想でしかなかったと考えられなくはない。しかし、
そんなことを信仰者である以上は疑ってはならないし、もしもそういう風に考えて
しまったならば、新約の記述などには何の有難みもないことになってしまうのである。
釈迦の説法も方便ばかりなら、それに後続する仏者たちの言説も方便だらけ。
それでいて、それらの方便がウソや芝居を踏まえていることが知れたところで、
だからといってその有難味に亀裂が生じるようなことも一切ない。それは、仏者の
根本的な発言姿勢からして、諸法実相のことわりをかたくわきまえたものであり、
形而上の超越神による世界の創造みたいな、全くの嘘偽りを教義の根幹に据えるような
過ちを徹底して排したものであるからで、発言以前、行動以前に仏者が本来在住して
いる「道」というものからして、常人やカルト教徒とは段違いなものなのである。
「百丈和尚が説法していると、一人の老人が『自分は参禅に失敗して五百回
野狐としての生を送らされている修行者の化身です。どうか自分を野狐としての
生から解き放ってください』と言った。百丈和尚が『不味因果』と言うと修行者は
悟りを開いて野狐としての生を脱した。『すでに野狐としての身は裏山にあります』
という修行者の言葉通り、裏山で野狐の死体が見つかり、荼毘に付した。(略省取意)」
上記の公案など、実は老人がただの参禅者で、百丈和尚との禅問答に
臨むために、あらかじめ狐を仕留めておいて一芝居うったのだとも考えられなくはない。
禅仏教が隆盛を極めていた当時の中国でなら、それぐらいする人間もいたかもしれず、
実際芝居だったのだろうが、だからといってこの公案の有難みが揺らぐわけでもない。
新約犯罪聖書におけるイエスの復活劇なども、読み方によっては、ただマリアか誰かが
イエスの遺体を穴蔵から持ち出しただけで、復活後のイエスによる弟子たちに対する
説法なども、単なる弟子たちの脳内妄想でしかなかったと考えられなくはない。しかし、
そんなことを信仰者である以上は疑ってはならないし、もしもそういう風に考えて
しまったならば、新約の記述などには何の有難みもないことになってしまうのである。
釈迦の説法も方便ばかりなら、それに後続する仏者たちの言説も方便だらけ。
それでいて、それらの方便がウソや芝居を踏まえていることが知れたところで、
だからといってその有難味に亀裂が生じるようなことも一切ない。それは、仏者の
根本的な発言姿勢からして、諸法実相のことわりをかたくわきまえたものであり、
形而上の超越神による世界の創造みたいな、全くの嘘偽りを教義の根幹に据えるような
過ちを徹底して排したものであるからで、発言以前、行動以前に仏者が本来在住して
いる「道」というものからして、常人やカルト教徒とは段違いなものなのである。
それ程にも拠って立つ境地が高尚であればこそ、巧みな方便までをも尽くしての説法
までもが許されるというもので、常人以下の品性しか持たないカルト教祖やカルト信者は
もちろんのこと、ごく一般的な常人ですら、方便的な比喩表現を濫用したりすべきではない。
字面通りとはまた別の意味があったり、大した意味もないことを大げさに述べ立てたり
といった寓意的表現は、精進を積んだ仏者の境地などからすれば善用も可能とした所で、
常人やそれ以下の境地においては、ほぼ悪用のためにしか用いられない。本格的な
仏門が軒並み絶やされた状態にある、今の日本で流通している寓意的表現なども、
十中八九、愚民化のためのメディア洗脳のような悪質な目的しか備わっていない。
悪巧方便まみれな今の世の中で、善巧方便こそを駆使した仏説を急激に取り入れてみても、
悪巧方便とくそみそに扱われて、かえってその貫目を下げるようなことにすらなりかねない。
だから、これからの世の中を改善していく指針としては、やはり方便的な表現を極力省いた
儒説などをまずは根幹に据えるべきで、仏門の興隆は「次の次」ぐらいに考えておくべき
だといえる。これも、方便が悪用のために駆使されている現状に即した便宜なのである。
「我が心は石に匪ずんば、転ばす可からざるなり。
我が心は席に匪ずんぱ、巻き込む可からざるなり。威儀は棣棣として、選るべからざるなり」
「我が心はそこいらの石っころでもないのだから、転ばせたりすることもできはしない。
我が心はむしろでもないのだないのだから、巻き込んだりすることもできはしない。
この意義深さまでは、決して譲れはしない。(むしろで巻かれて、墓穴の前に石っころを
転がされた刑死者の遺体が紛失したからといって、そこに心もなければ威儀深さもない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・邶風・柏舟より)
までもが許されるというもので、常人以下の品性しか持たないカルト教祖やカルト信者は
もちろんのこと、ごく一般的な常人ですら、方便的な比喩表現を濫用したりすべきではない。
字面通りとはまた別の意味があったり、大した意味もないことを大げさに述べ立てたり
といった寓意的表現は、精進を積んだ仏者の境地などからすれば善用も可能とした所で、
常人やそれ以下の境地においては、ほぼ悪用のためにしか用いられない。本格的な
仏門が軒並み絶やされた状態にある、今の日本で流通している寓意的表現なども、
十中八九、愚民化のためのメディア洗脳のような悪質な目的しか備わっていない。
悪巧方便まみれな今の世の中で、善巧方便こそを駆使した仏説を急激に取り入れてみても、
悪巧方便とくそみそに扱われて、かえってその貫目を下げるようなことにすらなりかねない。
だから、これからの世の中を改善していく指針としては、やはり方便的な表現を極力省いた
儒説などをまずは根幹に据えるべきで、仏門の興隆は「次の次」ぐらいに考えておくべき
だといえる。これも、方便が悪用のために駆使されている現状に即した便宜なのである。
「我が心は石に匪ずんば、転ばす可からざるなり。
我が心は席に匪ずんぱ、巻き込む可からざるなり。威儀は棣棣として、選るべからざるなり」
「我が心はそこいらの石っころでもないのだから、転ばせたりすることもできはしない。
我が心はむしろでもないのだないのだから、巻き込んだりすることもできはしない。
この意義深さまでは、決して譲れはしない。(むしろで巻かれて、墓穴の前に石っころを
転がされた刑死者の遺体が紛失したからといって、そこに心もなければ威儀深さもない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・邶風・柏舟より)
働け、地蔵
自分たちの最たる拠り所である新旧約聖書からして、芝居や妄想の塊でしかない。
だから聖書信者は「人生は芝居だ」という風にも潜在的に考えて、
芝居としての趣向を凝らしたような生き方を目指そうとしてしまう。
匹夫匹婦であるのなら、それでも構わない場合もあるが、
多くの衆生の命運を一手に引き受けるような君子階級の人間が
そのようであるのなら、舞台上と舞台裏を使い分ける姑息さが結局は、
より多くの負担を民に強いるような結果ともなってしまう。
一般に、芝居の得意な者は着実に生きることが苦手だし、逆に着実に生きることに
専念している者は、芝居を演じるようなことを「恥ずかしい」と感じるものである。
大国の社稷宗廟の壇上では盛大に振る舞えた所で、ほんの数人の観衆の前で
芝居がかった行いをさせられることすらをも恥ずかしがるようなこともあるわけで、
着実に生きることの誠実さと、あえて芝居を踏まえようとする浮つきとには、
排他関係が備わっているとすらいえるのである。
芝居ばかりを人生の全てだなどと考えて来た人間が、いざ実地に根ざした振る舞いを
させられるとしても、これまた小っ恥ずかしいものがあるだろうとうかがえる。
社交上やメディア上での振る舞いを、立派な修辞で塗り固めてきた人間ほど、
それを取り払ってまで真剣に生きさせられることが億劫に感じられるものだ。
だから聖書信者は「人生は芝居だ」という風にも潜在的に考えて、
芝居としての趣向を凝らしたような生き方を目指そうとしてしまう。
匹夫匹婦であるのなら、それでも構わない場合もあるが、
多くの衆生の命運を一手に引き受けるような君子階級の人間が
そのようであるのなら、舞台上と舞台裏を使い分ける姑息さが結局は、
より多くの負担を民に強いるような結果ともなってしまう。
一般に、芝居の得意な者は着実に生きることが苦手だし、逆に着実に生きることに
専念している者は、芝居を演じるようなことを「恥ずかしい」と感じるものである。
大国の社稷宗廟の壇上では盛大に振る舞えた所で、ほんの数人の観衆の前で
芝居がかった行いをさせられることすらをも恥ずかしがるようなこともあるわけで、
着実に生きることの誠実さと、あえて芝居を踏まえようとする浮つきとには、
排他関係が備わっているとすらいえるのである。
芝居ばかりを人生の全てだなどと考えて来た人間が、いざ実地に根ざした振る舞いを
させられるとしても、これまた小っ恥ずかしいものがあるだろうとうかがえる。
社交上やメディア上での振る舞いを、立派な修辞で塗り固めてきた人間ほど、
それを取り払ってまで真剣に生きさせられることが億劫に感じられるものだ。
体裁にばかりこだわり過ぎてきたから、いざ実質を直視させられるとなれば、
辛くて辛くて仕方がない。そういう人間が、特に大国の命運を左右するほどもの
場で立ち回るというのも危険極まりないので、やはり引退を勧める他はないといえる。
むしろ、体裁の修辞など苦手だった者のうちで、特に志しあるような者こそが、
体裁の取り繕いばかりに固執しすぎて瓦解してしまった後の旧聖書圏における、
諸国内での後始末役となったりするのにもふさわしいだろう。
修辞にばかりこだわり過ぎて、実質的なことに携われなくなった連中も、
ただ泣き寝入りするんじゃなくて、ピエロ的な存在として場を沸かせるぐらいの
仕事はできなくもないから、それは目指してもいいだろう。もう修辞をカッコ付けの
ために用いたりはせずに、純粋な笑いや楽しみのために用いる。そのためには当然、
芝居がかった修辞に神性を付与するような風潮も絶やしていかねばならない。
芝居でない、実地に根ざした言行の潤色こそは礼儀作法なのであり、
芝居がかった礼儀ほど、礼儀としては贋物としての様相を帯びてしまう。
そういう礼儀作法の特色をわきまえて、もっぱら礼節の修練に務めるものと、
礼制に縛られて堅苦しくなった世の中を罪の無い程度の道化的な芸能によって
楽しませてリラックスさせるものとの両方があったほうが、「礼楽統治」の名にも適う。
本来、四書五経は四書六経だったのであり、六経のうちに含まれていた「楽経」が
すでに絶えて現存していない。楽経の律をありのままに復興して今の世のにあてがうのも
無理があるんで、そこを新たに工夫して創造していくことにも、それなりの意義が
備わるといえる。儒学の実践も、復古主義ばかりでは最善が尽くされもしないのである。
辛くて辛くて仕方がない。そういう人間が、特に大国の命運を左右するほどもの
場で立ち回るというのも危険極まりないので、やはり引退を勧める他はないといえる。
むしろ、体裁の修辞など苦手だった者のうちで、特に志しあるような者こそが、
体裁の取り繕いばかりに固執しすぎて瓦解してしまった後の旧聖書圏における、
諸国内での後始末役となったりするのにもふさわしいだろう。
修辞にばかりこだわり過ぎて、実質的なことに携われなくなった連中も、
ただ泣き寝入りするんじゃなくて、ピエロ的な存在として場を沸かせるぐらいの
仕事はできなくもないから、それは目指してもいいだろう。もう修辞をカッコ付けの
ために用いたりはせずに、純粋な笑いや楽しみのために用いる。そのためには当然、
芝居がかった修辞に神性を付与するような風潮も絶やしていかねばならない。
芝居でない、実地に根ざした言行の潤色こそは礼儀作法なのであり、
芝居がかった礼儀ほど、礼儀としては贋物としての様相を帯びてしまう。
そういう礼儀作法の特色をわきまえて、もっぱら礼節の修練に務めるものと、
礼制に縛られて堅苦しくなった世の中を罪の無い程度の道化的な芸能によって
楽しませてリラックスさせるものとの両方があったほうが、「礼楽統治」の名にも適う。
本来、四書五経は四書六経だったのであり、六経のうちに含まれていた「楽経」が
すでに絶えて現存していない。楽経の律をありのままに復興して今の世のにあてがうのも
無理があるんで、そこを新たに工夫して創造していくことにも、それなりの意義が
備わるといえる。儒学の実践も、復古主義ばかりでは最善が尽くされもしないのである。
今日の引用は有名な「苛政は虎よりも猛なり」の典拠。
ちょっと長いが、よく読みさえすれば、この話に出てくる嬪婦と比べれば、いかにマリアが
貞順でもなければ、世のことわりをろくにわきまえられてもいない匹婦だったのかが分かる。
しかもそれは、イエスが復活したか否かに関わらずの、普遍的な巧拙の差異ともなっている。
「孔子泰山の側を過ぐ。婦人の墓に哭する者有りて哀し。夫子して之れを聴き、子貢を使いして之れに問わしむ。曰く、
子の哭するや、壹に重ねて憂い有る者に似たりと。而ち曰く、然り。昔者吾が舅虎に死し、吾が夫も又た死し、今吾が子も
又た死せりと。夫子曰く、何為れぞ去らざるや。曰く、苛政無ければなり。夫子曰く、小子之れを識せ、苛政は虎よりも猛なりと」
「孔子が泰山の麓を通り過ぎるとき、一人の婦人が墓の前でひどく号泣しているのを見て不憫な気持ちになった。孔子は弟子の
子貢を使わせて質問させた。『あなたの泣く様は尋常なものではありません。何か多難でもあったのでしょうか』 婦人は答えた。
『はい、私の舅はこの地で虎に襲われて死に、夫もまた死に、いままた我が子までもが虎に襲われて死んだのです』 孔子が問うた。
『そこまで多重の災難に遭われながら、なぜこの地を去らないのですか』 婦人。『ここでは苛政が敷かれるようなことが
ないからです』 孔子はこれを聞いて弟子に言った。『記録しておきなさい。苛政の危害は虎の危害よりも甚だしいものだと』
(マリアはおそらく哀しみのあまり幻覚を見て、イエスが復活したかのような妖言を触れ回ってしまったのだろうが、それによって
現聖書圏にもたらされた苛政の甚だしさは、貞順な婦人が舅と夫と我が子とを虎に殺されて二度と生き返らない以上のものだった)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・檀弓下第四より)
ちょっと長いが、よく読みさえすれば、この話に出てくる嬪婦と比べれば、いかにマリアが
貞順でもなければ、世のことわりをろくにわきまえられてもいない匹婦だったのかが分かる。
しかもそれは、イエスが復活したか否かに関わらずの、普遍的な巧拙の差異ともなっている。
「孔子泰山の側を過ぐ。婦人の墓に哭する者有りて哀し。夫子して之れを聴き、子貢を使いして之れに問わしむ。曰く、
子の哭するや、壹に重ねて憂い有る者に似たりと。而ち曰く、然り。昔者吾が舅虎に死し、吾が夫も又た死し、今吾が子も
又た死せりと。夫子曰く、何為れぞ去らざるや。曰く、苛政無ければなり。夫子曰く、小子之れを識せ、苛政は虎よりも猛なりと」
「孔子が泰山の麓を通り過ぎるとき、一人の婦人が墓の前でひどく号泣しているのを見て不憫な気持ちになった。孔子は弟子の
子貢を使わせて質問させた。『あなたの泣く様は尋常なものではありません。何か多難でもあったのでしょうか』 婦人は答えた。
『はい、私の舅はこの地で虎に襲われて死に、夫もまた死に、いままた我が子までもが虎に襲われて死んだのです』 孔子が問うた。
『そこまで多重の災難に遭われながら、なぜこの地を去らないのですか』 婦人。『ここでは苛政が敷かれるようなことが
ないからです』 孔子はこれを聞いて弟子に言った。『記録しておきなさい。苛政の危害は虎の危害よりも甚だしいものだと』
(マリアはおそらく哀しみのあまり幻覚を見て、イエスが復活したかのような妖言を触れ回ってしまったのだろうが、それによって
現聖書圏にもたらされた苛政の甚だしさは、貞順な婦人が舅と夫と我が子とを虎に殺されて二度と生き返らない以上のものだった)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・檀弓下第四より)
四書五経中では、主に孔子や曾子が、よく孝養を尽くして
親の事業を忠実に受け継ぎ、親のやり方を最低でも三年は
改めないでおくことなどを理想として掲げていたりするけども、
親が重大犯罪者やカルト信者だったりする場合にまで、これらの言説を
そのまま守っていくのもどうかと思われる。孝行が経書にあるような通りに
実践されてしかるべきなのも、「人中の人」たる君子階級の人間でこそあり、
犯罪者やカルト信者はおろか、単なる民間人の子供ですら、儒説のままの
孝行を心がけたりしたなら、色々と齟齬を来すことになりかねない。
そもそも、人類発祥の地であるアフリカから日出ずる東方へのグレート・ジャーニーを試み、
大陸の極東付近に安住したのが中国人や日本人であるわけで、その先祖代々の実績があればこそ、
孝行をも当たり前のこととして重んじているというのもある。人類発祥地のアフリカからさらに
日没する西方や日陰る北方へと、「暗闇への逃避」を先祖代々続けてきた欧米人などからすれば、
潜在面からの親や先祖への尊敬意識が低いということもあり得るわけで、だからこそ、
親子兄弟の殺し合いすらをも促す邪教などを好き好んで信仰できたのだともいえる。
そういった先天的な要素に即して、善行を為しやすかったり為しにくかったり、
悪行を為しやすかったり為しにくかったりすることも確かにあるが、決して「絶対」ではない。
偉人の親から小人の子が、小人の親から偉人の子が生まれるということもあるし、
仮に「蛙の子は蛙」だったとした所で、やはり相応の系譜の改善に勤めていくことができる。
理想的な家系に生まれた子供が、親の事業を忠実に受け継いでいく上でも、孝行の際に
親への絶対服従を固持したりするのではなく、親が過ちを犯した場合には諫言も辞さないぐらいの
自主性を持つべきだと「礼記」などにも記されているわけで、結局、先天的にであれ後天的にであれ、
自分が善行を為す上での肝心要となるのが、自らの自主性であることには変わりない。
親の事業を忠実に受け継ぎ、親のやり方を最低でも三年は
改めないでおくことなどを理想として掲げていたりするけども、
親が重大犯罪者やカルト信者だったりする場合にまで、これらの言説を
そのまま守っていくのもどうかと思われる。孝行が経書にあるような通りに
実践されてしかるべきなのも、「人中の人」たる君子階級の人間でこそあり、
犯罪者やカルト信者はおろか、単なる民間人の子供ですら、儒説のままの
孝行を心がけたりしたなら、色々と齟齬を来すことになりかねない。
そもそも、人類発祥の地であるアフリカから日出ずる東方へのグレート・ジャーニーを試み、
大陸の極東付近に安住したのが中国人や日本人であるわけで、その先祖代々の実績があればこそ、
孝行をも当たり前のこととして重んじているというのもある。人類発祥地のアフリカからさらに
日没する西方や日陰る北方へと、「暗闇への逃避」を先祖代々続けてきた欧米人などからすれば、
潜在面からの親や先祖への尊敬意識が低いということもあり得るわけで、だからこそ、
親子兄弟の殺し合いすらをも促す邪教などを好き好んで信仰できたのだともいえる。
そういった先天的な要素に即して、善行を為しやすかったり為しにくかったり、
悪行を為しやすかったり為しにくかったりすることも確かにあるが、決して「絶対」ではない。
偉人の親から小人の子が、小人の親から偉人の子が生まれるということもあるし、
仮に「蛙の子は蛙」だったとした所で、やはり相応の系譜の改善に勤めていくことができる。
理想的な家系に生まれた子供が、親の事業を忠実に受け継いでいく上でも、孝行の際に
親への絶対服従を固持したりするのではなく、親が過ちを犯した場合には諫言も辞さないぐらいの
自主性を持つべきだと「礼記」などにも記されているわけで、結局、先天的にであれ後天的にであれ、
自分が善行を為す上での肝心要となるのが、自らの自主性であることには変わりない。
自主性を排除して、全くの服従によってことを為したりする所にこそ、悪行がある。
服従的であれば絶対に悪行に結び付くわけでもないが、ある程度以上に劣悪な悪行は
ほぼ必ず卑屈な服従意識と共にある。自らの狂気によって近隣の児童を殺傷した神戸の少年Aも、
己れの狂気を「バモイドオキ神」などという架空神に仮託しての凶行に及んでいたわけで、
ある程度以上に非常識な凶行に走る人間というのは、必ずといっていいほど
そういった倒錯的な服従意識を原動力としているものなのである。
必ずしもではないが、自主性のほうが善行に結び付きやすく、服従性のほうが悪行に結び付きやすい。
特に、何物にも優先して自主性があることが善行に結び付きやすく、逆に何物にも優先して服従性が
あることが悪行に結び付きやすい。自主性によって拠り所を選んだり、服従的である中で自主的な
行いを為したりすることもあるが、何よりもまず優先すべきなのは、自主性のほうだといえる。
犯罪聖書の神への服従を捨てて、他の服従対象を探したりするのではなく、まず服従ありきなものの
考え方から卒業して、常にまず自主性がある生き方というものを、目指していくべきなのだといえる。
「先王の礼楽を制するや、〜将に以って民に好悪を平らかにすることを教え、人道の正しきに反らしんめんとすればなり」
「昔の聖王が礼楽による統制を実施したのは、それによって民たちに好悪の情を平らかにすることを教えて、
正しい人道に引き戻してやろうとしたからだ。(情念の汚濁を鎮めて自分たちの自性に返らせた)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・楽記第十九より)
服従的であれば絶対に悪行に結び付くわけでもないが、ある程度以上に劣悪な悪行は
ほぼ必ず卑屈な服従意識と共にある。自らの狂気によって近隣の児童を殺傷した神戸の少年Aも、
己れの狂気を「バモイドオキ神」などという架空神に仮託しての凶行に及んでいたわけで、
ある程度以上に非常識な凶行に走る人間というのは、必ずといっていいほど
そういった倒錯的な服従意識を原動力としているものなのである。
必ずしもではないが、自主性のほうが善行に結び付きやすく、服従性のほうが悪行に結び付きやすい。
特に、何物にも優先して自主性があることが善行に結び付きやすく、逆に何物にも優先して服従性が
あることが悪行に結び付きやすい。自主性によって拠り所を選んだり、服従的である中で自主的な
行いを為したりすることもあるが、何よりもまず優先すべきなのは、自主性のほうだといえる。
犯罪聖書の神への服従を捨てて、他の服従対象を探したりするのではなく、まず服従ありきなものの
考え方から卒業して、常にまず自主性がある生き方というものを、目指していくべきなのだといえる。
「先王の礼楽を制するや、〜将に以って民に好悪を平らかにすることを教え、人道の正しきに反らしんめんとすればなり」
「昔の聖王が礼楽による統制を実施したのは、それによって民たちに好悪の情を平らかにすることを教えて、
正しい人道に引き戻してやろうとしたからだ。(情念の汚濁を鎮めて自分たちの自性に返らせた)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・楽記第十九より)
イエスがイスラエルでの妄言妄動に及んでいた頃、すでに中国では漢帝国による
潤沢な礼楽統治が敷かれ、インドでも仏教振興による文化的な隆盛を迎えていた。
漢帝国が2100年前にはすでに、ペルシャやアレクサンドリアなどの国の存在も察知し、
それなりに使節をも向かわせていたことが「史記」などにも記録されている。さすれば、
2000年前に東方社会の隆盛がイスラエルやローマにまで聞き知られていなかったと、完全に
断定することもできない。とはいえ、当時の西方社会の人間の国際レベルでの社交性などは
知れたもので、古代のギリシャ人もシリア以東を「アジア」の一言で片付けるほどもの無知さ加減
だったわけだから、まあ、総体的にはまだまだ世間知らずの田舎者だったろうことが察せられる。
イエスもそのような、極西の部落社会の世間知らずな田舎者の一人だったに違いなく、
世界中を自らの教説によって征服する野望を抱いてみたところで、所詮はローマやその外縁を
征服するぐらいの視野でしかなかったはずである。それだけでイエスの抱いていたような
野望は満たされたことになるわけだが、哀しいかな、井の中の蛙であるイスラエルの部落民が
「全世界」と考えていたような世界なんてのは、本当の全世界のうちではごく一部の
部落社会でしかなかった。だから結局、キリスト教というものが全世界における多数派に
なるようなことは叶わず、大航海時代以降の暴力的な征服によっても、文化面から
キリスト教こそを世界の多数派が支持するものとさせることはついぞ叶わなかった。
存在性の根本からして、キリスト教やユダヤ教はその程度のものでしかあり得ない。
全世界を暴力によって「制覇」するぐらいのことはできた所で、完全な統治下に置いて
自分たちのものとするようなビジョンは始めから存在していない。だから、かつての
モンゴル帝国のように、世界中を暴力で荒らし回った挙句に自滅してしまうのが関の山で、
その先に何ら栄光や名誉などが待ち受けているわけでもないこともまた、原理的なことである。
その程度のものであることで、キリスト教やユダヤ教は始めから完全に満足しきっているのだから。
潤沢な礼楽統治が敷かれ、インドでも仏教振興による文化的な隆盛を迎えていた。
漢帝国が2100年前にはすでに、ペルシャやアレクサンドリアなどの国の存在も察知し、
それなりに使節をも向かわせていたことが「史記」などにも記録されている。さすれば、
2000年前に東方社会の隆盛がイスラエルやローマにまで聞き知られていなかったと、完全に
断定することもできない。とはいえ、当時の西方社会の人間の国際レベルでの社交性などは
知れたもので、古代のギリシャ人もシリア以東を「アジア」の一言で片付けるほどもの無知さ加減
だったわけだから、まあ、総体的にはまだまだ世間知らずの田舎者だったろうことが察せられる。
イエスもそのような、極西の部落社会の世間知らずな田舎者の一人だったに違いなく、
世界中を自らの教説によって征服する野望を抱いてみたところで、所詮はローマやその外縁を
征服するぐらいの視野でしかなかったはずである。それだけでイエスの抱いていたような
野望は満たされたことになるわけだが、哀しいかな、井の中の蛙であるイスラエルの部落民が
「全世界」と考えていたような世界なんてのは、本当の全世界のうちではごく一部の
部落社会でしかなかった。だから結局、キリスト教というものが全世界における多数派に
なるようなことは叶わず、大航海時代以降の暴力的な征服によっても、文化面から
キリスト教こそを世界の多数派が支持するものとさせることはついぞ叶わなかった。
存在性の根本からして、キリスト教やユダヤ教はその程度のものでしかあり得ない。
全世界を暴力によって「制覇」するぐらいのことはできた所で、完全な統治下に置いて
自分たちのものとするようなビジョンは始めから存在していない。だから、かつての
モンゴル帝国のように、世界中を暴力で荒らし回った挙句に自滅してしまうのが関の山で、
その先に何ら栄光や名誉などが待ち受けているわけでもないこともまた、原理的なことである。
その程度のものであることで、キリスト教やユダヤ教は始めから完全に満足しきっているのだから。
イエスが全世界とみなしていたごく一部の部落社会などではなく、本物の全世界においては、
キリスト教によって信じるものが救われ、信じぬものが救われないなどという道理が通らない。
全国全土がキリスト教に支配されたローマ国内において、信仰を拒むものが虐殺されたり
したとしても、全世界でその身勝手さが通用するようなことはあり得ず、無理に通用させよう
として大量破壊兵器による異教徒の殲滅などを試みたなら、自分たちまでもがその煽りを
受けての滅亡がまぬがれ得ない。自分たちよりも異教徒のほうが遥かに多数派なのだから、
異教徒全員を殲滅しようなどと試みたところで、自分たちのほうが先に絶滅して、
異教徒のほうが部分的に生き延びたりする可能性のほうがまだ高い。
キリスト教で、全世界が征服できると思ったことからして、すでに勘違いだった。
教祖イエスの「この教説なら世界が征服できる」という見込みも全くの当て外れなら、
それを信じて、イエスの教説に即した世界征服を試みたキリシタンの見込みもまた全くの当て外れ。
邪教というものは、勘違いや当て外れによってこそ生ずる。その間違いを無理に押し通そうとした
結果、世界中に災禍を振りまき、何らの偉大な成果も挙げられない。それが邪教の全てなのである。
「徳の流行は、置郵して命を伝うるよりも速やかなり」
「徳が世界に流行していく速度は、どんなに便利な手段によって命を宣べ伝えるよりも速い。
(徳が広がっていくときにはそれ程にも速やかなのだから、徳を宣教する必要などはない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・公孫丑章句上・一より)
キリスト教によって信じるものが救われ、信じぬものが救われないなどという道理が通らない。
全国全土がキリスト教に支配されたローマ国内において、信仰を拒むものが虐殺されたり
したとしても、全世界でその身勝手さが通用するようなことはあり得ず、無理に通用させよう
として大量破壊兵器による異教徒の殲滅などを試みたなら、自分たちまでもがその煽りを
受けての滅亡がまぬがれ得ない。自分たちよりも異教徒のほうが遥かに多数派なのだから、
異教徒全員を殲滅しようなどと試みたところで、自分たちのほうが先に絶滅して、
異教徒のほうが部分的に生き延びたりする可能性のほうがまだ高い。
キリスト教で、全世界が征服できると思ったことからして、すでに勘違いだった。
教祖イエスの「この教説なら世界が征服できる」という見込みも全くの当て外れなら、
それを信じて、イエスの教説に即した世界征服を試みたキリシタンの見込みもまた全くの当て外れ。
邪教というものは、勘違いや当て外れによってこそ生ずる。その間違いを無理に押し通そうとした
結果、世界中に災禍を振りまき、何らの偉大な成果も挙げられない。それが邪教の全てなのである。
「徳の流行は、置郵して命を伝うるよりも速やかなり」
「徳が世界に流行していく速度は、どんなに便利な手段によって命を宣べ伝えるよりも速い。
(徳が広がっていくときにはそれ程にも速やかなのだから、徳を宣教する必要などはない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・公孫丑章句上・一より)
古今東西を問わず、道理や真理は普遍的なもので、本来わざわざ文面におこすまでもない。
それでもあえてそれを文面におこしたなら、それは、四書五経や仏典のようになる。
文面におこそうと思えばおこせるのは、道理や真理にも少なからず「一概」な側面があるからで、
一概さが備わっているからには、その一概さを反転させることができる。たとえば、
道理でも真理でも是とされる理念に「中正(中庸、中道)」があるが、中正の反対には
両極端がある。中正に対して一概であることが理に適うのとは反対に、両極端であることに
対して一概であることが理に反することともなる。そうして道理や真理に反する「悪」が生ずる。
悪は正理の反対を行っているわけだから、意外と正理にも似ていたりする。
天使と悪魔みたいな、聖書圏における正義と悪のパブリックイメージは全くの虚構であり、
本物の道理や真理を基準とするなら、儒学や仏教こそは正義である一方、聖書信仰はそれ自体が
丸ごと悪の塊である。カトリックや正教も含む聖書信仰全体が悪そのものであるとしたならば、
いま人々が考えているような悪のパブリックイメージからはいささかかけ離れていて、それらが悪で
ある一方、儒学や仏教のほうが正義であるという断定には、なかなか納得がいきにくいものと思われる。
聖書信仰全体の中には、それなりに良さげなことも掲げられている。
モーセの十戒のうちにも、父母への尊崇や強盗殺人の禁止などのまともな戒律が一応は含まれているし、
人々に平和をもたらす、繁栄をもたらすといった、本物の正義においても最終目的とされるような
預言までもが存在していたりする。それでいてやはり聖書信仰が丸ごと悪であるのは、それらの
よさげな教義が所詮は虚飾の綺麗事止まりで、その具体的な実践手段にも乏しく、結局全体としての
教義の信仰や実践を心がけた以上は、破滅や滅亡こそが呼び込まれるものでしかないからだ。
聖書教義中の美辞麗句なども、そのような災禍を知らず知らずの内に呼び込ませる偽証としての
役割しか果たしていない。偽証も偽証で悪質なものであり、聖書教義の劣悪さを取り繕うどころか、
その編纂姿勢からの卑劣さを加味しての、より一層の粗悪さを裏付けるものともなっている。
それでもあえてそれを文面におこしたなら、それは、四書五経や仏典のようになる。
文面におこそうと思えばおこせるのは、道理や真理にも少なからず「一概」な側面があるからで、
一概さが備わっているからには、その一概さを反転させることができる。たとえば、
道理でも真理でも是とされる理念に「中正(中庸、中道)」があるが、中正の反対には
両極端がある。中正に対して一概であることが理に適うのとは反対に、両極端であることに
対して一概であることが理に反することともなる。そうして道理や真理に反する「悪」が生ずる。
悪は正理の反対を行っているわけだから、意外と正理にも似ていたりする。
天使と悪魔みたいな、聖書圏における正義と悪のパブリックイメージは全くの虚構であり、
本物の道理や真理を基準とするなら、儒学や仏教こそは正義である一方、聖書信仰はそれ自体が
丸ごと悪の塊である。カトリックや正教も含む聖書信仰全体が悪そのものであるとしたならば、
いま人々が考えているような悪のパブリックイメージからはいささかかけ離れていて、それらが悪で
ある一方、儒学や仏教のほうが正義であるという断定には、なかなか納得がいきにくいものと思われる。
聖書信仰全体の中には、それなりに良さげなことも掲げられている。
モーセの十戒のうちにも、父母への尊崇や強盗殺人の禁止などのまともな戒律が一応は含まれているし、
人々に平和をもたらす、繁栄をもたらすといった、本物の正義においても最終目的とされるような
預言までもが存在していたりする。それでいてやはり聖書信仰が丸ごと悪であるのは、それらの
よさげな教義が所詮は虚飾の綺麗事止まりで、その具体的な実践手段にも乏しく、結局全体としての
教義の信仰や実践を心がけた以上は、破滅や滅亡こそが呼び込まれるものでしかないからだ。
聖書教義中の美辞麗句なども、そのような災禍を知らず知らずの内に呼び込ませる偽証としての
役割しか果たしていない。偽証も偽証で悪質なものであり、聖書教義の劣悪さを取り繕うどころか、
その編纂姿勢からの卑劣さを加味しての、より一層の粗悪さを裏付けるものともなっている。
聖書信仰は、本物の善悪正邪を覆い隠す。そうして人々に悪逆非道を推進させるから、
誰も悪を悪とわきまえながら悪を為すようなことからしてない。だから悪ではないのではなく、
だからこそ真性の悪である。悪を悪だとわきまえながら悪を為すなんてことは人間には
不可能で、未だそのわきまえが疎かである限りにおいて悪行もまた推進されるものなのだから。
聖書信仰が未だ黙認されている現状の世界において、本物の正邪善悪は誰にもわきまえられていない。
正義も悪もいくらでも唱えられているというのに、誰一人として正義や悪の正体を見据えられてはいない。
だからまず、「誰も本物の正邪善悪を知らない」という前提に立ち返った上で、正しい善悪のわきまえを
養っていくべきだといえる。まず善悪を論ずるのではなく、未だ誰も善悪などわきまえられていないことを
思い知ることからやり直す。聖書信仰がもたらした史上最悪の災禍からの脱却も、そこからのみ可能となる。
「夫れ天は、未だ天下を平治するを欲せざるなり。如し天下を平治するを
欲すれば、今の世に当たりて我れを舍きて其れ誰ぞや。吾れ何為れぞ不予ならんや」
「天は未だにこの天下を平安に統治することを望んでおられない。もしも天下を平安に統治することを
望まれたなら、今の世で自分をおいて他に適任な補佐者がいるだろうか。どうしてめげたりする必要があろうか。
(天地懸隔、天道が是とも非ともなる実情をつぶさにわきまえてこそ、不遇にもめげない強さが養われる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・公孫丑章句下・一三より)
誰も悪を悪とわきまえながら悪を為すようなことからしてない。だから悪ではないのではなく、
だからこそ真性の悪である。悪を悪だとわきまえながら悪を為すなんてことは人間には
不可能で、未だそのわきまえが疎かである限りにおいて悪行もまた推進されるものなのだから。
聖書信仰が未だ黙認されている現状の世界において、本物の正邪善悪は誰にもわきまえられていない。
正義も悪もいくらでも唱えられているというのに、誰一人として正義や悪の正体を見据えられてはいない。
だからまず、「誰も本物の正邪善悪を知らない」という前提に立ち返った上で、正しい善悪のわきまえを
養っていくべきだといえる。まず善悪を論ずるのではなく、未だ誰も善悪などわきまえられていないことを
思い知ることからやり直す。聖書信仰がもたらした史上最悪の災禍からの脱却も、そこからのみ可能となる。
「夫れ天は、未だ天下を平治するを欲せざるなり。如し天下を平治するを
欲すれば、今の世に当たりて我れを舍きて其れ誰ぞや。吾れ何為れぞ不予ならんや」
「天は未だにこの天下を平安に統治することを望んでおられない。もしも天下を平安に統治することを
望まれたなら、今の世で自分をおいて他に適任な補佐者がいるだろうか。どうしてめげたりする必要があろうか。
(天地懸隔、天道が是とも非ともなる実情をつぶさにわきまえてこそ、不遇にもめげない強さが養われる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・公孫丑章句下・一三より)
自らの拠り所とするものが絶対的であることにかまけて驕り高ぶったりすることは、
女子供のような依存的傾向の強い者ですらもが、なるべく避けるべきことだといえる。
漢の呂后や淀殿のような、自らの夫が強大であることの嵩にかかって悪女ぶりを発揮した
歴史上の女も居るように、依存性を高めることによってこそ深刻化する驕りというものがある。
男であってもそれはあり得ることで、邪教の虚構神への依存によって驕り高ぶることもその一つである。
しかしたとえば、邪教信仰が正統な神仏への崇敬によってそれなりに抑制されているこの日本において
ですら、依存的傾向を強めて驕りを募らせる男というのがかなり居る。それらの男は神でも仏でもなく、
立憲制によって絶対化された「法権」を嵩にかかって偉ぶっている。特に分かりやすいのは現今の
腐敗甚だしい警察官などだが、ただの民間の企業社員などであっても、憲法27条に明記されて
いる「労働の義務」を自分が果たせていることなどに基づいて驕り高ぶったりする。これもまた、
一人前であるはずの男が、何らかの絶対的存在への精神的依存によって驕りを募らせた例だといえる。
一国における主君への忠義なども、時には隷従とすり替えられての驕りに発展してしまうことがある。
戦前の大日本帝国における権力者の驕りなどもその例で、主君たる天皇陛下への忠節に励むということを
口実に、自制を放棄してのやりたい放題に及んでいった。そうではなく、主君のために自ら自主性を持って
事業に務めることが真の忠義にもなるのであり、そこは奴隷的服従などとも混同してはならない部分だといえる。
実際問題として、この世界、この宇宙に絶対的な超越神などはいない。そんなものは存在しないから、
自らが自主的な存在であることにこそ恭しさが伴わねばならない。ドイツ人哲学者のニーチェのように、
キリスト教徒ばりの依存症を持ち越したままで無神論者となり、永遠を結婚相手に見立てての
思い上がりに及んだりしたなら、それによって気が狂ってしまうことにすらなりかねない。
女子供のような依存的傾向の強い者ですらもが、なるべく避けるべきことだといえる。
漢の呂后や淀殿のような、自らの夫が強大であることの嵩にかかって悪女ぶりを発揮した
歴史上の女も居るように、依存性を高めることによってこそ深刻化する驕りというものがある。
男であってもそれはあり得ることで、邪教の虚構神への依存によって驕り高ぶることもその一つである。
しかしたとえば、邪教信仰が正統な神仏への崇敬によってそれなりに抑制されているこの日本において
ですら、依存的傾向を強めて驕りを募らせる男というのがかなり居る。それらの男は神でも仏でもなく、
立憲制によって絶対化された「法権」を嵩にかかって偉ぶっている。特に分かりやすいのは現今の
腐敗甚だしい警察官などだが、ただの民間の企業社員などであっても、憲法27条に明記されて
いる「労働の義務」を自分が果たせていることなどに基づいて驕り高ぶったりする。これもまた、
一人前であるはずの男が、何らかの絶対的存在への精神的依存によって驕りを募らせた例だといえる。
一国における主君への忠義なども、時には隷従とすり替えられての驕りに発展してしまうことがある。
戦前の大日本帝国における権力者の驕りなどもその例で、主君たる天皇陛下への忠節に励むということを
口実に、自制を放棄してのやりたい放題に及んでいった。そうではなく、主君のために自ら自主性を持って
事業に務めることが真の忠義にもなるのであり、そこは奴隷的服従などとも混同してはならない部分だといえる。
実際問題として、この世界、この宇宙に絶対的な超越神などはいない。そんなものは存在しないから、
自らが自主的な存在であることにこそ恭しさが伴わねばならない。ドイツ人哲学者のニーチェのように、
キリスト教徒ばりの依存症を持ち越したままで無神論者となり、永遠を結婚相手に見立てての
思い上がりに及んだりしたなら、それによって気が狂ってしまうことにすらなりかねない。
そうではなく、禅僧のように徹底的なしごきの下で己れの自意識過剰を叩き潰し、
恭しさの中にも恭しさを湛えられるようになってこそ、超越神など存在しないこの世界、
この宇宙における最前線の自主性を自らが保てるようにもなるのである。
自主性と恭しさとでの良循環を本体として、社会的には君臣関係や父子夫婦関係などの上下関係も嗜む。
そういう人間であってこそ、社会においても有益無害な功績を挙げられる可能性が生ずる。それとは逆に、
何かにかけて依存を全てとしているようならば、結局、害以上の益を産み出せたりするようなこともない。
自主性によってこそ恭しさが養われ、依存性によってこそ驕りを募らせることになる。
それが、この世界この宇宙の実相に即した人間性の法則である。この世に介在する人間としては、
自主的であることも依存的であることも実際に両方ともあり得ることだが、どちらかといえば
依存的であることよりも自主的であることのほうを尊ぶべきで、より自主性の高い男や大人を、
より依存性の高い女や子供よりも尊ぶなどの実践がそのために推奨されもするのである。
虚構の絶対神への強依存などを至尊としたなら、この位相はひっくり返ってしまうが、そしたら人間は
恭しさを萎縮させて驕り高ぶりを募らせるようになる。知ってるようでいて誰も知らない基本法則だといえる。
「四夷の左衽も、咸な頼らざるは罔く、予れ小子も永く多福を膺けん」
「四方の遠方に至る異族までもが、この周朝の徳を依り頼まないことがない。私もまたその多福を受けたい。
(周の康王の即位時の言葉。世界中の誰しもを禍いから守る以上に、多福に与らせる。また周の威徳がそれほど
ものものであればこそ、周の王こそは最終的にそのおこぼれに与る。志しの高さと遠慮とが尽くされている)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・畢命より)
恭しさの中にも恭しさを湛えられるようになってこそ、超越神など存在しないこの世界、
この宇宙における最前線の自主性を自らが保てるようにもなるのである。
自主性と恭しさとでの良循環を本体として、社会的には君臣関係や父子夫婦関係などの上下関係も嗜む。
そういう人間であってこそ、社会においても有益無害な功績を挙げられる可能性が生ずる。それとは逆に、
何かにかけて依存を全てとしているようならば、結局、害以上の益を産み出せたりするようなこともない。
自主性によってこそ恭しさが養われ、依存性によってこそ驕りを募らせることになる。
それが、この世界この宇宙の実相に即した人間性の法則である。この世に介在する人間としては、
自主的であることも依存的であることも実際に両方ともあり得ることだが、どちらかといえば
依存的であることよりも自主的であることのほうを尊ぶべきで、より自主性の高い男や大人を、
より依存性の高い女や子供よりも尊ぶなどの実践がそのために推奨されもするのである。
虚構の絶対神への強依存などを至尊としたなら、この位相はひっくり返ってしまうが、そしたら人間は
恭しさを萎縮させて驕り高ぶりを募らせるようになる。知ってるようでいて誰も知らない基本法則だといえる。
「四夷の左衽も、咸な頼らざるは罔く、予れ小子も永く多福を膺けん」
「四方の遠方に至る異族までもが、この周朝の徳を依り頼まないことがない。私もまたその多福を受けたい。
(周の康王の即位時の言葉。世界中の誰しもを禍いから守る以上に、多福に与らせる。また周の威徳がそれほど
ものものであればこそ、周の王こそは最終的にそのおこぼれに与る。志しの高さと遠慮とが尽くされている)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・畢命より)
妾腹の子として孔子を産んでしまった自らの不徳を恥じて、自分からは父親の身元を教えなかった
孔子の母親と、不倫ないし売春で夫以外の男の子供を身ごもってしまったために気が狂って幻覚を見、
その子供(イエス)を「神の子」だなどと思い込んでしまったマリアとでは、いずれもが不徳な母親では
あったにしても、その往生際の善し悪しに大差があったというもの。その母親からの影響が、孔子にも
イエキリにもなかったとは言えず、成長後の人生に多大な影響を及ぼしただろうことも確かである。
孔子の母親には言うべきでないことを言わない分別があったから、孔子も分別ある物言いを心がけるように
なったのだろうし、マリアがあることないことしゃべくる気狂いの虚言者であったればこそ、イエスもまた
あることないこと平気で駄弁りまくる虚言癖持ちのカルト教祖になってしまったのだろうとも考えられる。
母親の善し悪しについては、確かにイエスの母親のマリアこそは最悪の狂人であり、孔子の母親は
そこまではいかない分別の持ち主だっということが言える。しかし、孔子には育ての父親がいなかった一方、
イエスには育ての父親ともなった義父のヨセフがいた。そのヨセフへの孝悌によって自らの正気を育んで
いくこともできなくはなかったはずなのに、イエスはあえてそれを拒んだ。大工屋というヨセフの
生業の卑しさに嫌悪を抱いたのか知らないが、少なくとも自らがヨセフの系譜を継いだりすることを、
マリアの「神の子を身ごもった」という妄言にも味方するかたちで退けた。
孔子が若年の頃に、倉庫番や農牧者などのさして尊貴とも言えない仕事に従事して、
それでも任務を忠実にこなすことを旨としていたことが「孟子」万章章句下・五などにも記録されている。
そういう、与えられた立場に即して真摯でいる姿勢がイエスにも備わっていたなら、狂った母親の
「おまえは神の子だ」なんていう言い分も退けて、大工であるヨセフへの孝悌などにも尽くせたはずだが、
それができなかったのは、イエスに孔子並みの自主的な立場のわきまえが欠けていたからで、イエスが
マリアの狂気に取り込まれて自らまでもが狂人と化してしまったことにも、イエス自身の責任があるといえる。
孔子の母親と、不倫ないし売春で夫以外の男の子供を身ごもってしまったために気が狂って幻覚を見、
その子供(イエス)を「神の子」だなどと思い込んでしまったマリアとでは、いずれもが不徳な母親では
あったにしても、その往生際の善し悪しに大差があったというもの。その母親からの影響が、孔子にも
イエキリにもなかったとは言えず、成長後の人生に多大な影響を及ぼしただろうことも確かである。
孔子の母親には言うべきでないことを言わない分別があったから、孔子も分別ある物言いを心がけるように
なったのだろうし、マリアがあることないことしゃべくる気狂いの虚言者であったればこそ、イエスもまた
あることないこと平気で駄弁りまくる虚言癖持ちのカルト教祖になってしまったのだろうとも考えられる。
母親の善し悪しについては、確かにイエスの母親のマリアこそは最悪の狂人であり、孔子の母親は
そこまではいかない分別の持ち主だっということが言える。しかし、孔子には育ての父親がいなかった一方、
イエスには育ての父親ともなった義父のヨセフがいた。そのヨセフへの孝悌によって自らの正気を育んで
いくこともできなくはなかったはずなのに、イエスはあえてそれを拒んだ。大工屋というヨセフの
生業の卑しさに嫌悪を抱いたのか知らないが、少なくとも自らがヨセフの系譜を継いだりすることを、
マリアの「神の子を身ごもった」という妄言にも味方するかたちで退けた。
孔子が若年の頃に、倉庫番や農牧者などのさして尊貴とも言えない仕事に従事して、
それでも任務を忠実にこなすことを旨としていたことが「孟子」万章章句下・五などにも記録されている。
そういう、与えられた立場に即して真摯でいる姿勢がイエスにも備わっていたなら、狂った母親の
「おまえは神の子だ」なんていう言い分も退けて、大工であるヨセフへの孝悌などにも尽くせたはずだが、
それができなかったのは、イエスに孔子並みの自主的な立場のわきまえが欠けていたからで、イエスが
マリアの狂気に取り込まれて自らまでもが狂人と化してしまったことにも、イエス自身の責任があるといえる。
こうやって、東洋随一の聖人君子である孔子の経歴とも丹念に照らし合わせてみればこそ、
イエスもまた決して悲劇の人というばかりではなく、自業自得で非業を呼び込んだならず者でもあった
ことが明らかになる。ただイエスやマリアの行業にしか目を向けないのならそこまでは察知できず、
ただ新約の物語構造の非業さ加減に打ちひしがれて、恐れおののくぐらいのことしかできなかったりする。
比較対象としての孔子を知らない内には、イエスを信奉してしまったとしても仕方がないほどに、
新約の物語構造は偽善劇として巧妙である。だから今までにイエスを信奉してしまったことを過失と
見なしても妥当だといえるが、こうしてイエスのならず者さ加減や、新約の物語構造の化けの皮が
剥がされたからには、もはやイエスや新約を信奉の対象などにすることも一切許されることはない。
未だ人口に膾炙するような形での情報発表を尽くしているわけではないから、聖書信仰に完全な歯止めを
かけることにも今少しの時間はかかるかも知れないが、理論的に証明された以上は、証明されていなかった
頃に立ち戻るなどということももはやない。人類の未来はもはや、聖書信仰が絶えていく方向にしかない。
「人、道を弘むに能う。道、人を弘むるに非ざるなり」
「人間自身のみが正道を弘めていくことができる。正道が道を弘めていくことなどはできない。
(外力によって何かをしてやれる神などには、永久に不可能なことである。実在しないとはいえ、
マリアはそのような妄想上の邪神にすがり、イエスもまたそのような悪癖をあえて継いだのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・衛霊公第十五・二九より)
イエスもまた決して悲劇の人というばかりではなく、自業自得で非業を呼び込んだならず者でもあった
ことが明らかになる。ただイエスやマリアの行業にしか目を向けないのならそこまでは察知できず、
ただ新約の物語構造の非業さ加減に打ちひしがれて、恐れおののくぐらいのことしかできなかったりする。
比較対象としての孔子を知らない内には、イエスを信奉してしまったとしても仕方がないほどに、
新約の物語構造は偽善劇として巧妙である。だから今までにイエスを信奉してしまったことを過失と
見なしても妥当だといえるが、こうしてイエスのならず者さ加減や、新約の物語構造の化けの皮が
剥がされたからには、もはやイエスや新約を信奉の対象などにすることも一切許されることはない。
未だ人口に膾炙するような形での情報発表を尽くしているわけではないから、聖書信仰に完全な歯止めを
かけることにも今少しの時間はかかるかも知れないが、理論的に証明された以上は、証明されていなかった
頃に立ち戻るなどということももはやない。人類の未来はもはや、聖書信仰が絶えていく方向にしかない。
「人、道を弘むに能う。道、人を弘むるに非ざるなり」
「人間自身のみが正道を弘めていくことができる。正道が道を弘めていくことなどはできない。
(外力によって何かをしてやれる神などには、永久に不可能なことである。実在しないとはいえ、
マリアはそのような妄想上の邪神にすがり、イエスもまたそのような悪癖をあえて継いだのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・衛霊公第十五・二九より)
「幸せ」を求めない
http://bbs0.meiwasuisan.com/bbs/bin/read/toriaezu/13462310...
幸いは、最悪かマシか、死刑か奴隷化かといった最悪状態での切り抜けを意味する。
モンゴル帝国が全世界に派遣を拡大させていった時にも、殺されるか、
さもなくば奴隷になるかという強要によって異民族を屈服させていた。
それによって征服下に置かれ、奴隷として何とか生き延びた人間の末裔が今の
中国人だったりするから、古代にはなかったような卑屈さをどこか帯びていたりもする。
大日本帝国において欧米列強と奮闘し、討ち死にした日本人は誇りを保てたのかも
しれないが、最終的に米英らに敗戦して支配下に置かれた今の日本人たるや、
民族としての誇りなどは皆無に等しい状態ともなってしまっている。
そんな、何とか今まで生き延びてきた中国人や日本人こそは、幸いでもある。
モンゴル帝国や米英に屈従してでも生き延びたが故に、殺された人間などよりも幸い。
幸いだが、そんなことを嬉しがる日本人や中国人も居はしない。ただ恥を忍んで生き延びた
ばかりのことで、むしろ戦って殺された人々に対するコンプレックスを抱いてすらいる。
米英やモンゴル帝国が、「殺すか奴隷にするか」みたいな粗悪な流儀によって世界中へと
覇権を拡大させていったことからして、あるよりもないほうがマシな災禍でしかなかった。
それによって死んだ人間も、隷従して生き延びた人間も、ないほうがマシな危害を被ったのみ。
しかしそもそも、欧米キリスト教圏やモンゴルからして、「不幸か幸いか」しかない社会だった。
キリスト教圏がそうであるのは聖書に書いてある通りだし、モンゴル地域もまた子が親を殺し、
同族間で奪い合い殺し合うことも辞さない状態であり続けていることが、古代の
北方民族である匈奴の「史記」や「漢書」などにおける記録からも明らかである。
http://bbs0.meiwasuisan.com/bbs/bin/read/toriaezu/13462310...
幸いは、最悪かマシか、死刑か奴隷化かといった最悪状態での切り抜けを意味する。
モンゴル帝国が全世界に派遣を拡大させていった時にも、殺されるか、
さもなくば奴隷になるかという強要によって異民族を屈服させていた。
それによって征服下に置かれ、奴隷として何とか生き延びた人間の末裔が今の
中国人だったりするから、古代にはなかったような卑屈さをどこか帯びていたりもする。
大日本帝国において欧米列強と奮闘し、討ち死にした日本人は誇りを保てたのかも
しれないが、最終的に米英らに敗戦して支配下に置かれた今の日本人たるや、
民族としての誇りなどは皆無に等しい状態ともなってしまっている。
そんな、何とか今まで生き延びてきた中国人や日本人こそは、幸いでもある。
モンゴル帝国や米英に屈従してでも生き延びたが故に、殺された人間などよりも幸い。
幸いだが、そんなことを嬉しがる日本人や中国人も居はしない。ただ恥を忍んで生き延びた
ばかりのことで、むしろ戦って殺された人々に対するコンプレックスを抱いてすらいる。
米英やモンゴル帝国が、「殺すか奴隷にするか」みたいな粗悪な流儀によって世界中へと
覇権を拡大させていったことからして、あるよりもないほうがマシな災禍でしかなかった。
それによって死んだ人間も、隷従して生き延びた人間も、ないほうがマシな危害を被ったのみ。
しかしそもそも、欧米キリスト教圏やモンゴルからして、「不幸か幸いか」しかない社会だった。
キリスト教圏がそうであるのは聖書に書いてある通りだし、モンゴル地域もまた子が親を殺し、
同族間で奪い合い殺し合うことも辞さない状態であり続けていることが、古代の
北方民族である匈奴の「史記」や「漢書」などにおける記録からも明らかである。
不幸か幸いかのいずれかでしかあり得ない社会というのは、それ以上の多福を追い求める
余地のある社会と比べて、総体的に、不幸か幸いかのうちの「不幸」の部類に入ってしまう。
争いによって外界を制覇して勝ち誇ったりした所で、自分たちが不幸か幸いかでしか
あり得ない以上は、所詮は清潔な世界にまでゴミを撒き散らしただけでしかなかった、
不幸まみれな自分たちの行状の真相に、いつかは気づいて打ちひしがれるしかない。
モンゴル帝国の場合は、自分たちがチベット仏教に帰依することでその恥をすすいだ。
欧米キリスト教勢力も結局は、仏教あたりへの帰依によって今までの汚辱を清算することに
なるのだろうが、自分たちで特段独自の信教を持ち合わせているわけでもなかったモンゴル人
と比べて、キリスト教徒には自分たちの信教がある。その信教を捨ててまで恥をすすぐ必要が
あるのは、モンゴル人などにはなかった障壁だといえ、より一層の思い切りが必要ともされる。
人類史上、全世界規模の覇権が掌握されることは、モンゴル帝国とキリスト教勢力とで最低二度
あった。しかいずれもが覇権止まりで、全世界が威徳ある王権によって統治された試しは未だない。
「三度目の正直」があるかないかは、世界規模の覇権主義の不実さが二度にわたって実証された
これからにこそ明らかになり得る。覇権はただのゴミの撒き散らし止まりだったが、王権は果たして。
「善人上に在れば、則ち国に幸民無し。
諺に曰く、民之の幸多きは、国の不幸なりと。是れ善人之り無きを謂うなり」
「善人が政治を執れば、国に幸いを乞い求める民がいなくなる。古語に『民に幸いを求める
者が多いのは、国が不幸である証拠だ』とあるのも、善人が政治を執っていないことを意味する。
(人々に幸いに与ることをけしかけるからには、国家社会規模での不幸を画策しているのだろう)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・宣公十六年より)
余地のある社会と比べて、総体的に、不幸か幸いかのうちの「不幸」の部類に入ってしまう。
争いによって外界を制覇して勝ち誇ったりした所で、自分たちが不幸か幸いかでしか
あり得ない以上は、所詮は清潔な世界にまでゴミを撒き散らしただけでしかなかった、
不幸まみれな自分たちの行状の真相に、いつかは気づいて打ちひしがれるしかない。
モンゴル帝国の場合は、自分たちがチベット仏教に帰依することでその恥をすすいだ。
欧米キリスト教勢力も結局は、仏教あたりへの帰依によって今までの汚辱を清算することに
なるのだろうが、自分たちで特段独自の信教を持ち合わせているわけでもなかったモンゴル人
と比べて、キリスト教徒には自分たちの信教がある。その信教を捨ててまで恥をすすぐ必要が
あるのは、モンゴル人などにはなかった障壁だといえ、より一層の思い切りが必要ともされる。
人類史上、全世界規模の覇権が掌握されることは、モンゴル帝国とキリスト教勢力とで最低二度
あった。しかいずれもが覇権止まりで、全世界が威徳ある王権によって統治された試しは未だない。
「三度目の正直」があるかないかは、世界規模の覇権主義の不実さが二度にわたって実証された
これからにこそ明らかになり得る。覇権はただのゴミの撒き散らし止まりだったが、王権は果たして。
「善人上に在れば、則ち国に幸民無し。
諺に曰く、民之の幸多きは、国の不幸なりと。是れ善人之り無きを謂うなり」
「善人が政治を執れば、国に幸いを乞い求める民がいなくなる。古語に『民に幸いを求める
者が多いのは、国が不幸である証拠だ』とあるのも、善人が政治を執っていないことを意味する。
(人々に幸いに与ることをけしかけるからには、国家社会規模での不幸を画策しているのだろう)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・宣公十六年より)
 古代オリエント文明の遺跡に刻まれた文字列なども、解読してみれば、
古代オリエント文明の遺跡に刻まれた文字列なども、解読してみれば、 どうということもないような内容のものばかりであることがすでに知られている。
そこに精神文化としての秀逸さなどはなく、かえって俗悪な文化ばかりが
当時の社会にもすでに根付いていたことが明らかとなっている。
ヘブライ文化や西洋文化も、その古代オリエント文化の系譜を汲む文化であり、
精神文化として特に優れているようなことは全くない一方で、俗悪さを極めることにかけては、
確かに東洋文化が忌避するような技巧が尽くされている。新旧約聖書や諸々の西洋古典も
そのような俗悪な文化を文章におこしたものであり、確かにそれによって金融物質主義的な
卑俗さを発展させていくことはできるが、何ら人間精神の洗練に与したりすることはない。
古代オリエントの豪華絢爛な遺跡と比べれば、随分と矮小であるインドのモヘンジョダロ遺跡
などは、矮小ながらにもインド独特の風水(バーストゥ・シャーストラ)を理念とした設計が
施されていて、その設計理念は寺院を始めとする東洋中の仏教建築にも受け継がれている。そして
ヴェーダやウパニシャッドや仏典といった、インド古典にもその理念は巧妙に埋め込まれていて、
俗悪さを排し、悟りを得た明鏡止水の境地こそを文明化していく指針としての価値をも帯びている。
しかしたとえば、仏教建築のうちでも浄土系の寺の堂内の造形などには、相当に卑俗なものもある。
内陣はキンキラキンに塗りたくられ、天井には数多の天女が待っているような下世話な造形は、
それこそ古代オリエントこそを源流とする西方浄土思想に根ざしたもの。浄土教を含む仏教全般
において提示されている「地獄」という観念もまた、元はといえば古代オリエントの発祥である。
仏教はそういった、古代オリエント発祥の俗悪文化も丸ごと飲み込んだ上での精神文化の
洗練を旨としているため、相当に清濁併せ飲んでもいる。ほとんど清濁を併せ飲んですらいない、
清浄一辺倒なのが日本の神道文化などで、部分的には古代中国の祭祀文化なども受け継いではいるが、
あまりにも清浄一辺倒であるために、すでに中国での伝統は絶えて、日本にのみ残るものとなってもいる。
「文化」にかけては、より精神性の洗練されたものこそを貴び、そうでないものを卑しむように
すべきだが、カネやモノの魔性を最大級に増幅してくれるのは、かえって俗悪な文化のほうである。
西洋文明こそは東洋文明よりも物質的に豊満だし、東洋においても、精神性の重視に特化された
神道文化がとっくの昔に中国では滅びるなど、洋の東西を問わず精神文化こそは「脆弱」である。
カネやモノを第一とする俗悪な文化によってこそ、古来から人々は自業自得の苦悩を募らせて来た。
始めからそのような俗悪な文化を退けて、高尚な文化にのみ与ればいいものを、カネやモノの魔性に
囚われて結局は俗悪な文化ばかりを貪り、そのせいであえて高尚な文化を退けてきてもしまった。
そのような、自業自得での苦難を呼び込む俗悪文化の、ここ2000年来の根幹となっているのは、
西洋文化のうちでも特に唯一無二とされる聖書文化でこそある。そのことは素直に認めた上で、
世界中を俗悪さの洪水で飲み込み尽くした後のけじめとして、思い切って聖書文化から捨て去る。
それがいま必要とされていることである上に、実現できたなら、極めて好ましいことでもある。
古代オリエントを源流とする物質主義的文化が、精神的に優れていたなんてことは一貫して
なかったのだから、数千年来の悪癖から人類が解放される、吉事中の吉事になるといえる。
洗練を旨としているため、相当に清濁併せ飲んでもいる。ほとんど清濁を併せ飲んですらいない、
清浄一辺倒なのが日本の神道文化などで、部分的には古代中国の祭祀文化なども受け継いではいるが、
あまりにも清浄一辺倒であるために、すでに中国での伝統は絶えて、日本にのみ残るものとなってもいる。
「文化」にかけては、より精神性の洗練されたものこそを貴び、そうでないものを卑しむように
すべきだが、カネやモノの魔性を最大級に増幅してくれるのは、かえって俗悪な文化のほうである。
西洋文明こそは東洋文明よりも物質的に豊満だし、東洋においても、精神性の重視に特化された
神道文化がとっくの昔に中国では滅びるなど、洋の東西を問わず精神文化こそは「脆弱」である。
カネやモノを第一とする俗悪な文化によってこそ、古来から人々は自業自得の苦悩を募らせて来た。
始めからそのような俗悪な文化を退けて、高尚な文化にのみ与ればいいものを、カネやモノの魔性に
囚われて結局は俗悪な文化ばかりを貪り、そのせいであえて高尚な文化を退けてきてもしまった。
そのような、自業自得での苦難を呼び込む俗悪文化の、ここ2000年来の根幹となっているのは、
西洋文化のうちでも特に唯一無二とされる聖書文化でこそある。そのことは素直に認めた上で、
世界中を俗悪さの洪水で飲み込み尽くした後のけじめとして、思い切って聖書文化から捨て去る。
それがいま必要とされていることである上に、実現できたなら、極めて好ましいことでもある。
古代オリエントを源流とする物質主義的文化が、精神的に優れていたなんてことは一貫して
なかったのだから、数千年来の悪癖から人類が解放される、吉事中の吉事になるといえる。
「公曰く、敢えて問う、何をか身を成すと謂う。孔子對えて曰く、物に過ぎざるなり。
公曰く敢えて問う、君子何をか天道を尊ぶや。孔子對えて曰く、其れ已まざるを尊ぶ。日月は東西相い従いて
已まざるが如し、是れ天道なり。閉じずして其れ久し、是れ天道なり。〜仁人は物に過ぎず、孝子は物に過ぎず。
是の故に、仁人の親に事うるや天に事うるが如く、天に事うるや親に事うるが如し。是の故に孝子は身を成す」
「哀公が孔子に問うた。『身を成すとはどういうことであろう』 孔子は答えた。『事物の理に合致して離れぬことを言います』
哀公。『君子はなぜ天道を尊ぶのか』 孔子。『天道はいつまでも止むことがありません。そのために尊ぶのです。
日月の軌道は東西に巡って決して止むことがありません、これが天道です。閉じることもなく久しい、これが天道です。
仁人や孝子は事物の理に合致して、決して逸脱することがありません。そのため仁人が親に仕える姿たるや、まるで
天道に仕えるが如くであり、天道に使える姿もまた、親に仕えるが如くであります。そうして孝子もまた身を成すのです』
(事物の理に合致して逸脱することのない仁人や孝子たれば、天道が永遠であるが如く、成道もまた永遠となる。
それは、久しくして止まぬ、太陽や月の運行の下でこそ計り知られることでもある)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・哀公問第二十七より)
公曰く敢えて問う、君子何をか天道を尊ぶや。孔子對えて曰く、其れ已まざるを尊ぶ。日月は東西相い従いて
已まざるが如し、是れ天道なり。閉じずして其れ久し、是れ天道なり。〜仁人は物に過ぎず、孝子は物に過ぎず。
是の故に、仁人の親に事うるや天に事うるが如く、天に事うるや親に事うるが如し。是の故に孝子は身を成す」
「哀公が孔子に問うた。『身を成すとはどういうことであろう』 孔子は答えた。『事物の理に合致して離れぬことを言います』
哀公。『君子はなぜ天道を尊ぶのか』 孔子。『天道はいつまでも止むことがありません。そのために尊ぶのです。
日月の軌道は東西に巡って決して止むことがありません、これが天道です。閉じることもなく久しい、これが天道です。
仁人や孝子は事物の理に合致して、決して逸脱することがありません。そのため仁人が親に仕える姿たるや、まるで
天道に仕えるが如くであり、天道に使える姿もまた、親に仕えるが如くであります。そうして孝子もまた身を成すのです』
(事物の理に合致して逸脱することのない仁人や孝子たれば、天道が永遠であるが如く、成道もまた永遠となる。
それは、久しくして止まぬ、太陽や月の運行の下でこそ計り知られることでもある)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・哀公問第二十七より)
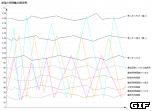 それを好き好んで得ようとするものに限って「摂取不捨」となるのが完全誤謬であるのに対し、
それを好き好んで得ようとするものに限って「摂取不捨」となるのが完全誤謬であるのに対し、 好むと好まざるとに関わらず、悟ってしまった以上は摂取不捨となるのが完全真理である。
そこは真理と誤謬とで決定的に異なる点であり、真理への悟りは拒んだところで二度と捨て
去れはしないのに対し、誤謬への惑溺は自分が拒みすらすればいつでも捨てられるものである。
仮に精神外科手術などによって、キリスト教レベルの劣悪教義にしか安住していられない
白痴状態を固定化してしまったとする。そしたらもう二度とキリスト信仰を拒絶することも
できなくなるわけだから、摂取不捨の強度が増すといえるが、その場合、悪知恵を駆使しての
キリスト信仰の体系的な実践も覚束なくなるため、害悪の度合いも皆無に帰することになる。
片やキリスト信仰による重度知的障害レベルへの知能退行を可能としながら、片や常人
以上の知能によって金融詐欺などの悪行に及び、不正な暴利をせしめることをも可能とする。
そういった、知能を乱高下させられる重度精神障害者のキリスト教徒であればこそ、信仰が
財物としての実利にも結び付く。ただ知能退行の酩酊に酔い痴れるだけでなく、高い知能を
駆使する能力もあればこそ、キリスト教圏が悪逆非道による勢力の拡大を推し進めていく
こともできたわけだが、残念ながら、その知能の高さこそが「善行は普遍的な安楽に結び付き、
悪行は普遍的な辛苦に結び付く」という、罪福異熟の絶対真理をも悟らざるを得なかったのである。
悪逆非道を可能とする高い知能を保つ以上は、悪因苦果に基づく自分たちの行いの惨めさに
気づかざるを得ない。一方で、そのような真理に気づかないでいようとしたなら、もう二度と
高い知能を駆使した悪行に及ぶことができない。ここが、キリスト信仰の頭打ち地点だといえる。
高知能を保てば不必要に苦しみ、低知能を固定化すれば廃人としての立場が決定的になる。
さすれば、キリスト信仰を保守するメリットなどはもはやどこにもない。今までも本当は
なかったが、これからはもう、信仰にメリットがあるかのように思い込んでいることすらできぬ。
イカサマで一方的に利益を巻き上げられ続けることが確実な違法賭博、キリスト信仰の実態は
そのようなもので、さっさとやめるに越したことはないが、博打中毒の心理に陥ってしまって
いるような人間には、それもなかなか難しい。博打を打つことそれ自体が脳内麻薬を分泌させて
くれるのが楽しいからやめられない。イカサマと分かっていてもやめられない、博打にかけての
バカであることが、当該の博打がイカサマであることへの冷静な認識を上回ってしまっている
ために、傍目には愚かしさ極まりない墓穴掘りを延々と続けるようなザマに陥ってしまっている。
「イカサマでしかない」という冷静な認識が、中毒状態からなるバカをほんの少しでも
上回れたなら、キリスト信仰をやめることだって実際にできる。真理はイカサマではないから、
そんな理由によって捨て去れはしないが、キリスト教教義は真理に違う完全誤謬だから、
誤謬であることに対する冷静な認識が、ほんの少しでも信仰狂いに打ち克てたなら、
キリスト信仰については、そういった手続きに即して確かに捨て去ることができる。
何の価値もないうえに害がある、しかもそうであることが理知によって完全に察知されて
しまっている。そこから目指すべきなのはもはや脱却のみで、これ以上の耽溺などであるはずもない。
そしてその手段は以上の如くであり、何一つとして不満や不足を唱える余地もないといえる。
「故旧、大故なければ、則ち棄てず」
「古くからの馴染みは、致命的に大きな過ちでもない限りは捨てない。
(キリスト信仰ももう2000近くの歴史を持つが、大きな過ちであったと
確認できたなら捨ててもよい。それが人道に根ざした分別ともなる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・微子第十八・一〇より)
そのようなもので、さっさとやめるに越したことはないが、博打中毒の心理に陥ってしまって
いるような人間には、それもなかなか難しい。博打を打つことそれ自体が脳内麻薬を分泌させて
くれるのが楽しいからやめられない。イカサマと分かっていてもやめられない、博打にかけての
バカであることが、当該の博打がイカサマであることへの冷静な認識を上回ってしまっている
ために、傍目には愚かしさ極まりない墓穴掘りを延々と続けるようなザマに陥ってしまっている。
「イカサマでしかない」という冷静な認識が、中毒状態からなるバカをほんの少しでも
上回れたなら、キリスト信仰をやめることだって実際にできる。真理はイカサマではないから、
そんな理由によって捨て去れはしないが、キリスト教教義は真理に違う完全誤謬だから、
誤謬であることに対する冷静な認識が、ほんの少しでも信仰狂いに打ち克てたなら、
キリスト信仰については、そういった手続きに即して確かに捨て去ることができる。
何の価値もないうえに害がある、しかもそうであることが理知によって完全に察知されて
しまっている。そこから目指すべきなのはもはや脱却のみで、これ以上の耽溺などであるはずもない。
そしてその手段は以上の如くであり、何一つとして不満や不足を唱える余地もないといえる。
「故旧、大故なければ、則ち棄てず」
「古くからの馴染みは、致命的に大きな過ちでもない限りは捨てない。
(キリスト信仰ももう2000近くの歴史を持つが、大きな過ちであったと
確認できたなら捨ててもよい。それが人道に根ざした分別ともなる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・微子第十八・一〇より)
死を闇とみなし、生を栄光と見なして、闇への恐怖を原動力とした
盲滅法な生を貪ろうとするから、そういった者同士での争いまでもが生ずる。
思い切って生こそを闇と見なし、死こそを光と見なしてしまう。
それにより暗愚な生を切り抜けての明るい死こそを目指す。
それぐらいのほうが、高い知能によって「個体の死」というものを
察知してしまっている人間のような生き物にとっては、適切なあり方ともなる。
もちろん、生が闇だからといって暗愚な生ばかりに専らでいようと
するのではなく、栄光の死に向けたなりの生をも送ればよい。
生きてる間の放辟邪侈ばかりに專らでいたなら、後世に笑いものにすら
なりかねない一方、未来永劫にわたって人々に好影響を及ぼし続けるような
偉大な功績を挙げたなら、それにより死後に至るまでの名声が得られるというもの。
その死後の名声も、自らの子孫の繁栄などの実利的価値を帯びもするわけで、
生きてる内から個体の生死を超えた大偉業を志すことにも、確かな意味があるのだと言える。
「どうせ死後に渡るまで評価されるような偉業を挙げた所で、自分自身には
何の利益もないじゃないか」と、重度の個人主義者であれば考えるのに違いない。
子々孫々の代々に至るまでの、自らの系譜の継承などにもさして価値を見い出せず、
とにかく自分が生きてるうちにどれだけ幸せでいられるかばかりを全てとしているのだから。
盲滅法な生を貪ろうとするから、そういった者同士での争いまでもが生ずる。
思い切って生こそを闇と見なし、死こそを光と見なしてしまう。
それにより暗愚な生を切り抜けての明るい死こそを目指す。
それぐらいのほうが、高い知能によって「個体の死」というものを
察知してしまっている人間のような生き物にとっては、適切なあり方ともなる。
もちろん、生が闇だからといって暗愚な生ばかりに専らでいようと
するのではなく、栄光の死に向けたなりの生をも送ればよい。
生きてる間の放辟邪侈ばかりに專らでいたなら、後世に笑いものにすら
なりかねない一方、未来永劫にわたって人々に好影響を及ぼし続けるような
偉大な功績を挙げたなら、それにより死後に至るまでの名声が得られるというもの。
その死後の名声も、自らの子孫の繁栄などの実利的価値を帯びもするわけで、
生きてる内から個体の生死を超えた大偉業を志すことにも、確かな意味があるのだと言える。
「どうせ死後に渡るまで評価されるような偉業を挙げた所で、自分自身には
何の利益もないじゃないか」と、重度の個人主義者であれば考えるのに違いない。
子々孫々の代々に至るまでの、自らの系譜の継承などにもさして価値を見い出せず、
とにかく自分が生きてるうちにどれだけ幸せでいられるかばかりを全てとしているのだから。
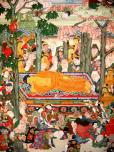 だからこそ、後世の笑い者になるような放辟邪侈にも及び、まるで暗愚な生の典型
だからこそ、後世の笑い者になるような放辟邪侈にも及び、まるで暗愚な生の典型 のような生ばかりを貪った挙句に死ぬ。そしてそのような人生を送った人間こそは、
死こそが闇であるかのようにも考える。本当は生きてる内こそが人並み以上の暗闇であり、
その暗闇から死によって解き放たれるのですらあるのに、自らの生こそが自業自得の
暗闇であった責任を死に擦り付け、死こそが闇であるかのように決め付ける。そうして
死を憎み、栄光としての生をより一層に追い求めようとするが、そのような人間が追い
求めている生こそは生粋の暗愚な生でもあるのだから、どこにも光の差し込む余地がない。
光を追い求めているつもりで、実はより一層の暗闇を追い求めてしまっているような
悪循環に陥ってしまっている人間ともなれば、死後に至るまでの栄光のような、
真の光を追い求めることに即座に鞍替えすることも覚束ない。まずは自分たちの
明暗に対する認知が転倒していることを悟って、その転倒を是正していくところ
から始めなければならない。主体的に光を追い求めることはまだ人に譲り、まず闇を
追い求める悪癖を癒すことから専念していく。そういった役割分担が必要となっていく。
「禹崩じ、三年の喪畢りて、益、禹の子を箕山の陰に避く。朝覲訟獄する者、益に
之かずして啓に之く。曰く、吾が君の子なりと。謳歌する者は益を謳歌せずして啓を謳歌す」
「夏の禹王が崩じて後、三年の喪が終わり、禹王の重臣だった益は禹の子の啓を箕山の陰に
追いやった。すると、拝謁するものも訴訟を請う者もみな益を避けて啓の所に通うようになった。
みな『啓こそは我が君の子ではないか』と称え、益の世を謳歌せずに啓の世を謳歌した。
(居場所の陰陽などどてはなく、自らの徳の有無が雌雄を決した例)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・万章章句上・六より)
 「漢書」食貨志などを読んでみても、漢の治世中、民が土に安んじて本業(農業など)に
「漢書」食貨志などを読んでみても、漢の治世中、民が土に安んじて本業(農業など)に 励んでいる頃には国レベルでの収支が安定し、蓄積も十分となったのに対し、
流民が増大して末業(商業など)ばかりを興じるようになった頃には、
国富が不足して餓え死ぬ民までもが頻発するようになったとある。
だから君子階級でもないような一般民が無闇に遠出することを推奨したりすべきではないし、
さらには為政者こそが必要もなく民を方々へと引きずり回すともなれば、なおさらのことである。
だからこそ昔の東洋の封建社会では、関所を設けて民の自由な往来に一定の制限をかけるなどしていた。
一方で、君子階級こそは科挙としての登用や参勤交代などを通じて中央と地方を頻繁に往来し、
諸国を皇帝や将軍の十分な統制下に置く助っ人としての役割をも発揮していた。
為政者は腰が軽く、民は腰が重いというのが、社会的な陽唱陰和の実現の上でも格好となり、
民をよく土着させて下手な往来をも思い止まらせられたなら、なにも全住民を戸籍登録し
尽くしたりする必要もない。関所による往来管理も厳粛だった江戸時代にこそ、無戸籍の
漂泊民などの存在も多少は容認されていたのに対し、関所も撤廃されて行商の往来なども
無制限と化した明治以降にこそ、全国民に対する住民登録が必須なものともなった。
民主主義社会において、民こそは諸国の往来なども勝手気ままに行える自由の徒となるのに対し、
為政者こそは地元の組織票みたいな、ある種の限られた勢力による拘束を被る存在となる。結果、
民間人の政商や悪徳外交家こそが国家権力以上もの権能を手に入れるようなことにもなりかねず、
そのような事態を来たした時にこそ、もはや世界レベルでの大破綻までもが逃れられるものではない。
中東地域のような、農産も覚束ない不毛の地に暮らす者が、シルクロード交易のような商業によって
食いつなぐことは不可避なことでもあるにしろ、モンスーン気候の東洋社会や、欧米社会のような、
土着による自活が可能である地域においてまで流民をのさぱらせるのは余計なことであり、
その程度があまりにもひどければ、上に書いたような理由での大破綻すらもが免れられない。
農産技術と交通機関が共に発展した近代社会において、かつての東洋的封建社会ほどもの
徹底的な民の土着や鎖国政策が敷かれるべきだとも断定できないが、少なくともこの地球上
から餓死者がいなくなる程度にまでは、民の身勝手な放浪にも制限をかけるべきだといえる。
具体的にどのくらいかといえば、やはり民間人のフットワークが為政者のフットワークを
下回る程度までだといえる。そしたら世界規模での財政破綻が回避できて、その結果として
飢餓や戦乱のような社会問題も未然に防がれるようになる。いくら文明が進歩しようとも、
為政者こそが民の一歩先を行くべきだという陰陽法則までもが破綻することはないのである。
「梁の恵王曰く、寡人の国に於けるや、心を尽くせるのみ。河内凶すれば、
則ち其の民を河東に移し、其の粟を河内に移す。河東凶せるも亦た然り。隣国の政を察するに、
寡人の心を用うるに如く者無し。隣国の民少なきを加えず、寡人の民多きを加えざるは何ぞや」
「梁の恵王が孟子に問うた。『わしのこの国に対する姿勢は、ただ心を尽くすというばかりのものだ。
もし河内地方が飢えるようなことがあればその民を河東に移し、河東からも支援の穀類を河内に運ばせる。
河東が飢えた場合にもこの逆の対策を施す。周りの国を見ても、これほどにも内政に心を尽くしている国は
ないというのに、周りの国の民が減ることもなければ、わしの国の民が増えることもないのはなぜだろう』
(このあと孟子が指摘するとおり、恵王は農繁期や斧斤時もお構いなしに民を身勝手に引きずり回しているから、
そのせいで自分こそが飢饉を引き起こしてしまっている。住民登録のために帝国の民を引きずり回して、ろくに
その宿場も用意しなかった皇帝アウグストゥスなども、この恵王並みかそれ以上の暗君だったことだろう)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・梁恵王章句上・三より)
徹底的な民の土着や鎖国政策が敷かれるべきだとも断定できないが、少なくともこの地球上
から餓死者がいなくなる程度にまでは、民の身勝手な放浪にも制限をかけるべきだといえる。
具体的にどのくらいかといえば、やはり民間人のフットワークが為政者のフットワークを
下回る程度までだといえる。そしたら世界規模での財政破綻が回避できて、その結果として
飢餓や戦乱のような社会問題も未然に防がれるようになる。いくら文明が進歩しようとも、
為政者こそが民の一歩先を行くべきだという陰陽法則までもが破綻することはないのである。
「梁の恵王曰く、寡人の国に於けるや、心を尽くせるのみ。河内凶すれば、
則ち其の民を河東に移し、其の粟を河内に移す。河東凶せるも亦た然り。隣国の政を察するに、
寡人の心を用うるに如く者無し。隣国の民少なきを加えず、寡人の民多きを加えざるは何ぞや」
「梁の恵王が孟子に問うた。『わしのこの国に対する姿勢は、ただ心を尽くすというばかりのものだ。
もし河内地方が飢えるようなことがあればその民を河東に移し、河東からも支援の穀類を河内に運ばせる。
河東が飢えた場合にもこの逆の対策を施す。周りの国を見ても、これほどにも内政に心を尽くしている国は
ないというのに、周りの国の民が減ることもなければ、わしの国の民が増えることもないのはなぜだろう』
(このあと孟子が指摘するとおり、恵王は農繁期や斧斤時もお構いなしに民を身勝手に引きずり回しているから、
そのせいで自分こそが飢饉を引き起こしてしまっている。住民登録のために帝国の民を引きずり回して、ろくに
その宿場も用意しなかった皇帝アウグストゥスなども、この恵王並みかそれ以上の暗君だったことだろう)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・梁恵王章句上・三より)
漢の高祖劉邦も、まだぶらつき者だった頃に見知らぬ老人から
「あなたの人相は見たこともないほど素晴らしい」と言われたといい、
おそらくそれを励みにしての出世をも志したのに違いない。
この手の、あまり根拠があるわけでもないような予言なり占いなりも、個人的な励みに
するぐらいなら他愛ないものだが、予言の内容が不埒だったり、無理に根拠を付けて
信憑性を持たせようとしたりし始めると、色々と度し難い側面を帯びてくるようになる。
魏の曹操がまだ下級役人の小倅でしかなかったころ、これまた顔相見の達人が
曹操の元に現れ、「おまえは乱世の奸雄の相を帯びている」と指摘した。それが警告目的
だったのか、そうなることを推奨したのかは知れないが、実際に曹操は、三国時代において
最も腐敗した国情を帯びた国でもある魏の実質的な帝王ともなった。その存命中には漢室の存命を
許したものの、息子の曹丕の代にはついに帝位を簒奪させ、後漢の治世に終止符をも打たせた。
おそらく、自他共に認める形で実行されただろうこの曹家の横暴も、元はといえば曹操がまだ若年
であった頃の「おまえは乱世の奸雄になる」という、人からの予言をも原動力にしていたに違いない。
予言とか瑞祥とかいったものを、一貫して善用に付すのならまだしも、悪用に及ぶこともいくらでもできる、
そして悪用に及ぶ場合のほうがその実践も遥かに込み入っていて、予言がそれだけで物語になっていたりする。
未来には、確定的な要素もあれば、不確定的な要素もある。全てを総合すれば少なからず不確定的だから、
予言に基づく必然性などばかりに頼らずに、自らもその場その場での自主的な判断を講じていくべきである。
そうともせず、予言への狂信ばかりに一辺倒で、もはや聞く耳も持たないというのならば、その姿勢自体が
すでに最善を尽くしていないあり方となる。何もかもを去来今の三世に渡って自由自在にできる超越神などは
実際に存在せず、予定調和的であることもあれば、そうでないこともあることにかけてこそ普遍的である
万事万物の実相に即して、予言などは参考程度のものとして、まず自助努力のほうを心がけるべきなのである。
「あなたの人相は見たこともないほど素晴らしい」と言われたといい、
おそらくそれを励みにしての出世をも志したのに違いない。
この手の、あまり根拠があるわけでもないような予言なり占いなりも、個人的な励みに
するぐらいなら他愛ないものだが、予言の内容が不埒だったり、無理に根拠を付けて
信憑性を持たせようとしたりし始めると、色々と度し難い側面を帯びてくるようになる。
魏の曹操がまだ下級役人の小倅でしかなかったころ、これまた顔相見の達人が
曹操の元に現れ、「おまえは乱世の奸雄の相を帯びている」と指摘した。それが警告目的
だったのか、そうなることを推奨したのかは知れないが、実際に曹操は、三国時代において
最も腐敗した国情を帯びた国でもある魏の実質的な帝王ともなった。その存命中には漢室の存命を
許したものの、息子の曹丕の代にはついに帝位を簒奪させ、後漢の治世に終止符をも打たせた。
おそらく、自他共に認める形で実行されただろうこの曹家の横暴も、元はといえば曹操がまだ若年
であった頃の「おまえは乱世の奸雄になる」という、人からの予言をも原動力にしていたに違いない。
予言とか瑞祥とかいったものを、一貫して善用に付すのならまだしも、悪用に及ぶこともいくらでもできる、
そして悪用に及ぶ場合のほうがその実践も遥かに込み入っていて、予言がそれだけで物語になっていたりする。
未来には、確定的な要素もあれば、不確定的な要素もある。全てを総合すれば少なからず不確定的だから、
予言に基づく必然性などばかりに頼らずに、自らもその場その場での自主的な判断を講じていくべきである。
そうともせず、予言への狂信ばかりに一辺倒で、もはや聞く耳も持たないというのならば、その姿勢自体が
すでに最善を尽くしていないあり方となる。何もかもを去来今の三世に渡って自由自在にできる超越神などは
実際に存在せず、予定調和的であることもあれば、そうでないこともあることにかけてこそ普遍的である
万事万物の実相に即して、予言などは参考程度のものとして、まず自助努力のほうを心がけるべきなのである。
「世子生まるれば、則ち君沐浴し朝服す。夫人も亦た之の如くす。皆な阼階に立ちて西卿す。
世婦、子を抱いて西階より升る。君之れに名づけ、乃ち降る。適子庶子は外寝に於いて見、其の首を撫で
咳きて之れに名づく。礼初めに帥うも、辞無し。凡そ子に名づくるに、日月を以てせず、国を以てせず、隱疾を以てせず、
大夫、士の子は敢えて世子と名を同じくせず。妾、将に子を生まんとするに、月辰に及び、夫れ人を使いて日に一たび
之れを問わしむ。子、生まれて三月の末、漱浣し夙斎して内寝に見ゆ。之れを礼すること始めて室に入るが如くす。
君已に食し徹し、之れを使して特り餕せしめ、遂に入御す。公庶子生まるるときは、側室に就く。三月の末、其の母
沐浴し朝服して君に見ゆ。擯者其の子を以て見ゆ。君賜ふ有る所なれば、君之れを名づく。衆子は則ち有司を使て之れを名づく」
世婦、子を抱いて西階より升る。君之れに名づけ、乃ち降る。適子庶子は外寝に於いて見、其の首を撫で
咳きて之れに名づく。礼初めに帥うも、辞無し。凡そ子に名づくるに、日月を以てせず、国を以てせず、隱疾を以てせず、
大夫、士の子は敢えて世子と名を同じくせず。妾、将に子を生まんとするに、月辰に及び、夫れ人を使いて日に一たび
之れを問わしむ。子、生まれて三月の末、漱浣し夙斎して内寝に見ゆ。之れを礼すること始めて室に入るが如くす。
君已に食し徹し、之れを使して特り餕せしめ、遂に入御す。公庶子生まるるときは、側室に就く。三月の末、其の母
沐浴し朝服して君に見ゆ。擯者其の子を以て見ゆ。君賜ふ有る所なれば、君之れを名づく。衆子は則ち有司を使て之れを名づく」
「国君の嫡子が生まれた時には、主君は沐浴して正装をする。夫人たちも同じようにし、東の階段に立って西を見る(追儺目的)。
宮女が子を抱いて西の階段から昇って来ると、主君がこれに名づけて、また階段を下る。嫡子の実弟や庶子の場合には寝殿の外で
その首を撫でながらつぶやくようにして名付ける。基本的な礼式は嫡子の場合と同じだが、訓戒などの辞を与えたりはしない。
子を名付ける上では日月星辰の名を以てせず、国名を以てせず、隠れた悪い意味があるような言葉を以てせぬようにする。
国君以下の大夫や士の子は、あえて主君の嫡子と同じ名前にしたりはしない。妾が子を産もうとするときには、臨月ごろから
使いを毎日よこして子が産まれたかを問う。子が生まれて三ヶ月の後に、略式の斎戒沐浴をして妾の居場所に行く。妾はまるで
初めて夫に出会ったかのように振る舞い、まず夫が先に料理を食してから、その食べ残しを食べ、後に正式に侍御するようになる。
公君の庶子が生まれた時には側室に養わせる。子が生まれて三月の後に、母は沐浴し正装して君に見え、乳母がその子を抱える。
特に気に入った妾の子であれば君自らが子に名付ける。そうでない諸々の庶子の場合には、係りの役人に任せて名付けさせる。
(一夫多妻が常套であった封建時代にも、それなりに子を名づけたり妾を侍御させたりする上での礼式があった。その礼式を尽く
破って、夢想に即した根拠で妾腹の私生児を無闇に祝福したり、神の子だなと呼ばわったりする。それら全てが患いごとであり、
そのような根拠に即して『イエス』と名付けたりしたことも、『子に名づくに隱疾を以てせず』という礼制に反している)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・内則第十二より)
宮女が子を抱いて西の階段から昇って来ると、主君がこれに名づけて、また階段を下る。嫡子の実弟や庶子の場合には寝殿の外で
その首を撫でながらつぶやくようにして名付ける。基本的な礼式は嫡子の場合と同じだが、訓戒などの辞を与えたりはしない。
子を名付ける上では日月星辰の名を以てせず、国名を以てせず、隠れた悪い意味があるような言葉を以てせぬようにする。
国君以下の大夫や士の子は、あえて主君の嫡子と同じ名前にしたりはしない。妾が子を産もうとするときには、臨月ごろから
使いを毎日よこして子が産まれたかを問う。子が生まれて三ヶ月の後に、略式の斎戒沐浴をして妾の居場所に行く。妾はまるで
初めて夫に出会ったかのように振る舞い、まず夫が先に料理を食してから、その食べ残しを食べ、後に正式に侍御するようになる。
公君の庶子が生まれた時には側室に養わせる。子が生まれて三月の後に、母は沐浴し正装して君に見え、乳母がその子を抱える。
特に気に入った妾の子であれば君自らが子に名付ける。そうでない諸々の庶子の場合には、係りの役人に任せて名付けさせる。
(一夫多妻が常套であった封建時代にも、それなりに子を名づけたり妾を侍御させたりする上での礼式があった。その礼式を尽く
破って、夢想に即した根拠で妾腹の私生児を無闇に祝福したり、神の子だなと呼ばわったりする。それら全てが患いごとであり、
そのような根拠に即して『イエス』と名付けたりしたことも、『子に名づくに隱疾を以てせず』という礼制に反している)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・内則第十二より)
本当の親子関係であれば、主従関係を尽くすことが
どこまでいっても「主人と奴隷の関係」ような殺伐としたものにはならない。
実の親子関係はもちろんのこと、養父子の関係であろうとも、
本当に恭敬を尽くした上下関係を志したなら、そこに殺伐さなどは介されない。
ただ、やはり養父と養子などだと、実の親子並みの親密さを育むことがなかなか難しい。
だから「君臣父子夫婦」の三綱に基づき、主君への忠誠に類推して養子が養父への
尊敬を尽くすということが昔は嗜まれていた。だからこそ、侍社会でも同等の
家格の武家同士での養子縁組などが滞りなく行われてもいたが、将軍や大名のような
三綱五常の実践対象ともできる実質的な主君が廃されて、天皇一尊の立憲君主制が敷かれた
明治以降にはそうもいかなくなり、旧来の養子縁組ありきな家系保全がままならなくなって
しまったことから、お家断絶などの憂き目に遭う武家が多発したりもしたのだった。
実の親子関係や、三綱五常の保護下にある養父子関係であれば、そこで上下関係を講じようとも、
決してその関係性が殺伐化したりすることはなく、むしろ無闇に対等関係であろうとしたりした
場合にこそ、対立や喧嘩などの問題が生ずる。それは、親子関係というものが「家」という
流れの中に自然と存在するものだからで、上下関係を講ずればその流れに自然と乗れる一方、
無闇な対等関係であろうとした場合にこそ、その流れに逆らうことにもなるからだ。
親戚関係でもないような、全くの赤の他人同士であるのなら、始めからそんな流れが
備わっていることはない。主君と臣下の関係ですら、他人同士ならそんな流れはないから、
まずは親子関係における序列を尽くした上で、その序列を君臣間に及ぼすのでなければ、
いくらそれ自体に恭敬を尽くした所で、君臣関係もまた殺伐としたものになりかねない。
どこまでいっても「主人と奴隷の関係」ような殺伐としたものにはならない。
実の親子関係はもちろんのこと、養父子の関係であろうとも、
本当に恭敬を尽くした上下関係を志したなら、そこに殺伐さなどは介されない。
ただ、やはり養父と養子などだと、実の親子並みの親密さを育むことがなかなか難しい。
だから「君臣父子夫婦」の三綱に基づき、主君への忠誠に類推して養子が養父への
尊敬を尽くすということが昔は嗜まれていた。だからこそ、侍社会でも同等の
家格の武家同士での養子縁組などが滞りなく行われてもいたが、将軍や大名のような
三綱五常の実践対象ともできる実質的な主君が廃されて、天皇一尊の立憲君主制が敷かれた
明治以降にはそうもいかなくなり、旧来の養子縁組ありきな家系保全がままならなくなって
しまったことから、お家断絶などの憂き目に遭う武家が多発したりもしたのだった。
実の親子関係や、三綱五常の保護下にある養父子関係であれば、そこで上下関係を講じようとも、
決してその関係性が殺伐化したりすることはなく、むしろ無闇に対等関係であろうとしたりした
場合にこそ、対立や喧嘩などの問題が生ずる。それは、親子関係というものが「家」という
流れの中に自然と存在するものだからで、上下関係を講ずればその流れに自然と乗れる一方、
無闇な対等関係であろうとした場合にこそ、その流れに逆らうことにもなるからだ。
親戚関係でもないような、全くの赤の他人同士であるのなら、始めからそんな流れが
備わっていることはない。主君と臣下の関係ですら、他人同士ならそんな流れはないから、
まずは親子関係における序列を尽くした上で、その序列を君臣間に及ぼすのでなければ、
いくらそれ自体に恭敬を尽くした所で、君臣関係もまた殺伐としたものになりかねない。
家においてこそ、上下関係が親密さと共に遍在できるのは、先祖代々に渡る系譜の継承があるから。
今から四代前ともなれば、父子ともにその先祖と触れ合ったことすらないのが当たり前なもので、
そのような神秘的な領域にまで配慮を働かせる必要があるから、親子関係が秩序的であることでこそ
親密さが損なわれなくても済む。別に、やたらと愛し合っているから親密でいられるというばかりでもない
のだから、他人同士で親子並みの愛し合いを心がけてみた所で、同等の結果が得られたりするものではない。
先祖代々の系譜の継承があるから、実の親子関係だけでなく、養父子関係すらもが秩序立てに
よってこそ親密さを保てる。一方で、そのような事実があるわけでもないから、他の上下関係をいくら
秩序立ててみたところで、それが親密さに結びつくようなことはなく、かえって殺伐さばかりを助長する。
だから本当は、全ての上下関係を親子関係の派生系として捉えるべきなのであり、それが叶わないのなら、
世界中が上下関係に基づく殺伐さに見舞われることになる。その殺伐さを嫌うあまり、あらゆる上下関係を
この世から排する平等主義などを希求し、挙句には父子の親までをも損なうことにすらなってしまうのである。
「今商王受、〜正士を囚奴とし、郊社を修めず、宗廟を享らず。
〜上帝順わず、祝ちて時の喪を降す。爾其れ孜孜として、予れ一人を奉じ、恭しみて天の罰を行え」
「いま殷の紂王は、(数多の暴虐を列挙して)立派な人々をも囚人や奴隷とし、社稷霊廟を修繕して
先祖の神を祭り尊ぶこともしない。天帝もまたこれを美しとせず、現状を断ち切っての大喪を下される。
おまえたちも孜孜としてよく励み、天命を受けた我れ(武王)こそを奉じて、慎んで天の罰を行うがよい」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・泰誓下より)
今から四代前ともなれば、父子ともにその先祖と触れ合ったことすらないのが当たり前なもので、
そのような神秘的な領域にまで配慮を働かせる必要があるから、親子関係が秩序的であることでこそ
親密さが損なわれなくても済む。別に、やたらと愛し合っているから親密でいられるというばかりでもない
のだから、他人同士で親子並みの愛し合いを心がけてみた所で、同等の結果が得られたりするものではない。
先祖代々の系譜の継承があるから、実の親子関係だけでなく、養父子関係すらもが秩序立てに
よってこそ親密さを保てる。一方で、そのような事実があるわけでもないから、他の上下関係をいくら
秩序立ててみたところで、それが親密さに結びつくようなことはなく、かえって殺伐さばかりを助長する。
だから本当は、全ての上下関係を親子関係の派生系として捉えるべきなのであり、それが叶わないのなら、
世界中が上下関係に基づく殺伐さに見舞われることになる。その殺伐さを嫌うあまり、あらゆる上下関係を
この世から排する平等主義などを希求し、挙句には父子の親までをも損なうことにすらなってしまうのである。
「今商王受、〜正士を囚奴とし、郊社を修めず、宗廟を享らず。
〜上帝順わず、祝ちて時の喪を降す。爾其れ孜孜として、予れ一人を奉じ、恭しみて天の罰を行え」
「いま殷の紂王は、(数多の暴虐を列挙して)立派な人々をも囚人や奴隷とし、社稷霊廟を修繕して
先祖の神を祭り尊ぶこともしない。天帝もまたこれを美しとせず、現状を断ち切っての大喪を下される。
おまえたちも孜孜としてよく励み、天命を受けた我れ(武王)こそを奉じて、慎んで天の罰を行うがよい」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・泰誓下より)
「人の患いは、好んで人の師となるに在り」
(離婁章句上・二三)
親子以外の上下関係、特に師弟関係などは、親が子に教師をあてがう場合でもないのなら、
あくまで弟子となる側の自由意思によって形成されるべきものだ。一旦師弟となって、
ものを教わるからには、厳しい教育姿勢なども受け入れなければならなくなるが、
まず師弟となるかどうかという所で、弟子となる側の自由意思による従属の
決断がないのならば、いくら師となろうとする側ばかりが師ぶったところで、
全く真の師弟関係と見なすには値しないままであり続けるのである。
古来から「信者になるか殺されるか」という最悪の覇道によって信者を獲得してきた
キリスト教の神なんぞに、真に自らの弟子であると見なすことのできる相手など、一人もいない。
自分が誰かの親代わりになる資格などがないのはもちろんのこと、人に何かを教えてあげる教師
として適格となる程度の資格すらをも、覇権志向によってあらかじめかなぐり捨てているといえる。
親でもなければ教師でもない、単なる「情報屋」としての役割ていどは、確かに聖書教が果たした。
世界の征服を企てる過程で博物志向をも大いに発揮し、理論と実物の両面における豊富な情報を収集した。
しかしそれとて、世界中の財宝を自分たちだけで独り占めにしようとする下衆な下心があってのことで、
実際にそれらの情報を駆使することで、世界中の資源の八割以上を欧米聖書圏だけで独占するほどもの
暴挙を実現しているわけだから、何ら尊敬するにも値しない。今さら情報屋としての仕事ぶりに
対する報酬を与えてやったりする必要もないし、大体そんな余裕ももうこの地球上にはない。
(離婁章句上・二三)
親子以外の上下関係、特に師弟関係などは、親が子に教師をあてがう場合でもないのなら、
あくまで弟子となる側の自由意思によって形成されるべきものだ。一旦師弟となって、
ものを教わるからには、厳しい教育姿勢なども受け入れなければならなくなるが、
まず師弟となるかどうかという所で、弟子となる側の自由意思による従属の
決断がないのならば、いくら師となろうとする側ばかりが師ぶったところで、
全く真の師弟関係と見なすには値しないままであり続けるのである。
古来から「信者になるか殺されるか」という最悪の覇道によって信者を獲得してきた
キリスト教の神なんぞに、真に自らの弟子であると見なすことのできる相手など、一人もいない。
自分が誰かの親代わりになる資格などがないのはもちろんのこと、人に何かを教えてあげる教師
として適格となる程度の資格すらをも、覇権志向によってあらかじめかなぐり捨てているといえる。
親でもなければ教師でもない、単なる「情報屋」としての役割ていどは、確かに聖書教が果たした。
世界の征服を企てる過程で博物志向をも大いに発揮し、理論と実物の両面における豊富な情報を収集した。
しかしそれとて、世界中の財宝を自分たちだけで独り占めにしようとする下衆な下心があってのことで、
実際にそれらの情報を駆使することで、世界中の資源の八割以上を欧米聖書圏だけで独占するほどもの
暴挙を実現しているわけだから、何ら尊敬するにも値しない。今さら情報屋としての仕事ぶりに
対する報酬を与えてやったりする必要もないし、大体そんな余裕ももうこの地球上にはない。
覇権主義の拡大を通じて、聖書圏こそはこの世界、この宇宙にまつわる最大級の物質的情報を獲得した。
そこにはあまりにも多くの犠牲が伴っていた上に、精神的理解も全く欠けたままであり続けてきたのだから、
専ら精神修養を心がけてきた東洋社会などと比べて、聖書圏がより偉大な功績を挙げられたなどということは
全くもってない。どこまでも小人の妄動ゆえの所産というまでのことで、見下されこそすれど、見上げられる
ことなどがあって然るべきでないことでは一貫している。そうであることがまず大前提としてあった上で、
あまりにも甚大な災禍を聖書圏がこの地球上にもたらしたことへの弁償代として、聖書圏において蓄積
されてきた博物的情報が提供されることにより、聖書権の人間の罪状が多少軽減するということはある。
全くの見返り抜きで、この世界の復興や繁栄のために聖書圏の博物情報が無制限に活用されて、それでやっと
聖書圏の人間の罪が差し引きゼロになるか、やっぱり有罪なままかといったところで、親代わりや教師は
おろか、単なる情報屋として自分たちを誇れるようなことすらまずないままであり続ける。所詮は聖書信者
として為したことが、少しでも有益無害であるようなことも決してないのだから、完全に聖書信仰を棄却し、
聖書信仰による罪も完全に償って後にやっと、元聖書信者が誇りを取り戻していく余地も生ずるのだといえる。
「其が心を懲らさずして、覆りてその正しきを怨む」
「自分の(過った)心を懲らしめることもせずに、(己の過ちと他人の正しきを)覆して正しいものを責めようとする。
(謂れ無き危害を他者に及ぼすようなやからの心理はえてしてこのようなもので、それほどもの
妄念に囚われた愚か者であるからこそ、自分を他人の親だなどとまで倒錯してしまえるのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・小雅・祈父之什・節南山より)
そこにはあまりにも多くの犠牲が伴っていた上に、精神的理解も全く欠けたままであり続けてきたのだから、
専ら精神修養を心がけてきた東洋社会などと比べて、聖書圏がより偉大な功績を挙げられたなどということは
全くもってない。どこまでも小人の妄動ゆえの所産というまでのことで、見下されこそすれど、見上げられる
ことなどがあって然るべきでないことでは一貫している。そうであることがまず大前提としてあった上で、
あまりにも甚大な災禍を聖書圏がこの地球上にもたらしたことへの弁償代として、聖書圏において蓄積
されてきた博物的情報が提供されることにより、聖書権の人間の罪状が多少軽減するということはある。
全くの見返り抜きで、この世界の復興や繁栄のために聖書圏の博物情報が無制限に活用されて、それでやっと
聖書圏の人間の罪が差し引きゼロになるか、やっぱり有罪なままかといったところで、親代わりや教師は
おろか、単なる情報屋として自分たちを誇れるようなことすらまずないままであり続ける。所詮は聖書信者
として為したことが、少しでも有益無害であるようなことも決してないのだから、完全に聖書信仰を棄却し、
聖書信仰による罪も完全に償って後にやっと、元聖書信者が誇りを取り戻していく余地も生ずるのだといえる。
「其が心を懲らさずして、覆りてその正しきを怨む」
「自分の(過った)心を懲らしめることもせずに、(己の過ちと他人の正しきを)覆して正しいものを責めようとする。
(謂れ無き危害を他者に及ぼすようなやからの心理はえてしてこのようなもので、それほどもの
妄念に囚われた愚か者であるからこそ、自分を他人の親だなどとまで倒錯してしまえるのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・小雅・祈父之什・節南山より)
欧米聖書圏ではごく当たり前な存在として受け止められている、
一部富裕層の組織的共謀に基づく大規模な金融犯罪や国際権力犯罪、
近ごろだとイルミナティやフリーメイソンのような外的名義で行われている
カルト犯罪が、たとえばこの日本だと「そんなものがあるわけがない」みたいな
受け止められ方をする。「そんなものが社会的な健在を許されるはずがないから」と、
自分たちの常識では考えてしまうから。キリスト教圏でもなければ、ユダヤ教徒を
庇護するような慣習があったこともないこの日本で、国や世界を破滅に陥れる程もの
カルト犯罪が容認され続けるなどということが、想像すらできるものではないから。
(オウム真理教によるカルトテロがあっという間に一掃された実例などもある)
そのような、日本でなら決して黙認されることもないような組織的カルト犯罪が聖書圏で
横行し続けているのも、他でもない、聖書圏が「聖書圏」であるからにほかならない。
別にカルト指定を受けているわけでもないような、正統とされているような
キリスト教であろうとも、普遍的な基準からいえば、その教義が十分にカルト的である。
神の所業であれ悪魔の所業であれ、聖書信仰は「マッチポンプ」を容認する信仰である。
犯罪聖書中における神や悪魔の所業が丸っきりマッチポンプそのものなのだから、どんなに
真っ当に聖書の記述を信じてみた所で、必ずマッチポンプを容認させられる破目におちいる。
だから、イルミナティのような悪魔崇拝のカルト犯罪組織が悪行を企てるのであっても、
そこに「大戦での勝利」みたいな正義めいた「ポンプ」の要素が付加されるのであれば、
それだけで全てのキリスト教徒がカルト犯罪全般を黙認してしまうことになる。
マッチポンプを宗教的に容認する風潮のある社会では、例えそれが、自分たちが敵視している
悪魔崇拝者によるものであろうとも、マッチポンプ型のカルト犯罪が横行することを、一定以上に
容認してしまう状態が続くことになる。それが聖書信仰に基づくとは限らないが、聖書信仰で
ある以上は必ず、マッチポンプ型の悪逆非道を容認し続けるザマに陥るようになっている。
一部富裕層の組織的共謀に基づく大規模な金融犯罪や国際権力犯罪、
近ごろだとイルミナティやフリーメイソンのような外的名義で行われている
カルト犯罪が、たとえばこの日本だと「そんなものがあるわけがない」みたいな
受け止められ方をする。「そんなものが社会的な健在を許されるはずがないから」と、
自分たちの常識では考えてしまうから。キリスト教圏でもなければ、ユダヤ教徒を
庇護するような慣習があったこともないこの日本で、国や世界を破滅に陥れる程もの
カルト犯罪が容認され続けるなどということが、想像すらできるものではないから。
(オウム真理教によるカルトテロがあっという間に一掃された実例などもある)
そのような、日本でなら決して黙認されることもないような組織的カルト犯罪が聖書圏で
横行し続けているのも、他でもない、聖書圏が「聖書圏」であるからにほかならない。
別にカルト指定を受けているわけでもないような、正統とされているような
キリスト教であろうとも、普遍的な基準からいえば、その教義が十分にカルト的である。
神の所業であれ悪魔の所業であれ、聖書信仰は「マッチポンプ」を容認する信仰である。
犯罪聖書中における神や悪魔の所業が丸っきりマッチポンプそのものなのだから、どんなに
真っ当に聖書の記述を信じてみた所で、必ずマッチポンプを容認させられる破目におちいる。
だから、イルミナティのような悪魔崇拝のカルト犯罪組織が悪行を企てるのであっても、
そこに「大戦での勝利」みたいな正義めいた「ポンプ」の要素が付加されるのであれば、
それだけで全てのキリスト教徒がカルト犯罪全般を黙認してしまうことになる。
マッチポンプを宗教的に容認する風潮のある社会では、例えそれが、自分たちが敵視している
悪魔崇拝者によるものであろうとも、マッチポンプ型のカルト犯罪が横行することを、一定以上に
容認してしまう状態が続くことになる。それが聖書信仰に基づくとは限らないが、聖書信仰で
ある以上は必ず、マッチポンプ型の悪逆非道を容認し続けるザマに陥るようになっている。
儒学や仏教のような、マッチポンプ型の悪行の有害無益さを具さに見極めて、始めから
そのような悪行の専らな防止に努めていく教学を本旨とするのであれば、例えばこの日本のように、
イルミナティの如きカルト犯罪組織の存在を徹底して拒絶し尽くす風潮を生み出すこともできる。
今はそのような国も限られているが、世界中が日本並みにカルト犯罪組織の市民権を全否定
していけるようになったならば、始めからイルミナティ級の激甚カルトは生じないようになる。
そうなるためには、ただマッチポンプの存在価値を否定し尽くす文化を広めていくのみならず、
マッチポンプを黙認してしまうような要素を含む文化を駆逐していく必要までもがある。
必ずしもマッチポンプによる悪行に自分たちが及ぶわけではなくても、キリスト教やユダヤ教は
全てが全て、マッチポンプを容認してしまうぐらいの要素は必ず含有しているものだから、
この世からマッチポンプ犯罪を根絶してくためには、キリスト教やユダヤ教の根絶から
務めて行く必要がある。カルト組織のマッチポンプ犯罪が人類の滅亡にすら手をかけ始めて
いる現今においては、もはや聖書信仰からの根絶が急務にすらなっているのである。
「昔の大猷に若って、治を未乱に制し、邦を未危に保んじよ」
「古えの大道に則って、未だ乱が生じぬ内からよく統制し、万邦が危機に陥る前からよく保全せよ。
(具体的には、大水の害が生じたりする前からの治水を心がけるなど。大水害を
生じさせてからのマッチポンプなども当然、始めから企てさせないようにする)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・周官より)
そのような悪行の専らな防止に努めていく教学を本旨とするのであれば、例えばこの日本のように、
イルミナティの如きカルト犯罪組織の存在を徹底して拒絶し尽くす風潮を生み出すこともできる。
今はそのような国も限られているが、世界中が日本並みにカルト犯罪組織の市民権を全否定
していけるようになったならば、始めからイルミナティ級の激甚カルトは生じないようになる。
そうなるためには、ただマッチポンプの存在価値を否定し尽くす文化を広めていくのみならず、
マッチポンプを黙認してしまうような要素を含む文化を駆逐していく必要までもがある。
必ずしもマッチポンプによる悪行に自分たちが及ぶわけではなくても、キリスト教やユダヤ教は
全てが全て、マッチポンプを容認してしまうぐらいの要素は必ず含有しているものだから、
この世からマッチポンプ犯罪を根絶してくためには、キリスト教やユダヤ教の根絶から
務めて行く必要がある。カルト組織のマッチポンプ犯罪が人類の滅亡にすら手をかけ始めて
いる現今においては、もはや聖書信仰からの根絶が急務にすらなっているのである。
「昔の大猷に若って、治を未乱に制し、邦を未危に保んじよ」
「古えの大道に則って、未だ乱が生じぬ内からよく統制し、万邦が危機に陥る前からよく保全せよ。
(具体的には、大水の害が生じたりする前からの治水を心がけるなど。大水害を
生じさせてからのマッチポンプなども当然、始めから企てさせないようにする)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・周官より)
「正統か異端かに関わらず、「マッチポンプ」という権力犯罪現象を容認するのが
全ての聖書信仰の通義だから、この世からマッチポンプ系の権力犯罪を根絶するためには、
正統派とされるものを含む、全ての聖書信仰の根絶にも務めなければならない」
今日書いたことを要約すれば、こうなる。
その理由は全文を読んで理解してもらう他はないが、
さしあたっての軍人などに対する速やかな情報伝達を必要とするのなら、こう言う。
全ての聖書信仰の通義だから、この世からマッチポンプ系の権力犯罪を根絶するためには、
正統派とされるものを含む、全ての聖書信仰の根絶にも務めなければならない」
今日書いたことを要約すれば、こうなる。
その理由は全文を読んで理解してもらう他はないが、
さしあたっての軍人などに対する速やかな情報伝達を必要とするのなら、こう言う。
他人が最悪の不幸に追い込まれている中で、
自分がそれよりはまだマシな境遇に置かれていることへの相対的な幸福感を抱く
という性向が、人間には残念ながら備わっている。日本の小中高におけるいじめ問題
などもそのような性向に起因していて、いじめっ子となる側も別にさして恵まれた境遇に
いるわけでもないが、そのような立場から同級生などをいじめることで相対的な優越感を
抱くという場合が非常に多く、教師や親にろくな教育を受けていないことなども常なので、
これは完全に人としての精神的な未熟さに基づいて来たしてしまった問題だといえる。
ほんの形式ばかり、体裁ばかりだけでも人よりマシそうでいられたらそれで幸せ、
そういった、人としての向上心が完全に途絶え切った人間ばかりが楽しみとする幸せも、
自分たち自身が全世界、全人類のうちでも最低最悪の立場に追い込まれた時には、ついに絶える。
自分たちよりももっと不幸そうなもの、もっと恵まれていなさそうなものを探し尽くしても、
もはやどこにもそんな相手が見つからない、それ程にも自分たち自身が最悪の立場に陥る。
そこまで自分たち自身を追い詰める人間もそう多くはないが、他者をより悲惨な境遇に
陥れることで、自身の境遇の相対的なマシさ加減を幸せがることを本旨とするユダヤ=
キリスト両聖書教が最終的に行き着いた帰結点というのは、まさにそれだった。
何が何でも他者を自分たち以上に貶めようとする意地汚さに即して、異教徒を硬軟織り混ぜた
徹底的な迫害下に置いてはみたものの、それによって全世界が人類滅亡級の危機に晒される
ことともなった。今の世界で最大級の影響力を誇っているのが自分たちで、しかもその世界を
究極の破滅に陥れている張本人も自分たちなのだから、もはや自分たちで責任を取る他はない。
責任を取る以上は自分たちが最下等の処遇に甘んじることすら必ずしも避けられるものではない、
そういった、実質面からの最悪の不遇がすでに確定してしまっていることがまず一つ。
自分がそれよりはまだマシな境遇に置かれていることへの相対的な幸福感を抱く
という性向が、人間には残念ながら備わっている。日本の小中高におけるいじめ問題
などもそのような性向に起因していて、いじめっ子となる側も別にさして恵まれた境遇に
いるわけでもないが、そのような立場から同級生などをいじめることで相対的な優越感を
抱くという場合が非常に多く、教師や親にろくな教育を受けていないことなども常なので、
これは完全に人としての精神的な未熟さに基づいて来たしてしまった問題だといえる。
ほんの形式ばかり、体裁ばかりだけでも人よりマシそうでいられたらそれで幸せ、
そういった、人としての向上心が完全に途絶え切った人間ばかりが楽しみとする幸せも、
自分たち自身が全世界、全人類のうちでも最低最悪の立場に追い込まれた時には、ついに絶える。
自分たちよりももっと不幸そうなもの、もっと恵まれていなさそうなものを探し尽くしても、
もはやどこにもそんな相手が見つからない、それ程にも自分たち自身が最悪の立場に陥る。
そこまで自分たち自身を追い詰める人間もそう多くはないが、他者をより悲惨な境遇に
陥れることで、自身の境遇の相対的なマシさ加減を幸せがることを本旨とするユダヤ=
キリスト両聖書教が最終的に行き着いた帰結点というのは、まさにそれだった。
何が何でも他者を自分たち以上に貶めようとする意地汚さに即して、異教徒を硬軟織り混ぜた
徹底的な迫害下に置いてはみたものの、それによって全世界が人類滅亡級の危機に晒される
ことともなった。今の世界で最大級の影響力を誇っているのが自分たちで、しかもその世界を
究極の破滅に陥れている張本人も自分たちなのだから、もはや自分たちで責任を取る他はない。
責任を取る以上は自分たちが最下等の処遇に甘んじることすら必ずしも避けられるものではない、
そういった、実質面からの最悪の不遇がすでに確定してしまっていることがまず一つ。
そもそも、他者を貶めることで自分たちの相対的なマシさを幸せがろうなどとすること自体が
専らな悪行であり、故につまらない。そのような所業に始めから手を染めないようにしてきた
他の人々などと比べて、悪因苦果の甘受という道理の面から不遇にあり続けてきたことが二つ。
実物面と心理面、両面において、聖書信者こそは世界最悪の不遇に追い込まれ、以って、
他社を貶めることで自分たちを幸せがる醜悪な論理の推進も、完全に潰えることとなった。
上にも書いたとおり、この論理は未成年における「いじめの論理」などにも通じているもので、
いじめっ子の抱くような未熟故の思い上がりを社会的に発展させ尽くしたなら、最終的に
どうなるのかといったことの見本ともなっている。結果は、他でもない最悪の破滅だったわけで、
聖書信者だけでなく、いじめを好んでいるような未成年や大人もまた、この事実を神妙に
受け止めて、自分たちが好き好んでいることの因果応報をも恐れ慎むようにすべきだといえる。
「周公、武王に相たり、紂を誅し奄を伐ち、三年にして其の君を討ち、飛廉を海隅に駆りて
之れを戮す。国を滅ぼす者五十、虎、豹、犀、象を駆りて之れを遠ざけ、天下大いに悦べり」
「魯の周公は武王の首相として殷の紂王を誅殺し、紂王を助けた奄国を征伐し、三年をかけて
そこの主君を討ち取り、紂王の寵臣だった飛廉も海辺の果てに追い込んでこれを誅戮した。
殷紂の暴虐の連帯責任で取り潰した国は五十に上り、トラやヒョウやサイやゾウのような害獣をも
遠方へと追っ払っため、天下の人々がみな大いに喜んだ。(仁者のもたらす喜びは局地的でない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・滕文公章句・九より)
専らな悪行であり、故につまらない。そのような所業に始めから手を染めないようにしてきた
他の人々などと比べて、悪因苦果の甘受という道理の面から不遇にあり続けてきたことが二つ。
実物面と心理面、両面において、聖書信者こそは世界最悪の不遇に追い込まれ、以って、
他社を貶めることで自分たちを幸せがる醜悪な論理の推進も、完全に潰えることとなった。
上にも書いたとおり、この論理は未成年における「いじめの論理」などにも通じているもので、
いじめっ子の抱くような未熟故の思い上がりを社会的に発展させ尽くしたなら、最終的に
どうなるのかといったことの見本ともなっている。結果は、他でもない最悪の破滅だったわけで、
聖書信者だけでなく、いじめを好んでいるような未成年や大人もまた、この事実を神妙に
受け止めて、自分たちが好き好んでいることの因果応報をも恐れ慎むようにすべきだといえる。
「周公、武王に相たり、紂を誅し奄を伐ち、三年にして其の君を討ち、飛廉を海隅に駆りて
之れを戮す。国を滅ぼす者五十、虎、豹、犀、象を駆りて之れを遠ざけ、天下大いに悦べり」
「魯の周公は武王の首相として殷の紂王を誅殺し、紂王を助けた奄国を征伐し、三年をかけて
そこの主君を討ち取り、紂王の寵臣だった飛廉も海辺の果てに追い込んでこれを誅戮した。
殷紂の暴虐の連帯責任で取り潰した国は五十に上り、トラやヒョウやサイやゾウのような害獣をも
遠方へと追っ払っため、天下の人々がみな大いに喜んだ。(仁者のもたらす喜びは局地的でない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・滕文公章句・九より)
親からもらった我が身を無闇に危うからしめることと、
我が身可愛さが全てで他者への配慮を著しく欠くこととの、両方が中正を損なっている。
前者は若者や男が陥りやすい傾向である一方、後者は年寄りや女が陥りやすい傾向であり、
ある程度は老若男女がそれぞれにそのような性向を帯びつつ世の中を形成していくものでもあるが、
それも無闇もっぱらであり過ぎたりしたのなら、必ず乱世などの弊害をもたらすものである。
今だと欧米聖書圏の人間の、自分たちばかりを可愛がって他者を顧みない性向の過剰が、
世界中のあらゆる災厄の元凶ともなっている。「人権」「自由」「平和」などと色々な美辞麗句で
飾り立ててみてはいるものの、要は自分たち自身を底なしに可愛がってい続けたいというだけのこと。
女々しすぎる事もとっくの昔に開き直り済みで、イギリスのように本当に老婆を王君にしている国もある。
高年の女あたりが最もその傾向を極大化させる「我が身可愛さが全て」という心理が、全世界における
金科玉条にまで指定され、捨て身の荒業はおろか、一人前の責任を負うために相応の苦労をすることすら
評価が保証されない事態と化している。とにかく自分個人の安居や栄華が達成されていることこそは
最評価の対象とされ、その条件を満たしやすい富豪あたりが成功者のみならず、偉人としてすら扱われている。
何も、誰しもが赤穂義士のような捨て身の生き方こそを目指すべきだなどということはないし、
それ以上にも見るべき所のない犬死になどなら、むしろ避けることを心がけるべきであるにも違いない。
しかし、今という時代があまりにも「我が身可愛さ」の偏重に振れきってしまっている世の中だから、
もう少し世相を中正に反す目的でも、自己犠牲的な生き方の復権を目指していくべきだといえる。
我が身可愛さが全てで他者への配慮を著しく欠くこととの、両方が中正を損なっている。
前者は若者や男が陥りやすい傾向である一方、後者は年寄りや女が陥りやすい傾向であり、
ある程度は老若男女がそれぞれにそのような性向を帯びつつ世の中を形成していくものでもあるが、
それも無闇もっぱらであり過ぎたりしたのなら、必ず乱世などの弊害をもたらすものである。
今だと欧米聖書圏の人間の、自分たちばかりを可愛がって他者を顧みない性向の過剰が、
世界中のあらゆる災厄の元凶ともなっている。「人権」「自由」「平和」などと色々な美辞麗句で
飾り立ててみてはいるものの、要は自分たち自身を底なしに可愛がってい続けたいというだけのこと。
女々しすぎる事もとっくの昔に開き直り済みで、イギリスのように本当に老婆を王君にしている国もある。
高年の女あたりが最もその傾向を極大化させる「我が身可愛さが全て」という心理が、全世界における
金科玉条にまで指定され、捨て身の荒業はおろか、一人前の責任を負うために相応の苦労をすることすら
評価が保証されない事態と化している。とにかく自分個人の安居や栄華が達成されていることこそは
最評価の対象とされ、その条件を満たしやすい富豪あたりが成功者のみならず、偉人としてすら扱われている。
何も、誰しもが赤穂義士のような捨て身の生き方こそを目指すべきだなどということはないし、
それ以上にも見るべき所のない犬死になどなら、むしろ避けることを心がけるべきであるにも違いない。
しかし、今という時代があまりにも「我が身可愛さ」の偏重に振れきってしまっている世の中だから、
もう少し世相を中正に反す目的でも、自己犠牲的な生き方の復権を目指していくべきだといえる。
ちょうど、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康の三武将が、命知らず・保身過剰・攻防自在の適例となっている。
信長は命知らずの破壊行為に及びすぎたし、秀吉は晩年に保身の鬼と化して人々からの信奉を失った。
この両者の両極性を反面教師として模範的な天下取りたり得たのが家康公であり、三方ヶ原の戦いで
先陣切って戦うことで命の危機に晒されたこともあれば、大坂の陣では血気にはやる若手の侍たちに制動
をかける側にも回っていた。かと思いきや、大やぐらに据えた最新型の大砲で大坂城を砲撃するなど、その
行いに出処進退自由自在な融通があり、これこそは保身にも捨て身にも振り切れない中正な生き方だといえる。
今が老齢期の秀吉のような、保身過剰ばかりに覆われている世の中だから、次は信長のような命知らずばかりに
世の中が覆われるべきだなどということもない。確かに、秦帝国崩壊後に項羽のような猪武者が暴れまわった
ようにして、保身に過ぎた世相の跳ねっ返りとしての捨て身屋の多発が生ずることも、必ずしも完全に避けられる
ことではないが、最終的に目指すべきなのは、あくまで家康公のような攻防自在の中正の境地であり、
そこに最終的に収まることでこそ、世の中も本当の平安や繁栄にあり付けるようになる。
うだる程にも保身まみれな時代が続いたからといって、漫画やSFでよく描かれているような「世紀末社会」
などを希求するのも考えものである。それこそ、カルト文化にとっての思うツボともなるのだから。
「父母没すと雖も、将に善を為さんとするに、父母の令名を貽さんと思いて、必ず果たす。
将に不善を為さんとするにも、父母の羞辱を貽さんことを思いて、必ず果たさず」
「すでに父母が没してからも、善を為すからには、父母の名を挙げることを念頭に置いて、必ず果たそうとする。
悪を為しそうになった時にも、そのせいで父母を辱めてしまうことを思い起こして、必ず踏みとどまるようにする。
(家の名誉や辱めは死後にまで続く。それは自分個人の保身ばかりに拘泥することで得たり守れたりするものでもない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・内則第十二より)
信長は命知らずの破壊行為に及びすぎたし、秀吉は晩年に保身の鬼と化して人々からの信奉を失った。
この両者の両極性を反面教師として模範的な天下取りたり得たのが家康公であり、三方ヶ原の戦いで
先陣切って戦うことで命の危機に晒されたこともあれば、大坂の陣では血気にはやる若手の侍たちに制動
をかける側にも回っていた。かと思いきや、大やぐらに据えた最新型の大砲で大坂城を砲撃するなど、その
行いに出処進退自由自在な融通があり、これこそは保身にも捨て身にも振り切れない中正な生き方だといえる。
今が老齢期の秀吉のような、保身過剰ばかりに覆われている世の中だから、次は信長のような命知らずばかりに
世の中が覆われるべきだなどということもない。確かに、秦帝国崩壊後に項羽のような猪武者が暴れまわった
ようにして、保身に過ぎた世相の跳ねっ返りとしての捨て身屋の多発が生ずることも、必ずしも完全に避けられる
ことではないが、最終的に目指すべきなのは、あくまで家康公のような攻防自在の中正の境地であり、
そこに最終的に収まることでこそ、世の中も本当の平安や繁栄にあり付けるようになる。
うだる程にも保身まみれな時代が続いたからといって、漫画やSFでよく描かれているような「世紀末社会」
などを希求するのも考えものである。それこそ、カルト文化にとっての思うツボともなるのだから。
「父母没すと雖も、将に善を為さんとするに、父母の令名を貽さんと思いて、必ず果たす。
将に不善を為さんとするにも、父母の羞辱を貽さんことを思いて、必ず果たさず」
「すでに父母が没してからも、善を為すからには、父母の名を挙げることを念頭に置いて、必ず果たそうとする。
悪を為しそうになった時にも、そのせいで父母を辱めてしまうことを思い起こして、必ず踏みとどまるようにする。
(家の名誉や辱めは死後にまで続く。それは自分個人の保身ばかりに拘泥することで得たり守れたりするものでもない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・内則第十二より)
古代のイスラエル宗教やギリシャ学の形成に携わった人間というのは、非常に少ない。
儒学の祖である孔子の下には3000人の弟子が集まっていたというし(「史記」孔子世家参照)、
その中でも六芸(易詩書礼楽春秋)に通じている高弟が72人に上ったという。その高弟の一人
である曾子などにも、常に七十人程度の従者がいたというから(「孟子)離婁章句下・三二参照)、
昔から儒学というものがいかに膨大な数の人々に支持され研鑽されてきたのかが分かるというもの。
片や、イエスに随順した弟子なんてのはたったの13人止まりで、その弟子すら、イエスの命令も
聞かずに居眠りしていたような体たらく。そのイエスの興したキリスト教が爆発的に広がったのも、
「信じるか殺されるか」という強圧的な態度によって宗教的覇権を拡大していったからに他ならず、
決して自分たちから進んでキリスト信仰を取り入れていったような人間がいたからでもない。
西洋では宗教だけでなく、学術のほうでも、古代のアカデミアの頃からの伝統として、学術を
完全な専門機関の寡占下に置き、在野の研究者の権威を一切認めないという姿勢が貫かれている。
科挙試験のような実地の役人登用試験こそが決定的な関門とされ、それまでの勉学は私塾に依ろうが
自学自習に依ろうが自由とされていた中国の学術姿勢などと比べても、「学問をする資格」自体を世間
一般から剥奪する性格が強かったため、学術の存在目的が全くの商工業目的に限られる様相をも呈した。
(アカデミアの如き専門機関を運営していくために、結局は商工組合などのスポンサーを必要とするから)
たとえば、秦帝国による法家支配が敷かれていた頃の中国などにおいても、在野の学者が勝手に
政治学的意見を述べたりする「横議」が法的に禁止されて、その禁を破った儒者を多数穴埋めにして
処刑するなどの暴政がまかり通っていた。とはいえ、市井に至るまでの儒学の普及率は、洋学のそれ
などとは段違いなものだから、家の壁に儒書を塗り込んで隠したり、狂人のフリをして摘発を免れたり
していた数多の儒者の協力にも基づいて秦帝国が討伐を受け、漢帝国が新たに樹立されもした。
儒学の祖である孔子の下には3000人の弟子が集まっていたというし(「史記」孔子世家参照)、
その中でも六芸(易詩書礼楽春秋)に通じている高弟が72人に上ったという。その高弟の一人
である曾子などにも、常に七十人程度の従者がいたというから(「孟子)離婁章句下・三二参照)、
昔から儒学というものがいかに膨大な数の人々に支持され研鑽されてきたのかが分かるというもの。
片や、イエスに随順した弟子なんてのはたったの13人止まりで、その弟子すら、イエスの命令も
聞かずに居眠りしていたような体たらく。そのイエスの興したキリスト教が爆発的に広がったのも、
「信じるか殺されるか」という強圧的な態度によって宗教的覇権を拡大していったからに他ならず、
決して自分たちから進んでキリスト信仰を取り入れていったような人間がいたからでもない。
西洋では宗教だけでなく、学術のほうでも、古代のアカデミアの頃からの伝統として、学術を
完全な専門機関の寡占下に置き、在野の研究者の権威を一切認めないという姿勢が貫かれている。
科挙試験のような実地の役人登用試験こそが決定的な関門とされ、それまでの勉学は私塾に依ろうが
自学自習に依ろうが自由とされていた中国の学術姿勢などと比べても、「学問をする資格」自体を世間
一般から剥奪する性格が強かったため、学術の存在目的が全くの商工業目的に限られる様相をも呈した。
(アカデミアの如き専門機関を運営していくために、結局は商工組合などのスポンサーを必要とするから)
たとえば、秦帝国による法家支配が敷かれていた頃の中国などにおいても、在野の学者が勝手に
政治学的意見を述べたりする「横議」が法的に禁止されて、その禁を破った儒者を多数穴埋めにして
処刑するなどの暴政がまかり通っていた。とはいえ、市井に至るまでの儒学の普及率は、洋学のそれ
などとは段違いなものだから、家の壁に儒書を塗り込んで隠したり、狂人のフリをして摘発を免れたり
していた数多の儒者の協力にも基づいて秦帝国が討伐を受け、漢帝国が新たに樹立されもした。
漢帝国においては市井での横議も許可され、私的な儒学の勉強によって能力を養ったものが
高官として登用されることなども頻発するようになった。それでこそ漢帝国も400年にわたる
治世を打ち立てられたわけで、学問が象牙の塔の内側などに隠し込まれずに、広く万人に
よって享受されていくことの有意義さが歴史的に証明された実例ともなっている。
徳川幕府開府後の江戸時代の日本においても、数多の経書や兵法書や仏典が官命で増刷され、
当時世界一の識字率と共に、人々が揃いも揃って最高級の学術文化を享受することができていた。
その頃に養われた民度の高さがあればこそ、明治以降、敗戦以降と徐々に強化されていった愚民化洗脳の
下でも、未だ日本人の民度が世界最高級の水準を保てている。「高尚なことは全て一部の人間に任せ、
あとの人間はみな畜生も同然ののんべんだらりとした生活を送る」という西洋的な俗悪支配が推進
され続けている中にも、未だ大多数の日本人が節度ある振る舞いを心がけようとしているのは、大昔に
先祖が取った杵柄としての、高尚な学術理解にも基づく本能からの品格が未だに残されているからだ。
大昔から「一部の宗教家や知識人と、大多数の愚民」という体制を続けてきた西洋社会などには、
当然そのような根拠に基づく民度の高さはない。民たち自身に自主的な民度の向上を促したところで
決してそんなことも不可能であり、権力者こそが高尚な文化を象牙の塔にしまい込む悪癖を払拭し、
人々に広く学問享受や勉学の余地を与えていくようにしなければ、これ以上の民度の向上も見込めない。
象牙の塔を打ち壊して大々的にその中身を開示してみた結果、洋学も聖書教もろくでもない代物で
あったことがバレてしまうというのならそれまでのことで、もうそんなものをもったいぶって
高嶺の花に掲げておくことから永久に辞めてしまうに越したことはないのである。
高官として登用されることなども頻発するようになった。それでこそ漢帝国も400年にわたる
治世を打ち立てられたわけで、学問が象牙の塔の内側などに隠し込まれずに、広く万人に
よって享受されていくことの有意義さが歴史的に証明された実例ともなっている。
徳川幕府開府後の江戸時代の日本においても、数多の経書や兵法書や仏典が官命で増刷され、
当時世界一の識字率と共に、人々が揃いも揃って最高級の学術文化を享受することができていた。
その頃に養われた民度の高さがあればこそ、明治以降、敗戦以降と徐々に強化されていった愚民化洗脳の
下でも、未だ日本人の民度が世界最高級の水準を保てている。「高尚なことは全て一部の人間に任せ、
あとの人間はみな畜生も同然ののんべんだらりとした生活を送る」という西洋的な俗悪支配が推進
され続けている中にも、未だ大多数の日本人が節度ある振る舞いを心がけようとしているのは、大昔に
先祖が取った杵柄としての、高尚な学術理解にも基づく本能からの品格が未だに残されているからだ。
大昔から「一部の宗教家や知識人と、大多数の愚民」という体制を続けてきた西洋社会などには、
当然そのような根拠に基づく民度の高さはない。民たち自身に自主的な民度の向上を促したところで
決してそんなことも不可能であり、権力者こそが高尚な文化を象牙の塔にしまい込む悪癖を払拭し、
人々に広く学問享受や勉学の余地を与えていくようにしなければ、これ以上の民度の向上も見込めない。
象牙の塔を打ち壊して大々的にその中身を開示してみた結果、洋学も聖書教もろくでもない代物で
あったことがバレてしまうというのならそれまでのことで、もうそんなものをもったいぶって
高嶺の花に掲げておくことから永久に辞めてしまうに越したことはないのである。
「君に事える者は量りて後に入り、入りて後に量らず。
凡そ人に乞い假るもの、人の為めに事え従う者も亦た然りとす。
故に上に怨み無く、下も罪から遠ざかるなり。密を窺わず、旁りに狎れず、旧故を道わず、戯色せず」
「主君に仕える者はまず可否を量って後に仕えるようにし、仕えてから量ったりしないようにする。
人に何かを乞い求めたり、君に限らず誰かに仕えたりする場合にも、必ずこれと同じようにする。
自分にとって秘密裏とされていることを濫りに窺ったりせず、無闇に馴れ馴れしくしたりせず、
昔の過ちを改めて指摘したりせず、巧言令色を弄んだりしないようにする。
(イエスの復活すら万人には秘密裏であるのに、上記のような正しい
礼儀に即してキリスト教が人々に受け入れられたはずもないのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・少儀第十七より)
凡そ人に乞い假るもの、人の為めに事え従う者も亦た然りとす。
故に上に怨み無く、下も罪から遠ざかるなり。密を窺わず、旁りに狎れず、旧故を道わず、戯色せず」
「主君に仕える者はまず可否を量って後に仕えるようにし、仕えてから量ったりしないようにする。
人に何かを乞い求めたり、君に限らず誰かに仕えたりする場合にも、必ずこれと同じようにする。
自分にとって秘密裏とされていることを濫りに窺ったりせず、無闇に馴れ馴れしくしたりせず、
昔の過ちを改めて指摘したりせず、巧言令色を弄んだりしないようにする。
(イエスの復活すら万人には秘密裏であるのに、上記のような正しい
礼儀に即してキリスト教が人々に受け入れられたはずもないのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・少儀第十七より)
善因楽果悪因苦果の因果応報に特定の超越的な基準などは存在せず、
全くの人間自身の定義に因っている。とはいえ人間は「五体を持つ胎生の霊長」
といったような特定の範囲内にのみ存在する生物だから、その範囲に即して
それぞれが善とみなすもの、悪とみなすものも自然と似通っていくことになる。
善とは本来楽果を期待すべきものであり、悪とは本来苦果を期待すべきもので
あると人間自身が言葉の交わし合いの中からも自然と定義していっているから、
誰しもが楽果に与れるものを善、苦果に苛まれるものを悪と、自然に定義しもする。
しかし、善因楽果悪因苦果の因果応報に何らかの超越的な基準が存在し、
その基準によって外的に善悪が決められるとしたなら、そうもいかなくなる。
自分が苦果の因子であるように思えるものも善である可能性があることになるし、
楽果の因子であるように思えるものが悪である可能性もまたあることになる。
善因楽果悪因苦果を人工的に規定しようとする試みの一つが実定法であり、
仮に実定法で「強盗殺人をしなければ死刑」と規定されていたために、強盗殺人を
しなかっただけで死刑になるとしたなら、それが苦果であるために、強盗殺人をしない
ことが悪であり、強盗殺人を行うことが比較的な善であることにすらなってしまう。
旧約冒頭のモーセ五書を「律法(トーラー)」とする犯罪聖書もかくの如くであり、
トーラーに規定されている法規の大半は、自然に人々が定義する善悪などとは
大幅に乖離した、虚構の善悪を取り決める「徒法」の集成となっている。人間個人の
自然な感覚とは全く以て無関係なところに、無機質な虚構の倫理構造を構築していく
そのあり方は、近代法学に基づく法治主義社会などにも少なからず応用されてしまっていて、
六法の如き法文構造による倫理的締め付けの強化が、人々に極度の精神的怠慢をもたらし、
もはや人間自身の自然な感覚に基づく善悪などはなかったことにすらされてしまっている。
全くの人間自身の定義に因っている。とはいえ人間は「五体を持つ胎生の霊長」
といったような特定の範囲内にのみ存在する生物だから、その範囲に即して
それぞれが善とみなすもの、悪とみなすものも自然と似通っていくことになる。
善とは本来楽果を期待すべきものであり、悪とは本来苦果を期待すべきもので
あると人間自身が言葉の交わし合いの中からも自然と定義していっているから、
誰しもが楽果に与れるものを善、苦果に苛まれるものを悪と、自然に定義しもする。
しかし、善因楽果悪因苦果の因果応報に何らかの超越的な基準が存在し、
その基準によって外的に善悪が決められるとしたなら、そうもいかなくなる。
自分が苦果の因子であるように思えるものも善である可能性があることになるし、
楽果の因子であるように思えるものが悪である可能性もまたあることになる。
善因楽果悪因苦果を人工的に規定しようとする試みの一つが実定法であり、
仮に実定法で「強盗殺人をしなければ死刑」と規定されていたために、強盗殺人を
しなかっただけで死刑になるとしたなら、それが苦果であるために、強盗殺人をしない
ことが悪であり、強盗殺人を行うことが比較的な善であることにすらなってしまう。
旧約冒頭のモーセ五書を「律法(トーラー)」とする犯罪聖書もかくの如くであり、
トーラーに規定されている法規の大半は、自然に人々が定義する善悪などとは
大幅に乖離した、虚構の善悪を取り決める「徒法」の集成となっている。人間個人の
自然な感覚とは全く以て無関係なところに、無機質な虚構の倫理構造を構築していく
そのあり方は、近代法学に基づく法治主義社会などにも少なからず応用されてしまっていて、
六法の如き法文構造による倫理的締め付けの強化が、人々に極度の精神的怠慢をもたらし、
もはや人間自身の自然な感覚に基づく善悪などはなかったことにすらされてしまっている。
ある程度以上に大規模な社会であれば、古今東西を問わず法制による社会管理というものが
多少は必要となるものである。とはいえ当該の社会が徳治社会であるのならば、法文による
善悪の規定などよりも、人間自身が自然と合致させる普遍的善悪のほうをより尊重する。
それすらなくなるのが法治社会であり、何も大社会だからといって必ずしも法治社会で
なければならないわけではなく、法治社会には必ず徳治を上乗せすることができる。
人間自身の自然な取り決めから乖離した所に作為的な善悪を置く、それを根絶すべきだ
などとまでは言わないが、少なくともそんな行いを良質なものだなどと見なすべきではない。
「神が即した法規に即して善を為し、神の計らいによって楽果を受ける」というような
虚構の因果応報の流布も大概にすべきであり、そんな所に真の善因楽果などあり得ない
とすら考えてしかるべきだ。そんな所に全てを還元するというのなら、かえって
それによる甚大な悪因苦果の最終的なぶり返しこそが危ぶまれるというものだ。
「仁は天下の表なり、義は天下の制なり、報は天下の利なり」
「仁は天下に遍くその正大さを表すものであり、義はその正大さに即して天下を制するものである。
そしてその仁義の報いが天下の大利となる。(大乗仏教の唯識思想などが構築される500年以上前から、
善因楽果の因果応報が自明なものとして把捉されている。仁徳に超越者の介在の余地などはない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・表記第三十二より)
多少は必要となるものである。とはいえ当該の社会が徳治社会であるのならば、法文による
善悪の規定などよりも、人間自身が自然と合致させる普遍的善悪のほうをより尊重する。
それすらなくなるのが法治社会であり、何も大社会だからといって必ずしも法治社会で
なければならないわけではなく、法治社会には必ず徳治を上乗せすることができる。
人間自身の自然な取り決めから乖離した所に作為的な善悪を置く、それを根絶すべきだ
などとまでは言わないが、少なくともそんな行いを良質なものだなどと見なすべきではない。
「神が即した法規に即して善を為し、神の計らいによって楽果を受ける」というような
虚構の因果応報の流布も大概にすべきであり、そんな所に真の善因楽果などあり得ない
とすら考えてしかるべきだ。そんな所に全てを還元するというのなら、かえって
それによる甚大な悪因苦果の最終的なぶり返しこそが危ぶまれるというものだ。
「仁は天下の表なり、義は天下の制なり、報は天下の利なり」
「仁は天下に遍くその正大さを表すものであり、義はその正大さに即して天下を制するものである。
そしてその仁義の報いが天下の大利となる。(大乗仏教の唯識思想などが構築される500年以上前から、
善因楽果の因果応報が自明なものとして把捉されている。仁徳に超越者の介在の余地などはない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・表記第三十二より)
なぜ「しれっと」した書き込みは連続規制ではないのですか
明和は今日で終わり。書き込みも無意味で無駄。
「聖書」の話題になるとしつこいのがいるからなぁ。
情報傍受システムで何もつくるきにもならない。ほんまに
しょうーもないのはその手段と結局自分等のはばきかせ。
明和は今日で終わり。書き込みも無意味で無駄。
「聖書」の話題になるとしつこいのがいるからなぁ。
情報傍受システムで何もつくるきにもならない。ほんまに
しょうーもないのはその手段と結局自分等のはばきかせ。
「最終的な安楽への到達」というものが、結局のところ、東洋では一貫して劣後されている。
極楽浄土への往生を乞い願う浄土教ですら、来世に往生する「体失往生」よりも、
現世でありのままに往生する「不体失往生」のほうが本懐だとされている。
他力信仰としてみれば不自然な気もするが、生きてるうちからの成道による有余涅槃があって、
死んで無余涅槃に達するという仏法のあり方に即すれば、むしろこのほうが至当となっている。
>>259の「礼記」からの引用を見ても分かるように、東洋文化というのは概ね、善因楽果悪因苦果の
罪福異熟に対する漠然とした察知が伴っている。罪福異熟を特に理論的に究明しているのは大乗仏教の
唯識学派だが、別に唯識派に限らずとも、他の多くの東洋思想哲学宗教が罪福異熟に相当する法則を予め
諾っている。また、それぐらいは当然のこととして踏まえているような教学(儒学や仏教など)こそが正統
とされ、それすら踏まえられていないような教学(縦横家や害為正法外道など)こそが異端ともされている。
自らの身命を損なってまで孝養に務められた者はいない、孝養にすら務められないのだから、
天下のための仁行などにも当然務められはしないというのが、儒家の基本的な姿勢でもある。
この考え方も、善因楽果の諾いに強固に根ざしていて、もしもこの逆に、自殺行為や親子兄弟での
殺し合いなどによって天国の到来のような結果が得られるとするならば、これは「悪因楽果」を肯定して
いることになり、実際にキリスト教などはかくの如き罪福異熟に違背する法則を肯定しているわけである。
「苦難の先に福徳が待っている」と言えばいかにも聞こえがよく、実際に孟子も告子章句下・一五で
それに似たことを言ったりもしているわけだが、楽果の因子となる行いはあくまで善行だから、
善行を為すにことかけての「浩然の気」からなる清々しさが必ず付帯している。だから、
行いとしてどんなに苦難であるとした所で、悪行を為す時に伴うような、疚しさからなる
不健全な苦しみなどは伴わない。だから「(悪徳商人のように)肩をそびやかして諂い笑うのは、
真夏の炎天下に田畑を耕すよりも疲れる(滕文公章句下・七)」ともいうのである。
極楽浄土への往生を乞い願う浄土教ですら、来世に往生する「体失往生」よりも、
現世でありのままに往生する「不体失往生」のほうが本懐だとされている。
他力信仰としてみれば不自然な気もするが、生きてるうちからの成道による有余涅槃があって、
死んで無余涅槃に達するという仏法のあり方に即すれば、むしろこのほうが至当となっている。
>>259の「礼記」からの引用を見ても分かるように、東洋文化というのは概ね、善因楽果悪因苦果の
罪福異熟に対する漠然とした察知が伴っている。罪福異熟を特に理論的に究明しているのは大乗仏教の
唯識学派だが、別に唯識派に限らずとも、他の多くの東洋思想哲学宗教が罪福異熟に相当する法則を予め
諾っている。また、それぐらいは当然のこととして踏まえているような教学(儒学や仏教など)こそが正統
とされ、それすら踏まえられていないような教学(縦横家や害為正法外道など)こそが異端ともされている。
自らの身命を損なってまで孝養に務められた者はいない、孝養にすら務められないのだから、
天下のための仁行などにも当然務められはしないというのが、儒家の基本的な姿勢でもある。
この考え方も、善因楽果の諾いに強固に根ざしていて、もしもこの逆に、自殺行為や親子兄弟での
殺し合いなどによって天国の到来のような結果が得られるとするならば、これは「悪因楽果」を肯定して
いることになり、実際にキリスト教などはかくの如き罪福異熟に違背する法則を肯定しているわけである。
「苦難の先に福徳が待っている」と言えばいかにも聞こえがよく、実際に孟子も告子章句下・一五で
それに似たことを言ったりもしているわけだが、楽果の因子となる行いはあくまで善行だから、
善行を為すにことかけての「浩然の気」からなる清々しさが必ず付帯している。だから、
行いとしてどんなに苦難であるとした所で、悪行を為す時に伴うような、疚しさからなる
不健全な苦しみなどは伴わない。だから「(悪徳商人のように)肩をそびやかして諂い笑うのは、
真夏の炎天下に田畑を耕すよりも疲れる(滕文公章句下・七)」ともいうのである。
浩然の気からなる清々しさすら伴わない、疚しさばかりにまみれた不健全な苦しみの先に、楽果が
期待できるなんてことまでは、さすがにない。それは罪福異熟の絶対真理にも即して断じられることだし、
上記のような儒学レベルの漠然とした論及に即しても、納得づくめで断定する他のないものである。
自分が強盗殺人を犯して逃亡し回っていて、当局の操作から逃げ回ってもはやヘトヘトでいる、それ程にも
苦労したから罪が報われるなんていう、都合のいい話が当然あるはずもなく、往生際も悪く逃げ回り続けて
来たことによる罪状が新たに加味されて、一層の重刑が科されるというばかりのことにしかならない。
「悪因楽果」などというものが存在しない実例もかくの如くであり、どこにも不思議な所はないといえる。
努力して苦労するにも、そうすべき処と、そうすべきでない処がある。考えてみれば、当たり前のことである。
「昔、仲尼蜡賓に与り、事畢りて、観の上に出て遊び、喟然と而て嘆く。
仲尼の嘆くは、蓋し魯を嘆くなり。言偃側らに在りて曰く、君子何を嘆く。孔子曰く、
大道の行われるや、三代の英に与れる、丘未だ之れに逮ばざるなり、而こうして志有り」
「昔、孔子が魯の蜡祭に賓客として招かれたとき、祭事の後に観台の上に登って、溜息をしながら嘆いた。
孔子が嘆いたのは魯の現状を嘆いてのことだった。近侍していた弟子の言偃が『なぜ嘆いているのですか』
と問うと、孔子は答えた。『夏殷周の三代の頃には、英智によって世に大道が敷かれていたというのに、
私は未だそれに及ぶことができない。志しだけはあるというのに』(その嘆き方も聖人君子ならではのもので、
心の中ではなく天下に大道が敷かれることこそが望みなのだから、下手な気休めも決して及びはしない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・礼運第九より)
期待できるなんてことまでは、さすがにない。それは罪福異熟の絶対真理にも即して断じられることだし、
上記のような儒学レベルの漠然とした論及に即しても、納得づくめで断定する他のないものである。
自分が強盗殺人を犯して逃亡し回っていて、当局の操作から逃げ回ってもはやヘトヘトでいる、それ程にも
苦労したから罪が報われるなんていう、都合のいい話が当然あるはずもなく、往生際も悪く逃げ回り続けて
来たことによる罪状が新たに加味されて、一層の重刑が科されるというばかりのことにしかならない。
「悪因楽果」などというものが存在しない実例もかくの如くであり、どこにも不思議な所はないといえる。
努力して苦労するにも、そうすべき処と、そうすべきでない処がある。考えてみれば、当たり前のことである。
「昔、仲尼蜡賓に与り、事畢りて、観の上に出て遊び、喟然と而て嘆く。
仲尼の嘆くは、蓋し魯を嘆くなり。言偃側らに在りて曰く、君子何を嘆く。孔子曰く、
大道の行われるや、三代の英に与れる、丘未だ之れに逮ばざるなり、而こうして志有り」
「昔、孔子が魯の蜡祭に賓客として招かれたとき、祭事の後に観台の上に登って、溜息をしながら嘆いた。
孔子が嘆いたのは魯の現状を嘆いてのことだった。近侍していた弟子の言偃が『なぜ嘆いているのですか』
と問うと、孔子は答えた。『夏殷周の三代の頃には、英智によって世に大道が敷かれていたというのに、
私は未だそれに及ぶことができない。志しだけはあるというのに』(その嘆き方も聖人君子ならではのもので、
心の中ではなく天下に大道が敷かれることこそが望みなのだから、下手な気休めも決して及びはしない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・礼運第九より)
悟りをひらいた者こそは、悲観を捨てて楽観(常楽我浄)に入るのでも
あるからこそ、西洋人などなら「ニヒリズムだ」などとも決め付けかねない
ような教義的特徴をも持つ仏教が、東洋では真摯に貴ばれて来てもいる。
厳格すぎて気が狂う者も昔はよく居たという、座禅修行などを通じて悟りをひらくことで、
かえって「蠢動含霊のウジ虫に至るまで価値があることに気づく(山本玄峰)」という。
禅仏教こそは特定の神を尊崇したりすることもない、ニヒリズムにも最も近しい教義を持つが、
ニーチェやヒトラーの如き西洋のニヒリストと違って、禅僧は無宗教的な愛執に至るまで
全ての情念を捨離しきって、無念無想の極みの先にこそ悟りをひらく。そしてその悟りこそは
無闇に事物を軽視したり嫌悪したりすることもない、歓喜と恭敬とを兼ね備えてもいるのである。
それは、ニヒリズムを抱いた人間が必ずしも到れるような境地ではなく、適切な精進修行も介さない
限りにおいては到底、到れるものでもない。特に、無宗教的な愛執に至るまでの全ての情念を俗世で
振り切ることが極めて困難で、それに失敗してしまうからこそ、単なるニヒリストというのは概ね、
悲観にまみれた情念に囚われて、万事万物に対する軽蔑や嫌悪を抱くようになってしまうのである。
その悲観的な情念を楽観的な情念に転換するために、ニヒリストから神格信仰者へと転向するとする、
それが先祖崇拝程度に止まるのなら決して悪くはないし、架空の神仏を信仰対象とするのであっても、
当該の神仏の品質がそれなりに上等であれば、情念そのものの制御が効いて問題を来すことがない。
しかし、信仰の対象が全知全能の絶対超越神などであるために、まるで何でも買ってくれる
売春相手を溺愛する娼婦か何かのような心境に自らが陥ったとする。そしたらそのような対象を
信仰してしまったせいでどこまでも情念が激化することになり、その情念が「失神」によって楽観から
悲観に転じたりしたならば、自殺級の悪念に自らが見舞われるようなことにすらなってしまうのである。
あるからこそ、西洋人などなら「ニヒリズムだ」などとも決め付けかねない
ような教義的特徴をも持つ仏教が、東洋では真摯に貴ばれて来てもいる。
厳格すぎて気が狂う者も昔はよく居たという、座禅修行などを通じて悟りをひらくことで、
かえって「蠢動含霊のウジ虫に至るまで価値があることに気づく(山本玄峰)」という。
禅仏教こそは特定の神を尊崇したりすることもない、ニヒリズムにも最も近しい教義を持つが、
ニーチェやヒトラーの如き西洋のニヒリストと違って、禅僧は無宗教的な愛執に至るまで
全ての情念を捨離しきって、無念無想の極みの先にこそ悟りをひらく。そしてその悟りこそは
無闇に事物を軽視したり嫌悪したりすることもない、歓喜と恭敬とを兼ね備えてもいるのである。
それは、ニヒリズムを抱いた人間が必ずしも到れるような境地ではなく、適切な精進修行も介さない
限りにおいては到底、到れるものでもない。特に、無宗教的な愛執に至るまでの全ての情念を俗世で
振り切ることが極めて困難で、それに失敗してしまうからこそ、単なるニヒリストというのは概ね、
悲観にまみれた情念に囚われて、万事万物に対する軽蔑や嫌悪を抱くようになってしまうのである。
その悲観的な情念を楽観的な情念に転換するために、ニヒリストから神格信仰者へと転向するとする、
それが先祖崇拝程度に止まるのなら決して悪くはないし、架空の神仏を信仰対象とするのであっても、
当該の神仏の品質がそれなりに上等であれば、情念そのものの制御が効いて問題を来すことがない。
しかし、信仰の対象が全知全能の絶対超越神などであるために、まるで何でも買ってくれる
売春相手を溺愛する娼婦か何かのような心境に自らが陥ったとする。そしたらそのような対象を
信仰してしまったせいでどこまでも情念が激化することになり、その情念が「失神」によって楽観から
悲観に転じたりしたならば、自殺級の悪念に自らが見舞われるようなことにすらなってしまうのである。
何もかもの願いを叶えてくれる全能の神など、この世界や宇宙には実在しない。
だからそんな神に仮託しての全能ごっこなどもいつかは潰えて、全能の神への狂信なども
強制的に途絶するしかなくなってしまう。そしたら今まで楽観的でいられた激烈な情念が、
一挙に悲観へと振れきってしまうしかなくなる。ちょうど躁病患者が鬱病患者に転換する
ようなことになり、躁がひどかったものほど、鬱に振れ切った時の自殺願望なども強くなる。
諸行無常の絶対真理にも即して、全能の超越神などに依存し過ぎた人間はそのような運命に
必ず見舞われることともなってしまうのだから、超越神への依存などによって情念を無闇に
激化させたりするようなことからして、あるべきでないことだといえる。本格の仏者のように
情念を丸ごと捨てきるのもなかなか難しいことではあるにしろ、最低でも、依存対象をあくまで
先祖やまともな神仏などに止めて、依存性からなる情念の激化にも歯止めをかけるべきだといえる。
「往く攸有るに利ろしからず、小人長ずればなり。
順に而て之れ止まる、象を観ればなり。君子消息盈虚を尚ぶ、天の行いなればなり」
「小人がその勢力を伸ばしている時には、何もかもが虚しくなって、何をするにも適さない。
このような事情をも真摯に見極めて、これに従って君子は行動を控える。天下の事情の
消息盈虚をよく尊んで蔑ろにしたりしないのも、全てが天の行いであるからに他ならぬ。」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・剥・彖伝より)
だからそんな神に仮託しての全能ごっこなどもいつかは潰えて、全能の神への狂信なども
強制的に途絶するしかなくなってしまう。そしたら今まで楽観的でいられた激烈な情念が、
一挙に悲観へと振れきってしまうしかなくなる。ちょうど躁病患者が鬱病患者に転換する
ようなことになり、躁がひどかったものほど、鬱に振れ切った時の自殺願望なども強くなる。
諸行無常の絶対真理にも即して、全能の超越神などに依存し過ぎた人間はそのような運命に
必ず見舞われることともなってしまうのだから、超越神への依存などによって情念を無闇に
激化させたりするようなことからして、あるべきでないことだといえる。本格の仏者のように
情念を丸ごと捨てきるのもなかなか難しいことではあるにしろ、最低でも、依存対象をあくまで
先祖やまともな神仏などに止めて、依存性からなる情念の激化にも歯止めをかけるべきだといえる。
「往く攸有るに利ろしからず、小人長ずればなり。
順に而て之れ止まる、象を観ればなり。君子消息盈虚を尚ぶ、天の行いなればなり」
「小人がその勢力を伸ばしている時には、何もかもが虚しくなって、何をするにも適さない。
このような事情をも真摯に見極めて、これに従って君子は行動を控える。天下の事情の
消息盈虚をよく尊んで蔑ろにしたりしないのも、全てが天の行いであるからに他ならぬ。」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・剥・彖伝より)
「焉んぞ仁人位に在る有りて、民を罔みして為むべけんや(滕文公章句上・三の重複文を引用済み)」
「どうして仁者が為政を執り行う上で、民を網で摸るような真似をすることが許されようか。
(『民を無みする』とも解す場合がある。『民を網する』と解すのは朱子の説)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・梁恵王章句上・七より)
たとえば、自由主義市場での経済戦争なり、国際紛争なりを煽ることで、万民の万民に対する
闘争状態を画策したとする。所詮はこの世界の富の絶対量も限られたものだから、闘争に勝って
富を得たものと、闘争に敗れて餓死級の貧困に見舞われるものとの両極に世界が振れきってしまう、
そのような勝ち負けの操作を行うことも、市場経済の金融システムを取り仕切っている人間などには
可能なことであり、金利の不正操作などの手続きを通じて、裏から勝ち負けを篩い分けられるのである。
そういった企てが、実際に「民を網する」行為ともなるわけで、許しがたいのは、
あくまでイカサマの博打経済に世界を司らせようとしている点にある。
孟子も反共産主義者であり(滕文公章句上・四参照)、市場にかける税などもできる限り簡素化
すべきだとの論陣を敷いているが(公孫丑章句上・五参照)、同時に無闇な商品の横流しのような、
行き過ぎた投機を戒めてもいる(公孫丑章句下・一〇参照)。上記のような言葉を述べた孟子と
いえども、市場経済の自由さを決して否定するものではないが、そこにイカサマが介在すること
まではさすがによしせず、イカサマの横行による裏からの統制が行われることを全くの非としている。
民を網するようなことがなくなったからといって、自由主義的な市場経済が滞るわけでもない。
それどころか、裏からの統制すらなくなることで、本物の自由主義市場こそが現出することともなる。
それはたとえば、江戸時代の日本の市場経済などがほぼその条件を満たせていたものであり、武士が
貧窮して刀を質屋に入れるほどにも、市場への介入が皆無であったことから発展した日本の市場経済は、
今に至っては、不正な統制を裏から行い続けてきた欧米経済をも圧倒するまでに至っている。
「どうして仁者が為政を執り行う上で、民を網で摸るような真似をすることが許されようか。
(『民を無みする』とも解す場合がある。『民を網する』と解すのは朱子の説)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・梁恵王章句上・七より)
たとえば、自由主義市場での経済戦争なり、国際紛争なりを煽ることで、万民の万民に対する
闘争状態を画策したとする。所詮はこの世界の富の絶対量も限られたものだから、闘争に勝って
富を得たものと、闘争に敗れて餓死級の貧困に見舞われるものとの両極に世界が振れきってしまう、
そのような勝ち負けの操作を行うことも、市場経済の金融システムを取り仕切っている人間などには
可能なことであり、金利の不正操作などの手続きを通じて、裏から勝ち負けを篩い分けられるのである。
そういった企てが、実際に「民を網する」行為ともなるわけで、許しがたいのは、
あくまでイカサマの博打経済に世界を司らせようとしている点にある。
孟子も反共産主義者であり(滕文公章句上・四参照)、市場にかける税などもできる限り簡素化
すべきだとの論陣を敷いているが(公孫丑章句上・五参照)、同時に無闇な商品の横流しのような、
行き過ぎた投機を戒めてもいる(公孫丑章句下・一〇参照)。上記のような言葉を述べた孟子と
いえども、市場経済の自由さを決して否定するものではないが、そこにイカサマが介在すること
まではさすがによしせず、イカサマの横行による裏からの統制が行われることを全くの非としている。
民を網するようなことがなくなったからといって、自由主義的な市場経済が滞るわけでもない。
それどころか、裏からの統制すらなくなることで、本物の自由主義市場こそが現出することともなる。
それはたとえば、江戸時代の日本の市場経済などがほぼその条件を満たせていたものであり、武士が
貧窮して刀を質屋に入れるほどにも、市場への介入が皆無であったことから発展した日本の市場経済は、
今に至っては、不正な統制を裏から行い続けてきた欧米経済をも圧倒するまでに至っている。
民を網するがごとき、イカサマの統制が裏から介され続けて来たことで、欧米経済を中心とする
世界経済は非常識な勢いでの膨張を続けてきた。稼働すればするほど金融システムの元締めに
暴利が流出して行ってしまうことからなる不安定さが、人々に狂乱的な経済競争をけしかけて来た。
それがもはや飽和点に達して、これ以上の膨張を維持するためには世界戦争すら避けられない様相を
呈してしまっている。当然、次の世界戦争では核攻撃により破滅的被害を被ることが避けられないので、
これ以上の"民を網する"イカサマ経済の膨張すなわち人類滅亡の事態ともあいなってしまっているのである。
そのような自体を回避するために必要なのは、自由主義経済全体の閉鎖ではなく、民を網する
イカサマ経済の終了である。無闇な投機の放任なり、金利の不正操作なり、各国中央銀行の談合なりの、
むしろ市場の健全性を損なってしまっているような要素こそを駆逐し、まともな商売を心がける
者には、今まで以上に自由なサービスを推進していけるような余地をも与えてやるのだ。
「是の月や、司空に命じて曰く、時雨将に降らんとし、下水上騰せん。
〜田獵の罝罘、羅網、畢翳、獣に騊わすの薬、九門より出す毋れと」
「川水の氾濫の危険もある雨期に至り、国土の保全を司る役人に命じ、
大小の鳥獣の狩りのために用いる網や麻酔薬などを城門から持ち出さないようにさせる。
(旧約創世記やイエスが到来を予言しているような非常時に、網を用いるような大規模な狩りは行わない。
日本の漁師なども当然、台風や暴風雨などの到来した時期の漁は休む。火事場泥棒的狩漁の禁)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・月令第六より)
世界経済は非常識な勢いでの膨張を続けてきた。稼働すればするほど金融システムの元締めに
暴利が流出して行ってしまうことからなる不安定さが、人々に狂乱的な経済競争をけしかけて来た。
それがもはや飽和点に達して、これ以上の膨張を維持するためには世界戦争すら避けられない様相を
呈してしまっている。当然、次の世界戦争では核攻撃により破滅的被害を被ることが避けられないので、
これ以上の"民を網する"イカサマ経済の膨張すなわち人類滅亡の事態ともあいなってしまっているのである。
そのような自体を回避するために必要なのは、自由主義経済全体の閉鎖ではなく、民を網する
イカサマ経済の終了である。無闇な投機の放任なり、金利の不正操作なり、各国中央銀行の談合なりの、
むしろ市場の健全性を損なってしまっているような要素こそを駆逐し、まともな商売を心がける
者には、今まで以上に自由なサービスを推進していけるような余地をも与えてやるのだ。
「是の月や、司空に命じて曰く、時雨将に降らんとし、下水上騰せん。
〜田獵の罝罘、羅網、畢翳、獣に騊わすの薬、九門より出す毋れと」
「川水の氾濫の危険もある雨期に至り、国土の保全を司る役人に命じ、
大小の鳥獣の狩りのために用いる網や麻酔薬などを城門から持ち出さないようにさせる。
(旧約創世記やイエスが到来を予言しているような非常時に、網を用いるような大規模な狩りは行わない。
日本の漁師なども当然、台風や暴風雨などの到来した時期の漁は休む。火事場泥棒的狩漁の禁)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・月令第六より)
試練は試練、それ自体はどこまでも苦しみ。
ただその試練が仁徳のような正義の実現のためのものであるからには、
善行の一環であるが故の善因楽果としての浩然の気が伴う。
だから、相当に厳しい試練の中でもケロッとしていられたりする。
戦時中、日本軍がフィリピンのバターン半島で行った、アメリカ兵やフィリピン兵の
捕虜に対する徒歩での移動措置、いわゆる「死の行進」で、日本兵は別に捕虜たちに
虐待を強いたようなつもりはなかった。自分たちが「当然このぐらいは可能だろう」
と考える程度の、日に約20キロの、炎天下での栄養不足状態での行進を強いた結果、
多数のアメリカ兵らが飢えや疲労などで死亡した。別に第二次世界大戦における日本の
戦いに必ずしも大義があったなどとも言えないが、少なくとも末端の兵士あたりは
自分たちの行いがアジア諸国の白人支配からの解放のような正当な目的を伴っていると
堅く信じていたから、米兵あたりにやらせれば即死してしまうような過酷な任務すらをも、
浩然の気からなるすがすがしさと共にたやすくこなしてしまえていたのである。
そういったすかすがしさは、戦後の日本人にこそなくなってしまった。
ただひたすら経済的覇権を拡大していくエコノミック・アニマルとしての勤めようを
何とか美化しようとしてみた所で、やはりそこに浩然の気までは伴っていないわけだから、
「ただひたすら過労の苦痛を耐え忍んで」というような表現の仕方しかしようがない。
それこそ、昭和天皇の「耐え難きを耐え、忍び難きを忍び」という玉音放送の一文にも
符合しているわけだが(この一文を考案したのが>>263で挙げた山本玄峰老師でもある)、
今の日本ではもはや社会的な行いの全てが浩然の気のすがすがしさ抜きでしかあり得ないから、
「耐え忍び難いところをあえて耐え忍んで」という所に、全てを還元するしかないのである。
ただその試練が仁徳のような正義の実現のためのものであるからには、
善行の一環であるが故の善因楽果としての浩然の気が伴う。
だから、相当に厳しい試練の中でもケロッとしていられたりする。
戦時中、日本軍がフィリピンのバターン半島で行った、アメリカ兵やフィリピン兵の
捕虜に対する徒歩での移動措置、いわゆる「死の行進」で、日本兵は別に捕虜たちに
虐待を強いたようなつもりはなかった。自分たちが「当然このぐらいは可能だろう」
と考える程度の、日に約20キロの、炎天下での栄養不足状態での行進を強いた結果、
多数のアメリカ兵らが飢えや疲労などで死亡した。別に第二次世界大戦における日本の
戦いに必ずしも大義があったなどとも言えないが、少なくとも末端の兵士あたりは
自分たちの行いがアジア諸国の白人支配からの解放のような正当な目的を伴っていると
堅く信じていたから、米兵あたりにやらせれば即死してしまうような過酷な任務すらをも、
浩然の気からなるすがすがしさと共にたやすくこなしてしまえていたのである。
そういったすかすがしさは、戦後の日本人にこそなくなってしまった。
ただひたすら経済的覇権を拡大していくエコノミック・アニマルとしての勤めようを
何とか美化しようとしてみた所で、やはりそこに浩然の気までは伴っていないわけだから、
「ただひたすら過労の苦痛を耐え忍んで」というような表現の仕方しかしようがない。
それこそ、昭和天皇の「耐え難きを耐え、忍び難きを忍び」という玉音放送の一文にも
符合しているわけだが(この一文を考案したのが>>263で挙げた山本玄峰老師でもある)、
今の日本ではもはや社会的な行いの全てが浩然の気のすがすがしさ抜きでしかあり得ないから、
「耐え忍び難いところをあえて耐え忍んで」という所に、全てを還元するしかないのである。
戦前といえども、政財界や軍部の上層部などの腐敗が著しかったことには変わりなく、
決して当時に戻りすらすればいいなんてはずもないわけだが、未だ徳育教育も行われていた頃の
庶民の道徳観の高さなどには、確かに見習うに値するものがあり、その頃の生存者が日本社会の
上層部にもある程度食い込めていたからこそ、ほんのこの前まで日本社会も最悪級の腐敗までは
どうにか免れられてもいた。もはやその時代も過ぎて、戦後生まれの団塊世代が世の中のトップ
に君臨し始めたために、世相の腐敗もついに極まり、権力者に見るべき所が少しもなくなった。
円高の野放しによる国内産業の空洞化が著しい一方、日本人だからこそこなせていた
過酷な生産労働を中国やインドなどに移管した結果、大きな反発を招き、領土問題などに
ことかけての反日運動を激化させる温床ともなっている。日本の権力者の行いにも、道義性の
欠片すら認められず、ただひたすら自分たちの利益を維持や拡大していこうとする魂胆ばかりが
見え透いているため、尖閣諸島などの領土問題については日本に分があるにしても、不満の矛先を
日本に向けたがる今の中国人の心境も、全く看過し去っていいものであるともいえないのである。
徳育教育も受けていた戦前生まれの日本人がトップを走っていた頃には、「耐え難きを耐え、
忍び難きを忍び」でも何とか持っていたが、それも過ぎ去った今となっては、もはやこのまま
でもいけない。奴隷か牛馬の如く苦しみに煩悶しつつこき使われるばかりでは道義性は伴わず、
浩然の気を保てるぐらいであってこそ道義性も保てる。その判別能力のある者が世の中から
完全に消え去ってしまった今、むしろ浩然の気と共に物事を為していくことを人工的に矯正して
いく必要性すらもが生じている。徳育教育の復活などもその手段になることはなるが、学生への
徳育が有効性を持つぐらいに世の中の側から変革していくことが、やはり必要ともなるだろう。
決して当時に戻りすらすればいいなんてはずもないわけだが、未だ徳育教育も行われていた頃の
庶民の道徳観の高さなどには、確かに見習うに値するものがあり、その頃の生存者が日本社会の
上層部にもある程度食い込めていたからこそ、ほんのこの前まで日本社会も最悪級の腐敗までは
どうにか免れられてもいた。もはやその時代も過ぎて、戦後生まれの団塊世代が世の中のトップ
に君臨し始めたために、世相の腐敗もついに極まり、権力者に見るべき所が少しもなくなった。
円高の野放しによる国内産業の空洞化が著しい一方、日本人だからこそこなせていた
過酷な生産労働を中国やインドなどに移管した結果、大きな反発を招き、領土問題などに
ことかけての反日運動を激化させる温床ともなっている。日本の権力者の行いにも、道義性の
欠片すら認められず、ただひたすら自分たちの利益を維持や拡大していこうとする魂胆ばかりが
見え透いているため、尖閣諸島などの領土問題については日本に分があるにしても、不満の矛先を
日本に向けたがる今の中国人の心境も、全く看過し去っていいものであるともいえないのである。
徳育教育も受けていた戦前生まれの日本人がトップを走っていた頃には、「耐え難きを耐え、
忍び難きを忍び」でも何とか持っていたが、それも過ぎ去った今となっては、もはやこのまま
でもいけない。奴隷か牛馬の如く苦しみに煩悶しつつこき使われるばかりでは道義性は伴わず、
浩然の気を保てるぐらいであってこそ道義性も保てる。その判別能力のある者が世の中から
完全に消え去ってしまった今、むしろ浩然の気と共に物事を為していくことを人工的に矯正して
いく必要性すらもが生じている。徳育教育の復活などもその手段になることはなるが、学生への
徳育が有効性を持つぐらいに世の中の側から変革していくことが、やはり必要ともなるだろう。
「予れ其れ懲りて、後の患えを鋆まん。予れ蜂を荓いて、自ら辛螫を求むる莫し」
「私は苦しみには素直に懲りて、後の患いを減らしていくことに務める。自分から
蜂をつついて刺されるような、痛苦をあえて求めるような馬鹿な真似はしない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・頌・周頌・閔予小子之什・小鋆より)
「私は苦しみには素直に懲りて、後の患いを減らしていくことに務める。自分から
蜂をつついて刺されるような、痛苦をあえて求めるような馬鹿な真似はしない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・頌・周頌・閔予小子之什・小鋆より)
「君子の徳は風なり、小人の徳は草なり。草に之れ風をくわうれば、必ずふす(既出)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・顔淵第十二・一九より)
犯罪聖書の暴言と比べれば、真正聖書における上記のような表現上の「風」が、
人々に良質な影響を及ぼす徳化の比喩であることが如実ともなっている。
「草に対する風」という表現は、いかにも下民に形而上的な立場から君臨する何者かであるらしい。
その形而上的な何者かが真正聖書中では「君子」と表現されていて、君子は「立派な人間」と共に、
「正規の為政者」という意味を帯びている。孔子や孟子も正規家臣としての士官をあくまで志し続けていたように、
下民に対して形而上的な存在として君臨するからには、それなりの正式な手続きを追わなければならないとしている。
一方、犯罪聖書における「草に対する風」は、そのまま「形而上の超越神」として表現されている。
実際にそうであるのならともかく、これは全くの架空であり、実際には政商や食客や縦横家の如き汚れ仕事に
よって世界を引っ掻き回す権力犯罪者のことを指している。古代ユダヤ人も政商詐欺集団であったように、権力に
不正な形で取り入るならず者こそは「草に対する風」とされ、故に、その風が吹けば草花も枯れてしまうのである。
真正聖書(四書五経)も犯罪聖書(新旧約聖書)も、形而上的な立場にある何者かによって下民が支配されるという
形式を執っていることには変わりなく、しかも現実的には、いずれもが社会的な実権を保持する権力者による支配を
念頭に置いている。違うのは、真正聖書は正規の権力者が公明正大に世の中を統治することを是としているのに対し、
犯罪聖書は不正な権力者が陰湿な手法によって世界を強権的な支配下に置くことを是としている点にある。
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・顔淵第十二・一九より)
犯罪聖書の暴言と比べれば、真正聖書における上記のような表現上の「風」が、
人々に良質な影響を及ぼす徳化の比喩であることが如実ともなっている。
「草に対する風」という表現は、いかにも下民に形而上的な立場から君臨する何者かであるらしい。
その形而上的な何者かが真正聖書中では「君子」と表現されていて、君子は「立派な人間」と共に、
「正規の為政者」という意味を帯びている。孔子や孟子も正規家臣としての士官をあくまで志し続けていたように、
下民に対して形而上的な存在として君臨するからには、それなりの正式な手続きを追わなければならないとしている。
一方、犯罪聖書における「草に対する風」は、そのまま「形而上の超越神」として表現されている。
実際にそうであるのならともかく、これは全くの架空であり、実際には政商や食客や縦横家の如き汚れ仕事に
よって世界を引っ掻き回す権力犯罪者のことを指している。古代ユダヤ人も政商詐欺集団であったように、権力に
不正な形で取り入るならず者こそは「草に対する風」とされ、故に、その風が吹けば草花も枯れてしまうのである。
真正聖書(四書五経)も犯罪聖書(新旧約聖書)も、形而上的な立場にある何者かによって下民が支配されるという
形式を執っていることには変わりなく、しかも現実的には、いずれもが社会的な実権を保持する権力者による支配を
念頭に置いている。違うのは、真正聖書は正規の権力者が公明正大に世の中を統治することを是としているのに対し、
犯罪聖書は不正な権力者が陰湿な手法によって世界を強権的な支配下に置くことを是としている点にある。
そもそも、一部の権力者による下民への一方的な支配に非を唱えたのが「民主主義」であり、いま民主主義国と
されているような国ではその目的が一程度は達成されているかのように表向き捉えられている。実際には全く
そんなことはなく、犯罪聖書が「形而上の超越神」と表現する所の、政商や悪徳外交家の如き権力犯罪者が
裏からの絶対的支配を確立しているのが民主主義社会なだけでしかない。「民は上に主君を頂くのでなければ、
自分たちで正し合って生きていくこともできない(書経・太甲中)」ともあるとおり、本当に無政府状態、
無支配状態と化してしまった民衆社会というのは、今のソマリアのような最悪の争乱状態に陥るしかない。
だから結局陰にであれ陽にであれ、一定以上に大規模な都市社会を健全に保っていくためには、ほとんど
形而上的な程もの権能を持つ強大な支配者が必須となるわけだが、陰ながらの支配だけでは、これまたどうしたって
不足する所がある。いくら監視者としての統制力などを強めてみた所で、裏からの支配ばかりでは、民たちの
思い上がりまでをも制することができない。思い上がりにまみれた民たちの欲望を無制限に叶え続けようとした結果、
他国への侵略戦争による資源の収奪みたいな悪逆非道にすら及ばなければならなくなる。当然そんな暴慢まみれの
統治がいつまでも持つわけがないから、民主制の革をかむった裏からの支配も、いつかは潰えるしかない。
裏からの支配が潰えて、表からの君子による支配を復権するしかなくなるとして、それが「民主化の挫折」などと
触れ回ったりするのは、欺瞞の至りだといえる。民主制だろうが独裁制だろうが、何者かによる強権的な支配が
存続し続けていたのには変わりない、ただ裏からの強権支配の挫折が、表向きの民主制の終焉に連動してしまう
というばかりのことなのだから、むしろその、裏からの強権支配の頓挫こそを専らな問題視の対象とせねばならない。
「大社会には絶対的な支配者が必須である」と再認識することによって、表向きばかりの幻想も絶たねばならない。
されているような国ではその目的が一程度は達成されているかのように表向き捉えられている。実際には全く
そんなことはなく、犯罪聖書が「形而上の超越神」と表現する所の、政商や悪徳外交家の如き権力犯罪者が
裏からの絶対的支配を確立しているのが民主主義社会なだけでしかない。「民は上に主君を頂くのでなければ、
自分たちで正し合って生きていくこともできない(書経・太甲中)」ともあるとおり、本当に無政府状態、
無支配状態と化してしまった民衆社会というのは、今のソマリアのような最悪の争乱状態に陥るしかない。
だから結局陰にであれ陽にであれ、一定以上に大規模な都市社会を健全に保っていくためには、ほとんど
形而上的な程もの権能を持つ強大な支配者が必須となるわけだが、陰ながらの支配だけでは、これまたどうしたって
不足する所がある。いくら監視者としての統制力などを強めてみた所で、裏からの支配ばかりでは、民たちの
思い上がりまでをも制することができない。思い上がりにまみれた民たちの欲望を無制限に叶え続けようとした結果、
他国への侵略戦争による資源の収奪みたいな悪逆非道にすら及ばなければならなくなる。当然そんな暴慢まみれの
統治がいつまでも持つわけがないから、民主制の革をかむった裏からの支配も、いつかは潰えるしかない。
裏からの支配が潰えて、表からの君子による支配を復権するしかなくなるとして、それが「民主化の挫折」などと
触れ回ったりするのは、欺瞞の至りだといえる。民主制だろうが独裁制だろうが、何者かによる強権的な支配が
存続し続けていたのには変わりない、ただ裏からの強権支配の挫折が、表向きの民主制の終焉に連動してしまう
というばかりのことなのだから、むしろその、裏からの強権支配の頓挫こそを専らな問題視の対象とせねばならない。
「大社会には絶対的な支配者が必須である」と再認識することによって、表向きばかりの幻想も絶たねばならない。
「民事を軽んずること無く、惟れを難くせよ」
「民衆たちの労役などの営みを決して軽んじてはならない。困難なものであることを察して尊重してやらねばならない。
(自分たちの営みが困難なものであればこそ、民たちも自分たちで政治までは取り仕切れないのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・商書・太甲下より)
「民衆たちの労役などの営みを決して軽んじてはならない。困難なものであることを察して尊重してやらねばならない。
(自分たちの営みが困難なものであればこそ、民たちも自分たちで政治までは取り仕切れないのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・商書・太甲下より)
税吏、酷吏、関所役人、このあたりは特に民衆から嫌われやすい官吏の典型だといえるが、さりとて
「賤業」にまでは当たらず、いっぱしの士人として扱われるべき役職でであることには違いない。
赤穂四十七士筆頭、大石内蔵助の息子の通称「主税(ちから)」なども、士人が
年貢などの民からの税によって力を得ていることをあからさまに示したものとなっている。
>>270-271でも述べた通り、ある程度以上に大規模な都市社会には形而上的な権限を持つ統制者
というものが少なからず必要になるもので、全くの無統制状態ではソマリア級の争乱すら避けられない。
どうしたって強大な統制者が必要である以上は、人々からの正式な信認を受けた政府がその立場を
担うべきで、正式な政府は当然、民からの納税によってその運営が保全される。人々を形而上的な
権限によって統制することも生半なことではないから、自分たち自身で耕し織りながら為政にも
携わるなんてことも無理なので、確信的に租税を食い物として人々の統制に臨むのである。
それが結局、世の中を統治する手法として最善であり、それと比べれば民間の政商による裏からの
支配などは、どうしたって大局社会の脆弱化や破綻を招いてしまうものだから、最善とは言えない。
所詮は租税を食い物とするものこそが専門的に人々の統治に取り組んでこそ最善となるのだから、
決して税制の存在自体を非難したりしてはならず、為政者の放辟邪侈のために民間人が重税を
強いられるような不正がある場合に限って、その問題のみを特定して非難するようにせねばならない。
税制を伴う正規の政府の価値を認めない、あるとした所でその存在を卑賤視する、
これこそは「最善を否定する」姿勢であり、劣悪か最悪かのいずれかでしかあり得ない態度となる。
特に度し難いのは、正規の政府を認めないこと以上にも、その存在価値を卑しむことのほうだといえる。
完全な無政府状態では現ソマリア級の争乱すらまぬがれ得ないから、完全な無政府主義なんてのも
そんなに勢力を保てるものじゃない。正規の政府の存在価値を卑しむことのほうが、キリスト教団の
ような形での勢力の拡大や維持に加担しやすいため、実質的にはこちらをより警戒すべきだといえる。
「賤業」にまでは当たらず、いっぱしの士人として扱われるべき役職でであることには違いない。
赤穂四十七士筆頭、大石内蔵助の息子の通称「主税(ちから)」なども、士人が
年貢などの民からの税によって力を得ていることをあからさまに示したものとなっている。
>>270-271でも述べた通り、ある程度以上に大規模な都市社会には形而上的な権限を持つ統制者
というものが少なからず必要になるもので、全くの無統制状態ではソマリア級の争乱すら避けられない。
どうしたって強大な統制者が必要である以上は、人々からの正式な信認を受けた政府がその立場を
担うべきで、正式な政府は当然、民からの納税によってその運営が保全される。人々を形而上的な
権限によって統制することも生半なことではないから、自分たち自身で耕し織りながら為政にも
携わるなんてことも無理なので、確信的に租税を食い物として人々の統制に臨むのである。
それが結局、世の中を統治する手法として最善であり、それと比べれば民間の政商による裏からの
支配などは、どうしたって大局社会の脆弱化や破綻を招いてしまうものだから、最善とは言えない。
所詮は租税を食い物とするものこそが専門的に人々の統治に取り組んでこそ最善となるのだから、
決して税制の存在自体を非難したりしてはならず、為政者の放辟邪侈のために民間人が重税を
強いられるような不正がある場合に限って、その問題のみを特定して非難するようにせねばならない。
税制を伴う正規の政府の価値を認めない、あるとした所でその存在を卑賤視する、
これこそは「最善を否定する」姿勢であり、劣悪か最悪かのいずれかでしかあり得ない態度となる。
特に度し難いのは、正規の政府を認めないこと以上にも、その存在価値を卑しむことのほうだといえる。
完全な無政府状態では現ソマリア級の争乱すらまぬがれ得ないから、完全な無政府主義なんてのも
そんなに勢力を保てるものじゃない。正規の政府の存在価値を卑しむことのほうが、キリスト教団の
ような形での勢力の拡大や維持に加担しやすいため、実質的にはこちらをより警戒すべきだといえる。
私的な宗教勢力や政商などが、正規の政府以上の存在として世に君臨したりすることも、
社会統治は正規の政府に任せることが最善とする立場からすれば、決して許されることではない。
ただ、正規の政府の存在価値を卑しむような立場からすれば、上記のような変則的支配者の存在性も
是とすらしかねないものだから、やはりそのような政府劣後の考え方から正していかなければならない。
財界と癒着しての腐敗が著しい、今の日本政府などを支持する気になれなかったとしても全く仕方のない
ことだが、だからといって正規の政府の存在意義までをも否定し去ってしまおうとするのは行き過ぎである。
正規の政府がいかに治世を成してくれるかこそを最優先に期待し、仁政に熱心であるようなら喜んで、
自分たちから納税はおろか、寄付すらする、それぐらいの姿勢が民間人の側にもあったほうがいい。
民間人だけを見るに、日本人などにはそのような気概がまだ保たれているように思えるが、欧米人
などにはありそうに見えて、実はない。政府や政治家なんざゴミ回収業者か何かぐらいにしか考えておらず、
民間人である自分たちこそはより偉大だとすら考えている。それが道家的な隠遁思想に基づいているのなら
ともかく、民間人としてこそ大業を成そうとするような歪んだ野望すらをも帯びているのだから、頂けない。
それも長年のキリスト信仰の禍根であり、ないに越したこともないものなのだから、深い反省が必須である。
よく正規の為政者こそを貴び、自らが大業を成そうというのであっても、まずは為政者を志す、
その逆ばかりであろうとし続けてきた自分たちの性向が、最善たり得ない劣悪さや最悪さばかりを
帯びていたことをよく反省するのでなければ、元祖為政主義国の中国あたりによる征服も免れ得まい。
社会統治は正規の政府に任せることが最善とする立場からすれば、決して許されることではない。
ただ、正規の政府の存在価値を卑しむような立場からすれば、上記のような変則的支配者の存在性も
是とすらしかねないものだから、やはりそのような政府劣後の考え方から正していかなければならない。
財界と癒着しての腐敗が著しい、今の日本政府などを支持する気になれなかったとしても全く仕方のない
ことだが、だからといって正規の政府の存在意義までをも否定し去ってしまおうとするのは行き過ぎである。
正規の政府がいかに治世を成してくれるかこそを最優先に期待し、仁政に熱心であるようなら喜んで、
自分たちから納税はおろか、寄付すらする、それぐらいの姿勢が民間人の側にもあったほうがいい。
民間人だけを見るに、日本人などにはそのような気概がまだ保たれているように思えるが、欧米人
などにはありそうに見えて、実はない。政府や政治家なんざゴミ回収業者か何かぐらいにしか考えておらず、
民間人である自分たちこそはより偉大だとすら考えている。それが道家的な隠遁思想に基づいているのなら
ともかく、民間人としてこそ大業を成そうとするような歪んだ野望すらをも帯びているのだから、頂けない。
それも長年のキリスト信仰の禍根であり、ないに越したこともないものなのだから、深い反省が必須である。
よく正規の為政者こそを貴び、自らが大業を成そうというのであっても、まずは為政者を志す、
その逆ばかりであろうとし続けてきた自分たちの性向が、最善たり得ない劣悪さや最悪さばかりを
帯びていたことをよく反省するのでなければ、元祖為政主義国の中国あたりによる征服も免れ得まい。
「象は其の国を為むること有るを得ず。
天子吏を使いして其の国を治め、其の貢税を納れしむ。故に之れを放つとも謂えり」
「舜帝の弟の象は、国を治める資格もないほどに暴虐な性格だったので、体裁上は国君としての立場を与えてやりながら、
代理の官吏を派遣して一切の政治を司らせた。徴税すら代行させたので、象は追放者も同然の存在とみなされた。
(徴税自体は下級役人が行う場合が多いが、それを命ずるのは国君ですらあるのだから、決して蔑んでいいものでもない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・万章章句上・三より)
天子吏を使いして其の国を治め、其の貢税を納れしむ。故に之れを放つとも謂えり」
「舜帝の弟の象は、国を治める資格もないほどに暴虐な性格だったので、体裁上は国君としての立場を与えてやりながら、
代理の官吏を派遣して一切の政治を司らせた。徴税すら代行させたので、象は追放者も同然の存在とみなされた。
(徴税自体は下級役人が行う場合が多いが、それを命ずるのは国君ですらあるのだから、決して蔑んでいいものでもない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・万章章句上・三より)
悲しむべき所を楽しんだり、楽しむべき所を悲しんだりする喜怒哀楽の転倒は、
本人の立場が、大社会から暴利を巻き上げて自分たちだけでの虚栄を謳歌するような
「ガン細胞人種」である場合などに生ずる。春秋戦国時代末期から秦代にかけての、
王侯たちの権力犯罪まみれな有り様もまさにそのようであったから、荀子もそのような
ガン細胞人種としての喜怒哀楽の転倒に耽る者どもを「狂生の者」と呼んで揶揄していた。
物事には悲しむべきところ、楽しむべきところが実際にある。
大まかな所では、天下国家の興亡や盛衰に自らの楽しみや悲しみを連動させることが、
人としてそうあるべき姿だといえる。国や天下が繁栄に与れていれば自分もそれと共に楽しみ、
困窮や諸国の衰亡が著しいようなら、それに伴って自分も悲しむべきである。
それが正順である一方で、天下国家の繁栄を妬んだり、衰亡を楽しんだりするのが
逆順であり、これこそは「狂生」の最たるものでもあるといえる。そう断じられるのは、
天下国家の興隆が引いては自らの福徳にも結びつく一方、その衰亡が自らへの災禍にも
結びつくことが絶対的だからで、いつまでも天下国家の興亡と自らの喜怒哀楽を
転倒させ続けていることのほうが絶対に不可能なことであるからに他ならない。
そして、天下国家の興亡と自らの非楽を正順に連動させた時にこそ、最大級の楽しみや悲しみにも与る。
それこそは、もう二度と非楽を転倒させることもできないほどにも完全な楽しみや悲しみであり、
概念夢想による感情の不埒な操作からも永久に卒業してしまうほどもの絶対的な楽しみや悲しみである。
実相と概念の内で、人間の苦楽を絶対的に決定づけるのは実相のほうであり、人間にとっての
最大級の実相の大局はあくまで天下国家だから、そこでこそ、最大級かつ絶対的な非楽にも与るのである。
本人の立場が、大社会から暴利を巻き上げて自分たちだけでの虚栄を謳歌するような
「ガン細胞人種」である場合などに生ずる。春秋戦国時代末期から秦代にかけての、
王侯たちの権力犯罪まみれな有り様もまさにそのようであったから、荀子もそのような
ガン細胞人種としての喜怒哀楽の転倒に耽る者どもを「狂生の者」と呼んで揶揄していた。
物事には悲しむべきところ、楽しむべきところが実際にある。
大まかな所では、天下国家の興亡や盛衰に自らの楽しみや悲しみを連動させることが、
人としてそうあるべき姿だといえる。国や天下が繁栄に与れていれば自分もそれと共に楽しみ、
困窮や諸国の衰亡が著しいようなら、それに伴って自分も悲しむべきである。
それが正順である一方で、天下国家の繁栄を妬んだり、衰亡を楽しんだりするのが
逆順であり、これこそは「狂生」の最たるものでもあるといえる。そう断じられるのは、
天下国家の興隆が引いては自らの福徳にも結びつく一方、その衰亡が自らへの災禍にも
結びつくことが絶対的だからで、いつまでも天下国家の興亡と自らの喜怒哀楽を
転倒させ続けていることのほうが絶対に不可能なことであるからに他ならない。
そして、天下国家の興亡と自らの非楽を正順に連動させた時にこそ、最大級の楽しみや悲しみにも与る。
それこそは、もう二度と非楽を転倒させることもできないほどにも完全な楽しみや悲しみであり、
概念夢想による感情の不埒な操作からも永久に卒業してしまうほどもの絶対的な楽しみや悲しみである。
実相と概念の内で、人間の苦楽を絶対的に決定づけるのは実相のほうであり、人間にとっての
最大級の実相の大局はあくまで天下国家だから、そこでこそ、最大級かつ絶対的な非楽にも与るのである。
あくまで、自分が民間人としての立場を貫いている人間などが、そのような最大級の非楽に
与るということは滅多にないことだが、全世界を支配下に置くほどもの強権を手に入れた政商あたりなら、
自らの悪逆非道に基づく逃れようのない天下国家レベルの敗亡によって、一切紛らわしようもない程の、
救いなき悲しみに見舞われることもあり得なくはない。秦帝国の宰相となった呂不韋などもそれに近い
立場にあったが、悲劇に見舞われた頃にはすでに公職にあったわけで、民間の政商などとしての立場を
保ったままに、天下国家の敗亡に連動する究極の悲しみを被った人間となれば、ついぞ見られない。
これから、そのような悲しみに見舞われる連中がいたとすれば、それこそ稀有なことだ。
稀有であり、未曾有だからこそ、その先にあるものをまだ侮っている所もあるだろうが、
実際にその悲しみがやって来るからには、帝国の責任者などとして亡国を体験させられる並みの悲しみに
見舞われることが間違いない。今までそのような運命に陥ることから逃れ続けてきた挙句に、絶体絶命の
運命と共に否応なくそのような悲しみに見舞われることが、それ以下で済むなんてことがあるはずもない。
そこには正式な為政者たらんとした者にはなかった惨めさまでもが付きまとうのだから、それ以上である可能性のほうが高い。
「予れ之れを懐いて悲しむ。万姓予れを仇とす、予れ将に疇れにか依らん。
郁陶乎たる予が心、顔厚にして忸怩たること有り。厥の徳を慎む弗く、悔ゆと雖も追う可けんや」
「私はひどく悲しんでいる。天下の万民が(暴政の主導者となってしまった)自分を仇敵とみなしている。
もはやどこにも頼るべき相手もいない。大いなる悲しみに打ちひしがれたこの心、恥辱のあまり少しも
晴れることもない。自らの行いを慎むことをも怠ってきたのだから、いくら悔いた所で取り返しも付かない。
(一切の救いのない自業自得による亡国の悲しみ。そこには一切幸せがるべき要素もない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・夏書・五子之歌より)
与るということは滅多にないことだが、全世界を支配下に置くほどもの強権を手に入れた政商あたりなら、
自らの悪逆非道に基づく逃れようのない天下国家レベルの敗亡によって、一切紛らわしようもない程の、
救いなき悲しみに見舞われることもあり得なくはない。秦帝国の宰相となった呂不韋などもそれに近い
立場にあったが、悲劇に見舞われた頃にはすでに公職にあったわけで、民間の政商などとしての立場を
保ったままに、天下国家の敗亡に連動する究極の悲しみを被った人間となれば、ついぞ見られない。
これから、そのような悲しみに見舞われる連中がいたとすれば、それこそ稀有なことだ。
稀有であり、未曾有だからこそ、その先にあるものをまだ侮っている所もあるだろうが、
実際にその悲しみがやって来るからには、帝国の責任者などとして亡国を体験させられる並みの悲しみに
見舞われることが間違いない。今までそのような運命に陥ることから逃れ続けてきた挙句に、絶体絶命の
運命と共に否応なくそのような悲しみに見舞われることが、それ以下で済むなんてことがあるはずもない。
そこには正式な為政者たらんとした者にはなかった惨めさまでもが付きまとうのだから、それ以上である可能性のほうが高い。
「予れ之れを懐いて悲しむ。万姓予れを仇とす、予れ将に疇れにか依らん。
郁陶乎たる予が心、顔厚にして忸怩たること有り。厥の徳を慎む弗く、悔ゆと雖も追う可けんや」
「私はひどく悲しんでいる。天下の万民が(暴政の主導者となってしまった)自分を仇敵とみなしている。
もはやどこにも頼るべき相手もいない。大いなる悲しみに打ちひしがれたこの心、恥辱のあまり少しも
晴れることもない。自らの行いを慎むことをも怠ってきたのだから、いくら悔いた所で取り返しも付かない。
(一切の救いのない自業自得による亡国の悲しみ。そこには一切幸せがるべき要素もない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・夏書・五子之歌より)
四書五経に明記されている倫理基準そのものは、決して体系的ではない。
孔子や孟子の提示する倫理判断も直観的で散逸的なものばかりで、
その一つ一つの言葉の絶対性に固執することが、儒学の粗雑な
宗教化(儒教化)を招く危険性をも孕んでいる。
一方で、四書五経を学ぶことで本人自身が体得する体系的な倫理基準というものは実在する。
特に、易詩書礼春秋の五経を的確に学ぶことで、自らに普遍的かつ体系的な倫理的判断力が
身に付くようになっていて、そこから派生する言行こそは確かに、孔孟のそれにも近似する。
特に基幹となるのは、易の陰陽法則を体得レベルで理解することで、それが経書の勉学の内
でも最難関となる一方、体得すらできたなら孔孟級の聖賢にすら決してなれなくはない。
四書五経を学ぶことによって体得する倫理体系そのものはあまりにも膨大すぎて、
完全に文面化しようとしても永遠にとりとめのないものとなってしまう。それは、
易の陰陽法則から有機的に派生する倫理体系が無尽蔵であると共に、それを勉学の対象
とした者自身が、全身全霊によって当該の無尽蔵な倫理体系を受け止めてもいるからだ。
脳の記憶容量は10テラバイト(5兆文字)以上といい、しかもその記憶構造が本人自身の人体構造や生活とも
密接に関係し合っている。易の陰陽法則もまた、そのような心身全体によって体得されるものであるため、
他人がちょっと聞きかじってみたりした所で、その全容は愚か、片鱗すら掴みようもない場合がほとんど。
しかし、それ程もの膨大さを湛えていればこそ、その倫理体系が実社会でも健全に機能できるのである。
孔子や孟子の提示する倫理判断も直観的で散逸的なものばかりで、
その一つ一つの言葉の絶対性に固執することが、儒学の粗雑な
宗教化(儒教化)を招く危険性をも孕んでいる。
一方で、四書五経を学ぶことで本人自身が体得する体系的な倫理基準というものは実在する。
特に、易詩書礼春秋の五経を的確に学ぶことで、自らに普遍的かつ体系的な倫理的判断力が
身に付くようになっていて、そこから派生する言行こそは確かに、孔孟のそれにも近似する。
特に基幹となるのは、易の陰陽法則を体得レベルで理解することで、それが経書の勉学の内
でも最難関となる一方、体得すらできたなら孔孟級の聖賢にすら決してなれなくはない。
四書五経を学ぶことによって体得する倫理体系そのものはあまりにも膨大すぎて、
完全に文面化しようとしても永遠にとりとめのないものとなってしまう。それは、
易の陰陽法則から有機的に派生する倫理体系が無尽蔵であると共に、それを勉学の対象
とした者自身が、全身全霊によって当該の無尽蔵な倫理体系を受け止めてもいるからだ。
脳の記憶容量は10テラバイト(5兆文字)以上といい、しかもその記憶構造が本人自身の人体構造や生活とも
密接に関係し合っている。易の陰陽法則もまた、そのような心身全体によって体得されるものであるため、
他人がちょっと聞きかじってみたりした所で、その全容は愚か、片鱗すら掴みようもない場合がほとんど。
しかし、それ程もの膨大さを湛えていればこそ、その倫理体系が実社会でも健全に機能できるのである。
四書五経よりもさらに些少な文面上に、「〜しろ」「〜してはならない」形式の実定法を多少
羅列しているだけの旧約の律法なぞが、実社会に適用することで問題を来さなくて済んだりする
わけがないのはもちろんのこと、日本国の中枢で日夜構築が続けられている六法等の現行法ですら、
実社会全体を司る倫理体系としては、あまりにも矮小かつ粗雑なもののままであり続けている。
ある一定の文章や教条などに、この世界を司らせて全く差し支えないなんてことがあるわけがない。
それは孔子や孟子の言葉といえども同じことで、ただ、その言葉が易の陰陽法則から派生している
ことを体得レベルで理解し、自らも同等の普遍法則に即した自主的な言行を心がけることによってのみ、
この世界を正規の為政者として司る君子たるに相応しい人間へと自分がなれるということがあるのみ。
だから、文面至上主義の対象として四書五経を扱うべきですらなく、特定の文面や教義に依存する
怠惰な姿勢を卒業していく取っ掛かりとしてこそ、四書五経を根幹とした為政が推奨できるのでもある。
この文面でも、あの教条でもうまくいかなかったから、今度は四書五経の文面に頼ろう、
そんなことばかりであっていいはずもないのである。
「其の笠伊れ糾きつけ、其の鎛と斯れ趙にて、以て荼蓼を薅う。
荼蓼は朽ちて止み、黍稷は茂りて止む。之れを穫りて桎桎、之れを積みて栗栗」
「菅笠を頭に巻きつけて、鋤鍬を手に田畑の夏草を切り払う。切り払った夏草が
朽ち果てた頃に、穀物もよく茂る。穀物もせっせと刈り取って、せっせと積み上げる。
(食えないものは切り払って朽ち果てさせ、食えるものも刈り取って食うというばかりのこと。
硬直的支配をありがたがっても、いつかは秦帝国のように崩壊して食い物になるばかりのこと)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・頌・周頌・閔予小子之什・良耜より)
羅列しているだけの旧約の律法なぞが、実社会に適用することで問題を来さなくて済んだりする
わけがないのはもちろんのこと、日本国の中枢で日夜構築が続けられている六法等の現行法ですら、
実社会全体を司る倫理体系としては、あまりにも矮小かつ粗雑なもののままであり続けている。
ある一定の文章や教条などに、この世界を司らせて全く差し支えないなんてことがあるわけがない。
それは孔子や孟子の言葉といえども同じことで、ただ、その言葉が易の陰陽法則から派生している
ことを体得レベルで理解し、自らも同等の普遍法則に即した自主的な言行を心がけることによってのみ、
この世界を正規の為政者として司る君子たるに相応しい人間へと自分がなれるということがあるのみ。
だから、文面至上主義の対象として四書五経を扱うべきですらなく、特定の文面や教義に依存する
怠惰な姿勢を卒業していく取っ掛かりとしてこそ、四書五経を根幹とした為政が推奨できるのでもある。
この文面でも、あの教条でもうまくいかなかったから、今度は四書五経の文面に頼ろう、
そんなことばかりであっていいはずもないのである。
「其の笠伊れ糾きつけ、其の鎛と斯れ趙にて、以て荼蓼を薅う。
荼蓼は朽ちて止み、黍稷は茂りて止む。之れを穫りて桎桎、之れを積みて栗栗」
「菅笠を頭に巻きつけて、鋤鍬を手に田畑の夏草を切り払う。切り払った夏草が
朽ち果てた頃に、穀物もよく茂る。穀物もせっせと刈り取って、せっせと積み上げる。
(食えないものは切り払って朽ち果てさせ、食えるものも刈り取って食うというばかりのこと。
硬直的支配をありがたがっても、いつかは秦帝国のように崩壊して食い物になるばかりのこと)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・頌・周頌・閔予小子之什・良耜より)
聖書信仰は、人の生死の惨めさを完全に開き直っている。
だからこそ、人が死への恐怖を緩和する手法としては最も稚拙な
「磔刑への恐怖に基づく思考停止。IQ40以下への知能停滞」
などという手法をも臆面もなく標榜している。
それによって実際に死への恐怖が緩和されるのであるにしても、
そんな手法によって恐怖を緩和するような人間たち自身が、あまりにも
小人然とし過ぎているために、その程度の品性の人間がこの世の中に増加
し過ぎたならば、世の中のほうが立ち行かなくなるのもまた、実際的なことだ。
だから、死への恐怖をもう少しマシな手段によって緩和する施策を講じていく必要が生じても来る。
仏門あたりにその手の手段は多数用意されているが、あえて一旦、仏門の話は捨て置くとする。
まだ仏教が存在しなかった頃、古代の中国などで慣習とされていた、親の死に際しての哭泣や断食、
三年に渡る服喪などもまた、遺族たち自身が死への恐怖を緩和する手段として確かに機能していた。
「永遠の命を手に入れる」という虚偽によって自己を慰める聖書信仰とも、虚空の徳によって死への
恐怖を技術的に捨て去る仏教とも違い、親族のような近親の人々の死への、心の底からの悲しみによって、
死への恐怖を捨て去るとも言わず、紛らわしていた。死への恐怖を乗り越える手段としては決して
便利なものではないし、見た目にも決して美しいものなどではない。しかし、それによって死への
恐怖を緩和できる人間ともなれば、確実に聖書信仰によって死への恐怖を和らげる人間などよりも、
マシな品性を持ち得ていた。マシな品性を持てていたから、そのような人間が世の中に多数
出回ったところで、聖書信者が溢れ返る場合のような世の中の破綻を招くこともない。
人はいつかは必ず死ぬ、常人であるからには死への恐怖も抱く、だから死への恐怖を緩和する。
そこまでは儒学も仏教も聖書信仰も何ら変わりはない。ただ、その手法の巧拙に差異があるために、
手堅い手法を擁する儒学や仏教に依れば、社会の破綻までは招かない一方で、稚拙な手法に
もっぱらである聖書信仰に依れば、世界中にヤク中患者が溢れ返る場合のようにして
世の中のほうが立ち行かなくなり、挙句には破滅を招くようなことにすらなる。
だからこそ、人が死への恐怖を緩和する手法としては最も稚拙な
「磔刑への恐怖に基づく思考停止。IQ40以下への知能停滞」
などという手法をも臆面もなく標榜している。
それによって実際に死への恐怖が緩和されるのであるにしても、
そんな手法によって恐怖を緩和するような人間たち自身が、あまりにも
小人然とし過ぎているために、その程度の品性の人間がこの世の中に増加
し過ぎたならば、世の中のほうが立ち行かなくなるのもまた、実際的なことだ。
だから、死への恐怖をもう少しマシな手段によって緩和する施策を講じていく必要が生じても来る。
仏門あたりにその手の手段は多数用意されているが、あえて一旦、仏門の話は捨て置くとする。
まだ仏教が存在しなかった頃、古代の中国などで慣習とされていた、親の死に際しての哭泣や断食、
三年に渡る服喪などもまた、遺族たち自身が死への恐怖を緩和する手段として確かに機能していた。
「永遠の命を手に入れる」という虚偽によって自己を慰める聖書信仰とも、虚空の徳によって死への
恐怖を技術的に捨て去る仏教とも違い、親族のような近親の人々の死への、心の底からの悲しみによって、
死への恐怖を捨て去るとも言わず、紛らわしていた。死への恐怖を乗り越える手段としては決して
便利なものではないし、見た目にも決して美しいものなどではない。しかし、それによって死への
恐怖を緩和できる人間ともなれば、確実に聖書信仰によって死への恐怖を和らげる人間などよりも、
マシな品性を持ち得ていた。マシな品性を持てていたから、そのような人間が世の中に多数
出回ったところで、聖書信者が溢れ返る場合のような世の中の破綻を招くこともない。
人はいつかは必ず死ぬ、常人であるからには死への恐怖も抱く、だから死への恐怖を緩和する。
そこまでは儒学も仏教も聖書信仰も何ら変わりはない。ただ、その手法の巧拙に差異があるために、
手堅い手法を擁する儒学や仏教に依れば、社会の破綻までは招かない一方で、稚拙な手法に
もっぱらである聖書信仰に依れば、世界中にヤク中患者が溢れ返る場合のようにして
世の中のほうが立ち行かなくなり、挙句には破滅を招くようなことにすらなる。
ヤク中患者ばかりが溢れ返っていたんじゃ世の中も立ち行かなくなるから、麻薬を規制するように、
聖書信仰も規制の対象となる、それは純粋な公益目的であり、私的な損益に立ち入ったことではない。
また、人々を生死の業の惨めさから救い出してやることを必ずしも保証してやる措置なわけでもない。
密教僧や禅僧のように、まるで旅行か何かに行くようにして、軽々と入定遷化することができるように
誰しもがなれることを、現時点で保証できるようなものではないし、場合によっては、古代の中国の
葬礼の慣習のように、聖書信仰よりも見た目には惨めにすら思えるような手段によって、死への恐怖を
緩和させていくようなことまでもがあり得る。純粋に世の中の破綻を免れるためであるからには、
それもまた一つの手段になり得るわけで、聖書信仰からの脱却=惨めさ全般からの脱却とも限らない。
人類社会の最終防衛戦の死守に、決して美しさばかりを期待していられるようなことはない。
むしろ、見てくれの美しさばかりを貪ってきた代償としての、惨めさ醜さを最大級に甘受して
いかなければならない時であり、それを諾える者こそは先頭に立つべき時でもある。
「隠れたるを求め怪しきを行うに、後世述ぶる有らん。吾れは之れを為さず」
「人の知らないようなことをあえて求めて、怪しげなことを企てたりするからこそ、
後に語り告げられたりすることもある。そういった功名の仕方を私(孔子)は目指さない。
(知識学問を閉鎖的な目的のために利用することもなければ、探求することもない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——中庸・一一より)
聖書信仰も規制の対象となる、それは純粋な公益目的であり、私的な損益に立ち入ったことではない。
また、人々を生死の業の惨めさから救い出してやることを必ずしも保証してやる措置なわけでもない。
密教僧や禅僧のように、まるで旅行か何かに行くようにして、軽々と入定遷化することができるように
誰しもがなれることを、現時点で保証できるようなものではないし、場合によっては、古代の中国の
葬礼の慣習のように、聖書信仰よりも見た目には惨めにすら思えるような手段によって、死への恐怖を
緩和させていくようなことまでもがあり得る。純粋に世の中の破綻を免れるためであるからには、
それもまた一つの手段になり得るわけで、聖書信仰からの脱却=惨めさ全般からの脱却とも限らない。
人類社会の最終防衛戦の死守に、決して美しさばかりを期待していられるようなことはない。
むしろ、見てくれの美しさばかりを貪ってきた代償としての、惨めさ醜さを最大級に甘受して
いかなければならない時であり、それを諾える者こそは先頭に立つべき時でもある。
「隠れたるを求め怪しきを行うに、後世述ぶる有らん。吾れは之れを為さず」
「人の知らないようなことをあえて求めて、怪しげなことを企てたりするからこそ、
後に語り告げられたりすることもある。そういった功名の仕方を私(孔子)は目指さない。
(知識学問を閉鎖的な目的のために利用することもなければ、探求することもない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——中庸・一一より)
「小人閑居して不善を為す。至らざる所なし」(大学)
「恒産無くして恒心あるは、ただ士のみ能く為す。
民の如きは、則ち恒産無ければ因って恒心無し。
苟くも恒心無ければ、放辟邪侈、為さざる無きのみ」(孟子)
匹夫小人の類いが多動を志して、何もかもをやってしまおうとするプロセスは
上記の既出の引用で完璧なまでに看破されている。民といえども、自らの生業に
専念して思う所がその位を出なければ、無闇な多動を志したりすることもないわけだが、
豪商や地主のドラ息子あたりの、富裕でいて有閑でもいるような類いの匹夫がこの条件に
必ずしも適う必要がないために、多動を志して為さざる所がなくなってしまう場合がある。
「君子は下流に居ることをにくむ(子張第十九・二〇)」という、いかにも差別主義めいた
言葉が真正福音書にあるけれども、この「下流」とは他でもない、殷の紂王のことを指している。
由緒正しき帝国の主君たる立場にありながら、盗賊や悪徳政商ともつるんでの放辟邪侈三昧に及んだ
その姿は、いくら君子階級の立場にあるといえども、閑居して不善を為して至らざる所のない小人のあり方
そのものだったから、「下流」の代名詞扱いをされるようにになったのも仕方のないことだというのである。
何も、不動の禅定ばかりを志さずとも、自らの身の程にも即した正行に専念するだけでも、
放辟邪侈を尽くして止まない下流に落ち込んだりはしなくて済むようにはなれるのである。
一心不乱な念仏行なども、自然とそれを達成させるものであるし、多少異端派の妄動などが目立つものの、
日蓮宗における題目なども、本来は一心不乱さによる恒心の養生を目指したもののはずだったのである。
「恒産無くして恒心あるは、ただ士のみ能く為す。
民の如きは、則ち恒産無ければ因って恒心無し。
苟くも恒心無ければ、放辟邪侈、為さざる無きのみ」(孟子)
匹夫小人の類いが多動を志して、何もかもをやってしまおうとするプロセスは
上記の既出の引用で完璧なまでに看破されている。民といえども、自らの生業に
専念して思う所がその位を出なければ、無闇な多動を志したりすることもないわけだが、
豪商や地主のドラ息子あたりの、富裕でいて有閑でもいるような類いの匹夫がこの条件に
必ずしも適う必要がないために、多動を志して為さざる所がなくなってしまう場合がある。
「君子は下流に居ることをにくむ(子張第十九・二〇)」という、いかにも差別主義めいた
言葉が真正福音書にあるけれども、この「下流」とは他でもない、殷の紂王のことを指している。
由緒正しき帝国の主君たる立場にありながら、盗賊や悪徳政商ともつるんでの放辟邪侈三昧に及んだ
その姿は、いくら君子階級の立場にあるといえども、閑居して不善を為して至らざる所のない小人のあり方
そのものだったから、「下流」の代名詞扱いをされるようにになったのも仕方のないことだというのである。
何も、不動の禅定ばかりを志さずとも、自らの身の程にも即した正行に専念するだけでも、
放辟邪侈を尽くして止まない下流に落ち込んだりはしなくて済むようにはなれるのである。
一心不乱な念仏行なども、自然とそれを達成させるものであるし、多少異端派の妄動などが目立つものの、
日蓮宗における題目なども、本来は一心不乱さによる恒心の養生を目指したもののはずだったのである。
何かにかけて一心不乱であることを、聖書圏の人間が「アスペルガー症候群」だの「モノマニア」だのと
いった言葉で病的に扱おうとすることがあるが、これもカルト洗脳の一環であると断ずるほかはない。
百姓も農作業に、工人も工作作業に一心不乱であってこそ自らの仕事を達成するのだから、何かにかけて
一心不乱であることこそは、人間にとっての欠くべからざる要素ですらあるといえる。にもかかわらず
その性向こそを病気扱いして、市場を傍観しての投機に走る悪徳商人あたりこそが必要とする能力でもある、
注意欠陥気味のなんでもし放題な心理こそを健康と見なしたりするのだから、これこそは完全なる顛倒だといえる。
百姓や工人が自らの正業に一心不乱であることによって仕事を成すのと同じように、士人もまた
模範的な者ほど仁徳に根ざした自らの仕事に専らであろうとする。「文明社会の原罪」たる商売を
専業とする者といえども、「売り手良し、買い手良し、世間良し」の三方よしを心がけるような
最低限の節度を保つのであれば、やはりそのために「ここまで」と押し止まる一線を持つはずなのである。
日本刀の刃ほどにも、鋭利かつ一直線なところに一筋であることこそは、人間にとっての実質的な「糧」となる。
そうであることによってこそ人は生きられる一方、そこから外れた所で人は無益な不善を為すしかなくなる。
然れば、何かに一心不乱である所にのみ正義もまたあるのだから、何もかもを為してしまおうとする不埒さを
非難することが許されようとも、正行に一心不乱であろうとする熱心さを非難していいなどということはない。
「仲尼は己甚だしきを為さざる者なり」
「孔先生は決して甚だしいことを企てたりはしない人だった。
(できるできない以前に、君子は甚だしいことなどやらないのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・離婁章句下・一〇より)
いった言葉で病的に扱おうとすることがあるが、これもカルト洗脳の一環であると断ずるほかはない。
百姓も農作業に、工人も工作作業に一心不乱であってこそ自らの仕事を達成するのだから、何かにかけて
一心不乱であることこそは、人間にとっての欠くべからざる要素ですらあるといえる。にもかかわらず
その性向こそを病気扱いして、市場を傍観しての投機に走る悪徳商人あたりこそが必要とする能力でもある、
注意欠陥気味のなんでもし放題な心理こそを健康と見なしたりするのだから、これこそは完全なる顛倒だといえる。
百姓や工人が自らの正業に一心不乱であることによって仕事を成すのと同じように、士人もまた
模範的な者ほど仁徳に根ざした自らの仕事に専らであろうとする。「文明社会の原罪」たる商売を
専業とする者といえども、「売り手良し、買い手良し、世間良し」の三方よしを心がけるような
最低限の節度を保つのであれば、やはりそのために「ここまで」と押し止まる一線を持つはずなのである。
日本刀の刃ほどにも、鋭利かつ一直線なところに一筋であることこそは、人間にとっての実質的な「糧」となる。
そうであることによってこそ人は生きられる一方、そこから外れた所で人は無益な不善を為すしかなくなる。
然れば、何かに一心不乱である所にのみ正義もまたあるのだから、何もかもを為してしまおうとする不埒さを
非難することが許されようとも、正行に一心不乱であろうとする熱心さを非難していいなどということはない。
「仲尼は己甚だしきを為さざる者なり」
「孔先生は決して甚だしいことを企てたりはしない人だった。
(できるできない以前に、君子は甚だしいことなどやらないのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・離婁章句下・一〇より)
「易経」繋辞上伝に、易学の効果的な利用方法としての「開物成務(物を開き務めを成す)」が提示されている。
易の法則に司られた自然現象自体は純粋に数理的なもので、そこに超越的な恣意などが介在する余地もないが、
たとえば、たびたび氾濫を起こす自然のままの河川の治水のために、底をさらったり分水路を切り開いたりする
といったような、天地万物の自然な化育に人が上手に介入していく活動というものがいくらでも想定できる。
そのような活動を実践していくことが開物成務となるわけで、決してそれが罰当たりになったりするわけでもない。
人間が企てる活動の内には、開物成務の条件を満たすものとそうでないものとの両方がある。開物成務の条件を
満たす活動とは、治水や灌漑やその恩恵に与っての農産などで、本当に世のため人のためになる公共事業は必ず
開物成務の条件を満たしている。一方、開成の条件を満たさない活動とは、世の中のためには特に害も益もない
活動や、世の中や自然に害ばかりをもたらす活動のことだといえる。他人が熱心な開成によって積み立てた公益を
私利私益のために不正に奪い取ったりとか、極度の自然破壊を伴う開発だとかは、開成の条件を満たしていない。
残念ながら、近現代の産業革命を発端とした世界発展は、開物成務の条件を満たせている頻度があまりにも低すぎる。
有益無害な構築活動よりも、有害無益な破壊活動のほうが常に優勢であり続けているから、全体としても有害無益で、
人類社会を繁栄以上の破滅に常に見舞わせ続け、挙句には滅亡の危機をも呼び込むこととなってしまったのである。
近現代の世界発展の主導者が聖書圏の人間ばかりであり続けて来たからこそ、開物成務が十分だった試しもない。
新旧約聖書で「絶対神」と寓意されている悪徳政商こそは、開成が絶対に不能な職分の最たるものであり、
そんなものが世界で絶対的な権限を握っているからには、総体としての開成が十分であることなどもあり得ないから。
政商行為を絶対的なものとして崇め立てる聖書圏の人間などが世界の支配者としてのさばっている以上は、
文明発展における開物成務の頻度が十分であるために世界が滅亡の危機から免れられるようなこともないのである。
易の法則に司られた自然現象自体は純粋に数理的なもので、そこに超越的な恣意などが介在する余地もないが、
たとえば、たびたび氾濫を起こす自然のままの河川の治水のために、底をさらったり分水路を切り開いたりする
といったような、天地万物の自然な化育に人が上手に介入していく活動というものがいくらでも想定できる。
そのような活動を実践していくことが開物成務となるわけで、決してそれが罰当たりになったりするわけでもない。
人間が企てる活動の内には、開物成務の条件を満たすものとそうでないものとの両方がある。開物成務の条件を
満たす活動とは、治水や灌漑やその恩恵に与っての農産などで、本当に世のため人のためになる公共事業は必ず
開物成務の条件を満たしている。一方、開成の条件を満たさない活動とは、世の中のためには特に害も益もない
活動や、世の中や自然に害ばかりをもたらす活動のことだといえる。他人が熱心な開成によって積み立てた公益を
私利私益のために不正に奪い取ったりとか、極度の自然破壊を伴う開発だとかは、開成の条件を満たしていない。
残念ながら、近現代の産業革命を発端とした世界発展は、開物成務の条件を満たせている頻度があまりにも低すぎる。
有益無害な構築活動よりも、有害無益な破壊活動のほうが常に優勢であり続けているから、全体としても有害無益で、
人類社会を繁栄以上の破滅に常に見舞わせ続け、挙句には滅亡の危機をも呼び込むこととなってしまったのである。
近現代の世界発展の主導者が聖書圏の人間ばかりであり続けて来たからこそ、開物成務が十分だった試しもない。
新旧約聖書で「絶対神」と寓意されている悪徳政商こそは、開成が絶対に不能な職分の最たるものであり、
そんなものが世界で絶対的な権限を握っているからには、総体としての開成が十分であることなどもあり得ないから。
政商行為を絶対的なものとして崇め立てる聖書圏の人間などが世界の支配者としてのさばっている以上は、
文明発展における開物成務の頻度が十分であるために世界が滅亡の危機から免れられるようなこともないのである。
商行為こそは、文明発展における原罪といえ、その活動のほとんどが開物成務の条件を満たさないにも関わらず、
カネやモノを右から左へと横流しするその行いによって、文明社会を雪だるま式に肥大化させる役割を担い得る。
そこには全く生産性が伴わない上に、政治権力との結託に及んでの政商ともなろうものなら、世の中にとっての
大害悪にすらなってしまいかねないわけだが、仮に「文明発展すなわち正義」だと考えるのなら、政商を含む
商行為にも全く存在意義がないわけではなく、「必要悪」程度の存在意義はあるということにすらなってしまう。
「文明発展すなわち正義」ではなく、「文明発展が人々の福徳に寄与する場合に限って正義」と捉えた場合にこそ、
政商や悪徳商売が必要悪ですらない不必要悪となり、三方よし(>>283参照)を常に心がける善賈の商売に限って、
必要悪程度の存在意義を獲得できるようになる。普遍的に見ても、そこにこそ正義の基準を定むべきだといえるし、
またこれからの時代においてはそう定めるのでなければ、もはや世の中もやって行けくなってしまうのである。
「唯だ天下の至誠、能く天下の大経を経綸し、天下の大本を立て、天地の化育を知ると為す。
(ここまで既出)夫れ焉んぞ倚る所有らん。肫肫たる其の仁、淵淵たる其の淵、浩浩たる其の天、
苟くも固に聡明聖知にして天徳に達する者ならずんば、其れ孰れか能く之れを知らん」
「ただ天下において至誠なる者だけが、天下の大筋を整え、天下を根本から正立せしめ、天地万物の化育に通達する。
そうでいられるとすれば、どうして偏頗でいたりすることがあろうか。(旧約の神のような偏頗はあり得ない)
ねんごろな仁徳と、深遠な厚徳と、広大な上天とを、聡明叡智にして天徳に達する者でなければどうして知り得ようか。」
(権力道徳聖書——通称四書五経——中庸・三二より)
カネやモノを右から左へと横流しするその行いによって、文明社会を雪だるま式に肥大化させる役割を担い得る。
そこには全く生産性が伴わない上に、政治権力との結託に及んでの政商ともなろうものなら、世の中にとっての
大害悪にすらなってしまいかねないわけだが、仮に「文明発展すなわち正義」だと考えるのなら、政商を含む
商行為にも全く存在意義がないわけではなく、「必要悪」程度の存在意義はあるということにすらなってしまう。
「文明発展すなわち正義」ではなく、「文明発展が人々の福徳に寄与する場合に限って正義」と捉えた場合にこそ、
政商や悪徳商売が必要悪ですらない不必要悪となり、三方よし(>>283参照)を常に心がける善賈の商売に限って、
必要悪程度の存在意義を獲得できるようになる。普遍的に見ても、そこにこそ正義の基準を定むべきだといえるし、
またこれからの時代においてはそう定めるのでなければ、もはや世の中もやって行けくなってしまうのである。
「唯だ天下の至誠、能く天下の大経を経綸し、天下の大本を立て、天地の化育を知ると為す。
(ここまで既出)夫れ焉んぞ倚る所有らん。肫肫たる其の仁、淵淵たる其の淵、浩浩たる其の天、
苟くも固に聡明聖知にして天徳に達する者ならずんば、其れ孰れか能く之れを知らん」
「ただ天下において至誠なる者だけが、天下の大筋を整え、天下を根本から正立せしめ、天地万物の化育に通達する。
そうでいられるとすれば、どうして偏頗でいたりすることがあろうか。(旧約の神のような偏頗はあり得ない)
ねんごろな仁徳と、深遠な厚徳と、広大な上天とを、聡明叡智にして天徳に達する者でなければどうして知り得ようか。」
(権力道徳聖書——通称四書五経——中庸・三二より)
人の命を重んずればこそ、死を不吉なものとして忌み避けることを慣習とするのもむべなることだといえる。
日本語で死(し)と読みが同じである数字の「四、4」を不用意に用いることが忌み嫌われたり、
六曜で不吉とされる日に「仏滅」という言葉が当てられたりするのも、迷信にしたって、罪の無い類いのもの。
特に、釈迦入滅を意味する「仏滅」が不吉な日に当てられている所など、東洋人の死生観の巧みさがよく現れている。
仏滅日が不吉であるのはやはり間違いないけれども、六曜の規則上は仏滅日もまた避けることはできない。
生きとし生けるものはみないつかは死に帰する、諸行無常の絶対真理を根本教義に掲げる仏教などに即して、
人の死を厳重に取り扱いはするが、ただやはり、その扱い方をどこまでも畏れ慎んでもいる。
「生は地獄、死こそはめでたい」なんていうような極論に走ることは、やっぱり避けるべきである。
というのも、それはそれで残念ながら実際にあることだから。さっさと死んでしまったほうがむしろ楽に
なれるほどにも地獄のような生を送ってしまうということも実際にあるわけで、それは、悪因苦果を
もたらす罪業まみれの生であるからこそ。そのような生き方になるべく陥らないようにすべきだから、
やはり生を吉、死を不吉なものとして扱う。「生きていることこそは死よりもめでたい」というほどにも、
よい生き方をしていくことを目指していくためにも、やはりを死こそを生よりも不吉なものとして扱うべきなのである。
不吉なものだから死を恐れるのと、命を失うから死を恐れるのとでは、似ているようで実は異なる。
35歳で悟りを拓いたとされる釈迦が、80歳の入滅時に抱いた「まだ死にたくない」という感興などは、
死が不吉なものであることへの恐れでこそあった一方、そんじょそこらの匹夫小人が死に対して抱く恐れなどは、
ただ命を失うことを恐れているばかりのことである。人間としての命を失うことへの恐れなどはとっくの昔に
乗り越えていながらも、善因楽果をもたらす生者としての功徳の積みようが死によってなくなってしまうから死を
恐れたのが釈迦であるのに対し、匹夫はただ自分の個我や肉体が消失することが嫌だから死を恐れているだけの存在である。
日本語で死(し)と読みが同じである数字の「四、4」を不用意に用いることが忌み嫌われたり、
六曜で不吉とされる日に「仏滅」という言葉が当てられたりするのも、迷信にしたって、罪の無い類いのもの。
特に、釈迦入滅を意味する「仏滅」が不吉な日に当てられている所など、東洋人の死生観の巧みさがよく現れている。
仏滅日が不吉であるのはやはり間違いないけれども、六曜の規則上は仏滅日もまた避けることはできない。
生きとし生けるものはみないつかは死に帰する、諸行無常の絶対真理を根本教義に掲げる仏教などに即して、
人の死を厳重に取り扱いはするが、ただやはり、その扱い方をどこまでも畏れ慎んでもいる。
「生は地獄、死こそはめでたい」なんていうような極論に走ることは、やっぱり避けるべきである。
というのも、それはそれで残念ながら実際にあることだから。さっさと死んでしまったほうがむしろ楽に
なれるほどにも地獄のような生を送ってしまうということも実際にあるわけで、それは、悪因苦果を
もたらす罪業まみれの生であるからこそ。そのような生き方になるべく陥らないようにすべきだから、
やはり生を吉、死を不吉なものとして扱う。「生きていることこそは死よりもめでたい」というほどにも、
よい生き方をしていくことを目指していくためにも、やはりを死こそを生よりも不吉なものとして扱うべきなのである。
不吉なものだから死を恐れるのと、命を失うから死を恐れるのとでは、似ているようで実は異なる。
35歳で悟りを拓いたとされる釈迦が、80歳の入滅時に抱いた「まだ死にたくない」という感興などは、
死が不吉なものであることへの恐れでこそあった一方、そんじょそこらの匹夫小人が死に対して抱く恐れなどは、
ただ命を失うことを恐れているばかりのことである。人間としての命を失うことへの恐れなどはとっくの昔に
乗り越えていながらも、善因楽果をもたらす生者としての功徳の積みようが死によってなくなってしまうから死を
恐れたのが釈迦であるのに対し、匹夫はただ自分の個我や肉体が消失することが嫌だから死を恐れているだけの存在である。
削除(by投稿者)
両者には似ているようで厳然たる違いがあり、前者の恐れは本人に妄念妄動をけしかけたりはしない一方で、
後者の恐れは、あまりにもの恐怖感からなる妄念妄動をけしかけるといった、効能面からの相違を伴っている。
恐怖のあまり妄念妄動にかられてしまうというのなら、みだりに死を思うのもむしろ避けるべきで、
実際に神道や儒学などは、下手に死を口にしたりすることからしてなるべく避けもする。貴人が死んだ場合にも
「お隠れになる」とか「お去りになる」とかいった言い方をあえてするわけで、別にそれが不誠実なわけでもない。
人の死と真っ向から向き合う教学として仏教に勝るものも他にないが、その仏教も出家第一の精進主義であり、
在俗の人間誰しもにまで死と向かい合い続けていることなどを要求するものではない。あまり人の死にばかり
囚われすぎてもうまくいかなくなるのが世の中というもので、なればこそ、儒学の礼法などにおいても、近親関係や
社会関係の如何によって、葬礼への携わり方に細密な差別を設けてもいる。まったく死から目を背けてのがむしゃら
ばかりでいるのも時に弊害をもたらしかねないが、常人なら、死との距離感を保つぐらいのことはあってしかるべきだといえる。
「葉公、子路に孔子を問う。子路対えず。子曰く、女じ奚ぞ曰わざる、其の人と為りや、
発奮して食を忘れ、楽しみて以て憂いを忘れ、老いの将に至らんとするを知らざるのみ、と」
「楚の県知事の葉公が子路に孔子の人となりを問うた。子路は答えられなかった。それを聞いて孔先生は言われた。
『どうしておまえ(子路)はこう答えなかったのだ。発奮しては食を忘れ、楽しみがあっては憂いを忘れ、
いつかは老いて死ぬことすら知らないでいるかのような人間だと』(この自己評価は若干謙遜じみているが、それ程
にも孔子が勉強熱心だったのも事実だろう。良からぬことにこれ程にも熱心であったりすればそれは考えものである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・述而第七・一八より)
後者の恐れは、あまりにもの恐怖感からなる妄念妄動をけしかけるといった、効能面からの相違を伴っている。
恐怖のあまり妄念妄動にかられてしまうというのなら、みだりに死を思うのもむしろ避けるべきで、
実際に神道や儒学などは、下手に死を口にしたりすることからしてなるべく避けもする。貴人が死んだ場合にも
「お隠れになる」とか「お去りになる」とかいった言い方をあえてするわけで、別にそれが不誠実なわけでもない。
人の死と真っ向から向き合う教学として仏教に勝るものも他にないが、その仏教も出家第一の精進主義であり、
在俗の人間誰しもにまで死と向かい合い続けていることなどを要求するものではない。あまり人の死にばかり
囚われすぎてもうまくいかなくなるのが世の中というもので、なればこそ、儒学の礼法などにおいても、近親関係や
社会関係の如何によって、葬礼への携わり方に細密な差別を設けてもいる。まったく死から目を背けてのがむしゃら
ばかりでいるのも時に弊害をもたらしかねないが、常人なら、死との距離感を保つぐらいのことはあってしかるべきだといえる。
「葉公、子路に孔子を問う。子路対えず。子曰く、女じ奚ぞ曰わざる、其の人と為りや、
発奮して食を忘れ、楽しみて以て憂いを忘れ、老いの将に至らんとするを知らざるのみ、と」
「楚の県知事の葉公が子路に孔子の人となりを問うた。子路は答えられなかった。それを聞いて孔先生は言われた。
『どうしておまえ(子路)はこう答えなかったのだ。発奮しては食を忘れ、楽しみがあっては憂いを忘れ、
いつかは老いて死ぬことすら知らないでいるかのような人間だと』(この自己評価は若干謙遜じみているが、それ程
にも孔子が勉強熱心だったのも事実だろう。良からぬことにこれ程にも熱心であったりすればそれは考えものである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・述而第七・一八より)
たとえば、我が子への健全な教育を志す家庭において、
今の俗悪な民法のテレビ放送を見せないようにするなどの措置を講じたとする。
仏教で言うところの「顕教」に相当するような教育を志しているのなら、それも結構なことで、
特に皇族のような尊貴な立場にある人々が、安全面にかけても万全を期した教育を
心がける場合などには、「密教」に相当するような教育までは省くのも賢明なことだといえる。
そうでなくたって、ある程度以上に我が子への自愛の豊かな親であるのなら、我が子に
危険要素を含む教育や鍛錬を受けさせることに躊躇を抱いたとしても、当然のことである。
「獅子は我が子を千尋の谷に突き落として、這い上がって来られた者だけを育てる」などという
ような発想も、過ぎたるはなお及ばざるが如しで、仮に我が子に厳しい教育などを施すにしても、
万全の信頼の置ける教師などを付けて、失敗や粗相のないようにさせるぐらいであるべきだといえる。
高貴な身分の家庭における教育はもちろんのこと、親が我が子に押し付ける教育全般のうちに、清濁併せ
呑ませてそれを乗り越えさせるような、「密教」的な教育までをもを組み込むようなことは奨励すべきでない。
弘法大師も、親の反対をも押し切っての、自らの意志によって出家し、真言密教の開祖ともなったように、
大きな危険すら伴うような荒行への従事は、あくまで本人自身の意志によって選択させるのが基本である。
これから全国的・世界的な教育改革が実施されるとして、親が我が子に惜しみなくその教育を
勧められる範囲の、顕教レベルの教育材料に指定されるうちでも、最も模範的なのが儒学教育である。
儒学のうちには本来、「爾雅」にあるようような言語教育も含まれるので、国語教育の一部はそのまま
儒学の範疇ともなる。史学や社会学なども本来は儒学の十八番であるし、算術や自然学なども本来、
多少は儒学の領分だったわけで、儒学道徳に即して無害と見なされた近現代の数学的、
科学的知識などが、多少は顕教教育のうちにも組み込まれることになるだろう。
他には、顕教である仏教教義の初歩、道家や兵家のようなためになる要素のある東洋学の知識も、
あまり込み入って立ち入らない範囲での教育が、顕教レベルの教育のうちに含まれ得る。
今の俗悪な民法のテレビ放送を見せないようにするなどの措置を講じたとする。
仏教で言うところの「顕教」に相当するような教育を志しているのなら、それも結構なことで、
特に皇族のような尊貴な立場にある人々が、安全面にかけても万全を期した教育を
心がける場合などには、「密教」に相当するような教育までは省くのも賢明なことだといえる。
そうでなくたって、ある程度以上に我が子への自愛の豊かな親であるのなら、我が子に
危険要素を含む教育や鍛錬を受けさせることに躊躇を抱いたとしても、当然のことである。
「獅子は我が子を千尋の谷に突き落として、這い上がって来られた者だけを育てる」などという
ような発想も、過ぎたるはなお及ばざるが如しで、仮に我が子に厳しい教育などを施すにしても、
万全の信頼の置ける教師などを付けて、失敗や粗相のないようにさせるぐらいであるべきだといえる。
高貴な身分の家庭における教育はもちろんのこと、親が我が子に押し付ける教育全般のうちに、清濁併せ
呑ませてそれを乗り越えさせるような、「密教」的な教育までをもを組み込むようなことは奨励すべきでない。
弘法大師も、親の反対をも押し切っての、自らの意志によって出家し、真言密教の開祖ともなったように、
大きな危険すら伴うような荒行への従事は、あくまで本人自身の意志によって選択させるのが基本である。
これから全国的・世界的な教育改革が実施されるとして、親が我が子に惜しみなくその教育を
勧められる範囲の、顕教レベルの教育材料に指定されるうちでも、最も模範的なのが儒学教育である。
儒学のうちには本来、「爾雅」にあるようような言語教育も含まれるので、国語教育の一部はそのまま
儒学の範疇ともなる。史学や社会学なども本来は儒学の十八番であるし、算術や自然学なども本来、
多少は儒学の領分だったわけで、儒学道徳に即して無害と見なされた近現代の数学的、
科学的知識などが、多少は顕教教育のうちにも組み込まれることになるだろう。
他には、顕教である仏教教義の初歩、道家や兵家のようなためになる要素のある東洋学の知識も、
あまり込み入って立ち入らない範囲での教育が、顕教レベルの教育のうちに含まれ得る。
顕教教育からは確実に排除されるべきであるのが、有害無益であることが明らかな洋学知識や異学異見、
そしてカルト宗教などの知識で、これはもう、親が子供に学習を奨められるような扱いは二度と受けなくなる。
ただ、だからといってこの世から完全に根絶されるのではなく、密教の修得を自分で選択した有志が、
その俗悪さを乗り越えるための材料として勉学することに限って、これからも許されることになる。
教育制度を顕教レベルと密教レベルに段階分けすべきだということは、これまでにも何度か提唱してきた。
その区分基準は、「まともな親が我が子に無条件にその学習を奨められるか否か」というのが相応しく、
国が義務教育に定める教育材料も、この条件を満たすものに絞るべきである一方、私塾や密教寺などでの
非正規の教育に止めるべきなのが、この条件を満たさない教育材料だといえる。非正規といえども、
そこに寺社奉行の如き公的な監査は入れるべきで、密教の体裁を借りながら、邪教邪学の悪用目的での
修得を企てていたような場合には最悪、取り潰し級の制裁措置をも科すようにしていくのである。
この世には実際、よっぽどの覚悟でもない限りは知らないでいたほうがいいような情報知識がいくらでもある。
それを何もかも知らせつくすというのは、親子の家族関係の睦まじさもあってこそであるこの世の中において、
決して通用することではないから、そのような知識に対する然るべき隔離措置を執ることもあるべきなのである。
そしてカルト宗教などの知識で、これはもう、親が子供に学習を奨められるような扱いは二度と受けなくなる。
ただ、だからといってこの世から完全に根絶されるのではなく、密教の修得を自分で選択した有志が、
その俗悪さを乗り越えるための材料として勉学することに限って、これからも許されることになる。
教育制度を顕教レベルと密教レベルに段階分けすべきだということは、これまでにも何度か提唱してきた。
その区分基準は、「まともな親が我が子に無条件にその学習を奨められるか否か」というのが相応しく、
国が義務教育に定める教育材料も、この条件を満たすものに絞るべきである一方、私塾や密教寺などでの
非正規の教育に止めるべきなのが、この条件を満たさない教育材料だといえる。非正規といえども、
そこに寺社奉行の如き公的な監査は入れるべきで、密教の体裁を借りながら、邪教邪学の悪用目的での
修得を企てていたような場合には最悪、取り潰し級の制裁措置をも科すようにしていくのである。
この世には実際、よっぽどの覚悟でもない限りは知らないでいたほうがいいような情報知識がいくらでもある。
それを何もかも知らせつくすというのは、親子の家族関係の睦まじさもあってこそであるこの世の中において、
決して通用することではないから、そのような知識に対する然るべき隔離措置を執ることもあるべきなのである。
「何をか言を知ると謂う。曰く、詖辞は其の蔽わるる所を知り、
淫辞は其の陥る所を知り、邪辞は其の離るる所を知り、遁辞は其の窮する所を知る」
「公孫丑『人の言葉を知るということは、たとえばどういったことでしょうか』
孟子『極端に偏った言葉からは、その人の心が濁念に覆われていることが知れるし、
ふしだらな言葉からは、その人の心が劣情に陥っていることが知れるし、
邪まな言葉からは、その人の心が道理からかけ離れてしまっていることが知れるし、
言い逃れの言葉からは、その人が心理的に窮してしまっていることが知れる』
(イエスを含む犯罪聖書の登場人物の言葉も、このような反面教師的な知識の
汲み取り対象としては扱えるが、やはり顕教レベルで奨められるものではない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・公孫丑章句上・二より)
淫辞は其の陥る所を知り、邪辞は其の離るる所を知り、遁辞は其の窮する所を知る」
「公孫丑『人の言葉を知るということは、たとえばどういったことでしょうか』
孟子『極端に偏った言葉からは、その人の心が濁念に覆われていることが知れるし、
ふしだらな言葉からは、その人の心が劣情に陥っていることが知れるし、
邪まな言葉からは、その人の心が道理からかけ離れてしまっていることが知れるし、
言い逃れの言葉からは、その人が心理的に窮してしまっていることが知れる』
(イエスを含む犯罪聖書の登場人物の言葉も、このような反面教師的な知識の
汲み取り対象としては扱えるが、やはり顕教レベルで奨められるものではない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・公孫丑章句上・二より)
 女子供はともかく、大人の男にとってまで「常日ごろから絶対的な拠り所とすべきもの」などは何もない。
女子供はともかく、大人の男にとってまで「常日ごろから絶対的な拠り所とすべきもの」などは何もない。 実際問題、主君や親のような拠り所とすべき対象もあるし、困った時の神頼み仏頼みということもある。しかし、
一人前の成人男性ともなれば、自主的な精進作善こそを第一として、その成果を人間関係に回向するためにこそ、
君臣父子夫婦その他の上下関係や、確かな根拠に根ざした神仏への崇敬などをも副次的に嗜むべきなのである。
武士が自家や君主の家紋を掲げて役儀をこなしたり、軍人や役人が自国の旗を掲げて任務に就いたりするのも、
あくまで見る者に自らの身分を示すためであるのが基本であって、自分自身が依存心を高めるのが本義ではない。
昔の家紋はともかく、国旗については、自分たち自身の国家主義を扇情するために掲げたりする場合も非常に多く、
中には「国旗侮辱罪」なんていう罪を法定している馬鹿な国までもがあるが、身分の識別という本来の用途を
重視すれば、国旗によって誇りを育てる、国旗への侮辱によって誇りを傷つけられるなんてこと自体が本末転倒の
事態であることが分かる。どちらかといえば、国旗を侮辱されたりすることよりも、身分証明以外の目的で妄りに
濫用されたりすることのほうを取り締まるべきなのに、よりにもよって、国旗侮辱罪などを制定しているような
国こそは、自国の国旗が好き勝手に利用されることを奨励していたりもするのだから、おかしなものだといえる。
戦前の日本の下級兵などが、「天皇陛下万歳」などと叫びながら玉砕していったのも、キリスト信仰並みに依存心
を高める国家神道に服していたからで、これも哀れみの対象にこそすれど、称賛の対象とまですべきものではない。
「皇帝陛下万歳」は本来「無門関」の表文などにもある禅語であり、自主性を重んずる日本人にも多少は馴染みのある
言葉なのだが、戦前の軍部がそんな意味で「天皇陛下万歳」を用いていたわけでもなく、ただ下級兵たちに自分たちの
激情を煽る言葉として用いさせていたまでで、その点「アーメン」や「アラーアクバル」とも何ら相違はなかったのである。
(だからこそ、臨済宗妙心寺派管長の山本玄峰老師も、太平洋戦争の早期終結を天皇陛下に進言したのだった)
念仏などは、他力本願の体裁を取りながらも、信者の不健全な依存心を立ち消えにさせる効能を伴っている。
現世で悪因苦果に苛まれた劣解の凡夫こそは、特筆して弥陀の計らいによる往生にも与れるという、
人間心理の深層にまで深く食い入った信教構造によって、自然と信者に現世からの自主的な断悪修善をも促してしまう。
そういった、依存心を逆手に取ることで自主性を育む離れ業的な他力信仰も一応はあるわけだけれども、
結局は自主的な精進こそが善因楽果を結実させるという法則の域内には完全に止まっているわけで、
決して「依存心を持って何かをする」ということが善因楽果に結び付く証拠になったりしているわけではない。
ただ、逆に独立意識にばかり専らでい過ぎたなら、今度は「独立」という概念への依存心を募らせることにもなる。
同様に、「自由」や「民主」などといった概念への依存心を強める場合もあり、まるで独立的であるかのような
理念によって、かえって依存心を募らせてしまうような落とし穴もあるわけだから、これまた警戒が必要である。
してみれば、「依存でもなければ独立でもない、理念でもなければ理念でないものでもない」といったような、
般若思想的な中観の確立によってのみ、人は不健全な依存心を脱した心持ちを保ち続けていられることが分かる。
このようなことは、大乗仏教以前の思想家である孟子によっても多少は提唱されていて、仏教か儒学か、
インドか中国か、西か東か今か昔かなどに依らない普遍性を具えていることまでもが知れるのである。
儒学の教条といえども、絶対的な理念などに掲げたりはせずに、自らの自主的な積功累徳のための参考にこそ
すべきであるとは>>278-279に書いた通りである。もちろん自分がここに書いている文章なども、利用するにしたって
そのような利用目的に止められるべきで、決して狂信の対象にすべき代物などではない。概念依存や実物依存、
そして文章依存の深刻化を防ぐためにも、こうして読みやすくもない、粗雑な文筆に止め置いてもいるのだから。
現世で悪因苦果に苛まれた劣解の凡夫こそは、特筆して弥陀の計らいによる往生にも与れるという、
人間心理の深層にまで深く食い入った信教構造によって、自然と信者に現世からの自主的な断悪修善をも促してしまう。
そういった、依存心を逆手に取ることで自主性を育む離れ業的な他力信仰も一応はあるわけだけれども、
結局は自主的な精進こそが善因楽果を結実させるという法則の域内には完全に止まっているわけで、
決して「依存心を持って何かをする」ということが善因楽果に結び付く証拠になったりしているわけではない。
ただ、逆に独立意識にばかり専らでい過ぎたなら、今度は「独立」という概念への依存心を募らせることにもなる。
同様に、「自由」や「民主」などといった概念への依存心を強める場合もあり、まるで独立的であるかのような
理念によって、かえって依存心を募らせてしまうような落とし穴もあるわけだから、これまた警戒が必要である。
してみれば、「依存でもなければ独立でもない、理念でもなければ理念でないものでもない」といったような、
般若思想的な中観の確立によってのみ、人は不健全な依存心を脱した心持ちを保ち続けていられることが分かる。
このようなことは、大乗仏教以前の思想家である孟子によっても多少は提唱されていて、仏教か儒学か、
インドか中国か、西か東か今か昔かなどに依らない普遍性を具えていることまでもが知れるのである。
儒学の教条といえども、絶対的な理念などに掲げたりはせずに、自らの自主的な積功累徳のための参考にこそ
すべきであるとは>>278-279に書いた通りである。もちろん自分がここに書いている文章なども、利用するにしたって
そのような利用目的に止められるべきで、決して狂信の対象にすべき代物などではない。概念依存や実物依存、
そして文章依存の深刻化を防ぐためにも、こうして読みやすくもない、粗雑な文筆に止め置いてもいるのだから。
「君子は貞にして諒ならず」
「立派な人間は(人の言うことをよく聞くような)貞順さは保つけれども、
何かを専らに信じ込んでそれに依存しきったりすることはない。(他力本願も貞順でいられる
範囲なら健全でもいられるが、専らであり過ぎて聞く耳も持たなくなるようなら不健全の極みとなる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・衛霊公第十五・三七より)
「立派な人間は(人の言うことをよく聞くような)貞順さは保つけれども、
何かを専らに信じ込んでそれに依存しきったりすることはない。(他力本願も貞順でいられる
範囲なら健全でもいられるが、専らであり過ぎて聞く耳も持たなくなるようなら不健全の極みとなる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・衛霊公第十五・三七より)
「性、相い近し。習えば、相い遠し」
「人の性分というのは、本来は似通っているものだが、
色々な学習によって成長していくに連れて、お互いの性分が遠ざかるようになる」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・陽貨第十七・二より)
人の本性には善も悪もない、成長によって後々に善悪の開きが出てくるというのが、
あまり形而上的な性情論を語りたがらなかった孔子の言い分である。その上で、成長過程における
学習の如何によって「上知と下愚は移らず(陽貨第十七・三)」という程もの格差が生じるとも言っている。
ここに、多少の形而上学的な解釈を加えたのが、孟子の性善説や朱子の性即理説であり、
これらも結局は、孔子の性情論を掘り下げた結果としてこのような結論に至ったものだといえる。
だからこそ、人間の本性が善であり理に適っているとしながらも、後天的な濁念からの侵害によって
人が悪や不条理に染まることがあることをも諾っているのである。ただ、極端に穿った見方をするなら、
孟子や朱子の直観的な論説を踏まえてもなお、「性には善も悪もない」という断定までに止めたほうが
普遍的があるかのように考えられなくもない。それでも、性善説や性即理説にもそれなりの存在価値があると
やはり考えられるのは、「性善」とか「性即理」とかいった主張を試みること自体が、人々の善性や理性への
引き止めに寄与する方便的な効果を伴い得るからで、孔子と比べれば二番煎じ三番煎じ的な立場に甘んじる儒者で
ある孟子や朱子が、自分たちの立場の低さを埋め合わせる目的で、あえてこのような主張を行ったのだとも考えられる。
荀子の性悪説などは、この逆の効果を持ち合わせてしまうわけだから、性善説や性即理説と比べれば
推奨の対象とはしにくい。性善説など全く通用しない春秋戦国時代末期に、学生たちの活躍を促す
目的でも荀子はこのような言説に及んでいたに違いなく、実際に荀子の門下からは韓非のような
大学者や、李斯のような秦帝国の重臣が輩出されもしたわけだが、いずれも非業の運命を辿っており、
性悪説に準じようとしたが故の悪因苦果に見舞われたのだとも考えざるを得ない所があるのである。
「人の性分というのは、本来は似通っているものだが、
色々な学習によって成長していくに連れて、お互いの性分が遠ざかるようになる」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・陽貨第十七・二より)
人の本性には善も悪もない、成長によって後々に善悪の開きが出てくるというのが、
あまり形而上的な性情論を語りたがらなかった孔子の言い分である。その上で、成長過程における
学習の如何によって「上知と下愚は移らず(陽貨第十七・三)」という程もの格差が生じるとも言っている。
ここに、多少の形而上学的な解釈を加えたのが、孟子の性善説や朱子の性即理説であり、
これらも結局は、孔子の性情論を掘り下げた結果としてこのような結論に至ったものだといえる。
だからこそ、人間の本性が善であり理に適っているとしながらも、後天的な濁念からの侵害によって
人が悪や不条理に染まることがあることをも諾っているのである。ただ、極端に穿った見方をするなら、
孟子や朱子の直観的な論説を踏まえてもなお、「性には善も悪もない」という断定までに止めたほうが
普遍的があるかのように考えられなくもない。それでも、性善説や性即理説にもそれなりの存在価値があると
やはり考えられるのは、「性善」とか「性即理」とかいった主張を試みること自体が、人々の善性や理性への
引き止めに寄与する方便的な効果を伴い得るからで、孔子と比べれば二番煎じ三番煎じ的な立場に甘んじる儒者で
ある孟子や朱子が、自分たちの立場の低さを埋め合わせる目的で、あえてこのような主張を行ったのだとも考えられる。
荀子の性悪説などは、この逆の効果を持ち合わせてしまうわけだから、性善説や性即理説と比べれば
推奨の対象とはしにくい。性善説など全く通用しない春秋戦国時代末期に、学生たちの活躍を促す
目的でも荀子はこのような言説に及んでいたに違いなく、実際に荀子の門下からは韓非のような
大学者や、李斯のような秦帝国の重臣が輩出されもしたわけだが、いずれも非業の運命を辿っており、
性悪説に準じようとしたが故の悪因苦果に見舞われたのだとも考えざるを得ない所があるのである。
孟子や朱子だけでなく、荀子もまた孔門の徒であり、「人の本性は似通っている」という孔子の言説を基本と
していたことには変わりない。拝火教やアブラハム教のように、「人の本性自体が始めから決定的に断絶している」
などという二元論的な発想は元から排しているわけで、そこは「純人道」たる儒道ならではの特殊要素だといえる。
儒学の性情論は一元論的二言論であり、本性の部分がみな同一であるとする点、道家の万物斉同論にも近似している。
一方で、儒家でも道家でも「男女の別」が先天的後天的に普遍視されているわけで、人類の半々である男と女が
決定的に別物であるというのに、男同士までもが善人や悪人に分裂してしまうような事態を根本的に忌んでいる。
だから儒家は勧善懲悪の一方的な推進を志す一方、道家は善悪の分裂や対立全般を不毛なものとして諦めている。
善悪二元の分裂の存在を認めながらも、決してそれを良しとしない大前提が儒家や道家にはあるわけで、
だからこそ儒学や玄学(道家の学)があまり宗教としては発展しなかった一方、結局はそれでよかったことが
今になってこそ判明してもいる。人の先天的な本性からの分裂を論拠とした恒久的な争いを促したことが、
狂信型の宗教の発端でもあったのだから、宗教という文化形態全般への反省と共に、二元的対立全般を
下賤なものとしてしか扱わない、シラフ文化の存在価値を見直していくことが勧められるべきだといえる。
「慎みて乃の僚を簡び、巧言令色、便辟側媚を以ってする無かれ、其れ吉士を惟れとせよ」
「よく慎んで汝の部下を選び、上辺の言葉や見てくれだけで飾ったり、媚び諂って機嫌を
取ろうとしたりする者を決して取り立てぬように。よくできた人間だけを取り上げるように。
(『巧言令色』は虞書・皋陶謨に初出。4000年前から口先だけを磨こうとする愚人はいた)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・冏命より)
していたことには変わりない。拝火教やアブラハム教のように、「人の本性自体が始めから決定的に断絶している」
などという二元論的な発想は元から排しているわけで、そこは「純人道」たる儒道ならではの特殊要素だといえる。
儒学の性情論は一元論的二言論であり、本性の部分がみな同一であるとする点、道家の万物斉同論にも近似している。
一方で、儒家でも道家でも「男女の別」が先天的後天的に普遍視されているわけで、人類の半々である男と女が
決定的に別物であるというのに、男同士までもが善人や悪人に分裂してしまうような事態を根本的に忌んでいる。
だから儒家は勧善懲悪の一方的な推進を志す一方、道家は善悪の分裂や対立全般を不毛なものとして諦めている。
善悪二元の分裂の存在を認めながらも、決してそれを良しとしない大前提が儒家や道家にはあるわけで、
だからこそ儒学や玄学(道家の学)があまり宗教としては発展しなかった一方、結局はそれでよかったことが
今になってこそ判明してもいる。人の先天的な本性からの分裂を論拠とした恒久的な争いを促したことが、
狂信型の宗教の発端でもあったのだから、宗教という文化形態全般への反省と共に、二元的対立全般を
下賤なものとしてしか扱わない、シラフ文化の存在価値を見直していくことが勧められるべきだといえる。
「慎みて乃の僚を簡び、巧言令色、便辟側媚を以ってする無かれ、其れ吉士を惟れとせよ」
「よく慎んで汝の部下を選び、上辺の言葉や見てくれだけで飾ったり、媚び諂って機嫌を
取ろうとしたりする者を決して取り立てぬように。よくできた人間だけを取り上げるように。
(『巧言令色』は虞書・皋陶謨に初出。4000年前から口先だけを磨こうとする愚人はいた)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・冏命より)
性別上の女はみんな「今が全て」だし、匹夫小人の男も大概は「今が全て」である。
過去に対する十分な反省も、未来に向けての十分な計画も疎かなままに、ただ今を生きる。
それだけで済むならそれに越したことはないが、残念ながら、そればかりでは済まない。
誰も彼もが「今が全て」の刹那主義に走った挙句に、船頭多くして船山に登る要領で
世の中全体が経済破綻などの破滅に陥ってしまう。だから去来今を等分に俯瞰できる
聖人君子の教導による救いが必要となってしまうわけだけども、民主主義の悪影響よろしく、
今のことしか頭にない自分たち一般人こそは偉いみたいな思い込みを持ち越したままでいたなら、
決してうまく救えることもない。今のことしか念頭に置けないような自分たちのあり方が、
甚だしい愚か者のそれでしかないことを十分に思い知って、自分自身が聖賢になれなくとも、
聖賢に素直に随順していくぐらいの心持ちは得るのでなければ、決してどうにもなりはしない。
当然、「今が全て」の心境を信者に強制的に植え付ける宗教や、そのような人間こそは貴いみたいな
思い込みを人々に植え付ける教義論説などにも、決して権威を与えてやったりしてはならない。
実際、民間人こそは、今のことしか頭に置けないような生活習慣を強いられることが多く、
それが重労働のせいであったりする場合もあることから、「今が全て」という感覚を美化
することもそう難しいことではないわけだが、その「今が全て」の過剰な蔓延によってこそ
世界が破滅に陥りすらしかねないのも上に書いた通りだし、そもそも民間人だからといって今を
追われるような重労働ばかりに従事させられていることからして為政者の不手際でしかないのである。
だからこそ、「今が全て」という感覚をどんな形で称賛していていいようなこともないのである。
過去に対する十分な反省も、未来に向けての十分な計画も疎かなままに、ただ今を生きる。
それだけで済むならそれに越したことはないが、残念ながら、そればかりでは済まない。
誰も彼もが「今が全て」の刹那主義に走った挙句に、船頭多くして船山に登る要領で
世の中全体が経済破綻などの破滅に陥ってしまう。だから去来今を等分に俯瞰できる
聖人君子の教導による救いが必要となってしまうわけだけども、民主主義の悪影響よろしく、
今のことしか頭にない自分たち一般人こそは偉いみたいな思い込みを持ち越したままでいたなら、
決してうまく救えることもない。今のことしか念頭に置けないような自分たちのあり方が、
甚だしい愚か者のそれでしかないことを十分に思い知って、自分自身が聖賢になれなくとも、
聖賢に素直に随順していくぐらいの心持ちは得るのでなければ、決してどうにもなりはしない。
当然、「今が全て」の心境を信者に強制的に植え付ける宗教や、そのような人間こそは貴いみたいな
思い込みを人々に植え付ける教義論説などにも、決して権威を与えてやったりしてはならない。
実際、民間人こそは、今のことしか頭に置けないような生活習慣を強いられることが多く、
それが重労働のせいであったりする場合もあることから、「今が全て」という感覚を美化
することもそう難しいことではないわけだが、その「今が全て」の過剰な蔓延によってこそ
世界が破滅に陥りすらしかねないのも上に書いた通りだし、そもそも民間人だからといって今を
追われるような重労働ばかりに従事させられていることからして為政者の不手際でしかないのである。
だからこそ、「今が全て」という感覚をどんな形で称賛していていいようなこともないのである。
際限のない快楽を貪り続けることに専らであるような人間の心境も、まさに「今が全て」だといえる。
これはもう、今さら新たに咎めるまでもなく、麻薬取締りや風俗規制などの実力行使によっても
すでに制限がかけられているものである。ただ、欧米産の俗悪文化の中には、快楽への惑溺こそを
高度に美化しようとするようなものが多く含まれているため、その手の文化に対する警戒も必要である。
とはいえ、快楽文化を完全に否定したりするのも世の中にとって現実的なことではないので、
極度の美化が伴わない範囲での快楽文化を容認したりするのが、江戸時代の日本人の知恵でもあった。
井原西鶴の好色もの小説なども、快楽の貪りが甚だしいにも程があるが、決してそこに美化などは
伴っていないから、単なる笑い者扱いとして好色を諦観できて、「今が全て」のような感覚を
戒める一方、去来今をよく俯瞰する気の長さを貴ぶことを侵害までするようなことは決してなかった。
去来今を諦観することにかけて白眉であるのも、やはり仏教だが、儒学もまた、古えの
聖賢の言葉や聖王賢臣の事績を参考に今後の世の中を切り開いていく、温故知新を勉学上の
最重要理念に掲げている。旧来の学説など淘汰してナンボであると考えられている洋学の感覚
などからすれば、儒者のあり方が古臭くて依存的に過ぎるように思われたりもするわけだけども、
儒学が勃興した春秋戦国時代にも、新規奇抜な学説で人々の奇を衒おうとしていたような学者は
名家などに多数いたわけで、儒学もそんな連中を横目にして構築されていったものでこそある。
そして名家の言説が世のため人のために寄与したような事実はほとんどない一方で、儒学が
東洋史上において与えてきた好影響は枚挙に暇がない。結局は去来今の三世をよく俯瞰できる
者こそが善美でいられるのが、この世界の実相法則でもあるのだから、温故知新を旨とする
儒者のあり方などを、洋学者風情があざ笑っていたりしていいようなはずもないのである。
これはもう、今さら新たに咎めるまでもなく、麻薬取締りや風俗規制などの実力行使によっても
すでに制限がかけられているものである。ただ、欧米産の俗悪文化の中には、快楽への惑溺こそを
高度に美化しようとするようなものが多く含まれているため、その手の文化に対する警戒も必要である。
とはいえ、快楽文化を完全に否定したりするのも世の中にとって現実的なことではないので、
極度の美化が伴わない範囲での快楽文化を容認したりするのが、江戸時代の日本人の知恵でもあった。
井原西鶴の好色もの小説なども、快楽の貪りが甚だしいにも程があるが、決してそこに美化などは
伴っていないから、単なる笑い者扱いとして好色を諦観できて、「今が全て」のような感覚を
戒める一方、去来今をよく俯瞰する気の長さを貴ぶことを侵害までするようなことは決してなかった。
去来今を諦観することにかけて白眉であるのも、やはり仏教だが、儒学もまた、古えの
聖賢の言葉や聖王賢臣の事績を参考に今後の世の中を切り開いていく、温故知新を勉学上の
最重要理念に掲げている。旧来の学説など淘汰してナンボであると考えられている洋学の感覚
などからすれば、儒者のあり方が古臭くて依存的に過ぎるように思われたりもするわけだけども、
儒学が勃興した春秋戦国時代にも、新規奇抜な学説で人々の奇を衒おうとしていたような学者は
名家などに多数いたわけで、儒学もそんな連中を横目にして構築されていったものでこそある。
そして名家の言説が世のため人のために寄与したような事実はほとんどない一方で、儒学が
東洋史上において与えてきた好影響は枚挙に暇がない。結局は去来今の三世をよく俯瞰できる
者こそが善美でいられるのが、この世界の実相法則でもあるのだから、温故知新を旨とする
儒者のあり方などを、洋学者風情があざ笑っていたりしていいようなはずもないのである。
「蟋蟀堂に在り、歳も聿に其れ莫れんとす。
今我れら楽しず、日月も其れ除らんとす。
大いには康しむ無かれ、職に其の居を思え。
楽しみを好みて荒む無かれ、良士は瞿瞿たり。
蟋蟀堂に在り、歳も聿に其れ逝かんとす。
今我れら楽しまず、日月も其れ邁かんとす。
大いには康しむ無かれ、職に其の外を思え。
楽しみを好みて荒む無かれ、良士は蹶蹶たり。
蟋蟀堂に在り、役車も其れ休らげり。
今我れ楽しまず、日月も其れ慆ぎんとす。
大いには康しむ無かれ、職に其の憂いを思え。
楽しみを好みて荒む無かれ、良士は休休たり」
「コオロギが家に入り込んでくるような季節、今年ももう暮れようとしている。
日月の早々と暮れ行く様を見て、私も今ばかりを楽しもうとすることを戒める。
無闇にうかれたりはせずに、家業の重要さをよくわきまえねばならない。
楽しみばかりに耽って惑乱するな、良き士こそは常日ごろから畏れ慎んでいる。
コオロギが家に入り込んでくるような季節、今年ももう過ぎようとしている。
日月の早々と過ぎ行く様を見て、私も今ばかりを楽しもうとすることを戒める。
無闇にうかれたりはせずに、家の周りのことにまでよく気を遣わねばならない。
楽しみばかりに耽って惑乱するな、良き士こそは常日ごろからこまめでいる。
コオロギが家に入り込んでくるような季節、仕事用の運送車も休める頃。
日月の早々と過ぎ去る様を見て、私も今ばかりを楽しもうとすることを戒める。
無闇にうかれたりはせずに、むしろよく憂患を尽くすぐらいでないといけない。
楽しみばかりに耽って惑乱するな、良き士こそは常日ごろから引き締まっている」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・唐風・蟋蟀より)
今我れら楽しず、日月も其れ除らんとす。
大いには康しむ無かれ、職に其の居を思え。
楽しみを好みて荒む無かれ、良士は瞿瞿たり。
蟋蟀堂に在り、歳も聿に其れ逝かんとす。
今我れら楽しまず、日月も其れ邁かんとす。
大いには康しむ無かれ、職に其の外を思え。
楽しみを好みて荒む無かれ、良士は蹶蹶たり。
蟋蟀堂に在り、役車も其れ休らげり。
今我れ楽しまず、日月も其れ慆ぎんとす。
大いには康しむ無かれ、職に其の憂いを思え。
楽しみを好みて荒む無かれ、良士は休休たり」
「コオロギが家に入り込んでくるような季節、今年ももう暮れようとしている。
日月の早々と暮れ行く様を見て、私も今ばかりを楽しもうとすることを戒める。
無闇にうかれたりはせずに、家業の重要さをよくわきまえねばならない。
楽しみばかりに耽って惑乱するな、良き士こそは常日ごろから畏れ慎んでいる。
コオロギが家に入り込んでくるような季節、今年ももう過ぎようとしている。
日月の早々と過ぎ行く様を見て、私も今ばかりを楽しもうとすることを戒める。
無闇にうかれたりはせずに、家の周りのことにまでよく気を遣わねばならない。
楽しみばかりに耽って惑乱するな、良き士こそは常日ごろからこまめでいる。
コオロギが家に入り込んでくるような季節、仕事用の運送車も休める頃。
日月の早々と過ぎ去る様を見て、私も今ばかりを楽しもうとすることを戒める。
無闇にうかれたりはせずに、むしろよく憂患を尽くすぐらいでないといけない。
楽しみばかりに耽って惑乱するな、良き士こそは常日ごろから引き締まっている」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・唐風・蟋蟀より)
日本の武道なども、非合理なほどもの努力主義が是とされるようになったのは、
明治や戦後以降のこと。いま各種古流剣術や、合気道や大東流柔術などに継承
されているような古武術技法も、合理的な身体の動きや刀捌きこそを洗練させて
いったもので、非合理な力技をごり押しするようなことはかえって戒めている。
それが明治以降、武術ではなくグラバーらから購入した重火器によって薩軍が倒幕をやらかし、
軍隊から警察に至るまでの武力利権を鹿児島人が自分たちばかりで牛耳るようになって、本来は
当地の田舎剣法に過ぎなかった猪突猛進主義の剣法である示現流が、剣道の基本技法に据えられるなど
したために、江戸時代までにこそなかったほどもの突進志向を武道が帯びていくようになってしまった。
それでも戦前までは、武道全般が大いに奨励されていたものだから、古流の剣術や柔術を武道の場において
参考にすることが大いにあったわけだが、武道禁止令が一時的に出された戦後にはそのような試みも
大幅な制限を受けるようになり、古武術の技法を応用した武道などは村八分扱いを受けるようになった。
そして、いま武道の主流とされている剣道や柔道こそは、技術研鑽なんかごく簡素なものに止めて、
ただひたすら力と気合いとで相手を押しまくることを全てとするスポーツ武道と化してしまっている。
幕末から明治、大正、昭和と時代を下るに連れて、武道はかえって徒労も辞さないような努力主義
一辺倒に陥っていった。それにもかかわらず、今の武道こそを鑑みて、「武道ばかりやってた昔の
人たちは非合理に過ぎるような人たちばかりだった」などと勝手に思い込んでしまっていたりもする。
本来武道こそは、人間工学も顔負けの合理的な身体躁法を突き止めたものであったのに、スポーツを含む
西洋文化が国内に大量流入して来たことの煽りを受けて、かえって部分的にはそうでなくなってしまった。
科学やその他の無宗教的学術が西洋から大量に輸入されたせいで、西洋こそは合理主義の牙城であり、
日本を含む東洋こそは非合理主義の吹き溜まりであったかのような勘違いが、未だに広く蔓延している。
明治や戦後以降のこと。いま各種古流剣術や、合気道や大東流柔術などに継承
されているような古武術技法も、合理的な身体の動きや刀捌きこそを洗練させて
いったもので、非合理な力技をごり押しするようなことはかえって戒めている。
それが明治以降、武術ではなくグラバーらから購入した重火器によって薩軍が倒幕をやらかし、
軍隊から警察に至るまでの武力利権を鹿児島人が自分たちばかりで牛耳るようになって、本来は
当地の田舎剣法に過ぎなかった猪突猛進主義の剣法である示現流が、剣道の基本技法に据えられるなど
したために、江戸時代までにこそなかったほどもの突進志向を武道が帯びていくようになってしまった。
それでも戦前までは、武道全般が大いに奨励されていたものだから、古流の剣術や柔術を武道の場において
参考にすることが大いにあったわけだが、武道禁止令が一時的に出された戦後にはそのような試みも
大幅な制限を受けるようになり、古武術の技法を応用した武道などは村八分扱いを受けるようになった。
そして、いま武道の主流とされている剣道や柔道こそは、技術研鑽なんかごく簡素なものに止めて、
ただひたすら力と気合いとで相手を押しまくることを全てとするスポーツ武道と化してしまっている。
幕末から明治、大正、昭和と時代を下るに連れて、武道はかえって徒労も辞さないような努力主義
一辺倒に陥っていった。それにもかかわらず、今の武道こそを鑑みて、「武道ばかりやってた昔の
人たちは非合理に過ぎるような人たちばかりだった」などと勝手に思い込んでしまっていたりもする。
本来武道こそは、人間工学も顔負けの合理的な身体躁法を突き止めたものであったのに、スポーツを含む
西洋文化が国内に大量流入して来たことの煽りを受けて、かえって部分的にはそうでなくなってしまった。
科学やその他の無宗教的学術が西洋から大量に輸入されたせいで、西洋こそは合理主義の牙城であり、
日本を含む東洋こそは非合理主義の吹き溜まりであったかのような勘違いが、未だに広く蔓延している。
福沢諭吉あたりも、明らかに確信犯としてそのような論説を世に広めていたわけだが、説として是か非か
という以前に、上記のような考えは全くの事実誤認でしかない。西洋の諸々の無宗教的学術も、非合理主義
の極みである聖書信仰を原因とした文化的荒廃を埋め合わせる目的で拵えられたものであり、聖書信仰が
西洋文化の根幹である以上は、西洋文化こそが非合理主義の牙城であると見なしたほうが正しいのである。
聖書信仰の極度な非合理主義による荒廃を埋め合わせる目的で、西洋人こそは合理主義の極みである
かのような無宗教的学術を拵えた。「あるかのような」というのは、結局はその手法を傍観的な観察や
大げさ過ぎる帰納法などに限り続けてきたからで、それがいかにも合理主義の極みらしく思われる一方で、
万物斉同の無為自然の先にこそ真理がある、この世界この宇宙の実相法則を合理的に取り扱うことにかけて、
東洋学や日本の古武術程度に有用であったような試しすらないことでも、一貫し続けてきたのである。
東洋の合理主義が健全な合理主義なら、西洋の合理主義はカタワの合理主義であり、その合理主義に
基づく文明構築を志した結果、かえって聖書信者級の非合理主義にまみれた愚人を量産していしまうという
弊害を生じさせてきた。学問の対象がモノやカネばかりに終始して、人間自身を問い学ぶことを全く疎かに
し続けて来たものだから、肝心の人間自身が全く合理主義の実践に与れない事態を持ち越して来たのだった。
西洋学では、未だに「0」という理念を人文学に導入することすら実質上、禁止されている。
だから「悪いことをするぐらいなら何もしないでいたほうがマシ」程度の倫理的判断すら覚束ない。
それもやはり、旧約の律法における労働の義務化などの、旧来の聖書文化の影響を持ち越してしまって
いるからで、洋学者自身、自分たちでも気づかないうちから非合理主義に沿ってしまっていたりもする。
川の上流が濁っていれば、下流も必ず濁るという致命問題に、未だ洋学者も苛まれ続けているのである。
という以前に、上記のような考えは全くの事実誤認でしかない。西洋の諸々の無宗教的学術も、非合理主義
の極みである聖書信仰を原因とした文化的荒廃を埋め合わせる目的で拵えられたものであり、聖書信仰が
西洋文化の根幹である以上は、西洋文化こそが非合理主義の牙城であると見なしたほうが正しいのである。
聖書信仰の極度な非合理主義による荒廃を埋め合わせる目的で、西洋人こそは合理主義の極みである
かのような無宗教的学術を拵えた。「あるかのような」というのは、結局はその手法を傍観的な観察や
大げさ過ぎる帰納法などに限り続けてきたからで、それがいかにも合理主義の極みらしく思われる一方で、
万物斉同の無為自然の先にこそ真理がある、この世界この宇宙の実相法則を合理的に取り扱うことにかけて、
東洋学や日本の古武術程度に有用であったような試しすらないことでも、一貫し続けてきたのである。
東洋の合理主義が健全な合理主義なら、西洋の合理主義はカタワの合理主義であり、その合理主義に
基づく文明構築を志した結果、かえって聖書信者級の非合理主義にまみれた愚人を量産していしまうという
弊害を生じさせてきた。学問の対象がモノやカネばかりに終始して、人間自身を問い学ぶことを全く疎かに
し続けて来たものだから、肝心の人間自身が全く合理主義の実践に与れない事態を持ち越して来たのだった。
西洋学では、未だに「0」という理念を人文学に導入することすら実質上、禁止されている。
だから「悪いことをするぐらいなら何もしないでいたほうがマシ」程度の倫理的判断すら覚束ない。
それもやはり、旧約の律法における労働の義務化などの、旧来の聖書文化の影響を持ち越してしまって
いるからで、洋学者自身、自分たちでも気づかないうちから非合理主義に沿ってしまっていたりもする。
川の上流が濁っていれば、下流も必ず濁るという致命問題に、未だ洋学者も苛まれ続けているのである。
「祈父よ、予れは王の爪牙なり。胡ぞ予れを恤に転ばしめ、止まり居ること靡からしむ。
祈父よ、予れは王の爪士なり。胡ぞ予れを恤に転ばしめ、底に止まること靡からしむ。
祈父よ、亶に不聡なる。胡ぞ予れを恤に転ばしめ、有た之れ尸饔すること母からしむ」
「大将さまよ、わしは王様の近衛兵だ。どうしてこれ程もの身分にありながら、
貧窮の中に転ばされて、ろくに安住もできないようなザマでいさせられるのだ。
大将さまよ、わしは王様の近衛兵だ。どうしてこれ程もの身分にありながら、
貧窮の中に転ばされて、少しも止まってすらいられないようなザマでいさせられるのだ。
大将さまよ、どうしてそれ程にも分からず屋なのだ。我々を貧窮の中に転ばせて、
もはやろくに食べて行けもしないようなザマにすら追い込まれているじゃないか。
(没落時の西周宣王の近衛兵が、自分たちの隊長を怨み謗る歌。軍人といえども心があり、
命令至上主義である軍役といえども、過酷で割りに合わなさ過ぎたりすれば不満が生ずる。
精神論でそのような怨みを抑えようにも、兵隊も必ずしも精神力旺盛な精鋭ばかりとも限らない。
だから将校も兵士を相応に労わるべきであると『六韜』『三略』などにもある。
軍隊ですらそうなのだから、民間人を相手にした為政などであれば尚更のことである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・小雅・祈父之什・祈父)
祈父よ、予れは王の爪士なり。胡ぞ予れを恤に転ばしめ、底に止まること靡からしむ。
祈父よ、亶に不聡なる。胡ぞ予れを恤に転ばしめ、有た之れ尸饔すること母からしむ」
「大将さまよ、わしは王様の近衛兵だ。どうしてこれ程もの身分にありながら、
貧窮の中に転ばされて、ろくに安住もできないようなザマでいさせられるのだ。
大将さまよ、わしは王様の近衛兵だ。どうしてこれ程もの身分にありながら、
貧窮の中に転ばされて、少しも止まってすらいられないようなザマでいさせられるのだ。
大将さまよ、どうしてそれ程にも分からず屋なのだ。我々を貧窮の中に転ばせて、
もはやろくに食べて行けもしないようなザマにすら追い込まれているじゃないか。
(没落時の西周宣王の近衛兵が、自分たちの隊長を怨み謗る歌。軍人といえども心があり、
命令至上主義である軍役といえども、過酷で割りに合わなさ過ぎたりすれば不満が生ずる。
精神論でそのような怨みを抑えようにも、兵隊も必ずしも精神力旺盛な精鋭ばかりとも限らない。
だから将校も兵士を相応に労わるべきであると『六韜』『三略』などにもある。
軍隊ですらそうなのだから、民間人を相手にした為政などであれば尚更のことである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・小雅・祈父之什・祈父)
諸行無常の絶対真理をうべなう所で人は善を為し、不滅の命などを追い求める所で人は悪を為す。
人間同士が社会的な関係性の中で自然と定義をすり合わせて言った所の、善や悪を為す。
「自分はこれが善いと思う」「あれは悪いと思う」などと個人的に主張する所の善悪であれば、
必ずしも上のような条件を満たさず、かえって上のような善悪を転倒させてしまいがちにすらなる。
この世界、この宇宙の全現象からして、諸行無常を原理的な法則とする物理構造によって司られており、
形あるもの全てがいつかは灰塵に帰するほどもの有機性が遍在していればこそ、全てのものが形を成している。
特に、「命」を具えるほどにも有機的な構造体=生命体こそは、この宇宙の原理的な構造に強度に依存
することでこそ生じているため、一定の寿命内での個体の死滅が決して免れられないようになっている。
そのような原理法則に沿おうとした時に人は善を為せる一方、抗おうとした時に人は悪を為してしまう。
ただそうであるだけでなく、そうであることに即した善悪の分別をも人間は一定以上にわきまえて来た。
そうでなければ人間関係を健全化させることもままならないから、規格を統一させた倫理体系というものを
否応なく構築して来た。それをそのまま世俗の言葉に起こしてみたのが、たとえば儒学の学説だったりする。
四書五経に代表される儒説の内容が、あまりにも当たり前なものばかりであり過ぎるせいで、
かえって軽んじられることが多いのも、元からして、人々が社会的な人間関係を育んでいく上で
自然と構築していった、当たり前な倫理体系を学説化したのが儒説でこそあるからで、その内容が
当たり前なものばかりであるのも、儒学が成立した経緯からいっても、これまた当たり前なことなのである。
人間にとってのごく当たり前な倫理体系こそを儒学として学説化した中国に限らずとも、世界中において、
儒説と同等の善悪の分別を具えた倫理体系というのは遍在している。その条件を満たせている限りにおいて、
人間は一定以上に大規模な社会構造を構築し得るのだから、例外である人間社会などもこの世界のどこにもない。
人間同士が社会的な関係性の中で自然と定義をすり合わせて言った所の、善や悪を為す。
「自分はこれが善いと思う」「あれは悪いと思う」などと個人的に主張する所の善悪であれば、
必ずしも上のような条件を満たさず、かえって上のような善悪を転倒させてしまいがちにすらなる。
この世界、この宇宙の全現象からして、諸行無常を原理的な法則とする物理構造によって司られており、
形あるもの全てがいつかは灰塵に帰するほどもの有機性が遍在していればこそ、全てのものが形を成している。
特に、「命」を具えるほどにも有機的な構造体=生命体こそは、この宇宙の原理的な構造に強度に依存
することでこそ生じているため、一定の寿命内での個体の死滅が決して免れられないようになっている。
そのような原理法則に沿おうとした時に人は善を為せる一方、抗おうとした時に人は悪を為してしまう。
ただそうであるだけでなく、そうであることに即した善悪の分別をも人間は一定以上にわきまえて来た。
そうでなければ人間関係を健全化させることもままならないから、規格を統一させた倫理体系というものを
否応なく構築して来た。それをそのまま世俗の言葉に起こしてみたのが、たとえば儒学の学説だったりする。
四書五経に代表される儒説の内容が、あまりにも当たり前なものばかりであり過ぎるせいで、
かえって軽んじられることが多いのも、元からして、人々が社会的な人間関係を育んでいく上で
自然と構築していった、当たり前な倫理体系を学説化したのが儒説でこそあるからで、その内容が
当たり前なものばかりであるのも、儒学が成立した経緯からいっても、これまた当たり前なことなのである。
人間にとってのごく当たり前な倫理体系こそを儒学として学説化した中国に限らずとも、世界中において、
儒説と同等の善悪の分別を具えた倫理体系というのは遍在している。その条件を満たせている限りにおいて、
人間は一定以上に大規模な社会構造を構築し得るのだから、例外である人間社会などもこの世界のどこにもない。
超越神からの救いによる不滅の命の獲得などを謳う、邪教に支配された西洋社会でも、それは同じこと。
違うのは、儒説並みにまともな倫理体系をわきまえている人間が皆、被支配者の側に回されて、一方的に
虐げられる体裁と共にのみ世の中を支えていくことを強要され続けて来た点のみであり、そのあたり、
不老不死を希求していた始皇帝によって支配されていた秦代の中国などとも似通っている。当時の中国でも、
被支配者こそは無責任な支配者の下で、世の中を営んでいく全責任をも負わされていたわけで、だからこそ、
革命によっていち百姓に過ぎなかった劉家が皇帝の座に就き直したことで、世相が安定を獲得しもしたのだった。
西洋でも「民主化」という手続きを通じて、邪教支配下で本当に世の中を支えている民衆たちにこそ
政治的権限を付与しようとする試みがなされたが、初戦は茶番の域に止まり続けた。正式な立場にある
為政者が、十分な責任を負ってこそ世の中も改善されるのに、為政者は相変わらず無責任なままで、自分たちには
また別に仕事のある民衆たちに主権だけは与えようとしたのだから、その片手落ちさ故にうまくいくこともなかった。
特に、人様の命を自由に左右できる程もの大権を掌握した者の内にこそ、不滅の命なぞを求めて悪行を為す
輩が生じてしまいがちなもの。まるで、本当に自分が不滅の命を得られるかのように勘違いしてしまい、
一般人にとっては当たり前であるような善悪の分別すらをも容易く見失ってしまう。だから、そのような
権力者のためにこそ、当たり前な倫理体系をそのまま学術化しただけの学問である儒学や、諸行無常を
帰依者に堅くわきまえさせる仏教などが必要にすらなって来る。社会的権限の絶大化に反比例して、
人としての当たり前なわきまえのほうは失いがちなもので、だからこそ儒学や仏教を舐めているわけにもいかない。
「厥の心疾很、死を畏るることも克わず」
「自らの心が病み患いひねくれきってしまっているために、死を畏れ謹むこともできない。
(これも聖書信者に共通する精神病理である。こんな人間ばかりでは世の中も保てない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・酒誥)
違うのは、儒説並みにまともな倫理体系をわきまえている人間が皆、被支配者の側に回されて、一方的に
虐げられる体裁と共にのみ世の中を支えていくことを強要され続けて来た点のみであり、そのあたり、
不老不死を希求していた始皇帝によって支配されていた秦代の中国などとも似通っている。当時の中国でも、
被支配者こそは無責任な支配者の下で、世の中を営んでいく全責任をも負わされていたわけで、だからこそ、
革命によっていち百姓に過ぎなかった劉家が皇帝の座に就き直したことで、世相が安定を獲得しもしたのだった。
西洋でも「民主化」という手続きを通じて、邪教支配下で本当に世の中を支えている民衆たちにこそ
政治的権限を付与しようとする試みがなされたが、初戦は茶番の域に止まり続けた。正式な立場にある
為政者が、十分な責任を負ってこそ世の中も改善されるのに、為政者は相変わらず無責任なままで、自分たちには
また別に仕事のある民衆たちに主権だけは与えようとしたのだから、その片手落ちさ故にうまくいくこともなかった。
特に、人様の命を自由に左右できる程もの大権を掌握した者の内にこそ、不滅の命なぞを求めて悪行を為す
輩が生じてしまいがちなもの。まるで、本当に自分が不滅の命を得られるかのように勘違いしてしまい、
一般人にとっては当たり前であるような善悪の分別すらをも容易く見失ってしまう。だから、そのような
権力者のためにこそ、当たり前な倫理体系をそのまま学術化しただけの学問である儒学や、諸行無常を
帰依者に堅くわきまえさせる仏教などが必要にすらなって来る。社会的権限の絶大化に反比例して、
人としての当たり前なわきまえのほうは失いがちなもので、だからこそ儒学や仏教を舐めているわけにもいかない。
「厥の心疾很、死を畏るることも克わず」
「自らの心が病み患いひねくれきってしまっているために、死を畏れ謹むこともできない。
(これも聖書信者に共通する精神病理である。こんな人間ばかりでは世の中も保てない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・酒誥)
 情念こそは、口先だけでどうにでもこねくり回せるものである一方、
情念こそは、口先だけでどうにでもこねくり回せるものである一方、 口先だけでどうにかなるような情念こそは、人間の心の内でも特に本性からかけ離れた要素ともなっている。
だから、口先で自分の心をどうにかしようとすればするほど、人は自らの本性を疎かにもしてしまうのであり、
そのような事態に陥るのを防ぐためには、般若思想のごとき一切皆空の境地に口語情報の全てを帰するのが得策ともなるのである。
人間の本性は臍下三寸の下丹田付近を在処としている一方、情念は脳や口先もある頭部の上丹田付近を在処としている。
この中間の、中丹田付近に相当する心臓が劣情の影響を受けて、動作を過剰化させてしまう(おだつ)ことが、
上丹田と下丹田の連絡を阻害する原因となり、性情が分裂してまでの劣情の独り歩きを促進することとなってしまう。
愚人や悪人はほぼ全員がそのような心理状態に陥ってしまっている一方、聖人や賢人は心臓の暴走による性情の
分裂などを十分に抑えられている。凡人や善人はその中間で、性情の分裂を抑えられていたりいなかったりする程度。
性情が完全に分裂した愚人が蒙昧さを開き直っての蛮行に及べば悪人となる一方、性情をよく一致させた
賢人がより一層の研鑽を尽くせば聖人になるといった程度の差違がある。善人と凡人の違いは、
ただ性情を分裂させないでおこうとする意志が自分自身にあるかないかといった程度のもので、
善人にはその程度の意志はある一方、凡人にはその意志すらない。善人と凡人のいずれも、必ずしも性情を
一致させられていない点では共通するが、自らに性情を一致させていこうとする意志があるぶんだけ、
善人のほうが凡人よりも、愚人や悪人へと豹変してしまったりはしにくいといった程度の違いはある。
性情の分裂を物理的に抑止する手段としては、「みそぎ」がある。斎戒沐浴などとも言われる冷水浴によって、
心臓の暴走が十分に抑えられて、上丹田と下丹田の性情の連絡を阻害することが防ぎとめられるようになる。
性情の連絡が阻害されるほどにも心臓の暴走が著しい人間ほど、冷水を浴びた瞬間に心臓がバクバクと驚嘆の
鼓動を生ずるのを感ずるはずで、お年寄りや心臓の弱い人間はそのせいでの心臓麻痺などにもなりかねないから、
少しずつ冷水を浴びたり、最初はぬるま湯から少しずつ水温を下げていくようにするなどの便宜を図ったほうがよい。
また、健康な人間といえども、身体全体の冷やしすぎが風邪の原因になったりもしかねないので、やり過ぎは禁物だといえる。
あと、自分がまだ性情の分裂を十分に控えられない人間であるというのなら、せめてでも凡人ではなく
善人であるように務めるだけでも、性情が分裂しきった愚人や悪人と化してしまうことを防止する程度の効果は持ち得る。
念仏が唱名者自身に及ぼす効果も実はそういったもので、さほど熱心に唱えなくても善人でいる程度のことは
容易に叶えられるし、熱心に唱えていれば賢人や聖人にだってなれなくはない。聖人ともなれば、
念仏以外の方法での精進をも志すのが普通だが、親鸞聖人のように念仏での聖化こそを達成した方も実際にいらっしゃる。
残念ながら、性情の分裂こそを信者に促しての妄念妄動をけしかけるカルト宗教も未だ数多いため、
信教全般が性情の分裂を抑止してくれることなどを期待することは全く期待できない。今の日本で宗教が嫌われている
頻度が高いいのも、信者に性情の分裂を促す類いの邪教こそが活動を活発化させている場合が多いからで、古来からの
念仏信仰などにもよってこそ、知らず知らずの内から性情の一致を本是とするようになってしまっている日本人が、意識的に
そのような宗教を嗜む必要性などを感じないのみならず、そのような宗教への嫌悪感すらも抱くようになっているのである。
心臓の暴走が十分に抑えられて、上丹田と下丹田の性情の連絡を阻害することが防ぎとめられるようになる。
性情の連絡が阻害されるほどにも心臓の暴走が著しい人間ほど、冷水を浴びた瞬間に心臓がバクバクと驚嘆の
鼓動を生ずるのを感ずるはずで、お年寄りや心臓の弱い人間はそのせいでの心臓麻痺などにもなりかねないから、
少しずつ冷水を浴びたり、最初はぬるま湯から少しずつ水温を下げていくようにするなどの便宜を図ったほうがよい。
また、健康な人間といえども、身体全体の冷やしすぎが風邪の原因になったりもしかねないので、やり過ぎは禁物だといえる。
あと、自分がまだ性情の分裂を十分に控えられない人間であるというのなら、せめてでも凡人ではなく
善人であるように務めるだけでも、性情が分裂しきった愚人や悪人と化してしまうことを防止する程度の効果は持ち得る。
念仏が唱名者自身に及ぼす効果も実はそういったもので、さほど熱心に唱えなくても善人でいる程度のことは
容易に叶えられるし、熱心に唱えていれば賢人や聖人にだってなれなくはない。聖人ともなれば、
念仏以外の方法での精進をも志すのが普通だが、親鸞聖人のように念仏での聖化こそを達成した方も実際にいらっしゃる。
残念ながら、性情の分裂こそを信者に促しての妄念妄動をけしかけるカルト宗教も未だ数多いため、
信教全般が性情の分裂を抑止してくれることなどを期待することは全く期待できない。今の日本で宗教が嫌われている
頻度が高いいのも、信者に性情の分裂を促す類いの邪教こそが活動を活発化させている場合が多いからで、古来からの
念仏信仰などにもよってこそ、知らず知らずの内から性情の一致を本是とするようになってしまっている日本人が、意識的に
そのような宗教を嗜む必要性などを感じないのみならず、そのような宗教への嫌悪感すらも抱くようになっているのである。
丹田や正中線の扱いを重視する武術などによっても、性情の分裂を抑制する修練を積んでいくことはできる。
性情の分裂を抑制するのは決して信教の特権ではないし、性情の一致や分裂が人々にもたらす影響も決して宗教的領域に
止まるものではない。性情の一致を嗜む人間こそは社会的な積善や不悪を心がけられる一方、性情の分裂に陥っている人間は
本当に犯罪やそれに準ずるような社会的悪行を犯してしまううになる。心と身体、心と社会的行動とは決して可分なものでは
ないのだから、実利面からいっても、性情分裂の抑止という課題に取り組んでいくことが奨励されてしかるべきなのである。
「其の輔頬舌に咸ず。其の輔頬舌に咸ずとは、口説を滕ぐるなり」
「(本人自身の自己性とも無関係に)ただ口舌が外物に感応して勝手に動いているだけ。
誠意もなく、ただ口舌だけで人とも付き合ったりしているのみ。(口舌はどこまでも上辺のものでしかない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・咸・上六‐象伝より)
性情の分裂を抑制するのは決して信教の特権ではないし、性情の一致や分裂が人々にもたらす影響も決して宗教的領域に
止まるものではない。性情の一致を嗜む人間こそは社会的な積善や不悪を心がけられる一方、性情の分裂に陥っている人間は
本当に犯罪やそれに準ずるような社会的悪行を犯してしまううになる。心と身体、心と社会的行動とは決して可分なものでは
ないのだから、実利面からいっても、性情分裂の抑止という課題に取り組んでいくことが奨励されてしかるべきなのである。
「其の輔頬舌に咸ず。其の輔頬舌に咸ずとは、口説を滕ぐるなり」
「(本人自身の自己性とも無関係に)ただ口舌が外物に感応して勝手に動いているだけ。
誠意もなく、ただ口舌だけで人とも付き合ったりしているのみ。(口舌はどこまでも上辺のものでしかない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・咸・上六‐象伝より)
基礎儒学の祖である孔子こそは、「世界でも最も偉大な寡婦(やもめ)の子」
でもあり、母子家庭での自学自習によって編み出したその教義学説の適用によって、
天下国家レベルでの治世が実現された事例も枚挙に暇がない。
漢代中国の人口が最大7000万人強、江戸時代の日本の人口も最大3000万人強であり、
いずれも儒学による治世がよく達成されていた世の中である。もしも近代文明の所産を
儒学の実戦のために専らに活用できたなら、70億人超の現代世界の人々をみな、餓死すら稀な
泰平の世に安んじさせることもできなくはないに違いない。近代文明こそは地球上における
深刻な人口爆発をもたらした原因でもあるのだから、その文明的所産を丸ごと儒学の実践の
ためだけに用いたならば、それで害益をプラスマイナスゼロに帰す贖罪も済むはずで、原理的に
考えてみれば、それで現代世界の争乱にも十分な収拾を付けられることが見込まれるのである。
ただ、近代文明の発展の主導者は西洋人であり、すでに相当に敬虔さを目減りさせているとはいえ、
西洋人は基本、聖書信者である。聖書の教義こそは儒学の学義と決定的に相容れず、キリストや
エホバを信仰しているような人間が少しでもいるうちは、一滴の糞尿でも混ざった浄水がもはや
飲めなくなるようにして、儒学の実践も全く覚束なくなるため、西洋人のせいで文明発展と
聖書信仰が不可分なままにされている現状での、儒学の実践も全くの不能なままにされている。
世界でも最も偉大なやもめの子、孔子が自らの逆境を乗り越えるための自学自習にもよって
打ち立てた権力道徳学たる儒学の復興を、イエス・キリストこそは決して許すことがない。
いま儒学の復興を許さないのみならず、世界侵略の拡大によって日本や中国からすらねんごろな
儒学の実践という選択肢を奪い去ったのも、他でもない、欧米キリスト教圏である。世界中から、
世界で最も偉大なやもめの子の学説の実践を滅ぼし尽くして、決して蘇らせることもできない
ようにさせてしまっているのがイエス・キリストでこそあるのだから、キリストの完全かつ
永久なるこの世からの死滅によってでしか、その罪責を履行することもあたわないのである。
でもあり、母子家庭での自学自習によって編み出したその教義学説の適用によって、
天下国家レベルでの治世が実現された事例も枚挙に暇がない。
漢代中国の人口が最大7000万人強、江戸時代の日本の人口も最大3000万人強であり、
いずれも儒学による治世がよく達成されていた世の中である。もしも近代文明の所産を
儒学の実戦のために専らに活用できたなら、70億人超の現代世界の人々をみな、餓死すら稀な
泰平の世に安んじさせることもできなくはないに違いない。近代文明こそは地球上における
深刻な人口爆発をもたらした原因でもあるのだから、その文明的所産を丸ごと儒学の実践の
ためだけに用いたならば、それで害益をプラスマイナスゼロに帰す贖罪も済むはずで、原理的に
考えてみれば、それで現代世界の争乱にも十分な収拾を付けられることが見込まれるのである。
ただ、近代文明の発展の主導者は西洋人であり、すでに相当に敬虔さを目減りさせているとはいえ、
西洋人は基本、聖書信者である。聖書の教義こそは儒学の学義と決定的に相容れず、キリストや
エホバを信仰しているような人間が少しでもいるうちは、一滴の糞尿でも混ざった浄水がもはや
飲めなくなるようにして、儒学の実践も全く覚束なくなるため、西洋人のせいで文明発展と
聖書信仰が不可分なままにされている現状での、儒学の実践も全くの不能なままにされている。
世界でも最も偉大なやもめの子、孔子が自らの逆境を乗り越えるための自学自習にもよって
打ち立てた権力道徳学たる儒学の復興を、イエス・キリストこそは決して許すことがない。
いま儒学の復興を許さないのみならず、世界侵略の拡大によって日本や中国からすらねんごろな
儒学の実践という選択肢を奪い去ったのも、他でもない、欧米キリスト教圏である。世界中から、
世界で最も偉大なやもめの子の学説の実践を滅ぼし尽くして、決して蘇らせることもできない
ようにさせてしまっているのがイエス・キリストでこそあるのだから、キリストの完全かつ
永久なるこの世からの死滅によってでしか、その罪責を履行することもあたわないのである。
無論、実際の所、神の子を騙る邪教の流布を通じて十字架にかけられ、二度と生き返ることもない
憤死に見舞われただけなのだから、イエスという人間自身の死滅を今さら追求するのも、少し違う。
命題は、イエスが聖書中の記述のような所業によって天国に召されたという、物語構造自体に付与
されている権威を死滅させていく所にこそあり、それが達成されれば自然と、儒学の復興をも妨げる
社会的な邪念の蔓延までもが雲散霧消する。便利のために必要なのは、そういった意味でのキリストの
死滅であり、科学的にイエスの復活を否定するとかいったこととは相当に意味が異なっているといえる。
無論、科学的にも聖書の記述の誤謬性が立証されるに越したことはなく、それに基づき
キリスト神話の権威が死滅していくというのなら、それも一つの手段であるには違いないが、
それ以前に、聖書の記述が純粋な倫理的観点から見て欺瞞の塊であり、決して権威を付与するに
値しない代物であるということを直観的に理解できるようになることのほうがより重要だといえる。
そのためには、純正な倫理学でもある儒学のほうをよく勉強して、聖書信仰の倫理的な不正さを直観的な
段階から見抜けるようになっていかなければならない。西洋人が主導的に拵えてきた近代科学によって
聖書の権威が否定されたからといって、西洋人並みの精神薄弱が必ずしも改善されていくとは限らないのだから、
むしろ儒学によって聖書信仰の不埒さを即座に見抜けるようになることのほうが、重要なことともなるである。
憤死に見舞われただけなのだから、イエスという人間自身の死滅を今さら追求するのも、少し違う。
命題は、イエスが聖書中の記述のような所業によって天国に召されたという、物語構造自体に付与
されている権威を死滅させていく所にこそあり、それが達成されれば自然と、儒学の復興をも妨げる
社会的な邪念の蔓延までもが雲散霧消する。便利のために必要なのは、そういった意味でのキリストの
死滅であり、科学的にイエスの復活を否定するとかいったこととは相当に意味が異なっているといえる。
無論、科学的にも聖書の記述の誤謬性が立証されるに越したことはなく、それに基づき
キリスト神話の権威が死滅していくというのなら、それも一つの手段であるには違いないが、
それ以前に、聖書の記述が純粋な倫理的観点から見て欺瞞の塊であり、決して権威を付与するに
値しない代物であるということを直観的に理解できるようになることのほうがより重要だといえる。
そのためには、純正な倫理学でもある儒学のほうをよく勉強して、聖書信仰の倫理的な不正さを直観的な
段階から見抜けるようになっていかなければならない。西洋人が主導的に拵えてきた近代科学によって
聖書の権威が否定されたからといって、西洋人並みの精神薄弱が必ずしも改善されていくとは限らないのだから、
むしろ儒学によって聖書信仰の不埒さを即座に見抜けるようになることのほうが、重要なことともなるである。
「老いて妻無きを鰥と曰い。老いて夫無きを寡と曰い。老いて子無きを独と曰い。
幼なくして父無きを孤と曰う。此の四者は天下の窮民にして告ぐる無き者なり。文王の政を発し
仁を施すに、必ず斯の四者を先にす。(故に詩に)云く、擥いかな富める人、此の煢独を哀れむと」
「老いて妻がない男を鰥夫といい、老いて夫がいない女を寡婦といい、老いて子がない者を独り者といい、
幼くして親がない子供を孤児という。この四者は、世の中で最も困窮している寄る辺なき人々である。
そのため周の文王は政治を興し仁を施す際に、この四者の救済を真っ先に心がけた。故に詩経
(小雅・正月)にも『素晴らしいかな、かの富める人(文王)は、鰥寡孤独をも哀れみ賜う』とある。
(鰥寡孤独の救済も正規の仁政によって執り行われるべきことであり、私人が妄りにその領分を
侵すべきでないし、カルト教義によって気休めの救済ばかりを施したりするのも以ての外である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・梁恵王章句下・五より)
幼なくして父無きを孤と曰う。此の四者は天下の窮民にして告ぐる無き者なり。文王の政を発し
仁を施すに、必ず斯の四者を先にす。(故に詩に)云く、擥いかな富める人、此の煢独を哀れむと」
「老いて妻がない男を鰥夫といい、老いて夫がいない女を寡婦といい、老いて子がない者を独り者といい、
幼くして親がない子供を孤児という。この四者は、世の中で最も困窮している寄る辺なき人々である。
そのため周の文王は政治を興し仁を施す際に、この四者の救済を真っ先に心がけた。故に詩経
(小雅・正月)にも『素晴らしいかな、かの富める人(文王)は、鰥寡孤独をも哀れみ賜う』とある。
(鰥寡孤独の救済も正規の仁政によって執り行われるべきことであり、私人が妄りにその領分を
侵すべきでないし、カルト教義によって気休めの救済ばかりを施したりするのも以ての外である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・梁恵王章句下・五より)
色々な行事を催したりすることにかけての、最適な時節などを精密に見計らうためにこそ、
人はこの世界この宇宙に遍在している不確定要素までをも考慮の内に入れなければならない。
全てを決定性によって支配し、一切の融通を利かせようともしないというのでは、風流を欠く。
それで人間自身を雁字搦めにすることができたとしても、全宇宙の物理法則までをも
包摂しきれたりすることは永遠にないのだから、自然法則と乖離し過ぎたがための
人間社会の側の破綻というものを、いつかは来たさざるを得なくなる。
自然法則にも当然、決定的な部分と不確定的な部分とがあり、日月星辰の法則的な運行などの
決定的な部分にかけては、人間ごときが作為的に作りこむ決定性などよりも遥かに揺るぎがない。
だから不確定性を考慮に入れることは愚か、決定性を精査したり工作したりすることにかけても
自然の法則こそを第一とせねばならず、それでこそ人間自身が策定した決定性までもが最大級の
普遍性を帯びることともなるのである。(日本の神事などはまさにこのあり方を第一としている)
この世界この宇宙に遍在する不確定要素を考慮に入れることもなければ、決定性にかけて
自然法則を人為以上に優先しようと心がけることもない、何もかもを専らな人為による決定性に
よって塗り固めてしまおうとする試みほど愚かなこともなく、これこそは破滅の元凶ともなる。
結局、聖書信仰が信者にけしかけて来たのも、そういった何ものにも優先される人為による、
何もかもの塗り固めでしかなかった。自然現象に不確定的な要素が実際あればこそ、自然は人間に
とっての敵と見なされ、一方的な開発の対象としてのみ扱われた。儒学や神道によっても自然の
開発が振興されることはあるが、それらはあくまで自然の普遍法則に準拠しようとするものである。
人はこの世界この宇宙に遍在している不確定要素までをも考慮の内に入れなければならない。
全てを決定性によって支配し、一切の融通を利かせようともしないというのでは、風流を欠く。
それで人間自身を雁字搦めにすることができたとしても、全宇宙の物理法則までをも
包摂しきれたりすることは永遠にないのだから、自然法則と乖離し過ぎたがための
人間社会の側の破綻というものを、いつかは来たさざるを得なくなる。
自然法則にも当然、決定的な部分と不確定的な部分とがあり、日月星辰の法則的な運行などの
決定的な部分にかけては、人間ごときが作為的に作りこむ決定性などよりも遥かに揺るぎがない。
だから不確定性を考慮に入れることは愚か、決定性を精査したり工作したりすることにかけても
自然の法則こそを第一とせねばならず、それでこそ人間自身が策定した決定性までもが最大級の
普遍性を帯びることともなるのである。(日本の神事などはまさにこのあり方を第一としている)
この世界この宇宙に遍在する不確定要素を考慮に入れることもなければ、決定性にかけて
自然法則を人為以上に優先しようと心がけることもない、何もかもを専らな人為による決定性に
よって塗り固めてしまおうとする試みほど愚かなこともなく、これこそは破滅の元凶ともなる。
結局、聖書信仰が信者にけしかけて来たのも、そういった何ものにも優先される人為による、
何もかもの塗り固めでしかなかった。自然現象に不確定的な要素が実際あればこそ、自然は人間に
とっての敵と見なされ、一方的な開発の対象としてのみ扱われた。儒学や神道によっても自然の
開発が振興されることはあるが、それらはあくまで自然の普遍法則に準拠しようとするものである。
一方、聖書信仰に基づく自然の開発はただ作為的であるだけでなく、自然法則に内在する絶対性まで
をも無視しての、完全な恣意に基づこうとするものであったため、自然を一方的な破壊の対象として、
それから文明構造を更地に積み上げていくといったものばかりだった。だからこそ西洋文明が
無機性にかけていかにも突出していて、それにより「文明の規範」みたいにまで扱われもしたが、
それは本当は、文明開発のあり方としてはヘタクソなものだったのであり、自然の絶対性までをも無視
しての身勝手な人為的開発ばかりに専らであり過ぎたからこそ、早急の崩壊すらもが免れ得ないのである。
物理的に、最も絶対的かつ普遍的なのは自然の絶対法則であり、人間自身が策定する法則などではない。
いくら脳内の概念として自明に絶対的であろうとも、実物の文明構造としてそれがおこされた時には
少なからず脆弱さを帯びる。その脆弱さを抑制するためには、構造物を自然法則の絶対性にこそ近似
させていく必要があるわけで、そこはイデア論が一歩も二歩も道を譲らなければならない部分である。
あまりいい譬えではないが、染色体の損傷によって奇形と化してしまったような生物と同等の、
奇形的な文明構造というものが、人間本位の文明構築によって生じてしまうことになる。
生物自身も染色体が健常であってこそ健全に育つように、文明構造も先天的な自然法則に
即して無理のないように構築していくことでこそ最大級の健全性を帯びる。健全だから
安定的となり、不健全な文明構造と比べれば牽強さ、寿命の長さなどの点でも秀でることになる。
自然の絶対法則を尊重しつつ人為的な開発を進めるのはこれからもありだが、自然法則を無視してまで
人為的な開発をごり押ししようとすることは、いい加減やめねばならない。それこそ、人間自身という
恣意の悪魔が、清浄なる自然界を汚損していく所業だともいえるわけで、そんな醜い人間のあり方などを、
虚構の神の所業に付託して推し進めたりすることも、これからはもってのほか扱いとしていかねばならない。
をも無視しての、完全な恣意に基づこうとするものであったため、自然を一方的な破壊の対象として、
それから文明構造を更地に積み上げていくといったものばかりだった。だからこそ西洋文明が
無機性にかけていかにも突出していて、それにより「文明の規範」みたいにまで扱われもしたが、
それは本当は、文明開発のあり方としてはヘタクソなものだったのであり、自然の絶対性までをも無視
しての身勝手な人為的開発ばかりに専らであり過ぎたからこそ、早急の崩壊すらもが免れ得ないのである。
物理的に、最も絶対的かつ普遍的なのは自然の絶対法則であり、人間自身が策定する法則などではない。
いくら脳内の概念として自明に絶対的であろうとも、実物の文明構造としてそれがおこされた時には
少なからず脆弱さを帯びる。その脆弱さを抑制するためには、構造物を自然法則の絶対性にこそ近似
させていく必要があるわけで、そこはイデア論が一歩も二歩も道を譲らなければならない部分である。
あまりいい譬えではないが、染色体の損傷によって奇形と化してしまったような生物と同等の、
奇形的な文明構造というものが、人間本位の文明構築によって生じてしまうことになる。
生物自身も染色体が健常であってこそ健全に育つように、文明構造も先天的な自然法則に
即して無理のないように構築していくことでこそ最大級の健全性を帯びる。健全だから
安定的となり、不健全な文明構造と比べれば牽強さ、寿命の長さなどの点でも秀でることになる。
自然の絶対法則を尊重しつつ人為的な開発を進めるのはこれからもありだが、自然法則を無視してまで
人為的な開発をごり押ししようとすることは、いい加減やめねばならない。それこそ、人間自身という
恣意の悪魔が、清浄なる自然界を汚損していく所業だともいえるわけで、そんな醜い人間のあり方などを、
虚構の神の所業に付託して推し進めたりすることも、これからはもってのほか扱いとしていかねばならない。
「王者の作らざる、未だ此の時より疏きは有らず。民の虐政に憔悴せる、未だ此の時より甚だしきは有らず」
「天命を得た王者が現れなくなってから、これ程にも久しい時も未だかつてない。人々が暴君の虐政に喘ぐ
ことにかけても、これ程にも甚だしかった時も未だかつてない。(時節論はこのような最悪の時をも
包含せねばならないのだから、そこに勧善懲悪を試みるのでもなければ、無為自然に甘んじるしかない。
そのいずれをも拒んだなら自らが悪逆非道に走ることにもなるわけで、労働を義務化している旧約の記述などに
基づくなら、時宜論に即してこそ悪逆非道すらをも義務的に行わなければならなくなってしまうのだから、しょうもない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・公孫中章句下・一より)
「天命を得た王者が現れなくなってから、これ程にも久しい時も未だかつてない。人々が暴君の虐政に喘ぐ
ことにかけても、これ程にも甚だしかった時も未だかつてない。(時節論はこのような最悪の時をも
包含せねばならないのだから、そこに勧善懲悪を試みるのでもなければ、無為自然に甘んじるしかない。
そのいずれをも拒んだなら自らが悪逆非道に走ることにもなるわけで、労働を義務化している旧約の記述などに
基づくなら、時宜論に即してこそ悪逆非道すらをも義務的に行わなければならなくなってしまうのだから、しょうもない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・公孫中章句下・一より)
http://bbs0.meiwasuisan.com/bbs/bin/read/toriaezu/13492733...
ここで論じていることにも関連するが、人は、必ずしも物事を決め付けてかからなくても済む
ぐらいの心の余裕があってから、便宜的に物事を断定するようなこともあったりしたほうがよい。
「AでもなければBでもない」「Aでもなければ非Aでもない」といった般若経的な中観の境地に
よく心を落ち着けて後に、便宜的に物事を断定したり、物事に挺身して行ったりしたほうが、
何事も余裕を持ってうまくなせるのだから、できるならそうするに越したことはない。
世の中の誰しもがそれぐらいの余裕を持てたなら、争いごとなども起こった所で控えめなものに
止められるし、そもそも争いごとなどの問題を始めから引き起こさないための最善の配慮が
尽くされることともなるだろう。物事を頭ごなしに決め付けてかかる人間ほど思考が億劫にも
なるもので、一旦決め付けたことを改めたりするのもなかなか困難なこととなってしまうが、
是もなければ非もない中観を大前提として物事を考える人間であれば、物事を断定したり
することもあくまで便宜として軽快に扱うから、思考を永続させ続けたり、一旦こうと断じた
ことを改め直したりすることも全くのお茶の子さいさいなままでい続けていられる。だからこそ
思考を永続させて、間違いは随時改めていく、人間の思考としては最善のあり方となる態度姿勢を
堅持していくことを通じて、世の中の安寧や繁栄にも最大級に貢献していけるようになるのである。
中観をよく育むということ自体、確かに高度なことで、誰しもが必ずしも達成できるものでもない。
ただ、自らが白か黒か、是か非かの両極ばかりに振り切れてしかいられない人間であったとした所で、
そうであることを「愚昧なことだ」とよく恥じ入った上での、最低限の精進などを目指すこともできる。
ここで論じていることにも関連するが、人は、必ずしも物事を決め付けてかからなくても済む
ぐらいの心の余裕があってから、便宜的に物事を断定するようなこともあったりしたほうがよい。
「AでもなければBでもない」「Aでもなければ非Aでもない」といった般若経的な中観の境地に
よく心を落ち着けて後に、便宜的に物事を断定したり、物事に挺身して行ったりしたほうが、
何事も余裕を持ってうまくなせるのだから、できるならそうするに越したことはない。
世の中の誰しもがそれぐらいの余裕を持てたなら、争いごとなども起こった所で控えめなものに
止められるし、そもそも争いごとなどの問題を始めから引き起こさないための最善の配慮が
尽くされることともなるだろう。物事を頭ごなしに決め付けてかかる人間ほど思考が億劫にも
なるもので、一旦決め付けたことを改めたりするのもなかなか困難なこととなってしまうが、
是もなければ非もない中観を大前提として物事を考える人間であれば、物事を断定したり
することもあくまで便宜として軽快に扱うから、思考を永続させ続けたり、一旦こうと断じた
ことを改め直したりすることも全くのお茶の子さいさいなままでい続けていられる。だからこそ
思考を永続させて、間違いは随時改めていく、人間の思考としては最善のあり方となる態度姿勢を
堅持していくことを通じて、世の中の安寧や繁栄にも最大級に貢献していけるようになるのである。
中観をよく育むということ自体、確かに高度なことで、誰しもが必ずしも達成できるものでもない。
ただ、自らが白か黒か、是か非かの両極ばかりに振り切れてしかいられない人間であったとした所で、
そうであることを「愚昧なことだ」とよく恥じ入った上での、最低限の精進などを目指すこともできる。
念仏行などもそのための手段として格好のものだが、念仏行といえども、自らの両極志向を開き直っての
驕り高ぶりなどと共にまで嗜めるものではなく、最低でもそのような身の程を恥じ入るぐらいの恭しさは
必要となる。自らの両極志向を恥じ入る恭しさすらないような人間でも帰依できるような信教は、それこそ
聖書信仰のようなカルト信教に限られるわけで、これこそは「病人に毒を盛る」代物とすらなってしまう。
自力作善による中観の養生が健康の増進なら、他力本願での最低限の中観の堅持は不養生に対する薬の処方、
中観の完全なる喪失を促す他力本願は、不養生に不養生を重ねさせてさらにそこに毒を盛るとでも言った所。
中観の存在意義を、それだけを見て計り知るのはなかなか難しいことだが、中観を欠いての悪逆非道に
一辺倒であり続けて来た連中の惨憺たる所業の数々を見てみればこそ、人が中観を養うことがいかに
重要なことであるのかまでもが明瞭となる。平安時代や江戸時代の日本社会だけを見れば、特にこれと
いった問題もないのほほんとした時代だったという程度の感想しか抱けなくとも、同時期の欧米社会の
引っ切り無しな戦乱状態などと見比べてみたなら、いかに当時の日本が泰平の維持にかけて優秀な実績を
挙げていたのかがよく分かるというもの。これまた当時の日本人には中観の養いが磐石であった一方、
欧米人のほうはカルト信仰にも基づく中観の喪失が著しかったからこそ、生じてしまった差違でもある。
「力を陳べて列に就き、能わざれば止む」
「力を尽くして職務に邁進し、至らないようであれば踏み止まる。
(出処進退自由自在、突進一辺倒などに決して陥らないのが聖賢の習い始めだといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・季氏第十六・一より)
驕り高ぶりなどと共にまで嗜めるものではなく、最低でもそのような身の程を恥じ入るぐらいの恭しさは
必要となる。自らの両極志向を恥じ入る恭しさすらないような人間でも帰依できるような信教は、それこそ
聖書信仰のようなカルト信教に限られるわけで、これこそは「病人に毒を盛る」代物とすらなってしまう。
自力作善による中観の養生が健康の増進なら、他力本願での最低限の中観の堅持は不養生に対する薬の処方、
中観の完全なる喪失を促す他力本願は、不養生に不養生を重ねさせてさらにそこに毒を盛るとでも言った所。
中観の存在意義を、それだけを見て計り知るのはなかなか難しいことだが、中観を欠いての悪逆非道に
一辺倒であり続けて来た連中の惨憺たる所業の数々を見てみればこそ、人が中観を養うことがいかに
重要なことであるのかまでもが明瞭となる。平安時代や江戸時代の日本社会だけを見れば、特にこれと
いった問題もないのほほんとした時代だったという程度の感想しか抱けなくとも、同時期の欧米社会の
引っ切り無しな戦乱状態などと見比べてみたなら、いかに当時の日本が泰平の維持にかけて優秀な実績を
挙げていたのかがよく分かるというもの。これまた当時の日本人には中観の養いが磐石であった一方、
欧米人のほうはカルト信仰にも基づく中観の喪失が著しかったからこそ、生じてしまった差違でもある。
「力を陳べて列に就き、能わざれば止む」
「力を尽くして職務に邁進し、至らないようであれば踏み止まる。
(出処進退自由自在、突進一辺倒などに決して陥らないのが聖賢の習い始めだといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・季氏第十六・一より)
削除(by投稿者)
削除(by投稿者)
削除(by投稿者)
削除(by投稿者)
おいおい、あらすなよ
もう、かけなくなるのかよ
▲ページ最上部
ログサイズ:700 KB 有効レス数:323 削除レス数:0
不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。
思想・哲学掲示板に戻る 全部 次100 最新50
スレッドタイトル:聖書 Part8

