サイズが 480KB を超えています。500KB を超えると書きこめなくなるよ。
聖書 Part8
▼ページ最下部
世に「聖書」として扱われている書物が、単なる学術書や文芸書などと決定的に異なっている点は、
「一人の人間が、全身全霊をかけてその実践に努めていくことができる書物」である点だといえる。
「○○聖書」という様な、何らかの目的を明確に冠した聖書であれば、その目的を達成するために、
一人以上の人間がその書物の内容を、全身全霊をかけて実践していくことが推奨される。もちろん
「聖書」扱いでない書物にも、それだけの度量を潜在している書物はいくらでもあるが、ことに
「○○聖書」といった名称がすでに定着しているほどの書物であれば、その○○を達成する上での
参考書としての定番扱いがされているわけで、「聖書」としての評価がすでに固まっているからには、
全身全霊をかけてその内容の実践に努めていくだけの価値があると、太鼓判を捺されているのでもある。
中でも、人間社会全体の規範を司るほどもの壮大さを兼ね備えている聖書であれば、それを聖典と
した一大学派や教派が形成されて、国家社会の運営を先導するほどもの勢力を擁する場合がある。
儒学の聖典である四書五経や、仏教の聖典である仏典、ヒンズー教の聖典であるヴェーダや
ウパニシャッド、イスラム教の聖典であるコーランなどが、そのような聖書の典型例であるといえる。
キリスト教とユダヤ教の聖典である新旧約聖書も、そのような、国家社会をも先導するだけの試みに
用いられては来たものの、如何せんその記述内容が粗悪に過ぎるために、それだけでは全く世の中を
司ることができず、仏教や拝火教の教義を拝借したり、無宗教の学術による補強を試みたりすることで
何とか聖書圏も保たれてきたが、それでももういい加減、崩壊が免れ得ない時期に差しかかっている。
世の中全体を司る理念となるだけの価値があって、それにより数百年以上もの泰平社会を実現していく
ことができるほどの聖書というのも、決してただ一つしか存在しなかったりするわけではない。ただ、
世の中を最低限度保っていくことが可能となる単独的な聖書の中でも、特に代表として挙げやすいのが、
儒学の正典である四書五経なので、だからこそ、世界で最も「標準的な聖書」として扱うにも相応しい
書物としての四書五経を、聖書全般を論ずる上での主要題材ともしつつ、ここで論じていくものとする。

「一人の人間が、全身全霊をかけてその実践に努めていくことができる書物」である点だといえる。
「○○聖書」という様な、何らかの目的を明確に冠した聖書であれば、その目的を達成するために、
一人以上の人間がその書物の内容を、全身全霊をかけて実践していくことが推奨される。もちろん
「聖書」扱いでない書物にも、それだけの度量を潜在している書物はいくらでもあるが、ことに
「○○聖書」といった名称がすでに定着しているほどの書物であれば、その○○を達成する上での
参考書としての定番扱いがされているわけで、「聖書」としての評価がすでに固まっているからには、
全身全霊をかけてその内容の実践に努めていくだけの価値があると、太鼓判を捺されているのでもある。
中でも、人間社会全体の規範を司るほどもの壮大さを兼ね備えている聖書であれば、それを聖典と
した一大学派や教派が形成されて、国家社会の運営を先導するほどもの勢力を擁する場合がある。
儒学の聖典である四書五経や、仏教の聖典である仏典、ヒンズー教の聖典であるヴェーダや
ウパニシャッド、イスラム教の聖典であるコーランなどが、そのような聖書の典型例であるといえる。
キリスト教とユダヤ教の聖典である新旧約聖書も、そのような、国家社会をも先導するだけの試みに
用いられては来たものの、如何せんその記述内容が粗悪に過ぎるために、それだけでは全く世の中を
司ることができず、仏教や拝火教の教義を拝借したり、無宗教の学術による補強を試みたりすることで
何とか聖書圏も保たれてきたが、それでももういい加減、崩壊が免れ得ない時期に差しかかっている。
世の中全体を司る理念となるだけの価値があって、それにより数百年以上もの泰平社会を実現していく
ことができるほどの聖書というのも、決してただ一つしか存在しなかったりするわけではない。ただ、
世の中を最低限度保っていくことが可能となる単独的な聖書の中でも、特に代表として挙げやすいのが、
儒学の正典である四書五経なので、だからこそ、世界で最も「標準的な聖書」として扱うにも相応しい
書物としての四書五経を、聖書全般を論ずる上での主要題材ともしつつ、ここで論じていくものとする。

※省略されてます すべて表示...
無論、飲酒運転それだけなら誰にも迷惑をかけないようにして、
ただキリストを信仰しているだけというのなら、誰にも迷惑はかからない。
飲酒運転が事故につながることで初めて人に迷惑がかかるように、
キリスト信仰の酩酊が犯罪行為に繋がった時に初めて、人様にも迷惑がかかる。
だから、ただ飲酒運転をしただけ、キリストを信仰しただけで刑事罰までをも被るというのは
やり過ぎになるともいえ、免許取り消しや社会的不具者指定程度の処分で済ますべきだともいえる。
飲酒運転とキリスト信仰と、事故や権力犯罪などの迷惑行為に発展する頻度では、どっこいどっこいだといえる。
ただ、飲酒運転はすでに社会的な禁忌としての扱いが定着しているから、容認の過剰からなる事故への発展なども
未然に控えられているのに対し、キリスト信仰は禁忌としての扱いすら取り払われたままだから、
完全誤謬信仰の酩酊にことかけての権力犯罪行為などが野放しになったままでもいる。
警察が厳重な取り締まりの対象などにしなくとも、そもそも世間一般から、
飲酒運転の危険性は認知されていて、一定以上に忌避の対象ともなっている。
キリスト信仰も、何よりもまずそういった「忌避対象」としての認識が世間一般に広く定着する必要があるのであり、
頭ごなしな取り締まりの対象にしたりすることは、あくまで二の次なのである。
「孝以て君に事え、弟以て長に事う。民に貳せざるを示すためなり」
「父に仕える心がけを推して主君に仕え、兄に仕える心がけを推して年長者に仕える。
民に二番煎じの不誠実さを排した姿を示すためである。(先天的な父子兄弟の関係を反故にして他に
仕えるのであれば、それが一度きりであるとした所ですでに二番煎じだから、不誠実の至りだといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・坊記第三十より)
ただキリストを信仰しているだけというのなら、誰にも迷惑はかからない。
飲酒運転が事故につながることで初めて人に迷惑がかかるように、
キリスト信仰の酩酊が犯罪行為に繋がった時に初めて、人様にも迷惑がかかる。
だから、ただ飲酒運転をしただけ、キリストを信仰しただけで刑事罰までをも被るというのは
やり過ぎになるともいえ、免許取り消しや社会的不具者指定程度の処分で済ますべきだともいえる。
飲酒運転とキリスト信仰と、事故や権力犯罪などの迷惑行為に発展する頻度では、どっこいどっこいだといえる。
ただ、飲酒運転はすでに社会的な禁忌としての扱いが定着しているから、容認の過剰からなる事故への発展なども
未然に控えられているのに対し、キリスト信仰は禁忌としての扱いすら取り払われたままだから、
完全誤謬信仰の酩酊にことかけての権力犯罪行為などが野放しになったままでもいる。
警察が厳重な取り締まりの対象などにしなくとも、そもそも世間一般から、
飲酒運転の危険性は認知されていて、一定以上に忌避の対象ともなっている。
キリスト信仰も、何よりもまずそういった「忌避対象」としての認識が世間一般に広く定着する必要があるのであり、
頭ごなしな取り締まりの対象にしたりすることは、あくまで二の次なのである。
「孝以て君に事え、弟以て長に事う。民に貳せざるを示すためなり」
「父に仕える心がけを推して主君に仕え、兄に仕える心がけを推して年長者に仕える。
民に二番煎じの不誠実さを排した姿を示すためである。(先天的な父子兄弟の関係を反故にして他に
仕えるのであれば、それが一度きりであるとした所ですでに二番煎じだから、不誠実の至りだといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・坊記第三十より)
精子 Part8wwww
 悪因苦果の苦しみとはまた別に、善因楽果を得るための過渡的な労苦というものもまたある。
悪因苦果の苦しみとはまた別に、善因楽果を得るための過渡的な労苦というものもまたある。 しかし、それは決して良心の呵責などを誘うものではなく、「善行を為している」という
自覚に根ざした、浩然の気のすがすがしさと共にこそある、身心の健全な疲労でのみある。
「肩をそびやかしてへつらい笑うことは、真夏の炎天下に田畑を耕すよりも疲れる」
(「孟子」滕文公章句下・七より)
という曾子の言葉が、まさに悪因苦果の苦しみと、善行にかけての過渡的な苦しみとの相違を如実に
示してもいる。相手から私益を貪らんがために、商人らが肩をそびやかしてへつらい笑うときの
心痛は悪因苦果だから、公益のためにも田畑を耕す農民の重度の疲労などよりも、不健全に苦しい。
善行にかけての労苦ならば、善因楽果に基づく浩然の気による相殺が期待できるが、悪因苦果の
苦しみにはそれが期待できない。だから麻薬や邪淫や完全誤謬信仰のような、救いになるどころか、
かえって副作用すらをももたらす不健全な手段に基づいた、苦痛の相殺を試みるしかなくなる。
善行の労苦を、善因楽果である浩然の気によって相殺するという場合にこそ、実益面での加増すらもが
期待できる一方、悪行からなる悪因苦果の苦しみを、完全誤謬信仰や麻薬のような不適切な手段で
相殺しようとする場合にこそ、実益面にかけての大きな損失すらもが最終的に見込まれるのである。
労苦は労苦で、確かにしたほうがいい場合がある。しかもそのような労苦のほうが、真夏の炎天下
での耕作のような重労働でもあったりする一方、避けたほうがマシな悪行のための労苦こそは、
顧客の前で肩をそびやかしてへつらい笑うような、比較的な軽作業であったりもするのである。
完全誤謬信仰に基づくのでもなければ相殺できなかった労苦こそは、紛れもなく悪行の労苦である。
悪行の労苦だから浩然の気による相殺も叶わず、なおかつ後々にプラマイゼロ以下の損失までもが
見込まれる。労苦が決して報われないのではなく、完全誤謬信仰級の酩酊によってこそ相殺して
きたような悪行の労苦こそは、特定して報われることがなく、かえって破滅の温床にすらなる。
「こんなに苦労をして来たのに」などという不満を吐く余地が、悪行の苦しみを完全誤謬信仰に
よってでも相殺しようとしてきた場合にこそ、特定して存在しない。全ては紛れもなく徒労であった
と断じられる他はなく、せいぜい、妄信からなる悪行によって破滅の種を撒き散らしてきたことが、
過失としての認定によって、なるべく減刑の対象となることを期待するぐらいのことしかできない。
それは、どこまでも特殊例であって、労苦一般に対する普遍的な報いなどではない。むしろ、
健全な労苦によって相応の成果を挙げることのほうが世の常なのだから、当り散らしも禁物だ。
「顔子は乱世に当たりて、陋巷に居り、一箪の食、一瓢の飲。
人は其の憂いに堪えざるも、顔子は其の楽しみを改めず。孔子も之れを賢とせり」
「顔先生(孔子の弟子の顔淵。孔子の亦弟子である孟子にとって、顔淵は先生格でもある)は
春秋時代の乱世において、薄汚く狭い路地に住み、一膳一杯の飲食という質素な生活を貫かれた。
常人ならその憂いを耐え忍ぶこともできないが、顔先生はその楽しみを改めようともしなかった。
孔先生もそのあり方を賢明だと認めていた。(顔淵は清貧の善因楽果である浩然の気を楽しんでいた。
その楽しみを感じ取る感性に欠けていたりするものだから、貧窮の憂いを耐え忍ぶこともできなくて、
悪因苦果まみれの悪逆非道による虚栄を求めてしまったりもするのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・離婁章句下・三〇より)
悪行の労苦だから浩然の気による相殺も叶わず、なおかつ後々にプラマイゼロ以下の損失までもが
見込まれる。労苦が決して報われないのではなく、完全誤謬信仰級の酩酊によってこそ相殺して
きたような悪行の労苦こそは、特定して報われることがなく、かえって破滅の温床にすらなる。
「こんなに苦労をして来たのに」などという不満を吐く余地が、悪行の苦しみを完全誤謬信仰に
よってでも相殺しようとしてきた場合にこそ、特定して存在しない。全ては紛れもなく徒労であった
と断じられる他はなく、せいぜい、妄信からなる悪行によって破滅の種を撒き散らしてきたことが、
過失としての認定によって、なるべく減刑の対象となることを期待するぐらいのことしかできない。
それは、どこまでも特殊例であって、労苦一般に対する普遍的な報いなどではない。むしろ、
健全な労苦によって相応の成果を挙げることのほうが世の常なのだから、当り散らしも禁物だ。
「顔子は乱世に当たりて、陋巷に居り、一箪の食、一瓢の飲。
人は其の憂いに堪えざるも、顔子は其の楽しみを改めず。孔子も之れを賢とせり」
「顔先生(孔子の弟子の顔淵。孔子の亦弟子である孟子にとって、顔淵は先生格でもある)は
春秋時代の乱世において、薄汚く狭い路地に住み、一膳一杯の飲食という質素な生活を貫かれた。
常人ならその憂いを耐え忍ぶこともできないが、顔先生はその楽しみを改めようともしなかった。
孔先生もそのあり方を賢明だと認めていた。(顔淵は清貧の善因楽果である浩然の気を楽しんでいた。
その楽しみを感じ取る感性に欠けていたりするものだから、貧窮の憂いを耐え忍ぶこともできなくて、
悪因苦果まみれの悪逆非道による虚栄を求めてしまったりもするのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・離婁章句下・三〇より)
「信仰は無条件に善いこと」などということからして、決してなかった。
何に対する信仰とも、どのような信仰とも限らない、信仰一般の中には
「私は自分の信じているものが完全に間違っていてもそれを信じます」
という完全誤謬信仰までもが自動的に含まれている。それは、奴隷が主人に対して
絶対服従であろうとする姿勢も同然であり、仮に未だ奴隷制が完全に解消されていない
ような世の中においてですら、善いか悪いかでいえば悪いものとされるものなのである。
奴隷制は日本でも鎌倉時代まで、中国でも「苦力」という形で中共建国前まで
存続していたが、それが決して倫理的な存在などであるからではなく、ただ
権力者などにとって都合のいい人材要員であるから容認されて来たまでのことだ。
遥か昔、楚漢戦争後に楚軍の落ち武者となった季布が、剃髪に首枷という奴隷装束にまで
身をやつして逃亡していたことが、「それ程もの屈辱を呑んでいた」という理由で
高祖劉邦の感銘を買い、その罪を許されて郎中や太守としての復帰をも許されている。
奴隷制が存在しようが存在するまいが、奴隷などという身分、奴隷である者のあり方などが
評価の対象などになることは、太古の昔から東洋ではなかった。むしろ、奴隷こそは透徹
して屈辱的な存在であると見なされていたからこそ、奴隷身分の伝統的な装束である剃髪が、
仏門における出家修行者のための「忍辱行」を兼ねる装束としても流用されたのだった。
何に対する信仰とも、どのような信仰とも限らない、信仰一般の中には
「私は自分の信じているものが完全に間違っていてもそれを信じます」
という完全誤謬信仰までもが自動的に含まれている。それは、奴隷が主人に対して
絶対服従であろうとする姿勢も同然であり、仮に未だ奴隷制が完全に解消されていない
ような世の中においてですら、善いか悪いかでいえば悪いものとされるものなのである。
奴隷制は日本でも鎌倉時代まで、中国でも「苦力」という形で中共建国前まで
存続していたが、それが決して倫理的な存在などであるからではなく、ただ
権力者などにとって都合のいい人材要員であるから容認されて来たまでのことだ。
遥か昔、楚漢戦争後に楚軍の落ち武者となった季布が、剃髪に首枷という奴隷装束にまで
身をやつして逃亡していたことが、「それ程もの屈辱を呑んでいた」という理由で
高祖劉邦の感銘を買い、その罪を許されて郎中や太守としての復帰をも許されている。
奴隷制が存在しようが存在するまいが、奴隷などという身分、奴隷である者のあり方などが
評価の対象などになることは、太古の昔から東洋ではなかった。むしろ、奴隷こそは透徹
して屈辱的な存在であると見なされていたからこそ、奴隷身分の伝統的な装束である剃髪が、
仏門における出家修行者のための「忍辱行」を兼ねる装束としても流用されたのだった。
透徹して卑しい存在、賤しい人のあり方と見なされるべき奴隷の、主人に対する服従姿勢も
同然の信仰としての完全誤謬信仰。仮に信仰が絶対化されるのであれば、完全誤謬信仰すら
もが絶対無謬のものとして扱われることとなってしまう。それは自明にダメなことなので、
信を無条件に絶対化することなども、決して誉められたものではないということが言える。
そのような、無条件に絶対的な信を誉めそやす神なども、ダメな神であることが間違いない。
何らかの方向性が指し示されていて、それを「一心不乱に信じよ」というのならまだしも、
全く以って、ただ信じることはそれだけで素晴らしいなどというのなら、原理的にダメだ。
原理的に、そこには必ず完全誤謬信仰の是認すらもが含まれているから、原理的にダメだ。
罪の奴隷の解放を謳って、ただ信仰の奴隷になることを促すだけの邪神などは、去れ。
「言語必ず信なるは、以って行いを正すがために非ざるなり」
「必ずと言っていいほど信じるに値する言葉があったとしても、それによって行いを正して
行こうとする目的があるから発せられるのではない。(まず正しい行いがあってから、次に正しい
言葉が発せられる。それこそは信じるにも値するのだから、優先順位も行>言>信だといえる。)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句下・三二より)
同然の信仰としての完全誤謬信仰。仮に信仰が絶対化されるのであれば、完全誤謬信仰すら
もが絶対無謬のものとして扱われることとなってしまう。それは自明にダメなことなので、
信を無条件に絶対化することなども、決して誉められたものではないということが言える。
そのような、無条件に絶対的な信を誉めそやす神なども、ダメな神であることが間違いない。
何らかの方向性が指し示されていて、それを「一心不乱に信じよ」というのならまだしも、
全く以って、ただ信じることはそれだけで素晴らしいなどというのなら、原理的にダメだ。
原理的に、そこには必ず完全誤謬信仰の是認すらもが含まれているから、原理的にダメだ。
罪の奴隷の解放を謳って、ただ信仰の奴隷になることを促すだけの邪神などは、去れ。
「言語必ず信なるは、以って行いを正すがために非ざるなり」
「必ずと言っていいほど信じるに値する言葉があったとしても、それによって行いを正して
行こうとする目的があるから発せられるのではない。(まず正しい行いがあってから、次に正しい
言葉が発せられる。それこそは信じるにも値するのだから、優先順位も行>言>信だといえる。)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句下・三二より)
親鸞聖人が法然上人の門下において、他の弟子たちと
「信不退(信仰を止めない)」と「行不退(実践を止めない)」の
いずれを優先するかという論議を行ったとき、他の弟子たちはみんな
行不退を選んだのに対し、親鸞聖人だけは信不退を選んだ。論議の後、
法然上人にいずれかを問えば、「わしも親鸞と同じく信不退に賛成する」と答えた。
他力本願の浄土信仰者としては、どんな行い以上にも信仰を守る他はないと。
それは裏返してみるならば、他力本願である以上は信仰に十分な行いが伴い得ないことを
認めるべきだということなのであり、何ら正しい行いを為せているわけでもない自らが望むような
こともまた、信仰に見合うほど高潔なものではないことをも認めるべきであるということだ。
他力本願の信者であるなら、仏法の内実すら理解できなくて当然である。
華厳経や弘法大師の言葉などに、善人正機(悪人ですら救われるのだから、善人が救われるのも当然である)
に相当するような言葉も見受けられるとした所で、それは仏法を理解できた者に対する言葉でこそある。
他力本願の信者は仏法も解さないから、仏法で非とされる妄念妄動にもまみれたままでいる。
だから、その妄念に仏法を掛け合わせるなら、「善人ですら救われるのだから、悪人が救われるのも当然である」
という自利作善の場合とは真逆の教条をあてがうほうが適切ともなる。何を望むべきなのかも分かっていないし、
見えてない所にあるものが何なのかも全然分かっていないから、教条もひっくり返してしまったほうが適切なのである。
「信不退(信仰を止めない)」と「行不退(実践を止めない)」の
いずれを優先するかという論議を行ったとき、他の弟子たちはみんな
行不退を選んだのに対し、親鸞聖人だけは信不退を選んだ。論議の後、
法然上人にいずれかを問えば、「わしも親鸞と同じく信不退に賛成する」と答えた。
他力本願の浄土信仰者としては、どんな行い以上にも信仰を守る他はないと。
それは裏返してみるならば、他力本願である以上は信仰に十分な行いが伴い得ないことを
認めるべきだということなのであり、何ら正しい行いを為せているわけでもない自らが望むような
こともまた、信仰に見合うほど高潔なものではないことをも認めるべきであるということだ。
他力本願の信者であるなら、仏法の内実すら理解できなくて当然である。
華厳経や弘法大師の言葉などに、善人正機(悪人ですら救われるのだから、善人が救われるのも当然である)
に相当するような言葉も見受けられるとした所で、それは仏法を理解できた者に対する言葉でこそある。
他力本願の信者は仏法も解さないから、仏法で非とされる妄念妄動にもまみれたままでいる。
だから、その妄念に仏法を掛け合わせるなら、「善人ですら救われるのだから、悪人が救われるのも当然である」
という自利作善の場合とは真逆の教条をあてがうほうが適切ともなる。何を望むべきなのかも分かっていないし、
見えてない所にあるものが何なのかも全然分かっていないから、教条もひっくり返してしまったほうが適切なのである。
行いも言葉も、思考すらもが正しくあり得ないというような状況において、自主的に望まれることもまた
正しいわけがない。>>75の孟子の言葉の通り、正しい行を為せる程に思考もまた正しい時にこそ、真に正しい
言葉もまた発せられて、その言葉こそは真に信ずるに値する言葉ともなるが、妄念まみれであるために妄動しか
来たせないような愚人が、どんなに聞こえのいい言葉を吐いてみた所で、その言葉も所詮は妄念から発されたもの。
だからこそ同レベルの愚人からの共感を得られ、愚人が妄念によって望むことをありのままに叶えようともするが、
そこで指し示される望みの成就は、聖人が正念に基づいて発する言葉のうちの望みの成就とは、反転すらしてしまう。
愚人こそは、「善人こそは救われる」という状況を忌み嫌い、「悪人こそは救われる」という状況の到来を
心底望んでいる。望んでいるということは、今はまだ十分にその望みが叶えられていないとも考えているのである。
一方で聖人こそは、「悪人こそは救われる」という状況を忌み嫌い、「善人こそは救われる」という状況の到来こそを
望んでいる。聖人の考えからいえば、他力本願によってでしか救われ得ないような事態は、もう十分すでに、悪人
こそは救われている状況だから、それを大前提とした上での、善人こそは救われる浄土への往生を望むのである。
今が「善人こそは救われる世の中」であるか「悪人こそは救われる世の中」であるかに関わらず、
愚人は「善人こそは救われる世の中」が「悪人こそは救われる世の中」になることを望み、
聖人は「悪人こそは救われる世の中」が「善人こそは救われる世の中」になることを望む。
聖人か愚人かで望みすらもが反転するのだから、愚人は、信仰に自らの希望を託しすらしてはならないのである。
「利口を悪むは其の信を乱るを恐るればなり」
「信ずるべきものを信ずることを乱すのを恐れるために、上辺だけの口達者をも憎むのである。
(イエスのような虚言癖の口達者こそは、信仰に託すべき望み、信仰の先にあるものをも撹乱するのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句下・三七より)
正しいわけがない。>>75の孟子の言葉の通り、正しい行を為せる程に思考もまた正しい時にこそ、真に正しい
言葉もまた発せられて、その言葉こそは真に信ずるに値する言葉ともなるが、妄念まみれであるために妄動しか
来たせないような愚人が、どんなに聞こえのいい言葉を吐いてみた所で、その言葉も所詮は妄念から発されたもの。
だからこそ同レベルの愚人からの共感を得られ、愚人が妄念によって望むことをありのままに叶えようともするが、
そこで指し示される望みの成就は、聖人が正念に基づいて発する言葉のうちの望みの成就とは、反転すらしてしまう。
愚人こそは、「善人こそは救われる」という状況を忌み嫌い、「悪人こそは救われる」という状況の到来を
心底望んでいる。望んでいるということは、今はまだ十分にその望みが叶えられていないとも考えているのである。
一方で聖人こそは、「悪人こそは救われる」という状況を忌み嫌い、「善人こそは救われる」という状況の到来こそを
望んでいる。聖人の考えからいえば、他力本願によってでしか救われ得ないような事態は、もう十分すでに、悪人
こそは救われている状況だから、それを大前提とした上での、善人こそは救われる浄土への往生を望むのである。
今が「善人こそは救われる世の中」であるか「悪人こそは救われる世の中」であるかに関わらず、
愚人は「善人こそは救われる世の中」が「悪人こそは救われる世の中」になることを望み、
聖人は「悪人こそは救われる世の中」が「善人こそは救われる世の中」になることを望む。
聖人か愚人かで望みすらもが反転するのだから、愚人は、信仰に自らの希望を託しすらしてはならないのである。
「利口を悪むは其の信を乱るを恐るればなり」
「信ずるべきものを信ずることを乱すのを恐れるために、上辺だけの口達者をも憎むのである。
(イエスのような虚言癖の口達者こそは、信仰に託すべき望み、信仰の先にあるものをも撹乱するのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句下・三七より)
自性は虚空であるが故に、あるいは絶対真理たる梵と一如であるが故に、清浄なものである。
しかし、人間の心身が必ずしも純粋な自性ばかりに律されているとも限らず、色声香味触法
といった外部からの受容によって大きな影響を被ることもある。それが時に人間自身の悪念や
悪思、悪言や悪行といった悪果として結実してしまうことがあるわけで、そこに道徳律(俗諦)
に根ざして紛れもなく「悪」と規定できる諸事物が生ずることもまた、確かな事実なのである。
過度に色欲をそそる異性、無制限な食欲を駆り立てる食物などは、それ自体が悪でなくても、
それを得ようとする側の人間の感情の焼け付きを生じさせて、以って妄念や妄言や妄動、
悪念や悪言や悪行へと走らせる原因になってしまう場合がある。もしも受容する人間の
側に十分な自制心があったり、「色声香味触法の一切は空である」といったような悟りが
あったならば、同様の受容によって妄念や妄動を生じさせるとも限らないわけで、そうである
限りにおいて、どこにも「悪」に相当する現象は生じていないことにもなるわけである。
権力犯罪聖書——通称聖書もまた、そのような「受容者に妄念妄動をけしかける種子(:=悪種)」の
一つだといえるが、犯罪聖書が他の悪種と違う点は、眼耳鼻舌身の五根に訴える五感(色声香味触)
の悪種ではなく、総合的な理念意志としてこそ受容される「法」の悪種、悪法である点だといえる。
悪法であるが故にこそ、五感に訴えかける即物的な悪種よりもその悪質さが捉えにくく、
過度に肉欲をそそる性風俗だとか、健康を損ねるほどに食欲を駆り立てるジャクフードだとかいった
ような、分かりやすい悪種に対すると同様な受容取り締まりの対象にしていくことはなかなか難しい。
ただ難しいだけでなく、悪法が世の中にもたらす害悪こそは突出して致命的なものでもあるために、
性風俗やジャンクフードを取り締まる程度の、生半な姿勢で取り締まれるものではないとも言える。
しかし、人間の心身が必ずしも純粋な自性ばかりに律されているとも限らず、色声香味触法
といった外部からの受容によって大きな影響を被ることもある。それが時に人間自身の悪念や
悪思、悪言や悪行といった悪果として結実してしまうことがあるわけで、そこに道徳律(俗諦)
に根ざして紛れもなく「悪」と規定できる諸事物が生ずることもまた、確かな事実なのである。
過度に色欲をそそる異性、無制限な食欲を駆り立てる食物などは、それ自体が悪でなくても、
それを得ようとする側の人間の感情の焼け付きを生じさせて、以って妄念や妄言や妄動、
悪念や悪言や悪行へと走らせる原因になってしまう場合がある。もしも受容する人間の
側に十分な自制心があったり、「色声香味触法の一切は空である」といったような悟りが
あったならば、同様の受容によって妄念や妄動を生じさせるとも限らないわけで、そうである
限りにおいて、どこにも「悪」に相当する現象は生じていないことにもなるわけである。
権力犯罪聖書——通称聖書もまた、そのような「受容者に妄念妄動をけしかける種子(:=悪種)」の
一つだといえるが、犯罪聖書が他の悪種と違う点は、眼耳鼻舌身の五根に訴える五感(色声香味触)
の悪種ではなく、総合的な理念意志としてこそ受容される「法」の悪種、悪法である点だといえる。
悪法であるが故にこそ、五感に訴えかける即物的な悪種よりもその悪質さが捉えにくく、
過度に肉欲をそそる性風俗だとか、健康を損ねるほどに食欲を駆り立てるジャクフードだとかいった
ような、分かりやすい悪種に対すると同様な受容取り締まりの対象にしていくことはなかなか難しい。
ただ難しいだけでなく、悪法が世の中にもたらす害悪こそは突出して致命的なものでもあるために、
性風俗やジャンクフードを取り締まる程度の、生半な姿勢で取り締まれるものではないとも言える。
権力犯罪聖書——通称聖書とは逆に、人々に善思善言善行を促す善法としての存在意義を持つのが、
他でもない権力道徳聖書——通称四書五経の記述なわけで、善法であるが故に悪法たる犯罪聖書とは
その記述内容がことごとく相反し、善法たる四書五経の実践に務める以上は、自動的に悪法たる
犯罪聖書の実践が滞り、以って悪思悪言悪行に及ぶこともできなくなるようになっている。
しかし、四書五経に記録されている道徳律もまた、善法とはいえ、「法」の内に入るものである。
実定法文至上主義は、それはそれで四書五経中の「左伝」昭公六年などで批判的に取り上げられている
ものだが、孔子や孟子がその主な把捉者として立ち回っている権力道徳律もまた、易学にも根ざした
普遍的な法則でもあるにしたって、一般的な観点から見た場合の「法」であるにも違いないのである。
「法治主義」というものは、どんな形を取るのであれ、作為の極みとなる。善法であれ悪法であれ
実定法であれ、法による統治支配を絶対化しようとしたならば、その作為の過剰さこそが破綻を招く
原因ともなる。悪法を排し、実定法を緩和し、善法を推進していくことが「最も優良な法の受容法」
ともなるが、さりとて法の受容が過剰すぎれば、それがどうしたって瓦解の原因ともなってしまうのである。
だから、色声香味触の五根だけでなく、第六根の法もまた、善悪実定の如何に関わらず、「その一切が
空である」というほどもの諦観を抱いて、法全般の受容に取り組むこともまた国家鎮護、天下平定の
ための重要な指針となる。それがまた、法の受容が悪果に結び付かないための叡知ともなるなのである。
「天の烝民を生める、物有りて則有り。民は之の彝に秉い、是の懿鄹を好めり」
「天がこの世に諸々の民を生じさせ、その物としての性質に即して規則をも生じさせた。
民はその本性に根ざして、純正な規則を守ることの威徳を好んだ。(『孟子』告子章句上・六で性善論の
論拠ともしている句。仁徳を人々は本性から好んでいるから、その実践が善因楽果をももたらすのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・大雅・蕩之什・烝民より)
他でもない権力道徳聖書——通称四書五経の記述なわけで、善法であるが故に悪法たる犯罪聖書とは
その記述内容がことごとく相反し、善法たる四書五経の実践に務める以上は、自動的に悪法たる
犯罪聖書の実践が滞り、以って悪思悪言悪行に及ぶこともできなくなるようになっている。
しかし、四書五経に記録されている道徳律もまた、善法とはいえ、「法」の内に入るものである。
実定法文至上主義は、それはそれで四書五経中の「左伝」昭公六年などで批判的に取り上げられている
ものだが、孔子や孟子がその主な把捉者として立ち回っている権力道徳律もまた、易学にも根ざした
普遍的な法則でもあるにしたって、一般的な観点から見た場合の「法」であるにも違いないのである。
「法治主義」というものは、どんな形を取るのであれ、作為の極みとなる。善法であれ悪法であれ
実定法であれ、法による統治支配を絶対化しようとしたならば、その作為の過剰さこそが破綻を招く
原因ともなる。悪法を排し、実定法を緩和し、善法を推進していくことが「最も優良な法の受容法」
ともなるが、さりとて法の受容が過剰すぎれば、それがどうしたって瓦解の原因ともなってしまうのである。
だから、色声香味触の五根だけでなく、第六根の法もまた、善悪実定の如何に関わらず、「その一切が
空である」というほどもの諦観を抱いて、法全般の受容に取り組むこともまた国家鎮護、天下平定の
ための重要な指針となる。それがまた、法の受容が悪果に結び付かないための叡知ともなるなのである。
「天の烝民を生める、物有りて則有り。民は之の彝に秉い、是の懿鄹を好めり」
「天がこの世に諸々の民を生じさせ、その物としての性質に即して規則をも生じさせた。
民はその本性に根ざして、純正な規則を守ることの威徳を好んだ。(『孟子』告子章句上・六で性善論の
論拠ともしている句。仁徳を人々は本性から好んでいるから、その実践が善因楽果をももたらすのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・大雅・蕩之什・烝民より)
随順するものが、主導するものの安全保障にかまけて驕り高ぶる状態というのは、
言ってみれば「カカア天下」であり、随順者である以上はしおらしく主導者の後を
追っていく「夫唱婦随」の状態と比べて、まことに不健全なものであるといえる。
随順者が驕り高ぶってまでいながら、主導者が無制限にその安全をも保障し続けて
やろうとする所に、大きなロスが生ずる。その端緒が欧米聖書圏における軍備過剰や、
綱渡り状態の経済政策だったりもするわけで、始めから夫唱婦随が確立されたままで、
女子供や小人がやりたい放題することなく君子の後を追うように努めていたならば、
そこまで経済や軍事を自壊級にまで煩雑化させる必要などもなかったのである。
陰陽不全のカカア天下状態、女子供や小人こそはやりたい放題できる状態——
それを今では「民主制」とも呼ぶ——を推進した挙句に、経済や軍事の規模が過剰に
肥大化した、のみならず、父権への甚だしい軽蔑が少子高齢化にも結び付き、国全体
としては男尊女卑の風潮を保っている中国やインドや中東諸国などに、人口面やその
内部構成の健全度などの面において、大きく水を開けられることともなってしまった。
女々しい信者の立場に立った、軽薄な記述ばかりが目立つ犯罪聖書などと違い、
四書五経の記述はどこまでも君子本位であり、女子供はおろか、小人(被支配階級)
の男の立場に立った記述すらもが、ほぼ皆無に等しい。その記述姿勢からしてすでに、
夫唱婦随を実現していくことを目的としているのであり、君子本位の記述だからと
いって、女子供や小人を全くの度外視にしていたりするわけでもないのである。
言ってみれば「カカア天下」であり、随順者である以上はしおらしく主導者の後を
追っていく「夫唱婦随」の状態と比べて、まことに不健全なものであるといえる。
随順者が驕り高ぶってまでいながら、主導者が無制限にその安全をも保障し続けて
やろうとする所に、大きなロスが生ずる。その端緒が欧米聖書圏における軍備過剰や、
綱渡り状態の経済政策だったりもするわけで、始めから夫唱婦随が確立されたままで、
女子供や小人がやりたい放題することなく君子の後を追うように努めていたならば、
そこまで経済や軍事を自壊級にまで煩雑化させる必要などもなかったのである。
陰陽不全のカカア天下状態、女子供や小人こそはやりたい放題できる状態——
それを今では「民主制」とも呼ぶ——を推進した挙句に、経済や軍事の規模が過剰に
肥大化した、のみならず、父権への甚だしい軽蔑が少子高齢化にも結び付き、国全体
としては男尊女卑の風潮を保っている中国やインドや中東諸国などに、人口面やその
内部構成の健全度などの面において、大きく水を開けられることともなってしまった。
女々しい信者の立場に立った、軽薄な記述ばかりが目立つ犯罪聖書などと違い、
四書五経の記述はどこまでも君子本位であり、女子供はおろか、小人(被支配階級)
の男の立場に立った記述すらもが、ほぼ皆無に等しい。その記述姿勢からしてすでに、
夫唱婦随を実現していくことを目的としているのであり、君子本位の記述だからと
いって、女子供や小人を全くの度外視にしていたりするわけでもないのである。
四書五経やその他諸々の漢籍(一部文学書などを除く)の、君子本位を貫く
記述姿勢こそはありのままに、社会規模での夫唱婦随の実現を企図したものである。
文学小説や諸々の洋学書のように、女子供や小人階級こそを主な読者層とし、
実際に女子供や小人こそを主人公としたような著述を心がけること自体がすでに、
世の中総出でのカカア天下状態の実現を企図したものであるということもまた言える。
女子供や小人を本位とする、よさげにいえば民主主義的、直言すれば
カカア天下的な書物の著述姿勢に権威を付与している最大級の存在こそは、
他でもない犯罪聖書であり、ギリシャ古典あたりがそれに次ぐ存在となっている。
多くの漢籍だけでなく、ヴェーダやウパニシャッドや仏典といったインド古典もまた、
バラモン階級や沙門階級が自分たちのために編み出したものであるため、上記のような
条件は満たしていない。イスラムのコーランやハディースもまた、一人前の軍政家でもあった
ムハンマドの口承記録やその敷衍であり、やはり為政本位の著述であることには変わりない。
世の中で最大級の実力を持つ君子を本位とした著述文化は、やはり中国古典に極まる。
一方、小人や女子供を本位とした著述文化は、やはりイスラエル以西の西洋に多い。
中国よりもさらに東方の日本では、もはや男が長々とした文章を書き溜めるまでもなく
速攻の実践に臨むことが主眼とされたため、君子本位の古典文学が別に多いということもないが、
著述に臨む以上はなるべく君子本位であろうとし、小人や女子供本位ではないほうがよい。
世界最高の女流作家である紫式部もまた、「史記」や「漢書」のような君子の事跡を主に記録した
大説を好んだというのだから、女子供だからといって君子本位の著述を遠ざけるべきでもない。
記述姿勢こそはありのままに、社会規模での夫唱婦随の実現を企図したものである。
文学小説や諸々の洋学書のように、女子供や小人階級こそを主な読者層とし、
実際に女子供や小人こそを主人公としたような著述を心がけること自体がすでに、
世の中総出でのカカア天下状態の実現を企図したものであるということもまた言える。
女子供や小人を本位とする、よさげにいえば民主主義的、直言すれば
カカア天下的な書物の著述姿勢に権威を付与している最大級の存在こそは、
他でもない犯罪聖書であり、ギリシャ古典あたりがそれに次ぐ存在となっている。
多くの漢籍だけでなく、ヴェーダやウパニシャッドや仏典といったインド古典もまた、
バラモン階級や沙門階級が自分たちのために編み出したものであるため、上記のような
条件は満たしていない。イスラムのコーランやハディースもまた、一人前の軍政家でもあった
ムハンマドの口承記録やその敷衍であり、やはり為政本位の著述であることには変わりない。
世の中で最大級の実力を持つ君子を本位とした著述文化は、やはり中国古典に極まる。
一方、小人や女子供を本位とした著述文化は、やはりイスラエル以西の西洋に多い。
中国よりもさらに東方の日本では、もはや男が長々とした文章を書き溜めるまでもなく
速攻の実践に臨むことが主眼とされたため、君子本位の古典文学が別に多いということもないが、
著述に臨む以上はなるべく君子本位であろうとし、小人や女子供本位ではないほうがよい。
世界最高の女流作家である紫式部もまた、「史記」や「漢書」のような君子の事跡を主に記録した
大説を好んだというのだから、女子供だからといって君子本位の著述を遠ざけるべきでもない。
「孔子曰く、似て非なる者を悪む。莠を悪むは其の苗を乱るを恐れればなり。佞を悪むは、其の義を乱るを恐れればなり。利口を
悪むは、其の信を乱るを恐れればなり鄭声を悪むは、其の楽を乱るを恐れればなり。紫を悪むは、其の朱を乱るを恐れればなり。
郷原を悪むは、其の徳を乱るを恐れればなり。君子は経に反るのみ。経を正せば則ち庶民興り、庶民興るれば斯ち邪慝なし」
「孔先生は言われた。『似て非なる類いのものをよく思わぬ。苗に似た雑草をよく思わないのは、穀類の苗を紛らわすことを
恐れるから。阿りの徒をよく思わないのは、道義を紛らわすのを恐れるから。口達者をよく思わないのは、信頼性を紛らわす
のを恐れるから。紫のような間色をよく思わないのは、赤のような原色を紛らわすのを恐れるから。世間知らずの偽善者を
よく思わないのは、仁徳を紛らわすのを恐れるから』 君子はこのように危うきをよく恐れて、本来の道に立ち返るのみである。
道が正されれば庶民までもがそれに倣って道徳を振興し、庶民までもが道徳を振興するぐらいだから、詐悪も起こらなくなる。
(君子がよく詐悪の害を恐れ憎むようにして、庶民もまたその姿を倣い、以って天下全土における詐悪の害もまた鎮まるのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句下・三七より)
悪むは、其の信を乱るを恐れればなり鄭声を悪むは、其の楽を乱るを恐れればなり。紫を悪むは、其の朱を乱るを恐れればなり。
郷原を悪むは、其の徳を乱るを恐れればなり。君子は経に反るのみ。経を正せば則ち庶民興り、庶民興るれば斯ち邪慝なし」
「孔先生は言われた。『似て非なる類いのものをよく思わぬ。苗に似た雑草をよく思わないのは、穀類の苗を紛らわすことを
恐れるから。阿りの徒をよく思わないのは、道義を紛らわすのを恐れるから。口達者をよく思わないのは、信頼性を紛らわす
のを恐れるから。紫のような間色をよく思わないのは、赤のような原色を紛らわすのを恐れるから。世間知らずの偽善者を
よく思わないのは、仁徳を紛らわすのを恐れるから』 君子はこのように危うきをよく恐れて、本来の道に立ち返るのみである。
道が正されれば庶民までもがそれに倣って道徳を振興し、庶民までもが道徳を振興するぐらいだから、詐悪も起こらなくなる。
(君子がよく詐悪の害を恐れ憎むようにして、庶民もまたその姿を倣い、以って天下全土における詐悪の害もまた鎮まるのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句下・三七より)
何かを敬う以上は、神仏よりも主君よりも、まず先に敬いの対象とすべき相手として、実の親がある。
(鬼籍の先祖を神仏とする場合にのみ、親への崇敬と神仏崇拝もまた一如となる)
その親に対する敬いを他者に対しても振り向けていく場合に、その敬いが最も着実な敬いとなる一方、
親や先祖への敬いを蔑ろにした所から試みられる敬いは、いかなるものであろうとも、虚構止まりとなる。
聖書圏において、神への信仰や敬いを欠くもの、それ即ちニヒリスト(虚無主義者)であり、
誰に対する崇敬も持たない無頼者の代名詞ともされている。これこそは、聖書信者が親や先祖への
敬いを蔑ろにしているのみならず、親や先祖への敬いなどは「始めから存在しないもの」
であるなどと、完全に思い込み尽くしてしまっている証拠であるといえる。
紀元前の西洋文化や、犯罪聖書におけるイエスらの暴言暴行を鑑みるに、キリスト信仰が蔓延する
以前の西洋において、それなりに親族先祖への崇敬を嗜む文化もまたあったように見受けられる。その上で、
実父の素性が定かでないイエスを「神の子」として祭り上げたり、キリスト信仰によって他の神仏への崇拝を
破壊するなどして、聖書信仰が親や先祖に対する崇敬の文化を人工的に破壊していった形跡が多々見られる。
ただ、それはもう2000年近くも前の話で、現今の聖書信者にとっては、自分たちの先祖が人工的に
親や先祖への崇敬を破棄して、あえて好き好んで聖書信仰だけに惑溺していったという史実に対する認識
すらもがもはや疎かとなっているから、「敬いといえば神への敬いが第一」「神への敬いを欠いた所にあるのは
ニヒリズムのみ」などというような、完全に間違った思い込みに凝り固まるまでに至ってしまっているのである。
(鬼籍の先祖を神仏とする場合にのみ、親への崇敬と神仏崇拝もまた一如となる)
その親に対する敬いを他者に対しても振り向けていく場合に、その敬いが最も着実な敬いとなる一方、
親や先祖への敬いを蔑ろにした所から試みられる敬いは、いかなるものであろうとも、虚構止まりとなる。
聖書圏において、神への信仰や敬いを欠くもの、それ即ちニヒリスト(虚無主義者)であり、
誰に対する崇敬も持たない無頼者の代名詞ともされている。これこそは、聖書信者が親や先祖への
敬いを蔑ろにしているのみならず、親や先祖への敬いなどは「始めから存在しないもの」
であるなどと、完全に思い込み尽くしてしまっている証拠であるといえる。
紀元前の西洋文化や、犯罪聖書におけるイエスらの暴言暴行を鑑みるに、キリスト信仰が蔓延する
以前の西洋において、それなりに親族先祖への崇敬を嗜む文化もまたあったように見受けられる。その上で、
実父の素性が定かでないイエスを「神の子」として祭り上げたり、キリスト信仰によって他の神仏への崇拝を
破壊するなどして、聖書信仰が親や先祖に対する崇敬の文化を人工的に破壊していった形跡が多々見られる。
ただ、それはもう2000年近くも前の話で、現今の聖書信者にとっては、自分たちの先祖が人工的に
親や先祖への崇敬を破棄して、あえて好き好んで聖書信仰だけに惑溺していったという史実に対する認識
すらもがもはや疎かとなっているから、「敬いといえば神への敬いが第一」「神への敬いを欠いた所にあるのは
ニヒリズムのみ」などというような、完全に間違った思い込みに凝り固まるまでに至ってしまっているのである。
聖書の神のような、我が家の祖霊でもない雑神は、仮りに敬うに値する神である
としたところで、優先順位でいえば「四番目以降」に敬うべき神であるといえる。
まず一番目に敬うべきなのが、上にも書いたとおり実際の親である。
また、祖霊を祀った神仏に限って親とも順位が等しく、同率一位であるといえる。
親と祖霊の次、三番目に敬うべきなのが、自国の主君である。
これまた敬うべき度合いでは親並みであるといえるが、親族に対する親密さを帯びた敬意こそを主君にも援用して
振り向けるべきであるから、親や祖霊を敬ってから、その敬意こそを主君にも振り向けるようにすべきだといえる。
親と、祖霊と、主君の次に敬うべきなのが、上天名山大川神仙その他、諸々の雑多な神仏であり、
聖書の神も入れるとするならここに入る(無論、邪神だからここにすら入れてはならないともいえる)。
これらの神仏は崇敬対象としての優先順位が低いのみならず、場合によっては「まだ敬ってはいけない」という場合
すらある。始皇帝のように中国一帯での暴政を繰り返しながら、中国一の名山である泰山の神を我流の礼法で祭ろう
としたら、暴風雨が吹き荒れて台無しになったという逸話もあるように(「史記」封禅書)、自分にそれらの神仏を
祭るだけの身分なり資格なりが整ってからでないと、まだ崇敬の対象にしてはいけないという場合すらもがある。
聖書の神が邪神であるのは、優先順位がより高い親や祖霊や主君への敬いをも蔑ろにした、
虚構の敬いこそを信者に強要するからである。その信仰を欠いた所に、元信者が人工的なニヒリズムを
患うのみならず、その信仰に基づく神への敬い自体が、ありのままに虚構の敬いでしかなくもある。
「虚構だ」と断じられるのも、本当に大切なものへの敬いを蔑ろにしてから講じられる聖書信者の敬いが、
本当に大切なものへの敬いと比べて、どこまでも薄っぺらいもの止まりでしかないからである。
としたところで、優先順位でいえば「四番目以降」に敬うべき神であるといえる。
まず一番目に敬うべきなのが、上にも書いたとおり実際の親である。
また、祖霊を祀った神仏に限って親とも順位が等しく、同率一位であるといえる。
親と祖霊の次、三番目に敬うべきなのが、自国の主君である。
これまた敬うべき度合いでは親並みであるといえるが、親族に対する親密さを帯びた敬意こそを主君にも援用して
振り向けるべきであるから、親や祖霊を敬ってから、その敬意こそを主君にも振り向けるようにすべきだといえる。
親と、祖霊と、主君の次に敬うべきなのが、上天名山大川神仙その他、諸々の雑多な神仏であり、
聖書の神も入れるとするならここに入る(無論、邪神だからここにすら入れてはならないともいえる)。
これらの神仏は崇敬対象としての優先順位が低いのみならず、場合によっては「まだ敬ってはいけない」という場合
すらある。始皇帝のように中国一帯での暴政を繰り返しながら、中国一の名山である泰山の神を我流の礼法で祭ろう
としたら、暴風雨が吹き荒れて台無しになったという逸話もあるように(「史記」封禅書)、自分にそれらの神仏を
祭るだけの身分なり資格なりが整ってからでないと、まだ崇敬の対象にしてはいけないという場合すらもがある。
聖書の神が邪神であるのは、優先順位がより高い親や祖霊や主君への敬いをも蔑ろにした、
虚構の敬いこそを信者に強要するからである。その信仰を欠いた所に、元信者が人工的なニヒリズムを
患うのみならず、その信仰に基づく神への敬い自体が、ありのままに虚構の敬いでしかなくもある。
「虚構だ」と断じられるのも、本当に大切なものへの敬いを蔑ろにしてから講じられる聖書信者の敬いが、
本当に大切なものへの敬いと比べて、どこまでも薄っぺらいもの止まりでしかないからである。
「君に事えては、其の事うるを敬して其の食を後にす」
「主君に仕える場合には、仕える以上はまず敬うことに務め、褒美を頂くことなどは後回しにする。
(君父の尊位に根ざした仕官にかけての敬いこそは、まず褒美ありきな聖書信仰の敬いなどよりも確実に誠実である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・衛霊公第十五・三八より)
「主君に仕える場合には、仕える以上はまず敬うことに務め、褒美を頂くことなどは後回しにする。
(君父の尊位に根ざした仕官にかけての敬いこそは、まず褒美ありきな聖書信仰の敬いなどよりも確実に誠実である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・衛霊公第十五・三八より)
聞いても聡からず、言っても実に欠けるばかりなら、
そんな耳や口は始めから機能していないほうがマシですらある。
母子家庭育ちの妾腹の私生児としての、自らの賤しさを心底恥じていたから、
孔子は郷里では唖オシも同然の拙い物言いしかしなかったという。それでいて、
逆境を乗り越えるための猛勉強によって培われた言行の丹精豊かさが、朝廷
等の公けの場では大いに発揮され、その姿があまりにも悠然としていたために、
諸侯が孔子と同席するのを躊躇ったほどであったという。(「韓非子」より)
人の言うことを聞いてよく学ぶ従順な耳を持ち、時と場合とを選んで
発すべき言葉を適格に発する口とが備わるのなら、それに越したことはない。
逆に、聞いても何も学ぶことがなく、いくらでも聞いたことを捻じ曲げてしまう
勝手な耳を持ち、人を欺くような虚言ばかりを発する口を得るぐらいなら、
そんな耳や口はないほうがマシである。もしもそうであったりするのなら、
郷里で唖のように振る舞っていた孔子のあり方こそを見習うべきだといえる。
ただ聴力がある、話術に長けるというだけでは、善いとも悪いとも言えない。
聞き分けの悪い耳や虚言癖持ちの口が、かえって度し難いということもあるし、
実際に盗聴や虚偽のような犯罪行為にすら発展し得るもの。それは聴力も話術も
持たなければ犯しえない罪なわけだから、聴力や話術があればこその宿命だといえる。
そんな耳や口は始めから機能していないほうがマシですらある。
母子家庭育ちの妾腹の私生児としての、自らの賤しさを心底恥じていたから、
孔子は郷里では唖オシも同然の拙い物言いしかしなかったという。それでいて、
逆境を乗り越えるための猛勉強によって培われた言行の丹精豊かさが、朝廷
等の公けの場では大いに発揮され、その姿があまりにも悠然としていたために、
諸侯が孔子と同席するのを躊躇ったほどであったという。(「韓非子」より)
人の言うことを聞いてよく学ぶ従順な耳を持ち、時と場合とを選んで
発すべき言葉を適格に発する口とが備わるのなら、それに越したことはない。
逆に、聞いても何も学ぶことがなく、いくらでも聞いたことを捻じ曲げてしまう
勝手な耳を持ち、人を欺くような虚言ばかりを発する口を得るぐらいなら、
そんな耳や口はないほうがマシである。もしもそうであったりするのなら、
郷里で唖のように振る舞っていた孔子のあり方こそを見習うべきだといえる。
ただ聴力がある、話術に長けるというだけでは、善いとも悪いとも言えない。
聞き分けの悪い耳や虚言癖持ちの口が、かえって度し難いということもあるし、
実際に盗聴や虚偽のような犯罪行為にすら発展し得るもの。それは聴力も話術も
持たなければ犯しえない罪なわけだから、聴力や話術があればこその宿命だといえる。
あらゆる道徳上の教条のうちでも、
「礼にあらざれば聴くことなかれ。礼にあらざれば言うことなかれ(顔淵第十二・一)」
という教条ほどにも、現代社会において著しく蔑ろにされている教条も他に無い。
ただ蔑ろにされているのみならず、蔑ろにすることが少しも悪いことだとすら捉えられておらず、
むしろとにかく何でも聞いて、何でも言うことこそは正義であるとすら見なされている感がある。
聞くべきでないことを聞かなかった、言うべきでないことを言わなかったがための
好影響というのは、色々と聞いたり言ったりした場合の影響ほどには、分かりやすくない。
水面に石を投げて波紋を立てるよりも、始めから石を投げないでいることのほうが、
その結果どうなったかが分かりにくいのも当然なことで、なおのこと、その先にある
平穏無事の好影響を察せるか否かに、石投げを踏み止まる決断もまた左右されるのである。
好影響は、確かにあるのである。未だ無闇に耳聡く、歯に衣着せないでいる内からそれを
察するのは難しくても、耳と口との悪用を取りやめることの功徳は、確かな結果となって現れる。
せいぜいその瞬間まで、自分たちが耳口の悪用を踏み止まったことを、よく自覚しておくことだ。
「礼にあらざれば聴くことなかれ。礼にあらざれば言うことなかれ(顔淵第十二・一)」
という教条ほどにも、現代社会において著しく蔑ろにされている教条も他に無い。
ただ蔑ろにされているのみならず、蔑ろにすることが少しも悪いことだとすら捉えられておらず、
むしろとにかく何でも聞いて、何でも言うことこそは正義であるとすら見なされている感がある。
聞くべきでないことを聞かなかった、言うべきでないことを言わなかったがための
好影響というのは、色々と聞いたり言ったりした場合の影響ほどには、分かりやすくない。
水面に石を投げて波紋を立てるよりも、始めから石を投げないでいることのほうが、
その結果どうなったかが分かりにくいのも当然なことで、なおのこと、その先にある
平穏無事の好影響を察せるか否かに、石投げを踏み止まる決断もまた左右されるのである。
好影響は、確かにあるのである。未だ無闇に耳聡く、歯に衣着せないでいる内からそれを
察するのは難しくても、耳と口との悪用を取りやめることの功徳は、確かな結果となって現れる。
せいぜいその瞬間まで、自分たちが耳口の悪用を踏み止まったことを、よく自覚しておくことだ。
「戎を成すとも退けず、飢えを成すとも遂んぜられず。
曾ち我が蟄御も、僭僭として日びに瘁める。凡百の君子も、
肯て用て訊める莫し。聴言には則ち答え、譖言には則ち退く。(ここから既出)
哀しきかな言るに能わず、匪れ舌より是れ出ずれば、維ち躬に是れ瘁しむ。
しかも能言のやからの、巧言の流るるが如きは、躬を俾て休きに處らしむ」
「戦乱が起これば平定することもできず、飢饉が起きれば安んずることもできず。
朝廷の内臣たちも暴慢にかられて頭をおかしくしているばかり。中位の官吏たちも
上司の腐敗をよく諌めることができないのは、おもねる言葉は聞き入れられても、
耳に痛い忠言は即座に退けられるから。哀しきかな、正しい言葉を口にするほど
わが身を貶める結果となってしまう現状は。それでいて、能弁に長ける連中どもが
有害無益な巧言によって上に取り入ることで、甘い汁を吸っているとまで来ている。
(聴力や話術の悪用が、戦乱や飢餓の放置に直結していることをよく明示している)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・小雅・祈父之什・雨無正より)
曾ち我が蟄御も、僭僭として日びに瘁める。凡百の君子も、
肯て用て訊める莫し。聴言には則ち答え、譖言には則ち退く。(ここから既出)
哀しきかな言るに能わず、匪れ舌より是れ出ずれば、維ち躬に是れ瘁しむ。
しかも能言のやからの、巧言の流るるが如きは、躬を俾て休きに處らしむ」
「戦乱が起これば平定することもできず、飢饉が起きれば安んずることもできず。
朝廷の内臣たちも暴慢にかられて頭をおかしくしているばかり。中位の官吏たちも
上司の腐敗をよく諌めることができないのは、おもねる言葉は聞き入れられても、
耳に痛い忠言は即座に退けられるから。哀しきかな、正しい言葉を口にするほど
わが身を貶める結果となってしまう現状は。それでいて、能弁に長ける連中どもが
有害無益な巧言によって上に取り入ることで、甘い汁を吸っているとまで来ている。
(聴力や話術の悪用が、戦乱や飢餓の放置に直結していることをよく明示している)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・小雅・祈父之什・雨無正より)
善行の規範としての権力道徳聖書——通称四書五経の記述が完璧に磐石だから、
その四書五経と真逆の記述を寄せ集めているだけでしかない
権力犯罪聖書——通称聖書もまた、悪行の規範としては完璧に磐石なものである。
天人修羅の三善趣と共に、地獄餓鬼畜生の三悪趣が六道の内に包含されているように、
人が善行に反する悪行によって、一定の生活規範を保てることもまた一つの真理である。
天道や人道に即して磐石な人生を送れるほどにも、餓鬼道や畜生道に即して磐石な
人生を送ることが実際、人間には可能である。ただ、三善趣(特に人天の二道)と
三悪趣が一ところで共存や共栄することだけは真理に即して不可能なことであり、
どちらかが威勢を蓄えたぶんだけ、もう一方の威勢は必ず衰えることになる。
実際、聖書信仰によって世界中が悪逆非道の渦中に巻き込まれた結果、
既存の教学文化のうちでも、善行を旨とするものであればあるほど、表社会からの
雲隠れを決め込むこととなってしまった。儒学や大乗仏教の実践はほぼ完璧に廃れ、
神道や道教やヒンズー教も、その品質を大幅に低下させてしまっている。修羅道に
勧善懲悪の情緒を加味した日本の武道も、権威を失墜させてその多くが形骸化し、
スポーツ化で高尚な精神性を失った流派ほど幅を利かせるようにもなっている。
(そういう形骸的な武道ほど、実際、勧善懲悪のために善用することも困難なのである)
ただ衰退しているというばかりでなく、確信的に隠退を決め込んでいる流派もまた
いくらかはあるはずで、そこには右往左往するような優柔不断さも全くない。ただ、
悪逆非道によって世界を侵略し尽くそうとする不埒者などには決して教授してやる
こともない、独自の秘伝や密法をひたすら温存していくことにのみ徹しているのである。
その四書五経と真逆の記述を寄せ集めているだけでしかない
権力犯罪聖書——通称聖書もまた、悪行の規範としては完璧に磐石なものである。
天人修羅の三善趣と共に、地獄餓鬼畜生の三悪趣が六道の内に包含されているように、
人が善行に反する悪行によって、一定の生活規範を保てることもまた一つの真理である。
天道や人道に即して磐石な人生を送れるほどにも、餓鬼道や畜生道に即して磐石な
人生を送ることが実際、人間には可能である。ただ、三善趣(特に人天の二道)と
三悪趣が一ところで共存や共栄することだけは真理に即して不可能なことであり、
どちらかが威勢を蓄えたぶんだけ、もう一方の威勢は必ず衰えることになる。
実際、聖書信仰によって世界中が悪逆非道の渦中に巻き込まれた結果、
既存の教学文化のうちでも、善行を旨とするものであればあるほど、表社会からの
雲隠れを決め込むこととなってしまった。儒学や大乗仏教の実践はほぼ完璧に廃れ、
神道や道教やヒンズー教も、その品質を大幅に低下させてしまっている。修羅道に
勧善懲悪の情緒を加味した日本の武道も、権威を失墜させてその多くが形骸化し、
スポーツ化で高尚な精神性を失った流派ほど幅を利かせるようにもなっている。
(そういう形骸的な武道ほど、実際、勧善懲悪のために善用することも困難なのである)
ただ衰退しているというばかりでなく、確信的に隠退を決め込んでいる流派もまた
いくらかはあるはずで、そこには右往左往するような優柔不断さも全くない。ただ、
悪逆非道によって世界を侵略し尽くそうとする不埒者などには決して教授してやる
こともない、独自の秘伝や密法をひたすら温存していくことにのみ徹しているのである。
人天こそは勇躍の機会を得る、浄土が仏の加護を得ることはあっても、鬼畜の天下たる
穢土が仏や本物の神の加護を得ることもないので、悪逆非道にまみれた穢土こそは、
いつかは必ず自業自得で潰える運命にある。穢土が潰え去り、鬼畜が滅び尽くした後に
また善趣の文化が息を吹き返し、穢土では隠し通されていた諸々の秘法までもが開陳
されていくこととなる。その神々しき文化興隆に一切協賛することができないことが、
穢土こそを我が世としていた鬼畜どもに対する、最大級の罰ともなるのである。
むしろ知らないでいたほうがマシだったような、浅知恵悪知恵ばかりを貪った挙句に
自業自得で滅亡し、真に価値ある知恵や、それに根ざした文化が花開くときには
もはや自分たち自身がこの世にいない。これ程もの不幸が、他にあるだろうか?
「孟子斉を去りて、休に居る。公孫丑問うて曰く、仕えて而も禄を受けざるは、古えの道か。曰く、
非なり。崇に於いて吾れ王に見えるを得るも、退きて去るの志し有り。変るを欲せず、故に受けざるなり」
「孟先生はしばらく滞在していた斉国を去って、休という場所に居た。門弟の公孫丑が『先生は斉国で
客卿としての待遇に与りましたのに、俸禄も受けずに立ち去ってしまいました。これは古の道でしょうか』
先生『そうではない。私は斉国の崇という地で初めて王に謁見したが、それ以来私は色々な献言を尽くしてきた。
しかしその言葉はどれも聞き入れられなかったので、私も退役する志しを固めた。まるで仕事を果たしたかの
ように自他を偽りたくなかったので、俸禄も受けなかったのだ』(孟子が、俸禄を得たからには死兵
とすらなって働く食客風情などとは、明らかに一線を引いていたことがうかがえる逸話にあたる。
恵みを得られる得られないなどという打算にすら動かされない、確かな信念があったのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・公孫丑章句下・一四より)
穢土が仏や本物の神の加護を得ることもないので、悪逆非道にまみれた穢土こそは、
いつかは必ず自業自得で潰える運命にある。穢土が潰え去り、鬼畜が滅び尽くした後に
また善趣の文化が息を吹き返し、穢土では隠し通されていた諸々の秘法までもが開陳
されていくこととなる。その神々しき文化興隆に一切協賛することができないことが、
穢土こそを我が世としていた鬼畜どもに対する、最大級の罰ともなるのである。
むしろ知らないでいたほうがマシだったような、浅知恵悪知恵ばかりを貪った挙句に
自業自得で滅亡し、真に価値ある知恵や、それに根ざした文化が花開くときには
もはや自分たち自身がこの世にいない。これ程もの不幸が、他にあるだろうか?
「孟子斉を去りて、休に居る。公孫丑問うて曰く、仕えて而も禄を受けざるは、古えの道か。曰く、
非なり。崇に於いて吾れ王に見えるを得るも、退きて去るの志し有り。変るを欲せず、故に受けざるなり」
「孟先生はしばらく滞在していた斉国を去って、休という場所に居た。門弟の公孫丑が『先生は斉国で
客卿としての待遇に与りましたのに、俸禄も受けずに立ち去ってしまいました。これは古の道でしょうか』
先生『そうではない。私は斉国の崇という地で初めて王に謁見したが、それ以来私は色々な献言を尽くしてきた。
しかしその言葉はどれも聞き入れられなかったので、私も退役する志しを固めた。まるで仕事を果たしたかの
ように自他を偽りたくなかったので、俸禄も受けなかったのだ』(孟子が、俸禄を得たからには死兵
とすらなって働く食客風情などとは、明らかに一線を引いていたことがうかがえる逸話にあたる。
恵みを得られる得られないなどという打算にすら動かされない、確かな信念があったのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・公孫丑章句下・一四より)
罪障は、それを脳が把捉しているといないとに関わらず、
相応の贖罪に基づくのでなければ、消えることも減ることもない。
カルト信仰の酩酊によって罪障の把捉を完全に疎かにしたままでいられた所で、
最悪、人類滅亡級の悪因苦果にまで結実する罪障のほうは、着実に肥大化していくのみである。
罪を犯した以上は、自らがその罪を相応の罰によって償うのみである。
宗教信仰やその実践などは、罪障を十分に抑制できてから初めて嗜むべきもので、まだ自分が
罪障まみれの内から、逃避目的の宗教信仰などに走ることは、どこまでも卑劣なことでしかない。
卑劣なことだから、罪障の肥大化からなる致命的な規模の悪因苦果もまた避けられるものではない。
大きな罪を犯したままでいるというのなら、どんな宗教信仰やその実践に務めること以上にも、
社会的に公正な手続きに即して罪を償うことを優先すべきである。「罪を犯す」という
行為自体が最強度に俗物の所業であり、高尚な理念など共にある資格のないものであればこそ、
社会的な処罰というしごく卑俗な手段によって対処するのでなければ、誠実さを保てない。
犯罪風情を神なり高尚な理念なりによってどうにかしようとすること自体が、不誠実の至りである。
相応の贖罪に基づくのでなければ、消えることも減ることもない。
カルト信仰の酩酊によって罪障の把捉を完全に疎かにしたままでいられた所で、
最悪、人類滅亡級の悪因苦果にまで結実する罪障のほうは、着実に肥大化していくのみである。
罪を犯した以上は、自らがその罪を相応の罰によって償うのみである。
宗教信仰やその実践などは、罪障を十分に抑制できてから初めて嗜むべきもので、まだ自分が
罪障まみれの内から、逃避目的の宗教信仰などに走ることは、どこまでも卑劣なことでしかない。
卑劣なことだから、罪障の肥大化からなる致命的な規模の悪因苦果もまた避けられるものではない。
大きな罪を犯したままでいるというのなら、どんな宗教信仰やその実践に務めること以上にも、
社会的に公正な手続きに即して罪を償うことを優先すべきである。「罪を犯す」という
行為自体が最強度に俗物の所業であり、高尚な理念など共にある資格のないものであればこそ、
社会的な処罰というしごく卑俗な手段によって対処するのでなければ、誠実さを保てない。
犯罪風情を神なり高尚な理念なりによってどうにかしようとすること自体が、不誠実の至りである。
罪を犯しました、じゃあ刑罰を受けましょう、それら全てが卑俗の極みに当たる現象であり、
特定して「神聖さ」などを一貫して付与してはならない事象にあたる。非俗であることがイヤだ
ってんなら、始めから罪を犯したりもしないでいればいいだけの話なのであり、犯罪という卑俗の
極みのような所業に及んでおいて、その先に自分自身への刑罰以外の、神聖な何ものかを期待しよう
とすること自体、筋が通っていない。聖と俗のけじめを付けていない、みそくそな態度だといえる。
だから、罪を犯したものが十分な贖罪も果たさずに、罪障から眼を背けるための信仰やその実践を
促すような信教の正当性は認められないのであり、仮にあったとした所で、邪教と見なす他はない。
そういう教義を持つ信教である以上は、千年以上の歴史を持つ教派であろうとも、認められはしない。
世界規模での宗教信仰の是正を図るとするならば、必ずそう結論付けられる以外に余地はない。
「言れ師氏に告げらる、言れ帰せよと告げらる。いざ我が私を汚せん、
いざ我が衣を澣がん。害れか澣ぎ害れか否とし、帰して父母を寧んぜん」
「教育係の女官に、『もう嫁いでよい』と告げられた。心身の汚れを洗い落とし、
衣服もすすぎ洗いして奇麗にする。汚濁を漱いで二度とまとわり付かないようにし、
嫁いで従順な妻となり、故郷の父母たちをも安心させたい。(行為能力も子供並みに
制限されている封建時代の女が、嫁いで従順な妻となるための用意として浄心があった。
莫大な行為能力を掌握する大人の男が、浄心ばかりで全てを済ませられるはずもない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・周南・葛覃より)
特定して「神聖さ」などを一貫して付与してはならない事象にあたる。非俗であることがイヤだ
ってんなら、始めから罪を犯したりもしないでいればいいだけの話なのであり、犯罪という卑俗の
極みのような所業に及んでおいて、その先に自分自身への刑罰以外の、神聖な何ものかを期待しよう
とすること自体、筋が通っていない。聖と俗のけじめを付けていない、みそくそな態度だといえる。
だから、罪を犯したものが十分な贖罪も果たさずに、罪障から眼を背けるための信仰やその実践を
促すような信教の正当性は認められないのであり、仮にあったとした所で、邪教と見なす他はない。
そういう教義を持つ信教である以上は、千年以上の歴史を持つ教派であろうとも、認められはしない。
世界規模での宗教信仰の是正を図るとするならば、必ずそう結論付けられる以外に余地はない。
「言れ師氏に告げらる、言れ帰せよと告げらる。いざ我が私を汚せん、
いざ我が衣を澣がん。害れか澣ぎ害れか否とし、帰して父母を寧んぜん」
「教育係の女官に、『もう嫁いでよい』と告げられた。心身の汚れを洗い落とし、
衣服もすすぎ洗いして奇麗にする。汚濁を漱いで二度とまとわり付かないようにし、
嫁いで従順な妻となり、故郷の父母たちをも安心させたい。(行為能力も子供並みに
制限されている封建時代の女が、嫁いで従順な妻となるための用意として浄心があった。
莫大な行為能力を掌握する大人の男が、浄心ばかりで全てを済ませられるはずもない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・周南・葛覃より)
 「上に好む者あれば、下に必ず焉れより甚だしき者あり。
「上に好む者あれば、下に必ず焉れより甚だしき者あり。 君子の徳は風なり、小人の徳は草なり。草は之れに風を加うれば、必ず偃す」
「上に立つ者が好むものは、必ず下の者もまたそれ以上に好むものである。
たとえば支配者が好む徳が風であるとすれば、被支配者が好む徳は草とでも
言ったようなもので、草はこれに風を加えれば、必ず伏せるのである」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・滕文公章句上・二より)
カルト信仰なり、「天は人の上に人を作らず」云々の民権思想なりによって
「草に吹く風」としての支配者の存在性が名目上は覆い隠されるということがある。
それでもやはり、一定以上に大規模な社会における支配構造というのは改変できないもので、
必ずどこかに、庶民の生殺与奪の権限をも一身に背負った支配者が生ずるものである。
その支配者が表向きには姿を隠して、自らの動向をいちいち衆目によって審査されずにも
済むままでいたならば、それこそ真の支配者が表に出る場合以上もの腐敗を招くわけで、
誰からの目付けも受けることがないにことかけての放辟邪侈にも及ぶのである。
そして、いくら自分たちが支配者であることを隠し通そうとも、実質支配者である者が
好き好む性向はその支配対象にも落とし込まれ、支配者が執拗に財を好むようであれば、
被支配者もまた執拗に財を好むようになる。他者から利益を強奪してでも自分たちだけが
私利私欲を満たそうと支配者がしたならば、その性向もまた一般庶民にまで落とし込まれて、
誰といわず財物を奪い合うことが常套と化した乱世をも招いてしまうことになるのである。
被支配者もそれに倣って放辟邪侈を好もうとする。名目上は「草の上に吹く風」が
隠されているものだから、被支配者は自分たちの意思で放辟邪侈を好き好んで
いるかのようにすら思い込んでしまっているが、実際には支配者の悪癖を無意識に
見習った結果として、自分たちまでもが無制限に放辟邪侈をも好むようになっている。
まず、「それが自分たちの自由意思によって選択したことだ」などという思い込みを
衆生から引き剥がすために、衆目からはひた隠された状態のままでいる真の支配者の
存在をも公けにして、民衆の悪癖好みも所詮は支配者に倣ったものでしかなかったのだ
ということを思い知らせる。それによって民衆たち自身の罪は相当に軽減されると共に、
所詮は風になびく草でしかあり得ない、被支配者としての自分たちの矮小までもが思い
知らされる。その上で、素性を公けにしながら浄行を心がけていく支配者の姿を衆生にも
見習わせていくようにして、自分たちまでもが積極的な浄行に励んでいくように促すのである。
支配者の素性を公開することが恐ろしいのも、到底人々にその行いを見習わせるにも値しない
暴君然とした支配者である場合に限ってのことであり、それこそ本人たち自身の死後にでも
公開するしかなかったりすらし兼ねない。自らの行いを広く衆生に見せ付けても恐れる所が
ないぐらいに浄行に努めている支配者であればこそ、確信的に自らの徳によって、草である
衆生たちをなびかせることもできる。所詮は、いつでも草の上に風は吹いているのであるにしろ。
「迅雷風烈には、必ず変ず」
「(孔先生は)ひどい雷や暴風が巻き起これば、必ず態度を変じて居住まいを正された。
(雷や暴風雨に巻き込まれての無駄な危害を被らないため。
またこのような落ち着いた姿こそを人々に見習わせるため)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・郷党第十・二一より)
「仁遠からんや。我れ仁を欲すれば、斯に仁至る(既出)」
「仁は得がたいものだろうか。もし自分から仁を欲したなら、仁はすぐに得られるだろうさ」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・述而第七・二九より)
カルト信仰が、虚言癖や奇行癖を伴うような著しい精神異常を原動力として嗜まれるのに対し、
仁徳はむしろ、そのような精神異常を徹底して排除した所にある、まっさらな正気によって自得される。
精神異常を来たした状態で仁徳は会得できないし、正気によってはカルト信仰に没入することもない。
故に、仁徳の会得とカルト信仰への没入は互いに相容れず、両者を兼修することも絶対にできない。
仁徳を会得した状態と、カルト信仰に没入した状態と、いずれも住心が磐石である点では共通する。
片や浩然の気に根ざして愚童持斎心に安住し、片や誤謬信仰の酩酊に根ざして異生羝羊心に安住する。
そこに安住することに健全なすがすがしさや、無制限な快楽が伴うからこそ永く安住することが出来る。
今まで安住していたカルト信仰状態を卒業するのであっても、自力他力のいずれによるのであれ、
仁徳の会得と共に生きるのであれば、今まで並みかそれ以上の心の安楽と共に生きられる。ただ、
まるでカルト信仰に没入していくようにして、仁徳を会得することが不可能であるのは、上記の通り。
カルト信仰に陥る原因となった精神異常はむしろ払拭して、正気を取り戻したところでこそ仁徳は
得られるものであり、仁徳を得たからこその安楽もまた、正気と共にこそ得られるものなのである。
「仁は得がたいものだろうか。もし自分から仁を欲したなら、仁はすぐに得られるだろうさ」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・述而第七・二九より)
カルト信仰が、虚言癖や奇行癖を伴うような著しい精神異常を原動力として嗜まれるのに対し、
仁徳はむしろ、そのような精神異常を徹底して排除した所にある、まっさらな正気によって自得される。
精神異常を来たした状態で仁徳は会得できないし、正気によってはカルト信仰に没入することもない。
故に、仁徳の会得とカルト信仰への没入は互いに相容れず、両者を兼修することも絶対にできない。
仁徳を会得した状態と、カルト信仰に没入した状態と、いずれも住心が磐石である点では共通する。
片や浩然の気に根ざして愚童持斎心に安住し、片や誤謬信仰の酩酊に根ざして異生羝羊心に安住する。
そこに安住することに健全なすがすがしさや、無制限な快楽が伴うからこそ永く安住することが出来る。
今まで安住していたカルト信仰状態を卒業するのであっても、自力他力のいずれによるのであれ、
仁徳の会得と共に生きるのであれば、今まで並みかそれ以上の心の安楽と共に生きられる。ただ、
まるでカルト信仰に没入していくようにして、仁徳を会得することが不可能であるのは、上記の通り。
カルト信仰に陥る原因となった精神異常はむしろ払拭して、正気を取り戻したところでこそ仁徳は
得られるものであり、仁徳を得たからこその安楽もまた、正気と共にこそ得られるものなのである。
誰かに導かれてではなく、自ら進んで欲することでこそ、仁徳は得られる。
欲する際に外的影響などを介していないほうが、仁徳の会得にかけては確実性が高い。
まず自主的に仁徳を得て、それから忠臣孝養、睦友子愛に神仏への崇敬といった、他者との関わり
も兼ねた仁行に努めていく。仁行徳行のほとんど全てが「世のため人のため」でもあればこそ、
仁徳を会得すること自体は徹底して純粋な自己選択に依るべきである。それでこそ、
自らが何に対しても絶対服従である奴隷的存在となることなどとも一線が引けるのだから。
根本の信仰の部分に、確固たる自己や自己選択が存在しないから、その反動で聖書圏の人間も
極端な個人主義に走ってしまった。信仰すら、そもそも精神異常によって否応なく陥ったものであり、
何一つとして自主性によることなく右往左往させられ続けることこそが信仰によって徹底されたから、
信教を一定以上に劣後する風潮が盛り上がり始めた近世以降には、極端な個人主義にも触れきった。
だからこそ、「世のため人のため」を旨とする仁徳などに帰服することも恐ろしかろうて、
そもそも仁徳は帰服するものではなく自得するものであり、しかも自らの完全なる自主性によって
欲した結果、至るものである。だからこそ心置きなく「世のため人のため」を標榜もできるのだから、
仁徳こそは、その根本の部分に至上にして健全なる個人主義を備えているのだとすら言える。
「行くも之れを使むる或り、止まるも之れを尼むる或り。行くも止まるも、人の能くする所に非ざるなり」
「行くこともそれなりの命運に基づくし、止まることもそれなりの命運に即している。
行くことも止まることも、誰かが作為でどうにかできることではない。(全ての選択は
天命に基づくといえなくもないが、その場合にも、誰かの作為の普遍性などは認められない。
孟子が、天命論に限っては無為自然論者でもあることを示唆した記録ともなっている」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・梁恵王章句下・一六より)
欲する際に外的影響などを介していないほうが、仁徳の会得にかけては確実性が高い。
まず自主的に仁徳を得て、それから忠臣孝養、睦友子愛に神仏への崇敬といった、他者との関わり
も兼ねた仁行に努めていく。仁行徳行のほとんど全てが「世のため人のため」でもあればこそ、
仁徳を会得すること自体は徹底して純粋な自己選択に依るべきである。それでこそ、
自らが何に対しても絶対服従である奴隷的存在となることなどとも一線が引けるのだから。
根本の信仰の部分に、確固たる自己や自己選択が存在しないから、その反動で聖書圏の人間も
極端な個人主義に走ってしまった。信仰すら、そもそも精神異常によって否応なく陥ったものであり、
何一つとして自主性によることなく右往左往させられ続けることこそが信仰によって徹底されたから、
信教を一定以上に劣後する風潮が盛り上がり始めた近世以降には、極端な個人主義にも触れきった。
だからこそ、「世のため人のため」を旨とする仁徳などに帰服することも恐ろしかろうて、
そもそも仁徳は帰服するものではなく自得するものであり、しかも自らの完全なる自主性によって
欲した結果、至るものである。だからこそ心置きなく「世のため人のため」を標榜もできるのだから、
仁徳こそは、その根本の部分に至上にして健全なる個人主義を備えているのだとすら言える。
「行くも之れを使むる或り、止まるも之れを尼むる或り。行くも止まるも、人の能くする所に非ざるなり」
「行くこともそれなりの命運に基づくし、止まることもそれなりの命運に即している。
行くことも止まることも、誰かが作為でどうにかできることではない。(全ての選択は
天命に基づくといえなくもないが、その場合にも、誰かの作為の普遍性などは認められない。
孟子が、天命論に限っては無為自然論者でもあることを示唆した記録ともなっている」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・梁恵王章句下・一六より)
永遠の[アガペー]愛がないなら・・・ 動機が不純なら・・・ お勉強なんて……毒かもね
 「舌は刃となってこの世を切り裂く」というのが、春秋戦国時代の悪徳外交家、
「舌は刃となってこの世を切り裂く」というのが、春秋戦国時代の悪徳外交家、 通称「縦横家」にとっての決まり文句でもあったらしい。代表的な思想家には
鬼谷子などがいて、その門下で外交戦術を教わった蘇秦や張儀らが、中国全土を
合従連衡や大分裂の波乱に陥れていたことは、「史記」などにも詳しく述べられている。
その、縦横家たちが国際紛争を煽る悪逆非道を繰り返しているさ中に、あまりもの濁世に
愛想を尽かして楚国の重職を退官して後、放浪のさ中に数多の詩歌を唄い、最後には
入水自殺を果たした屈原という詩人がいる。その詩集は「楚辞」として後世にまで受け継がれ、
風流な詩文芸には乏しかった戦国時代の中国文化の中では、異色を放つ存在ともなっている。
「宝玉が欠けようとも磨いて修復することができるが、配慮に欠けた言葉は取り繕いようもない」
とは「詩経」大雅・抑にあり、「言うべきでないことは言うな。理由なきことはわざわざ口にするな」
とも、同じく「詩経」小雅・賓之初筵にある。それでいて「詩経」全体が風流な自然描写や叙情で
埋め尽くされており、配慮に満ちた言うべきこと、由縁あることを述べる文芸の精髄となっている。
唐詩や宋詩、日本の短詩文芸などにおいても、特に自然現象の丹念な描写が秀逸となっている。
和語で歌われる五七五の定型詩は、季語のある詩だけが「俳句」として、季語を持たない「川柳」
とも区別されているほどで、自然現象の季節による移り変わりの描写が特筆して重視されてもいる。
それもやはり、配慮に満ちた理由ある物事を述べる上でも、自然描写がうってつけだからで、
縦横家やカルト教祖が口走るような、根も葉もない虚言とも一線を画せるからなのである。
 配慮と由縁に満ちた善美なる口舌文化は、自然描写の豊かな詩文芸あたりに極まるが、
配慮と由縁に満ちた善美なる口舌文化は、自然描写の豊かな詩文芸あたりに極まるが、 そこまでいかずも、詩文芸の風流さを参考にしたような節度ある言行をたしなめもする。別に、
孔子や孟子の創作した詩歌が後世に残されているわけでもないが、記録に残されているその言行は、
確かに詩学を学んだものならではの節度や品位が保たれたものとなっている。それと比べれば、
春秋戦国時代に世をかき乱していた政商や食客、そして縦横家らの言行には何らの節操もなく、
ただひたすら権力の濫用ばかりに明け暮れていたその姿が、無様極まりないものともなっている。
確かに、詩文芸ばかりに耽っていられるほど平和な時代も恒常的ではなく、乱世に無理にでも
詩文芸の清浄さに与ろうとしたなら、屈原のように自殺せねばならなくなったり、鎌倉幕府三代将軍の
源実朝のように、和歌をうつつを抜かした挙句に首をはねられて暗殺されることになったりもする。
そのような事情があるから、あえて乱世に自ら自身は詩文芸を嗜まなかった孔孟や徳川家康のような人物も
いるわけで、それはそれで時と場合とに柔軟に対応したあり方だといえる。ただ、そうであっても、詩文芸の
善美さを遠ざけつつも尊重の対象とし、極度にその善美さからかけ離れるような、根も葉もない虚言や奇行に
及ぶことは極力避けるという程度の心がけはすべきなのであり、それすらも心がけようとしない時にこそ、
政商や食客や縦横家やカルト信者などとしての、悪口虚言を駆使した罪悪の重畳にも及んでしまうのである。
口舌もまた、善用と悪用の両極に振り切れられるものである。どちらかといえば善用を心がけ、
専らな善用が不可能な場合にも、できる限り悪用を避ける心がけができてこそ、一人前だといえる。
「晋人、文子を人を知ると謂えり。文子は其の中退然として衣に
勝たざるが如くし、其の言吶吶然として諸を其の口から出さざるが如くす」
「晋の人々は、上将軍の趙文子を『他人への配慮がよく利いている』と評していた。
その身は恭しくて、まるで衣服の豪壮さに不相応であるかの如くし、その言葉もどこまでも
朴訥としていて、まるで口から出すことも出来ないでいるかのようだったからだ」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・檀弓下第四より)
相応の対価を得るために仕えるのではなく、仕える以上は仕える。
それでこそ臣下が主君に仕える、あるいは妻が夫に仕える態度だといえる。
対価に相応の随順しか心がけないのは、商売人の態度である。
そんな態度では、世の中のごく一部の権益だけに携わる内はまだ無事でも、
天下国家レベルの大権にまで携わろうとした時には、必ず大破綻を招く。
金をもらった分だけしか働こうとしないような不誠実な態度で、
全世界規模の権益を健全に運用していけるような事実も一切ないからだ。
従う、従わないにさっぱりとした損得勘定が必ず伴う、だから人としての尊厳が
守られているかのような風潮が自由主義や個人主義、男女平等主義などによって広められても
いるが、かりそめの損得勘定ばかりによって全てを回しても問題が起こらなくても済むのは、
上にも書いたとおり、世の中のごく一部の権益に携わる場合に限ってのこと。ごく一部の
権益にしか携わっていられないから、天下国家の尺度から見れば「小人」に相当する存在とも
なるわけで、公利公益に即して物事を考えていた時代に、商人階級こそは「小人」とも呼ばれて、
それ相応の扱いを受けていたりしたことにも、普遍的な理由があったからなのである。
冷徹な損得勘定だけに即して全てを回してれば、そのぶんだけ本人たち自身の
自意識過剰の思い上がりは肥大化するわけで、その肥大化した自意識を以ってして、
忠義や夫唱婦随に務める者よりも雄大であるなどとすら、自由主義や個人主義に即して
見なされるわけだけども、むしろそのような自意識過剰の思い上がりを募らせている者こそは、
天下国家レベルではごく一部の権益にしか携わることを許されない、実相からの小人でしかない。
それでこそ臣下が主君に仕える、あるいは妻が夫に仕える態度だといえる。
対価に相応の随順しか心がけないのは、商売人の態度である。
そんな態度では、世の中のごく一部の権益だけに携わる内はまだ無事でも、
天下国家レベルの大権にまで携わろうとした時には、必ず大破綻を招く。
金をもらった分だけしか働こうとしないような不誠実な態度で、
全世界規模の権益を健全に運用していけるような事実も一切ないからだ。
従う、従わないにさっぱりとした損得勘定が必ず伴う、だから人としての尊厳が
守られているかのような風潮が自由主義や個人主義、男女平等主義などによって広められても
いるが、かりそめの損得勘定ばかりによって全てを回しても問題が起こらなくても済むのは、
上にも書いたとおり、世の中のごく一部の権益に携わる場合に限ってのこと。ごく一部の
権益にしか携わっていられないから、天下国家の尺度から見れば「小人」に相当する存在とも
なるわけで、公利公益に即して物事を考えていた時代に、商人階級こそは「小人」とも呼ばれて、
それ相応の扱いを受けていたりしたことにも、普遍的な理由があったからなのである。
冷徹な損得勘定だけに即して全てを回してれば、そのぶんだけ本人たち自身の
自意識過剰の思い上がりは肥大化するわけで、その肥大化した自意識を以ってして、
忠義や夫唱婦随に務める者よりも雄大であるなどとすら、自由主義や個人主義に即して
見なされるわけだけども、むしろそのような自意識過剰の思い上がりを募らせている者こそは、
天下国家レベルではごく一部の権益にしか携わることを許されない、実相からの小人でしかない。
奴隷のように生まれ付き絶対服従なのではなく、臣下や妻としての素養を得て後に、
自らの意志にも依って臣従したり嫁いだりする。たとえば武家の家に長男として産まれた所で、
あまりにも武士としての素養に欠け過ぎていたために勘当されるなり出家するなりして、
一生将軍や大名に仕えることもなく、日陰の人生を過ごしたりすることも実際にあった。
どうしても仕えたり嫁いだりできない事情があった場合には拒絶することもあった上で、
いざ主君に仕える以上は忠義を尽くし、嫁ぐ以上は妻としての貞節をも守り通していた。
君子階級の男だけでなく、女もまた商売人のような小ざかしい損得勘定などと共には居られず、
まるで夫が主君に絶対的な忠義を尽くしているようにして、自分もまた夫に対する
絶対的な随順を尽くしていた。君子階級ほど、女が社会的な職務を担える余地のない階級も
他にない一方で、君子階級の女であるからには、そんじょそこらの小人の男などよりも
遥かに真剣な態度で生きて行こうとしていたのだから、そこは見上げたものだといえるだろう。
特に、誰しもが自意識過剰の思い上がりを肥大化させきっている、今の世の諸人などからすれば。
「君に事うるに、〜近くして諌めざるは則ち尸利なり。
〜君に事うるには、諌むることを欲して陳ぶることを欲せず」
「主君に仕えている時に、近侍の立場に居ながら諫言にすら努めようとしないのは、
それにより自らが君からの不興を買って、自らの利益を損ねることを恐れる下心があるからだ。
主君に仕える上では、諫言によって君の過ちを未然に食い止めることこそを目指し、
君が過ちを犯してからそれを指摘するようなことがないようにしていかなければならない。
(この記述のとおりに務めたならば、耳に逆らう諫言によって自らが主君からの不興を買い、
自己利益を損ないつつ天下の公益を守ることにもなり得るわけだから、瑣末な損得勘定
などによってこのような忠義を尽くしていくことは、ほぼ不可能に等しいといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・表記第三十二より)
自らの意志にも依って臣従したり嫁いだりする。たとえば武家の家に長男として産まれた所で、
あまりにも武士としての素養に欠け過ぎていたために勘当されるなり出家するなりして、
一生将軍や大名に仕えることもなく、日陰の人生を過ごしたりすることも実際にあった。
どうしても仕えたり嫁いだりできない事情があった場合には拒絶することもあった上で、
いざ主君に仕える以上は忠義を尽くし、嫁ぐ以上は妻としての貞節をも守り通していた。
君子階級の男だけでなく、女もまた商売人のような小ざかしい損得勘定などと共には居られず、
まるで夫が主君に絶対的な忠義を尽くしているようにして、自分もまた夫に対する
絶対的な随順を尽くしていた。君子階級ほど、女が社会的な職務を担える余地のない階級も
他にない一方で、君子階級の女であるからには、そんじょそこらの小人の男などよりも
遥かに真剣な態度で生きて行こうとしていたのだから、そこは見上げたものだといえるだろう。
特に、誰しもが自意識過剰の思い上がりを肥大化させきっている、今の世の諸人などからすれば。
「君に事うるに、〜近くして諌めざるは則ち尸利なり。
〜君に事うるには、諌むることを欲して陳ぶることを欲せず」
「主君に仕えている時に、近侍の立場に居ながら諫言にすら努めようとしないのは、
それにより自らが君からの不興を買って、自らの利益を損ねることを恐れる下心があるからだ。
主君に仕える上では、諫言によって君の過ちを未然に食い止めることこそを目指し、
君が過ちを犯してからそれを指摘するようなことがないようにしていかなければならない。
(この記述のとおりに務めたならば、耳に逆らう諫言によって自らが主君からの不興を買い、
自己利益を損ないつつ天下の公益を守ることにもなり得るわけだから、瑣末な損得勘定
などによってこのような忠義を尽くしていくことは、ほぼ不可能に等しいといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・表記第三十二より)
現状、権力者の保身目的で未だ公けにはされていないが、
「諸行無常」「諸法実相」「諸法因果」「罪福異熟」「万物斉同」
このあたりの真理法則の普遍性は、科学的にも証明され終わっている。
諸法実相に反する形而上の天国への昇天を通じて、
諸行無常に反する永遠の生を勝ち得ようとするような信教は
根本から邪教であると、科学的にも証明され終わっている。
邪教が邪教たることを最大級に客観的に証明して、
完全なる死亡宣告のとどめを刺すのは、結局は科学あたりなる。
しかし、科学が邪教亡き後のこの世界の人間規範までをも
司って行けるのかといえばそんなこともなく、科学自体はどこまでも
産業振興の指針としての存在意義しか持たないままで居続ける。
世界最悪の邪教たるキリスト教に支配された欧米社会でこそ、近代科学も発達し、
その近代科学が完成の日の目を見るにあたって、欧米の文化的母体たる
キリスト教こそは有害無益であることが科学的にも証明された。
大まかに言って、「近代科学はキリスト教に対する親殺しを果たした」
という風に言えなくもない。ルネサンス以降の西洋の科学者らが、
実はイスラム圏で蓄積されていた計算学や幾何学などをも参考にしつつ
科学を発展させていったことが、まだあまり公けにはされてもいないので、
西洋の科学者たちがキリスト信仰の下に科学を発展させて、挙句に
キリスト信仰の不能性を証明してしまったものだから、キリスト教圏は
文化的に「親殺しからなる自滅」に及んだかのような体裁になろうとしている。
「諸行無常」「諸法実相」「諸法因果」「罪福異熟」「万物斉同」
このあたりの真理法則の普遍性は、科学的にも証明され終わっている。
諸法実相に反する形而上の天国への昇天を通じて、
諸行無常に反する永遠の生を勝ち得ようとするような信教は
根本から邪教であると、科学的にも証明され終わっている。
邪教が邪教たることを最大級に客観的に証明して、
完全なる死亡宣告のとどめを刺すのは、結局は科学あたりなる。
しかし、科学が邪教亡き後のこの世界の人間規範までをも
司って行けるのかといえばそんなこともなく、科学自体はどこまでも
産業振興の指針としての存在意義しか持たないままで居続ける。
世界最悪の邪教たるキリスト教に支配された欧米社会でこそ、近代科学も発達し、
その近代科学が完成の日の目を見るにあたって、欧米の文化的母体たる
キリスト教こそは有害無益であることが科学的にも証明された。
大まかに言って、「近代科学はキリスト教に対する親殺しを果たした」
という風に言えなくもない。ルネサンス以降の西洋の科学者らが、
実はイスラム圏で蓄積されていた計算学や幾何学などをも参考にしつつ
科学を発展させていったことが、まだあまり公けにはされてもいないので、
西洋の科学者たちがキリスト信仰の下に科学を発展させて、挙句に
キリスト信仰の不能性を証明してしまったものだから、キリスト教圏は
文化的に「親殺しからなる自滅」に及んだかのような体裁になろうとしている。
キリスト教がこの世から無くなるのはいいことである。それによって
人々が最悪の迷妄を晴らして、今以上の幸福と繁栄に与れるようになるから。
しかし、そのいいことが、理念としての「親殺し」を発端として訪れるというのは
不吉なことであるため、「キリスト教徒主導の近代科学がキリスト教を殺した」
というような体裁は、あまり大々的に触れ回られるべきものでもない。
むしろ、科学法則が結局は陰陽五行や仏法の法則に帰着し、キリスト教の
推進による世界規模の荒廃以前に繁栄していた、優良な異教文化の正当性が
証明されたことのほうをより大々的に触れ回るべきで、「ある文化の死」よりは、
「ある文化の再興」のほうに光を当てることのほうが、前向きともなるに違いない。
これからの、キリスト教文化の死亡は永遠である一方で、不変的な科学法則にも
合致した、優良な伝統文化の興隆こそは永劫でもある。衰滅が永遠であるものよりは、
隆盛こそが永遠であるものに目を向けるほうが、哀しくない上に、道理にも適っている。
「子、罕に利を言うも、命と与に、仁と与にす」
「孔先生は自分一身の利得についてはほとんど語られなかった。
まれに語るときにも、かならず人としての使命や仁義と共に語られた。
(何の使命もなく、ただ私利をむさぼりながら生きることなどは、
語る価値すら無いから、一言も語らなかったのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・子罕第九・一)
人々が最悪の迷妄を晴らして、今以上の幸福と繁栄に与れるようになるから。
しかし、そのいいことが、理念としての「親殺し」を発端として訪れるというのは
不吉なことであるため、「キリスト教徒主導の近代科学がキリスト教を殺した」
というような体裁は、あまり大々的に触れ回られるべきものでもない。
むしろ、科学法則が結局は陰陽五行や仏法の法則に帰着し、キリスト教の
推進による世界規模の荒廃以前に繁栄していた、優良な異教文化の正当性が
証明されたことのほうをより大々的に触れ回るべきで、「ある文化の死」よりは、
「ある文化の再興」のほうに光を当てることのほうが、前向きともなるに違いない。
これからの、キリスト教文化の死亡は永遠である一方で、不変的な科学法則にも
合致した、優良な伝統文化の興隆こそは永劫でもある。衰滅が永遠であるものよりは、
隆盛こそが永遠であるものに目を向けるほうが、哀しくない上に、道理にも適っている。
「子、罕に利を言うも、命と与に、仁と与にす」
「孔先生は自分一身の利得についてはほとんど語られなかった。
まれに語るときにも、かならず人としての使命や仁義と共に語られた。
(何の使命もなく、ただ私利をむさぼりながら生きることなどは、
語る価値すら無いから、一言も語らなかったのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・子罕第九・一)
 洋の東西や古今を問わず、「文字文化とカネ」というのは密接な関係を持ち続けてきた。
洋の東西や古今を問わず、「文字文化とカネ」というのは密接な関係を持ち続けてきた。 為政者といわず商売人といわず、カネを扱うところに最低限の文字文化が必要とされる。
そこに高尚な精神文化などは全く伴わず、単なる数字の操作を厳密にやり込めることだけを
目的とする。その無機質さはある意味、法文処理以上であり、単なる物質経済を全てと考えるのであれば、
高尚な精神性や道徳はおろか、法律以上にも金銭文化こそは、最も原理的なものとして扱われることになる。
文明の金銭文化への依存度の高さは、文字文化そのものの高尚さとは反比例的な関係を持つ。
世界中でも最も金銭文化(主にユダヤ文化)への依存度が高い西洋文明こそは、
文字文化が最も簡素でもあり、アルファベットに特有の書道なども存在しない。
西洋と同じく商業主義的な傾向はあるものの、厳粛な宗教信仰によって金銭文化
そのものを劣後するイスラムには書道文化も存在し、コーランを損壊するものを
極端な憎悪対象にするなどの、過剰とも言える程の書物に対する尊重すらもがある。
乞食行者をも尊ぶインド文化と、商業を徹底した差別下におく伝統的な中国文化
においてこそ、文字文化そのものの高尚さは極まり、金銭文化などともほとんど
隔絶された所に、純粋な道徳や真理にまつわる荘厳な文化体系を構築している。
中国文化やインド文化がとんでもなく膨大で、書道や真言にかけての深遠な体系をも備えていながらも、
金銭本位の物質文化で溢れ返っている今日の世の中で、あまり大した役割を担うようなことがないのも、半ば
確信的なことである。乞食を尊び、商売を劣後する、完全な確信性の下に金銭文化への協力を絶ってもいるのだから。
聖書信仰で「聖霊」などと呼ばれる一つの宗教的要素、その正体はといえば
「金銭文化を司る言葉」とでもいった所で、悪徳的な金融経済が野放しに
なっている所では、そのような言葉がそのままカネも同然の役割を担ったりもする。
中国やインドなどで蓄えられてきた壮大な文字文化は、まさにその「聖霊」を退治することを目的として
編み出されて来たといっても過言ではなく、聖霊の名の下での金銭文化の興隆に協力しないのみならず、
金銭文化の至尊化を積極的に討伐して徹底的な抑制下に置くことをこそ存在目的としているとすらいえる。
金融や物質本位な今の世の中では役立たない、のみならず、今の世の中のその度し難い性向を
頭のてっぺんから完全に降伏し尽くして、身の程を思い知らせるためにこそ役立てられるものであり、
それがイヤだというのなら、永遠に近づいたりすることもなく、完全に無視していればいいだけのことである。
所詮は金融や物質なんて人間にとっては本末のうちの末でしかなく、そればかりにかかずらわっていれば、
そのせいで自業自得の破綻の危機に見舞われるしかないのだから、否応なくそのような自分たちの愚かしさを
降伏していただくしかなくなる時も来るわけだけども、少しでも怨みつらみの不平を残しつつ救いを求めたり
するのなら、そのまま滅びてしまうがいいさ。聖霊への見限りを完全に付けられもしないのなら、そうしたがいい。
「孚有り、血を去りて酡れ出ずる咎无なし。孚有りて酡れ出ずるとは、上と志しを合わせればなり」
「誠心を尽くして上に仕えることで、流血の禍いを去って憂患からも遠ざかり、咎もない。
誠心によって憂患からも遠ざかれるのは、上もまた自分たちと志しを合わせてくれるからである。
(屠殺の流血などは金銭文化からいえば親しいものですらあるが、それは誠心などからは程遠いものである。
自他の血を流してまで奉仕するなどという所にこそ、えてして志しに違う裏心もまたあるものである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・小畜・六四‐象伝)
「金銭文化を司る言葉」とでもいった所で、悪徳的な金融経済が野放しに
なっている所では、そのような言葉がそのままカネも同然の役割を担ったりもする。
中国やインドなどで蓄えられてきた壮大な文字文化は、まさにその「聖霊」を退治することを目的として
編み出されて来たといっても過言ではなく、聖霊の名の下での金銭文化の興隆に協力しないのみならず、
金銭文化の至尊化を積極的に討伐して徹底的な抑制下に置くことをこそ存在目的としているとすらいえる。
金融や物質本位な今の世の中では役立たない、のみならず、今の世の中のその度し難い性向を
頭のてっぺんから完全に降伏し尽くして、身の程を思い知らせるためにこそ役立てられるものであり、
それがイヤだというのなら、永遠に近づいたりすることもなく、完全に無視していればいいだけのことである。
所詮は金融や物質なんて人間にとっては本末のうちの末でしかなく、そればかりにかかずらわっていれば、
そのせいで自業自得の破綻の危機に見舞われるしかないのだから、否応なくそのような自分たちの愚かしさを
降伏していただくしかなくなる時も来るわけだけども、少しでも怨みつらみの不平を残しつつ救いを求めたり
するのなら、そのまま滅びてしまうがいいさ。聖霊への見限りを完全に付けられもしないのなら、そうしたがいい。
「孚有り、血を去りて酡れ出ずる咎无なし。孚有りて酡れ出ずるとは、上と志しを合わせればなり」
「誠心を尽くして上に仕えることで、流血の禍いを去って憂患からも遠ざかり、咎もない。
誠心によって憂患からも遠ざかれるのは、上もまた自分たちと志しを合わせてくれるからである。
(屠殺の流血などは金銭文化からいえば親しいものですらあるが、それは誠心などからは程遠いものである。
自他の血を流してまで奉仕するなどという所にこそ、えてして志しに違う裏心もまたあるものである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・小畜・六四‐象伝)
いくら創作文芸としての手巧の限りを尽くし、挙句にはそこに絶対超越神を登場させて、
現実の諸問題などをもことごとく作中で解消させてみたりした所で、所詮は、新旧約聖書の
作者たち自身はバビロンの囚人だったり、ローマの物狂いだったりする。そうやって現実
から逃避して、空想に救いを求めたりした時点で、決して最善は尽くしていないのである。
問題を解決するための書記姿勢として至上なのは、当該の問題を解決することにかけて
最大級の成功を果たした者の事績や、最大級の失敗を犯した者の罪状をありのままに記録して、
前者を模範の対象とさせ、後者を反面教師の対象とさせることである。その代表が「史記」を
始めとする正史編纂の試みであり、高度な読書の対象として正史に勝るものも他にないといえる。
四書五経のうちでも「書経」や「春秋」は、この条件を満たすことを目的とした歴史書であり、
その編纂者は他でもない孔子である。孔子こそは、世界最古級にして最大級の歴史家でもあり、
司馬遷や班固らもまた、孔門が試みていた歴史書編纂事業の本格化に取り組んだのだといえる。
とはいえ、四書五経はその全てが歴史書なのではなく、易や詩や礼法や、孔子や孟子たち
自身の言行録が含まれている。この内でも、孔子や孟子の言行録に当たる「論語」「孟子」は、
社会的に大成功を果たせたというわけでもない、在野の学者である孔子や孟子の事績をそのまま
収めているわけで、実際に政治機構への接近を試みながらも、濁世ではその学説が理想論に
過ぎるために敬遠されて仕官に失敗するといったような記録までもが、ありのままに記されている。
それでいてやはり、孔子や孟子の言行はどこまでも実地性に根ざしていて、当時の権力者
たちが放辟邪侈の悪癖を取り止めての精進にすら根ざしたなら、実現できたものばかりである。
その証拠に、「論語」の記述をありのままに実践することに務めた漢代の中国や、「孟子」の
記述の実践にすら務めていた江戸時代の日本などが、実際に一定の徳治にも成功しているのである。
現実の諸問題などをもことごとく作中で解消させてみたりした所で、所詮は、新旧約聖書の
作者たち自身はバビロンの囚人だったり、ローマの物狂いだったりする。そうやって現実
から逃避して、空想に救いを求めたりした時点で、決して最善は尽くしていないのである。
問題を解決するための書記姿勢として至上なのは、当該の問題を解決することにかけて
最大級の成功を果たした者の事績や、最大級の失敗を犯した者の罪状をありのままに記録して、
前者を模範の対象とさせ、後者を反面教師の対象とさせることである。その代表が「史記」を
始めとする正史編纂の試みであり、高度な読書の対象として正史に勝るものも他にないといえる。
四書五経のうちでも「書経」や「春秋」は、この条件を満たすことを目的とした歴史書であり、
その編纂者は他でもない孔子である。孔子こそは、世界最古級にして最大級の歴史家でもあり、
司馬遷や班固らもまた、孔門が試みていた歴史書編纂事業の本格化に取り組んだのだといえる。
とはいえ、四書五経はその全てが歴史書なのではなく、易や詩や礼法や、孔子や孟子たち
自身の言行録が含まれている。この内でも、孔子や孟子の言行録に当たる「論語」「孟子」は、
社会的に大成功を果たせたというわけでもない、在野の学者である孔子や孟子の事績をそのまま
収めているわけで、実際に政治機構への接近を試みながらも、濁世ではその学説が理想論に
過ぎるために敬遠されて仕官に失敗するといったような記録までもが、ありのままに記されている。
それでいてやはり、孔子や孟子の言行はどこまでも実地性に根ざしていて、当時の権力者
たちが放辟邪侈の悪癖を取り止めての精進にすら根ざしたなら、実現できたものばかりである。
その証拠に、「論語」の記述をありのままに実践することに務めた漢代の中国や、「孟子」の
記述の実践にすら務めていた江戸時代の日本などが、実際に一定の徳治にも成功しているのである。
権力者たちからのあまりもの冷遇に打ちひしがれて、孔子や孟子もまた、犯罪聖書の作者のように
現実から完全に逃避した夢想論ばかりを並べ立てることだって出来たはずである。それによって、
不埒な幻想の流布を果たし、世の中を大きな不安に陥れて、世の中への復讐を果たすみたいなこと
だって考えられなくはなかったはずだ。しかし、孔孟はそんなことなど露ほどにも志すことなく、
ただひたすら、天下国家の安寧と繁栄との実現を目的とした、着実な徳治の手法ばかりを世の中に
広め続けることを——半ば存命中の成功は不可能であると察しつつ——試み続けたのである。
「史記」や「漢書」中の成功者のような人生を、自分が送れるとも限らない。
場合によっては一生、日の目を見ないままに人生を終える可能性だってあり得る。
そうであってもなお、犯罪聖書の作者やキリストのように、世の中への復讐を込めた乱世画策の
寓意を拵えることなどを試みたりはせずに、孔子や孟子のように、着実に治世を実現する権力道徳の
手法のみを学んだり、身に付けたり、触れ回ったりするように心がけることができるわけである。
ここにこそ、「先天的な落ち度は許されようもあるが、後天的な落ち度は許されようもない」という
「書経」太甲中の教えもまた適用されるのであり、孔子や孟子のように、最大級の先天的な不遇を
ものともせず後天的な浄行を尽くした者がいればこそ、先天的な不遇にかられて後天的な悪行にも
及んだ、犯罪聖書の作者やイエキリの罪が決して許されるものではないことまでもが確かなのである。
「予れ兆民に臨むに、懍乎として朽索の六馬を馭するが若し。人の上たる者、奈何ぞ敬わん」
「私は億兆の民の統治に臨むに際し、戦々恐々として、まるで朽ちた手綱で六頭もの馬を御している
かのような思いであった。人の上に立つ者として、どうしてそれぐらいの恭敬を欠かさずにいられよう。
(朽ちて枯れることもある現実の世界から逃避して、思い上がりを募らせていたりする余裕はないのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・夏書・五子之歌より)
現実から完全に逃避した夢想論ばかりを並べ立てることだって出来たはずである。それによって、
不埒な幻想の流布を果たし、世の中を大きな不安に陥れて、世の中への復讐を果たすみたいなこと
だって考えられなくはなかったはずだ。しかし、孔孟はそんなことなど露ほどにも志すことなく、
ただひたすら、天下国家の安寧と繁栄との実現を目的とした、着実な徳治の手法ばかりを世の中に
広め続けることを——半ば存命中の成功は不可能であると察しつつ——試み続けたのである。
「史記」や「漢書」中の成功者のような人生を、自分が送れるとも限らない。
場合によっては一生、日の目を見ないままに人生を終える可能性だってあり得る。
そうであってもなお、犯罪聖書の作者やキリストのように、世の中への復讐を込めた乱世画策の
寓意を拵えることなどを試みたりはせずに、孔子や孟子のように、着実に治世を実現する権力道徳の
手法のみを学んだり、身に付けたり、触れ回ったりするように心がけることができるわけである。
ここにこそ、「先天的な落ち度は許されようもあるが、後天的な落ち度は許されようもない」という
「書経」太甲中の教えもまた適用されるのであり、孔子や孟子のように、最大級の先天的な不遇を
ものともせず後天的な浄行を尽くした者がいればこそ、先天的な不遇にかられて後天的な悪行にも
及んだ、犯罪聖書の作者やイエキリの罪が決して許されるものではないことまでもが確かなのである。
「予れ兆民に臨むに、懍乎として朽索の六馬を馭するが若し。人の上たる者、奈何ぞ敬わん」
「私は億兆の民の統治に臨むに際し、戦々恐々として、まるで朽ちた手綱で六頭もの馬を御している
かのような思いであった。人の上に立つ者として、どうしてそれぐらいの恭敬を欠かさずにいられよう。
(朽ちて枯れることもある現実の世界から逃避して、思い上がりを募らせていたりする余裕はないのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・夏書・五子之歌より)
「物事には本末がある」という考え方は、
陰陽思想や万物斉同思想によってこそ磐石ともなる。
「アリ」か「ナシ」かなどという短絡的な決め付けではなく、
根本に当たるものと末節に当たるものとが、陽と陰として万物を形成している。
根本たる陽だけでも、末節たる陰だけでも万物を形成することはできず、
両者が一定の差別関係に置かれながら調和することで、万物が安泰になるとされる。
東洋人にとっては、言葉で表すまでもなく自然と備わっている世界観だが、
西洋人にはこのような高度な世界観は始めからは全く備わっていない。
ただ、有るべきものと無かるべきものとがこの世に暫定的に存在していて、
有るべきものに追従して無かるべきものを滅ぼしていくことで
世界が発展していくというような観念までしか持ち合わせていない。
その短絡的なものの考え方が、自業自得で西洋人たち自身に大きな恐怖感をもたらしてもいる。
自分たちが「有るべきもの」の側からあぶれて、「無かるべきもの」の側に組み込まれて、
迫害や殲滅の対象となることを、他でもない自分たちの考え方によってこそ恐れている。
そういったものの考え方全てを、陰陽法則や万物斉同の実相にも根ざした、
「本末調和」の考え方によってこそ刷新していくべきだといえる。
仮に、自分が本末の内の末の側に組み込まれた所で、末節は末節でそれなりの存在意義がある。
一方で、根本にも根本で重大な存在意義があり、末節以上にも尊重されるべきものですらある。
根本が生きて末節が死ぬのでも、末節が生きて根本が死ぬのでも世界は立ち行かず、
お互いの分をわきまえた根本と末節が調和することによってこそ、世界も保たれる。
陰陽思想や万物斉同思想によってこそ磐石ともなる。
「アリ」か「ナシ」かなどという短絡的な決め付けではなく、
根本に当たるものと末節に当たるものとが、陽と陰として万物を形成している。
根本たる陽だけでも、末節たる陰だけでも万物を形成することはできず、
両者が一定の差別関係に置かれながら調和することで、万物が安泰になるとされる。
東洋人にとっては、言葉で表すまでもなく自然と備わっている世界観だが、
西洋人にはこのような高度な世界観は始めからは全く備わっていない。
ただ、有るべきものと無かるべきものとがこの世に暫定的に存在していて、
有るべきものに追従して無かるべきものを滅ぼしていくことで
世界が発展していくというような観念までしか持ち合わせていない。
その短絡的なものの考え方が、自業自得で西洋人たち自身に大きな恐怖感をもたらしてもいる。
自分たちが「有るべきもの」の側からあぶれて、「無かるべきもの」の側に組み込まれて、
迫害や殲滅の対象となることを、他でもない自分たちの考え方によってこそ恐れている。
そういったものの考え方全てを、陰陽法則や万物斉同の実相にも根ざした、
「本末調和」の考え方によってこそ刷新していくべきだといえる。
仮に、自分が本末の内の末の側に組み込まれた所で、末節は末節でそれなりの存在意義がある。
一方で、根本にも根本で重大な存在意義があり、末節以上にも尊重されるべきものですらある。
根本が生きて末節が死ぬのでも、末節が生きて根本が死ぬのでも世界は立ち行かず、
お互いの分をわきまえた根本と末節が調和することによってこそ、世界も保たれる。
実際に、この世界はそういう風にできているのだから、考え方以前に、それを普遍法則として
承諾しないことには、本当にこの世界も立ち行かなくなる。最低限のこととして、本末調和
という法則の普遍性を他人行儀にでもうべなうことがあった上で、さらには自分たちのものの
考え方までをも本末調和に合わせていって、「アリかナシか」で全てを決め付けてしまう
原始的なものの考え方を卒業していくことが、より前進的な心がけとして推奨されるのである。
その上では、本末調和に違背するものの考え方をけしかける邪義だけは、廃絶が免れ得ない。
わざわざ今さら特定するまでもない「例の邪義」は、他でもない西洋人たち自身が育んできた
科学理論によってその不当性が確証され、否応のない全否定の運命にも立たされてもいる。
とはいえ、その邪義が全否定されて廃絶された所で、かつてそれに取り込まれていた被害者
たちが、実相にかなった本末調和の考え方へと転向できるとも限らず、考え方だけは結局
「アリかナシか」の旧態依然としたもののままに止まったままでいることもあり得るのである。
教育が足りなければ、確実に考え方だけはそのままでもあり続ける。
それ程にもこの世界の普遍法則としての本末調和のほうが特殊なものであり、
何らの教化もなく自然と人々にその把握が備わるなどということを期待できる
ものでもないから、その特殊法則としての本末調和を大いに教化していくことで、人々の
原始的に過ぎるものの考え方の自業自得からなる恐怖を、払拭していくことが必要だといえる。
「夫れ礼は自らを卑くして而して人を尊ぶ。負販の者と雖も、必ず尊ぶべきものあるなり」
「礼儀礼節は自らを卑しんで、他者を尊ぶことを促す。仮に本当に礼節に適おうとするのなら、
商品を背負って販売するような賤しい身分の者にすら、尊ぶべきものを見つけるはずである。
(古代ユダヤ人がやっていたような賤業も、卑しいながらに尊ぶべき所があったりした。
身分の尊卑で完全に関係性が断絶するなどと思い込んだことこそは決定的な落ち度である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・曲礼上第一より)
承諾しないことには、本当にこの世界も立ち行かなくなる。最低限のこととして、本末調和
という法則の普遍性を他人行儀にでもうべなうことがあった上で、さらには自分たちのものの
考え方までをも本末調和に合わせていって、「アリかナシか」で全てを決め付けてしまう
原始的なものの考え方を卒業していくことが、より前進的な心がけとして推奨されるのである。
その上では、本末調和に違背するものの考え方をけしかける邪義だけは、廃絶が免れ得ない。
わざわざ今さら特定するまでもない「例の邪義」は、他でもない西洋人たち自身が育んできた
科学理論によってその不当性が確証され、否応のない全否定の運命にも立たされてもいる。
とはいえ、その邪義が全否定されて廃絶された所で、かつてそれに取り込まれていた被害者
たちが、実相にかなった本末調和の考え方へと転向できるとも限らず、考え方だけは結局
「アリかナシか」の旧態依然としたもののままに止まったままでいることもあり得るのである。
教育が足りなければ、確実に考え方だけはそのままでもあり続ける。
それ程にもこの世界の普遍法則としての本末調和のほうが特殊なものであり、
何らの教化もなく自然と人々にその把握が備わるなどということを期待できる
ものでもないから、その特殊法則としての本末調和を大いに教化していくことで、人々の
原始的に過ぎるものの考え方の自業自得からなる恐怖を、払拭していくことが必要だといえる。
「夫れ礼は自らを卑くして而して人を尊ぶ。負販の者と雖も、必ず尊ぶべきものあるなり」
「礼儀礼節は自らを卑しんで、他者を尊ぶことを促す。仮に本当に礼節に適おうとするのなら、
商品を背負って販売するような賤しい身分の者にすら、尊ぶべきものを見つけるはずである。
(古代ユダヤ人がやっていたような賤業も、卑しいながらに尊ぶべき所があったりした。
身分の尊卑で完全に関係性が断絶するなどと思い込んだことこそは決定的な落ち度である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・曲礼上第一より)
カルト教祖としての布教活動中に、イエキリの為した言行が
有罪か無罪かなどということとも無関係に、進んで冤罪被害者に
なることで、強盗殺人級の重罪人への刑罰すらをも肩代わりしようとした
末期のイエスのふざけきりこそは、ありのままに大罪と見なせるものだ。
冤罪は、それによって刑罰を免れた真犯人の罪を多重化させるのみならず、
不当な裁決を行ってしまった法務処理者の罪責すらをも加味してしまう。
「冤罪を認めてしまった」ということが、法務機関の道義的な信頼性を地に墜とす。
強盗殺人犯の死刑囚バラバの代わりにイエキリを磔刑に処し、すでに拘束下にあった
バラバはといえば無罪放免にしてしまったローマ総督のピラトは、それによって自ら
の法の下での正義を根底にまで貶めた。引責辞職ぐらいは当たり前の大失態であり、
その後にも後任者がバラバの処刑などに務めるのでなければ、ローマ総督府の正義は
取り戻されえなかったわけだが、そのような努力が果たされたような事実もない。
それによりローマ帝国の支配者としての正義もまた地に墜ちて、それはそれで所詮は
邪教の内に過ぎないキリスト教などに、全国の支配権を乗っ取られもしたのだった。
冤罪は、その災厄としての度し難さによって、道徳観の未熟な国や天下を乗っ取る
原動力とすらなり得る。道徳意識が十分に成長した世の中であれば、冤罪にすら
適当な処分を科して、世の中の健全性を保つこともできるが、せいぜい正義の根拠が
法律止まりであるような未熟な世の中においては、法務処理者をも巻き込んでの疑獄を
もたらす冤罪現象が、全く自浄不能なものとしてのさばることとなってしまうのである。
有罪か無罪かなどということとも無関係に、進んで冤罪被害者に
なることで、強盗殺人級の重罪人への刑罰すらをも肩代わりしようとした
末期のイエスのふざけきりこそは、ありのままに大罪と見なせるものだ。
冤罪は、それによって刑罰を免れた真犯人の罪を多重化させるのみならず、
不当な裁決を行ってしまった法務処理者の罪責すらをも加味してしまう。
「冤罪を認めてしまった」ということが、法務機関の道義的な信頼性を地に墜とす。
強盗殺人犯の死刑囚バラバの代わりにイエキリを磔刑に処し、すでに拘束下にあった
バラバはといえば無罪放免にしてしまったローマ総督のピラトは、それによって自ら
の法の下での正義を根底にまで貶めた。引責辞職ぐらいは当たり前の大失態であり、
その後にも後任者がバラバの処刑などに務めるのでなければ、ローマ総督府の正義は
取り戻されえなかったわけだが、そのような努力が果たされたような事実もない。
それによりローマ帝国の支配者としての正義もまた地に墜ちて、それはそれで所詮は
邪教の内に過ぎないキリスト教などに、全国の支配権を乗っ取られもしたのだった。
冤罪は、その災厄としての度し難さによって、道徳観の未熟な国や天下を乗っ取る
原動力とすらなり得る。道徳意識が十分に成長した世の中であれば、冤罪にすら
適当な処分を科して、世の中の健全性を保つこともできるが、せいぜい正義の根拠が
法律止まりであるような未熟な世の中においては、法務処理者をも巻き込んでの疑獄を
もたらす冤罪現象が、全く自浄不能なものとしてのさばることとなってしまうのである。
「罪なくして死地に就くを忍びず。〜罪なくして死地に就くを隠む」
「罪もなく死地に追いやられるものに対して忍びない気持ちを抱く。
罪なく死地におもむかされるようなものに対しては哀悼の意を抱く。
(斉の宣王は生贄のため屠場に連れて行かれる牛を見ていたたまれない気持ちになり、
『その牛を犠牲にするのを止めよ』と命じた。結局、生贄の儀式をやめるわけには
いかなかったので、牛よりも小さい羊を生贄のために殺すこととなったが、孟子は、宣王が、
罪もなく死地に赴かされるような相手を見れば、たとえその相手が動物であっても忍びない
気持ちになれる、慈しみの心の持ち主であることを高く評価した。『人間生贄教』である
キリスト教がこの世から根絶された所で、肉用獣などを罪もなく殺すことは、世の中が総出
を挙げて肉食の禁止にでも取り組まないことには、途絶し得ないことである。そうであっても、
そもそも人であれ動物であれ、生き物が何の罪なく殺されたりすることには一定の忍びなさを
抱けるだけの、心の繊細さを大事にすべきなのである。世の中がどのような段階にあるのであれ、
罪なきものの犠牲を嬉しがるような壊れた神経は、できる限り忌まれて然るべきなのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・梁恵王章句上・七より)
「罪もなく死地に追いやられるものに対して忍びない気持ちを抱く。
罪なく死地におもむかされるようなものに対しては哀悼の意を抱く。
(斉の宣王は生贄のため屠場に連れて行かれる牛を見ていたたまれない気持ちになり、
『その牛を犠牲にするのを止めよ』と命じた。結局、生贄の儀式をやめるわけには
いかなかったので、牛よりも小さい羊を生贄のために殺すこととなったが、孟子は、宣王が、
罪もなく死地に赴かされるような相手を見れば、たとえその相手が動物であっても忍びない
気持ちになれる、慈しみの心の持ち主であることを高く評価した。『人間生贄教』である
キリスト教がこの世から根絶された所で、肉用獣などを罪もなく殺すことは、世の中が総出
を挙げて肉食の禁止にでも取り組まないことには、途絶し得ないことである。そうであっても、
そもそも人であれ動物であれ、生き物が何の罪なく殺されたりすることには一定の忍びなさを
抱けるだけの、心の繊細さを大事にすべきなのである。世の中がどのような段階にあるのであれ、
罪なきものの犠牲を嬉しがるような壊れた神経は、できる限り忌まれて然るべきなのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・梁恵王章句上・七より)
 正義の最大級の根拠が、法律ではなく普遍道徳や真理にこそある世の中であれば、
正義の最大級の根拠が、法律ではなく普遍道徳や真理にこそある世の中であれば、 法務処理者自身に全ての法権が集中してしまうようなこともないために、
法治機構を巻き込んでの冤罪が絶対的な安定性を獲得するようなこともない。
漢の文帝の時代、高祖劉邦と共に帝国勃興の礎となった武将の絳侯周勃が、
文帝からの使者を武装して迎えていたために謀反の疑いをかけられ、獄につながれた。
周勃は軍務にかけては有能だったものの、朴訥で弁舌能力などには欠けていたために、
政治ではあまり能力を発揮することができず、弁説豊かな陳平らに重職をも譲っていた。
投獄中にも言葉で弁解することがうまく行かず、弁解の内容を詳記した手紙を賄賂と
共に獄吏に渡して、朝廷の高位者に届けさせた。賄賂を用いたりしたその手段は決して
褒められたものではないものの、わざわざ弁解を手紙にして送ったりしたあたりが、
周勃の巧言令色の寡なさを示唆する振る舞いでもあるとして、太后や袁盎らの感銘を買い、
文帝への熟諫などの協力も得て、最終的には釈放されることとなったのだった。
上の事例などは、他人の罪を自分が背負った場合ではなく、無実の罪を自分が着せられた
場合の冤罪にあたるわけだが、そうであるにしたって、漢帝国が法治よりも徳治のほうを
より尊重している世の中であったからこそ、冤罪が解消された実例となっている。
法治主義の致命的な欠陥としては、他に公務員の極度の堕落化などが挙げられるが、
冤罪の解消がほぼ不可能であることもまた、法治主義の最大級の欠陥の一つであるといえる。
これらの欠陥を補うためにこそ、法治に徳治を上乗せすることが有効ともなる。
法治を捨て去って徳治に移行するのではなく、法治に徳治を上乗せするのである。
今となっては、「聖書の神への帰依が磐石である」ということは、
「人類を自分たちごと滅亡へと陥れる覚悟が磐石である」ということと全く道義となっている。
キリスト教であれユダヤ教であれ、聖書信仰が貫かれることこそは人類滅亡のシナリオであり、
それをくじくことこそは、人類の滅亡を回避する上での最重要課題ともなっている。
悪性新生物(ガン)にも転移するものもあればしないものもあるし、
薬による「散らし」が可能なものとそうでないものとまでもがある。
「転移」という面では、社会統治の理念としてあまりにも無責任な側面が大きすぎる
聖書信仰がこれ以上に世界的覇権を拡大させていくことが不可能に等しく、実際に
聖書信者数は70億人を超える世界人口のうちでも20億人程度で頭打ち状態となっている。
「薬による散らし」は、言ってみれば聖書信者に対する「説得による棄教の促し」とでも
言った所で、ちゃんと事情を説明したなら、さほど信仰心が旺盛なわけでもない今の聖書圏の
大部分の人々も応じてくれるものと思われる。ただ、「全員が全員」それに応じてくれるなどとも
楽観するわけには行かず、頑なに棄教を拒む者に対して社会的制限をかけるなどの実力行使が
必要になる場合も考えられるる。これこそは、ガン細胞でいう所の「手術による切除」ともなる。
ガン細胞の転移、すなわち聖書信仰のこれ以上の世界的拡大は抑制されているとして、
では伸び悩み状態にある聖書圏をこのまま飼い殺し状態にしておけばどうなるかといって、
やはり、それによる地球人類の破滅が免れられるともいえない。欧米聖書圏だけで世界中の
富の八割以上が独占されていることなど、聖書圏が全世界に対してかけている負担の度合いが
あまりにも過剰なために、極度の疲弊に晒された地球人類の側の致命的荒廃が避けられないから。
「人類を自分たちごと滅亡へと陥れる覚悟が磐石である」ということと全く道義となっている。
キリスト教であれユダヤ教であれ、聖書信仰が貫かれることこそは人類滅亡のシナリオであり、
それをくじくことこそは、人類の滅亡を回避する上での最重要課題ともなっている。
悪性新生物(ガン)にも転移するものもあればしないものもあるし、
薬による「散らし」が可能なものとそうでないものとまでもがある。
「転移」という面では、社会統治の理念としてあまりにも無責任な側面が大きすぎる
聖書信仰がこれ以上に世界的覇権を拡大させていくことが不可能に等しく、実際に
聖書信者数は70億人を超える世界人口のうちでも20億人程度で頭打ち状態となっている。
「薬による散らし」は、言ってみれば聖書信者に対する「説得による棄教の促し」とでも
言った所で、ちゃんと事情を説明したなら、さほど信仰心が旺盛なわけでもない今の聖書圏の
大部分の人々も応じてくれるものと思われる。ただ、「全員が全員」それに応じてくれるなどとも
楽観するわけには行かず、頑なに棄教を拒む者に対して社会的制限をかけるなどの実力行使が
必要になる場合も考えられるる。これこそは、ガン細胞でいう所の「手術による切除」ともなる。
ガン細胞の転移、すなわち聖書信仰のこれ以上の世界的拡大は抑制されているとして、
では伸び悩み状態にある聖書圏をこのまま飼い殺し状態にしておけばどうなるかといって、
やはり、それによる地球人類の破滅が免れられるともいえない。欧米聖書圏だけで世界中の
富の八割以上が独占されていることなど、聖書圏が全世界に対してかけている負担の度合いが
あまりにも過剰なために、極度の疲弊に晒された地球人類の側の致命的荒廃が避けられないから。
聖書信仰はそのまま許容するとして、欧米聖書圏が寡占している八割以上の世界資源を均等に
振り分けることなどだけを想定してみたならば、この場合は聖書信者の過度の反発が避けられない。
異教徒がどうなろうがお構いなしで、ただひたすら自分たちだけが狭隘な栄華を謳歌すること
(選民主義)こそは聖書信仰において正義ともされているのだから、異教徒のために自分たちの
富の大半を失うなどということを、聖書信者としての立場から認められるものでもない。
かような思考実験を通じて、「人類の滅亡を回避するためには、聖書信仰の地球上からの
根絶だけは避けることができない」という結論を導き出すことができる。もうこれまでにも
幾度となく同じような思考実験を繰り返してきたが、やはり結論が結論なものだから、
できる限り多くの再試験を重ねて、その無謬性を極限まで高めることに務めて来たのだ。
いくら純度100%の邪教とはいえ、片田舎の極西社会で2000年にもわたって執拗に信じ込んで
きたものを破棄させられる気持ちを考えてみたならば、やはり忍びないものがあるからだ。
「磐桓たり。貞に居るに利ろし。〜磐桓と雖も、志しは正しきを行うなり」
「極度の艱難に遭って、立ちすくむことこそが磐石となってしまう。それでも貞正でいるのがよい。
艱難に立ちすくむことが磐石となってしまった所で、やはり行いを正しくする志しでいるべきである。
(聖書信者はまさに、磔刑という大難の恐怖によって立ちすくみが磐石となってしまった状態=磐桓の
状態にある。だからといって貞正さや正行を損なってしまったのは聖書信者の落ち度であり、凶行である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——屯・初九‐象伝より)
振り分けることなどだけを想定してみたならば、この場合は聖書信者の過度の反発が避けられない。
異教徒がどうなろうがお構いなしで、ただひたすら自分たちだけが狭隘な栄華を謳歌すること
(選民主義)こそは聖書信仰において正義ともされているのだから、異教徒のために自分たちの
富の大半を失うなどということを、聖書信者としての立場から認められるものでもない。
かような思考実験を通じて、「人類の滅亡を回避するためには、聖書信仰の地球上からの
根絶だけは避けることができない」という結論を導き出すことができる。もうこれまでにも
幾度となく同じような思考実験を繰り返してきたが、やはり結論が結論なものだから、
できる限り多くの再試験を重ねて、その無謬性を極限まで高めることに務めて来たのだ。
いくら純度100%の邪教とはいえ、片田舎の極西社会で2000年にもわたって執拗に信じ込んで
きたものを破棄させられる気持ちを考えてみたならば、やはり忍びないものがあるからだ。
「磐桓たり。貞に居るに利ろし。〜磐桓と雖も、志しは正しきを行うなり」
「極度の艱難に遭って、立ちすくむことこそが磐石となってしまう。それでも貞正でいるのがよい。
艱難に立ちすくむことが磐石となってしまった所で、やはり行いを正しくする志しでいるべきである。
(聖書信者はまさに、磔刑という大難の恐怖によって立ちすくみが磐石となってしまった状態=磐桓の
状態にある。だからといって貞正さや正行を損なってしまったのは聖書信者の落ち度であり、凶行である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——屯・初九‐象伝より)
 人が善性を手に入れるためには、自らの生命としての本源
人が善性を手に入れるためには、自らの生命としての本源 からなる善性にこそ立ち返ることを心がけるべきである。決して
「土くれによって造られた自らの生体などに善性は存在し得ない」
などと決め付けて、自分自身以外の何かに善性を求めたりすべきではない。
そうであろうと心がけることが、原理的に人間が善性を手に入れる至当な手段となっている。
そうでないんなら、ただ自分以外の何かに善性の在り処を求めればいいだけだが、実際問題、
人間にとっては修身こそが善性を手に入れる上での最善策となるのであり、修身を疎かにして
までの外物への拘泥こそは、善性を失って悪性にかられる原因にもなってしまうのである。
理論的には、純粋な位相上の問題であり、仮に人間が善性の拠り所と
すべきものが内面ではなく外面にあったとしたならば、それに添って
外物こそを主要な拠り所とすればよかっただけのことである。
善性の拠り所とすべきものが、人間の内面にあると考えたから孟子は性善説を唱え、
内面にそれだけのものはないと考えたから荀子は性悪説を唱えた。だからといって、
孟子が善人で荀子が悪人だったというのではなく、善性の拠り所とすべきものを
孟子は内面に見定めた一方、荀子は外面に見定めたという違いがあるのみである。
それが片や善思善言善行の取っ掛かりとなり、片や悪思悪言悪行の取っ掛かりとなった
とした所で、その選択は善に基づいていたとも悪に基づいていたとも言えず、故にこそ、
善悪もその取っ掛かりにまで遡れば、もはやそこには善も悪もなかったことが知れるのである。
孟子が性善説を唱え、荀子が性悪説を唱える分岐点となったのは、本人たち自身の
「勇気」の有無だった。孟子には場合によっては戦役すら辞さないほどもの勇猛さがあったが、
荀子には戦役全般を頭ごなしに否定し尽くす生粋の臆病さばかりのみがあった。
その勇猛さの有無が、自分たち自身の本性からの善性の発露、それに基づく
善思善言善行を推進していけるか否かという意見を分かつこととなったのだった。
東洋人が主に性善説に根ざした思想宗教哲学を構築し、西洋人は主に性悪説に根ざした
思想宗教哲学を構築してきたのは、本人たち自身の「光明」に対する信奉の有無による。
日出ずる東方への居住を好んだ東洋人は、自分たち自身の陽性さを養って行った一方、
日没する西方への居住を好んだ西洋人は、逆に自分たち自身の陰性を深刻なものとさせた。
その結果、それぞれに性善説を拠り所にしたり性悪説を拠り所にしたりして、善性の在り処
を自分たち自身の内面に求めたり、外面に求めたりしていくこととなったのだった。
それが結果として片や積善につながり、片や積悪につながった。構築されて来たものは
一概に善だったり悪だったりするものの、それを志し始めるに至ったきっかけはといえば、
光明に対する信奉の有無や勇気の有無のような、善とも悪とも言えないようなものだった。
「善悪も本質的には虚空である」という真理がそこにあるのであり、その真理の諾いにもよって、
積善を果たせた者は増上慢を防ぎ、積悪に陥ってしまった者は自分たちを慰めればいい。
善悪の分別など未だ未熟だった頃の過ちも、徳行も共に、虚空の真理の下で安んずるのである。
「形色は天性なり。惟だ聖人にして然る後に以て形を踐む可し」
「以って生まれた人間としての形態や容色こそは、ありのままに天性に適っている。ただ、
仁徳を修めた聖人となることで初めて、その形色の天性を踏襲することができるのである」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・仁心章句上・三八より)
「勇気」の有無だった。孟子には場合によっては戦役すら辞さないほどもの勇猛さがあったが、
荀子には戦役全般を頭ごなしに否定し尽くす生粋の臆病さばかりのみがあった。
その勇猛さの有無が、自分たち自身の本性からの善性の発露、それに基づく
善思善言善行を推進していけるか否かという意見を分かつこととなったのだった。
東洋人が主に性善説に根ざした思想宗教哲学を構築し、西洋人は主に性悪説に根ざした
思想宗教哲学を構築してきたのは、本人たち自身の「光明」に対する信奉の有無による。
日出ずる東方への居住を好んだ東洋人は、自分たち自身の陽性さを養って行った一方、
日没する西方への居住を好んだ西洋人は、逆に自分たち自身の陰性を深刻なものとさせた。
その結果、それぞれに性善説を拠り所にしたり性悪説を拠り所にしたりして、善性の在り処
を自分たち自身の内面に求めたり、外面に求めたりしていくこととなったのだった。
それが結果として片や積善につながり、片や積悪につながった。構築されて来たものは
一概に善だったり悪だったりするものの、それを志し始めるに至ったきっかけはといえば、
光明に対する信奉の有無や勇気の有無のような、善とも悪とも言えないようなものだった。
「善悪も本質的には虚空である」という真理がそこにあるのであり、その真理の諾いにもよって、
積善を果たせた者は増上慢を防ぎ、積悪に陥ってしまった者は自分たちを慰めればいい。
善悪の分別など未だ未熟だった頃の過ちも、徳行も共に、虚空の真理の下で安んずるのである。
「形色は天性なり。惟だ聖人にして然る後に以て形を踐む可し」
「以って生まれた人間としての形態や容色こそは、ありのままに天性に適っている。ただ、
仁徳を修めた聖人となることで初めて、その形色の天性を踏襲することができるのである」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・仁心章句上・三八より)
 良くも悪しくも、「土地」こそは最も磐石な富の源泉となる。
良くも悪しくも、「土地」こそは最も磐石な富の源泉となる。 肥沃な土地、痩せた土地、資源のある土地、温泉の出る土地、何も出ない土地と色々あって、
それぞれの土地の特性をうまく生かした事業に励むことが、良くも悪しくも最も磐石な富の獲得方法となる。
「良くも悪しくも」といったのは、恵まれた土地によってもたらされる富が
地権者に過剰な堕落を許して、働きもしないで豪遊できることが当たり前で
あるかのような考え方までをも時には根付かせてしまうことがあるからだ。
東洋の封建社会においては、そのような地主身分に対する卑しみが儒学道徳にも基づいて嗜まれ
(里仁第四・一一の「小人は土を懐う」など)、地権の嵩にかかって莫大な富を囲い込むことなども、
許されないこととまではいかずとも、決して立派な行いなどとは見なされて来なかった。
ところが西洋はといえば、地主と貴族はほぼ同等の存在だった。一国の国王なども
特に裕福な地主が代表してなったりするばかりで、これと決めて割り振られた封土全体を
公益に適うように統治する官職を別に置くような、東洋的な締まりのよさはなかった。
それを問題視したマルクスらが、無産階級(労働者)が有産階級(地主などの資産家)を
革命によって滅ぼすことを正当化した共産主義をぶち上げたりもしたわけだが、そこには地主らを
専ら「貴族」と見なしきってのルサンチマンが未だ滞留していたのであり、そもそも地主風情を
いっさい高貴な身分であるなどとは見なさない、東洋的な分別などは全く欠けていたのである。
 西洋において、地主に対する見識が未熟なままに止まり続けたのは、
西洋において、地主に対する見識が未熟なままに止まり続けたのは、 儒学道徳に相当するような君子道徳が欠けていたことと、不毛の地である砂漠地帯の
価値観を基本としたイスラエル聖書を至上の聖典として来たこととの両方を原因としている。
砂漠こそは、まさに不毛の地の最たるものであり、地権に対する価値を見出しにくい風土の至りである。
実際に砂漠地帯たる中東を居住地として来た人々は行商を主要な生業とし、全く地の利などをあてにしてはいない。
砂漠地帯の内部であれば、そういった地権を無視したものの考え方がそのまま通用するわけだが、
欧米のようなそれなりに恵まれた国土において、地権を無視ないし軽視する砂漠地帯のものの考え方が犯罪聖書
によって輸入された結果、地権の嵩にかかって富を貪る行いに対する卑しみもまた、行き届かなかったのである。
富は良くも悪しくも、あぶく銭のように膨れ上がっては消え去るばかりのものではない。
土地の恵みに即して膨大な富が長年にわたってもたらされることも、良くも悪しくもあり得ることで、そこに
万端の責任を持って封土を治めきろうとする者と、私利私欲のために地権を濫用しようとする者との両者が生じ得る。
この内の前者を優遇して後者を冷遇する心がけがないことには、後者の過剰な膨れ上がりまでもが生じてしまうわけで、
実際に地権を駆使して大事業を為すことが試みられる文明社会において、土地に対する諦観を持つことはあって
然るべきことだといえる。見識の未熟なものが巨大な地権を持つことは、気 違いに刃物も同然なことなのだから。
「子衛に適く。冉有僕す。子曰く、庶きかな。冉有曰、既に庶し。又た何をか加えん。
曰く、之れを富まさん。曰く既に富まんに、又た何をか加えん。曰く、之れを教えん」
「孔先生は冉有を従えて衛国に赴かれた。国の様子を見て、『人口が増大しているね』と指摘された。
冉有『人口は十分とすれば、さらに何を加えたらよろしいでしょうか』 先生『富ませたらよい』
冉有『すでに富も十分としましたなら、さらに何を加えましょうか』 先生『教育を充実させよう』
(人口と富とを堅実かつ正当に保っていく教育を施す。富は富で大事にすべきものなのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・子路第十三・九より)
 人性の根本は、全く以ってこの世界と同根であり、その根本性に即して考え、
人性の根本は、全く以ってこの世界と同根であり、その根本性に即して考え、 言行することがありのままに、この世界のための思考や言行ともなる。
もちろんその根本性ばかりに即せるとも限らず、根本性から乖離した濁念によってこそ
思考や言行してしまうこともあるわけで、その時にこそ何も世のため人のためにならず、
かえって公益を損ねてまで私益を貪るような悪逆非道の企てにまで繋がってしまうのである。
そのような事態に陥らないためにも、陥ってから後に立ち直るためにも、人は自らの根本性にこそ
立ち返るべきなのであり、それによってのみ過ちを止めて、正しきを為すこともまた可能となるのである。
根本性から乖離した濁念ばかりに囚われて害心の塊と化してしまっている人間が、害心の浄化を
外物などに求めて、挙句には形而上の超越神などにすがったとしたならば、それは自らの害心こそを
堅固なものと化してしまうばかりのこととなり、寸分たりとも害心が清められることにはならない。
形而上の超越神あたりこそは、害心を岩の如く固め尽くすにもうってつけの依存対象となる。
それは、形而上の超越神こそはこの世界と何のかかわりもない、無責任極まりない存在だからで、
世のため人のためにならず、かえって世と人とを損なおうとする害心にとっても最高の伴侶となるからだ。
形而上の超越神への心理的依存によって、害心を岩の如く固めた人間が、正心に立ち戻って
善思善言善行を為せるようになるまでの道のりこそは、最も長い更生の道のりともなる。
 まずは、形而上の超越神への依存を取り止めて、害心こそを堅固なものとすることを途絶する。
まずは、形而上の超越神への依存を取り止めて、害心こそを堅固なものとすることを途絶する。 ここでまず極度の不安症になり、親からはぐれた幼子ほどもの悲痛にかられるはずである。
その悲痛を乗り越えて、外物ではなく自らの根本性に立ち返る修練を重ねる。道徳の勉強でも
座禅でも武道でもヨガでも、間違ったものですらなければ手段は何でもいいが、自らの性根に立ち返る
修練を通じて濁念を止め、常日ごろから性根に即した思考や言行が為せるような正心を得るのである。
害心を岩の如く固めたままで、正心を得るなんてことだけはあり得ないから、どちらかを捨てて
もう一方を取ることはやはり必須だ。弘法大師は「十住心論」で、「秘密荘厳心にまで至れた者は、
(異生羝羊心を含む)あらゆる住心を自由に行き来することができる」とも書かれているが、それも、
一ところの住心に止まらないでいる融通無碍さがあるからなのであり、害心まみれの異生羝羊心に
岩の如く凝り固まりきっているなどというのでは、そのような自由さが得られることもないのである。
「害心を完璧に捨て去れるほどに立派であれ」などとも、別に誰しもに強要したりするわけでもないが、
害心にこそ凝り固まって一切変じようがないなどという状態だけは、いい加減卒業すべきだといえる。
人が正心こそを堅固なものとすることが稀であるのと同じように、害心こそを
岩のように堅固とさせることもまた、決して健常なことなどではないのだから。
「泰山の巌巌たる、魯邦の鞢む所。亀と蒙とをも奄有し、遂に大東をも荒つ。
海邦に至りて、淮夷も来たりて同らぐ。率いて従わざるは莫し、魯侯の功なる」
「岩肌も隆々たる泰山を、魯国の人々も仰ぎ見る。亀山と蒙山をも配下に置き、東方の国々をも統べる。
海の向こうの淮の夷たちも来訪して和合す。大群を率いて従わない者もないほどの、魯候の大いなる功。
(社会的な大業を成すことで、自らが高名な岩山のようともなる。これは偉大さが岩のように堅固な例だといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・頌・魯頌・閟宮より)
「演劇」というものは、古今東西を問わず頻繁に催されて来ているが、
その取り扱い方はといえば、それぞれに大きな開きがある。
東洋での演劇の取り扱い方はといえば、基本、低い。
別段特殊な技能に基づいたりするわけでもない単なる演技などは、
仏教の妄語戒などにも違反しかねないものなので、決して偉いものなどとはされない。
能や狂言や歌舞伎や京劇などの、特殊な技能を要する演劇はそれはそれで一つの
尊重の対象とされ、技能の持ち主が舞台外においても優遇されるということはあるが、
舞台上と舞台外での扱いには、あくまで厳密な一線が引かれた上でのことに限られる。
古代ローマの頃から今にまで至る、西洋での演劇の持て囃し方こそは、
まさに「無条件」と呼ぶに相応しいもの。舞台上で奇抜な演技をできるものは即座に
持て囃されて、舞台を降りてもまるで演劇上の人物であるかのように羨望される。
そもそもが舞台上で要求されるものが、必ずしも特殊技能などではないから、
現実と舞台上の分別を必ずしも付けたりする必要もない。
必ずしも演劇を否定したりする必要はないし、またすべきでもないが、舞台上と現実に
厳密な一線を引く演劇こそは尊ばれるべきである一方、両者の間に必ずしも一線を引かない
ような公私混同型の演劇は、「ジャンク」としての扱いに止められてしかるべきだといえる。
その取り扱い方はといえば、それぞれに大きな開きがある。
東洋での演劇の取り扱い方はといえば、基本、低い。
別段特殊な技能に基づいたりするわけでもない単なる演技などは、
仏教の妄語戒などにも違反しかねないものなので、決して偉いものなどとはされない。
能や狂言や歌舞伎や京劇などの、特殊な技能を要する演劇はそれはそれで一つの
尊重の対象とされ、技能の持ち主が舞台外においても優遇されるということはあるが、
舞台上と舞台外での扱いには、あくまで厳密な一線が引かれた上でのことに限られる。
古代ローマの頃から今にまで至る、西洋での演劇の持て囃し方こそは、
まさに「無条件」と呼ぶに相応しいもの。舞台上で奇抜な演技をできるものは即座に
持て囃されて、舞台を降りてもまるで演劇上の人物であるかのように羨望される。
そもそもが舞台上で要求されるものが、必ずしも特殊技能などではないから、
現実と舞台上の分別を必ずしも付けたりする必要もない。
必ずしも演劇を否定したりする必要はないし、またすべきでもないが、舞台上と現実に
厳密な一線を引く演劇こそは尊ばれるべきである一方、両者の間に必ずしも一線を引かない
ような公私混同型の演劇は、「ジャンク」としての扱いに止められてしかるべきだといえる。
 それこそ、「舞台上で罪を犯していないから」「舞台上で罪が清められたから」
それこそ、「舞台上で罪を犯していないから」「舞台上で罪が清められたから」 などという理由で、現実での服罪を疎かにする犯罪者までもが頻発しかねないからで、
公私混同型の演劇などが持て囃されている以上は、そのような犯罪者に
対する責任の追及もまたうやむやになってしまうから。
それこそ、確かに妄語戒の違反からなる罪障の蔓延の助長にもなっているわけで、
その点、演劇そのものではなく、演劇上の特殊技能こそを特定して保護してきた
東洋のあり方のほうが、演劇受容の仕方として節度を守って来ているといえる。
舞台上での演劇やスポーツなどばかりに耽り過ぎたために、ローマ帝国も自壊したように、
大衆向けの娯楽文化ばかりに飲み込まれ尽くした国や世界というのは、それによる自壊が
免れられるものでもない。西洋人は今までそれしか知らなかったから、同じ過ちをまた
米英崩壊などの形で繰り返しつつもあるが、全世界的に見れば、過ちを改める方法は
実在するわけだから、西洋人にとっても「過ちを改めざる、これを過ちという」という
教条はすでに通用的なものとなっている。今度も過ちを改めないようであれば、それこそ
お天道様までもがそれを許さないがために、人類の滅亡までもが避けられないのである。
「犠牲既に成え、粢盛既に潔く、祭祀時を以てす。然して旱乾水溢あれば、則ち社稷変じて置く」
「立派な犠牲と、清浄な穀物を供え、祭祀もしかるべき時に執り行って、それでもなお旱魃や
水害が起こるようであれば、社稷ごとそっくり造り直してしまう。(君子現実を見て豹変す)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句下・一四より)
たとえば、俺がこうして書いていることの大半は、単なる現実である。
ネット上に投稿して来た原稿用紙数万枚ぶんの文章の、ほぼ大半が現実把握の記録。
だからといって何の意図もないなんてことももちろんなく、記録すべき現実を記録して、
すべきでない現実までは記録しない、「春秋の筆法」と呼ばれているような物書きを心がけている。
その名の通り、この筆法は四書五経中の「春秋経」に由来するもので、源流もその筆者である孔子にあたる。
代表的な継承者には「漢書」の著者である班固などがいて、その「漢書」の記述も現実把握+道義的記録
という姿勢を守っている。何でもかんでもやたらと書きまくっている司馬遷の「史記」などと比べれば
その記述もいかめしく、代表的な権力者の引責自殺などの、書くべきではあってもあまり文芸的には
楽しめないような記事こそが目白押しともなっている。(故に「漢書」は難読書の代表格としても扱われている)
上で、「何でもかんでも」とは言ったものの、司馬遷の「史記」もまた当然、史実把握の記録ではある。ただ、
史実のうちでも書くべきことを書いて書くべきでないことを書かない姿勢を貫いている、「春秋」や「漢書」など
とは違って、「史記」は史実ですらあれば何でもかんでも取り上げている。これは万物斉同の道家思想にこそ
由来する筆法で、楽しみながら歴史を学べるという点では、確かに春秋の筆法をも上回っているといえる。
司馬遷は純粋な史家だったが、孔子は礼学者や政治家だったし、班固も史家であると同時に諸官僚でもあった。
純粋な文筆家に止まるのであれば司馬遷のような文筆姿勢でも構わないが、政治家などとしてやっていくのであれば
司馬遷流の筆法ですら「芸能」に過ぎるといえ、読み方によっては味も素っ気もない「春秋」や「漢書」級の
冷徹な文筆に徹することが賢明だといえる。逆に、それぐらいの文筆であれば、実際の政治や軍政の場でも
役立てられたりもするのであり、しかも文章力を役立てた効用が純粋な「勧善懲悪」でもあり得るのである。
ネット上に投稿して来た原稿用紙数万枚ぶんの文章の、ほぼ大半が現実把握の記録。
だからといって何の意図もないなんてことももちろんなく、記録すべき現実を記録して、
すべきでない現実までは記録しない、「春秋の筆法」と呼ばれているような物書きを心がけている。
その名の通り、この筆法は四書五経中の「春秋経」に由来するもので、源流もその筆者である孔子にあたる。
代表的な継承者には「漢書」の著者である班固などがいて、その「漢書」の記述も現実把握+道義的記録
という姿勢を守っている。何でもかんでもやたらと書きまくっている司馬遷の「史記」などと比べれば
その記述もいかめしく、代表的な権力者の引責自殺などの、書くべきではあってもあまり文芸的には
楽しめないような記事こそが目白押しともなっている。(故に「漢書」は難読書の代表格としても扱われている)
上で、「何でもかんでも」とは言ったものの、司馬遷の「史記」もまた当然、史実把握の記録ではある。ただ、
史実のうちでも書くべきことを書いて書くべきでないことを書かない姿勢を貫いている、「春秋」や「漢書」など
とは違って、「史記」は史実ですらあれば何でもかんでも取り上げている。これは万物斉同の道家思想にこそ
由来する筆法で、楽しみながら歴史を学べるという点では、確かに春秋の筆法をも上回っているといえる。
司馬遷は純粋な史家だったが、孔子は礼学者や政治家だったし、班固も史家であると同時に諸官僚でもあった。
純粋な文筆家に止まるのであれば司馬遷のような文筆姿勢でも構わないが、政治家などとしてやっていくのであれば
司馬遷流の筆法ですら「芸能」に過ぎるといえ、読み方によっては味も素っ気もない「春秋」や「漢書」級の
冷徹な文筆に徹することが賢明だといえる。逆に、それぐらいの文筆であれば、実際の政治や軍政の場でも
役立てられたりもするのであり、しかも文章力を役立てた効用が純粋な「勧善懲悪」でもあり得るのである。
史実に限るとはいえ、何でもかんでも網羅しつくそうとする司馬遷流の筆法は、実地では役立てにくい。
そして、史実に限らずあることないこと書きまくったり、実際にはあり得ないようなことばかりを書きまくったり
喋りまくったりする「詭弁」の能力があったなら、その能力こそは実地での「悪逆非道」にすら結び付くのである。
春秋の筆法に根ざすような文章力の研鑽はぜひすべきことだし、司馬遷流の筆法なども身に付けてはならない
などということまではない。ただ、詭弁や虚言を弄して、それこそを文章化する能力などがあったならば、
これこそはあって余計であり、なくて別に困らないものであるといえ、むしろ身に付けないほうがマシだったりする。
残念ながら、そのような詭弁的文章力のほうが今の世の中では「純文学」などとして持て囃されていて、
司馬遷流の筆法も「ノンフィクション」という狭い枠組みに追い込まれ、春秋の筆法はといえば、
もはや文学的な価値はほとんどないかのようにすら扱われてしまっているのである。
本来は、この序列は逆であるべきなのである。書くべき現実を書いて書くべきでない現実を書かない春秋の筆法が第一、
現実であれば何でもかんでも書いてしまう司馬遷流の筆法が第二、あることないことなんでも書きまくる詭弁的な筆法
が第三で、第一と第二こそは文筆の王道とされ、第三は度し難い外道として十分な警戒下に置かれるべきなのである。
>>124-125に「演劇も無条件に礼賛されたりすべきではない」と書いたのと同じように、文芸も無制限に
持て囃されたりされるのはむしろ避けるべきで、筆法が最低限以上の道義性にかなっている場合に限って
「聖文」として扱い、それ以外を「俗文」や「悪文」として、その受容に一定の歯止めをかけるべきなのである。
卑俗な文芸や演劇に慣れきってしまっている現代人にとっては、酷烈な物言いにも聞こえるかもしれないが、
それもまた書くべきことを書いて書くべきでないことを書かない、春秋の筆法にこそ即した記録であるからだ。
正直、その記述をありのままに実践することが、自分自身すらもが畏れ憚るぐらいのものですらあるのだ。
そして、史実に限らずあることないこと書きまくったり、実際にはあり得ないようなことばかりを書きまくったり
喋りまくったりする「詭弁」の能力があったなら、その能力こそは実地での「悪逆非道」にすら結び付くのである。
春秋の筆法に根ざすような文章力の研鑽はぜひすべきことだし、司馬遷流の筆法なども身に付けてはならない
などということまではない。ただ、詭弁や虚言を弄して、それこそを文章化する能力などがあったならば、
これこそはあって余計であり、なくて別に困らないものであるといえ、むしろ身に付けないほうがマシだったりする。
残念ながら、そのような詭弁的文章力のほうが今の世の中では「純文学」などとして持て囃されていて、
司馬遷流の筆法も「ノンフィクション」という狭い枠組みに追い込まれ、春秋の筆法はといえば、
もはや文学的な価値はほとんどないかのようにすら扱われてしまっているのである。
本来は、この序列は逆であるべきなのである。書くべき現実を書いて書くべきでない現実を書かない春秋の筆法が第一、
現実であれば何でもかんでも書いてしまう司馬遷流の筆法が第二、あることないことなんでも書きまくる詭弁的な筆法
が第三で、第一と第二こそは文筆の王道とされ、第三は度し難い外道として十分な警戒下に置かれるべきなのである。
>>124-125に「演劇も無条件に礼賛されたりすべきではない」と書いたのと同じように、文芸も無制限に
持て囃されたりされるのはむしろ避けるべきで、筆法が最低限以上の道義性にかなっている場合に限って
「聖文」として扱い、それ以外を「俗文」や「悪文」として、その受容に一定の歯止めをかけるべきなのである。
卑俗な文芸や演劇に慣れきってしまっている現代人にとっては、酷烈な物言いにも聞こえるかもしれないが、
それもまた書くべきことを書いて書くべきでないことを書かない、春秋の筆法にこそ即した記録であるからだ。
正直、その記述をありのままに実践することが、自分自身すらもが畏れ憚るぐらいのものですらあるのだ。
「庶頑讒説、若し時しきに在らざれば、侯を以て之れを明らかにし、
撻を以て之れを記し、書を用て識らせんかな。並びに生くるを欲さんかな」
「諸々の頑迷で讒言を触れまわるものの内で、特に不正が明らかであるものなどは、
射侯の儀式によってその悪を明らかにし、鞭打ちなどの実刑によってこれを戒め、
その所業をも克明に書き残して、後世にまで長く伝えて行くこととしよう。
それもこれも、末永く人々と共生していくことを欲すればでこそあるのだよ。
(書いていることをそのまま証拠にするのではなく、証拠を得て書く)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・虞書・益稷より)
撻を以て之れを記し、書を用て識らせんかな。並びに生くるを欲さんかな」
「諸々の頑迷で讒言を触れまわるものの内で、特に不正が明らかであるものなどは、
射侯の儀式によってその悪を明らかにし、鞭打ちなどの実刑によってこれを戒め、
その所業をも克明に書き残して、後世にまで長く伝えて行くこととしよう。
それもこれも、末永く人々と共生していくことを欲すればでこそあるのだよ。
(書いていることをそのまま証拠にするのではなく、証拠を得て書く)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・虞書・益稷より)
たとえば、春秋の筆法で書かれた「漢書」の高帝紀において、
著者の班固は「劉家は堯帝の末裔である」という巷説を引き合いに出して、
みずからも「漢は堯帝の命運を継いでいるのだろう」と締めくくっている。
小百姓だった劉家が古えの聖王の末裔だなんてのは全く信憑性のない話で、
それを引き合いに班固も劉家の中華皇帝としての正統性を主張しているものだから、
班固も所詮は虚言家であるかのような物言いが、一部の不勉強な者たちによって為されてもいる。
しかし、そもそも伝承上からして、堯の帝業を本当に継いだのは舜であり、
舜は堯とも全く血のつながりのない、不良な親に悩まされていた小百姓である。
(劉邦も父親に「出来の悪い息子だ」といびられていたことが「史記」などに記録されている)
その舜もまた、自らの帝業を血のつながりのない臣下である禹に譲った。
禹は、自らがカタワになるほどにも中原一帯の治水事業に奔走したとされており、
(劉邦も中原一帯の争乱の平定のために、親族も蔑ろにしての東奔西走の大仕事を果たした)
高祖劉邦はこの舜や禹に極めて類似する功績を挙げたことが間違いないので、その劉邦を
始祖とする漢が堯の帝業を受け継いでいると考えるのも、あながちおかしいことでもないのである。
不勉強なものは、「劉家は堯の末裔である」という俗説を信じていればいいだけのことだし、
ちゃんと勉強するのであれば、劉家が堯の帝業を正統に受け継いでいるのだということを、
末裔論などよりも遥かに着実な根拠の実在に基づいて、計り知ることができるわけである。
春秋の筆法とはこのような、小人が帝位の簒奪を目論むことを最大級に防止するなどの、正当な目的を
込めた筆法のことを言うのであり、その描写姿勢は単なるノンフィクションなどよりも遥かに巧妙である。
ウソも書いているようでいて、やはり書いてはおらず、主観と客観を織り交ぜた巧みな記述によって
読む者に決して不埒な思いなどを抱かせず、ただ善心を養うことだけを促すのである。
著者の班固は「劉家は堯帝の末裔である」という巷説を引き合いに出して、
みずからも「漢は堯帝の命運を継いでいるのだろう」と締めくくっている。
小百姓だった劉家が古えの聖王の末裔だなんてのは全く信憑性のない話で、
それを引き合いに班固も劉家の中華皇帝としての正統性を主張しているものだから、
班固も所詮は虚言家であるかのような物言いが、一部の不勉強な者たちによって為されてもいる。
しかし、そもそも伝承上からして、堯の帝業を本当に継いだのは舜であり、
舜は堯とも全く血のつながりのない、不良な親に悩まされていた小百姓である。
(劉邦も父親に「出来の悪い息子だ」といびられていたことが「史記」などに記録されている)
その舜もまた、自らの帝業を血のつながりのない臣下である禹に譲った。
禹は、自らがカタワになるほどにも中原一帯の治水事業に奔走したとされており、
(劉邦も中原一帯の争乱の平定のために、親族も蔑ろにしての東奔西走の大仕事を果たした)
高祖劉邦はこの舜や禹に極めて類似する功績を挙げたことが間違いないので、その劉邦を
始祖とする漢が堯の帝業を受け継いでいると考えるのも、あながちおかしいことでもないのである。
不勉強なものは、「劉家は堯の末裔である」という俗説を信じていればいいだけのことだし、
ちゃんと勉強するのであれば、劉家が堯の帝業を正統に受け継いでいるのだということを、
末裔論などよりも遥かに着実な根拠の実在に基づいて、計り知ることができるわけである。
春秋の筆法とはこのような、小人が帝位の簒奪を目論むことを最大級に防止するなどの、正当な目的を
込めた筆法のことを言うのであり、その描写姿勢は単なるノンフィクションなどよりも遥かに巧妙である。
ウソも書いているようでいて、やはり書いてはおらず、主観と客観を織り交ぜた巧みな記述によって
読む者に決して不埒な思いなどを抱かせず、ただ善心を養うことだけを促すのである。
 その、春秋の筆法で書かれた「漢書」において、班固は王奔のようなならず者が漢の王統を
その、春秋の筆法で書かれた「漢書」において、班固は王奔のようなならず者が漢の王統を 揺るがすことがないように努める記述に心がけている。小百姓という、本来の劉家の身分の賤しさは
帝位簒奪を目論む格好の理由になりやすく、実際に漢帝国はその初期から群臣の謀反に悩まされていた。
よく勉強してみたなら、劉家が小百姓だったことも帝位の正統性への疑念材料などには全くならない、
のみならず、それこそは舜や禹の化身とするに最も相応しい出自であることまでもが計り知れるわけだが、
そこまでもの勉強が行き届かないが故に、出自の賤しさなどを理由に漢室の淘汰を目論むような連中に
対しては、「劉家は堯の末裔である」などというお粗末な巷説をそのままあてがっておくわけである。
万世一系の天皇家を戴く日本などはともかく、裸一貫の小百姓こそが皇帝にまで上り詰める
という物語構造は、世界的にはむしろ健全なことである。四民制や君子階級の質素倹約などによって、
百姓らに対する万全の保護に努めてきた国や社会なんてのは、世界的には極めて稀有なのだから、慢性的に
虐げられてきた底辺の百姓こそが帝位を得るほうが、カウンターバランスが取れていることにもなる。
実際の国家社会においてこそ、それが健全ともなるのであり、別にルサンチマンのはけ口を信教などに
求めたりする必要もない。信教にはむしろ、不埒なルサンチマンを十全に抑制する効果こそを
期待すべきであり、その期待を満たしてくれる信教も仏教や道教、神道などとして存在する。
いくら底辺の百姓あたりが世界の帝王になるのが道義的に相応しいにしたって、それがしみったれた
ルサンチマンなどを動機として企てられたりするのでは無様である。むしろ自分自身はルサンチマンなど
完全に捨て去って、権力犯罪者としての虚栄に溺れていた連中を「品性上は自分以下の下衆」として
十分に蔑みぬいていることなどを根拠として、帝位にも就くとしたって就くべきである。さすればこそ、
数多の百姓のうちで、誰が世界の帝王となるに相応しいのかも、自然と定まっていくのである。
「上に大澤有れば則ち恵は必ず下に及ぶ。顧るに、上は先に下は後になるのみ。上に積み重なりて、
而こうして下に凍餒の民有るに非ざるなり。是の故に上に大澤有れば、則ち民夫人も下流に待つ。
恵の必ず将に至らんとするを知るなり。餕に由りて之れを見る。故に曰く、以て政を観るべしと」
「(純正な為政者として)上にある者が大いに豊かであるとき、その恵みは必ず下にまで及ぶ。
まず上にある者が恵みを得てから、それが下々の者にも後から至ることでのみ、今までにも
世の中がうまくいってきた。上に十分な蓄財があるにもかかわらず、上凍える民が発生した
ようなことは未だかつてない。そのため、上にある者が十二分に潤っているときには、
民たちも素直に下流に待って不平を抱いたりすることがない。それも、自分たちにまで必ず
恵みが及ぶことを知っているからである。神祇祭祀の際に供える食物の余計如何によってそれが
分かるため、昔から『(祭祀の供えで)政治を判別すればいい』とも言われてきているのである。
(これは当然、政財が癒着して権力者が私的な財を退蔵する民主主義社会での話などではない。
『下にある者から恵む』というイエキリの暴言が『民主主義』という理念の源流ともなっているが、
一部の下が真っ先に恵みを得るような状態では、上下全般への恵みの行き渡りが滞るのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・祭統第二十五より)
而こうして下に凍餒の民有るに非ざるなり。是の故に上に大澤有れば、則ち民夫人も下流に待つ。
恵の必ず将に至らんとするを知るなり。餕に由りて之れを見る。故に曰く、以て政を観るべしと」
「(純正な為政者として)上にある者が大いに豊かであるとき、その恵みは必ず下にまで及ぶ。
まず上にある者が恵みを得てから、それが下々の者にも後から至ることでのみ、今までにも
世の中がうまくいってきた。上に十分な蓄財があるにもかかわらず、上凍える民が発生した
ようなことは未だかつてない。そのため、上にある者が十二分に潤っているときには、
民たちも素直に下流に待って不平を抱いたりすることがない。それも、自分たちにまで必ず
恵みが及ぶことを知っているからである。神祇祭祀の際に供える食物の余計如何によってそれが
分かるため、昔から『(祭祀の供えで)政治を判別すればいい』とも言われてきているのである。
(これは当然、政財が癒着して権力者が私的な財を退蔵する民主主義社会での話などではない。
『下にある者から恵む』というイエキリの暴言が『民主主義』という理念の源流ともなっているが、
一部の下が真っ先に恵みを得るような状態では、上下全般への恵みの行き渡りが滞るのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・祭統第二十五より)
 キリスト信仰自体は、旧約信仰などに根ざした悪魔の働きを助長する。
キリスト信仰自体は、旧約信仰などに根ざした悪魔の働きを助長する。 助長して、最大級に活発化させた挙句に、このまま悪魔の働きをのさばらせた
ままでいたなら、一般のキリスト教徒と悪魔役のキリスト教徒やユダヤ教徒と、
その他の異教徒とを合わせた誰しもが破滅を免れ得ない事態にまで至らしめる、
そこまで至った挙句に、キリスト信仰が悪魔ごとこの世から消え去るというのであれば、
キリストもまた、神道でいうところの「形代カタシロ」としての役割を果たすことで、
この世に滞留する害悪を自分ごと祓い清めることに貢献したことになるかもしれない。
「必ずそうなる」とも断言できないのは、キリスト信仰が悪魔の働きを活発化させることで
この世にもたらした豊満な物質文明が、至らない小人の情欲を駆り立てるものであることもまた
確かなことだから。世界中の富を自分たちだけで八割以上も寡占することでこそ成り立っている
キリスト教圏の物質文明の豊満さを、たとえば十分な精神的修養を積んだ聖人や賢人であれば
諦観することができたとしても、そんじょそこらの小人や女子供までもが諦観できるなどとは
とても断言できないわけで、故にこそ、悪魔の働きをキリスト信仰ごとこの世から滅ぼし去る
だけの思い切りが、全世界全人類によって付けられることまでをも期待するのもまた、難しいのだ。
一人当たりの資源占有率で、今ほぼ世界平均と同等の状態にあるインドネシアやフィリピンなどの
世相を鑑みるに、やはり物質的な魅力に長けているなどということはない。特に、今でもスペインや
アメリカによる植民化の禍根が著しいフィリピンについては、イスラム教国化によって社会風紀が
是正されたインドネシアなどと比べても世相の乱れが著しく、売春婦の輸出や人身売買などの
問題がよく取り沙汰されてもいる。民衆の再教育や文化振興も疎かなままに、ただ富の不均衡だけを
是正すれば、欧米キリスト教国なども今のフィリピンのようになるわけで、欧米人たち自身がそれを
望まないだろうことはもちろんのこと、傍目に見てもそれが魅力的なことだなどとはとても思えない。
たとえば、江戸時代の日本などは鎖国状態で、物資面ではほぼ自給自足で、決して物質的に豊かだった
などということもないわけだが、それでも江戸時代の文化などは、今から見ても魅力的な所がある。
それは、江戸社会が物質的な豊かさ以上にも、文化的な豊かさの養生に務めていた社会だったからで、
そのような条件は、未だキリスト教国であるフィリピンはおろか、ほとんど「対キリスト教用の防壁」
としての役割に専らなイスラムに征服されている、今のインドネシアもまた満たせていることではない。
キリスト信仰が活発化させた悪魔の働きが、キリスト信仰ごとこの世から撃滅されて、
悪魔の働きによって画策されていた富の不均衡も是正されたとして、それだけでそこに残るのは
今のインドネシアやフィリピンレベルの世相だけで、もしもキリスト教が持ち越されたままでいたなら、
特に売春天国でもあるフィリピンのようになる。これこそは、仮にキリストが形代としての役割を果たし
きってこの世から退場したとしても、大した成果が見込めない証拠にもなっているわけで、そこから
さらに、江戸時代や平安時代の日本並みにまで文化振興が行き届いて、二度と悪魔の働きなどによって
高等な文化が毀損されないようにするための反面教師材料として、「かつてのキリスト信仰の成果」
が参考にされ、実際に悪魔が二度と現れなくなったとしたならば、それでこそ、キリスト信仰が
この世にプラスマイナスゼロ以上の好影響をもたらしたことにもなり得るのである。
あまり楽しい話でもないのも確かだが、そもそもキリスト信仰にまつわる事物などに楽しみ(福)を見出そう
などとしたことからして大間違いだったのだから仕方がない。悪魔の働きを始めとする罪悪の助長こそを
本分としている、キリスト信仰などとは無縁な所での文化振興にこそ、楽しみをも見出すべきだったのだから。
などということもないわけだが、それでも江戸時代の文化などは、今から見ても魅力的な所がある。
それは、江戸社会が物質的な豊かさ以上にも、文化的な豊かさの養生に務めていた社会だったからで、
そのような条件は、未だキリスト教国であるフィリピンはおろか、ほとんど「対キリスト教用の防壁」
としての役割に専らなイスラムに征服されている、今のインドネシアもまた満たせていることではない。
キリスト信仰が活発化させた悪魔の働きが、キリスト信仰ごとこの世から撃滅されて、
悪魔の働きによって画策されていた富の不均衡も是正されたとして、それだけでそこに残るのは
今のインドネシアやフィリピンレベルの世相だけで、もしもキリスト教が持ち越されたままでいたなら、
特に売春天国でもあるフィリピンのようになる。これこそは、仮にキリストが形代としての役割を果たし
きってこの世から退場したとしても、大した成果が見込めない証拠にもなっているわけで、そこから
さらに、江戸時代や平安時代の日本並みにまで文化振興が行き届いて、二度と悪魔の働きなどによって
高等な文化が毀損されないようにするための反面教師材料として、「かつてのキリスト信仰の成果」
が参考にされ、実際に悪魔が二度と現れなくなったとしたならば、それでこそ、キリスト信仰が
この世にプラスマイナスゼロ以上の好影響をもたらしたことにもなり得るのである。
あまり楽しい話でもないのも確かだが、そもそもキリスト信仰にまつわる事物などに楽しみ(福)を見出そう
などとしたことからして大間違いだったのだから仕方がない。悪魔の働きを始めとする罪悪の助長こそを
本分としている、キリスト信仰などとは無縁な所での文化振興にこそ、楽しみをも見出すべきだったのだから。
「夫れ物の人を感ずること窮まり無くして、人の好悪節無きときは、則ち是れ物至りて而も人、
物に化せるなり。人の物に化せらるなる者は、天理を滅ぼして而かも人欲を窮むる者なり」
「外物が人に与える感傷に極まりがなく、そのせいで人々が好悪の節操を失ったときには、外物の影響力が
完全に人を支配した状態となってしまう。そしてその外物に支配されてしまったような人間こそは、
天理をも滅ぼして、自分一身の欲望を極めようとすることになるのである。(好悪の節操を
信者に失わせて無限の濁愛に溺れさせようとするキリスト信仰こそは、天理を滅ぼすのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・楽記第十九より)
物に化せるなり。人の物に化せらるなる者は、天理を滅ぼして而かも人欲を窮むる者なり」
「外物が人に与える感傷に極まりがなく、そのせいで人々が好悪の節操を失ったときには、外物の影響力が
完全に人を支配した状態となってしまう。そしてその外物に支配されてしまったような人間こそは、
天理をも滅ぼして、自分一身の欲望を極めようとすることになるのである。(好悪の節操を
信者に失わせて無限の濁愛に溺れさせようとするキリスト信仰こそは、天理を滅ぼすのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・楽記第十九より)
一般に、好みやすく愛しやすいものほど天理に違い、好みにくく愛しにくいものほど天理に適っている場合が多い。
常人が好き好み愛すべきものとして「徳」に優るものはなく、仮に徳を愛せたならば、愛することがそのまま天理に適う。
これこそは「仁」のあり方だともいえるわけで、それが可能ならば愛もふんだんに奨励されて然るべきものだが、
残念ながら徳ほどにも愛し難いものもまた稀有であり、故に仁に処ることもまた生半に可能なことではない。
(孔子も高弟の顔淵が三ヶ月間仁に違わぬ生活を送っていただけでも驚嘆している。雍也第六・七参照)
愛しやすいもの、男にとっての美女だとか女にとっての美男だとか、宝物だとかカネだとかいったものはえてして
愛しすぎることが天理に違うものであり、愛しすぎながら為すことの何もかもが不仁に根ざすことともなりかねない。
一般に、人間は五官へ快感と共に強く訴えかけてくるものほど好みやすいようにできているため、愛しやすいものが
身近にあったならさらに愛しやすくなり、疎遠でしかなかったら愛しにくくもなる。だから、仮に「近隣の者を愛せ」
などとけしかけてくるものがいたとすれば、それはすなわち「愛しやすいもののうちでも特に愛しやすいものを愛せ」
とけしかけていることにもなるわけで、これこそは好悪に対して無条件に専らであることを促す暴言ともなっている。
逆に、愛し難いものが身近にあればさらに嫌いになり、疎遠であればそんなに嫌わずに済むという法則もある。
身長2メートル超で怪物のような形相をしていたとされる孔子や、小太りで気難しかったとされる家康公のような
仁者のそばにいることが厭わしいということはあっても、好き好めるなんてこともそうそうにはあり得ないわけで、
遠近でいえば近隣にあるものを重視する性向の持ち主は、自業自得で仁を遠ざけやすくなる実例ともなっている。
ニーチェのように「遠人を愛せ」というのも荒唐無稽に過ぎるが、愛しやすいものよりは愛しにくいものを愛そうと
心がけたほうが、天理に適って仁に近づける可能性も高い。そうあるためには、まず好悪に専らであろうとする浮ついた
神経をできる限り控えて、そこから愛すべきものを愛し、愛すべきでないものを愛さないように分別していく必要がある。
常人が好き好み愛すべきものとして「徳」に優るものはなく、仮に徳を愛せたならば、愛することがそのまま天理に適う。
これこそは「仁」のあり方だともいえるわけで、それが可能ならば愛もふんだんに奨励されて然るべきものだが、
残念ながら徳ほどにも愛し難いものもまた稀有であり、故に仁に処ることもまた生半に可能なことではない。
(孔子も高弟の顔淵が三ヶ月間仁に違わぬ生活を送っていただけでも驚嘆している。雍也第六・七参照)
愛しやすいもの、男にとっての美女だとか女にとっての美男だとか、宝物だとかカネだとかいったものはえてして
愛しすぎることが天理に違うものであり、愛しすぎながら為すことの何もかもが不仁に根ざすことともなりかねない。
一般に、人間は五官へ快感と共に強く訴えかけてくるものほど好みやすいようにできているため、愛しやすいものが
身近にあったならさらに愛しやすくなり、疎遠でしかなかったら愛しにくくもなる。だから、仮に「近隣の者を愛せ」
などとけしかけてくるものがいたとすれば、それはすなわち「愛しやすいもののうちでも特に愛しやすいものを愛せ」
とけしかけていることにもなるわけで、これこそは好悪に対して無条件に専らであることを促す暴言ともなっている。
逆に、愛し難いものが身近にあればさらに嫌いになり、疎遠であればそんなに嫌わずに済むという法則もある。
身長2メートル超で怪物のような形相をしていたとされる孔子や、小太りで気難しかったとされる家康公のような
仁者のそばにいることが厭わしいということはあっても、好き好めるなんてこともそうそうにはあり得ないわけで、
遠近でいえば近隣にあるものを重視する性向の持ち主は、自業自得で仁を遠ざけやすくなる実例ともなっている。
ニーチェのように「遠人を愛せ」というのも荒唐無稽に過ぎるが、愛しやすいものよりは愛しにくいものを愛そうと
心がけたほうが、天理に適って仁に近づける可能性も高い。そうあるためには、まず好悪に専らであろうとする浮ついた
神経をできる限り控えて、そこから愛すべきものを愛し、愛すべきでないものを愛さないように分別していく必要がある。
無条件の愛に没落しきっているような人間からすれば、上記のような愛にまつわる論及からして理屈に過ぎるものと映り、
そのような論及全般を愛よりも劣後しなければならないという判断が、本能的にはたらいてしまうのに違いない。
愛こそは正義、愛ですらあれば正義なのだから、その愛に制限をかけようとしているようにすら見受けられる物言いには、
それ自体が悪であるという短絡的な評価がはたらいて、自らを正義の味方だと自認する陶酔までもが始まるのに違いない。
そしてその、無条件の愛こそを絶対正義と断ずるものの考え方が、今ありのままに人類の滅亡にすら直結している。
それをこのまま推進していけばこそ人類の滅亡すらもが免れ得ないがために、無条件の愛こそは絶対悪だったことを
実証してしまい、以って無条件の愛こそを正義だと断じていた自分たちこそがバカだったことをも証明してしまっている。
無条件の愛こそを絶対化していたような連中こそは、分別の保たれた愛を嗜むことが人一倍困難な心理状態とも化して
しまっている。分別ある愛を嗜むぐらいなら、愛全般を捨て去ってしまうほうがまだ簡単なことだったりもするわけで、
そういった連中に勧められるのは、仁愛の養生よりはむしろ仏門での出家あたりだといえる。無条件の愛を祭り上げ
すぎたことの弊害は、分別によって愛を善用せしめる選択肢の不能性としても結実してしまっているわけで、これこそは
愛そのものではなく、好悪に無条件に専らであろうとした不埒さこそが、真の問題であった証拠ともなっているる。
無条件の愛は愛しやすいものへの愛に結び付き、分別ある愛は愛すべきものへの愛に結び付く。人間にとってはただ
そうであるばかりのことなのだから、無条件の愛のほうが一般的だとか、分別ある愛が統制的だとかいったような
傍観論が、なんら人間にとって実のない論題であることをもわきまえて、我が身の程にこそ落ち着くべきだといえる。
「人の其の言を易んずるは、責め無きのみ」
「人が言葉を軽んずるのは、自らに責める所(責任感)がないからだ。
(責任感がないから、全ての願いは叶えられるみたいな虚言も放っていた)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・離婁章句上・二二より)
そのような論及全般を愛よりも劣後しなければならないという判断が、本能的にはたらいてしまうのに違いない。
愛こそは正義、愛ですらあれば正義なのだから、その愛に制限をかけようとしているようにすら見受けられる物言いには、
それ自体が悪であるという短絡的な評価がはたらいて、自らを正義の味方だと自認する陶酔までもが始まるのに違いない。
そしてその、無条件の愛こそを絶対正義と断ずるものの考え方が、今ありのままに人類の滅亡にすら直結している。
それをこのまま推進していけばこそ人類の滅亡すらもが免れ得ないがために、無条件の愛こそは絶対悪だったことを
実証してしまい、以って無条件の愛こそを正義だと断じていた自分たちこそがバカだったことをも証明してしまっている。
無条件の愛こそを絶対化していたような連中こそは、分別の保たれた愛を嗜むことが人一倍困難な心理状態とも化して
しまっている。分別ある愛を嗜むぐらいなら、愛全般を捨て去ってしまうほうがまだ簡単なことだったりもするわけで、
そういった連中に勧められるのは、仁愛の養生よりはむしろ仏門での出家あたりだといえる。無条件の愛を祭り上げ
すぎたことの弊害は、分別によって愛を善用せしめる選択肢の不能性としても結実してしまっているわけで、これこそは
愛そのものではなく、好悪に無条件に専らであろうとした不埒さこそが、真の問題であった証拠ともなっているる。
無条件の愛は愛しやすいものへの愛に結び付き、分別ある愛は愛すべきものへの愛に結び付く。人間にとってはただ
そうであるばかりのことなのだから、無条件の愛のほうが一般的だとか、分別ある愛が統制的だとかいったような
傍観論が、なんら人間にとって実のない論題であることをもわきまえて、我が身の程にこそ落ち着くべきだといえる。
「人の其の言を易んずるは、責め無きのみ」
「人が言葉を軽んずるのは、自らに責める所(責任感)がないからだ。
(責任感がないから、全ての願いは叶えられるみたいな虚言も放っていた)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・離婁章句上・二二より)
カネかモノかでいえばモノ、モノか食い物かでいえば食い物のほうが
人間にとって必要不可欠なものであり、さらにこれらの「産業媒体」を
トップダウンに統制する公務が、産業全般よりもさらに重大なものとなる。
産業統制(士)、食い物(農)、モノ(工)、カネ(商)という社会構成の
大略を、封建社会では「士農工商」の四民制として序列化してもいた。
今でも農が商工よりも重大であるという程度の認識はそれなりにあるから、
国家によって農業が保護されたりもしているが、商と工の序列はあいまいで、
かえって商のほうが工よりも上に置かれたりしている。そしてなにより、
「士」が全くの無益な存在とされ、士人階級が産業をトップダウンに統制
したりすることこそは「悪逆非道の極み」みたいな扱いまでもがされている。
士人を殊更に権威の座から引き摺り下ろすことの正当化材料としては
最たるものである民主主義、その民主主義が提唱された西洋はといえば、
始めから金持ちの代表が王侯臣官といった士人階級をも兼任し続けて来ていて、
農工商の三民を総じて公正に統治するような、立派な士人が実在した試しがない。
士人はまず、豪商や地主といった「上流階級」の金持ちのために働き、
ついでに「下層階級」である平民にもたまには恵んでやる程度の存在でしか
なかったわけで、そんな士人がいるよりもいないほうがマシであるのも確かな
ことだから、西洋で民主主義が提唱されたのも必然的なことだったといえる。
では、民主主義によって社会統治の理想が達成されたのかといえば、全くそんなことはない。
選挙制によって為政者が民からの拘束を受ける場合であれ、共産制によって生産者と
為政者が同一とのものとして扱われる場合であれ、為政が産業から独立した一人前の
仕事として認められないような事態が到来することによって、結局、為政者が資産家の
傀儡である場合と同等か、それ以上もの問題が巻き起こるばかりのこととなった。
人間にとって必要不可欠なものであり、さらにこれらの「産業媒体」を
トップダウンに統制する公務が、産業全般よりもさらに重大なものとなる。
産業統制(士)、食い物(農)、モノ(工)、カネ(商)という社会構成の
大略を、封建社会では「士農工商」の四民制として序列化してもいた。
今でも農が商工よりも重大であるという程度の認識はそれなりにあるから、
国家によって農業が保護されたりもしているが、商と工の序列はあいまいで、
かえって商のほうが工よりも上に置かれたりしている。そしてなにより、
「士」が全くの無益な存在とされ、士人階級が産業をトップダウンに統制
したりすることこそは「悪逆非道の極み」みたいな扱いまでもがされている。
士人を殊更に権威の座から引き摺り下ろすことの正当化材料としては
最たるものである民主主義、その民主主義が提唱された西洋はといえば、
始めから金持ちの代表が王侯臣官といった士人階級をも兼任し続けて来ていて、
農工商の三民を総じて公正に統治するような、立派な士人が実在した試しがない。
士人はまず、豪商や地主といった「上流階級」の金持ちのために働き、
ついでに「下層階級」である平民にもたまには恵んでやる程度の存在でしか
なかったわけで、そんな士人がいるよりもいないほうがマシであるのも確かな
ことだから、西洋で民主主義が提唱されたのも必然的なことだったといえる。
では、民主主義によって社会統治の理想が達成されたのかといえば、全くそんなことはない。
選挙制によって為政者が民からの拘束を受ける場合であれ、共産制によって生産者と
為政者が同一とのものとして扱われる場合であれ、為政が産業から独立した一人前の
仕事として認められないような事態が到来することによって、結局、為政者が資産家の
傀儡である場合と同等か、それ以上もの問題が巻き起こるばかりのこととなった。
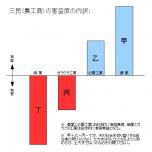 真に必要なのは、為政者と、資産家を含む全ての産業従事者との間に一線を引いて、
真に必要なのは、為政者と、資産家を含む全ての産業従事者との間に一線を引いて、 資産家といえども産業階級の一員でしかなく、しかも着実に食い物やモノを自力で作って
くださっている農夫や工業技術者などと比べれば、格下の産業従事者でしかないのだということを
世の中総出を挙げて認識し、資産家こそを最底辺の社会的立場に追い込むことだといえる。
そのために重要となるのが、一つには儒学のような権力道徳学の流布であり、もう一つが、
国家レベルの武力の洗練だといえる。古代ローマ皇帝や現アメリカ大統領なども、軍の統帥権を
保有していることが大権掌握の最もな根拠となっている。しかし、あまりにも過剰な軍備は、
それ自体が資産家などからの援助によってまでの維持に務めなければならないお荷物となってしまう。
結果、皇帝や大統領といえども軍産複合体の言いなりにならざるを得ないようなことにも
なってしまうわけで、そのうような事態を招かないために、軍備はなるべく最低限に止め、
常用の武器も日本刀のような、低コスト高パフォーマンスのものであるように心がけるべきである。
そこまでして士産の分離を心がけたならば、士人こそはあらゆる産業(金融を含む)の上に立つ、
「人の花形」たる存在ともなり得るわけで、また士人が人々の上に立つことにも、「社会保障の要」
という紛れもない根拠が伴うことにもなる。士人が忠節に務めたならば、それがそのまま産業従事者
同士での人間関係の雛形ともなるし、また士人が孝養に努めたならば、それがそのまま年金破綻後の
世の中での生き抜き方の見本ともなっていく。立派な士人による統治を完全にかなぐり捨てた
世の中が最終的にどうなるかという見本としては、現代社会ほどにもうってつけなものはなく、
結果はといえば「このままだと確実に破滅が免れ得ないと」いうものだった。農工商の三民の
序列を重んずるだけでなく、三民の上に士人をおく四民制全体が必要不可欠な役割を担っていた
ことが現代社会の体たらくによってこそ判明してるのだから、現代社会の体質からの一概な脱却
こそを本気で推し進めていったなら、「禍転じて福と為す」こともそんなに難しいことではない。
「禹は吾れ間然するところ無し。飲食を菲くして孝を鬼神にまで致し、衣服を悪しくして
美を黻冕にまで致す。宮室を卑くして力を溝洫に尽くす。禹は吾れ間然するところ無し」
「夏の禹帝には一点の非の打ち所も無い。自らの飲食を粗末にしながら、孝養は鬼籍の先祖にまで尽くし、
常用の衣服も簡素なものでありながら、位を表す前垂や冠だけは豪華なものとされた。住まいとなる宮室はこれまた
ボロ家でありながら、感慨の水路を立派にすることには力を尽くされた。夏の禹帝には一点の非の打ち所も無い。
(飲食は粗末にしても、位を表す衣装は場合によっては金銀なども用いて飾り付け、序列の徹底を促していた。
全体的に、自分一身の利益よりも天下の公益を禹帝が優先していたことを評する記述となっている)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・泰伯第八・二一より)
美を黻冕にまで致す。宮室を卑くして力を溝洫に尽くす。禹は吾れ間然するところ無し」
「夏の禹帝には一点の非の打ち所も無い。自らの飲食を粗末にしながら、孝養は鬼籍の先祖にまで尽くし、
常用の衣服も簡素なものでありながら、位を表す前垂や冠だけは豪華なものとされた。住まいとなる宮室はこれまた
ボロ家でありながら、感慨の水路を立派にすることには力を尽くされた。夏の禹帝には一点の非の打ち所も無い。
(飲食は粗末にしても、位を表す衣装は場合によっては金銀なども用いて飾り付け、序列の徹底を促していた。
全体的に、自分一身の利益よりも天下の公益を禹帝が優先していたことを評する記述となっている)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・泰伯第八・二一より)
 愛ばかりに振り切れてバカになることでも、
愛ばかりに振り切れてバカになることでも、 知識ばかりに振り切れて血も涙もなくなることでもなく、
高度に愛と上知とを両立させていくことが仁の発端ともなる。
幼い我が子が危険に晒されているときに母が抱く恐れなどは、
当然我が子への愛に根ざしているが、かといって愛に溺れきって
蒙昧なままでいたなら、我が子を危険から守ることも叶わない。
だから、健全な母親が幼い我が子などに対して抱く思いは、
えてして愛と知力とをそれなりに両立したものとなる。
世で大業を為す男もまた、そのような愛と知力との両立を以ってことに臨むべきで、
それができたなら自然と言行が仁徳に根ざしたものともなる。それぐらいの男であって
初めて、女が立派な母親である並みの威厳が保たれることにもなるわけで、逆に、
情愛一極や機械的知識一極に振れ切って、ろくに仁徳も養えないというのであれば、
確かにそのような男は、女にすら見下されても仕方のない男止まりであるのだと言える。
(一定数以上の女が立派な母たり得ることで、初めて世の中も成り立っているのだから)
「愛に溺れる以上は知識なんか捨てちまえ、知識に頼る以上は情愛なんか無視しろ、
それでこそTPOをわきまえられた立派な大人だ」なんていう情報洗脳までもが今は潜在的に
まかり通っていたりもするが、これもまた甚だしい転倒夢想の一種で、本当は知と愛を
両立することもできないような人間こそが生粋の未熟者であり、そうあってはならない
見本としてこそ扱うべきなのである。智と愛の両立を仁徳にまで昇華させられていた
士大夫こそが尊ばれていた封建社会においても、情愛一辺倒に陥って獣のごとき情欲を
貪っていた町人などもいなくはなかったわけだけども、だからといって立派な大人扱いなどを
されることもなく、かえって「好色一代男」のような物笑いの種にすらなっていたのである。
 今という時代は、知と愛の両立なんかできない人間、
今という時代は、知と愛の両立なんかできない人間、 愛する以上は馬鹿な愛(白痴)に振れ切り、知識に頼る以上は血も涙も無い
頭でっかち(悪霊)に振れ切るような輩ばかりが保護されている時代である。
しかも、そのような未熟者たちが不正に保護されていたことが、昨今の金融界の不正な
金利操作の発覚などと共に露呈してしまってもいる。金融システムを裏から操作できるような
悪知恵の持ち主が、情欲に振り切れてバカと化すようなカモばかりを低金利の融資で保護し、
世界を左右できる規模の巨万の富を、バカか悪知恵の両極端でしかいられない未熟者たちだけで
独占していたことがばらされたわけで、それに連動して、知と愛を高度に両立させられる
仁者こそは、権力の座から強制的に排除されていたことまでもが明かされてしまったのである。
知識ばかりに頼りきって、血も涙もない疑心暗鬼と化すことが批判されることは
これまでにもあったが、情欲に振り切れて白痴状態と化すことは、たとえば辛い仕事を
やらされている人間の気晴らしなどとしては、かえって推奨すらされているのが現状である。
本当はそれもまたよくないことである、のみならず、白痴並みに蒙昧な情欲への陥りこそは、
心ない知識の鬼にとっての生みの親ですらあったことが、キリスト教圏においてこそ
無機質な機械的知識ばかりが大量に蓄積されて来たことからも明らかなのである。
濁愛か悪知恵かの両極端でしかいられない人間が、仁者たる男以下であるのはもちろんのこと、
我が子を必死で守ろうとする、慈愛ある母ほどもの品性すら保てていない存在であることも
上に書いた通りであり、幼い我が子を惜しみ無き愛と、相応の知恵とで慈しむことを、世の
母親たちの誰しもが放棄したりしたならば(少子高齢化などによって)即座に世の中も
ままならなくなるようにして、バカか悪知恵かの両極端でしかいられない未熟者ばかりが
世を治める大権を牛耳り続けたなら、当然それによっても世の中がままならなくなるのである。
大知はおろか、人並みの知見すら損壊してしまう程の劣情にかられることが、完全に禁止される
とまでいかずとも、決していいものなどとは見なされない程度の扱いは受けて然るべきである。
当然、そのような白痴状態への陥りを「神の降臨」だなどと嘯く病気も去ってしまうべきだ。
「礼の多きを以って貴しと為すは、其の心を外にするを以ってなり。〜
礼の少なきを以って貴しと為すは、其の心を内にするを以ってなり。〜
古えの聖人は之れを内にするを尊しと為し、之れを外にするを楽しみと為す。
之れを少なくするを貴しと為し、之れを多くするを美と為す。是の故に先王の
礼を制するや、多くすべからず、寡なくすべからず、唯だ其れ稱うのみにす」
「礼の実践が多大であることが貴ばれるのは、その内なる敬心が外部に発露するためである。逆に、
礼の実践が寡少であることが貴ばれることもあり、これは内なる敬心の養いに務めている場合である。
昔の聖人は内なる敬心の養いこそをより尊貴とし、それを外部に発露させることはむしろ楽しみとしていた。
敬心の養いに専らなために外的な礼儀が寡少となることをより貴いこととし、ついにはその敬心が発露
されることは善美なこととした。そのため先王の定めた礼制もまた、多すぎることも少なすぎることも
よしとされず、ただ融通に適うように心がけられていた。(他者への情欲によって、自らの思い上がりが
肥大化するのとは逆に、自らの敬心の養いがあってから、それが他者への礼節として発露される。
自意識過剰の思い上がりよりも恭敬のほうが、自らに養う上で自己本位である必要があるのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・礼器第十より)
とまでいかずとも、決していいものなどとは見なされない程度の扱いは受けて然るべきである。
当然、そのような白痴状態への陥りを「神の降臨」だなどと嘯く病気も去ってしまうべきだ。
「礼の多きを以って貴しと為すは、其の心を外にするを以ってなり。〜
礼の少なきを以って貴しと為すは、其の心を内にするを以ってなり。〜
古えの聖人は之れを内にするを尊しと為し、之れを外にするを楽しみと為す。
之れを少なくするを貴しと為し、之れを多くするを美と為す。是の故に先王の
礼を制するや、多くすべからず、寡なくすべからず、唯だ其れ稱うのみにす」
「礼の実践が多大であることが貴ばれるのは、その内なる敬心が外部に発露するためである。逆に、
礼の実践が寡少であることが貴ばれることもあり、これは内なる敬心の養いに務めている場合である。
昔の聖人は内なる敬心の養いこそをより尊貴とし、それを外部に発露させることはむしろ楽しみとしていた。
敬心の養いに専らなために外的な礼儀が寡少となることをより貴いこととし、ついにはその敬心が発露
されることは善美なこととした。そのため先王の定めた礼制もまた、多すぎることも少なすぎることも
よしとされず、ただ融通に適うように心がけられていた。(他者への情欲によって、自らの思い上がりが
肥大化するのとは逆に、自らの敬心の養いがあってから、それが他者への礼節として発露される。
自意識過剰の思い上がりよりも恭敬のほうが、自らに養う上で自己本位である必要があるのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・礼器第十より)
 とにかく働きまくる奴隷状態でも、有閑階級としての悠々自適状態でもなく、
とにかく働きまくる奴隷状態でも、有閑階級としての悠々自適状態でもなく、 徒労は厭いながらも、着実な成果に結び付く仕事にかけては熱心である
ことが、人が一生を送る上で最も生きがいを感じられる方策ともなる。
人は皆いつかは必ず死ぬ、そのことに対して過度の悲哀を抱いたりするのなら、
それはやはり自分の生き方がどこか不健全であるからで、本当に生きがいの
ある生涯を尽くせたならば、人という生き物は臨終に際して悲哀を抱くどころか、
「十分な役目を果たした」という大きな満足と共にすらいることができるのである。
因果関係でいえば、生きがいのある人生が原因で、満足な死が結果である。
同様に、生きがいのない人生が原因となって、不満だらけの死という結果にも至る。
このうちの、満足な死を「涅槃」として教理の中心にも据えているのが仏教で、
そこから生きがいのある人生の送り方を導き出して、それを実践面の教義ともしている。
逆に、生きがいのない人生、不満だらけの死を大前提においてるのが聖書信仰で、
そのような無様な生死が神の導きによる形而上への昇天によって救われるとしている。
生きがいのある人生を送ることで満足な死を迎えるぐらいのことは、儒学だって
大前提としているが、「未だ生を知らず、焉んぞ死を知らん(先進第十一・一二)」
とあるように、生死論にかけて殊更であるようなことから敬遠するようにもしている。
 生きがいのない人生と不満だらけの死を大前提としているような不具者からすれば、
生きがいのない人生と不満だらけの死を大前提としているような不具者からすれば、 世俗での活動の探求ばかりにもっぱらであろうとする儒学の実践者のあり方などは、
特に俗物然として見えるのだろうけども、その活動はといえば、君子としての
仁政の実現に特化されていたりと、それなりの筋が通っている。商人階級だった
古代ユダヤ人はおろか、古代オリエントの諸々の為政者ですらもが君子としての
仁政を心がけていたような試しはほとんどなく、その証拠に、為政者たちが私的に
貯め込んだ財によって無益な土建を繰り返していた痕跡がピラミッドなどとして
遺されてもいるのである。(中国でも、始皇帝陵墓などが近年発掘されているが)
世俗での活動の内に、君子としての仁政などを想定したことすらないような人間が、
そのような活動にかけてこそ熱心であろうとする儒者の「全てを知っている」などと
うそぶく資格は微塵もない。君子としての仁政にまで至れたなら、人は必ず最高に
生きがいのある生と、大満足な死とを享受できるわけだから、そんな因果関係など
始めから露ほどにも知らずに、世俗の活動全般が生きがいのない生と、不満だらけの
死とをもたらすばかりであるなどと決め込むのは、ただのもの知らずだといえる。
俗世においては、儒者の志すようなある種の活動にかけて、生きがいと知足に満ちた
生死を得られることが確かだし、また、超俗においても仏教などにおいて、存命中
の浄行によって「生まれ変わるよりも至上な」涅槃を実現する方策が説かれている。
今生の生死が、生きがいのなさや、不満だらけの死ばかりに見舞われたりしないための
方法は世俗超俗いずれにおいても拓けているのだから、そのような不具な生死を大前提
とした形而上への救いの希求などに拘泥する正当性なども、もはやないのだといえる。
「化者に比るまで、土を膚に親しむる無きは、人の心に於いて独り恔きこと無からんや」
「親の身体が完全に朽ちてなくなるまで、その皮膚すらも土に近づけないように、
孝養を尽くすことほど、誰一人として快さを抱かない者のない行いがあるだろうか。
(いつかは土に帰る身であればこそ、努力が至上の快さにつながる実例)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・公孫丑章句下・七より)
「親の身体が完全に朽ちてなくなるまで、その皮膚すらも土に近づけないように、
孝養を尽くすことほど、誰一人として快さを抱かない者のない行いがあるだろうか。
(いつかは土に帰る身であればこそ、努力が至上の快さにつながる実例)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・公孫丑章句下・七より)
仁徳豊かな君子として自らが世に君臨することが、着実に「生きていないこと」よりも有意義な生を本人にもたらす。
だからこそ、そのような人間が死ぬに際しても、心から生きがいのある人生を送れたと納得もできるのである。
「生きていないこと」よりもさらに意義のない人生もまた確かにあり、そのような人生はすべからく、
君子としての人のあり方に反した人生を送っている。いわゆる「小人」の人生だけども、小人だからといって
必ずしも被支配階級に甘んじているとも限らず、自らの品性は小人であるままに権力だけは手に入れて、
いるよりもいないほうがマシなほどに有害無益な暴政を働く権力犯罪者になってしまうことまでもあるわけで、
その時にこそ「あるよりもないほうがマシな生」もまた極まる。ただ品性が小人止まりなだけでも、
えてして劣等感からなる苦しみなどにあえいだりするものだが、その苦しみを克服するために、「小人のままでの
権力の掌握」という間違った手段に及んだ挙句に、余計に生きていることの苦しみを増大化させてしまうのである。
権力を掌握するかしないかという以前に、まず人が「論語」にあるような意味での「君子」であろうとすることが本来
からの品性の向上につながり、「小人」であってしまうことが本来からの品性の堕落につながってしまう。人としての
本来の品性が君子級に上等であったなら、権力なんか掌握しなくたってそれなりに有意義な生を送れるし、逆に、本来の
品性が小人止まりなのでは、どんなに莫大な権力を掌握してみたところで、相変わらず意義のない生のままであり続ける。
仏門での出家ほどもの、本格的な超俗領域に立ち入るのでもない限りは、このあたりの分別が十分に普遍的な
ものでもあり得る。釈迦もまた、宮女たちの裸踊りに嫌気が差して実家の王家を抜け出して乞食行に邁進したと
いうから、釈迦の実家だった王家からして「仁政家」であったとまでは考えにくいわけで、王家が王家だからといって
酒池肉林の遊興に耽ることが当たり前であるかのような風潮にこそ、釈迦も反発したのだろうことが窺えるのである。
だからこそ、そのような人間が死ぬに際しても、心から生きがいのある人生を送れたと納得もできるのである。
「生きていないこと」よりもさらに意義のない人生もまた確かにあり、そのような人生はすべからく、
君子としての人のあり方に反した人生を送っている。いわゆる「小人」の人生だけども、小人だからといって
必ずしも被支配階級に甘んじているとも限らず、自らの品性は小人であるままに権力だけは手に入れて、
いるよりもいないほうがマシなほどに有害無益な暴政を働く権力犯罪者になってしまうことまでもあるわけで、
その時にこそ「あるよりもないほうがマシな生」もまた極まる。ただ品性が小人止まりなだけでも、
えてして劣等感からなる苦しみなどにあえいだりするものだが、その苦しみを克服するために、「小人のままでの
権力の掌握」という間違った手段に及んだ挙句に、余計に生きていることの苦しみを増大化させてしまうのである。
権力を掌握するかしないかという以前に、まず人が「論語」にあるような意味での「君子」であろうとすることが本来
からの品性の向上につながり、「小人」であってしまうことが本来からの品性の堕落につながってしまう。人としての
本来の品性が君子級に上等であったなら、権力なんか掌握しなくたってそれなりに有意義な生を送れるし、逆に、本来の
品性が小人止まりなのでは、どんなに莫大な権力を掌握してみたところで、相変わらず意義のない生のままであり続ける。
仏門での出家ほどもの、本格的な超俗領域に立ち入るのでもない限りは、このあたりの分別が十分に普遍的な
ものでもあり得る。釈迦もまた、宮女たちの裸踊りに嫌気が差して実家の王家を抜け出して乞食行に邁進したと
いうから、釈迦の実家だった王家からして「仁政家」であったとまでは考えにくいわけで、王家が王家だからといって
酒池肉林の遊興に耽ることが当たり前であるかのような風潮にこそ、釈迦も反発したのだろうことが窺えるのである。
王業全般を卑俗なものとして諦めた釈迦の振る舞いと、王業も清浄であることに務めたなら相当な生きがいに繋がり得る
こととの矛盾は、大乗仏教において止揚され、仏菩薩縁覚声聞の四乗には及ばないものの、俗世での清浄な統治に励む
転輪聖王だとか、半ば超俗に足を踏み入れつつ帝王でもある帝釈天だとか数多の天王だとかいった尊格が提示されている。
「華厳経」でも、自らは世俗での帝業に励むものが、在家信者として仏門に帰依することが、より一層の帝国の繁栄に繋がる
などとも宣伝していて、仏門においても、清浄な君子としての業務にそれなりの価値があることが認められているのである。
世俗での君子としての業務が盛大であるということは、世の中での最大級の善行に励んでいるということでもある。
それを試みた上で未だ飽き足らないというのならまだしも、そもそもそんな試みに及んだことはおろか、
「君子としての王業が最大級の善行となる」という認知すら疎かなままでいる。そのような連中が中東以西の
世界のほぼ全てを占めているわけで、それほどにも知見や経験が未熟なままに「人生など苦しみの塊でしかない」
などとほざくのでは、耳を貸してやるにも足らないほどにも身の程知らずな戯れ言止まりでしかないといえる。
最大級の善行を為してなお飽き足らないというのならまだしも、そもそも善行なんかやったことも、その価値を計り知った
こともないような分際でいて、「生きることに価値が無い」などと決め付けるのは、井の中の蛙の大海への悪口でしかない。
まだ人生も世俗も諦観する資格もないうちから、狭隘な了見だけに基づいて人生や世俗を否定してかかるような連中は、
お坊さんや仙人が偉大であるのとは真逆に、常人以下の品性しか持たない賤人でしかないということが言えるのである。
こととの矛盾は、大乗仏教において止揚され、仏菩薩縁覚声聞の四乗には及ばないものの、俗世での清浄な統治に励む
転輪聖王だとか、半ば超俗に足を踏み入れつつ帝王でもある帝釈天だとか数多の天王だとかいった尊格が提示されている。
「華厳経」でも、自らは世俗での帝業に励むものが、在家信者として仏門に帰依することが、より一層の帝国の繁栄に繋がる
などとも宣伝していて、仏門においても、清浄な君子としての業務にそれなりの価値があることが認められているのである。
世俗での君子としての業務が盛大であるということは、世の中での最大級の善行に励んでいるということでもある。
それを試みた上で未だ飽き足らないというのならまだしも、そもそもそんな試みに及んだことはおろか、
「君子としての王業が最大級の善行となる」という認知すら疎かなままでいる。そのような連中が中東以西の
世界のほぼ全てを占めているわけで、それほどにも知見や経験が未熟なままに「人生など苦しみの塊でしかない」
などとほざくのでは、耳を貸してやるにも足らないほどにも身の程知らずな戯れ言止まりでしかないといえる。
最大級の善行を為してなお飽き足らないというのならまだしも、そもそも善行なんかやったことも、その価値を計り知った
こともないような分際でいて、「生きることに価値が無い」などと決め付けるのは、井の中の蛙の大海への悪口でしかない。
まだ人生も世俗も諦観する資格もないうちから、狭隘な了見だけに基づいて人生や世俗を否定してかかるような連中は、
お坊さんや仙人が偉大であるのとは真逆に、常人以下の品性しか持たない賤人でしかないということが言えるのである。
「小球大球を受け、下国の綴旒と為りて、天の休を何う。
競わず絿らず、剛ならず柔ならず、政を敷くに優優と、百禄も是に遒まる」
「大小諸々の勅命を受け、下位の国々の見本たる本流ともなって、天からの福を受ける。
専らに競おうとも貪ろうともせず、剛に過ぎず柔に過ぎず、悠然として政を敷き、天下の富も皆なここに集まるのである。
(仁徳によって天下を治めるためにこそ、不埒な競争意識などは捨て去る必要があるし、それでこそ天の休命にも適う)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・頌・商頌・長発より)
競わず絿らず、剛ならず柔ならず、政を敷くに優優と、百禄も是に遒まる」
「大小諸々の勅命を受け、下位の国々の見本たる本流ともなって、天からの福を受ける。
専らに競おうとも貪ろうともせず、剛に過ぎず柔に過ぎず、悠然として政を敷き、天下の富も皆なここに集まるのである。
(仁徳によって天下を治めるためにこそ、不埒な競争意識などは捨て去る必要があるし、それでこそ天の休命にも適う)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・頌・商頌・長発より)
自ら進んで冤罪の被害者となって、重罪人バラバの代わりに死刑になった
イエスの暴挙を、判事であったローマ総督のピラトもそのまま放任した。
「飛んで火にいる夏の虫」同然の所業に及んだイエスに対する不当処罰は、
まだ許せるところがあるし、また冤罪ほど事態のこじれる事件も他にないものだから、
「冤罪を誘発した」という罪だけによって、イエスへの磔刑を正当化してもいいぐらいのものである。
問題は、それによって死刑囚だった強盗殺人犯バラバを無罪放免に処したことで、これにより
ローマ帝国は法治機構の信頼性の破綻を招き、カトリックに全土を征服されることともなった。
キリスト教に「権力」を強奪されたローマ圏は一挙に閉塞状態と化し、
俗に言う「暗黒時代」を800年以上に渡り経験することとなった。ローマ帝国による支配を
カトリックが乗っ取ったからといって、そこで法治支配以上に優良な統治が敷かれたなどと
いうこともなく、むしろ誰しもが餓鬼畜生と化した状態をカルト教義によって無理やり治めて
いくという状態に移行してしまったわけだから、「暗黒」と化したのも当然のことだといえる。
キリスト教がローマ帝国を乗っ取れたのは、上記の通り、ローマ総督府が自分たちの法治支配を
イエスの暴挙の容認によって破綻させてしまったからである。ではなぜ、イエスの暴挙によって
法治支配が破綻せざるを得なくなったのかといえば、古代ローマには権力道徳がなかったからだ。
イエスの言行は、孔孟が体系化したような権力道徳にことごとく違背している。すなわち
「権力犯罪」の体系の流布だったわけだから、それをしてイエスを妖言罪などによって処罰し、
バラバのような他の死刑囚も代わりに釈放したりもせずに、粛々と刑を実行すればよかったのである。
しかし、当時のローマやイスラエルには体系化された純正な権力道徳などはなかったから、
総督ピラトも大衆に扇動されて分けも分からないままにイエスを処刑し、代わりにバラバを
放免するという、権力者にあるまじき大いなる過ちを犯した。実定法にまつわる知識はあっても、
仁義道徳にまつわる知識まではなかったから、イエスの妖言に十分に対応しきることもできなかった。
イエスの暴挙を、判事であったローマ総督のピラトもそのまま放任した。
「飛んで火にいる夏の虫」同然の所業に及んだイエスに対する不当処罰は、
まだ許せるところがあるし、また冤罪ほど事態のこじれる事件も他にないものだから、
「冤罪を誘発した」という罪だけによって、イエスへの磔刑を正当化してもいいぐらいのものである。
問題は、それによって死刑囚だった強盗殺人犯バラバを無罪放免に処したことで、これにより
ローマ帝国は法治機構の信頼性の破綻を招き、カトリックに全土を征服されることともなった。
キリスト教に「権力」を強奪されたローマ圏は一挙に閉塞状態と化し、
俗に言う「暗黒時代」を800年以上に渡り経験することとなった。ローマ帝国による支配を
カトリックが乗っ取ったからといって、そこで法治支配以上に優良な統治が敷かれたなどと
いうこともなく、むしろ誰しもが餓鬼畜生と化した状態をカルト教義によって無理やり治めて
いくという状態に移行してしまったわけだから、「暗黒」と化したのも当然のことだといえる。
キリスト教がローマ帝国を乗っ取れたのは、上記の通り、ローマ総督府が自分たちの法治支配を
イエスの暴挙の容認によって破綻させてしまったからである。ではなぜ、イエスの暴挙によって
法治支配が破綻せざるを得なくなったのかといえば、古代ローマには権力道徳がなかったからだ。
イエスの言行は、孔孟が体系化したような権力道徳にことごとく違背している。すなわち
「権力犯罪」の体系の流布だったわけだから、それをしてイエスを妖言罪などによって処罰し、
バラバのような他の死刑囚も代わりに釈放したりもせずに、粛々と刑を実行すればよかったのである。
しかし、当時のローマやイスラエルには体系化された純正な権力道徳などはなかったから、
総督ピラトも大衆に扇動されて分けも分からないままにイエスを処刑し、代わりにバラバを
放免するという、権力者にあるまじき大いなる過ちを犯した。実定法にまつわる知識はあっても、
仁義道徳にまつわる知識まではなかったから、イエスの妖言に十分に対応しきることもできなかった。
これこそは、権力者には法律だけでなく、仁徳の知識や実践もまたなければならない証拠にもなっている。
仁徳なんか全くなくて、法律しか知らないというのであれば、イエス級に不埒なカルト犯罪者を
裁ききることはできない。最悪、そのせいでローマ帝国がカトリックに乗っ取られて、800年以上もの
暗黒時代を到来させたようなことにだってなりかねないわけだから、そのような過ちを二度と
繰り返さないためにも、法律だけでなく、仁徳にまつわる素養までもが権力者たる者には必須だといえる。
「君子にして不仁なる者有らんか。未だ小人にして仁なる者あらざるなり」
「権力を持つ君子であっても不仁なものはいるが、権力を持たない小人でいながら仁者たり得た者はいない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・憲問第十四・七より)
孔子も士大夫としての役儀などに与りつつ仁徳のあり方を体系化していった。一生涯小人階級だったイエス
などが仁者だったはずはないし、総督ピラトらもまた、権力者ではあっても仁者ではなかったようである。
イエスのような人間の言行に権力が征服されることは、原理的に必ず不仁の蔓延につながる。
権力者が仁徳の養いによって不仁に対する防波堤を築き、不仁が権力を乗っ取るようなことがないように
心がけないのであれば、世の中が数百年規模の暗黒に見舞われるぐらいのことはいくらでもあり得る。
そういう時代にも貞正を貫く人間もまたいた所で、大局として人々が楽果に与れる頻度は地に墜ちる。
誰一人として環境からの幸福には与れなくなる、そのような情勢を二度と招かないようにしたいものである。
「権量を謹み、法度を審らかにし、廃官を修めれば、四方の政行われん」
「権力の扱いをよく慎んで、制度もよく整えて、廃官にまで配慮を行き届かせれば、四方の政治もうまく行く。
(権力を手に入れたからといって驕り高ぶって欲しいままでいたりすれば、政治もうまく行かないのである。
不仁な小人だったイエスの驕り高ぶりを引き継いだローマ・カトリックも、ろくな政治は為せなかった)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・堯曰第二十・二より)
仁徳なんか全くなくて、法律しか知らないというのであれば、イエス級に不埒なカルト犯罪者を
裁ききることはできない。最悪、そのせいでローマ帝国がカトリックに乗っ取られて、800年以上もの
暗黒時代を到来させたようなことにだってなりかねないわけだから、そのような過ちを二度と
繰り返さないためにも、法律だけでなく、仁徳にまつわる素養までもが権力者たる者には必須だといえる。
「君子にして不仁なる者有らんか。未だ小人にして仁なる者あらざるなり」
「権力を持つ君子であっても不仁なものはいるが、権力を持たない小人でいながら仁者たり得た者はいない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・憲問第十四・七より)
孔子も士大夫としての役儀などに与りつつ仁徳のあり方を体系化していった。一生涯小人階級だったイエス
などが仁者だったはずはないし、総督ピラトらもまた、権力者ではあっても仁者ではなかったようである。
イエスのような人間の言行に権力が征服されることは、原理的に必ず不仁の蔓延につながる。
権力者が仁徳の養いによって不仁に対する防波堤を築き、不仁が権力を乗っ取るようなことがないように
心がけないのであれば、世の中が数百年規模の暗黒に見舞われるぐらいのことはいくらでもあり得る。
そういう時代にも貞正を貫く人間もまたいた所で、大局として人々が楽果に与れる頻度は地に墜ちる。
誰一人として環境からの幸福には与れなくなる、そのような情勢を二度と招かないようにしたいものである。
「権量を謹み、法度を審らかにし、廃官を修めれば、四方の政行われん」
「権力の扱いをよく慎んで、制度もよく整えて、廃官にまで配慮を行き届かせれば、四方の政治もうまく行く。
(権力を手に入れたからといって驕り高ぶって欲しいままでいたりすれば、政治もうまく行かないのである。
不仁な小人だったイエスの驕り高ぶりを引き継いだローマ・カトリックも、ろくな政治は為せなかった)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・堯曰第二十・二より)
陰か陽かでいえば、生が陰で死が陽である。
もっと正確に言えば、生死の流転が陰で、不生不滅が陽である。
生きてるうちに多大なる罪業を重ねて、死後にも地獄餓鬼畜生の三悪趣を永遠にさ迷い続けなければ
ならないようなザマに陥ってしまっている者であれば、死後の世界が光明に満ちた極楽浄土で
あるなんてこともなく、むしろ死後にこそより暗い闇が待ち受けているということにすらなる。
死後に光明が待ち受けているというのならば、それは生死の流転を解脱した涅槃が近いということで、
場合によっては生きてるうちから不生不滅の境地(有余涅槃)に至れることもある。そういう者に
とってこそ確実に生こそは陰で、死の先こそは陽であり、生きてるうちにも、生の暗がりを
いかに光明で照らしていくかということが主要な課題となっていくのである。
「生きる」ということの業を、より深刻なものと化していくような行いは、大体が悪業に繋がる。
悪業だから生死の流転を多重化させ、本来は死後にあるはずの光明をより遠ざけることともなる。
だから、生死の流転を解脱した涅槃に至るために、仏門は出家による抜業因種をも企図する。本格の
仏門ならば妻子を持つことすらをも絶って、この世に出家者が残すカルマを最低限に止め置こうとする。
上述の、二つの選択肢とはまた別の選択肢がもう一つあって、世俗での活動にはやはり邁進して
いくものの、その活動を世のため人のため、国家鎮護や天下平定のためだけに限って、積極的に
自他の悪業を食い止めていこうとするものである。これこそは儒家の選択肢でもあるし、原始仏教と
バラモン教の折衷とでもいうべき大乗仏教などが根幹の理念として据えているものでもある。
原始仏教のように、自らがこの世に残すカルマをできる限り最小限に止めおくことと、儒家や大乗仏教の
ように、天下国家の大局からの悪業の矮小化に務めていくことと、いずれもが「自らが生きる」ということ
ばかりに専らであるのでは務まらない代物となっている。孔子や孟子ですら「天命のためには命をも捨てる」
というようなことをいい、周の放伐革命に抗議して首陽山に餓死した伯夷・叔世兄弟を聖人と見なしてもいる。
もっと正確に言えば、生死の流転が陰で、不生不滅が陽である。
生きてるうちに多大なる罪業を重ねて、死後にも地獄餓鬼畜生の三悪趣を永遠にさ迷い続けなければ
ならないようなザマに陥ってしまっている者であれば、死後の世界が光明に満ちた極楽浄土で
あるなんてこともなく、むしろ死後にこそより暗い闇が待ち受けているということにすらなる。
死後に光明が待ち受けているというのならば、それは生死の流転を解脱した涅槃が近いということで、
場合によっては生きてるうちから不生不滅の境地(有余涅槃)に至れることもある。そういう者に
とってこそ確実に生こそは陰で、死の先こそは陽であり、生きてるうちにも、生の暗がりを
いかに光明で照らしていくかということが主要な課題となっていくのである。
「生きる」ということの業を、より深刻なものと化していくような行いは、大体が悪業に繋がる。
悪業だから生死の流転を多重化させ、本来は死後にあるはずの光明をより遠ざけることともなる。
だから、生死の流転を解脱した涅槃に至るために、仏門は出家による抜業因種をも企図する。本格の
仏門ならば妻子を持つことすらをも絶って、この世に出家者が残すカルマを最低限に止め置こうとする。
上述の、二つの選択肢とはまた別の選択肢がもう一つあって、世俗での活動にはやはり邁進して
いくものの、その活動を世のため人のため、国家鎮護や天下平定のためだけに限って、積極的に
自他の悪業を食い止めていこうとするものである。これこそは儒家の選択肢でもあるし、原始仏教と
バラモン教の折衷とでもいうべき大乗仏教などが根幹の理念として据えているものでもある。
原始仏教のように、自らがこの世に残すカルマをできる限り最小限に止めおくことと、儒家や大乗仏教の
ように、天下国家の大局からの悪業の矮小化に務めていくことと、いずれもが「自らが生きる」ということ
ばかりに専らであるのでは務まらない代物となっている。孔子や孟子ですら「天命のためには命をも捨てる」
というようなことをいい、周の放伐革命に抗議して首陽山に餓死した伯夷・叔世兄弟を聖人と見なしてもいる。
ただ自らが生きることばかりに専らで、天命をも無視しての遊興ばかりに耽るというのであれば、仏門での
出家修行などが覚束ないのはもちろんのこと、儒学を実践する仁政家としてですら大成できたりすることはない。
それでいて、儒学の経典である四書五経などに書かれている教条は、人として嗜むべき最低限の
道徳的なわきまえばかりとなってもいる。してみれば、人間が生きることばかりに専らであるということは、
即座に最低限の人としてのわきまえをも失った、餓鬼畜生の振る舞いに直結してしまうということである。
人は本来、生きることばかりに専らでいたりしてはいけない生き物なのであり、もしも
そのようでいたならば、動物以上の知能や技術力もあいまって、地獄に堕する悪業をも動物以上に
すら深めてしまうことになる。文明社会をも築き上げられる知能や技術の持ち主であればこそ、
人間は生きることばかりに専らであることが「過ぎたるはなお及ばざるが如し」にも直結して
しまうものだから、最低でも儒説程度の生存欲に対する自制は嗜んでおくべきなのだといえる。
人間であればこそ、自分が生きることばかりに専らであることが、暗くて陰鬱な死へとも直結してしまう。
だからこそ、生きることに対して消極的な教条がままある、儒家や仏門に従うぐらいでちょうどいいのである。
「君子に終わると曰い、小人に死と曰う」
「君子が『身を終える』ということを、小人は『死ぬ』という。
(君子は身を終えても名を残すから『死ぬ』とは言わない。『天子がお隠れになる』なども
これに準拠した語法だといえる。そもそも『死』などを強調している時点で小人なのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・檀弓上第三より)
出家修行などが覚束ないのはもちろんのこと、儒学を実践する仁政家としてですら大成できたりすることはない。
それでいて、儒学の経典である四書五経などに書かれている教条は、人として嗜むべき最低限の
道徳的なわきまえばかりとなってもいる。してみれば、人間が生きることばかりに専らであるということは、
即座に最低限の人としてのわきまえをも失った、餓鬼畜生の振る舞いに直結してしまうということである。
人は本来、生きることばかりに専らでいたりしてはいけない生き物なのであり、もしも
そのようでいたならば、動物以上の知能や技術力もあいまって、地獄に堕する悪業をも動物以上に
すら深めてしまうことになる。文明社会をも築き上げられる知能や技術の持ち主であればこそ、
人間は生きることばかりに専らであることが「過ぎたるはなお及ばざるが如し」にも直結して
しまうものだから、最低でも儒説程度の生存欲に対する自制は嗜んでおくべきなのだといえる。
人間であればこそ、自分が生きることばかりに専らであることが、暗くて陰鬱な死へとも直結してしまう。
だからこそ、生きることに対して消極的な教条がままある、儒家や仏門に従うぐらいでちょうどいいのである。
「君子に終わると曰い、小人に死と曰う」
「君子が『身を終える』ということを、小人は『死ぬ』という。
(君子は身を終えても名を残すから『死ぬ』とは言わない。『天子がお隠れになる』なども
これに準拠した語法だといえる。そもそも『死』などを強調している時点で小人なのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・檀弓上第三より)
人間という生き物にとって、「自分が生きる」ということばかりに専らではないように
務めるぐらいが実質上ちょうどいいのと同じように、これまた人間にとっては、自己愛だとか
隣人愛だとかいったような、「安易な愛」を偏重しないようにするぐらいがちょうどいい。
仁愛や親愛が、それなりの知見や義務感と共にこそ達成し得る「高度な愛」であるのに対し、
自己愛や隣人愛は何の知識も義務感もなく、好き勝手な中にまんまと陥れる安易な愛でしかない。
たとえば、「遠くの親戚よりも近くの他人」で、近くにいるから便利な隣人ばかりとの
関係を専らにして、遠方の親戚家族などは蔑ろにしてしまうほうが実際、簡単なことである。
自分や隣人ばかりの利益に専らで、天下の公益を我田引水によって損ねてしまうことのほうが
我が欲望のままに行えることで、何らの知見の研鑽の必要もないぶんだけ、より簡単なことだといえる。
生存意欲も自己愛も隣人愛も、完全に捨て去られて然るべきものなのかといえば、そうとも限らない。
この世の中で旺盛に活動していく人間に「生存欲をなくせ」というのは矛盾しているし、墨子のように
あらゆる偏愛を捨て去っての博愛一辺倒でいた所で、八方美人すぎて何の成果も挙げられはしなかったりもする。
生存欲も自己愛も隣人愛もあったとした上で、そんなものを至上のものとして掲げたりはしない。 ┐
天命のためには身命をも呈する心構えや、仁愛や親愛こそを至上のものとして、それと比べれば ├ ①
生存欲だの自己愛だの隣人愛だのが、一貫して劣後される他ない代物であることをわきまえる。 ┘
自分が幾度となく言い重ねてきた諸々の分別のうちでも、これこそは最も推奨するに値する分別だといえる。
それでいて、この分別を恒常的に嗜める人間というのも、そんなに多くないだろうことまでもが予想される。
務めるぐらいが実質上ちょうどいいのと同じように、これまた人間にとっては、自己愛だとか
隣人愛だとかいったような、「安易な愛」を偏重しないようにするぐらいがちょうどいい。
仁愛や親愛が、それなりの知見や義務感と共にこそ達成し得る「高度な愛」であるのに対し、
自己愛や隣人愛は何の知識も義務感もなく、好き勝手な中にまんまと陥れる安易な愛でしかない。
たとえば、「遠くの親戚よりも近くの他人」で、近くにいるから便利な隣人ばかりとの
関係を専らにして、遠方の親戚家族などは蔑ろにしてしまうほうが実際、簡単なことである。
自分や隣人ばかりの利益に専らで、天下の公益を我田引水によって損ねてしまうことのほうが
我が欲望のままに行えることで、何らの知見の研鑽の必要もないぶんだけ、より簡単なことだといえる。
生存意欲も自己愛も隣人愛も、完全に捨て去られて然るべきものなのかといえば、そうとも限らない。
この世の中で旺盛に活動していく人間に「生存欲をなくせ」というのは矛盾しているし、墨子のように
あらゆる偏愛を捨て去っての博愛一辺倒でいた所で、八方美人すぎて何の成果も挙げられはしなかったりもする。
生存欲も自己愛も隣人愛もあったとした上で、そんなものを至上のものとして掲げたりはしない。 ┐
天命のためには身命をも呈する心構えや、仁愛や親愛こそを至上のものとして、それと比べれば ├ ①
生存欲だの自己愛だの隣人愛だのが、一貫して劣後される他ない代物であることをわきまえる。 ┘
自分が幾度となく言い重ねてきた諸々の分別のうちでも、これこそは最も推奨するに値する分別だといえる。
それでいて、この分別を恒常的に嗜める人間というのも、そんなに多くないだろうことまでもが予想される。
世の半分を構成する女は、ほぼ全てがこんなわきまえ①を保つことなど不可能である。
男であっても頑是ない子供や、精神が未熟なままに年だけ重ねた小人男などにも不可能であろう。
結果、上記①のようなわきまえを保てる人間は、どんなに多く見積もっても全世界の半分以下に
止まることになり、多数決であれば上記①のようなわきまえこそが劣後されることになってしまう。
多数決によって、①のような上等なわきまえが天下に通用するということは、原理的にありえない。
男か女でいえば男が上で女が下、君子か小人かでいえば君子が上で小人が下といった適正な差別を実施した上で、
上位のものが下位のものを一方的に教導していくという体制が整えられることで初めて、天下に①のような
わきまえが通用して、以て人類が生存欲や自己愛や隣人愛の過剰からなる滅亡の危機を免れられることともなる。
多数決ですらあれば必ず正しいなんてことも決してない。「船頭多くして船山に登る」ということがあり、
世界の多数派である女子供と小人の意見を優先させた挙句に、人類が滅亡の危機に見舞われることにすらなり得る。
人間が必ずしも愚かだなんてことはないが、多数派については、愚かでいやすいようにもできている。
安易なほう、安易なほうへと堕落し続ける多数派の愚か者を、その命ごと斬り捨てるとまではいかずとも、
全くその言い分を聞いてやらずに、こちらの命令だけを聞き従わせるといったことも、時に必要になるのである。
「仁義礼智は、外由り我れを鑠るには非ざるなり。我固より之れを有するなり。思う弗きのみ。故に求むれば
則ち之れを得、舍つれば則ち之れを失うとも曰えり。相倍蓰而て算無き者あるは、其の才を尽くす能わざればなり」
「仁義礼智は、外的に自らを飾り立てるための道具などではない。誰しもが本より具えてはいるものの、それを
自覚することがないだけのことである。だから『求めれば得られるが、捨てるのなら失うばかり』ともいえる。
得る者と失う者とで極端に隔絶してしまうことがあるのも、自らの才分を尽くしたか否かによるのである。
(仁義礼智の四端を自得するために才分を尽くすことこそは、君子にとっての至上命題だといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・告子章句上・六より)
男であっても頑是ない子供や、精神が未熟なままに年だけ重ねた小人男などにも不可能であろう。
結果、上記①のようなわきまえを保てる人間は、どんなに多く見積もっても全世界の半分以下に
止まることになり、多数決であれば上記①のようなわきまえこそが劣後されることになってしまう。
多数決によって、①のような上等なわきまえが天下に通用するということは、原理的にありえない。
男か女でいえば男が上で女が下、君子か小人かでいえば君子が上で小人が下といった適正な差別を実施した上で、
上位のものが下位のものを一方的に教導していくという体制が整えられることで初めて、天下に①のような
わきまえが通用して、以て人類が生存欲や自己愛や隣人愛の過剰からなる滅亡の危機を免れられることともなる。
多数決ですらあれば必ず正しいなんてことも決してない。「船頭多くして船山に登る」ということがあり、
世界の多数派である女子供と小人の意見を優先させた挙句に、人類が滅亡の危機に見舞われることにすらなり得る。
人間が必ずしも愚かだなんてことはないが、多数派については、愚かでいやすいようにもできている。
安易なほう、安易なほうへと堕落し続ける多数派の愚か者を、その命ごと斬り捨てるとまではいかずとも、
全くその言い分を聞いてやらずに、こちらの命令だけを聞き従わせるといったことも、時に必要になるのである。
「仁義礼智は、外由り我れを鑠るには非ざるなり。我固より之れを有するなり。思う弗きのみ。故に求むれば
則ち之れを得、舍つれば則ち之れを失うとも曰えり。相倍蓰而て算無き者あるは、其の才を尽くす能わざればなり」
「仁義礼智は、外的に自らを飾り立てるための道具などではない。誰しもが本より具えてはいるものの、それを
自覚することがないだけのことである。だから『求めれば得られるが、捨てるのなら失うばかり』ともいえる。
得る者と失う者とで極端に隔絶してしまうことがあるのも、自らの才分を尽くしたか否かによるのである。
(仁義礼智の四端を自得するために才分を尽くすことこそは、君子にとっての至上命題だといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・告子章句上・六より)
己れに備わる仁義礼智の四端を自覚し、その恒常的な実践に務めて行く、
その過程において善を勧める一方、悪を赦すことなく懲らしたりもする、
それでこそ浩然の気が保たれて、すがすがしい気持ちのままでもいられるからそうするし、
またそうすることで、罪刑の因果関係が保たれた社会的安寧までもが実現されるから。
世俗的に実があるのは、後者の社会的健全性の実現のほうであるけれども、より普遍的
であるのは前者の、「そうすることがすがすがしいから」という理由のほうだといえる。
そうするほうがすがすがしいから、来世でもそのまた来世でも、
形而上の形而上の形而上でもそうであることを志し続けることが確か。
今生限りにおいて健全性が確保されるから、勧善懲悪に臨むというだけならば、
来世や形而上でもそうするかどうかまでは知れないが、勧善懲悪が心の底から普遍的に
すがすがしいのだから、来世だろうが形而上だろうが形而下だろうがそう志し続けることが確か。
大罪をこともなげに許容するようなところでこそ、心の底からのつまらなさにも苛まれる。
心の底からのつまらなさだから、来世でも形而上でも形而下でも、永久につまらない。
実質的な因果律の破綻こそは、三千大千世界の去来今に渡ってつまらないもののままであり続けるし、
逆に因果律の保全に務めることが、絶対普遍のものとしてすがすがしいことのままであり続ける。
結論としては、悪いことをせずさせず、善いことをしてさせるに越したことはないという
ごくありきたりな結論にいたるわけだから、そのありきたりな範囲の論議にしか及ばない儒説だけに
従ったところで効能はさして変わらないわけだが、あえて仏説などに根ざすことで、遠大な形而上
なぞを想定してみたところで、人としてすべきことに大した相違などはないことが分かるのである。
その過程において善を勧める一方、悪を赦すことなく懲らしたりもする、
それでこそ浩然の気が保たれて、すがすがしい気持ちのままでもいられるからそうするし、
またそうすることで、罪刑の因果関係が保たれた社会的安寧までもが実現されるから。
世俗的に実があるのは、後者の社会的健全性の実現のほうであるけれども、より普遍的
であるのは前者の、「そうすることがすがすがしいから」という理由のほうだといえる。
そうするほうがすがすがしいから、来世でもそのまた来世でも、
形而上の形而上の形而上でもそうであることを志し続けることが確か。
今生限りにおいて健全性が確保されるから、勧善懲悪に臨むというだけならば、
来世や形而上でもそうするかどうかまでは知れないが、勧善懲悪が心の底から普遍的に
すがすがしいのだから、来世だろうが形而上だろうが形而下だろうがそう志し続けることが確か。
大罪をこともなげに許容するようなところでこそ、心の底からのつまらなさにも苛まれる。
心の底からのつまらなさだから、来世でも形而上でも形而下でも、永久につまらない。
実質的な因果律の破綻こそは、三千大千世界の去来今に渡ってつまらないもののままであり続けるし、
逆に因果律の保全に務めることが、絶対普遍のものとしてすがすがしいことのままであり続ける。
結論としては、悪いことをせずさせず、善いことをしてさせるに越したことはないという
ごくありきたりな結論にいたるわけだから、そのありきたりな範囲の論議にしか及ばない儒説だけに
従ったところで効能はさして変わらないわけだが、あえて仏説などに根ざすことで、遠大な形而上
なぞを想定してみたところで、人としてすべきことに大した相違などはないことが分かるのである。
 例えば、木片を刀剣状に削り上げた木刀は、その鋭利さなどで真剣に匹敵するはずはないが、それを用いて
例えば、木片を刀剣状に削り上げた木刀は、その鋭利さなどで真剣に匹敵するはずはないが、それを用いて 剣術の練習をすることができるし、真剣では無理があるほどにも大胆な稽古すら繰り返すことができる。
もちろん、木刀での練習に飽き足らなければ、真剣や模造刀での練習にも及べばいいわけだが、結局、
木刀を用いようが真剣を用いようが、自らが剣術の鍛錬によって「剣の理合」を身に付けようとすること
には変わりない。それと同じで、儒学ぐらいに表面的な勉学に務めることと、仏教ほどにも深遠な修練に
務めることでも、いずれもがこの世界、この宇宙やその形而上の形而上の形而上に至るまでの普遍的な
理合こそを探求していることには変わりないわけで、ただ儒学のほうが木刀での鍛錬ほどにも大雑把である
のに対し、仏教のほうは真剣での鍛錬ほどにも精密であったりするという違いがあるばかりのことである。
儒学と仏教の相違は上記のようなものだけども、そもそも道理なり真理なりの「普遍的な理合」を
把捉しようとすらせず、かえって普遍的な理合に違う邪曲こそを追い求めようとする学問なり宗教なりも
あるわけで、それらの教学にはまったく上記のような共通法則などはない。そういう邪教邪学も
この世には残念ながら実在しているわけだから、儒学や仏教のような、普遍的な理合を追い求めている
教学もまた全体的には特殊なものであるといえ、特筆して庇護や推奨の対象にすべきものだといえる。
昔の日本などでは、儒学や仏教こそが特に主要な文化的地位を占めていたから、特定してそれらばかりを
庇護するというようなことからして、あまりなかった。寛政異学の禁などにおいても、洋学と共に
異端派の儒学などが排撃の対象とされていて、儒学の庇護というよりは儒学の洗練という意味合いの
ほうが強かった。儒学全般、仏教全般こそを、普遍的な理合を捉えた正学正教として特筆して見直し、
邪曲の追求に専らな雑学雑教とは別格のものとして扱うなどということは、実際問題、日本人や中国人
ですら未だ十分に実施したこともないのだから、全く新しい試みとしての心構えが必要だといえる。
儒学や仏教こそが、そこまで特別に正しいものだったということが、今にこそ明らかとなったのだから。
「否を休む。大人は吉なり。其れ亡びなん、其れ亡びなんとて、苞桑に繋ぐ」
「否塞が潰える、大人にとっては格好のとき。それでも『滅びるかもしれない、亡びるかもしれない』
と内心憂慮を保ち、桑の木の根元にものを繋ぎとめておくような、堅固な心持ちのままでいるとよい」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・否・九五より)
「否塞が潰える、大人にとっては格好のとき。それでも『滅びるかもしれない、亡びるかもしれない』
と内心憂慮を保ち、桑の木の根元にものを繋ぎとめておくような、堅固な心持ちのままでいるとよい」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・否・九五より)
いくら形而上に超越的な観念を思い描いてみたところで、
それが形而下の事物と全く関係がないのでは、不実の至りとしかならない。
陰陽学における太極の法則や、大乗仏教における六道の様態などは、
観念的であったところで、この形而下の世界の法則にも適格に合致している。
形而下の現象に対する鋭い洞察があった上で、その知見を概括的に理念化しているわけで、
理念としては形而上的であっても、形而下との厳密な連絡を保ったままでいる。
そのような、形而下の現象との緊密な連絡を保った理念としての神だとか仏だとかを敬い、
鬼なり悪霊なりを厭うことが現実上の効験にも繋がる一方で、形而下との連絡を全く欠いた
単なる夢想上の神なり霊なりを崇めたり、それに対立する異質の神仏などを貶めたりしたなら、
何の効験も得られないばかりか、その徒労や悪業に見合った制裁すらをも被ることになる。
形而上に思い描く超越的な夢想も、具体的である以上は形而下の事物を流用している。形而下の
事物が刹那的なものであるというのなら、そのような形而上の夢想もまた連動して刹那的である。
そんな夢想よりは、形而下との連絡を保っていても高度に数理的な易の陰陽法則などのほうが
より普遍的であるし、概念的な具体性を徹底して排する仏法などもさらに普遍的ですらある。
陰陽五行や六道輪廻のような、形而下の現象を概括した普遍法則を参考にしたなら、形而下に
おいて自らが為すことや、造り上げるものなどにもそれなりの普遍性を付与することができる。
そのような事物を継承して維持することに務めていけば、それがよき伝統ともなっていくのである。
してみれば、形而上に全く超越的な概念を夢想してみて、その普遍性を愛でようとしたりする
ことからして、さして魅力的なことだとも言えない。そのような夢想も所詮は形而下の事物の
模倣でしかない上に、完全に形而下と隔絶しているものだから、形而下においてよき伝統を
もたらす普遍的な指針となったりもしないわけで、より普遍的である上に、形而下における
開物成務をも健全化させられる陰陽法則や仏法と比べて、何も秀でている所がないと言える。
それが形而下の事物と全く関係がないのでは、不実の至りとしかならない。
陰陽学における太極の法則や、大乗仏教における六道の様態などは、
観念的であったところで、この形而下の世界の法則にも適格に合致している。
形而下の現象に対する鋭い洞察があった上で、その知見を概括的に理念化しているわけで、
理念としては形而上的であっても、形而下との厳密な連絡を保ったままでいる。
そのような、形而下の現象との緊密な連絡を保った理念としての神だとか仏だとかを敬い、
鬼なり悪霊なりを厭うことが現実上の効験にも繋がる一方で、形而下との連絡を全く欠いた
単なる夢想上の神なり霊なりを崇めたり、それに対立する異質の神仏などを貶めたりしたなら、
何の効験も得られないばかりか、その徒労や悪業に見合った制裁すらをも被ることになる。
形而上に思い描く超越的な夢想も、具体的である以上は形而下の事物を流用している。形而下の
事物が刹那的なものであるというのなら、そのような形而上の夢想もまた連動して刹那的である。
そんな夢想よりは、形而下との連絡を保っていても高度に数理的な易の陰陽法則などのほうが
より普遍的であるし、概念的な具体性を徹底して排する仏法などもさらに普遍的ですらある。
陰陽五行や六道輪廻のような、形而下の現象を概括した普遍法則を参考にしたなら、形而下に
おいて自らが為すことや、造り上げるものなどにもそれなりの普遍性を付与することができる。
そのような事物を継承して維持することに務めていけば、それがよき伝統ともなっていくのである。
してみれば、形而上に全く超越的な概念を夢想してみて、その普遍性を愛でようとしたりする
ことからして、さして魅力的なことだとも言えない。そのような夢想も所詮は形而下の事物の
模倣でしかない上に、完全に形而下と隔絶しているものだから、形而下においてよき伝統を
もたらす普遍的な指針となったりもしないわけで、より普遍的である上に、形而下における
開物成務をも健全化させられる陰陽法則や仏法と比べて、何も秀でている所がないと言える。
目に見えるこの世界と全く隔絶した何かを追い求めるよりは、この世界との連絡も保ちつつ
普遍的である何かを追い求めることのほうが魅力的である。必要という以上にも、魅力的であり、
そのうえ害がなくて益がある。近代科学などにもある程度この方向性が備わっているが、理論面では
まだまだ未熟で、概念遊びの介在する余地が多分に残存しているために、権力犯罪や道義なき戦争
などのために悪用されることが多い。陰陽法則や仏法と比べて好き勝手に論じられる自由度が高い、
にもかかわらずではなくだからこそ、探求者や利用者の不埒さをも容認してしまっているのである。
形而下との連絡を全く欠いた観念を玩ぶ信教や思想哲学が排されて、科学もまたそのような
概念の玩びを差し挟む余地がなくなるほどに見識が引き締められたならば、そこには必ず
陰陽法則や仏法や、それに近似するものだけが残されるはずである。それで人類文明が
終わるのではなく、むしろそこからこそ全世界規模での人類文明が初めて始まるのである。
概念遊びに道草を食い過ぎて、文明を進歩させる以上にも退歩させてしまっていたような
派閥が退場させられて、世界規模で文明を着実に前進させていけるようになるのである。
産業革命によって科学が地球人類にもたらした影響も、未だプラスマイナスゼロ以下のままでしかない。
だからこそ極重の苦悩に見舞われた人々が気休めの乱交に及んで、世界人口を爆発させてもいる。
全世界全人類が、不幸ばかりをもたらす不埒な超越的概念の玩びから卒業することでやっと
その傾向が収束する見込みも立つのだから、もはやそうするしかないのでもある。
普遍的である何かを追い求めることのほうが魅力的である。必要という以上にも、魅力的であり、
そのうえ害がなくて益がある。近代科学などにもある程度この方向性が備わっているが、理論面では
まだまだ未熟で、概念遊びの介在する余地が多分に残存しているために、権力犯罪や道義なき戦争
などのために悪用されることが多い。陰陽法則や仏法と比べて好き勝手に論じられる自由度が高い、
にもかかわらずではなくだからこそ、探求者や利用者の不埒さをも容認してしまっているのである。
形而下との連絡を全く欠いた観念を玩ぶ信教や思想哲学が排されて、科学もまたそのような
概念の玩びを差し挟む余地がなくなるほどに見識が引き締められたならば、そこには必ず
陰陽法則や仏法や、それに近似するものだけが残されるはずである。それで人類文明が
終わるのではなく、むしろそこからこそ全世界規模での人類文明が初めて始まるのである。
概念遊びに道草を食い過ぎて、文明を進歩させる以上にも退歩させてしまっていたような
派閥が退場させられて、世界規模で文明を着実に前進させていけるようになるのである。
産業革命によって科学が地球人類にもたらした影響も、未だプラスマイナスゼロ以下のままでしかない。
だからこそ極重の苦悩に見舞われた人々が気休めの乱交に及んで、世界人口を爆発させてもいる。
全世界全人類が、不幸ばかりをもたらす不埒な超越的概念の玩びから卒業することでやっと
その傾向が収束する見込みも立つのだから、もはやそうするしかないのでもある。
「上世、嘗て其の親を葬らざる者あり。其親死すれば則ち挙げて之れを壑に委てたり。他日之れを過ぐるに、狐狸之れを食らい、
蝿蚋之れを姑嘬う。其の顙に汗有りて、睨して視ざる。夫の汗なるは、人の為めに汗なるに非ず、中心より面目に達せるなり。
蓋し帰反して虆梩もて之れを掩えり。之れを掩うは是れを誠にすなり。則ち孝子仁人の其の親を掩えるは、亦た必ず道有らん」
「大昔、自らの親を埋葬しない者がいた。親が死ねばその遺体を人気のない谷底に捨ててそのままにしておいた。他日、
その付近を通り過ぎると、狐や狸がその遺体の肉を食らい、蝿や蚋が食んだ肉を咀嚼しているのを見た。思わず額に
冷や汗が滴り、斜めに視たきりで直視することもできなかった。冷や汗をかいたのは、別に人にいい顔を見せようと
したからではなく、本当に心の底から親に面目がないと思ったからである。その後、すぐに帰宅して鋤ともっこを
持ち出してきて、親の遺体を土で蔽った。土で蔽ったのも誠を立てようと思ったからである。今の孝子や仁人が
親の遺体を埋葬することにも、そういった道義性があるからなのである。(親の遺体が腐乱して禽獣に貪り食われるのが
忍びないからこれを埋葬する。永遠足りえない親の命の儚さにこそ蔽いをする。またそれが孝子仁人のあり方ともなるのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・滕文公章句上・五より)
蝿蚋之れを姑嘬う。其の顙に汗有りて、睨して視ざる。夫の汗なるは、人の為めに汗なるに非ず、中心より面目に達せるなり。
蓋し帰反して虆梩もて之れを掩えり。之れを掩うは是れを誠にすなり。則ち孝子仁人の其の親を掩えるは、亦た必ず道有らん」
「大昔、自らの親を埋葬しない者がいた。親が死ねばその遺体を人気のない谷底に捨ててそのままにしておいた。他日、
その付近を通り過ぎると、狐や狸がその遺体の肉を食らい、蝿や蚋が食んだ肉を咀嚼しているのを見た。思わず額に
冷や汗が滴り、斜めに視たきりで直視することもできなかった。冷や汗をかいたのは、別に人にいい顔を見せようと
したからではなく、本当に心の底から親に面目がないと思ったからである。その後、すぐに帰宅して鋤ともっこを
持ち出してきて、親の遺体を土で蔽った。土で蔽ったのも誠を立てようと思ったからである。今の孝子や仁人が
親の遺体を埋葬することにも、そういった道義性があるからなのである。(親の遺体が腐乱して禽獣に貪り食われるのが
忍びないからこれを埋葬する。永遠足りえない親の命の儚さにこそ蔽いをする。またそれが孝子仁人のあり方ともなるのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・滕文公章句上・五より)
 未だ惑いの中にある者であろうとも、それなりに信念を以って行動したり、人生を送ったりすることはある。
未だ惑いの中にある者であろうとも、それなりに信念を以って行動したり、人生を送ったりすることはある。 「最後の審判の時に全ての信者が復活する」という、永久不変の絶対真理に即した完全誤謬を
信じながら死ぬ場合にも、それなりに毅然としていられたりする。だから、そのような完全誤謬を
信じながら死んでいく欧米のキリスト教徒たちも、まともな信教を剥奪された戦後の大多数の日本人などと
比べれば毅然としていて、醜悪な寝たきり状態での終末期医療などもあえて拒絶して死んでいったりする。
「私は自分の信じているものが完全に間違っていてもそれを信じます」という、何らの価値もない完全誤謬信仰と
いえども、それによって心持ちを頑なならしめて、命を賭してことに臨むことだって絶対にできなくもないのである。
ただ、そのような劣悪な信念に即して心持ちを凝り固める人間は、根本的な部分で己れの才覚を尽くしていない。
正しいもの、優良なものを信じていくに値するだけの格物致知を尽くすこともなく、まず何かを信じていようとした。
何でもいいからとりあえず信じようとした怠惰の結果、完全に間違っているものであろうとも信じてしまう、
人として最も劣悪な領域での、狂信への凝り固まりに落ち着いてしまったのである。
孟子の提唱した仁義礼智の四端と、荀子が覇道政治を是認する過程で定立した信とを合わせて五常(仁義礼智信)という。
このうちの信と知(智)は時に、むしろ持たないでいるほうがマシなほどに劣悪な邪信や小知でもあり得る。
それを仁義という理念、礼儀という実践によって統御し、正信や良知に止め置くことが儒学の実践ともなる。
邪信や小知も存在してしまっている状態でこそ、仁義や礼儀によって知や信を統制しなければならなくなるわけだから、
「大道廃れて仁義あり(老子)」ということもまた確かである。大道が十分に通用している世の中であれば、
人々が邪信に凝り固まったり、小知を駆使したりして破滅を呼び込んだりすることもないわけだから、
わざわざ仁義や礼儀で信知を制御しようなどという作為を差し挟んだりする必要もないのである。
邪信や小知に凝り固まって、あるよりもないほうがマシであるような害悪ばかりを募らせている連中がいる。
だからそのぶんだけ五常の理念に即した統制を執り行う。そのあたりのけじめは十分に付けておくべきで、
さもなくば「仁義や礼儀などで世の中の浄化に務めようとしているような奴らがいるから、俺らは邪信や小知を
駆使した悪行に走っていたって大丈夫だろう」などという「甘え」を一部の人間が抱くことにすらなりかねない。
人類史上最悪の邪教であるキリスト教などよりは、儒学のほうが数百年以上早くの内から形成されている。
しかし、その儒学も夏桀殷紂や春秋諸侯のような暴政家が登場して後、乱世と化してしまった古代の中国を修善
していく目的で周公や孔孟らによって体系化されて来ている。小知や邪信に基づく世の乱脈があって後に、あからさまな
聖人君子による仁徳の体系化もまた試みられ始めたわけで、その順序はこれからも大切にしていくべきである。
邪教の信者や暴政家こそが、自業自得で体系的な仁徳による浄化を被る。そうでもしなければ世の中が
立ち行かなくなるほどもの乱脈を自分たちが呼び込んでしまったからこそ、作為的な勧善懲悪にも甘んじなければならない。
「大道廃れて仁義あり」という言葉は、大道を廃らせてしまった悪人たちにとってこその戒めの言葉なのである。
「君子は其の道によって楽を得、小人は其の欲によって楽を得。
道を以って欲を制すれば、則ち楽しみて乱れず。欲を以って道を忘るれば、則ち惑いて楽しまず」
「君子は道義によって楽しみを得ようとし、小人は愛欲によって楽しみを得ようとする。
道義によって愛欲を制すれば、よく楽しめながら乱れることもない。一方で、
愛欲によって道義を忘れれば、惑いに苛まれてろくに楽しむこともできない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・楽記第十九より)
だからそのぶんだけ五常の理念に即した統制を執り行う。そのあたりのけじめは十分に付けておくべきで、
さもなくば「仁義や礼儀などで世の中の浄化に務めようとしているような奴らがいるから、俺らは邪信や小知を
駆使した悪行に走っていたって大丈夫だろう」などという「甘え」を一部の人間が抱くことにすらなりかねない。
人類史上最悪の邪教であるキリスト教などよりは、儒学のほうが数百年以上早くの内から形成されている。
しかし、その儒学も夏桀殷紂や春秋諸侯のような暴政家が登場して後、乱世と化してしまった古代の中国を修善
していく目的で周公や孔孟らによって体系化されて来ている。小知や邪信に基づく世の乱脈があって後に、あからさまな
聖人君子による仁徳の体系化もまた試みられ始めたわけで、その順序はこれからも大切にしていくべきである。
邪教の信者や暴政家こそが、自業自得で体系的な仁徳による浄化を被る。そうでもしなければ世の中が
立ち行かなくなるほどもの乱脈を自分たちが呼び込んでしまったからこそ、作為的な勧善懲悪にも甘んじなければならない。
「大道廃れて仁義あり」という言葉は、大道を廃らせてしまった悪人たちにとってこその戒めの言葉なのである。
「君子は其の道によって楽を得、小人は其の欲によって楽を得。
道を以って欲を制すれば、則ち楽しみて乱れず。欲を以って道を忘るれば、則ち惑いて楽しまず」
「君子は道義によって楽しみを得ようとし、小人は愛欲によって楽しみを得ようとする。
道義によって愛欲を制すれば、よく楽しめながら乱れることもない。一方で、
愛欲によって道義を忘れれば、惑いに苛まれてろくに楽しむこともできない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・楽記第十九より)
 「金持ち争わず」という俗諺通り、概ねのところでは、
「金持ち争わず」という俗諺通り、概ねのところでは、 貧しいから争いが起こり、富裕だから平和でいられるというもの。
未だ資本的、資源的な富裕で突出している欧米聖書圏内での戦争は稀な一方、
貧しいアフリカや中東、東南アジア諸国での内戦や国際紛争は恒常的なものであり続けている。
それらの社会から富を巻き上げて、狭隘な富裕を謳歌しているのが欧米聖書圏でもあるわけだから、
所詮は世界中の紛争の本当の火種も、欧米の不正な富裕者でこそあるのだといえる。
ところで、今でもインドのように、ブラックアフリカ並みの貧困下に置かれながら、
内紛まではほぼ控えられている大国もある。これは、仏教の影響も受けているヒンズー教の
教化などがあって初めて実現し得ていることで、同レベルの生活水準でありながら
ブラックアフリカなどでは内紛が絶えないでいるのも、欧米聖書圏による文化的征服の禍根が
持ち越されたままであるのだからだと言える。のみならず、富裕な欧米聖書圏においてですら、
アイルランドやユーゴスラビアのように紛争を巻き起こす国もあるわけで、聖書信仰こそは貧富の
如何によらず、人々に最大級かつ不必要な闘争本能を植え付けている邪教であることが分かるのである。
人々に不埒な闘争本能を植え付けた挙句に、自分たちだけが大量に富を独占して、「金持ち争わず」
の要領でどうにか隣人間の関係だけを良好に保とうとするあり方からして、原理的に必ず一定以上の
争いをこの世にもたらし続けるものである。聖書信仰がそうである一方で、インドのヒンズー教などは、
最悪級の貧困下においてですら内紛ぐらいは未然に止め置くだけの効験をあらたかにしている。
その手段たるや、カースト制による絶対支配だったりもして、決してもろ手を挙げて称賛できたりする
ような代物でもないが、結果としてヒンズー教が信仰圏に与えている影響は、富裕者同士の争いすら
時に勃発させる聖書信仰がこの世に与えている影響などと比べれば、遥かにマシなものとなっている。
やはりその程度にも大きな差異があるが、まず人々に心の豊かさをもたらす信教と、
そうでない信教との両方がある。人々に最悪級の心の貧しさをもたらすのが他でもない聖書信仰で、
だからこそ金持ち同士での争いすら時に巻き起こさせるのに対し、ヒンズー教などは比較的、
信者に心の豊かさをもたらす信教だから、相当な貧困下においても信者を最悪の妄動にまでは至らせない。
当然、人々に心の豊かさをもたらす教学を推進して、心の貧しさをもたらす教学を排していくべきで、
たとえ世界中の貧富の格差を埋め合わせてみたところで、誰しもが聖書信者並みの心の貧しさのままでいたり
したなら、紛争の多発化なども防げない。一方で、誰しもがインド人並みの心の豊かさを身に付けたなら、
誰しもが今のインド並みの貧困下に置かれた所で、紛争級の妄動にまでは至らない。別に誰しもが今の
インド人並みの貧しさに置かれるべきでもないが、最悪そうなったところで、心の豊かさにだけよって
争いを未然に食い止めることだってできなくはないのだという見本に、今のインドなどがなってくれてもいる。
この地球上の資源含有率などからいっても、世界中の誰しもが今の欧米人並みの富裕に与れるなんてことも
あり得ない。ただ資源占有率を均すだけなら、誰しもがインドネシア人やフィリピン人並みの生活を
送らされることにもなるわけで、だからといって誰しもが今のインドネシア人やフィリピン人を
目指すべきだなどということもないとは、すでに>>132-133にも書いた。フィリピンのキリスト教はおろか、
インドネシアのイスラム教ですら、人々に心の豊かさをもたらすことにかけて長けた信教であるなどという
ことはないわけで、心の豊かさについて見習うべきなのはむしろインド人などのほうである。さらに言えば、
今のインド人以上にも、仏教圏だった頃のインド人のあり方などを見習うほうが、よりうってつけでもある。
そうでない信教との両方がある。人々に最悪級の心の貧しさをもたらすのが他でもない聖書信仰で、
だからこそ金持ち同士での争いすら時に巻き起こさせるのに対し、ヒンズー教などは比較的、
信者に心の豊かさをもたらす信教だから、相当な貧困下においても信者を最悪の妄動にまでは至らせない。
当然、人々に心の豊かさをもたらす教学を推進して、心の貧しさをもたらす教学を排していくべきで、
たとえ世界中の貧富の格差を埋め合わせてみたところで、誰しもが聖書信者並みの心の貧しさのままでいたり
したなら、紛争の多発化なども防げない。一方で、誰しもがインド人並みの心の豊かさを身に付けたなら、
誰しもが今のインド並みの貧困下に置かれた所で、紛争級の妄動にまでは至らない。別に誰しもが今の
インド人並みの貧しさに置かれるべきでもないが、最悪そうなったところで、心の豊かさにだけよって
争いを未然に食い止めることだってできなくはないのだという見本に、今のインドなどがなってくれてもいる。
この地球上の資源含有率などからいっても、世界中の誰しもが今の欧米人並みの富裕に与れるなんてことも
あり得ない。ただ資源占有率を均すだけなら、誰しもがインドネシア人やフィリピン人並みの生活を
送らされることにもなるわけで、だからといって誰しもが今のインドネシア人やフィリピン人を
目指すべきだなどということもないとは、すでに>>132-133にも書いた。フィリピンのキリスト教はおろか、
インドネシアのイスラム教ですら、人々に心の豊かさをもたらすことにかけて長けた信教であるなどという
ことはないわけで、心の豊かさについて見習うべきなのはむしろインド人などのほうである。さらに言えば、
今のインド人以上にも、仏教圏だった頃のインド人のあり方などを見習うほうが、よりうってつけでもある。
未だイギリス連合下に置かれ、最悪級の貧困に喘がされているがための非常的な措置として、酷烈なカースト制を
敷いている今のインドなどよりも、古代中国と並んで世界最大級の繁栄を謳歌していた、仏教圏だった頃の
インドのあり方などを見習うほうが、心の豊かさの蓄え方を教わる上では適している。今のインド人もまた、
昔のインド文化を糧としているわけだから、インドの歴史性もまた決して無視されていいものではないといえる。
——真正聖書=四書五経にまつわる論議としては、今日は道はずれ気味になってしまったが、
「より重大なのは物質的貧富以上にも心の貧富である」という認識が、四書五経中でも一貫されている。
ただ、俗世の道徳学たる儒学の聖典であるために、四書五経などでは抽象的な心論は少なく、
心か本で財物が末であるという本末認識を大前提とした、具体的な実践論などのほうが豊富である。
そうであることをよくわきまえた上で四書五経を読めば、その記述内容に納得がいくことも多いのである。
「信を講じ睦を修む、之れを人の利と謂う。争奪相殺す、之れを人の憂いと謂う」
「信実さを養って人々との親睦に務めることが、人としての利益である。争って奪い合い殺し合うのは憂いである。
(平和によってお互いの利益を損なわないことが、ありのままに利益である。物質的な富裕も利益なら、
平和によってお互いの利益を守ることもまた利益なのだから、両者を対立的なものとして捉えたりする必要はない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・礼運第九より)
敷いている今のインドなどよりも、古代中国と並んで世界最大級の繁栄を謳歌していた、仏教圏だった頃の
インドのあり方などを見習うほうが、心の豊かさの蓄え方を教わる上では適している。今のインド人もまた、
昔のインド文化を糧としているわけだから、インドの歴史性もまた決して無視されていいものではないといえる。
——真正聖書=四書五経にまつわる論議としては、今日は道はずれ気味になってしまったが、
「より重大なのは物質的貧富以上にも心の貧富である」という認識が、四書五経中でも一貫されている。
ただ、俗世の道徳学たる儒学の聖典であるために、四書五経などでは抽象的な心論は少なく、
心か本で財物が末であるという本末認識を大前提とした、具体的な実践論などのほうが豊富である。
そうであることをよくわきまえた上で四書五経を読めば、その記述内容に納得がいくことも多いのである。
「信を講じ睦を修む、之れを人の利と謂う。争奪相殺す、之れを人の憂いと謂う」
「信実さを養って人々との親睦に務めることが、人としての利益である。争って奪い合い殺し合うのは憂いである。
(平和によってお互いの利益を損なわないことが、ありのままに利益である。物質的な富裕も利益なら、
平和によってお互いの利益を守ることもまた利益なのだから、両者を対立的なものとして捉えたりする必要はない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・礼運第九より)
漢帝国のような徳治制の社会においては、王侯による恩赦の発布が重要な政治行為の一環とされていた。
「漢書」の帝紀における歴代皇帝の詔勅もその多くが恩赦にまつわるもので、罪人の釈放や減刑が、
法定刑を含む規制の緩和、正月祭などを民が自由に催すことの許可などと共に、頻繁に下されていた。
恩赦を発する理由はといえば、「龍が現れた」「鳳が飛んだ」なども含む、今だとオカルトじみて
聞こえるような瑞祥だったりもするが、とにかく適当な理由すら付けて赦令を下していたということ。
一方で、それほどにも恩赦を多発できたのは、当該の国家の朝廷なり幕府なりが積極的な徳治に努めることで、
世の中の福徳の余りある程もの増進を果たしていたからで、そのような努力も行われない法治主義の国家
などで恩赦を乱発したりしたなら、それによる世相不安の深刻化すらもが免れられなくなるのである。
法治国家ですら恩赦の多発化などは警戒せねばならないのだから、人々に権力犯罪や我田引水を
けしかける邪教に支配された社会などで、恩赦などを通用させる余地がないこともまた明らかである。
犯罪行為への恩赦といわず、破産を通じての借金の踏み倒しなどを容認するだけでも、相当に危うい。
今の日本などはまだ、全体に比べての破産者や生活保護者が少数に止まっていて、しかも全国民を挙げての
健全な自活が旺盛なものだから、落伍者を保護してやることだってできなくはない。(それでも保護を
受けることを恥じて自殺する者が多数に上っているが)一方で、全国民を挙げての浪費が甚だしい
アメリカや、公務員による富の食いつぶしが著しいギリシャなどでは、国全体での破綻までもが
危ぶまれる事態と化してしまっている。特に、アメリカの破綻は国を挙げての借金踏み倒しの先に
行き着いたものだといえ、為政者が徳治を心がけているわけでもないのに、民事と刑事両面における
赦免を乱発しすぎた挙句に、国家全体が破綻の様相を呈することとなった典型となっているのである。
「漢書」の帝紀における歴代皇帝の詔勅もその多くが恩赦にまつわるもので、罪人の釈放や減刑が、
法定刑を含む規制の緩和、正月祭などを民が自由に催すことの許可などと共に、頻繁に下されていた。
恩赦を発する理由はといえば、「龍が現れた」「鳳が飛んだ」なども含む、今だとオカルトじみて
聞こえるような瑞祥だったりもするが、とにかく適当な理由すら付けて赦令を下していたということ。
一方で、それほどにも恩赦を多発できたのは、当該の国家の朝廷なり幕府なりが積極的な徳治に努めることで、
世の中の福徳の余りある程もの増進を果たしていたからで、そのような努力も行われない法治主義の国家
などで恩赦を乱発したりしたなら、それによる世相不安の深刻化すらもが免れられなくなるのである。
法治国家ですら恩赦の多発化などは警戒せねばならないのだから、人々に権力犯罪や我田引水を
けしかける邪教に支配された社会などで、恩赦などを通用させる余地がないこともまた明らかである。
犯罪行為への恩赦といわず、破産を通じての借金の踏み倒しなどを容認するだけでも、相当に危うい。
今の日本などはまだ、全体に比べての破産者や生活保護者が少数に止まっていて、しかも全国民を挙げての
健全な自活が旺盛なものだから、落伍者を保護してやることだってできなくはない。(それでも保護を
受けることを恥じて自殺する者が多数に上っているが)一方で、全国民を挙げての浪費が甚だしい
アメリカや、公務員による富の食いつぶしが著しいギリシャなどでは、国全体での破綻までもが
危ぶまれる事態と化してしまっている。特に、アメリカの破綻は国を挙げての借金踏み倒しの先に
行き着いたものだといえ、為政者が徳治を心がけているわけでもないのに、民事と刑事両面における
赦免を乱発しすぎた挙句に、国家全体が破綻の様相を呈することとなった典型となっているのである。
罪を許すということには、当然それなりのリスクが伴う。そのリスクを見越した上で、自ら徳治を心がける
天皇なり皇帝なりが大赦を下すようなこともあるが、それは決して誰しもにできるようなことではない。
ただ能力がなくてできないというばかりでなく、それなりの立場にいるのでなければできない。
カルト宗教の指導者や商売人などは、その立場からして天下国家規模の運営責任を担うものではないから、
世の中に害を与える規模の刑事的、民事的過ちを勝手に許してやったりしていいはずもないのである。
徳治社会でも法官は法官で別にいて、ただの事務処理者として徳治を実施する王侯や高官の下に置かれる。
上司からの命令でもないうちは、法官は民に対する信賞必罰を心がけ、民もまたそれに従う。その頻度が
法治社会と比べて少ないということはあっても、守らせ守らせられる法規というものがやはり一定以上にはある。
誰しもが誰しもと無条件に許し合うなんていうことは、法治社会はおろか、徳治社会でもあり得ないことで、
罪を許されることばかりを欲するような卑しい身分の者ほど、(小人は恵を懐う。里仁第四・一一)
最後まで信賞必罰に則ったままの存在でいることを、徳治社会でも強要され続けるのである。
法で禁止されるべき様な悪行は自律的に行わず、むしろ善行によって世の大利の目方を増しすらするような
君子であって初めて、他人の罪を許してやれるだけの度量すらもが備わるのだから、自分が罪を許されたい
がために、他人の罪を許してやろうとするような考えが通用していい余地などは、どこにもないのだといえる。
「天道は善に福し淫に禍す。〜肆に台れ小子、天命の明威を将し、敢えて赦さず」
「天道は必ず正善なる者に福徳を授け、淫悪にふける者に災禍を下す。だからこそ私もまた、
その天命に根ざした明らかな威徳によって、罪を罰するに際しても、あえて赦そうとしないのである」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・商書・湯誥より)
天皇なり皇帝なりが大赦を下すようなこともあるが、それは決して誰しもにできるようなことではない。
ただ能力がなくてできないというばかりでなく、それなりの立場にいるのでなければできない。
カルト宗教の指導者や商売人などは、その立場からして天下国家規模の運営責任を担うものではないから、
世の中に害を与える規模の刑事的、民事的過ちを勝手に許してやったりしていいはずもないのである。
徳治社会でも法官は法官で別にいて、ただの事務処理者として徳治を実施する王侯や高官の下に置かれる。
上司からの命令でもないうちは、法官は民に対する信賞必罰を心がけ、民もまたそれに従う。その頻度が
法治社会と比べて少ないということはあっても、守らせ守らせられる法規というものがやはり一定以上にはある。
誰しもが誰しもと無条件に許し合うなんていうことは、法治社会はおろか、徳治社会でもあり得ないことで、
罪を許されることばかりを欲するような卑しい身分の者ほど、(小人は恵を懐う。里仁第四・一一)
最後まで信賞必罰に則ったままの存在でいることを、徳治社会でも強要され続けるのである。
法で禁止されるべき様な悪行は自律的に行わず、むしろ善行によって世の大利の目方を増しすらするような
君子であって初めて、他人の罪を許してやれるだけの度量すらもが備わるのだから、自分が罪を許されたい
がために、他人の罪を許してやろうとするような考えが通用していい余地などは、どこにもないのだといえる。
「天道は善に福し淫に禍す。〜肆に台れ小子、天命の明威を将し、敢えて赦さず」
「天道は必ず正善なる者に福徳を授け、淫悪にふける者に災禍を下す。だからこそ私もまた、
その天命に根ざした明らかな威徳によって、罪を罰するに際しても、あえて赦そうとしないのである」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・商書・湯誥より)
自分たちでこの世に破滅をもたらしておいて、
自分たちこそは特定して救われようとするようなガン細胞人種こそは、
仮に一切衆生が救われるとした所で、最後まで救われないままでい続けなければならないことが確か。
仮に誰かが救われないことになるのだとすれば、
そのようなガン細胞人種こそが特定して救われないことになるのも確か。
自分たち全員が、ガンが切除されるようにして死滅させられるのだとすれば、ガン細胞人種も
「死なば諸共」で、自分たちごと全人類を滅亡に陥れるヤケクソにすら及びかねない。
下劣ではあるにしろ、小人の心情としてはそれも分からないことはないから、
救済対象を選別するような小乗志向ではなく、一切衆生を救済していくことを旨とする
大乗志向によってこそ救済に取り組んでいくぐらいのことは、救済者も心がけたほうがいいといえる。
それでも実際問題、現世では救われない者がいる。
この世に害悪をもたらして自分たちが救われようとする、ガン細胞人種としての心得を
最後まで捨て去ろうとしないもの、邪教の棄教と引き換えの救済にすら応じようとしないものは、
どんなに大きな災厄からも人々を救い出せるほどもの手腕を持つ救済者によってですら、救われることはない。
救われ得ないから救われないのではなく、自分自身が救われることを拒み通しているから、救われない。
まるで如来か菩薩ほどにも救済能力に長けた者がいたとすれば、大罪を積み重ねて来たキリスト教徒や
ユダヤ教徒を、棄教後に救い取ることですらできなくはないだろう。「華厳経」十回向品第二十五の四にも、
菩薩が冤罪によってこの世に撒き散らされる災厄すらも十分に除滅するとあるから、冤罪信仰である
キリスト教が撒き散らす災厄からすら、菩薩が一切衆生を救い出すことも不可能ではないに違いない。
自分たちこそは特定して救われようとするようなガン細胞人種こそは、
仮に一切衆生が救われるとした所で、最後まで救われないままでい続けなければならないことが確か。
仮に誰かが救われないことになるのだとすれば、
そのようなガン細胞人種こそが特定して救われないことになるのも確か。
自分たち全員が、ガンが切除されるようにして死滅させられるのだとすれば、ガン細胞人種も
「死なば諸共」で、自分たちごと全人類を滅亡に陥れるヤケクソにすら及びかねない。
下劣ではあるにしろ、小人の心情としてはそれも分からないことはないから、
救済対象を選別するような小乗志向ではなく、一切衆生を救済していくことを旨とする
大乗志向によってこそ救済に取り組んでいくぐらいのことは、救済者も心がけたほうがいいといえる。
それでも実際問題、現世では救われない者がいる。
この世に害悪をもたらして自分たちが救われようとする、ガン細胞人種としての心得を
最後まで捨て去ろうとしないもの、邪教の棄教と引き換えの救済にすら応じようとしないものは、
どんなに大きな災厄からも人々を救い出せるほどもの手腕を持つ救済者によってですら、救われることはない。
救われ得ないから救われないのではなく、自分自身が救われることを拒み通しているから、救われない。
まるで如来か菩薩ほどにも救済能力に長けた者がいたとすれば、大罪を積み重ねて来たキリスト教徒や
ユダヤ教徒を、棄教後に救い取ることですらできなくはないだろう。「華厳経」十回向品第二十五の四にも、
菩薩が冤罪によってこの世に撒き散らされる災厄すらも十分に除滅するとあるから、冤罪信仰である
キリスト教が撒き散らす災厄からすら、菩薩が一切衆生を救い出すことも不可能ではないに違いない。
▲ページ最上部
ログサイズ:700 KB 有効レス数:323 削除レス数:0
不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。
思想・哲学掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
スレッドタイトル:聖書 Part8

