サイズが 480KB を超えています。500KB を超えると書きこめなくなるよ。
聖書 Part9
▼ページ最下部
地球人類社会において、四書五経こそは、ここ2500年の長きにわたって、わざわざ
特筆するまでもないほどに標準的な聖書としての、その地位を守り続けてきている。
その理由は、四書五経が「社会統治の聖書」であるからで、その他の用途に
用いられる諸々の聖書一般と比べれば、書物活用の場でもある世の中全体を司る
聖書である点において、やはり別格級の存在意義を持っているからでこそある。
夏・殷・周の三代に渡る古代中国の治世のあり方を、春秋時代に孔子が五経として体系化し、
その孔子自身や弟子や亦弟子(孟子含む)の言説を取りまとめた四書がさらに朱子に
よって権威化された。両者を合わせて「四書五経」というが、四書五経は宋代に定型化された
儒学正典の代表書というまでのことで、これに漏れた「孝経」「周礼」「儀礼」「大載礼記」「国語」
などの儒書も、四書五経に勝るとも劣らない聖書として扱ってもまったく差し支えないもの
となっており、四書五経を含むこれら全ての聖書が、実際に天下国家全土における治世を
実現していく上でのマニュアルとなるに相応しいだけの、十分な度量を備えている。
実際に、当時世界最大規模の国力を誇った漢帝国や唐帝国や宋帝国、
死刑一つない治世を実験した平安朝や、識字率世界最高を誇った江戸の日本
などにおいて、四書五経に代表される儒学の聖書こそは、権力者から庶民に
至るまでの、「必須の教養」としての扱いを受け続けていたのだった。
四書五経の記述に基づくような治世が実現されて後に初めて興隆する、儒学以外の高度な文化
というものもまた別に多くあり、むしろそちらのほうが治世実現後の世の中における「花形」
としての扱いを受けたりもする。唐代における詩文芸の興隆や、宋代における禅仏教の興隆、
平安時代における密教文化や女流文芸の興隆、江戸時代における武芸文化や演劇文化の興隆などが
その好例であり、そのような人々を楽しませることにかけてより秀でている文化の興隆を実現する
「縁の下の力持ち」としての役割をも儒学は担って来たから、必ずしも目立つ存在ではなかった
せいで、あまり人々にその偉大さを意識されることすらないままでいることが多かったのだ。
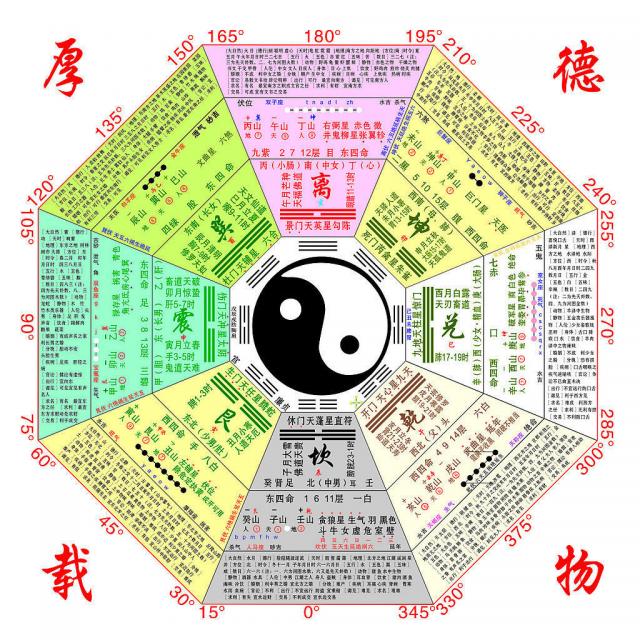
特筆するまでもないほどに標準的な聖書としての、その地位を守り続けてきている。
その理由は、四書五経が「社会統治の聖書」であるからで、その他の用途に
用いられる諸々の聖書一般と比べれば、書物活用の場でもある世の中全体を司る
聖書である点において、やはり別格級の存在意義を持っているからでこそある。
夏・殷・周の三代に渡る古代中国の治世のあり方を、春秋時代に孔子が五経として体系化し、
その孔子自身や弟子や亦弟子(孟子含む)の言説を取りまとめた四書がさらに朱子に
よって権威化された。両者を合わせて「四書五経」というが、四書五経は宋代に定型化された
儒学正典の代表書というまでのことで、これに漏れた「孝経」「周礼」「儀礼」「大載礼記」「国語」
などの儒書も、四書五経に勝るとも劣らない聖書として扱ってもまったく差し支えないもの
となっており、四書五経を含むこれら全ての聖書が、実際に天下国家全土における治世を
実現していく上でのマニュアルとなるに相応しいだけの、十分な度量を備えている。
実際に、当時世界最大規模の国力を誇った漢帝国や唐帝国や宋帝国、
死刑一つない治世を実験した平安朝や、識字率世界最高を誇った江戸の日本
などにおいて、四書五経に代表される儒学の聖書こそは、権力者から庶民に
至るまでの、「必須の教養」としての扱いを受け続けていたのだった。
四書五経の記述に基づくような治世が実現されて後に初めて興隆する、儒学以外の高度な文化
というものもまた別に多くあり、むしろそちらのほうが治世実現後の世の中における「花形」
としての扱いを受けたりもする。唐代における詩文芸の興隆や、宋代における禅仏教の興隆、
平安時代における密教文化や女流文芸の興隆、江戸時代における武芸文化や演劇文化の興隆などが
その好例であり、そのような人々を楽しませることにかけてより秀でている文化の興隆を実現する
「縁の下の力持ち」としての役割をも儒学は担って来たから、必ずしも目立つ存在ではなかった
せいで、あまり人々にその偉大さを意識されることすらないままでいることが多かったのだ。
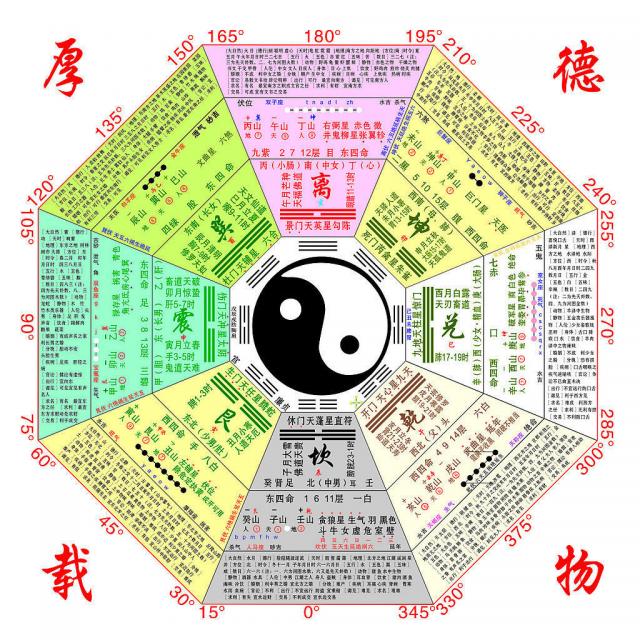
※省略されてます すべて表示...
「神は権力の上に置かれるか、さもなくば完全に撤廃されるか」といった極論から、まず脱却せねばならない。
それは、どちらもよろしくない選択肢であり、どちらを採ったところでマシな世の中すら実現され得ない代物なのだから。
そのような極論にばかり思考回路が追い詰められてしまっている人間にとっては、
そこからの脱却が死ぬほど恐ろしいことのように思われるかもしれないが、別にそれによって死ぬわけでもない。
むしろ、万民が神仏や王侯への帰依を「最適化」して、より快適な生活を送れるようになるきっかけとなるわけだから、
人としてのより活気ある将来こそを期待して、それに臨むべきなのだといえる。
「君に事うるには、貴かる可く、賤かる可く、富む可く、貧しかる可く、生く可く、殺さる可く、而して乱を為さしむ可からず」
「君侯に仕える以上は、自らが高貴となることも卑賤となることも、富裕となることも貧乏となることも、
生かされることも殺されることも全て受け入れる覚悟であった上で、自分はただ乱を招かないように務めるのみである。
(自分自身が君侯から利益を得たいばかりであるような人間には、始めから君侯に仕える資格すらないのである。)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・表記第三十二より)
それは、どちらもよろしくない選択肢であり、どちらを採ったところでマシな世の中すら実現され得ない代物なのだから。
そのような極論にばかり思考回路が追い詰められてしまっている人間にとっては、
そこからの脱却が死ぬほど恐ろしいことのように思われるかもしれないが、別にそれによって死ぬわけでもない。
むしろ、万民が神仏や王侯への帰依を「最適化」して、より快適な生活を送れるようになるきっかけとなるわけだから、
人としてのより活気ある将来こそを期待して、それに臨むべきなのだといえる。
「君に事うるには、貴かる可く、賤かる可く、富む可く、貧しかる可く、生く可く、殺さる可く、而して乱を為さしむ可からず」
「君侯に仕える以上は、自らが高貴となることも卑賤となることも、富裕となることも貧乏となることも、
生かされることも殺されることも全て受け入れる覚悟であった上で、自分はただ乱を招かないように務めるのみである。
(自分自身が君侯から利益を得たいばかりであるような人間には、始めから君侯に仕える資格すらないのである。)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・表記第三十二より)
思慮深く慎重であることと、ただハラハラドキドキしてるのとでは、当然全くの別物である。
何もかもにひどく一喜一憂させられる、嬉しがり悲しがりなどはかえって慎んで、
それでも恐るべきものを恐れ、楽しむべきものを楽しむものこそは、
薄氷を踏むように何事にも慎重で注意深くあろうとする人間だといえる。
ただのハラハラドキドキでもなければ、全くの無感情なのでもない。
厳重な思慮深さの中にこそ得られる歓喜や悲哀などというものもあるのであり、
厳しい修行の果てに啓いた悟りの歓喜だとか、必死の介護の果てに親が死んだことへの悲しみだとかが
それに当たる。それは、常日ごろからウレシがりカナシがりでばかりいるような人間などには決して
抱けないような、充実した歓喜や悲哀なのであり、(悲哀が充実しているというのは多少語弊があるが)
それ程にも実の伴った悲喜に与ればこそ、人は人としての人生を最大級に全うもするのである。
叙事詩「オデュッセイア」で主人公のオデュッセウスが、慎重な計画の末に一矢を報いたキュプロクスに対し、
逃走しながら感情を爆発させての罵倒の限りを尽くす場面だとか、長旅の末に妻ペネロペのいる自宅へと
戻ってきたら、しょうもない男どもが蝿のようにペネロペにたかっていたことに憤激して男どもを殺し回り、
中には男の性器を切り落とす場面までもがあったりとかいった所から鑑みるに、西洋流の思慮深さや慎重さ
というのは、ただただ感情を押し殺して機械のようにことを企てることばかりを指しているのが窺える。
東洋流の思慮深さ慎重深さというのはそれとは違い、上記のように、慎重で思慮深い中にこそそれなりの
情感を保つことを是とする。それにより、常日ごろから無理なく慎重さや思慮深さを保っていようとし、
オデュッセウスのように作戦や仕事が終わったからといって緊張の糸が切れるようなことも防ぎ続けるのである。
何もかもにひどく一喜一憂させられる、嬉しがり悲しがりなどはかえって慎んで、
それでも恐るべきものを恐れ、楽しむべきものを楽しむものこそは、
薄氷を踏むように何事にも慎重で注意深くあろうとする人間だといえる。
ただのハラハラドキドキでもなければ、全くの無感情なのでもない。
厳重な思慮深さの中にこそ得られる歓喜や悲哀などというものもあるのであり、
厳しい修行の果てに啓いた悟りの歓喜だとか、必死の介護の果てに親が死んだことへの悲しみだとかが
それに当たる。それは、常日ごろからウレシがりカナシがりでばかりいるような人間などには決して
抱けないような、充実した歓喜や悲哀なのであり、(悲哀が充実しているというのは多少語弊があるが)
それ程にも実の伴った悲喜に与ればこそ、人は人としての人生を最大級に全うもするのである。
叙事詩「オデュッセイア」で主人公のオデュッセウスが、慎重な計画の末に一矢を報いたキュプロクスに対し、
逃走しながら感情を爆発させての罵倒の限りを尽くす場面だとか、長旅の末に妻ペネロペのいる自宅へと
戻ってきたら、しょうもない男どもが蝿のようにペネロペにたかっていたことに憤激して男どもを殺し回り、
中には男の性器を切り落とす場面までもがあったりとかいった所から鑑みるに、西洋流の思慮深さや慎重さ
というのは、ただただ感情を押し殺して機械のようにことを企てることばかりを指しているのが窺える。
東洋流の思慮深さ慎重深さというのはそれとは違い、上記のように、慎重で思慮深い中にこそそれなりの
情感を保つことを是とする。それにより、常日ごろから無理なく慎重さや思慮深さを保っていようとし、
オデュッセウスのように作戦や仕事が終わったからといって緊張の糸が切れるようなことも防ぎ続けるのである。
 一時だけまったくの無信仰状態で厳密に分析的な学説を論及したりすることよりも、常日ごろから「智>信」
一時だけまったくの無信仰状態で厳密に分析的な学説を論及したりすることよりも、常日ごろから「智>信」 という序列を保ち続けることのほうがより重要である。それを五常としてわきまえるのが儒学でもあるから、
そんなわきまえのない洋学よりも儒学のほうがより純学問的だとは>>168-170でもすでに述べたことである。
それと全く同じで、一時だけ完全な無感情で徹底的に思慮深く慎重であったりするよりも、多少は感情を
差し挟む余地があってもいいから、常日ごろから一定以上の思慮深さ慎重さを保つようにしたほうがよい。
それでこそ、人は最大級の「総合的な思慮深さや慎重さ」を獲得することができるものでもあるからだ。
総合的に思慮深さ慎重さが多大であるということは、人が一生の内に嗜む思慮深さや慎重さが、
質でも量でもより多大であるということである。多少の感情も差し挟みながら、常日ごろからの
慎重さを保つことこそは、一時だけ完全な無感情状態での慎重さを極めたりすることよりも、
総合的な思慮深さや慎重さで上回る。上回るからこそ、安全保障の錬度や確度でも前者が後者を
上回るのであり、女子供や庶民までもが恒常的な拠り所とするに足るものともなるのである。
女子供や庶民のような弱者が、自分たちから最大級の思慮深さや慎重さの持ち主を頼りにしたがるとも限らない。
そんな人間は畏れ多くて近づくこともできず、むしろオデュッセウスみたいな危なっかしい側面の持ち主
にこそ親しみを抱いて近づきたがるかも知れない。だとすれば、女子供や小人たちもまた、自分たちより
優等な相手を嫉むルサンチマンに駆られたりしているに違いないわけで、それを払拭して、真に頼りとするに
値するからこそ、自分たちよりも優等であるような相手に対する崇敬を育んでいく所から始めなければならない。
ハラハラドキドキは女子供や小人の常である。
全くの無感情も、女子供や小人が嫉みまでをも抱くような対象ではない。
最大級の思慮深さと共に大人びた情緒までをも湛えていられることこそは、
それが確かに優れていると察せる一方で、自分たちには決して到達できない
境地でもあるものだから、女子供や小人にとっての嫉妬の対象ともなる。
嫉妬は羨望の裏返しでこそあるのだから、素直に羨望させればいいのである。
「所謂身を修むるは其の心を正すに在りとは、身に忿懥する所有れば、則ち其の正を得ず、恐懼する所有れば、
則ち其の正を得ず、好楽する所有れば、則ち其の正を得ず、憂患する所有れば、則ち其の正を得ざればなり」
「身を修めるためにはまず心から正さねばならない。もしやたらと怒りに駆られたり、恐れおののいたり、
好み楽しんだり、憂患したりするようであれば、それは心が正されていないからだ。(中庸・一には
『君子は見えぬ所にまで戒め慎み、聞こえぬ所にまで恐懼する』とあるが、これは上記のような、
無闇やたらなハラハラドキドキを払拭した上での慎重さを期すことこそを促しているのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——大学・七より)
全くの無感情も、女子供や小人が嫉みまでをも抱くような対象ではない。
最大級の思慮深さと共に大人びた情緒までをも湛えていられることこそは、
それが確かに優れていると察せる一方で、自分たちには決して到達できない
境地でもあるものだから、女子供や小人にとっての嫉妬の対象ともなる。
嫉妬は羨望の裏返しでこそあるのだから、素直に羨望させればいいのである。
「所謂身を修むるは其の心を正すに在りとは、身に忿懥する所有れば、則ち其の正を得ず、恐懼する所有れば、
則ち其の正を得ず、好楽する所有れば、則ち其の正を得ず、憂患する所有れば、則ち其の正を得ざればなり」
「身を修めるためにはまず心から正さねばならない。もしやたらと怒りに駆られたり、恐れおののいたり、
好み楽しんだり、憂患したりするようであれば、それは心が正されていないからだ。(中庸・一には
『君子は見えぬ所にまで戒め慎み、聞こえぬ所にまで恐懼する』とあるが、これは上記のような、
無闇やたらなハラハラドキドキを払拭した上での慎重さを期すことこそを促しているのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——大学・七より)
政財の癒着を徹底して分断するなどの清廉を尽くした道徳統治の持続などは、
完全な踏襲主義、世襲主義であるのが好ましく、仮に目付のような能力主義の陪臣家を
助役として別に置くとしても、あくまで下位のものとしての領分を守らせるべきである。
そうであるべきなのは、「新しいことをやりたがるような欲求」を為政に差し挟んだり
することがかえって害にばかりなるからで、無為自然の心持ちによって世の中を平穏に
司っていくためにも、むしろ世襲で仕方なく士業を引き継いで行くぐらいのほうがいいのである。
(>>160の左伝からの引用なども参照)
「天下国家を治めるが如き大業は、予め万端の準備を整えてから成せ」とは「中庸」二〇にも
大略としてある。世襲や良き前例の踏襲といった温故はもちろんのこと、事業を為すにかけての、
よく踏み止まっての準備なども、大業に欠かせられはしない。ほとんどそれらばかりを主として、
事業を推進していくことなどは完全な成り行きに任せるぐらいのつもりでいたほうがよい。
天下国家を司るような大業であればあるほど、過去に遡ることや、
じっと踏み止まって万端の準備を敷くことが必須となる。大業でないのならそんな
必要もなかったりするのは、あたかも小児の戯れが何もかも行き当たりばったりで
あるのと同時に、規模的には大したことでもないようなものだといえる。
過去の踏襲も、現在の注意も全く疎かにしての、ただ先へ先への行き当たりばったりで
全社会規模の大事業などを企てたりした場合にこそ、人も致命的な破滅から免れられなくなる。
小児や動物にそんな能力はないが、大人の男などには大事業を成す能力がある。にもかかわらず、
そうであるなりの温故や注意を欠いた場合にこそ、自業自得の破滅を呼び込んでしまうのである。
完全な踏襲主義、世襲主義であるのが好ましく、仮に目付のような能力主義の陪臣家を
助役として別に置くとしても、あくまで下位のものとしての領分を守らせるべきである。
そうであるべきなのは、「新しいことをやりたがるような欲求」を為政に差し挟んだり
することがかえって害にばかりなるからで、無為自然の心持ちによって世の中を平穏に
司っていくためにも、むしろ世襲で仕方なく士業を引き継いで行くぐらいのほうがいいのである。
(>>160の左伝からの引用なども参照)
「天下国家を治めるが如き大業は、予め万端の準備を整えてから成せ」とは「中庸」二〇にも
大略としてある。世襲や良き前例の踏襲といった温故はもちろんのこと、事業を為すにかけての、
よく踏み止まっての準備なども、大業に欠かせられはしない。ほとんどそれらばかりを主として、
事業を推進していくことなどは完全な成り行きに任せるぐらいのつもりでいたほうがよい。
天下国家を司るような大業であればあるほど、過去に遡ることや、
じっと踏み止まって万端の準備を敷くことが必須となる。大業でないのならそんな
必要もなかったりするのは、あたかも小児の戯れが何もかも行き当たりばったりで
あるのと同時に、規模的には大したことでもないようなものだといえる。
過去の踏襲も、現在の注意も全く疎かにしての、ただ先へ先への行き当たりばったりで
全社会規模の大事業などを企てたりした場合にこそ、人も致命的な破滅から免れられなくなる。
小児や動物にそんな能力はないが、大人の男などには大事業を成す能力がある。にもかかわらず、
そうであるなりの温故や注意を欠いた場合にこそ、自業自得の破滅を呼び込んでしまうのである。
小児や動物はもちろんのこと、大人の女にだって、自力で大事業を成す能力などはない。
だからこそというべきか、歴史を体系的に学びたがる女というのも少ない。歴史上の大人物の
ほとんどは男であり、女は出てきても悪女だったりするから、それがつまらなくもあるのだろうが、
だからといって、歴史的な大事業を成す能力のある大人の男にまで歴史忌避を強要するのもおかしい。
歴史感覚の豊かな男こそは、歴史的大事業をも磐石に成すことができる。故にこそ、本当に
女子供を養っていくにも値する。一方で、歴史感覚も注意力もない行き当たりばったりの男こそは、
ヘタに大事業に手を付けて自業自得の大破滅を招いたりするのだから、これこそは女子供を
守るにも値しない匹夫であると見なす他はない。してみればこそ、自分自身が歴史などに全く
興味のない女といえども、男に対しては、歴史に対する豊富な見解や、ことにあたっての慎重さ
などを期待すべきなのであり、そうでないような軽薄な男こそを「自分ともさして変わらない
品性の下劣さの持ち主」として親しんだりするようなことがないようにしなければならない。
それでこそ、女なりの婦徳を持った賢婦であるということまでもが言えるだろう。
そんな女は、今みたいな仁徳皆無の世の中には、共に皆無でもいるわけだが。
「君子は徳性を尊んで問学を道とし、広大を致して精微を尽くし、
高明を極めて中庸を道とし、故きを温めて新しきを知り、厚きを敦くして以って礼を崇ぶ」
「君子は徳性を尊びつつあらゆる事物に問い学ぶことを常道とし、その知見は広大さと精微さを尽くし、
高明さを極めてなおのこと中庸を常とし、古えを尋ねて新しきを知り、より重んずるべきものを
重んずることを通じて礼への崇敬を育む。(去来今にかけて広大精微な問学を志せばこそ、
儒者はその当然なる一環として、温故知新をも嗜むのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——中庸・二七より)
だからこそというべきか、歴史を体系的に学びたがる女というのも少ない。歴史上の大人物の
ほとんどは男であり、女は出てきても悪女だったりするから、それがつまらなくもあるのだろうが、
だからといって、歴史的な大事業を成す能力のある大人の男にまで歴史忌避を強要するのもおかしい。
歴史感覚の豊かな男こそは、歴史的大事業をも磐石に成すことができる。故にこそ、本当に
女子供を養っていくにも値する。一方で、歴史感覚も注意力もない行き当たりばったりの男こそは、
ヘタに大事業に手を付けて自業自得の大破滅を招いたりするのだから、これこそは女子供を
守るにも値しない匹夫であると見なす他はない。してみればこそ、自分自身が歴史などに全く
興味のない女といえども、男に対しては、歴史に対する豊富な見解や、ことにあたっての慎重さ
などを期待すべきなのであり、そうでないような軽薄な男こそを「自分ともさして変わらない
品性の下劣さの持ち主」として親しんだりするようなことがないようにしなければならない。
それでこそ、女なりの婦徳を持った賢婦であるということまでもが言えるだろう。
そんな女は、今みたいな仁徳皆無の世の中には、共に皆無でもいるわけだが。
「君子は徳性を尊んで問学を道とし、広大を致して精微を尽くし、
高明を極めて中庸を道とし、故きを温めて新しきを知り、厚きを敦くして以って礼を崇ぶ」
「君子は徳性を尊びつつあらゆる事物に問い学ぶことを常道とし、その知見は広大さと精微さを尽くし、
高明さを極めてなおのこと中庸を常とし、古えを尋ねて新しきを知り、より重んずるべきものを
重んずることを通じて礼への崇敬を育む。(去来今にかけて広大精微な問学を志せばこそ、
儒者はその当然なる一環として、温故知新をも嗜むのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——中庸・二七より)
磔刑への極度の恐怖による心神喪失状態だとか、
あるいは麻薬の服用や性交による朦朧状態だとかが真理に通ずるというのなら、
「真理は知能を極度に低下させたところにこそある」ということになる。
1+1が3にも4にもなり、馬も鹿になるようなところにこそ真理があることになる。
確かに「そうでもあり得る」というほうが、誤謬数理や矛盾許容論理までをも包含することになるから、
「真理は全て」という観点からいえば、真理を肯定し尽くすことに真摯であるということにすらなる。
それは万物斉同を唱える荘子なども是としていることであり、だからこそ荘子本人の著作であることが
ほぼ確かな「荘子」内篇の斉物論第二において、荘子も「動物の毛ほど大きいものはなく、泰山ほど小さいものはなく、
幼くして死んだ子供ほど長生きしたものはなく、八百歳生きたという彭祖ほど短命だったものもない」というような、
全く人間らしい正常な尺度を度外視した物言いにもあえて及んだのだった。
そういったバカアホ級の何でもありと、儒家で解くような善悪の分別との両方を理解できてこその、真理把捉者である。
老荘列などの道家は、儒家に対する否定的な見解も述べてはいたけれども、それでも、儒家の言わんとすることに対する
理解ぐらいはあったようである。特に、列子の物言いにその傾向が顕著だし、老荘も儒家の教条を理解した上であえてそこに
天邪鬼を唱えているからこそ、儒家への理解をほぼ完全に喪失している現代人にとってその論及が難解だったりするのである。
儒家が重んずる善悪の分別と、老荘が重んずる、誤謬や矛盾を含む万物の肯定の両者を止揚しているのが、大乗仏教である。
「あるもない、ないもない」といった般若の空の論理によって、厳密に論理的に万事万物を全否定することで等価なものとする。
そこから万事万物に対する無意識からの肯定意識を養っていく離れ業をやってのけているものだから、わざわざ意識的に肯定
するまでもないほどの好感(可愛楽)を常に湛えながら、善悪の分別に即した現実の俗世での処断すらもが自在となる。
あるいは麻薬の服用や性交による朦朧状態だとかが真理に通ずるというのなら、
「真理は知能を極度に低下させたところにこそある」ということになる。
1+1が3にも4にもなり、馬も鹿になるようなところにこそ真理があることになる。
確かに「そうでもあり得る」というほうが、誤謬数理や矛盾許容論理までをも包含することになるから、
「真理は全て」という観点からいえば、真理を肯定し尽くすことに真摯であるということにすらなる。
それは万物斉同を唱える荘子なども是としていることであり、だからこそ荘子本人の著作であることが
ほぼ確かな「荘子」内篇の斉物論第二において、荘子も「動物の毛ほど大きいものはなく、泰山ほど小さいものはなく、
幼くして死んだ子供ほど長生きしたものはなく、八百歳生きたという彭祖ほど短命だったものもない」というような、
全く人間らしい正常な尺度を度外視した物言いにもあえて及んだのだった。
そういったバカアホ級の何でもありと、儒家で解くような善悪の分別との両方を理解できてこその、真理把捉者である。
老荘列などの道家は、儒家に対する否定的な見解も述べてはいたけれども、それでも、儒家の言わんとすることに対する
理解ぐらいはあったようである。特に、列子の物言いにその傾向が顕著だし、老荘も儒家の教条を理解した上であえてそこに
天邪鬼を唱えているからこそ、儒家への理解をほぼ完全に喪失している現代人にとってその論及が難解だったりするのである。
儒家が重んずる善悪の分別と、老荘が重んずる、誤謬や矛盾を含む万物の肯定の両者を止揚しているのが、大乗仏教である。
「あるもない、ないもない」といった般若の空の論理によって、厳密に論理的に万事万物を全否定することで等価なものとする。
そこから万事万物に対する無意識からの肯定意識を養っていく離れ業をやってのけているものだから、わざわざ意識的に肯定
するまでもないほどの好感(可愛楽)を常に湛えながら、善悪の分別に即した現実の俗世での処断すらもが自在となる。
善悪の分別を万物の肯定とまた別に理解する必要があることは、これまた大乗仏教の唯識思想で確証されている。
人間にとっての善悪の分別にもそれなりの真理性があって、全くの蔑ろにするのでは最悪の苦痛や完全なる破滅までもが
免れられなくなるから、人間にとっての厄除けの処方としての普遍的な善悪の分別ぐらいは嗜むべきだとするのである。
1+1=3も鹿の馬呼ばわりも、何でもありの万事万物の肯定だけがあって、善悪の分別のほうは
全く疎かにしているというのなら、むしろ万物の肯定などしないでいる場合以上にも下劣なこととなる。
1+1=2、馬は馬、鹿は鹿、この程度の分別は小学生でもできることである。にもかかわらず、それに違う誤謬や
矛盾ばかりを是とするようなら、もはや小学生以下、多少頭のいい幼稚園児以下の品性にまで自らが下落したことともなる。
そうならないためには、まともな分別はまともな分別でよく貴んでいく必要があるわけで、1+1を2だけでなく3や4にも
してしまってそれでよしとするような人間にこそ、それは必須なことである。にもかかわらず、ただただ誤謬や矛盾を許容
しまくって、分別など全くの疎かにしたりするものだから、小学生以下の下品下生さしか残らないこととなるのである。
真理を知った人間こそは愚か者だろうか、そんなはずはない。真理こそは本来、人を人並み以上に成長させるものである。
それは、万事万物への理解とそれに対する分別という、全ての手管を尽くせばこそ達成されることであり、それこそは
本人自身が真理に適った姿ともなっている(だからこそ真理学である仏教にも断悪修善の教義が伴っているのである)。
誤謬や矛盾を含む万事万物を愛でようとしながら、分別だけは疎かにする、それは自分自身が全ての手管を尽くして
いないが故に真理にも悖っているのであり、故に上記のような原理で以って、人並み以下や小学生以下の品性にまで
没落させてしまうことともなる。真理への近づき方が真理に適っていないからこそ、真理などに近づかないでいる
場合以上にも下劣な自分自身と化してしまう。それは真理が悪いからではなく、自分が悪いからである。
人間にとっての善悪の分別にもそれなりの真理性があって、全くの蔑ろにするのでは最悪の苦痛や完全なる破滅までもが
免れられなくなるから、人間にとっての厄除けの処方としての普遍的な善悪の分別ぐらいは嗜むべきだとするのである。
1+1=3も鹿の馬呼ばわりも、何でもありの万事万物の肯定だけがあって、善悪の分別のほうは
全く疎かにしているというのなら、むしろ万物の肯定などしないでいる場合以上にも下劣なこととなる。
1+1=2、馬は馬、鹿は鹿、この程度の分別は小学生でもできることである。にもかかわらず、それに違う誤謬や
矛盾ばかりを是とするようなら、もはや小学生以下、多少頭のいい幼稚園児以下の品性にまで自らが下落したことともなる。
そうならないためには、まともな分別はまともな分別でよく貴んでいく必要があるわけで、1+1を2だけでなく3や4にも
してしまってそれでよしとするような人間にこそ、それは必須なことである。にもかかわらず、ただただ誤謬や矛盾を許容
しまくって、分別など全くの疎かにしたりするものだから、小学生以下の下品下生さしか残らないこととなるのである。
真理を知った人間こそは愚か者だろうか、そんなはずはない。真理こそは本来、人を人並み以上に成長させるものである。
それは、万事万物への理解とそれに対する分別という、全ての手管を尽くせばこそ達成されることであり、それこそは
本人自身が真理に適った姿ともなっている(だからこそ真理学である仏教にも断悪修善の教義が伴っているのである)。
誤謬や矛盾を含む万事万物を愛でようとしながら、分別だけは疎かにする、それは自分自身が全ての手管を尽くして
いないが故に真理にも悖っているのであり、故に上記のような原理で以って、人並み以下や小学生以下の品性にまで
没落させてしまうことともなる。真理への近づき方が真理に適っていないからこそ、真理などに近づかないでいる
場合以上にも下劣な自分自身と化してしまう。それは真理が悪いからではなく、自分が悪いからである。
「人亦た言える有り、柔ければ則ち之れを茹い、剛ければ則ち之れを吐くと。
維れ仲山甫のみは、柔きをも亦ち茹わず、剛きをも亦た吐かず、矜寡を侮らず、疆禦をも畏れず。
人亦た言える有り、徳の輶きこと毛の如くなるも、民に克く之れを挙ぐるものは鮮なしと。
我れ之れを儀図するに、維れ仲山甫のみ之れを挙ぐ、しむらくは之れを助くるもの莫し」
「ある人がこう言った。『柔らかい食い物は好んで食らい、硬い食い物は吐き捨てる。(意志薄弱なものの譬え)』
近ごろでは(周の卿士の)仲山甫ばかりがこれに違い、柔らかいからといって食わず、硬いからといって吐き捨てず、
鰥寡孤独の者をだからといって侮ったりもせず、荒くれ者をもだからといって畏怖したりもしないでいる。
またある人がこう言った。『徳を実践する軽さは毛ほどのものであるのに、民のうちでこれを挙げられるものもいない』
自分の推し量るに、やはり仲山甫のみがこれを挙げられているという他はなく、彼を助けられる者すら見当たりはしない。
(毛を挙げるほどにも簡単な徳の実践を人々が率先して為すことはおろか、人が為すのを助けようとすらしないのも、
柔らかいものだけを食べて硬いものは吐き捨てようとするような薄弱さによる。そのような薄弱さの持ち主こそは、
自らの多重人格の別人格を『神』に見立てるような、常人には到底受け入れがたい内面的所業にも及ぶのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・大雅・蕩之什・烝民より)
維れ仲山甫のみは、柔きをも亦ち茹わず、剛きをも亦た吐かず、矜寡を侮らず、疆禦をも畏れず。
人亦た言える有り、徳の輶きこと毛の如くなるも、民に克く之れを挙ぐるものは鮮なしと。
我れ之れを儀図するに、維れ仲山甫のみ之れを挙ぐ、しむらくは之れを助くるもの莫し」
「ある人がこう言った。『柔らかい食い物は好んで食らい、硬い食い物は吐き捨てる。(意志薄弱なものの譬え)』
近ごろでは(周の卿士の)仲山甫ばかりがこれに違い、柔らかいからといって食わず、硬いからといって吐き捨てず、
鰥寡孤独の者をだからといって侮ったりもせず、荒くれ者をもだからといって畏怖したりもしないでいる。
またある人がこう言った。『徳を実践する軽さは毛ほどのものであるのに、民のうちでこれを挙げられるものもいない』
自分の推し量るに、やはり仲山甫のみがこれを挙げられているという他はなく、彼を助けられる者すら見当たりはしない。
(毛を挙げるほどにも簡単な徳の実践を人々が率先して為すことはおろか、人が為すのを助けようとすらしないのも、
柔らかいものだけを食べて硬いものは吐き捨てようとするような薄弱さによる。そのような薄弱さの持ち主こそは、
自らの多重人格の別人格を『神』に見立てるような、常人には到底受け入れがたい内面的所業にも及ぶのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・大雅・蕩之什・烝民より)
元日早々から犯罪聖書の駄文を読まされるのも目障りなんで、まずは真正聖書の
「論語」の頁を無作為に開いてみた。そのとき真っ先に目に飛び込んできたのが以下の言葉。
「戦戦兢兢として、深淵に臨むが如く、薄氷を履むが如し」
(泰伯第八・三)
曾子が「詩経」小旻から引用した言葉で、このとき曾子は重篤だったため遺言も兼ねていた。今までは
戦々恐々として、薄氷を踏むように慎重な人生を送ってきたけれども、いま死の床について、やっと自分も
その緊張から解放されると、曾子は自らの五体満足な身体の手先などを見せながら弟子に言ったのだった。
深淵に臨むが如く、薄氷を踏むが如しとはいっても、実際に儒者が深山に立ち入ったり、薄氷を踏んだり
することを好き好んで行うわけではない。むしろそのような危うい行いに及ぶことから避けていく、
その回避にかけての慎重さからして、深淵に望むが如く、薄氷を踏むが如しでいようとするのである。
だから結局、儒者の行いはどこまでも常道の踏襲でいるわけで、平和の上にも平和を尽くす保守系なわけだけども、
それでいて心内はやはりいつも「戦戦兢兢」としている。平和だからといって平和に安んじきるのではなく、
いつ問題を来たさぬか、争いを招かぬかと、内憂外患の警戒を尽くし続けるのである。
儒者が必ず君子階級であるとは限らないが、これはまさに君子階級こそがそうあるべき姿勢だといえる。
匹夫小人なら世の中の情勢如何にかかわらず、ただ自分自身が安穏としていたいばかりでいたりするわけだが、
世の中の平穏の責任をも司る君子士人であるならば、逆に世の情勢の如何に関わらず、
常日ごろから戦戦兢兢とした警戒を続けていかなければならない。
「論語」の頁を無作為に開いてみた。そのとき真っ先に目に飛び込んできたのが以下の言葉。
「戦戦兢兢として、深淵に臨むが如く、薄氷を履むが如し」
(泰伯第八・三)
曾子が「詩経」小旻から引用した言葉で、このとき曾子は重篤だったため遺言も兼ねていた。今までは
戦々恐々として、薄氷を踏むように慎重な人生を送ってきたけれども、いま死の床について、やっと自分も
その緊張から解放されると、曾子は自らの五体満足な身体の手先などを見せながら弟子に言ったのだった。
深淵に臨むが如く、薄氷を踏むが如しとはいっても、実際に儒者が深山に立ち入ったり、薄氷を踏んだり
することを好き好んで行うわけではない。むしろそのような危うい行いに及ぶことから避けていく、
その回避にかけての慎重さからして、深淵に望むが如く、薄氷を踏むが如しでいようとするのである。
だから結局、儒者の行いはどこまでも常道の踏襲でいるわけで、平和の上にも平和を尽くす保守系なわけだけども、
それでいて心内はやはりいつも「戦戦兢兢」としている。平和だからといって平和に安んじきるのではなく、
いつ問題を来たさぬか、争いを招かぬかと、内憂外患の警戒を尽くし続けるのである。
儒者が必ず君子階級であるとは限らないが、これはまさに君子階級こそがそうあるべき姿勢だといえる。
匹夫小人なら世の中の情勢如何にかかわらず、ただ自分自身が安穏としていたいばかりでいたりするわけだが、
世の中の平穏の責任をも司る君子士人であるならば、逆に世の情勢の如何に関わらず、
常日ごろから戦戦兢兢とした警戒を続けていかなければならない。
基本そうであらねばならないのは君子だが、江戸初期の日本のように、巷で兵法書の購読が流行るほどにも、
人々がみな憂患を尽くすようになったなら、それもまた好ましいことである。戦国時代のような乱世だから
誰しもが孫呉に飛びついたりするのではなく、平和の獲得された治世においても、誰しもがよく警戒的でいる。
それがいわゆる、江戸っ子のいう「粋」の原形ともなったわけで、ただただ平民を家畜のようにのんべんだらり
とさせていたがために、人々の怠慢さを助長してしまった中国や今の欧米などとは一線を画す点なのである。
むろん、中国や欧米のような大規模な大陸社会では、世相の乱脈を防いで人々を安穏ならしめるだけでも精一杯
というところがありもするわけで、小人にまで君子並みの機敏さを持たせようなんてことからして夢のまた夢
のような話であるのかもしれない。日本人の機敏さは、魚食忠心の食生活などからもきているわけで、大陸の人間
誰しもが日本人みたいな食生活を目指したなら、海洋の食資源があっという間に枯渇するなどの限界点もまたある。
少なくとも、平和が獲得されたからといって誰しもがのんべんだらりとしててよくなるなん考え方だけは、
島国といわず大陸国といわず排さねばならない。どんな世の中でも君子は最大級の警戒を欠かさず、小人もまた
怠慢でいるよりは警戒的であったほうがよい。世の中全般、天下万民がなるべくそうあるべき指針としては、
「戦戦兢兢として、深淵に臨むが如く、薄氷を履むが如し」が理想であり、そうであることを忌むようなことが
ないようにせねばならない。あくまで指針上の話であって、どこまで達成されるかということには個体差がある。
人々がみな憂患を尽くすようになったなら、それもまた好ましいことである。戦国時代のような乱世だから
誰しもが孫呉に飛びついたりするのではなく、平和の獲得された治世においても、誰しもがよく警戒的でいる。
それがいわゆる、江戸っ子のいう「粋」の原形ともなったわけで、ただただ平民を家畜のようにのんべんだらり
とさせていたがために、人々の怠慢さを助長してしまった中国や今の欧米などとは一線を画す点なのである。
むろん、中国や欧米のような大規模な大陸社会では、世相の乱脈を防いで人々を安穏ならしめるだけでも精一杯
というところがありもするわけで、小人にまで君子並みの機敏さを持たせようなんてことからして夢のまた夢
のような話であるのかもしれない。日本人の機敏さは、魚食忠心の食生活などからもきているわけで、大陸の人間
誰しもが日本人みたいな食生活を目指したなら、海洋の食資源があっという間に枯渇するなどの限界点もまたある。
少なくとも、平和が獲得されたからといって誰しもがのんべんだらりとしててよくなるなん考え方だけは、
島国といわず大陸国といわず排さねばならない。どんな世の中でも君子は最大級の警戒を欠かさず、小人もまた
怠慢でいるよりは警戒的であったほうがよい。世の中全般、天下万民がなるべくそうあるべき指針としては、
「戦戦兢兢として、深淵に臨むが如く、薄氷を履むが如し」が理想であり、そうであることを忌むようなことが
ないようにせねばならない。あくまで指針上の話であって、どこまで達成されるかということには個体差がある。
削除(by投稿者)
「惰農自らを安んじ、作労を昏めず、田畝に服さず、越に其れ黍稷有ること罔し。
汝じ吉言にて百姓を和せざるは、惟れ汝じ自ら毒を生すなり。乃ち敗禍姦宄、
以て自ら厥の身に災す。乃ち既に悪を民に先んじ、乃ち其の恫みを奉ず。汝じ悔いるも
身に何ぞ及ばん。時の憸民を相るに、猶お箴言を胥い顧み、其れ逸口を発して有らん」
「怠惰な農夫が自らの安楽ばかりを求めて農作に努めず、田畝に赴こうともしないために、
作物も実らない。(そうなってしまうほどにも、民を化育する立場にあるおまえたちが)よい言葉によって
百姓を平和に導いてやりもしないでいるのは、おまえたち自身が害毒を為しているも同然のことだ。
(百姓が平和となるためには、せっせと田畑を耕して穀物を実らせる必要があるのである。
『礼記』楽記第十九や『左伝』昭公元年など、『平和』という言葉は、五穀豊穣を神に感謝する
ための雅楽が人々を相い和ませることこそを指して、最原初の頃には用いられてもいたのである)
その腐敗的な所業こそは、おまえたちに免れようのない禍いをもたらすだろう。民に先んじて悪を行い、
それにより禍いを被ってしまってから悔いたところで、それで助かるようなこともありはしない。
(化育者としての怠惰はありのままに、民に先んずる悪行と見なして差し支えないのである)
今の民たちですら、自分たちで自主的に警戒を促す言葉(それを昔は箴言といった)を
重んじて、失言を為さないように努めてすらいるのに。(犯罪聖書の箴言は失言の間違いだろう)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・商書・盤庚上より)
汝じ吉言にて百姓を和せざるは、惟れ汝じ自ら毒を生すなり。乃ち敗禍姦宄、
以て自ら厥の身に災す。乃ち既に悪を民に先んじ、乃ち其の恫みを奉ず。汝じ悔いるも
身に何ぞ及ばん。時の憸民を相るに、猶お箴言を胥い顧み、其れ逸口を発して有らん」
「怠惰な農夫が自らの安楽ばかりを求めて農作に努めず、田畝に赴こうともしないために、
作物も実らない。(そうなってしまうほどにも、民を化育する立場にあるおまえたちが)よい言葉によって
百姓を平和に導いてやりもしないでいるのは、おまえたち自身が害毒を為しているも同然のことだ。
(百姓が平和となるためには、せっせと田畑を耕して穀物を実らせる必要があるのである。
『礼記』楽記第十九や『左伝』昭公元年など、『平和』という言葉は、五穀豊穣を神に感謝する
ための雅楽が人々を相い和ませることこそを指して、最原初の頃には用いられてもいたのである)
その腐敗的な所業こそは、おまえたちに免れようのない禍いをもたらすだろう。民に先んじて悪を行い、
それにより禍いを被ってしまってから悔いたところで、それで助かるようなこともありはしない。
(化育者としての怠惰はありのままに、民に先んずる悪行と見なして差し支えないのである)
今の民たちですら、自分たちで自主的に警戒を促す言葉(それを昔は箴言といった)を
重んじて、失言を為さないように努めてすらいるのに。(犯罪聖書の箴言は失言の間違いだろう)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・商書・盤庚上より)
実際、この世界には、「神の意思」かと見紛われるほどにも作為的な極大現象というものがある。
とはいえ、それは別に特定の超越神の作為によるものだったりするのではなく、人間という
生物種族が本能的な集団意思を集約させることによって自然と捻出するものなのである。
およそ世界史上において、貧農から天下取りにまでのし上がるほどもの成功を果たした人物としては、
漢の高祖劉邦、明の太祖朱元璋、そして日本の豊臣秀吉などが挙げられる。ただ、このうちで
世襲の王朝継続までは実現できなかったのが豊臣秀吉であり、王朝を持続させられはしたものの
官僚腐敗などの致命的な問題を来たしたのが朱元璋であり、そのような問題を来たすことなく、
中国史上でも屈指の良王朝を築き上げられたのが劉邦だったという程度の違いがある。
豊臣秀吉が世襲の家門相続すら覚束なかったのは、何もかもを自分一人の意思ばかりに頼りすぎて、
王朝や幕府を形成して行けるだけのまとまった勢力確保を存続することができなかったからである。
朱元璋の興した明が深刻な腐敗を来たしたのも、やはり太祖たる本人からして孟子嫌い
だったりしながら、無理やり朱子学を国学に据えるなどのイビツな歴史的経緯があったからで、
形骸化した儒学の需要が政財界の癒着からなる経済的腐敗をも黙認してしまったからだった。
漢の高祖劉邦が興した漢王朝こそが、模範的な長期の治世をも実現することができたのは、
前二人と違い、劉邦が自らの意思ではなく寛容さこそを主体として天下取りにまで躍り出たからだった。
秀吉のように自らが戦略を練り込むのでもなく、主要な戦略はほとんど張良や韓信に任せきり、
項羽追討によって天下取りとしての立場が固まる瞬間まで、劉邦は虚心を第一として続けたのだった。
漢帝国の皇帝に即位して後も、為政にかけて我を張り通すようなことは極力避け、当初は儒者嫌いだった
にもかかわらず、陸賈の説得や、叔孫通の気の利いた礼楽の再興などを受けて全面的に儒学統治を取り入れもした。
とはいえ、それは別に特定の超越神の作為によるものだったりするのではなく、人間という
生物種族が本能的な集団意思を集約させることによって自然と捻出するものなのである。
およそ世界史上において、貧農から天下取りにまでのし上がるほどもの成功を果たした人物としては、
漢の高祖劉邦、明の太祖朱元璋、そして日本の豊臣秀吉などが挙げられる。ただ、このうちで
世襲の王朝継続までは実現できなかったのが豊臣秀吉であり、王朝を持続させられはしたものの
官僚腐敗などの致命的な問題を来たしたのが朱元璋であり、そのような問題を来たすことなく、
中国史上でも屈指の良王朝を築き上げられたのが劉邦だったという程度の違いがある。
豊臣秀吉が世襲の家門相続すら覚束なかったのは、何もかもを自分一人の意思ばかりに頼りすぎて、
王朝や幕府を形成して行けるだけのまとまった勢力確保を存続することができなかったからである。
朱元璋の興した明が深刻な腐敗を来たしたのも、やはり太祖たる本人からして孟子嫌い
だったりしながら、無理やり朱子学を国学に据えるなどのイビツな歴史的経緯があったからで、
形骸化した儒学の需要が政財界の癒着からなる経済的腐敗をも黙認してしまったからだった。
漢の高祖劉邦が興した漢王朝こそが、模範的な長期の治世をも実現することができたのは、
前二人と違い、劉邦が自らの意思ではなく寛容さこそを主体として天下取りにまで躍り出たからだった。
秀吉のように自らが戦略を練り込むのでもなく、主要な戦略はほとんど張良や韓信に任せきり、
項羽追討によって天下取りとしての立場が固まる瞬間まで、劉邦は虚心を第一として続けたのだった。
漢帝国の皇帝に即位して後も、為政にかけて我を張り通すようなことは極力避け、当初は儒者嫌いだった
にもかかわらず、陸賈の説得や、叔孫通の気の利いた礼楽の再興などを受けて全面的に儒学統治を取り入れもした。
劉邦の没後には、本人の遺言に即して、陳平や周勃が、正室家にして半ば政商でもあった呂氏を殲滅し、
漢室における政財癒着の問題の根をも断ち切った。劉邦の曾孫の武帝の代には大々的な贋金造りの摘発も行われ、
公務に失敗しようものなら引責自殺も辞さないような忠臣ばかりで君子階級が固められることともなった。
かような手続きを通じて、漢帝国は明や豊臣政権が来たしたような問題を予防や克服しつつの治世を築き上げた。
ほとんど裸一貫からのし上がった点では共通している三例であればこそ如実なのが、そうであって
なおかつ無我虚心を貫いたのが漢の劉家だった一方、ヘタクソな意思を差し挟んだのが明の朱家であり、
ほとんど自分自身の意思ばかりで全てを塗り固めようとしたのが豊臣秀吉だったという点である。
貧農ほどにも最底辺の身分であればこそ、世の中の大局をも俯瞰して、世界レベルの集団意思の大波に
乗ることすらもが可能となる場合がある。ただそれは、あくまで本人が劉邦のような虚心さを保ち続けられる
限りにおけるのであり、多少の恣意を差し挟んだりした時点ですでに、それなりの身分の持ち主などともさして
俯瞰力が変わらなくなる。俯瞰力も位持ち並みで、しかも自分は位なしというのだから、もはや何の価値も無くなる。
最底辺級の身分の持ち主こそは、それなりの身分の持ち主以上もの俯瞰力によって天命すらをも味方に付けられる
場合があるのは、天命も本質的には虚空の真理に即するものだからだ。天命を左右する主体などというものは
この世界にもその外側にもありはしないが、無為自然の中に自然と形成される天命らしきものがある。
それが決して誰かの恣意によって左右されるようなものではないからこそ、常日ごろから恣意を控えている
必要がある底辺身分の人間こそが、運気に乗っかって天命に与れるようなことがあるのである。
ただし、底辺身分こそはそのような運気に乗っかれるようであるとするなら、それは、世の中の有位者たちが
揃いも揃って天命に真っ向から反する凶事ばかりを働いている時代だったりもするに違いないわけだが。
漢室における政財癒着の問題の根をも断ち切った。劉邦の曾孫の武帝の代には大々的な贋金造りの摘発も行われ、
公務に失敗しようものなら引責自殺も辞さないような忠臣ばかりで君子階級が固められることともなった。
かような手続きを通じて、漢帝国は明や豊臣政権が来たしたような問題を予防や克服しつつの治世を築き上げた。
ほとんど裸一貫からのし上がった点では共通している三例であればこそ如実なのが、そうであって
なおかつ無我虚心を貫いたのが漢の劉家だった一方、ヘタクソな意思を差し挟んだのが明の朱家であり、
ほとんど自分自身の意思ばかりで全てを塗り固めようとしたのが豊臣秀吉だったという点である。
貧農ほどにも最底辺の身分であればこそ、世の中の大局をも俯瞰して、世界レベルの集団意思の大波に
乗ることすらもが可能となる場合がある。ただそれは、あくまで本人が劉邦のような虚心さを保ち続けられる
限りにおけるのであり、多少の恣意を差し挟んだりした時点ですでに、それなりの身分の持ち主などともさして
俯瞰力が変わらなくなる。俯瞰力も位持ち並みで、しかも自分は位なしというのだから、もはや何の価値も無くなる。
最底辺級の身分の持ち主こそは、それなりの身分の持ち主以上もの俯瞰力によって天命すらをも味方に付けられる
場合があるのは、天命も本質的には虚空の真理に即するものだからだ。天命を左右する主体などというものは
この世界にもその外側にもありはしないが、無為自然の中に自然と形成される天命らしきものがある。
それが決して誰かの恣意によって左右されるようなものではないからこそ、常日ごろから恣意を控えている
必要がある底辺身分の人間こそが、運気に乗っかって天命に与れるようなことがあるのである。
ただし、底辺身分こそはそのような運気に乗っかれるようであるとするなら、それは、世の中の有位者たちが
揃いも揃って天命に真っ向から反する凶事ばかりを働いている時代だったりもするに違いないわけだが。
「長者に於いて謀るには必ず几杖を操りて以て之れに従う。長者問うに、辞讓せずして対えるは非礼なり」
「年長者と共に物事を計画する場合には、必ず杖を携えてこれに従う。年長者が質問してきた場合にも、
『私の考えなど聞くに耐える程のものでもありません』などと謙りもせずに、即座に答えるようならば非礼である。
(真正聖書四書五経のほうが、犯罪聖書通称聖書よも、その成立時期からして数百年以上年長である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・曲礼上第一より)
「年長者と共に物事を計画する場合には、必ず杖を携えてこれに従う。年長者が質問してきた場合にも、
『私の考えなど聞くに耐える程のものでもありません』などと謙りもせずに、即座に答えるようならば非礼である。
(真正聖書四書五経のほうが、犯罪聖書通称聖書よも、その成立時期からして数百年以上年長である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・曲礼上第一より)
>>178の「中庸」からの引用を見ても分かるように、
儒者は去来今の広大無辺に渡る積極性の一環として、温故知新などの故旧をも貴んでいく。
これは大乗仏教の華厳思想などにも通ずる「時空の超越」であり、
ただの一方向ばかりに積極性を限らぬが故にこそ、積極性の極致でもあるといえる。
将来ばかりに積極的であるというのは、前向きのようでいて、実は「逃避」にかけてこそ積極的なのである。
過去からも、現在からも逃げて、ただ未来を追い求めて行くことにばかり積極的でいる、それは、
あらゆる積極性の中でもむしろ消極的な部類の積極性なのであり、そんなものを追い求めたりしなくても
自然と「時間ありて有あり、有ありて時間あり(正法眼蔵)」という不変法則に即して時間は流れて行く。
わざわざ希求しなくたって自然とやってくるものばかりを積極的に希求するというのだから、
易行か難行かでいえば易行であり、易行にしか積極的でいられないからには自分が愚か者なのである。
自分もまだ生まれていなかった頃の歴史にまで思いを馳せ、自らの行いとも照合して、何ら恥じるところが無く、
むしろ誇らしげにすら思えたりするのなら、それは時空を超越した愉悦であるといえ、世襲であれ否であれ、
己れの業を引き継がせて行くことを通じて、後継者にその愉悦をも受け継がせて行くことができる。
それが礼楽刑政の「楽」の要ともなり、代々の泰平統治の礎とすらなって行く。
そのような、去来今の三世を超越した時の流れの征服者であることこそは、人間としての最大の栄誉で
あると共に、自らが超人的な領域、神仏の域にすら近似する福寿ともなる。自分一身の命や意思をも超越した
絶対的なものとの合致によって、自分自身こそは最大級の福徳にも与ることができる。もしも人が永遠の命を
手に入れられたりするのならそうとも限らないだろうが、実際のところ諸行無常が真理でもあるから、永久不変の
絶対法則として、時空を超越した「歴史的人間」としての大成こそは、個人としても無常の栄華となるのである。
儒者は去来今の広大無辺に渡る積極性の一環として、温故知新などの故旧をも貴んでいく。
これは大乗仏教の華厳思想などにも通ずる「時空の超越」であり、
ただの一方向ばかりに積極性を限らぬが故にこそ、積極性の極致でもあるといえる。
将来ばかりに積極的であるというのは、前向きのようでいて、実は「逃避」にかけてこそ積極的なのである。
過去からも、現在からも逃げて、ただ未来を追い求めて行くことにばかり積極的でいる、それは、
あらゆる積極性の中でもむしろ消極的な部類の積極性なのであり、そんなものを追い求めたりしなくても
自然と「時間ありて有あり、有ありて時間あり(正法眼蔵)」という不変法則に即して時間は流れて行く。
わざわざ希求しなくたって自然とやってくるものばかりを積極的に希求するというのだから、
易行か難行かでいえば易行であり、易行にしか積極的でいられないからには自分が愚か者なのである。
自分もまだ生まれていなかった頃の歴史にまで思いを馳せ、自らの行いとも照合して、何ら恥じるところが無く、
むしろ誇らしげにすら思えたりするのなら、それは時空を超越した愉悦であるといえ、世襲であれ否であれ、
己れの業を引き継がせて行くことを通じて、後継者にその愉悦をも受け継がせて行くことができる。
それが礼楽刑政の「楽」の要ともなり、代々の泰平統治の礎とすらなって行く。
そのような、去来今の三世を超越した時の流れの征服者であることこそは、人間としての最大の栄誉で
あると共に、自らが超人的な領域、神仏の域にすら近似する福寿ともなる。自分一身の命や意思をも超越した
絶対的なものとの合致によって、自分自身こそは最大級の福徳にも与ることができる。もしも人が永遠の命を
手に入れられたりするのならそうとも限らないだろうが、実際のところ諸行無常が真理でもあるから、永久不変の
絶対法則として、時空を超越した「歴史的人間」としての大成こそは、個人としても無常の栄華となるのである。
自分個人の刹那的な栄華ばかりを追いかけて、後を振り返ってみれば醜悪な放辟邪侈の残骸ばかり、
だからこれからも将来の栄華ばかりを追い求めて行く、そのような悪循環に陥ってしまっている人間がいざ
自らの死に直面させられる時ほど、絶望的なことも他にない。人間である以上はいつかは死ぬ、にもかかわらず
誰にも褒められようのないような、邪まな無道ばかりをひた走り続けてきたままに命を終える、だからこそ、
大業ではなくともそれなりに堅実な人生を送ってきたような人間以上もの絶望にすら見舞われることとなる。
永遠の命などあり得ない、諸行無常こそは真理であるというわきまえが磐石であるなら、人は最大級の栄華を
追い求めるためにこそ、いち個人としての栄華以上にも、歴史的人物としての栄華こそを追い求めるはずである。
いつかは誰しもが死して灰燼に帰する、にもかかわらず自分一身の栄華ばかりを追い求めたりするよりは、
先人たちの偉業を引き継いで、自分もまた最善を尽くした大業を後継者へと受け継がせて行くようにする中での
栄華を追い求めていくほうが、明らかにより壮大かつ普遍的な栄華を追い求めていくことともなるのだから。
栄華など追い求めずに隠遁や出家に甘んじるというのなら、それも一つの生き方だといえる。ただ、
仮に自分が社会的な栄華を追い求めようと思うのならば、個人的な栄華以上にも、個人性を超えた
歴史的な大業を通じての栄華こそを追い求めて行くべきである。それでこそ、人と人とがお互いに
助け合うことでこそ成り立っている世の中における、純正な栄華の追い求め方ともなるのだから。
「日に省み月に試み、既廩事に称うは、百工を勧むる所以なり」
「工業従事者の生産労働などは特にその巧拙の落差が甚だしいため、日々その仕事を
省みて月々に技巧試験なども科し、仕事の手堅さに相応の報酬を与えて行くようにする必要がある。
(共産化による産業従事の平坦化が深刻な職務怠惰を招いた元凶の指摘。そのような問題を未然に防いでいる
というのなら、そのような人間こそは、共産主義と聖書信仰両方ともを非としているのだから、結構なことだ)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——中庸・二〇より)
だからこれからも将来の栄華ばかりを追い求めて行く、そのような悪循環に陥ってしまっている人間がいざ
自らの死に直面させられる時ほど、絶望的なことも他にない。人間である以上はいつかは死ぬ、にもかかわらず
誰にも褒められようのないような、邪まな無道ばかりをひた走り続けてきたままに命を終える、だからこそ、
大業ではなくともそれなりに堅実な人生を送ってきたような人間以上もの絶望にすら見舞われることとなる。
永遠の命などあり得ない、諸行無常こそは真理であるというわきまえが磐石であるなら、人は最大級の栄華を
追い求めるためにこそ、いち個人としての栄華以上にも、歴史的人物としての栄華こそを追い求めるはずである。
いつかは誰しもが死して灰燼に帰する、にもかかわらず自分一身の栄華ばかりを追い求めたりするよりは、
先人たちの偉業を引き継いで、自分もまた最善を尽くした大業を後継者へと受け継がせて行くようにする中での
栄華を追い求めていくほうが、明らかにより壮大かつ普遍的な栄華を追い求めていくことともなるのだから。
栄華など追い求めずに隠遁や出家に甘んじるというのなら、それも一つの生き方だといえる。ただ、
仮に自分が社会的な栄華を追い求めようと思うのならば、個人的な栄華以上にも、個人性を超えた
歴史的な大業を通じての栄華こそを追い求めて行くべきである。それでこそ、人と人とがお互いに
助け合うことでこそ成り立っている世の中における、純正な栄華の追い求め方ともなるのだから。
「日に省み月に試み、既廩事に称うは、百工を勧むる所以なり」
「工業従事者の生産労働などは特にその巧拙の落差が甚だしいため、日々その仕事を
省みて月々に技巧試験なども科し、仕事の手堅さに相応の報酬を与えて行くようにする必要がある。
(共産化による産業従事の平坦化が深刻な職務怠惰を招いた元凶の指摘。そのような問題を未然に防いでいる
というのなら、そのような人間こそは、共産主義と聖書信仰両方ともを非としているのだから、結構なことだ)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——中庸・二〇より)
人並みの罪識能力を保てることを「死」などと呼んで貶め、
罪識能力が保てないことを「生」などと呼んで誉めそやすことがあるとすれば、
これはありのままに人々の精神病質を助長する邪教であることが自明であり、
宗派教派の如何に関わらず、そんな教条を持つ信教などを倫理的な非難や
取締りの対象としていかなければならないことが明らかである。
実際に罪があるということ、罪を罪だと認識できることが生に近いか死に近いかということは、
解釈の仕方によってどうとでも言えることである。自分が罪を犯して、罪識があるために
良心の呵責に苛まれて苦しむ、そのことを以ってして「死に近い」などと小人なら
考えてしまいがちなものである。しかし君子としての見識から、良心の呵責を抱けるような
機敏な性情の持ち主こそは精神的な生者であり、罪に対する良心の呵責も抱けなくなって
しまっているような精神病質者こそは精神的な死者であると見なすこともできるのである。
ここは、真理ではなく道理の問題である。
解釈の仕方によってどうとでも言えるところを、あえて「一人前の罪識能力の持ち主こそは
生者であり、そうでない人間こそは死者である」と形容することのほうが道理に適っている一方、
「良心の呵責に苛まれているような人間こそは死者であり、良心の呵責などを抱かないで
いられる人間こそは生者である」などと形容することのほうが道理に反している。
孔子が「性相い近し、習えば相い遠し(陽貨第十七・二)」と言っていたのを引き継いで、
孟子は「人は本来性善だが、後天的に濁悪にまみれる場合がある」と言ったのに対し、
荀子は「人の生は本来悪であり、礼節の修得によって改善されて行く」といったのも、
孟子には人々をより根本から徳化していこうとする積極性があった一方、荀子には
そんな積極性はなく、濁悪まみれだった当時のような世の中でも受け入れられやすい
ような「同調圧力に屈した論及」をこしらえることしかできなかったからである。
罪識能力が保てないことを「生」などと呼んで誉めそやすことがあるとすれば、
これはありのままに人々の精神病質を助長する邪教であることが自明であり、
宗派教派の如何に関わらず、そんな教条を持つ信教などを倫理的な非難や
取締りの対象としていかなければならないことが明らかである。
実際に罪があるということ、罪を罪だと認識できることが生に近いか死に近いかということは、
解釈の仕方によってどうとでも言えることである。自分が罪を犯して、罪識があるために
良心の呵責に苛まれて苦しむ、そのことを以ってして「死に近い」などと小人なら
考えてしまいがちなものである。しかし君子としての見識から、良心の呵責を抱けるような
機敏な性情の持ち主こそは精神的な生者であり、罪に対する良心の呵責も抱けなくなって
しまっているような精神病質者こそは精神的な死者であると見なすこともできるのである。
ここは、真理ではなく道理の問題である。
解釈の仕方によってどうとでも言えるところを、あえて「一人前の罪識能力の持ち主こそは
生者であり、そうでない人間こそは死者である」と形容することのほうが道理に適っている一方、
「良心の呵責に苛まれているような人間こそは死者であり、良心の呵責などを抱かないで
いられる人間こそは生者である」などと形容することのほうが道理に反している。
孔子が「性相い近し、習えば相い遠し(陽貨第十七・二)」と言っていたのを引き継いで、
孟子は「人は本来性善だが、後天的に濁悪にまみれる場合がある」と言ったのに対し、
荀子は「人の生は本来悪であり、礼節の修得によって改善されて行く」といったのも、
孟子には人々をより根本から徳化していこうとする積極性があった一方、荀子には
そんな積極性はなく、濁悪まみれだった当時のような世の中でも受け入れられやすい
ような「同調圧力に屈した論及」をこしらえることしかできなかったからである。
結局、その論及姿勢としては、朱子などの主要な後代の儒者がみな、荀子ではなく孟子の
物言いにこそ軍配を挙げ、性即理説のような自前の論説による支援すらをも試みている。
(王陽明の心即理説も、孟子の性善説を過剰なほどに補強しようとするものでこそあった)
そのような諸々の儒者のあり方こそはありのままに、道理の啓発をより積極的に推進して
いくものであった。超俗の真理ではなく世俗の道理を専門的に司って行くのが儒者の本分で
あればこそ、道理をただ静観するだけでなく、積極的に啓発して行くことをも試みたのである。
無理だけでなく、道理もまた積極的に推進して行けるものである。
「無理が通れば道理が引っ込む」の逆として、「道理を通して無理を引っ込める」という
こともまたできることであり、撥乱反正が実現された長期の泰平社会などにおいては、ほぼ必ず
作為的な道理の啓発までもが推進されている。それ以前に乱世の辛酸を嘗め尽くしていればこそ、
「もうあんな時代はこりごり」という思いも込めて、より積極的に道理が肯んじられることとなる。
そういうことがあり得るからこそ、無理ばかりが通ることを恐れたりする必要もないのである。
精神病質の蔓延を推進するような邪教に急進的な傾向があるのと同じように、無理を排して
道理を通していく正学もまた健全な急進性を伴い得る。1+1=3であることなどを許さず、
馬は馬、鹿は鹿であることこそをより積極的に承認して行く道理の急進的な推進によってこそ、
無理を玩ぶ大火すらもが消し止められて、厳重な防火の用意すらもが整えられることとなる。
そこにこそ、人としての最高の楽しみまでもがある。人が最大級に精神的に活きられもする。
もちろん邪悪の楽しみなどというものもあるにしろ、それとはまた別に、それほどもの楽しみだとか
活気だとかがある。少なくともそういう解釈の仕方もできて、自分はそうであることこそを標榜し
もする。そのような姿勢こそが積極的な道理の推進ともなっていて、なおかつ本当に楽しいからだ。
物言いにこそ軍配を挙げ、性即理説のような自前の論説による支援すらをも試みている。
(王陽明の心即理説も、孟子の性善説を過剰なほどに補強しようとするものでこそあった)
そのような諸々の儒者のあり方こそはありのままに、道理の啓発をより積極的に推進して
いくものであった。超俗の真理ではなく世俗の道理を専門的に司って行くのが儒者の本分で
あればこそ、道理をただ静観するだけでなく、積極的に啓発して行くことをも試みたのである。
無理だけでなく、道理もまた積極的に推進して行けるものである。
「無理が通れば道理が引っ込む」の逆として、「道理を通して無理を引っ込める」という
こともまたできることであり、撥乱反正が実現された長期の泰平社会などにおいては、ほぼ必ず
作為的な道理の啓発までもが推進されている。それ以前に乱世の辛酸を嘗め尽くしていればこそ、
「もうあんな時代はこりごり」という思いも込めて、より積極的に道理が肯んじられることとなる。
そういうことがあり得るからこそ、無理ばかりが通ることを恐れたりする必要もないのである。
精神病質の蔓延を推進するような邪教に急進的な傾向があるのと同じように、無理を排して
道理を通していく正学もまた健全な急進性を伴い得る。1+1=3であることなどを許さず、
馬は馬、鹿は鹿であることこそをより積極的に承認して行く道理の急進的な推進によってこそ、
無理を玩ぶ大火すらもが消し止められて、厳重な防火の用意すらもが整えられることとなる。
そこにこそ、人としての最高の楽しみまでもがある。人が最大級に精神的に活きられもする。
もちろん邪悪の楽しみなどというものもあるにしろ、それとはまた別に、それほどもの楽しみだとか
活気だとかがある。少なくともそういう解釈の仕方もできて、自分はそうであることこそを標榜し
もする。そのような姿勢こそが積極的な道理の推進ともなっていて、なおかつ本当に楽しいからだ。
「書に曰く、安きに居りて危うきを思えと。
思えば則ち備え有り。備え有れば患え無し、と。敢えて此を以て規とす」
「書経(説命中、一部遺失)に『未だ安全である内にも危難を思って警戒せよ。予め危難を思って警戒することにより
備えができる。備えあれば憂いなし』とある。これこそを通用的な規則として、自分たちを正していくべきだといえる。
(規則とは本来、危難を避けるための備えなのだから、規則を取り払えばただ危難に見舞われるのみである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・襄公十一年より)
思えば則ち備え有り。備え有れば患え無し、と。敢えて此を以て規とす」
「書経(説命中、一部遺失)に『未だ安全である内にも危難を思って警戒せよ。予め危難を思って警戒することにより
備えができる。備えあれば憂いなし』とある。これこそを通用的な規則として、自分たちを正していくべきだといえる。
(規則とは本来、危難を避けるための備えなのだから、規則を取り払えばただ危難に見舞われるのみである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・襄公十一年より)
今年始め>>182-183の書き込みでも論じたように、心内はむしろ常日ごろからの警戒を尽くし、
現実における安全や平和こそを真摯に追い求めて行くのが、正しい人間のあり方である。
その逆のあり方、安からざる所に安らぎ、楽しむべからざる所に楽しむ体たらくを
荀子が「狂生(君道第十二)」と呼んだのに順ずるなら、上記のような内面の警戒と
外面の平安を尽くそうとするあり方こそは「正気の生」だといえる。
正気の生を保つためにこそ、人は決して一人だけでは生きられない、複数の人々が
家庭や世の中を共に形作ることを通じて初めて個人もまた生きられているのだということを
わきまえねばならない。それをわきまえることができて初めて、自分一身の安楽ばかりを
追い求めることなく、まずは他人を含む世の中の側の平安こそを優先して企図するようにもなれる。
理想としては、そのような正気の生に与れる人間だけで世の中が形成されるに越したことはない。
それでこそ、世の中もそこに住まう人間も総てが「健康体」でいられているともいえるわけだが、
なかなかそこにまで到達するのも難しいことで、多少は世の中の平安よりも
自分個人の安楽のほうを追い求めるような人間が生じもするものである。
それもまた、十分な抑制下に置かれてすらいれば、別に問題はないことである。
昔の日本などでも、豪商や地主身分の人間が相当に個人的な富裕を誇ることがあったわけだが、
それとて、武家による威力的な牽制が利いてもいたものだから、傾国級の問題にまでは発展しなかった。
(部落階級が人身御供的な差別対象となることで、素封の富裕が観念面から戒められてもいた)
治世を企図する立場から許されるのは、ここまでである。
現実における安全や平和こそを真摯に追い求めて行くのが、正しい人間のあり方である。
その逆のあり方、安からざる所に安らぎ、楽しむべからざる所に楽しむ体たらくを
荀子が「狂生(君道第十二)」と呼んだのに順ずるなら、上記のような内面の警戒と
外面の平安を尽くそうとするあり方こそは「正気の生」だといえる。
正気の生を保つためにこそ、人は決して一人だけでは生きられない、複数の人々が
家庭や世の中を共に形作ることを通じて初めて個人もまた生きられているのだということを
わきまえねばならない。それをわきまえることができて初めて、自分一身の安楽ばかりを
追い求めることなく、まずは他人を含む世の中の側の平安こそを優先して企図するようにもなれる。
理想としては、そのような正気の生に与れる人間だけで世の中が形成されるに越したことはない。
それでこそ、世の中もそこに住まう人間も総てが「健康体」でいられているともいえるわけだが、
なかなかそこにまで到達するのも難しいことで、多少は世の中の平安よりも
自分個人の安楽のほうを追い求めるような人間が生じもするものである。
それもまた、十分な抑制下に置かれてすらいれば、別に問題はないことである。
昔の日本などでも、豪商や地主身分の人間が相当に個人的な富裕を誇ることがあったわけだが、
それとて、武家による威力的な牽制が利いてもいたものだから、傾国級の問題にまでは発展しなかった。
(部落階級が人身御供的な差別対象となることで、素封の富裕が観念面から戒められてもいた)
治世を企図する立場から許されるのは、ここまでである。
世の中の平安よりも自分一身の安楽ばかりを追い求めることが抑制の対象にすらされず、挙句には
積極的な推進の対象にすらされるとなれば、これはもう乱世や亡国すらもが免れられるものではない。
今はもはや、自分個人の安楽ばかりを追い求めることが常識とすら化してしまっている時代である。
「自分第一世の中第二」や「自分が全て世の中無視」であるような人間こそは一般的な常識人としてすら
扱われている時代であり、しかもそれが「いつの時代にも共通する世の常」だとすら考えられている。
そんな常識は恒久的に通用するものではないから、いま人類社会も滅亡の危機に瀕している。そんな
常識が通用しないにもかかわらず、これまで人類はどうにかやって来ているわけだから、上記のような
現代にこそ特有の常識が、人類社会において持続的に通用していた試しもまたないことが確かである。
ジョンレノンは「今の世界は狂人が支配している」と言ったが、そもそも今の世の一般人からして
狂っている。別に精神病診断を受けたりしているわけでもない、健康体とされているような人間
からして、人類の滅亡にすら加担してやまぬほどもの深刻な病理を内に抱えてしまっている。
その狂気が正されるとき、人はかえってそれこそを狂気との遭遇だなどと勘違いしかねない。
本当は狂気から脱していく時なのに、狂気に駆られている現状こそを正気だなどと倒錯しているもの
だから、その倒錯に即して、狂気からの脱却こそを狂気への没入だなどと思い込んでしまうのである。
「江戸時代の人間は精神主義すぎて狂ってた」みたいなことが言われるのも、そのためである。
むしろ、何百年もの治世を保つためにこそ、江戸時代の日本人並みの精神力が必須なのであり、
今の人間並みに精神がへたり過ぎていることこそは、我と人とを破滅へと追いやる狂態なのである。
積極的な推進の対象にすらされるとなれば、これはもう乱世や亡国すらもが免れられるものではない。
今はもはや、自分個人の安楽ばかりを追い求めることが常識とすら化してしまっている時代である。
「自分第一世の中第二」や「自分が全て世の中無視」であるような人間こそは一般的な常識人としてすら
扱われている時代であり、しかもそれが「いつの時代にも共通する世の常」だとすら考えられている。
そんな常識は恒久的に通用するものではないから、いま人類社会も滅亡の危機に瀕している。そんな
常識が通用しないにもかかわらず、これまで人類はどうにかやって来ているわけだから、上記のような
現代にこそ特有の常識が、人類社会において持続的に通用していた試しもまたないことが確かである。
ジョンレノンは「今の世界は狂人が支配している」と言ったが、そもそも今の世の一般人からして
狂っている。別に精神病診断を受けたりしているわけでもない、健康体とされているような人間
からして、人類の滅亡にすら加担してやまぬほどもの深刻な病理を内に抱えてしまっている。
その狂気が正されるとき、人はかえってそれこそを狂気との遭遇だなどと勘違いしかねない。
本当は狂気から脱していく時なのに、狂気に駆られている現状こそを正気だなどと倒錯しているもの
だから、その倒錯に即して、狂気からの脱却こそを狂気への没入だなどと思い込んでしまうのである。
「江戸時代の人間は精神主義すぎて狂ってた」みたいなことが言われるのも、そのためである。
むしろ、何百年もの治世を保つためにこそ、江戸時代の日本人並みの精神力が必須なのであり、
今の人間並みに精神がへたり過ぎていることこそは、我と人とを破滅へと追いやる狂態なのである。
どんなに現時点で明白に訴えてみたところで、現状こそは普通であり、
現状から脱却させられることこそは狂気の沙汰だなどと考えてしまう人間を
今すぐに絶やし尽くすことまではできもしないとも知れている。「変化はどんなに善いことでもイヤだ」
と考えてしまうのは老人の常であり、今の資本主義先進国の大半も少子高齢化が深刻化してしまっているのだから、
(名目上の少子高齢化が抑えられている国なども、若い移民によって平均年齢を下げたりしているだけである)
現状の特殊性だけでなく、いつの世でもの常に即してすら、意識改革などなかなか覚束かないことだといえる。
過ちにこそ安住し、正されることこそを苦痛に思う、それは自分が人としての過ちを尽くし過ぎたからであり、
ちょうどゴミ屋敷を作ってしまった人間がそこに安住してしまうようなものだといえる。誰の目から見ても
ゴミを片付けたほうがいいように思えるが、ゴミ屋敷の住人自身は、それこそが普通のあり方だとする。
そういう観点から現状を捉えられる人間が、できる限り早くの内から多く現れてくれることを願うまでである。
「貞に安んずれば吉なり。〜貞に安んずるの吉なるは、地の疆り无きに應ずればなり」
「正しきに安んじれば吉である。正しきに安んじれば吉であるのは、地の果てに至るまでの正直に適うからである。
(正しからざるに安んずるのが狂生であり、狂生は不吉であるである一方、その逆はむしろ吉祥である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・坤・卦辞‐彖伝より)
現状から脱却させられることこそは狂気の沙汰だなどと考えてしまう人間を
今すぐに絶やし尽くすことまではできもしないとも知れている。「変化はどんなに善いことでもイヤだ」
と考えてしまうのは老人の常であり、今の資本主義先進国の大半も少子高齢化が深刻化してしまっているのだから、
(名目上の少子高齢化が抑えられている国なども、若い移民によって平均年齢を下げたりしているだけである)
現状の特殊性だけでなく、いつの世でもの常に即してすら、意識改革などなかなか覚束かないことだといえる。
過ちにこそ安住し、正されることこそを苦痛に思う、それは自分が人としての過ちを尽くし過ぎたからであり、
ちょうどゴミ屋敷を作ってしまった人間がそこに安住してしまうようなものだといえる。誰の目から見ても
ゴミを片付けたほうがいいように思えるが、ゴミ屋敷の住人自身は、それこそが普通のあり方だとする。
そういう観点から現状を捉えられる人間が、できる限り早くの内から多く現れてくれることを願うまでである。
「貞に安んずれば吉なり。〜貞に安んずるの吉なるは、地の疆り无きに應ずればなり」
「正しきに安んじれば吉である。正しきに安んじれば吉であるのは、地の果てに至るまでの正直に適うからである。
(正しからざるに安んずるのが狂生であり、狂生は不吉であるである一方、その逆はむしろ吉祥である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・坤・卦辞‐彖伝より)
以前にも、摩擦抵抗や関節の可動領域などの自由度の制限があるからこそ、
人間という生き物もまた成立しているということは述べた。そのような
制限による束縛をほとんど受けないアメーバやクラゲなどの生物もいるものの、
あまりにも原始的で、人間のような精密な有機性を持ち得てもいないわけで、
もしも人間が「完全なる自由」だの「永遠の命」だのを追い求めたところで、
そのような原始化の付帯が避けられない、ということも凡そ述べたことである。
無制限の自由を追い求めた先にあるのは、いつも原始化である。
人間にとっては稚拙化となり、それこそは「下劣」と見なされるに値するものである。
自由は稚拙であり、下劣である、そうであることを知った上でなお自由を求めるということも
完全に禁止されるべきことでもない。出家者でもない俗人が多少ハメを外して酒を飲んだり
することがあったって別に構いやしないが、それも度を越せば戒められるべきこととなる。
節度を保った自由ならいくらでもありだが、完全に無制限な自由ともなれば問題となる。
そのような自由こそを神聖化しようなどとする試みもまた、決してよしとすべきものではない。
必要悪としての自由ではなく、善いものとしての自由などを希求したりすることだけがいけない。
以上の論及で用いた「自由」は、福沢諭吉が英語のlibertyやfreedomを和訳した所の「自由」である。
「自由」という言葉自体は本来「臨済録」などに出てくる禅語であり、禅語としての「自由」は
むしろ追い求められて然るべきものである。というのは、英語のlibertyやfreedomが意味する所は
「行為能力の自由」であるのに対し、禅語の「自由」は「精神の自由」こそを指しているからだ。
人間という生き物もまた成立しているということは述べた。そのような
制限による束縛をほとんど受けないアメーバやクラゲなどの生物もいるものの、
あまりにも原始的で、人間のような精密な有機性を持ち得てもいないわけで、
もしも人間が「完全なる自由」だの「永遠の命」だのを追い求めたところで、
そのような原始化の付帯が避けられない、ということも凡そ述べたことである。
無制限の自由を追い求めた先にあるのは、いつも原始化である。
人間にとっては稚拙化となり、それこそは「下劣」と見なされるに値するものである。
自由は稚拙であり、下劣である、そうであることを知った上でなお自由を求めるということも
完全に禁止されるべきことでもない。出家者でもない俗人が多少ハメを外して酒を飲んだり
することがあったって別に構いやしないが、それも度を越せば戒められるべきこととなる。
節度を保った自由ならいくらでもありだが、完全に無制限な自由ともなれば問題となる。
そのような自由こそを神聖化しようなどとする試みもまた、決してよしとすべきものではない。
必要悪としての自由ではなく、善いものとしての自由などを希求したりすることだけがいけない。
以上の論及で用いた「自由」は、福沢諭吉が英語のlibertyやfreedomを和訳した所の「自由」である。
「自由」という言葉自体は本来「臨済録」などに出てくる禅語であり、禅語としての「自由」は
むしろ追い求められて然るべきものである。というのは、英語のlibertyやfreedomが意味する所は
「行為能力の自由」であるのに対し、禅語の「自由」は「精神の自由」こそを指しているからだ。
精神の自由を得るためには、むしろ行為能力利用の適切な自制や制限こそが必要である。
他人から無理やり制限を被るよりは、自分から進んで自制を心がけるほうがより有効であり、
その真摯さこそが精神の自由にも寄与しやすい。禅僧なども、親などに強制されて出家した場合よりは、
自分から進んで出家した場合のほうが大成しやすいとは、後者の理由に即して自主的に出家し、厳しい
修行をこなして日本臨済宗最大教派である妙心寺派の管長となった玄峰老師も言われていたことである。
精神の自由は、人としての稚拙化などを徹底して防ぎ止めた所にこそある。精神的な成熟を
極めたところにこそ、最大級の精神の自由もまたあるのだから、行為能力の濫用などによって
己れの品性を下落させてしまったのでは、かえって精神の自由は損なわれることになるのである。
「精神の自由と行為能力の自由は反比例関係にある」といっても、過言ではない。ただ、
行為能力を適正に活用することで精神の自由を保ったり助成したりすることは可能である。
それは、日本刀の刃筋ほどにも細く長い一本道を歩き続けるようなもので、決して行為能力の
自由などと共にあり得るものではない。仁政専門の為政者となったりすることがそれに当たるが、
仁政家になったからといってそれで自分が得するようなこともないわけで、行為能力の自由など
もむしろ制限される。それよりは、民間の素封家ででもいたほうがよっぽど金銭面などで自由で
いられるのは、昔の武家や公家などよりも、豪商や地主のほうがよっぽど潤っていたことからも窺える。
他人から無理やり制限を被るよりは、自分から進んで自制を心がけるほうがより有効であり、
その真摯さこそが精神の自由にも寄与しやすい。禅僧なども、親などに強制されて出家した場合よりは、
自分から進んで出家した場合のほうが大成しやすいとは、後者の理由に即して自主的に出家し、厳しい
修行をこなして日本臨済宗最大教派である妙心寺派の管長となった玄峰老師も言われていたことである。
精神の自由は、人としての稚拙化などを徹底して防ぎ止めた所にこそある。精神的な成熟を
極めたところにこそ、最大級の精神の自由もまたあるのだから、行為能力の濫用などによって
己れの品性を下落させてしまったのでは、かえって精神の自由は損なわれることになるのである。
「精神の自由と行為能力の自由は反比例関係にある」といっても、過言ではない。ただ、
行為能力を適正に活用することで精神の自由を保ったり助成したりすることは可能である。
それは、日本刀の刃筋ほどにも細く長い一本道を歩き続けるようなもので、決して行為能力の
自由などと共にあり得るものではない。仁政専門の為政者となったりすることがそれに当たるが、
仁政家になったからといってそれで自分が得するようなこともないわけで、行為能力の自由など
もむしろ制限される。それよりは、民間の素封家ででもいたほうがよっぽど金銭面などで自由で
いられるのは、昔の武家や公家などよりも、豪商や地主のほうがよっぽど潤っていたことからも窺える。
世の中の公益に寄与することだけを目的として行為能力を自制するのでは、堅苦しい。むしろ
精神の自由を得るためにこそ、そのための障りになる行為能力の自由を制限するぐらいであるべきだ。
金持ちや権力犯罪者こそは「精神の不能者」であることを戒めとして、行為能力の自制という精進に励む。
元より「精進」という言葉もそのような意味合いこそを伴っていたのであり、宗教法人法に守られる
ことで私腹を肥やしている今の日本の僧団などが本当に精進できているようなことも、極めて稀である。
精神の自由と行為能力の自由が別物であることすら、今はほとんど認知されてもいない。
両者が反比例関係にあることはおろか、比例的に連動しないことすら察知されてはいないものだから、
精神の自由こそを追い求めて行為能力の濫用に及んでしまっているような人間すらもが多々いる。
アルファベット圏の人間の多くはそうであり、禅語の「自由」をlibertyやfreedomの訳語として
用いてしまっている今の日本人にもそのような人間は多い。本来、「自由」という言葉はそんな
低劣な意味ばかりを持ち合わせいてたわけではないことを、今一度啓発し直していかねばならない。
精神の自由を得るためにこそ、そのための障りになる行為能力の自由を制限するぐらいであるべきだ。
金持ちや権力犯罪者こそは「精神の不能者」であることを戒めとして、行為能力の自制という精進に励む。
元より「精進」という言葉もそのような意味合いこそを伴っていたのであり、宗教法人法に守られる
ことで私腹を肥やしている今の日本の僧団などが本当に精進できているようなことも、極めて稀である。
精神の自由と行為能力の自由が別物であることすら、今はほとんど認知されてもいない。
両者が反比例関係にあることはおろか、比例的に連動しないことすら察知されてはいないものだから、
精神の自由こそを追い求めて行為能力の濫用に及んでしまっているような人間すらもが多々いる。
アルファベット圏の人間の多くはそうであり、禅語の「自由」をlibertyやfreedomの訳語として
用いてしまっている今の日本人にもそのような人間は多い。本来、「自由」という言葉はそんな
低劣な意味ばかりを持ち合わせいてたわけではないことを、今一度啓発し直していかねばならない。
「天下の士之れに悦するは人の欲する所なるも、以て憂いを解くに足らず。妃色は人の欲する所なるも、
帝の二女を妻とするといえども、以て憂いを解くに足らず。富は人の欲する所なるも、天下を富として有すれども、
以て憂いを解くに足らず。貴きは人の欲する所なるも、天子と為れども、以て憂いを解くに足らず。人之れに悦すと、
色を好むと、富貴なると、以て憂いを解くに足らず。惟だ父母に順るることのみ、以て憂いを解くに足る可し」
「天下の権力者たちがみな自分に従うこともまた欲せはするが、それによって憂いを解くには足らない。
妻女を得ることもまた欲せはするが、たとえ帝王の娘二人をめあわされた所で、それで憂いを解くには足らない。
富もまた欲せるものではあるが、たとえ天下全てを富として私有できたところで、それで憂いを解くには足らない。
尊貴であることも欲せるものではあるが、たとえ天下を統べる皇帝になれたとしても、それで憂いを解くには足らない。
権力者が服従すること、妻女を得ること、富貴に与れることのどれも憂いを解くには足らず、
ただ自らの親に喜ばれることのみが、真に自らの憂いを解くに値することである」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・万章章句上・一より)
帝の二女を妻とするといえども、以て憂いを解くに足らず。富は人の欲する所なるも、天下を富として有すれども、
以て憂いを解くに足らず。貴きは人の欲する所なるも、天子と為れども、以て憂いを解くに足らず。人之れに悦すと、
色を好むと、富貴なると、以て憂いを解くに足らず。惟だ父母に順るることのみ、以て憂いを解くに足る可し」
「天下の権力者たちがみな自分に従うこともまた欲せはするが、それによって憂いを解くには足らない。
妻女を得ることもまた欲せはするが、たとえ帝王の娘二人をめあわされた所で、それで憂いを解くには足らない。
富もまた欲せるものではあるが、たとえ天下全てを富として私有できたところで、それで憂いを解くには足らない。
尊貴であることも欲せるものではあるが、たとえ天下を統べる皇帝になれたとしても、それで憂いを解くには足らない。
権力者が服従すること、妻女を得ること、富貴に与れることのどれも憂いを解くには足らず、
ただ自らの親に喜ばれることのみが、真に自らの憂いを解くに値することである」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・万章章句上・一より)
神道で主に忌まれている血肉の穢れなども一種の汚れには違いないが、その他
にも色々な汚れというものはある。結局、最も致命的なのは「心の汚れ」であって、
その他のあらゆる汚れもまた心の汚れに結び付くことこそが最たる問題となるのである。
心の汚れは精神面における汚れであり、視聴覚や嗅覚によって外的に精神が
汚されることもあるし、自他の行業の粗悪さによって精神が汚されることもある。
精神が汚される原因となる現象はいくらでもあるが、それらの現象は根本的に
何なのであるかといえば、「命の不正な操作にまつわる現象」であるのだといえる。
簡単に言えば「罪のある現象」だが、法律や宗教の戒律に基づいて
定義される「罪」が「命の不正な操作」であるとは限らない。旧約の割礼や
飲酒運転などのように、それ自体がなんら命の操作に関わりのないものである
場合もあるわけだから、罪一般を帯びた現象が必ず汚れをもたらすとも限らない。
殺人は人の命を奪うことだから、命の不正な操作である場合がほとんどである。
(重罪人に対する相応の刑罰としての死刑などを除く)傷害も緩慢な命の不正操作となるし、
窃盗も他人の財物を奪うことで相手を貧窮に追いやったりすることが、間接的な命の
不正操作となる。このあたりの通用的な罪は、まさに汚れの元凶となるものである。
動物を殺してまでその肉を食らおうとすることなども、度を越せばBSEや
鳥獣インフルエンザのような人間にまで危害を及ぼす災禍をもたらすわけだから、
多少は人間たち自身の命の不正操作にも結び付き得ることである。大気汚染や
森林伐採などの環境破壊も、人間自身がそれによって諸々の悪影響を被るのだから、
人命の不正操作にまつわるものであり得るが故に、汚れをも帯びるものだといえる。
にも色々な汚れというものはある。結局、最も致命的なのは「心の汚れ」であって、
その他のあらゆる汚れもまた心の汚れに結び付くことこそが最たる問題となるのである。
心の汚れは精神面における汚れであり、視聴覚や嗅覚によって外的に精神が
汚されることもあるし、自他の行業の粗悪さによって精神が汚されることもある。
精神が汚される原因となる現象はいくらでもあるが、それらの現象は根本的に
何なのであるかといえば、「命の不正な操作にまつわる現象」であるのだといえる。
簡単に言えば「罪のある現象」だが、法律や宗教の戒律に基づいて
定義される「罪」が「命の不正な操作」であるとは限らない。旧約の割礼や
飲酒運転などのように、それ自体がなんら命の操作に関わりのないものである
場合もあるわけだから、罪一般を帯びた現象が必ず汚れをもたらすとも限らない。
殺人は人の命を奪うことだから、命の不正な操作である場合がほとんどである。
(重罪人に対する相応の刑罰としての死刑などを除く)傷害も緩慢な命の不正操作となるし、
窃盗も他人の財物を奪うことで相手を貧窮に追いやったりすることが、間接的な命の
不正操作となる。このあたりの通用的な罪は、まさに汚れの元凶となるものである。
動物を殺してまでその肉を食らおうとすることなども、度を越せばBSEや
鳥獣インフルエンザのような人間にまで危害を及ぼす災禍をもたらすわけだから、
多少は人間たち自身の命の不正操作にも結び付き得ることである。大気汚染や
森林伐採などの環境破壊も、人間自身がそれによって諸々の悪影響を被るのだから、
人命の不正操作にまつわるものであり得るが故に、汚れをも帯びるものだといえる。
家の部屋を汚いままにして掃除もしないでいれば、そのせいで自分が鼻炎などの
アレルギー反応を催したりするのも、ごく軽微ではあるが、命の不正操作にまつわる
現象であるといえる。そういったわかりやすい汚れから、地球規模の環境破壊による
人間自身の破滅の危機に至るまで、実害を伴うものこそは不可避に汚れてもいる。
偽物の血や死体を用いたホラー映画などで汚れを演出してみたところで、
実害を伴う現象の汚れには遠く及ばないものとなっている。
ただ、汚い部屋でも平気でいられるような人間もまたいるようにして、
実害の伴う現象の汚れにこそ鈍感な人間もまたいる。そのような人間に限って、架空の
ホラー映画あたりには心底恐怖したりもするわけで、それは正常な危機意識を欠いている
がための問題点であり、そのような人間こそは汚れに染まりきった人間であるともいえる。
まともに汚れを汚れだと把握できるうちは、自分自身が汚れてはいない。
もはや汚れを汚れだと認識することもできなくなってしまっているような人間こそは、
自分自身が汚れに染まりきってしまってもいる。そのような人間こそはかえって、
「自分は汚れから遠ざかっている」などとすら勘違いもする。俗世には汚れなど掃いて
捨てるほどあるにもかかわらず、自分の周りに汚れなんて見当たらないなんて思える人間が
いたとしたなら、そんな人間はほぼ間違いなく自分自身が汚れてしまっているのだといえる。
アレルギー反応を催したりするのも、ごく軽微ではあるが、命の不正操作にまつわる
現象であるといえる。そういったわかりやすい汚れから、地球規模の環境破壊による
人間自身の破滅の危機に至るまで、実害を伴うものこそは不可避に汚れてもいる。
偽物の血や死体を用いたホラー映画などで汚れを演出してみたところで、
実害を伴う現象の汚れには遠く及ばないものとなっている。
ただ、汚い部屋でも平気でいられるような人間もまたいるようにして、
実害の伴う現象の汚れにこそ鈍感な人間もまたいる。そのような人間に限って、架空の
ホラー映画あたりには心底恐怖したりもするわけで、それは正常な危機意識を欠いている
がための問題点であり、そのような人間こそは汚れに染まりきった人間であるともいえる。
まともに汚れを汚れだと把握できるうちは、自分自身が汚れてはいない。
もはや汚れを汚れだと認識することもできなくなってしまっているような人間こそは、
自分自身が汚れに染まりきってしまってもいる。そのような人間こそはかえって、
「自分は汚れから遠ざかっている」などとすら勘違いもする。俗世には汚れなど掃いて
捨てるほどあるにもかかわらず、自分の周りに汚れなんて見当たらないなんて思える人間が
いたとしたなら、そんな人間はほぼ間違いなく自分自身が汚れてしまっているのだといえる。
邪教信仰で自分自身が汚れに染まり、汚れを汚れだと認識できなくなるようなこともあるが、
むしろより根本的なのは、カネの濫用で汚れを汚れだと認識できなくなることのほうである。
古代のユダヤ人なども、政商として巨万の富を思うがままに操れることに精神をやられて、
ユダヤ教やキリスト教などの元祖「汚穢認識喪失型邪教」をでっち上げもしたわけで、
市場での投機資金や国家規模の税収のような大金の濫用こそは、自分自身がそうとも
気づかないうちから、人名の不正操作に加担する元凶の最たるものともなっている。
殺傷や窃盗のようなあからさまな犯罪は警戒もしやすいから、その規模もさほどには
ならない。肉食依存や地球規模の環境破壊もまた、未だ不十分とはいえ、それなりに
問題意識が高められつつある。大金の不正な取り回しによる窮乏者の死傷こそは、
未だまともな問題意識が抱かれることもなく野放しのままにされていると同時に、
今の世界における未曾有の規模の大害悪ともなっている。
そのようなことが現代に限った問題でないのは、金融犯罪(主に贋金造り)が
野放しにされていた武帝即位時の前漢帝国で数多の餓死者が発生していたという
「漢書」の記録などからも察せられることである。いくら血肉の汚れを忌んで見たところで、
自分がカネを不正に取り回した挙句に人々を窮死に追いやるという問題に対する忌避感は生じない。
故に、日本列島のような商売が一定以上の規模とはなり得ない狭隘地でもない限りは、
士農工商の位階すらをも徹底することで、悪徳商売の横行を防いで行くようにするのでも
なければ、金融犯罪の蔓延からなる大破綻すらもが免れ得なくなるのである。
むしろより根本的なのは、カネの濫用で汚れを汚れだと認識できなくなることのほうである。
古代のユダヤ人なども、政商として巨万の富を思うがままに操れることに精神をやられて、
ユダヤ教やキリスト教などの元祖「汚穢認識喪失型邪教」をでっち上げもしたわけで、
市場での投機資金や国家規模の税収のような大金の濫用こそは、自分自身がそうとも
気づかないうちから、人名の不正操作に加担する元凶の最たるものともなっている。
殺傷や窃盗のようなあからさまな犯罪は警戒もしやすいから、その規模もさほどには
ならない。肉食依存や地球規模の環境破壊もまた、未だ不十分とはいえ、それなりに
問題意識が高められつつある。大金の不正な取り回しによる窮乏者の死傷こそは、
未だまともな問題意識が抱かれることもなく野放しのままにされていると同時に、
今の世界における未曾有の規模の大害悪ともなっている。
そのようなことが現代に限った問題でないのは、金融犯罪(主に贋金造り)が
野放しにされていた武帝即位時の前漢帝国で数多の餓死者が発生していたという
「漢書」の記録などからも察せられることである。いくら血肉の汚れを忌んで見たところで、
自分がカネを不正に取り回した挙句に人々を窮死に追いやるという問題に対する忌避感は生じない。
故に、日本列島のような商売が一定以上の規模とはなり得ない狭隘地でもない限りは、
士農工商の位階すらをも徹底することで、悪徳商売の横行を防いで行くようにするのでも
なければ、金融犯罪の蔓延からなる大破綻すらもが免れ得なくなるのである。
別に、世界中を見回してみても、現状でそのような教条が一般的に
広められたことがあるわけでもないが、これからは「カネは汚れている」
という風に考えて行くぐらいがちょうどいいのではないかと思う。
別にカネが必ずしも汚れているわけではない。正常に扱えば物流の便利な道具となるのみだが、
多少儲かる商売などが横行しただけでもはや、利益の我田引水を通じての人命の不正操作に
直結してしまうわけだから、カネが極めて汚れやすいものであることだけは間違いがない。
商売人が多少儲けたりすることがあるのならば、もはや天下のゼニもみな少なからず汚れて
しまっているのだといえる。だから、カネは汚れていると考えてもほとんどおかしくはない。
そういった通念が十分に行き渡ったなら、別に身分制度によって商工階級を徹底的な
差別下に置いたりする必要もなくなるだろうが、それもまた難しいことだろうか。
「川沢も汚を納れ、山藪も疾を蔵し、瑾瑜も瑕を匿す。国君も垢を含むは、天の道なり」
「川や沢にも汚水が流れ込むことがあり、山や藪も毒のある生き物を宿し、美しい宝玉もその内に
疵を隠し持っている。国君といえども恥汚れを呑まなければならないことがあるのが天道である。
(仏道帰依で天人五衰を予防することもできはするものの、それは天道とは別物である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・宣公十五年より)
「春秋の稱は微にして顕われ、志にして晦く、婉にして章を成し、 尽にして汚ならず、悪を懲らして善を勧む」
「『春秋経』の筆法は、字数は少ないがその意味は明らかであり、 明確に言うときにも露骨になることを避け、
遠回しに言うときにも筋道を通し、実際のところを直言して事実を曲げず、 勧善懲悪を基調として書かれている。
(この引用は既出。『汚』とは『事実を曲げる』という意味でもあり、事実歪曲甚だしい犯罪聖書も
『汚書』と呼ぶに値するものとなっている。また、事実を曲げることは勧善懲悪にも反している」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・成公十四年より)
広められたことがあるわけでもないが、これからは「カネは汚れている」
という風に考えて行くぐらいがちょうどいいのではないかと思う。
別にカネが必ずしも汚れているわけではない。正常に扱えば物流の便利な道具となるのみだが、
多少儲かる商売などが横行しただけでもはや、利益の我田引水を通じての人命の不正操作に
直結してしまうわけだから、カネが極めて汚れやすいものであることだけは間違いがない。
商売人が多少儲けたりすることがあるのならば、もはや天下のゼニもみな少なからず汚れて
しまっているのだといえる。だから、カネは汚れていると考えてもほとんどおかしくはない。
そういった通念が十分に行き渡ったなら、別に身分制度によって商工階級を徹底的な
差別下に置いたりする必要もなくなるだろうが、それもまた難しいことだろうか。
「川沢も汚を納れ、山藪も疾を蔵し、瑾瑜も瑕を匿す。国君も垢を含むは、天の道なり」
「川や沢にも汚水が流れ込むことがあり、山や藪も毒のある生き物を宿し、美しい宝玉もその内に
疵を隠し持っている。国君といえども恥汚れを呑まなければならないことがあるのが天道である。
(仏道帰依で天人五衰を予防することもできはするものの、それは天道とは別物である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・宣公十五年より)
「春秋の稱は微にして顕われ、志にして晦く、婉にして章を成し、 尽にして汚ならず、悪を懲らして善を勧む」
「『春秋経』の筆法は、字数は少ないがその意味は明らかであり、 明確に言うときにも露骨になることを避け、
遠回しに言うときにも筋道を通し、実際のところを直言して事実を曲げず、 勧善懲悪を基調として書かれている。
(この引用は既出。『汚』とは『事実を曲げる』という意味でもあり、事実歪曲甚だしい犯罪聖書も
『汚書』と呼ぶに値するものとなっている。また、事実を曲げることは勧善懲悪にも反している」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・成公十四年より)
人間は一人では生きられない生き物であり、
なおかつ誰かと共にい続けることもできない生き物である。
親も自然と自分よりも早く死ぬものだし、妻や夫も自分とは別個に死ぬのが普通である。
軍人なら戦死で友と別れるなんてのはありきたりなことだし、他の社会人でも
友や兄弟と死に別れたり生き別れたりすることは決して少ないことではない。それでいて、
人間という生き物はある程度以上そういった相手がいないと成り立たない生き物なのでもある。
仏教で、人間が免れることができないとされる八つの苦しみの中にも「愛別離苦」がある。
愛するものと離別することを苦しまなければならないのは、愛するものと一時は共にあることでこそ
人間や人間社会といったものが成り立つからでもある。夫婦陰陽相和するのでなければ万物の化育も
あり得ない。いつかはまた分かれなければならない夫婦親子が共に家を形作るのでもなければ、人間社会
の最小単位すら成立することがない。故に、人間と愛別離苦の苦しみとは不可分なものなのである。
その苦しみを真理の悟りによって克服して行くのなら、人間として特に問題のあることではない。
昔の正統な仏門で、出家するものが自家から出たなら、それによって家の側が長きの繁栄に与れるともされた。
それは、愛別離苦などの苦しみにかられて家を損なうようなことが、家から出家者を出すことでこそ予防する
ことができたからで、現代人が出家に対して抱いている暗いイメージなどとはかけ離れている側面だといえる。
よくないのは、愛別離苦の苦しみを不実な気休めで紛らわしたりすることである。
実在しない超越神をでっち上げて「永遠にそばにいてくださる」などとし、それで別れの苦しみを紛らわし
たりしたとしたなら、それで家の繁栄を助成するどころか、かえって家を損なうことにすらなってしまう。
なおかつ誰かと共にい続けることもできない生き物である。
親も自然と自分よりも早く死ぬものだし、妻や夫も自分とは別個に死ぬのが普通である。
軍人なら戦死で友と別れるなんてのはありきたりなことだし、他の社会人でも
友や兄弟と死に別れたり生き別れたりすることは決して少ないことではない。それでいて、
人間という生き物はある程度以上そういった相手がいないと成り立たない生き物なのでもある。
仏教で、人間が免れることができないとされる八つの苦しみの中にも「愛別離苦」がある。
愛するものと離別することを苦しまなければならないのは、愛するものと一時は共にあることでこそ
人間や人間社会といったものが成り立つからでもある。夫婦陰陽相和するのでなければ万物の化育も
あり得ない。いつかはまた分かれなければならない夫婦親子が共に家を形作るのでもなければ、人間社会
の最小単位すら成立することがない。故に、人間と愛別離苦の苦しみとは不可分なものなのである。
その苦しみを真理の悟りによって克服して行くのなら、人間として特に問題のあることではない。
昔の正統な仏門で、出家するものが自家から出たなら、それによって家の側が長きの繁栄に与れるともされた。
それは、愛別離苦などの苦しみにかられて家を損なうようなことが、家から出家者を出すことでこそ予防する
ことができたからで、現代人が出家に対して抱いている暗いイメージなどとはかけ離れている側面だといえる。
よくないのは、愛別離苦の苦しみを不実な気休めで紛らわしたりすることである。
実在しない超越神をでっち上げて「永遠にそばにいてくださる」などとし、それで別れの苦しみを紛らわし
たりしたとしたなら、それで家の繁栄を助成するどころか、かえって家を損なうことにすらなってしまう。
実際、そのような気休めで別れの苦しみを紛らわしてきた欧米社会たるや、まともに家系が保たれた試しもない。
せいぜい遺産が莫大である場合などに名を継ぐものが多少続いたりするだけで、家を守るということそれ自体が
貴ばれるということがない。それは、愛する家族が死に別れる苦しみを虚構の超越神への帰依などによって
紛らわし続けること自体に無理があるからで、そのペースで家を守っていく志しなど生じようもないからだ。
いま、社会の最小単位としての家をよく守っていくということが、地球人類社会にとっての急務ともなっている。
個々人ではなく個々の家から尊重して、その厳重な継続に務めていくのでなければ、やりたい放題からなる
人口爆発にも歯止めがかからないから、禁治産措置によって子孫を絶やしたりするのでもない限りは、
家を守っていく心がけを保てる生き方をしていくことが必須となる。そのためには、家の繁栄を約束する
仏教や神道に帰依することは許される一方で、愛別離苦の苦しみを紛らわしながらかえって増幅させてしまう
虚構の超越神への心理的帰依などは排して行かなければならない。「聖書信仰を排すべし」ということは
すでに幾度も述べてきているが、そうせざるを得ない具体的証拠の一つが、以上のような論及ともなっている。
「日昃くの離なり。缶を鼓みて歌わざれば、則ち大耋の嗟きあらん。凶なり」
「太陽も日没には天上から離別するようにして、人の命もまたいつかは寿命でなくなるものである。
その時に酒杯を叩いて唄うぐらいの朗らかさでなければ、八十を過ぎても老衰を嘆くことになる。凶である。
(諸行無常のわきまえがあればこそ、その思い切りも付く。それを妨げたりはすべきでない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・離・九三)
せいぜい遺産が莫大である場合などに名を継ぐものが多少続いたりするだけで、家を守るということそれ自体が
貴ばれるということがない。それは、愛する家族が死に別れる苦しみを虚構の超越神への帰依などによって
紛らわし続けること自体に無理があるからで、そのペースで家を守っていく志しなど生じようもないからだ。
いま、社会の最小単位としての家をよく守っていくということが、地球人類社会にとっての急務ともなっている。
個々人ではなく個々の家から尊重して、その厳重な継続に務めていくのでなければ、やりたい放題からなる
人口爆発にも歯止めがかからないから、禁治産措置によって子孫を絶やしたりするのでもない限りは、
家を守っていく心がけを保てる生き方をしていくことが必須となる。そのためには、家の繁栄を約束する
仏教や神道に帰依することは許される一方で、愛別離苦の苦しみを紛らわしながらかえって増幅させてしまう
虚構の超越神への心理的帰依などは排して行かなければならない。「聖書信仰を排すべし」ということは
すでに幾度も述べてきているが、そうせざるを得ない具体的証拠の一つが、以上のような論及ともなっている。
「日昃くの離なり。缶を鼓みて歌わざれば、則ち大耋の嗟きあらん。凶なり」
「太陽も日没には天上から離別するようにして、人の命もまたいつかは寿命でなくなるものである。
その時に酒杯を叩いて唄うぐらいの朗らかさでなければ、八十を過ぎても老衰を嘆くことになる。凶である。
(諸行無常のわきまえがあればこそ、その思い切りも付く。それを妨げたりはすべきでない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——易経・離・九三)
家から出家者を出すことによる家の繁栄を図るためには、
当然二男三男や分家の人間などを優先的ゆ出家させるようにしなければならない。
本家の長男あたりまで出家させようものなら、本末転倒となる。
そういった便宜を図って行くのであれば、家族主義の神道と
出家主義の仏教もまた共存が可能となって、いい具合となる。
当然二男三男や分家の人間などを優先的ゆ出家させるようにしなければならない。
本家の長男あたりまで出家させようものなら、本末転倒となる。
そういった便宜を図って行くのであれば、家族主義の神道と
出家主義の仏教もまた共存が可能となって、いい具合となる。
人間が本当に苦しみから解放されるのは、それこそ死ぬ時である。
生きるということは基本苦しみの塊であり、その中に多少苦しみの軽減や
楽しみがあるだけのことであるというのが仏教の「一切皆苦」の教えでもある。
悲観ではなく、単なる現実としての一切皆苦という法則を把握して、断悪修善や勧善懲悪による
苦しみの軽減や楽しみを追い求めていくことでこそ、人は最高級の楽しみや苦しまずに与ることができる。
そもそも「生きる」ということ自体が楽しみの塊であるなどと思い込んで、ただ過剰な生を謳歌しようとして放辟邪侈
などに走った場合に、人は楽しみを追い求めているつもりでいながら、より大きな苦しみに苛まれることともなる。
生きるということは基本、死ぬ以上もの苦しみなのだから、ただただ粗大な生を貪ったりしたなら、
自然とより大きな苦しみに苛まれることとなるのである。それよりは、細々としながらも罪のない人生を
送っていくほうがはるかに苦しみの少ない人生を送れるものである。だからといってそんな仙人か坊主みたいな
人生を送るばかりが全てでもなく、勧善懲悪や断悪修善を推進していくことにかけてこそ盛大であるような
生き方をすることでこそ、人として最大級に楽しくて苦しゅうない人生を送ることができるのでもある。
何度もいうが、それを可能とするのが「権力道徳者」としての活動である。
権力道徳者としての活動を活発化すらさせたなら、それによってほぼ必ず純粋な勧善懲悪を推進して行ける。
他の立場、たとえば商売人としての活動を活発化させたからといってそれが勧善懲悪の推進などになることは
ほぼ全くないが、聖王賢臣としての仁政などを推進すらしていったなら、それは自動的に勧善懲悪の推進ともなる。
権力道徳者としての活動以外の活動というものを活発化させていくことも当然、人間には可能であり、
現代人など、その手の活動しかやっていなかったりする。仁政不能の乱世に特有の活動ばかりを好き好んでやっていて、
それらの活動こそは、たとえば江戸時代に賢い殿様が敷いていた善政などよりも遥かに「如実に粗大」であったりする。
生きるということは基本苦しみの塊であり、その中に多少苦しみの軽減や
楽しみがあるだけのことであるというのが仏教の「一切皆苦」の教えでもある。
悲観ではなく、単なる現実としての一切皆苦という法則を把握して、断悪修善や勧善懲悪による
苦しみの軽減や楽しみを追い求めていくことでこそ、人は最高級の楽しみや苦しまずに与ることができる。
そもそも「生きる」ということ自体が楽しみの塊であるなどと思い込んで、ただ過剰な生を謳歌しようとして放辟邪侈
などに走った場合に、人は楽しみを追い求めているつもりでいながら、より大きな苦しみに苛まれることともなる。
生きるということは基本、死ぬ以上もの苦しみなのだから、ただただ粗大な生を貪ったりしたなら、
自然とより大きな苦しみに苛まれることとなるのである。それよりは、細々としながらも罪のない人生を
送っていくほうがはるかに苦しみの少ない人生を送れるものである。だからといってそんな仙人か坊主みたいな
人生を送るばかりが全てでもなく、勧善懲悪や断悪修善を推進していくことにかけてこそ盛大であるような
生き方をすることでこそ、人として最大級に楽しくて苦しゅうない人生を送ることができるのでもある。
何度もいうが、それを可能とするのが「権力道徳者」としての活動である。
権力道徳者としての活動を活発化すらさせたなら、それによってほぼ必ず純粋な勧善懲悪を推進して行ける。
他の立場、たとえば商売人としての活動を活発化させたからといってそれが勧善懲悪の推進などになることは
ほぼ全くないが、聖王賢臣としての仁政などを推進すらしていったなら、それは自動的に勧善懲悪の推進ともなる。
権力道徳者としての活動以外の活動というものを活発化させていくことも当然、人間には可能であり、
現代人など、その手の活動しかやっていなかったりする。仁政不能の乱世に特有の活動ばかりを好き好んでやっていて、
それらの活動こそは、たとえば江戸時代に賢い殿様が敷いていた善政などよりも遥かに「如実に粗大」であったりする。
為政者のやっていることというのは、それこそ「雲上の仕事」であり、庶民にはどうしたって分かりにくい所がある。
それは民主制を敷いている今の諸国でも同じことで、結局のところ政治なんかより、民間企業がやっていること
などのほうが庶民からすれば親しみやすい。親しみやすくて分かりやすいから、その仕事が大きければ、
その大きさも実感しやすい。故に、民間の商売人としての活動などが極大化している今の社会での活動こそは、
権力道徳者が行う盛大な活動などよりも遥かに「如実に粗大」なものともなっている。
「仏の救いは微妙不可思議なものである」とは、他力本願の浄土門ですら肯んじられていることである。
権力道徳者の活動も、庶民にはなかなか図り知りがたい雲上の仕事であればこそ、世の中を丸ごと吉方へと導くような、
純粋な勧善懲悪の事業たりうるのである。逆に民間の商売人としての仕事などは、私利私益を求めることばかりに
専らであるからこそ庶民にも分かりやすいのであり、分かりやすいからといってそれが善美だったりするわけではない。
邪学邪教の流布によってルサンチマンを極大化させられてしまっている現代人の多くは、為政者即悪人というほどもの
固定観念すら持ち合わせてしまっている。特に、封建社会の為政者などは「お山の大将」「過去の遺物」などとしてその
存在価値を顧みようともしない。確かに、封建社会の為政者が権力犯罪をやらかす場合ほど如実に醜悪なことも他に
ないが、それと同時に、封建制に基づく権力道徳の実践こそが、人として最大級の勧善懲悪たり得るのでもある。
民間の商売人としての事業などは、よさげな部分はいかにもよさげに見せびらかせる一方で、悪い部分はいくらでも
隠し通せる。そもそも同じ民間人である大衆などにわざわざお伺いを立てなければならないような身分ではないと、
特に民主主義社会の素封家こそは認められるわけで、為政者による抑圧を解かれた民間の素封家たちは、
それこそ人として最大級の放辟邪侈にまみれた所業をもやってのけ始めたのである。
それは民主制を敷いている今の諸国でも同じことで、結局のところ政治なんかより、民間企業がやっていること
などのほうが庶民からすれば親しみやすい。親しみやすくて分かりやすいから、その仕事が大きければ、
その大きさも実感しやすい。故に、民間の商売人としての活動などが極大化している今の社会での活動こそは、
権力道徳者が行う盛大な活動などよりも遥かに「如実に粗大」なものともなっている。
「仏の救いは微妙不可思議なものである」とは、他力本願の浄土門ですら肯んじられていることである。
権力道徳者の活動も、庶民にはなかなか図り知りがたい雲上の仕事であればこそ、世の中を丸ごと吉方へと導くような、
純粋な勧善懲悪の事業たりうるのである。逆に民間の商売人としての仕事などは、私利私益を求めることばかりに
専らであるからこそ庶民にも分かりやすいのであり、分かりやすいからといってそれが善美だったりするわけではない。
邪学邪教の流布によってルサンチマンを極大化させられてしまっている現代人の多くは、為政者即悪人というほどもの
固定観念すら持ち合わせてしまっている。特に、封建社会の為政者などは「お山の大将」「過去の遺物」などとしてその
存在価値を顧みようともしない。確かに、封建社会の為政者が権力犯罪をやらかす場合ほど如実に醜悪なことも他に
ないが、それと同時に、封建制に基づく権力道徳の実践こそが、人として最大級の勧善懲悪たり得るのでもある。
民間の商売人としての事業などは、よさげな部分はいかにもよさげに見せびらかせる一方で、悪い部分はいくらでも
隠し通せる。そもそも同じ民間人である大衆などにわざわざお伺いを立てなければならないような身分ではないと、
特に民主主義社会の素封家こそは認められるわけで、為政者による抑圧を解かれた民間の素封家たちは、
それこそ人として最大級の放辟邪侈にまみれた所業をもやってのけ始めたのである。
民間の商売人などによる放辟邪侈まみれの事業が、権力道徳者の活動を規模面で上回ることもある。
呂不韋のような政商の活動を大々的に容認していた秦国こそは、それよりはまだ清浄な為政を
執り行っている場合もあった春秋戦国時代の諸国を征服して統一帝国を立ち上げられもした。
政治家の活動は旺盛でも民間人の活動は貧弱である場合よりは、政治家も民間人も
共に活動が旺盛である場合のほうが一時的な国力などを極大化させられもする。しかし、
そのような形での国力の増強はそう長く持つものではなく、秦帝国も短期で瓦解したし、
政財両面の活動が活発である今の資本主義諸国も、少子高齢化などによるどん詰まり化が著しい。
政治家を自分たちにとって都合のいいノミの夫婦の夫状態とさせてまでのやりたい放題に及んでいた
民間の素封家などが、権力道徳者とそのまま共存できたりするわけもない。増税ぐらいで済むなら
まだしも、服装や乗車の制限みたいな封建的差別すらをも講じなければならなくなりもする。
結局、封建制というものを敷かなければならない最大の理由もそういったところにあるのであり、
放辟邪侈まみれの粗大な活動を適正に取り締まっていくことこそは、勧善懲悪の実践ともなるのである。
してみれば、勧善懲悪と放辟邪侈はコインの裏表であり、一方の活動が旺盛であるならば、
もう一方の活動もそれと同じぐらいに活発であり得るということである。春秋諸国や秦帝国が
もたらした国土の荒廃の治癒に取り組んだ漢帝国の事業こそは、秦帝国のそれ並みに盛大たり得もした。
始皇帝が失敗した泰山での封禅も武帝が成功させ、当時までの中国史上では最大級の繁栄をも実現した。
だからこそ、放辟邪侈主体だった時代が勧善懲悪主体の時代に転換するからといって、その活動が
矮小化することなどを危惧したりする必要はない。むしろそれから後の世界においてこそ、健全かつ
最大級の繁栄すらもが約束されているのだから、民間の商売人などが自分たちの都合に合わせて「世界が
暗黒の時代に突入する」みたいな触れ回りをしていたりしたとしても、決してそれに耳を貸すべきではない。
呂不韋のような政商の活動を大々的に容認していた秦国こそは、それよりはまだ清浄な為政を
執り行っている場合もあった春秋戦国時代の諸国を征服して統一帝国を立ち上げられもした。
政治家の活動は旺盛でも民間人の活動は貧弱である場合よりは、政治家も民間人も
共に活動が旺盛である場合のほうが一時的な国力などを極大化させられもする。しかし、
そのような形での国力の増強はそう長く持つものではなく、秦帝国も短期で瓦解したし、
政財両面の活動が活発である今の資本主義諸国も、少子高齢化などによるどん詰まり化が著しい。
政治家を自分たちにとって都合のいいノミの夫婦の夫状態とさせてまでのやりたい放題に及んでいた
民間の素封家などが、権力道徳者とそのまま共存できたりするわけもない。増税ぐらいで済むなら
まだしも、服装や乗車の制限みたいな封建的差別すらをも講じなければならなくなりもする。
結局、封建制というものを敷かなければならない最大の理由もそういったところにあるのであり、
放辟邪侈まみれの粗大な活動を適正に取り締まっていくことこそは、勧善懲悪の実践ともなるのである。
してみれば、勧善懲悪と放辟邪侈はコインの裏表であり、一方の活動が旺盛であるならば、
もう一方の活動もそれと同じぐらいに活発であり得るということである。春秋諸国や秦帝国が
もたらした国土の荒廃の治癒に取り組んだ漢帝国の事業こそは、秦帝国のそれ並みに盛大たり得もした。
始皇帝が失敗した泰山での封禅も武帝が成功させ、当時までの中国史上では最大級の繁栄をも実現した。
だからこそ、放辟邪侈主体だった時代が勧善懲悪主体の時代に転換するからといって、その活動が
矮小化することなどを危惧したりする必要はない。むしろそれから後の世界においてこそ、健全かつ
最大級の繁栄すらもが約束されているのだから、民間の商売人などが自分たちの都合に合わせて「世界が
暗黒の時代に突入する」みたいな触れ回りをしていたりしたとしても、決してそれに耳を貸すべきではない。
「不仁、不智、無礼、無義は、人に役せらるものなり。人に役せらるものにして役を為すを恥ずるは、由お
弓人にして弓を為るを恥じ、矢人にして矢を為るを恥ずるが如し。之れを恥ずるなら、仁と為るに如くは莫し」
「不仁や無知や無礼や不義でいるものは、人に夫役を課せられる身分であるのが当たり前である。召使の身分
でありながら召使であることを恥じるのは、弓職人が弓を作るのを恥じ、矢職人が矢を作るのを恥じるのと全く
同じことだ。それが恥であるというのなら、仁者となる他はない。(不仁者は永遠に召使であり続ける他はない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・公孫丑章句上・七より)
弓人にして弓を為るを恥じ、矢人にして矢を為るを恥ずるが如し。之れを恥ずるなら、仁と為るに如くは莫し」
「不仁や無知や無礼や不義でいるものは、人に夫役を課せられる身分であるのが当たり前である。召使の身分
でありながら召使であることを恥じるのは、弓職人が弓を作るのを恥じ、矢職人が矢を作るのを恥じるのと全く
同じことだ。それが恥であるというのなら、仁者となる他はない。(不仁者は永遠に召使であり続ける他はない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・公孫丑章句上・七より)
大道が廃れ、さらには仁義までもが廃れてから、すでに久しい。
つまり、真理に適うことも、道理を守ることも、共に廃れきってしまっているが現代という時代である。
その証拠に、儒者として飯を食っていくことも、自力作善の仏者として食っていくことも覚束ない。
大学の中国哲学科や仏教哲学科なども単なる知識を学び教えるというばかりのこと止まりで、
最高級の学者といえどもその知識内容を忠実に実践したりすることはない。せいぜい
自分の知識を我流の筆法で披露した書籍を販促して儲けたりすることがあるぐらいである。
個人的に儒学や仏教の教えを好むようなことがあっても、それに忠実に従うなどということはできない。
渋沢栄一なぞも、本来は権力道徳のための倫理である儒学上の倫理体系を、商売哲学として相当に
曲解することで初めて、近代における実践対象としていた。それは当然、儒学の忠実な実践などには
なっていないわけで、かえって人々に儒学への偏見を抱かせる原因ばかりになったのである。
ただ、それらも現状、大いに肯んじる他はない現実である。
「そんなことはない、これほどもの乱世であっても、それなりに儒学や仏教を実践して行ける余地はある」
などという綺麗ごとを言うことはできても、実際そんなことはない。他力本願の念仏や曲解儒学の実践なら
ともかく、自力作善の本格仏教や、道徳統治を本分とする本物の儒学の実践までもが覚束くものではない。
だからこそ、今のような破滅寸前の乱世の責任を、儒学や仏教に押し付けたりすることもまた全くの不可能である。
儒学が中国発祥の学問であるからといって、今の中国を敵対視してみたりしたところで、とっくの昔に
儒学も中国本土からその姿を消してしまっている。文化大革命などを通じて古来の伝統文化の継承が徹底的に
絶やされて、かろうじて歴史的価値のある寺院建築の保全などが存続している程度でしかなくなって
しまっているわけだから、今の中国と戦争をして侵略対象などにしてみたところで、それで
儒学や仏教文化がより損なわれるなどということもほとんど皆無に等しい。
つまり、真理に適うことも、道理を守ることも、共に廃れきってしまっているが現代という時代である。
その証拠に、儒者として飯を食っていくことも、自力作善の仏者として食っていくことも覚束ない。
大学の中国哲学科や仏教哲学科なども単なる知識を学び教えるというばかりのこと止まりで、
最高級の学者といえどもその知識内容を忠実に実践したりすることはない。せいぜい
自分の知識を我流の筆法で披露した書籍を販促して儲けたりすることがあるぐらいである。
個人的に儒学や仏教の教えを好むようなことがあっても、それに忠実に従うなどということはできない。
渋沢栄一なぞも、本来は権力道徳のための倫理である儒学上の倫理体系を、商売哲学として相当に
曲解することで初めて、近代における実践対象としていた。それは当然、儒学の忠実な実践などには
なっていないわけで、かえって人々に儒学への偏見を抱かせる原因ばかりになったのである。
ただ、それらも現状、大いに肯んじる他はない現実である。
「そんなことはない、これほどもの乱世であっても、それなりに儒学や仏教を実践して行ける余地はある」
などという綺麗ごとを言うことはできても、実際そんなことはない。他力本願の念仏や曲解儒学の実践なら
ともかく、自力作善の本格仏教や、道徳統治を本分とする本物の儒学の実践までもが覚束くものではない。
だからこそ、今のような破滅寸前の乱世の責任を、儒学や仏教に押し付けたりすることもまた全くの不可能である。
儒学が中国発祥の学問であるからといって、今の中国を敵対視してみたりしたところで、とっくの昔に
儒学も中国本土からその姿を消してしまっている。文化大革命などを通じて古来の伝統文化の継承が徹底的に
絶やされて、かろうじて歴史的価値のある寺院建築の保全などが存続している程度でしかなくなって
しまっているわけだから、今の中国と戦争をして侵略対象などにしてみたところで、それで
儒学や仏教文化がより損なわれるなどということもほとんど皆無に等しい。
俺もまた、別に現状で儒学を実践できているわけでもない。ただ文面の知識を学んでいるだけの匹夫の
身分であり、そんな相手を迫害対象にしてみたりしたところで、儒学や仏教のほうは痛くもかゆくもない。
真理を把捉した教学の代表としては仏教を、道理を把捉した学問の代表としては儒学をここでは主に挙げて
いるけども、真理や道理を忠実に把捉しているような教学はいずれも、その実践が覚束なくなってしまっている。
真理や道理にたがう邪教邪学が最大級に幅を利かせることで、善良な教学はその立場を追われてしまっているのが現状
であるからこそ、今の世界を破滅に陥れている邪教邪学が、他の教学などにその責任を押し付けることもできないのである。
自分たちの教えにたがう者であるからこそ、自分たち以上の破滅に陥れられる相手などというのを、
この地球上のどこにも見つけることができない。自分たちこそがそのような人間を現世から絶やして
しまったのだから、そうである責任を自分たち以外の誰かに押し付けたりすることもまた、全くの不能である。
「他人がもたらした禍いは、たとえ天からの禍いであっても多少の逃れようがあるが、
自らがもたらした禍いは、それほどの逃れようすらない」とは「書経」にもあるとおり。
そうである如実なるケースの一つが、現代における邪教邪学の自業自得の破滅ともなっている。
身分であり、そんな相手を迫害対象にしてみたりしたところで、儒学や仏教のほうは痛くもかゆくもない。
真理を把捉した教学の代表としては仏教を、道理を把捉した学問の代表としては儒学をここでは主に挙げて
いるけども、真理や道理を忠実に把捉しているような教学はいずれも、その実践が覚束なくなってしまっている。
真理や道理にたがう邪教邪学が最大級に幅を利かせることで、善良な教学はその立場を追われてしまっているのが現状
であるからこそ、今の世界を破滅に陥れている邪教邪学が、他の教学などにその責任を押し付けることもできないのである。
自分たちの教えにたがう者であるからこそ、自分たち以上の破滅に陥れられる相手などというのを、
この地球上のどこにも見つけることができない。自分たちこそがそのような人間を現世から絶やして
しまったのだから、そうである責任を自分たち以外の誰かに押し付けたりすることもまた、全くの不能である。
「他人がもたらした禍いは、たとえ天からの禍いであっても多少の逃れようがあるが、
自らがもたらした禍いは、それほどの逃れようすらない」とは「書経」にもあるとおり。
そうである如実なるケースの一つが、現代における邪教邪学の自業自得の破滅ともなっている。
「君仁なれば不仁なるもの莫く、君義なれば不義なるもの莫し」
「主君に仁があれば不仁なものもなく、主君に義があれば不義を働くものもない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・離婁章句下・五)
「仲子は不義にして之れに斉国を与うるも受けること弗からん、人皆な之れを信ずるも、
是れ箪食豆羹を舎つるの義なり。人の親戚、君臣、上下を亡するより大なるは莫し」
「斉の陳仲子はたとえ斉一国をくれるとしてもそこに不義があればもらわないほど潔癖だという。
みなそれを信じて仲子を称えているが、私に言わせれば、そんなのはちょっとした食い物の贈り物を
不義だからといって断る程度のものでしかない。親戚君臣上下の序列を乱すことの不義には遠く及ばない。
(上の引用と合わせて。主君に不義を働かせて国中不義まみれにしたり、君臣上下の序列を乱して民に勝手に
不義を働かせたりすること両方ともが大罪である。犯罪聖書の神は必ずいずれかの罪を犯している)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句上・三四より)
「主君に仁があれば不仁なものもなく、主君に義があれば不義を働くものもない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・離婁章句下・五)
「仲子は不義にして之れに斉国を与うるも受けること弗からん、人皆な之れを信ずるも、
是れ箪食豆羹を舎つるの義なり。人の親戚、君臣、上下を亡するより大なるは莫し」
「斉の陳仲子はたとえ斉一国をくれるとしてもそこに不義があればもらわないほど潔癖だという。
みなそれを信じて仲子を称えているが、私に言わせれば、そんなのはちょっとした食い物の贈り物を
不義だからといって断る程度のものでしかない。親戚君臣上下の序列を乱すことの不義には遠く及ばない。
(上の引用と合わせて。主君に不義を働かせて国中不義まみれにしたり、君臣上下の序列を乱して民に勝手に
不義を働かせたりすること両方ともが大罪である。犯罪聖書の神は必ずいずれかの罪を犯している)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句上・三四より)
どんな形であれ、この世で役に立つ言葉は、この世の内側の言葉である。
この世との密接な関係性によってのみその存在意義を帯びる言葉である。
そのような限定的な有用性を超越しているのが他でもない仏説であり、この世での有用性などに
飽き足りていないからこそ、その意味も俗人にはなかなか計り知りがたいものとなっている。
そういった分かりにくさは儒説にはないし、犯罪聖書の言葉にもない。
犯罪聖書の場合、極度の精神薄弱者やサイコパス患者が落書きした言葉であるために、
構文などが稚拙なせいで分かりにくいということはあるが、書いてある内容が難解だから
分かりにくいなどということはない。あくまでもこの世の内側の範疇に止まる意味の言葉であり、
そのセット数も厳密に四書五経以内の四書五経以下なものに止まっている。
それでいて、ただの俗人が適当に述べる言葉などとは決定的に違う点が、四書五経の言葉にも
犯罪聖書の言葉にもある。四書五経の言葉が俗人の戯言などと決定的に違うのは、易の法則に
即した陽唱陰和を念頭にした言葉こそを集成している点である。しかもそれを俗世の言葉で簡潔に
述べているものだから、それが「勧善懲悪」の理念に適った言葉であるとも考えられるのである。
犯罪聖書の言葉はその逆で、易の法則でいえば陽唱陰和の逆を行く言葉の集成となっている。
それは別に犯罪聖書の編纂者がそれを狙ったからではなく、政商犯などとしての自分たちの
素行の悪さに即してものを書こうとした結果、自然とそうなってしまったのであり、
自分たちでも知らず知らずのうちから、悪逆非道の黄金比こそを体系化てしまったのである。
四書五経の言葉と犯罪聖書の言葉のうちで、どちらのほうがより形而上的かといえば、
それもむしろ四書五経のほうである。別に儒説が形而上的な物言いなどを心がけているわけでは
ないが、精一杯この世界のすべてを捉えきろうとしていることは間違いがない。そのために、
易の法則の如きこの世界のすべてを包括する法則の把握にまで及んでいる。犯罪聖書の著者には
そんな心がけはなく、この世界の内側のごく一部の法則の把握までにしか心がけが及んでいない。
この世との密接な関係性によってのみその存在意義を帯びる言葉である。
そのような限定的な有用性を超越しているのが他でもない仏説であり、この世での有用性などに
飽き足りていないからこそ、その意味も俗人にはなかなか計り知りがたいものとなっている。
そういった分かりにくさは儒説にはないし、犯罪聖書の言葉にもない。
犯罪聖書の場合、極度の精神薄弱者やサイコパス患者が落書きした言葉であるために、
構文などが稚拙なせいで分かりにくいということはあるが、書いてある内容が難解だから
分かりにくいなどということはない。あくまでもこの世の内側の範疇に止まる意味の言葉であり、
そのセット数も厳密に四書五経以内の四書五経以下なものに止まっている。
それでいて、ただの俗人が適当に述べる言葉などとは決定的に違う点が、四書五経の言葉にも
犯罪聖書の言葉にもある。四書五経の言葉が俗人の戯言などと決定的に違うのは、易の法則に
即した陽唱陰和を念頭にした言葉こそを集成している点である。しかもそれを俗世の言葉で簡潔に
述べているものだから、それが「勧善懲悪」の理念に適った言葉であるとも考えられるのである。
犯罪聖書の言葉はその逆で、易の法則でいえば陽唱陰和の逆を行く言葉の集成となっている。
それは別に犯罪聖書の編纂者がそれを狙ったからではなく、政商犯などとしての自分たちの
素行の悪さに即してものを書こうとした結果、自然とそうなってしまったのであり、
自分たちでも知らず知らずのうちから、悪逆非道の黄金比こそを体系化てしまったのである。
四書五経の言葉と犯罪聖書の言葉のうちで、どちらのほうがより形而上的かといえば、
それもむしろ四書五経のほうである。別に儒説が形而上的な物言いなどを心がけているわけでは
ないが、精一杯この世界のすべてを捉えきろうとしていることは間違いがない。そのために、
易の法則の如きこの世界のすべてを包括する法則の把握にまで及んでいる。犯罪聖書の著者には
そんな心がけはなく、この世界の内側のごく一部の法則の把握までにしか心がけが及んでいない。
故にこそ、いくら卑俗な言葉の集成であるにしても、
四書五経の言葉のほうが比較的形而上に近い一方、どんなに思わせぶりでも、
犯罪聖書の言葉のほうが比較的形而上から遠いものだといえる。
四書五経のような模範的な儒説を会得できたものこそは、この世界の内側にいながら、
この世界の全てを知る。世界の全てを知るがゆえに、自分自身が形而上的な存在とすらなれる。
犯罪聖書の言葉はその逆で、この世界の内側の、さらにごく一部の矮小な領域に
のみ信者たちを閉じ込めてしまうものである。そのせいで信者たちは、自分たちが
形而上的な存在であることを禁止される一方、自分たちがごく矮小な領域に閉じ込め
られたことを以ってして、「形而上への昇天」だなどと倒錯してしまいもするのである。
儒術の体得は結局、この世界の法則を超越する真理の法(仏法)に合致しようとする仏教の修養
にも漸近する。儒学が専門とするのはあくまでこの世界の内側の問題であるが、この世界の全てを
捉えきるほどにも儒学を修め尽くせたなら、もはやその人間自身の境地は形而上にあるも同然である、
故にこそ、始めからそれを狙っている仏門の境地にも、図らずとも合致することとなるのである。
(実際には、仏教の修得が儒学の修養を助成するようなことのほうが多いようである)
この世界の内側の、さらにごく一部の矮小な領域の法則ばかりに拘泥して、それを
形而上への昇天だなどと倒錯する件の邪教への耽溺は、儒学の修養と仏教の修養
いずれとも相容れないものである。形而下の全てを知って形而上の境地に赴くことも、
始めから形而上の境地を目指すことも、いずれをも不能と化してしまうものである。
そんな所ばかりに自分たちが陥ってしまうことほど、もったいないことも他にないのである。
「天地の害を除去す、之れを義と謂う」
「天地に跋扈する害、天地を害するものを除去して行くことこそを『義』という。
(所詮天地が滅んだりすることはないわけだが、天地が害されて懸隔状態となり、万物が利を損なう
ようなことはいくらでもある。そのようになるのを黙認したり、助長したりすることこそは不義である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・経解第二十六より)
四書五経の言葉のほうが比較的形而上に近い一方、どんなに思わせぶりでも、
犯罪聖書の言葉のほうが比較的形而上から遠いものだといえる。
四書五経のような模範的な儒説を会得できたものこそは、この世界の内側にいながら、
この世界の全てを知る。世界の全てを知るがゆえに、自分自身が形而上的な存在とすらなれる。
犯罪聖書の言葉はその逆で、この世界の内側の、さらにごく一部の矮小な領域に
のみ信者たちを閉じ込めてしまうものである。そのせいで信者たちは、自分たちが
形而上的な存在であることを禁止される一方、自分たちがごく矮小な領域に閉じ込め
られたことを以ってして、「形而上への昇天」だなどと倒錯してしまいもするのである。
儒術の体得は結局、この世界の法則を超越する真理の法(仏法)に合致しようとする仏教の修養
にも漸近する。儒学が専門とするのはあくまでこの世界の内側の問題であるが、この世界の全てを
捉えきるほどにも儒学を修め尽くせたなら、もはやその人間自身の境地は形而上にあるも同然である、
故にこそ、始めからそれを狙っている仏門の境地にも、図らずとも合致することとなるのである。
(実際には、仏教の修得が儒学の修養を助成するようなことのほうが多いようである)
この世界の内側の、さらにごく一部の矮小な領域の法則ばかりに拘泥して、それを
形而上への昇天だなどと倒錯する件の邪教への耽溺は、儒学の修養と仏教の修養
いずれとも相容れないものである。形而下の全てを知って形而上の境地に赴くことも、
始めから形而上の境地を目指すことも、いずれをも不能と化してしまうものである。
そんな所ばかりに自分たちが陥ってしまうことほど、もったいないことも他にないのである。
「天地の害を除去す、之れを義と謂う」
「天地に跋扈する害、天地を害するものを除去して行くことこそを『義』という。
(所詮天地が滅んだりすることはないわけだが、天地が害されて懸隔状態となり、万物が利を損なう
ようなことはいくらでもある。そのようになるのを黙認したり、助長したりすることこそは不義である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・経解第二十六より)
己れの利得が道義に適っているか否かを、仁者はあくまで自分自身が判断する。
その判断基準は「公益を害していないか否か」であり、害しているような
場合には不正利得とみなして、自らが受けたりすることも拒む。
公益を害しているか否かということが、普遍的な判断材料によって判別することが難しいから、
「仁」という理念も漠然としている所がある。なぜ普遍的な判断材料に乏しいかといって、
それは、商売人なり何なりが、私利私益の追求をあたかも公益寄与であるかのように
見せかける手段にも枚挙に暇がないからである。本当はただ私腹を肥やしたいだけであり、
実際に、世の中に利益以上の損害をもたらすことで不当な利得をかすめたりもするわけだが、
そうであることがあからさまだと凶賊もいいとこだから、そうであることを開き直っている
わけでもないような商売人などの場合、手を変え品を変えしての我田引水の隠蔽にも務めるのである。
その手段は、日に日に進化して行く。かつては黙認されたりすることがあった贋金作りも、
今は公然では厳禁とされている。だからといって悪徳商人などによるあぶく銭の膨らましが
完全に禁じられていたりするのではなく、株式市場での実態に沿わない景況の釣り上げだとか、
一部の富豪が各国中央銀行を私物化しての紙幣増刷の身勝手な操作だとかまでもが企てられている。
要は、贋金作りの手段が巧妙化したというばかりのことであり、事態はむしろ深刻化すらしてしまっている。
そういった現状において仁政を尽くすというのであれば、ただ贋金作りを禁止するだけで済んでいた
かつてのままの取り締まり手段などではとうてい済むはずもない。悪徳金融の犯行が巧妙化して
しまったぶんだけ、取り締まりの手法にも手管を尽くさねばならない。なればこそ、それを試みて
いくための「仁」という理念もまた、漠然とした範疇にとどめられておく必要があるのである。
その判断基準は「公益を害していないか否か」であり、害しているような
場合には不正利得とみなして、自らが受けたりすることも拒む。
公益を害しているか否かということが、普遍的な判断材料によって判別することが難しいから、
「仁」という理念も漠然としている所がある。なぜ普遍的な判断材料に乏しいかといって、
それは、商売人なり何なりが、私利私益の追求をあたかも公益寄与であるかのように
見せかける手段にも枚挙に暇がないからである。本当はただ私腹を肥やしたいだけであり、
実際に、世の中に利益以上の損害をもたらすことで不当な利得をかすめたりもするわけだが、
そうであることがあからさまだと凶賊もいいとこだから、そうであることを開き直っている
わけでもないような商売人などの場合、手を変え品を変えしての我田引水の隠蔽にも務めるのである。
その手段は、日に日に進化して行く。かつては黙認されたりすることがあった贋金作りも、
今は公然では厳禁とされている。だからといって悪徳商人などによるあぶく銭の膨らましが
完全に禁じられていたりするのではなく、株式市場での実態に沿わない景況の釣り上げだとか、
一部の富豪が各国中央銀行を私物化しての紙幣増刷の身勝手な操作だとかまでもが企てられている。
要は、贋金作りの手段が巧妙化したというばかりのことであり、事態はむしろ深刻化すらしてしまっている。
そういった現状において仁政を尽くすというのであれば、ただ贋金作りを禁止するだけで済んでいた
かつてのままの取り締まり手段などではとうてい済むはずもない。悪徳金融の犯行が巧妙化して
しまったぶんだけ、取り締まりの手法にも手管を尽くさねばならない。なればこそ、それを試みて
いくための「仁」という理念もまた、漠然とした範疇にとどめられておく必要があるのである。
とはいえ、仁という理念を実践して行くために適切となる手段として、現代でも普遍的に
通用する古来からの儒説というものもまたやはりある。それが、それぞれの国家の体制をよく
整えて、国益をよく尊重して行くということである。そのために必要なのは、一国や二国ばかりの
国益が偏重されることではなく、天下全土の国家の権益が相応に守られて行く必要がある。
今も、公私織り交ぜた悪徳外交家(縦横家)が多数暗躍している時代であり、それらの人間によって、
一国や同盟国の利益すら守られればそれでいいというような偏見の流布までもが企てられている時代である。
それはむしろあらゆる国家の長期的な国益を損なうと共に、仁義道徳に反する狭隘に過ぎた見識でもある
のだから、そんな讒言に囚われることなく、天下国家の公益というものを第一に考えて行かなければならない。
これもまた、実際に企図していくとなると、画一的な手法ばかりに囚われていてはならない所がある。
それもやはり、悪徳外交家による国益横領の手段が昔以上に巧妙化したりしているからで、戦時中は
嘘八百を並べ立てる説客などとしても活躍していた儒者の叔孫通ぐらいの機転を利かせるのでなければ、
縦横家の権謀術数にもとうてい対抗しきれるものではない。もちろん縦横家や悪徳商人の暗躍が絶やされて
治世が確立されて後には、これまた叔孫通のような礼楽統治の復興にも務めて行けばいいわけで、仁政の
ための手段というものは乱世においてこそ不定なものとなり、治世においては定まるものであるのだといえる。
「仁を里とするを美と為す。択んで仁に処らずんば、焉んぞ知なることを得ん」
「仁を自らの居場所とすることこそは善美なことである。自分から選んで仁に居ようとするのでなければ、
どうして知者であるなどということが言えようか。(仁なることを強要する他者など居ないし、また
居てはならない。強制されて仁となるようでは、仁義礼智>信という五条の徳の序列にももとるから)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——里仁第四・一より)
通用する古来からの儒説というものもまたやはりある。それが、それぞれの国家の体制をよく
整えて、国益をよく尊重して行くということである。そのために必要なのは、一国や二国ばかりの
国益が偏重されることではなく、天下全土の国家の権益が相応に守られて行く必要がある。
今も、公私織り交ぜた悪徳外交家(縦横家)が多数暗躍している時代であり、それらの人間によって、
一国や同盟国の利益すら守られればそれでいいというような偏見の流布までもが企てられている時代である。
それはむしろあらゆる国家の長期的な国益を損なうと共に、仁義道徳に反する狭隘に過ぎた見識でもある
のだから、そんな讒言に囚われることなく、天下国家の公益というものを第一に考えて行かなければならない。
これもまた、実際に企図していくとなると、画一的な手法ばかりに囚われていてはならない所がある。
それもやはり、悪徳外交家による国益横領の手段が昔以上に巧妙化したりしているからで、戦時中は
嘘八百を並べ立てる説客などとしても活躍していた儒者の叔孫通ぐらいの機転を利かせるのでなければ、
縦横家の権謀術数にもとうてい対抗しきれるものではない。もちろん縦横家や悪徳商人の暗躍が絶やされて
治世が確立されて後には、これまた叔孫通のような礼楽統治の復興にも務めて行けばいいわけで、仁政の
ための手段というものは乱世においてこそ不定なものとなり、治世においては定まるものであるのだといえる。
「仁を里とするを美と為す。択んで仁に処らずんば、焉んぞ知なることを得ん」
「仁を自らの居場所とすることこそは善美なことである。自分から選んで仁に居ようとするのでなければ、
どうして知者であるなどということが言えようか。(仁なることを強要する他者など居ないし、また
居てはならない。強制されて仁となるようでは、仁義礼智>信という五条の徳の序列にももとるから)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——里仁第四・一より)
信仰は情念のほとばしりである。
何を信じるのであれそれは共通していて、その情念こそを正信によって善用することもできれば、
邪信によって悪用することもできる。全く知性を欠いた情念が正信に踏み止まれるか邪信に
陥るかは不定なことだから、まずは十分な分別知によって正信と邪信を区別できるものが
社会的に後者を排して前者を推奨するなどして、たとえ妄信にしか耽っていられないような
人間であっても自然と正信を選択できるような風潮を盛り立てて行ってやる必要がある。
キリシタンや日蓮カルトが排されて、最低でも念仏信仰ぐらいに踏み止まっていられる体制が
敷かれていた頃の日本などはまさにそのようだった。みんながやってる当たり前なものとしての
念仏唱名が無知な百姓あたりにまで行き渡り、さして善行は為せずとも、最悪の悪行にまでは
走らないでいられる程度の正信による「結界」が日本中に張り巡らされていた。
キリシタンが解禁された明治以降、さらにはマッカーサー憲法で「信教の自由」が謳われて、
カルト教団でも宗教法人法による税制優遇が受けられるようになった敗戦後などには、誰かが
正信と邪信をより分けて、邪信を排して正信を奨めておいてやるなんていうことは不可能となった。
正信を促す正統な信教こそは泰然として、無闇な布教などにも及ばないでいる一方、邪信を促すカルト
こそは、信者獲得による儲けのために必死で布教を試みているものだから、特に目に付く宗教といえば
カルトばかりとなって、そのせいで宗教全般への嫌悪感が日本人に植え付けられることともなったのだった。
誰しもが信仰なんか抜きにして、己れの知恵によってまともな生活や社会活動を営めるというのなら、
全くそれでいいのである。しかし残念ながら、そこまで誰しもが賢良方正であるほど世の中という
ものもできていないものだから、己れの知恵だけでは生きていくこともままならないような愚人を
精神面から統御してやるための手段として、信教が有効となる場合がある。科学至上主義の時代に
未だ宗教なんてものが残存していることが不可解に思われたりもするが、そう思えてしまう
ような人間は、世の中のダメな部分に対する配慮が未だ足りていないのである。
何を信じるのであれそれは共通していて、その情念こそを正信によって善用することもできれば、
邪信によって悪用することもできる。全く知性を欠いた情念が正信に踏み止まれるか邪信に
陥るかは不定なことだから、まずは十分な分別知によって正信と邪信を区別できるものが
社会的に後者を排して前者を推奨するなどして、たとえ妄信にしか耽っていられないような
人間であっても自然と正信を選択できるような風潮を盛り立てて行ってやる必要がある。
キリシタンや日蓮カルトが排されて、最低でも念仏信仰ぐらいに踏み止まっていられる体制が
敷かれていた頃の日本などはまさにそのようだった。みんながやってる当たり前なものとしての
念仏唱名が無知な百姓あたりにまで行き渡り、さして善行は為せずとも、最悪の悪行にまでは
走らないでいられる程度の正信による「結界」が日本中に張り巡らされていた。
キリシタンが解禁された明治以降、さらにはマッカーサー憲法で「信教の自由」が謳われて、
カルト教団でも宗教法人法による税制優遇が受けられるようになった敗戦後などには、誰かが
正信と邪信をより分けて、邪信を排して正信を奨めておいてやるなんていうことは不可能となった。
正信を促す正統な信教こそは泰然として、無闇な布教などにも及ばないでいる一方、邪信を促すカルト
こそは、信者獲得による儲けのために必死で布教を試みているものだから、特に目に付く宗教といえば
カルトばかりとなって、そのせいで宗教全般への嫌悪感が日本人に植え付けられることともなったのだった。
誰しもが信仰なんか抜きにして、己れの知恵によってまともな生活や社会活動を営めるというのなら、
全くそれでいいのである。しかし残念ながら、そこまで誰しもが賢良方正であるほど世の中という
ものもできていないものだから、己れの知恵だけでは生きていくこともままならないような愚人を
精神面から統御してやるための手段として、信教が有効となる場合がある。科学至上主義の時代に
未だ宗教なんてものが残存していることが不可解に思われたりもするが、そう思えてしまう
ような人間は、世の中のダメな部分に対する配慮が未だ足りていないのである。
宗教なんて、なくて済むならそれに越したことはない。ただ、どうしても必要というのなら、
正信を促すまともな信教に限るべきだ。どんな宗教でも信じることは自由、むしろ邪な宗教こそを
信じてしまえなんていうのなら、本当に宗教保護なんか一切取り去ってしまったほうがマシである。
信仰にそれなりの統制が効かされていた頃の日本でも、朝廷や幕府からの手厚い庇護を受けていた
仏門宗派(天台真言禅など)と、ほとんど民間からの支援だけで成り立っていた宗派(一向宗や日蓮宗)
との両方があった。信仰を禁じる・禁じないなんてのは極端な話で、禁教まで施される必要があるような
信教はごくごく限られている。禁教まではされない信教のうちでも、権力者からの手厚い庇護を受ける
宗門と、庇護を受けられない宗門とを分けたりすべきなのだから、禁教すべき邪教はさっさと禁教して、
さらにその先、保護すべき秀教と保護まではすべきでない凡教との選別へと早急に向かうべきである。
宗教なんて世の中の必要悪でしかないからこそ、そうするのである。まずは、宗教というジャンル
に対する無駄な憧憬を軒並み排すべきである。そうしたなら、信仰なんてそれなりの統制を受けて当然、
信教の自由なんて非常識極まりないことだとも自然と思えるはずである。そういう風に考えられる人間が
世の中の大多数となり、権力機構には必ずその程度の達観の持ち主が従事するようになることを心がける
べきである。宗教というものを排することまではできなくとも、それぐらいのことは目指すべきである。
「信を惇くし義を明らかにし、徳を崇び功に報ずれば、垂拱して天下治まる」
「信心を篤くして道義を明らかにし、仁徳を貴んで功業にも相応の報償を施せば、
指一つ動かさずとも天下はよく治まる。(正信は戦いを収めるものである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・武成より)
正信を促すまともな信教に限るべきだ。どんな宗教でも信じることは自由、むしろ邪な宗教こそを
信じてしまえなんていうのなら、本当に宗教保護なんか一切取り去ってしまったほうがマシである。
信仰にそれなりの統制が効かされていた頃の日本でも、朝廷や幕府からの手厚い庇護を受けていた
仏門宗派(天台真言禅など)と、ほとんど民間からの支援だけで成り立っていた宗派(一向宗や日蓮宗)
との両方があった。信仰を禁じる・禁じないなんてのは極端な話で、禁教まで施される必要があるような
信教はごくごく限られている。禁教まではされない信教のうちでも、権力者からの手厚い庇護を受ける
宗門と、庇護を受けられない宗門とを分けたりすべきなのだから、禁教すべき邪教はさっさと禁教して、
さらにその先、保護すべき秀教と保護まではすべきでない凡教との選別へと早急に向かうべきである。
宗教なんて世の中の必要悪でしかないからこそ、そうするのである。まずは、宗教というジャンル
に対する無駄な憧憬を軒並み排すべきである。そうしたなら、信仰なんてそれなりの統制を受けて当然、
信教の自由なんて非常識極まりないことだとも自然と思えるはずである。そういう風に考えられる人間が
世の中の大多数となり、権力機構には必ずその程度の達観の持ち主が従事するようになることを心がける
べきである。宗教というものを排することまではできなくとも、それぐらいのことは目指すべきである。
「信を惇くし義を明らかにし、徳を崇び功に報ずれば、垂拱して天下治まる」
「信心を篤くして道義を明らかにし、仁徳を貴んで功業にも相応の報償を施せば、
指一つ動かさずとも天下はよく治まる。(正信は戦いを収めるものである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・武成より)
麻雀は哲学だ、とか
商売は哲学だ、とか
哲学のての字も知らないような俗物がよく嘯いてるでしょ。しかし頭は悪いにしてもされはそれである意味正しいんですね。どういうことかと言うと、
そら何ごとであれ一生懸命やれば古典哲学的あるいは形示上学的な世界を垣間見ることはあるでしょう。
儒教をやれば真理に近づくなんて論法も全く同じですよ。
真理を求めるのであれば儒教から攻める必要性はないし、それなら正面切ってそれを求める宗教の方が好感がもてるし、そのやり方を俗人が聖人のふりをしてとやかく言う資格もないでしょう。
商売は哲学だ、とか
哲学のての字も知らないような俗物がよく嘯いてるでしょ。しかし頭は悪いにしてもされはそれである意味正しいんですね。どういうことかと言うと、
そら何ごとであれ一生懸命やれば古典哲学的あるいは形示上学的な世界を垣間見ることはあるでしょう。
儒教をやれば真理に近づくなんて論法も全く同じですよ。
真理を求めるのであれば儒教から攻める必要性はないし、それなら正面切ってそれを求める宗教の方が好感がもてるし、そのやり方を俗人が聖人のふりをしてとやかく言う資格もないでしょう。
「小道と雖ども、必ず観るべき者有り。遠きを致すには
泥まぬことを恐る。是を以て君子は為さざるなり(既出)」
「小道にも全く見所がないわけではない。 しかし、遠く進んで行けば
必ず泥沼にはまることになる。だから君子はその道を歩まないのだ」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・子張第十九・四より)
「君子の道は闇然として而も日に章らかに、小人の道は的然として日に亡ぶ(既出)」
「君子の道は(謙譲を尽くすので)始めは暗がりのようだが、日々の積み重ねで次第に明らかになり、
小人の道は(巧言令色を尽くすので)始めは明るげでも、風化によって次第に衰亡していく。」
(権力道徳聖書——通称四書五経——中庸・三三より)
「非可換なものの実在」を、これから改めて人々に啓蒙して行く必要がある。
それは、昔は直観的に認識されていたものだが、今は無理に無きものとされている。
しかし、残念ながらやっぱり実在していたわけだから、それはわきまえて行くほかない。
泥まぬことを恐る。是を以て君子は為さざるなり(既出)」
「小道にも全く見所がないわけではない。 しかし、遠く進んで行けば
必ず泥沼にはまることになる。だから君子はその道を歩まないのだ」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・子張第十九・四より)
「君子の道は闇然として而も日に章らかに、小人の道は的然として日に亡ぶ(既出)」
「君子の道は(謙譲を尽くすので)始めは暗がりのようだが、日々の積み重ねで次第に明らかになり、
小人の道は(巧言令色を尽くすので)始めは明るげでも、風化によって次第に衰亡していく。」
(権力道徳聖書——通称四書五経——中庸・三三より)
「非可換なものの実在」を、これから改めて人々に啓蒙して行く必要がある。
それは、昔は直観的に認識されていたものだが、今は無理に無きものとされている。
しかし、残念ながらやっぱり実在していたわけだから、それはわきまえて行くほかない。
安らぐべからざる所に安んじ、楽しむべからざる所を楽しむような状態を
荀子は「狂生」と呼んだ。ただ、この言葉は唱えられ始めた頃からすでに誤用されていたようで、
戦国時代末期から荀子学派の儒者であった酈食其なども、自らが始皇帝の焚書坑儒から逃れるために
アル中の狂人を装っていたために、人々から「狂生」と呼ばれていたという。(「漢書」酈生列伝参照)
おそらく本人自身が、秦帝国の権力者などを「狂生者」などと呼んでいたのだろうが、その時にはむしろ
自分のほうが狂人を装っていたわけだから、自らの言葉を跳ね返されて、自分自身まこそが人から「狂生」と
呼ばれてしまったのである。(この『狂生』には『狂った先生』という皮肉めいた意味までもが込められている)
ただ、結果はやはり本物の狂生者にこそ最大級の禍いを報い、そうでない者にはそれなりの厚遇を処した。
秦帝国は民衆レベルの反乱によって完全崩壊し、その王統に至るまで中国では完全に絶やされた。
酈食其もまた楚漢戦争中に韓信(正確にはその参謀の蒯通)の策略の犠牲となって斉国で客死するも、
一度は斉国を説得で帰服させたその功績が認められて、子孫が万戸侯として封ぜられるなどしている。
酈食其も結局は戦死したわけだから、必ずしも救われたとまではいえないが、中国本土でも逃亡先の
日本などでも、天下の笑い者としての恥辱に見舞われ続けることとなった秦帝国の徒輩などと比べれば、
ずいぶんとマシな運命を辿ることとなったものだといえる。荀子が定義した「狂生」という言葉の意味も、
本来からしてそういった長期的な普遍性に即したものだったはずで、本物の狂生者は不謹慎な安静を
追い求めて最悪の破滅に見舞われる一方、あてつけや言いがかりで狂生者扱いされたような人間は、
いつかは誤解が解かれて名誉を取り戻し、子孫代々にいたるまでのマシ以上な処遇に与れるものである。
荀子は「狂生」と呼んだ。ただ、この言葉は唱えられ始めた頃からすでに誤用されていたようで、
戦国時代末期から荀子学派の儒者であった酈食其なども、自らが始皇帝の焚書坑儒から逃れるために
アル中の狂人を装っていたために、人々から「狂生」と呼ばれていたという。(「漢書」酈生列伝参照)
おそらく本人自身が、秦帝国の権力者などを「狂生者」などと呼んでいたのだろうが、その時にはむしろ
自分のほうが狂人を装っていたわけだから、自らの言葉を跳ね返されて、自分自身まこそが人から「狂生」と
呼ばれてしまったのである。(この『狂生』には『狂った先生』という皮肉めいた意味までもが込められている)
ただ、結果はやはり本物の狂生者にこそ最大級の禍いを報い、そうでない者にはそれなりの厚遇を処した。
秦帝国は民衆レベルの反乱によって完全崩壊し、その王統に至るまで中国では完全に絶やされた。
酈食其もまた楚漢戦争中に韓信(正確にはその参謀の蒯通)の策略の犠牲となって斉国で客死するも、
一度は斉国を説得で帰服させたその功績が認められて、子孫が万戸侯として封ぜられるなどしている。
酈食其も結局は戦死したわけだから、必ずしも救われたとまではいえないが、中国本土でも逃亡先の
日本などでも、天下の笑い者としての恥辱に見舞われ続けることとなった秦帝国の徒輩などと比べれば、
ずいぶんとマシな運命を辿ることとなったものだといえる。荀子が定義した「狂生」という言葉の意味も、
本来からしてそういった長期的な普遍性に即したものだったはずで、本物の狂生者は不謹慎な安静を
追い求めて最悪の破滅に見舞われる一方、あてつけや言いがかりで狂生者扱いされたような人間は、
いつかは誤解が解かれて名誉を取り戻し、子孫代々にいたるまでのマシ以上な処遇に与れるものである。
子孫代々の将来にまで至るような、長期的な視点に即した安寧の希求こそは正善である一方、
その場しのぎの事なかれ主義は狂生だし、間違った方法での長期的安定の企図もまた狂生である。
後二つの方針に即した平和の追い求めは、より大きな破滅を後々にもたらす原因ともなる。
故にこそ狂生である。破滅をもたらすような偽りの平和を追い求めているからこそ、狂生である。
平和なんかわざと追い求めなくたって、自然と平和ということがある。人々の濁念が根本から清められて、
争いの火種になるような不埒な言行なども始めから試みられないような状態、それこそを理想とするのが
正しい平和の追い求め方である一方、人々の濁念は肥大化させっぱなし、争いや奪い合いの火種はそこら中に
撒き散らしておいた上で、腕力によって無理やり停戦状態を持続させようなどとするのが、狂生然とした平和の
追い求め方である。狂生者は、自分自身が不埒な濁念にまみれきっているからこそ、人々の濁念を根本から清めて
いくことこそは無理があることのように自分では思ったりするわけだが、それ以上にも、戦乱の火種で溢れ返って
いる世の中を、極大級の暴力で無理やり抑え付け続けたりすることのほうが、よっぽと無理のあることである。
人々の本然からの清浄さの養生に基づく平和状態は数百年と持たせられる一方、暴力による抑え付けでの平和は
百年と持たない。百年持てば自分の人生だけは平和裡に済ませられるからそれでいいなどとも、極度の狂生者
であれば考えるわけで、実際、前ロスチャイルド家当主なども、英米帝国の完全崩壊が決定的となった2008年
には早々とこの世を去った。哀れなのはその子孫や残党であり、これから人類史上でも最悪級の破滅や恥辱
に見舞われる運命ばかりが待っている。自分たちをそんな非業の運命に見舞わせたのも自分たちの先代でこそある。
にもかかわらず逆恨みを外部の人間に当て付けたりするようならば、それこそ一族郎党皆殺し級の処遇すらもが
免れられるものではない。自分たちは、自分たちや自分たちの先祖の狂生によって不可避なる破滅に見舞われた
のだということへの切なる反省がある場合にのみ、狂生の報いとしての破滅や恥辱が軽減されることもあり得る。
その場しのぎの事なかれ主義は狂生だし、間違った方法での長期的安定の企図もまた狂生である。
後二つの方針に即した平和の追い求めは、より大きな破滅を後々にもたらす原因ともなる。
故にこそ狂生である。破滅をもたらすような偽りの平和を追い求めているからこそ、狂生である。
平和なんかわざと追い求めなくたって、自然と平和ということがある。人々の濁念が根本から清められて、
争いの火種になるような不埒な言行なども始めから試みられないような状態、それこそを理想とするのが
正しい平和の追い求め方である一方、人々の濁念は肥大化させっぱなし、争いや奪い合いの火種はそこら中に
撒き散らしておいた上で、腕力によって無理やり停戦状態を持続させようなどとするのが、狂生然とした平和の
追い求め方である。狂生者は、自分自身が不埒な濁念にまみれきっているからこそ、人々の濁念を根本から清めて
いくことこそは無理があることのように自分では思ったりするわけだが、それ以上にも、戦乱の火種で溢れ返って
いる世の中を、極大級の暴力で無理やり抑え付け続けたりすることのほうが、よっぽと無理のあることである。
人々の本然からの清浄さの養生に基づく平和状態は数百年と持たせられる一方、暴力による抑え付けでの平和は
百年と持たない。百年持てば自分の人生だけは平和裡に済ませられるからそれでいいなどとも、極度の狂生者
であれば考えるわけで、実際、前ロスチャイルド家当主なども、英米帝国の完全崩壊が決定的となった2008年
には早々とこの世を去った。哀れなのはその子孫や残党であり、これから人類史上でも最悪級の破滅や恥辱
に見舞われる運命ばかりが待っている。自分たちをそんな非業の運命に見舞わせたのも自分たちの先代でこそある。
にもかかわらず逆恨みを外部の人間に当て付けたりするようならば、それこそ一族郎党皆殺し級の処遇すらもが
免れられるものではない。自分たちは、自分たちや自分たちの先祖の狂生によって不可避なる破滅に見舞われた
のだということへの切なる反省がある場合にのみ、狂生の報いとしての破滅や恥辱が軽減されることもあり得る。
狂生者の悲哀は、
自分たちの過ちを認めて贖罪と反省の限りを尽くす所にしか、
自分たち自身の救いまでもが見込めなくなるところにこそある。
自分たちを救うためにこそ、世のため人のためにも尽くさねばならない、
すでに罪悪の限りを尽くしているわけだから、その手段も当分は贖罪や反省で
しかあり得ないわけだが、そうであるにしたって、自分たち自身が仁徳に適った
相応の振る舞いを為すのでなければ、自分たちの救いもないというわけであって、
世界でも最も仁徳を忌み嫌って来た部類の者たちこそが、完全に強制的に、仁徳に
適った振る舞いを実行していかなければならないというのだから、悲惨の限りである。
仁徳こそは、それを慕う者にとっての福果ともなる一方、それを忌み嫌う者にとっての
地獄の仕打ちともなるのである。故に、始めから慕っておくに越したこともないのである。
「是の月や、日短至れり。陰陽争い、諸生蕩ず。君子斎戒し、処るには必ず身を掩い、身寧からんことを欲す。
声色を去り、耆欲を禁ず。形性を安んじ、事は静かならんことを欲し、以て陰陽の定むる所を待つ」
「日照時間が一番短くなる冬至のころ、陰陽の和気は乱れて互いに相い争い、諸々の生き物も蕩心を
帯びやすくなる。君子は斎戒沐浴して安居中には必ず身を覆い、己れの身が安からんことを企図する。
大声をあげたりすることを慎み、欲にまみれることも戒める。それにより万物の形性をも安んじ、
物事が静穏であるように企図し、陰陽の和気が定まることを待つのである。(自分一身の安静ではなく、
天下万物万人諸生の安静を修己治人にもよって企図している。狂生とは程遠いあり方だといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・月令第六より)
自分たちの過ちを認めて贖罪と反省の限りを尽くす所にしか、
自分たち自身の救いまでもが見込めなくなるところにこそある。
自分たちを救うためにこそ、世のため人のためにも尽くさねばならない、
すでに罪悪の限りを尽くしているわけだから、その手段も当分は贖罪や反省で
しかあり得ないわけだが、そうであるにしたって、自分たち自身が仁徳に適った
相応の振る舞いを為すのでなければ、自分たちの救いもないというわけであって、
世界でも最も仁徳を忌み嫌って来た部類の者たちこそが、完全に強制的に、仁徳に
適った振る舞いを実行していかなければならないというのだから、悲惨の限りである。
仁徳こそは、それを慕う者にとっての福果ともなる一方、それを忌み嫌う者にとっての
地獄の仕打ちともなるのである。故に、始めから慕っておくに越したこともないのである。
「是の月や、日短至れり。陰陽争い、諸生蕩ず。君子斎戒し、処るには必ず身を掩い、身寧からんことを欲す。
声色を去り、耆欲を禁ず。形性を安んじ、事は静かならんことを欲し、以て陰陽の定むる所を待つ」
「日照時間が一番短くなる冬至のころ、陰陽の和気は乱れて互いに相い争い、諸々の生き物も蕩心を
帯びやすくなる。君子は斎戒沐浴して安居中には必ず身を覆い、己れの身が安からんことを企図する。
大声をあげたりすることを慎み、欲にまみれることも戒める。それにより万物の形性をも安んじ、
物事が静穏であるように企図し、陰陽の和気が定まることを待つのである。(自分一身の安静ではなく、
天下万物万人諸生の安静を修己治人にもよって企図している。狂生とは程遠いあり方だといえる)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・月令第六より)
 日本の戦国時代、あらん限りの手管を尽くしての総力戦にいそしんでいた武将や武士たちこそは、
日本の戦国時代、あらん限りの手管を尽くしての総力戦にいそしんでいた武将や武士たちこそは、 防護のための甲冑にも趣向を凝らし、立てこもりにも向いた城普請などにも多額の費用をかけていた。
信長のように頑丈な木柵をこしらえて、その隙間からの連射戦法を企てることで武田の騎馬軍を
打ち破るものもあった。(これは近代戦におけるトーチカや戦車や機関銃の原型ともなっている)
総力戦だからこそ、そのような防護にかけての手管が尽くされるということがあった。
泰平が確立された江戸時代には銃砲も取り締まられ、城の造営も厳しく制限され、戦国時代に
用いられていた甲冑なども破棄されるなり、お蔵入りするなりして実用の場を追われて行った。
武家社会の中枢たる江戸城ですら、明暦の大火で焼失して後には天守閣の再建が断念された。
それ程にも、世の中総出を挙げての武装解除ならぬ防護解除が推進されて後になお、
正規の武士たちは大小二本の刀を差して街を歩き、浪人も一本差しで武家としての面子を守っていた。
刀にも刃長制限などのそれなりの取締りが講じられたものの、武士の魂としての刀の温存は
それなりに認められ、場合によってはそれを実用しての仇討ちや無礼討ちすらもが実行に移された。
この時にこそ、人々は戦国時代以上もの勇気が場合によっては必要とされるようにもなったのだった。
上記の事例は、特に分かりやすいものとして挙げたわけだが、実際、戦時だからといって
危険というわけでもなければ、平時だからといって安全というわけでもないようなことはいくら
でもある。利権がらみでの謀殺なんてのは、今の日本でですら陰に陽に横行していることであり、
その実情を大っぴらにしなかったりするぶんだけ、戦死以上にも陰惨なものですらある。
だから結局、戦地に赴く勇気などではなく、常日頃から死への覚悟を欠かさずにいる
勇気こそは、実質的にも必要だったりするものであるが故にこそ、本物の大勇でもあるといえる。
平時にもただ凶事がひた隠されているだけであって、実際にはどこかでくすぶっている刃傷沙汰が
あったりする。そのような影の側面も宿している所、少なくとも宿しうる所である世の中という
ものに対して、常に泰然自若としながら対峙できる者こそは、真の大勇の持ち主だといえる。
蛮勇や匹夫の勇には隙があるが、大勇には隙がない。常日頃からの死への覚悟、
勇気の善用にかけて最善を尽くす配慮などがあればこそ、隙がない。
そんな勇気が実在し得ること自体、西洋などでは認知されて来たことですらない。
ギリシャ神話における勇士アキレウスと策士オデュッセウスの対比以来、
勇気のあるものには知謀がなく、知謀のあるものには勇気がないというのが
西洋社会における固定観念と化したままであり続けてきてしまったものだから、
配慮にかけても最善を尽くす所にこそ大勇があるなどとは考えられもしなかったのである。
東洋においても、大勇こそは知謀にも長け、匹夫の勇こそは知謀を欠くということをちゃんと
理解している人間はそんなに多くない。真の大勇の持ち主だった劉邦や源頼朝や徳川家康よりも、
匹夫の勇止まりだった項羽や源義経や織田信長のほうが人気があったりするのもそのためである。
前者三人を軽んじて後者三人を無責任に持て囃すような人間は、東洋人といえどもろくに政治責任を
負う覚悟もないような人間である可能性が高い。自分自身が責任を担って為政を働いていくことを
本格的に想定してみたならば、ただ劉邦や頼朝や家康を慕いやすくなるだけでなく、彼らこそは
項羽や義経や信長以上もの大勇の持ち主であったことすらもが計り知れるはずなのだから。
討ち死にを果たした項羽や義経や信長の死に様と比べても、劉邦や頼朝や家康の死に様が別段
華々しいなどということもない。矢傷や落馬や食あたりを原因として、床の上で亡くなっている。
それは、乱世の最終勝利者であるが故にこその、比較的平穏な死だったのであり、生存中に
命の危機に見舞われた頻度では、項羽や義経や信長に勝るとも劣らないものとなっている。
そうであることを計り知るためには、ちゃんと数十年以上にわたる偉人たちの事跡を調べ通す必要が
あるわけだから、勉強嫌いな人間こそは大勇の何たるかを計り知ることもできないままに終わるのである。
勇気の善用にかけて最善を尽くす配慮などがあればこそ、隙がない。
そんな勇気が実在し得ること自体、西洋などでは認知されて来たことですらない。
ギリシャ神話における勇士アキレウスと策士オデュッセウスの対比以来、
勇気のあるものには知謀がなく、知謀のあるものには勇気がないというのが
西洋社会における固定観念と化したままであり続けてきてしまったものだから、
配慮にかけても最善を尽くす所にこそ大勇があるなどとは考えられもしなかったのである。
東洋においても、大勇こそは知謀にも長け、匹夫の勇こそは知謀を欠くということをちゃんと
理解している人間はそんなに多くない。真の大勇の持ち主だった劉邦や源頼朝や徳川家康よりも、
匹夫の勇止まりだった項羽や源義経や織田信長のほうが人気があったりするのもそのためである。
前者三人を軽んじて後者三人を無責任に持て囃すような人間は、東洋人といえどもろくに政治責任を
負う覚悟もないような人間である可能性が高い。自分自身が責任を担って為政を働いていくことを
本格的に想定してみたならば、ただ劉邦や頼朝や家康を慕いやすくなるだけでなく、彼らこそは
項羽や義経や信長以上もの大勇の持ち主であったことすらもが計り知れるはずなのだから。
討ち死にを果たした項羽や義経や信長の死に様と比べても、劉邦や頼朝や家康の死に様が別段
華々しいなどということもない。矢傷や落馬や食あたりを原因として、床の上で亡くなっている。
それは、乱世の最終勝利者であるが故にこその、比較的平穏な死だったのであり、生存中に
命の危機に見舞われた頻度では、項羽や義経や信長に勝るとも劣らないものとなっている。
そうであることを計り知るためには、ちゃんと数十年以上にわたる偉人たちの事跡を調べ通す必要が
あるわけだから、勉強嫌いな人間こそは大勇の何たるかを計り知ることもできないままに終わるのである。
天性によって、知らず知らずの内から大勇を持てるような人間も居はするが、大勇の何たるかを
自主的に計り知った上でそれにあやかろうとするのであれば、惜しみのない勉強が必須ともなる。
その心がけもないのに、短絡的な勇猛さを追い求めたりすれば、それが匹夫の勇に転んだりするのである。
「雄雉于こに飛ぶ、泄泄たる其の羽。我れ之れを懐いて、自ら伊の阻いを詒す。
雄雉于こに飛ぶ、下上する其の音。展なる君子、実に我が心を労せしむ。
彼の日月を瞻れば、悠悠として我れ思う。道の云こに遠き、曷か云こに能く来たらん。
百そ爾じ君子、徳行を知らざらんや。忮わず求めざれば、何ぞ用て臧からざらんや」
「雄キジがその羽を打ち立てて飛び立つように、わが夫も出征して行く。私はそれを思うと憂いばかりが募る。
雄キジが天空を羽音を立てて上下するように、わが夫も出征して行く。かの君子は、私の心を労させるばかり。
空に日月を見上げれば、憂患を募らせながらまた思う。遠い道を往きて、またここに帰ってくださることを。
あなたは君子だから、徳行にかけては私などよりもずっと知っていることでしょう。ただ、害悪を好んだり
無闇に利益を追い求めたりしないことで、不善に手を染めないことばかりを私は願うのみです。(雄雄しく
出征して行く夫を思い慕う妻の歌。『忮わず求めざれば、何ぞ用て臧からざらんや』は、孔子の弟子の子路が
好んで謳っていた一節で、孔子は『そんなことばかりでいいはずがない』と子路に苦言を呈していたわけだが、
上記のような文脈で歌われた言葉なわけだから、この言葉にもそれなりの含蓄があることがわかる。雄雄しく
ある夫こそは、最悪の不善にまでは手を染めないで居てくれというのが、妻たるものの切なる願いなのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・邶風・雄雉)
自主的に計り知った上でそれにあやかろうとするのであれば、惜しみのない勉強が必須ともなる。
その心がけもないのに、短絡的な勇猛さを追い求めたりすれば、それが匹夫の勇に転んだりするのである。
「雄雉于こに飛ぶ、泄泄たる其の羽。我れ之れを懐いて、自ら伊の阻いを詒す。
雄雉于こに飛ぶ、下上する其の音。展なる君子、実に我が心を労せしむ。
彼の日月を瞻れば、悠悠として我れ思う。道の云こに遠き、曷か云こに能く来たらん。
百そ爾じ君子、徳行を知らざらんや。忮わず求めざれば、何ぞ用て臧からざらんや」
「雄キジがその羽を打ち立てて飛び立つように、わが夫も出征して行く。私はそれを思うと憂いばかりが募る。
雄キジが天空を羽音を立てて上下するように、わが夫も出征して行く。かの君子は、私の心を労させるばかり。
空に日月を見上げれば、憂患を募らせながらまた思う。遠い道を往きて、またここに帰ってくださることを。
あなたは君子だから、徳行にかけては私などよりもずっと知っていることでしょう。ただ、害悪を好んだり
無闇に利益を追い求めたりしないことで、不善に手を染めないことばかりを私は願うのみです。(雄雄しく
出征して行く夫を思い慕う妻の歌。『忮わず求めざれば、何ぞ用て臧からざらんや』は、孔子の弟子の子路が
好んで謳っていた一節で、孔子は『そんなことばかりでいいはずがない』と子路に苦言を呈していたわけだが、
上記のような文脈で歌われた言葉なわけだから、この言葉にもそれなりの含蓄があることがわかる。雄雄しく
ある夫こそは、最悪の不善にまでは手を染めないで居てくれというのが、妻たるものの切なる願いなのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・邶風・雄雉)
損なわず求めないが故に不善ではない——
そんなことは、多少できた婦女子でも分かることだってんだ。
女だから害悪を求めるわけじゃない。
老若男女に関わりない人でなしだからこそ、害悪を可とするんだ。
そんなことは、多少できた婦女子でも分かることだってんだ。
女だから害悪を求めるわけじゃない。
老若男女に関わりない人でなしだからこそ、害悪を可とするんだ。
この世界、天地万物全宇宙は生々流転の易の法則に即しているから、それなりの柔軟性や流動性を
持ち合わせている事物こそは、ただただ堅固であるような事物以上にも普遍的である場合が多々ある。
故に老子も「柔よく剛を制す」と言ったのであり、決してただの草の根志向だったりしたのではない。
生々流転の易の法則に即した上で、なおかつこの世界この宇宙は自己完結的なものであり、
形而上との連絡などが可能となったりすることもない。故に、形而上における絶対に普遍的な事物への
寄りすがりなどが実質性を帯びたりすることもなく、そのような試みは必ず不毛に終わることともなる。
ただただ堅固なだけでは柔軟でもあるものに敵わない。かといってただただ柔軟なのでは張り合いがない。
だから剛柔織り交ぜての為政を心がけるのが儒家の推奨する礼楽統治だったりもする。ただただ世の中を
制度で雁字搦めにする法家支配よりも柔軟でいて、何もかもをやらせたい放題なままにおく道家的統治
などと比べれば、メリハリがある。礼楽統治といえども数百年も経てば腐敗を来たして瓦解してしまう
のが常ではあるけれども、人間が実現する治世としては最上級のものであることにも間違いがない。
礼楽統治が法家支配や道家的統治よりも長寿で上質となるからには、剛柔織り交ぜた中正なあり方こそが
至上ともなるということである。ただただ硬いばかりでは脆くもなるが、ただただ柔らかいのでも
腐敗を来たす。硬いばかりじゃダメだからヤワヤワに振れ切るというのも極端なことであり、それが
休暇程度に許容されるのは可であるにしたって、振り切れてそのまんまというのでは賢いもんじゃない。
ただただ強固なものを追い求めるものにとって、ただただ柔弱なものが絶対に相容れないものなのではない。
法家の韓非も老子に傾倒していたし、キリスト教圏のままである近現代の欧米社会においても、自分たちで
示し合わせた範囲でのアンチキリストだとかアナーキズムだとかはそれなりに許容されている。あくまでその
勢力を矮小化させたりした範囲での活動ではあるものの、共存が絶対に不可能だったりまではしないのである。
持ち合わせている事物こそは、ただただ堅固であるような事物以上にも普遍的である場合が多々ある。
故に老子も「柔よく剛を制す」と言ったのであり、決してただの草の根志向だったりしたのではない。
生々流転の易の法則に即した上で、なおかつこの世界この宇宙は自己完結的なものであり、
形而上との連絡などが可能となったりすることもない。故に、形而上における絶対に普遍的な事物への
寄りすがりなどが実質性を帯びたりすることもなく、そのような試みは必ず不毛に終わることともなる。
ただただ堅固なだけでは柔軟でもあるものに敵わない。かといってただただ柔軟なのでは張り合いがない。
だから剛柔織り交ぜての為政を心がけるのが儒家の推奨する礼楽統治だったりもする。ただただ世の中を
制度で雁字搦めにする法家支配よりも柔軟でいて、何もかもをやらせたい放題なままにおく道家的統治
などと比べれば、メリハリがある。礼楽統治といえども数百年も経てば腐敗を来たして瓦解してしまう
のが常ではあるけれども、人間が実現する治世としては最上級のものであることにも間違いがない。
礼楽統治が法家支配や道家的統治よりも長寿で上質となるからには、剛柔織り交ぜた中正なあり方こそが
至上ともなるということである。ただただ硬いばかりでは脆くもなるが、ただただ柔らかいのでも
腐敗を来たす。硬いばかりじゃダメだからヤワヤワに振れ切るというのも極端なことであり、それが
休暇程度に許容されるのは可であるにしたって、振り切れてそのまんまというのでは賢いもんじゃない。
ただただ強固なものを追い求めるものにとって、ただただ柔弱なものが絶対に相容れないものなのではない。
法家の韓非も老子に傾倒していたし、キリスト教圏のままである近現代の欧米社会においても、自分たちで
示し合わせた範囲でのアンチキリストだとかアナーキズムだとかはそれなりに許容されている。あくまでその
勢力を矮小化させたりした範囲での活動ではあるものの、共存が絶対に不可能だったりまではしないのである。
ただただ強固であろうとするような姿勢と、剛柔織り交ぜた中正の尊重こそは、決して相容れることがない。
礼楽統治もまた礼法などにかけて格式ばるところがある、そしてその取り決めこそは、実定法の規律などとも
全く次元の違うものであり、礼節の範囲で人々の品性を根本から正していくものだから、そのぶんだけ
実定法によって人々の活動を取り締まったりする必要がなくなる。お互いに権益を脅かし合うもの同士で
あればこそ、ただただ頑なな法家支配と、剛柔織り交ぜる礼楽統治もまた相容れることがないのである。
ただただ強固であることにばかり慣れきってしまった人間こそは、中正の実践にも参画のしようがない。
ただの一般人以上にも、中正を守ることへの素養を欠いてしまっていて、もはや中正の何たるかも分からない。
そんな人間ばかりが支配層を占めてしまっていたりするようなら、革命すらもが避けられるものではなく、
革命によって地位を追われた旧支配層こそは、治産行為を強く制限される被差別階級にすらならねばならない。
キリスト教がそのような強固一辺倒の姿勢を信者に深く植え付けたのなら、キリスト教こそは、信者たる
欧米人などから、自分たちが世界の支配者たる資格を奪い去ったのだといえる。強固一辺倒を基調とした
世界支配などが、どんな形であれ長続きするものではなく、最悪の場合は滅亡級の破綻すらもが免れるもの
ではない、だから中正に適った礼楽統治を実現できるものにこの世を明け渡して、自分たちは飼い犬か飼い猫
も同然の立場に甘んじるしかない、そのような自分たちの運命を、キリスト教こそは決定付けたのである。
「有の扁りし石は、之れを履むにも卑き兮む」
「形のゆがんだ踏み石は、それを踏むときに自分の姿勢をもゆがめる必要がある。
(堅固な岩石であればこそ、それ自体が歪んでいれば、それを踏襲するものも態度姿勢が歪む)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・大雅・都人士之什・白華より)
礼楽統治もまた礼法などにかけて格式ばるところがある、そしてその取り決めこそは、実定法の規律などとも
全く次元の違うものであり、礼節の範囲で人々の品性を根本から正していくものだから、そのぶんだけ
実定法によって人々の活動を取り締まったりする必要がなくなる。お互いに権益を脅かし合うもの同士で
あればこそ、ただただ頑なな法家支配と、剛柔織り交ぜる礼楽統治もまた相容れることがないのである。
ただただ強固であることにばかり慣れきってしまった人間こそは、中正の実践にも参画のしようがない。
ただの一般人以上にも、中正を守ることへの素養を欠いてしまっていて、もはや中正の何たるかも分からない。
そんな人間ばかりが支配層を占めてしまっていたりするようなら、革命すらもが避けられるものではなく、
革命によって地位を追われた旧支配層こそは、治産行為を強く制限される被差別階級にすらならねばならない。
キリスト教がそのような強固一辺倒の姿勢を信者に深く植え付けたのなら、キリスト教こそは、信者たる
欧米人などから、自分たちが世界の支配者たる資格を奪い去ったのだといえる。強固一辺倒を基調とした
世界支配などが、どんな形であれ長続きするものではなく、最悪の場合は滅亡級の破綻すらもが免れるもの
ではない、だから中正に適った礼楽統治を実現できるものにこの世を明け渡して、自分たちは飼い犬か飼い猫
も同然の立場に甘んじるしかない、そのような自分たちの運命を、キリスト教こそは決定付けたのである。
「有の扁りし石は、之れを履むにも卑き兮む」
「形のゆがんだ踏み石は、それを踏むときに自分の姿勢をもゆがめる必要がある。
(堅固な岩石であればこそ、それ自体が歪んでいれば、それを踏襲するものも態度姿勢が歪む)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・大雅・都人士之什・白華より)
今の法人法の改正によっても、医療法人はそのほとんどが公益法人としての認可を
受けることが出来ず、おおむね社団法人として扱われるようにもなっている。
この実情一つとっても、怪我や病気を押してでも人間が無理に
生き続けようとすること自体、私欲の充足でしかないことが分かる。
公共機関で重要な職務に就いている人間が、己れの職務を果たすために健康や長寿を企図するとする。
その場合においても、まず病気や怪我に見舞われるような不摂生や不注意から排除して行くべきだし、
それでも老齢による心身の衰弱は免れられないから、潔く後代に職務を譲るなどする必要が出てくる。
人間、個人個人が独立的な生に執着することが公益に適う場合があるとは、この場合にも言えはしない。
家康公のように、天下の情勢が定まるまで死にきろうにも死にきれないでいた挙句に、
当時としては非常に高齢な75歳まで生きたような事例もあるが、やはり征夷大将軍としての
座は早急に息子の秀忠に譲り、駿府城からの半隠居状態での時局の見守りに徹したのだった。
生きる限りにおいても、やはり消極的に生きるということが仁者の事跡にこそ顕著であり、
やたらめったら自分自身が生きて個人的な繁栄を謳歌するようなことは控えている。
少なくとも、そうだったりすることを恥じて、見せびらかしたりはしないようにしている。
(一汁三菜を基本としていたという家康公の食生活も、本人の恰幅のよさなどからいえば疑わしい
ことだが、それでも大食いだったりしたことは恥じて隠している。その姿勢からして仁者である)
最大級に世のため人のためにあろうとする仁者であってなお、なるべく自分自身の健康を保つ程度までが、
自らが生きることに積極的であることが道義に適う限度だといえる。それ以上にも、利得をむさぼって
遊興に耽ったりするのなら、その時点で道義からは外れるのである。清廉すぎる物言いのように
思われるかもしれないが、それはそれで事実であり、それをわきまえた上で、適度に清濁
併せ呑んだ生き方をして行くことが、現実上から仁を為していく手立てともなるのである。
受けることが出来ず、おおむね社団法人として扱われるようにもなっている。
この実情一つとっても、怪我や病気を押してでも人間が無理に
生き続けようとすること自体、私欲の充足でしかないことが分かる。
公共機関で重要な職務に就いている人間が、己れの職務を果たすために健康や長寿を企図するとする。
その場合においても、まず病気や怪我に見舞われるような不摂生や不注意から排除して行くべきだし、
それでも老齢による心身の衰弱は免れられないから、潔く後代に職務を譲るなどする必要が出てくる。
人間、個人個人が独立的な生に執着することが公益に適う場合があるとは、この場合にも言えはしない。
家康公のように、天下の情勢が定まるまで死にきろうにも死にきれないでいた挙句に、
当時としては非常に高齢な75歳まで生きたような事例もあるが、やはり征夷大将軍としての
座は早急に息子の秀忠に譲り、駿府城からの半隠居状態での時局の見守りに徹したのだった。
生きる限りにおいても、やはり消極的に生きるということが仁者の事跡にこそ顕著であり、
やたらめったら自分自身が生きて個人的な繁栄を謳歌するようなことは控えている。
少なくとも、そうだったりすることを恥じて、見せびらかしたりはしないようにしている。
(一汁三菜を基本としていたという家康公の食生活も、本人の恰幅のよさなどからいえば疑わしい
ことだが、それでも大食いだったりしたことは恥じて隠している。その姿勢からして仁者である)
最大級に世のため人のためにあろうとする仁者であってなお、なるべく自分自身の健康を保つ程度までが、
自らが生きることに積極的であることが道義に適う限度だといえる。それ以上にも、利得をむさぼって
遊興に耽ったりするのなら、その時点で道義からは外れるのである。清廉すぎる物言いのように
思われるかもしれないが、それはそれで事実であり、それをわきまえた上で、適度に清濁
併せ呑んだ生き方をして行くことが、現実上から仁を為していく手立てともなるのである。
生きるということに積極的であり過ぎることをほとんどの東洋教学が戒めている一方、
「さっさと死んじまえ」などという虚無主義を前面に押し出しているものもまた、まれである。
「荘子」の雑篇などに、国王になることを薦められたが、権力嫌悪のあまり逃亡して自殺してしまう
隠者の逸話などもあるが、これも権力者としての奢り高ぶりなどに対するアンチテーゼとして提示された
方便的な極論なのであり、とにかく死をよしとするような所にまで暴論が及んでいるわけではないのである。
生きるか死ぬか、そんな極論に振り切れないような人生やその死に与れることこそは理想である。
偉大な人間は誰しもがその生を羨望し、死ねば誰しもがその死を悲しむ、外的にそのようであることはいい
としても、自分自身は生きることにも死ぬことにも積極的であり過ぎない、楚々とした態度でこそあるべきだ。
肉体や頭脳は所詮は単なる物質であり、それが死して廃壊するのも単なる物質の損壊であるまでだ。
そこに命をもたらしていた精神そのものは、肉体の生死などに関わらず不滅である。さほど大事で
ないものこそは生死の乱脈に翻弄される一方、本当に大事なものは始めから生じることも滅ぶことも
ありはしない。故にこそ、生死というものをさほど偏重して取り扱ったりする必要もないのである。
「我れ生の初め、尚お為すこと無し。
我れ生れて後、此の百罹に逢う。尚くは寐ねて吪くこと無からん」
「私は生まれたばかりの頃には無為の清浄に与れていたのに、長らく生きて後の今には
もはや百千万の難儀に見舞われるばかりである。もう寝たままで一切動かずにでもいたいものだ。
(仏法の一切皆苦ほど極端ではないが、生きるということの濁悪さをよく捉えた一節である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・王風・兔爰より)
「さっさと死んじまえ」などという虚無主義を前面に押し出しているものもまた、まれである。
「荘子」の雑篇などに、国王になることを薦められたが、権力嫌悪のあまり逃亡して自殺してしまう
隠者の逸話などもあるが、これも権力者としての奢り高ぶりなどに対するアンチテーゼとして提示された
方便的な極論なのであり、とにかく死をよしとするような所にまで暴論が及んでいるわけではないのである。
生きるか死ぬか、そんな極論に振り切れないような人生やその死に与れることこそは理想である。
偉大な人間は誰しもがその生を羨望し、死ねば誰しもがその死を悲しむ、外的にそのようであることはいい
としても、自分自身は生きることにも死ぬことにも積極的であり過ぎない、楚々とした態度でこそあるべきだ。
肉体や頭脳は所詮は単なる物質であり、それが死して廃壊するのも単なる物質の損壊であるまでだ。
そこに命をもたらしていた精神そのものは、肉体の生死などに関わらず不滅である。さほど大事で
ないものこそは生死の乱脈に翻弄される一方、本当に大事なものは始めから生じることも滅ぶことも
ありはしない。故にこそ、生死というものをさほど偏重して取り扱ったりする必要もないのである。
「我れ生の初め、尚お為すこと無し。
我れ生れて後、此の百罹に逢う。尚くは寐ねて吪くこと無からん」
「私は生まれたばかりの頃には無為の清浄に与れていたのに、長らく生きて後の今には
もはや百千万の難儀に見舞われるばかりである。もう寝たままで一切動かずにでもいたいものだ。
(仏法の一切皆苦ほど極端ではないが、生きるということの濁悪さをよく捉えた一節である)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・王風・兔爰より)
「困った時の神頼み」という言葉は、ご都合主義の神仏帰依として
批判目的で用いられる場合が多いことわざだが、これはこれで一つの真実の提示である。
困ってない時は神仏なんかにすがらない。自分から積極的に善行すら為していくというのなら、
神仏も我が子の自立を遠くから見守る親ぐらいのものでしかあり得ないというのが実際である。
本当に善を為して行く時には、もはや自問自答すらすべきでない。
一切の雑念を排した無念夢想の境地と共にこそ、真の善行もまた為し得るものである。
だからこそ幼少期の頃から儒学や武芸を学び込んでいた武家なども、
さらに禅寺での座禅によって雑念を排する修養を積んだりしていたのである。
「信仰によってこそ善が為せる、信仰がなければ善は為せない」というところにまで固定観念が
定着しきってしまっているようなら、そのせいでこそ、誰も善は為せなくなる。善を為そうとして
無為以上の悪しか為せなくなる。せいぜい信仰によって不善を最小限に控えるぐらいのことしかできはせず、
そのような信仰を辛うじて保っているのが浄土信仰や正統のイスラム信仰だったりするのみである。
不善を為さなかったり、最小限に止めたりすることは、それだけでは善と呼ぶにも値しないとは孔子も
子罕第九・二八に言い遺していることである。ただ、不善を為さないという程度のことも、女子供や
小人にとってはそれなりに重大なことであるのが、>>228の詩経からの引用を読んでも分かることである。
自分たちではさして大きな善行を為すこともできない、やもすれば大悪すらをも働きかねない
小人や女子供にとって、ただ不善や悪を為さないことだけでも一大命題となるのであり、
ただそれを守り通せただけでも、十分に賞賛に値するものだといえなくもないのである。
批判目的で用いられる場合が多いことわざだが、これはこれで一つの真実の提示である。
困ってない時は神仏なんかにすがらない。自分から積極的に善行すら為していくというのなら、
神仏も我が子の自立を遠くから見守る親ぐらいのものでしかあり得ないというのが実際である。
本当に善を為して行く時には、もはや自問自答すらすべきでない。
一切の雑念を排した無念夢想の境地と共にこそ、真の善行もまた為し得るものである。
だからこそ幼少期の頃から儒学や武芸を学び込んでいた武家なども、
さらに禅寺での座禅によって雑念を排する修養を積んだりしていたのである。
「信仰によってこそ善が為せる、信仰がなければ善は為せない」というところにまで固定観念が
定着しきってしまっているようなら、そのせいでこそ、誰も善は為せなくなる。善を為そうとして
無為以上の悪しか為せなくなる。せいぜい信仰によって不善を最小限に控えるぐらいのことしかできはせず、
そのような信仰を辛うじて保っているのが浄土信仰や正統のイスラム信仰だったりするのみである。
不善を為さなかったり、最小限に止めたりすることは、それだけでは善と呼ぶにも値しないとは孔子も
子罕第九・二八に言い遺していることである。ただ、不善を為さないという程度のことも、女子供や
小人にとってはそれなりに重大なことであるのが、>>228の詩経からの引用を読んでも分かることである。
自分たちではさして大きな善行を為すこともできない、やもすれば大悪すらをも働きかねない
小人や女子供にとって、ただ不善や悪を為さないことだけでも一大命題となるのであり、
ただそれを守り通せただけでも、十分に賞賛に値するものだといえなくもないのである。
「信仰によって善を為すことなんかできない、せいぜい不善を止める効果があったりするのみであり、
積極的な善行ともなれば、もはや無念無想によって為すぐらいでなければ勤まらない」といった認識こそを
誰しもに広めて行ったとき、せいぜい不善を為さない程度の所にしか自分たちの目的を定められなくなる
人間が多々生じ得る。自分たちでも善を為せるつもりでいたのが、せいぜい不善を控える程度のことしか
自分たちにはできないのだと思い知らされた時の小人男や女子供の落胆たるや、生半可なものではあるまい。
それこそ、身の程を思い知らされたがための落胆であるわけで、時には鬱病の発症すらもが免れ得ないだろう。
しかし、実際に世の中で為して行ける大規模な善行というのも、実物からして地味なものでもある。
権力道徳者としての活動こそは純粋かつ極大級の善行ともなるわけだが、そこで心がけられるのも万人の
食糧確保だとか、贋金作りや盗賊活動の取り締まりだとかで、とうてい女子供や小人男などがそれをこなして
行くことを欲しすらできないものである。しかもそれらの善行を為したからといって、貧民に寄付を恵んで
やった時の笑顔のような、己れの良心をくすぐるあからさまな見返りが得られたりするとも限らない。
仁政がよく行き届いている世の中においてこそ、恵みをありがたがる貧民なども始めから生じないのだから、
はじめからそのような世の中を保全していく権力道徳者の活動たるや、どこまでも「縁の下の力持ち」
であることこそを主体として行かねばならない。ゆえに、あからさまな見返りばかりを求めたがる
小人や女子供が率先して実行して行くことなどは、到底できないようにもなっているのである。
積極的な善行ともなれば、もはや無念無想によって為すぐらいでなければ勤まらない」といった認識こそを
誰しもに広めて行ったとき、せいぜい不善を為さない程度の所にしか自分たちの目的を定められなくなる
人間が多々生じ得る。自分たちでも善を為せるつもりでいたのが、せいぜい不善を控える程度のことしか
自分たちにはできないのだと思い知らされた時の小人男や女子供の落胆たるや、生半可なものではあるまい。
それこそ、身の程を思い知らされたがための落胆であるわけで、時には鬱病の発症すらもが免れ得ないだろう。
しかし、実際に世の中で為して行ける大規模な善行というのも、実物からして地味なものでもある。
権力道徳者としての活動こそは純粋かつ極大級の善行ともなるわけだが、そこで心がけられるのも万人の
食糧確保だとか、贋金作りや盗賊活動の取り締まりだとかで、とうてい女子供や小人男などがそれをこなして
行くことを欲しすらできないものである。しかもそれらの善行を為したからといって、貧民に寄付を恵んで
やった時の笑顔のような、己れの良心をくすぐるあからさまな見返りが得られたりするとも限らない。
仁政がよく行き届いている世の中においてこそ、恵みをありがたがる貧民なども始めから生じないのだから、
はじめからそのような世の中を保全していく権力道徳者の活動たるや、どこまでも「縁の下の力持ち」
であることこそを主体として行かねばならない。ゆえに、あからさまな見返りばかりを求めたがる
小人や女子供が率先して実行して行くことなどは、到底できないようにもなっているのである。
偽りでない本物の善というものもそれはそれである、ただ、それは意外と微妙不可思議なものであり、
あからさまに分かりやすいものとして現出するほうがまれである。中国の三国時代の群雄割拠だとか、
寛政期の火盗改長官である長谷川平蔵の活躍をフィクション混じりに描いた時代劇だとかが、一般にも
分かりやすい善の姿ともなっているが、それはむしろ当時の中国や日本の世相が乱れていたからこそ、
それを対症的に取り締まる英雄たちの姿が分かりやいというばかりのことなのであって、それで
善たるもののあり方をわかり切ったつもりになったりするのも、危険なことだといえる。
第一に微妙不可思議なものであり、第二に辛うじて分かりやすかったりすることがある、
そういう風に善というものを捉えて行くべきなのであり、何よりも分かりやすさばかりを善に要求
したりするようなことがあってはならない。善は分かりにくいが故にこそ旺盛でもあったりする一方、
脆弱化してしまったればこそ分かりやすくなってしまったりもするのだから、分かりにくいぐらいのほうがいいのだ。
「徳に常師無し、善を主とするを師と為す。善に常主無し、克く一なるに協うのみ」
「徳に恒常的な師というものはない、ただ善を主とするものを師とするのみ。
善にも恒常的な主というものはない、よく一を以って貫くことに適っているものが主たるのみ。
(死ぬことで生きるみたいな一貫しない態度姿勢からしてすでに善の主たるものではない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・商書・咸有一徳より)
あからさまに分かりやすいものとして現出するほうがまれである。中国の三国時代の群雄割拠だとか、
寛政期の火盗改長官である長谷川平蔵の活躍をフィクション混じりに描いた時代劇だとかが、一般にも
分かりやすい善の姿ともなっているが、それはむしろ当時の中国や日本の世相が乱れていたからこそ、
それを対症的に取り締まる英雄たちの姿が分かりやいというばかりのことなのであって、それで
善たるもののあり方をわかり切ったつもりになったりするのも、危険なことだといえる。
第一に微妙不可思議なものであり、第二に辛うじて分かりやすかったりすることがある、
そういう風に善というものを捉えて行くべきなのであり、何よりも分かりやすさばかりを善に要求
したりするようなことがあってはならない。善は分かりにくいが故にこそ旺盛でもあったりする一方、
脆弱化してしまったればこそ分かりやすくなってしまったりもするのだから、分かりにくいぐらいのほうがいいのだ。
「徳に常師無し、善を主とするを師と為す。善に常主無し、克く一なるに協うのみ」
「徳に恒常的な師というものはない、ただ善を主とするものを師とするのみ。
善にも恒常的な主というものはない、よく一を以って貫くことに適っているものが主たるのみ。
(死ぬことで生きるみたいな一貫しない態度姿勢からしてすでに善の主たるものではない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・商書・咸有一徳より)
危難を外界にしわ寄せすることで、領域内の人間の安全を確保してやっていた邪教があったとして、
もはや危難をしわ寄せする余地が外界になくなって、自分たち領域内の人間たち自身で危難を甘受して
行かなければならなくなった場合に、「(邪教の)神の保護から離れざるを得なくなった」などと嘆いたりする
のはおかしい。あくまで、自分たちで危難を甘受しなければならなくなったことまで含めて邪教やその神の責任
なのであり、責任はそれらや、そんなものを信じてしまった自分たちにこそあるのだとわきまえねばならない。
今まで他者に危難を押し付けてきたぶんだけ、人並み以上もの危難を自分たちが受け入れて行かなければならない。
それもまた邪教やその神の責任なのであり、怨むのならそれらこそを対象としなければならない。
(実在しない架空神であるのなら、そんなものを捏造した人間こそを怨むべきだ)
「完全なる平和」「完全なる秩序」、そんなものを本当に望めるような人間からして稀である。
まずは心から安寧を欲することのできる衆生こそを育て上げて行くのでなければ、みんな戦乱を望んでいるにも
関わらず、極大級の軍力で強制的に世情を鎮圧するなんていう状態にすらなってしまう。それこそ、名目上は平和で
あるにもかかわらず、その平和を謳歌する人間自身がろくにいないという、本末転倒の事態となってしまうのである。
心から安寧を求めるというのなら、当然マッチポンプの結果としての安全や平和などを欲したりもしない。
それは、より大きな危難をもたらしつつのなけなしの安全や平和でしかないのだから、本当に心から平安を求める
人間こそは、そんな風であってはならないと考えるのである。仮にマッチポンプ込みの安全や平和を欲することが
あるとすれば、そんな人間は本当は安全も平和も求めてはいない、暴虎馮河の危難こそを本質的に求めているのである。
もはや危難をしわ寄せする余地が外界になくなって、自分たち領域内の人間たち自身で危難を甘受して
行かなければならなくなった場合に、「(邪教の)神の保護から離れざるを得なくなった」などと嘆いたりする
のはおかしい。あくまで、自分たちで危難を甘受しなければならなくなったことまで含めて邪教やその神の責任
なのであり、責任はそれらや、そんなものを信じてしまった自分たちにこそあるのだとわきまえねばならない。
今まで他者に危難を押し付けてきたぶんだけ、人並み以上もの危難を自分たちが受け入れて行かなければならない。
それもまた邪教やその神の責任なのであり、怨むのならそれらこそを対象としなければならない。
(実在しない架空神であるのなら、そんなものを捏造した人間こそを怨むべきだ)
「完全なる平和」「完全なる秩序」、そんなものを本当に望めるような人間からして稀である。
まずは心から安寧を欲することのできる衆生こそを育て上げて行くのでなければ、みんな戦乱を望んでいるにも
関わらず、極大級の軍力で強制的に世情を鎮圧するなんていう状態にすらなってしまう。それこそ、名目上は平和で
あるにもかかわらず、その平和を謳歌する人間自身がろくにいないという、本末転倒の事態となってしまうのである。
心から安寧を求めるというのなら、当然マッチポンプの結果としての安全や平和などを欲したりもしない。
それは、より大きな危難をもたらしつつのなけなしの安全や平和でしかないのだから、本当に心から平安を求める
人間こそは、そんな風であってはならないと考えるのである。仮にマッチポンプ込みの安全や平和を欲することが
あるとすれば、そんな人間は本当は安全も平和も求めてはいない、暴虎馮河の危難こそを本質的に求めているのである。
引っ切り無しの動乱こそを欲しているような輩に対して平和をあてがってやったりするのは、
猫に小判もいいとこである。むしろ武力支配の到来などによって、己れの剣呑さをよく自覚させて、
それでも乱世を欲するか否かを問うてみればいい。それでも相変わらず欲するようであれば武力支配を継続、
それに懲りて心から平和を求めるようになるようなら、より柔弱な統治方法に切り替えるようにしてやればいい。
(京都に朝廷を置き、東京に幕府を置くような両輪統治もまた不可能ではない)
マッチポンプの一環としてのなけなしの平和などを欲したりする人間にも、自分たちが本当は平和以上にも
乱世こそを欲しているのだということを思い知らせた上で、それでも乱世を欲し続けるか、本物の平和を求める
ようになるかを問うべきである。そしてその答えようによって、武力統治か文治かのいずれかをあてがったりする。
それでこそ、本当に平和を企図することにもなる。乱世以上の平和を現実に呼び込む施策となる。
それと比べれば、ただ引っ切り無しの乱世を呼び込むのはもちろんのこと、マッチポンプの平和を希求したり
することですら、むしろ乱世を呼び込むことのうちに入るものである。日本の武家統治など、今の欧米聖書圏の
統治などと比べてもあからさまにこわもてではあるが、心から平和を追い求めたりすることのできない愚かな
人間を統治対象とするうえでは、むしろ武家統治のほうが真の平和を企図する手段ともなっていたのである。
「彼の譖人を取らえて、豺虎に投げ畀えよ。
豺虎も食わずんば、有北に投げ畀えよ。有北も受けずんば、有昊に投げ畀えよ」
「讒言を放つあの凶人をひっ捕らえて、豹や虎に投げ与えよ。豹や虎も嫌がって口にしないようなら、
北の果ての鬼に食わせよ。北の果ての鬼すら嫌がって受けぬようなら、後は天の裁きにかけるばかり。
(猛獣の害を免れられたからといって、さらにその先により大きな危難が待ち受けるのみである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・小雅・小旻之什・巷伯より)
猫に小判もいいとこである。むしろ武力支配の到来などによって、己れの剣呑さをよく自覚させて、
それでも乱世を欲するか否かを問うてみればいい。それでも相変わらず欲するようであれば武力支配を継続、
それに懲りて心から平和を求めるようになるようなら、より柔弱な統治方法に切り替えるようにしてやればいい。
(京都に朝廷を置き、東京に幕府を置くような両輪統治もまた不可能ではない)
マッチポンプの一環としてのなけなしの平和などを欲したりする人間にも、自分たちが本当は平和以上にも
乱世こそを欲しているのだということを思い知らせた上で、それでも乱世を欲し続けるか、本物の平和を求める
ようになるかを問うべきである。そしてその答えようによって、武力統治か文治かのいずれかをあてがったりする。
それでこそ、本当に平和を企図することにもなる。乱世以上の平和を現実に呼び込む施策となる。
それと比べれば、ただ引っ切り無しの乱世を呼び込むのはもちろんのこと、マッチポンプの平和を希求したり
することですら、むしろ乱世を呼び込むことのうちに入るものである。日本の武家統治など、今の欧米聖書圏の
統治などと比べてもあからさまにこわもてではあるが、心から平和を追い求めたりすることのできない愚かな
人間を統治対象とするうえでは、むしろ武家統治のほうが真の平和を企図する手段ともなっていたのである。
「彼の譖人を取らえて、豺虎に投げ畀えよ。
豺虎も食わずんば、有北に投げ畀えよ。有北も受けずんば、有昊に投げ畀えよ」
「讒言を放つあの凶人をひっ捕らえて、豹や虎に投げ与えよ。豹や虎も嫌がって口にしないようなら、
北の果ての鬼に食わせよ。北の果ての鬼すら嫌がって受けぬようなら、後は天の裁きにかけるばかり。
(猛獣の害を免れられたからといって、さらにその先により大きな危難が待ち受けるのみである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・小雅・小旻之什・巷伯より)
善徳や罪悪と利害とは、必ずしも関連付けて論じられるとも限らないものである。
しかし、結局のところこれらは不可分な関係にあるのであり、
全くの別物として捉えてまでいいものではないのである。
善徳は結局のところ公益寄与であり、罪悪は結局のところ公的害悪である。
ただ、人間必ずしも善行ばかりをやっていられるものでもなければ、悪行ばかりに専らでいるものでも
ないから、純粋な公益寄与か公的害悪ばかりを善や悪として捉えていると実情からかけ離れることになる。
金融詐欺で世界中に多大なる損害を及ぼしておきながら、それによって得た金の一部で貧窮者を救済したり
する場合もあり、その救済という部分だけをみれば善行のように思えたりすることもあるわけだから、
上記のような結局論ばかりを念頭に置くこともあまり奨められたものではないのである。
己れが天下に及ぼしている公益が公害を上回れば善、公害が公益を上回れば悪である。
これならより厳密な善悪の定義になるが、これまた実社会における分析的な把握は困難である。
商売なんていう職業は大元のところ、商売人本人が世の中に及ぼす利益よりも、本人が世の中から奪い取る
利益のほうがより大きくなるものである。そうであっても、商売人たちはあたかも自分たちの労働が
公益に寄与しているかのように手を変え品を変え見せかけてくる。それらの偽りを全て見抜いて、
害悪を分析的に糾弾するのも難しいことであり(商売人もあえてそうしているのだから)、
結局は上の定義を実社会で厳密に援用して行くのもなかなか難しいこととなるのである。
実社会における勧善懲悪の実践のためには、どうしたって直観的、本能的な判断にも頼る必要が出てくる。
上二つのような理論的な定義を、偽善詐悪の限りを尽くす悪徳商人なども入り混じる世の中で
いちいち通用させ尽くすことにこそ無理があるから、善悪の分別を漠然とした理念に止めて、
己れの直観に基づく勧善懲悪こそを実践して行く必要がある。
しかし、結局のところこれらは不可分な関係にあるのであり、
全くの別物として捉えてまでいいものではないのである。
善徳は結局のところ公益寄与であり、罪悪は結局のところ公的害悪である。
ただ、人間必ずしも善行ばかりをやっていられるものでもなければ、悪行ばかりに専らでいるものでも
ないから、純粋な公益寄与か公的害悪ばかりを善や悪として捉えていると実情からかけ離れることになる。
金融詐欺で世界中に多大なる損害を及ぼしておきながら、それによって得た金の一部で貧窮者を救済したり
する場合もあり、その救済という部分だけをみれば善行のように思えたりすることもあるわけだから、
上記のような結局論ばかりを念頭に置くこともあまり奨められたものではないのである。
己れが天下に及ぼしている公益が公害を上回れば善、公害が公益を上回れば悪である。
これならより厳密な善悪の定義になるが、これまた実社会における分析的な把握は困難である。
商売なんていう職業は大元のところ、商売人本人が世の中に及ぼす利益よりも、本人が世の中から奪い取る
利益のほうがより大きくなるものである。そうであっても、商売人たちはあたかも自分たちの労働が
公益に寄与しているかのように手を変え品を変え見せかけてくる。それらの偽りを全て見抜いて、
害悪を分析的に糾弾するのも難しいことであり(商売人もあえてそうしているのだから)、
結局は上の定義を実社会で厳密に援用して行くのもなかなか難しいこととなるのである。
実社会における勧善懲悪の実践のためには、どうしたって直観的、本能的な判断にも頼る必要が出てくる。
上二つのような理論的な定義を、偽善詐悪の限りを尽くす悪徳商人なども入り混じる世の中で
いちいち通用させ尽くすことにこそ無理があるから、善悪の分別を漠然とした理念に止めて、
己れの直観に基づく勧善懲悪こそを実践して行く必要がある。
すると、衆生に対する厳密な説明というのが追い付かなくなる。悪徳商人なんざを摘発するにしたって、
どんな悪いことをやって来たのかということをいちいち厳密に説明し尽くすのでは埒が明かない。
そうなるように悪徳商人の側こそはあの手この手の権謀術数の限りを尽くして来たのだから、
摘発に際して十分な説明が追い付かないこともまた、悪徳商人の側の自業自得というものである。
そしてそのような、直観的な方法に基づく勧善懲悪の指針を示したのが、他でもない儒学である。
孔子も全く利害と善悪を別物として扱っていたわけではないが、そもそも利害について語ること
自体が稀であったという(子罕第九・一)。実際的な勘定なども抜きにした純粋なな善悪論こそを
述べ立てていたのも、実は勧善懲悪の現実的な実践こそを目的としていたからなのであり、
だからといって現実への適用に無理があるなどと考えるのでは誤解となってしまうのである。
直観に基づく活動を尊重するためには、密教的なものに対する尊重もまた必要となる。
何もかもを明らかに説明されなければ気が済まないなどというのは、密教的なものへの尊重が足りない
からであり、それ自体、是正されて行かねばならない不埒さの一種なのである。そのための手段は、
仏門の密教への尊崇でもいいし、神道の神への誠意ある崇敬でもかまわない、信教などを抜きにして、
「密談中らしき部屋があるようなら立ち入るな(礼記・曲礼上第一)」という礼法に即するのでもいい。
何もかもをあからさまにしてしまおうとする意地汚さすら正されたなら、それでいいのである。
「事典を制し、法罪を正す」
「諸事の典礼を制して、法の定める所の罪や罰を正す。
(そもそも悪法を正して善法に替え、それを守らせることこそが自他の善行となるのだから、
法規に触れることを不善と見なしもしないようなことからしておかしい)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左子伝・文公六年より)
どんな悪いことをやって来たのかということをいちいち厳密に説明し尽くすのでは埒が明かない。
そうなるように悪徳商人の側こそはあの手この手の権謀術数の限りを尽くして来たのだから、
摘発に際して十分な説明が追い付かないこともまた、悪徳商人の側の自業自得というものである。
そしてそのような、直観的な方法に基づく勧善懲悪の指針を示したのが、他でもない儒学である。
孔子も全く利害と善悪を別物として扱っていたわけではないが、そもそも利害について語ること
自体が稀であったという(子罕第九・一)。実際的な勘定なども抜きにした純粋なな善悪論こそを
述べ立てていたのも、実は勧善懲悪の現実的な実践こそを目的としていたからなのであり、
だからといって現実への適用に無理があるなどと考えるのでは誤解となってしまうのである。
直観に基づく活動を尊重するためには、密教的なものに対する尊重もまた必要となる。
何もかもを明らかに説明されなければ気が済まないなどというのは、密教的なものへの尊重が足りない
からであり、それ自体、是正されて行かねばならない不埒さの一種なのである。そのための手段は、
仏門の密教への尊崇でもいいし、神道の神への誠意ある崇敬でもかまわない、信教などを抜きにして、
「密談中らしき部屋があるようなら立ち入るな(礼記・曲礼上第一)」という礼法に即するのでもいい。
何もかもをあからさまにしてしまおうとする意地汚さすら正されたなら、それでいいのである。
「事典を制し、法罪を正す」
「諸事の典礼を制して、法の定める所の罪や罰を正す。
(そもそも悪法を正して善法に替え、それを守らせることこそが自他の善行となるのだから、
法規に触れることを不善と見なしもしないようなことからしておかしい)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左子伝・文公六年より)
「力(特に剛力)」こそは、人間を世俗の汚濁や深刻な情欲と
切っても切れない関係に追いやってしまうものである。
力を競うのは修羅道であり、修羅道こそは人間を六道輪廻の業から引き止めて離すことがない。
特に100%純粋な修羅道は、ただただ腕力の強大さばかりを競い合い、技巧や謀略での勝利なども邪道とする。
歴史上に多々出没する「猪武者」こそはまさに純粋な修羅道を体現していて(項羽や呂布や不破数右衛門など)、
動乱にかけての名物的な存在ともなり得るものの、決して「最高の武人」たり得ているわけでもない点が共通する。
力を駆使する中にも、まだ剛柔織り交ぜる要素を織り込むようであれば、神仏の域にも達することがある。
合気柔術など小手先の腕力は全くといっていいほど用いず、姿勢制御や深層筋の潜在力だけで屈強な相手を
投げ飛ばしもする。和風プロレス化した今の柔道などにはほとんど見られなくなった「柔よく剛を制す(老子)」
という理念もまた天道に適うものであり、天道に適うからには、多少は世俗の汚濁を脱却しかけてもいるのだといえる。
ただ、修羅道から天道や仏道に向かうにかけて、単なる剛力の出しゃばる余地は次第になくなって行く。
修羅道然とした剣術である一刀流や次元流のほうが力にものをいわせる一方で、神道や仏道の理念も取り入れた
新当流や新陰流こそは腕力を超えたところにある崇高な理念に基づく武芸を旨としている。幕末に腕力で幕府から
政権を乗っ取ろうとした反幕勢力が主要な修得対象としていたのも一刀流や次元流であり、(ただし実際に倒幕を
決定付ける原因となったのは、連中が大阪堺の豪商から借金して外国の武器商人から購入した重火器であった)
力で何かを達成しようとするものにとっては、神仏の域に達するような武芸などもまた邪道扱いになるのである。
力の競い合いにかけて専らであろうとすることこそは、世俗の汚濁にまみれきる原因となる一方、
そんなことに専らでなけれはこそ、多少なりとも世俗の汚濁から離縁していくことができるようになる。
切っても切れない関係に追いやってしまうものである。
力を競うのは修羅道であり、修羅道こそは人間を六道輪廻の業から引き止めて離すことがない。
特に100%純粋な修羅道は、ただただ腕力の強大さばかりを競い合い、技巧や謀略での勝利なども邪道とする。
歴史上に多々出没する「猪武者」こそはまさに純粋な修羅道を体現していて(項羽や呂布や不破数右衛門など)、
動乱にかけての名物的な存在ともなり得るものの、決して「最高の武人」たり得ているわけでもない点が共通する。
力を駆使する中にも、まだ剛柔織り交ぜる要素を織り込むようであれば、神仏の域にも達することがある。
合気柔術など小手先の腕力は全くといっていいほど用いず、姿勢制御や深層筋の潜在力だけで屈強な相手を
投げ飛ばしもする。和風プロレス化した今の柔道などにはほとんど見られなくなった「柔よく剛を制す(老子)」
という理念もまた天道に適うものであり、天道に適うからには、多少は世俗の汚濁を脱却しかけてもいるのだといえる。
ただ、修羅道から天道や仏道に向かうにかけて、単なる剛力の出しゃばる余地は次第になくなって行く。
修羅道然とした剣術である一刀流や次元流のほうが力にものをいわせる一方で、神道や仏道の理念も取り入れた
新当流や新陰流こそは腕力を超えたところにある崇高な理念に基づく武芸を旨としている。幕末に腕力で幕府から
政権を乗っ取ろうとした反幕勢力が主要な修得対象としていたのも一刀流や次元流であり、(ただし実際に倒幕を
決定付ける原因となったのは、連中が大阪堺の豪商から借金して外国の武器商人から購入した重火器であった)
力で何かを達成しようとするものにとっては、神仏の域に達するような武芸などもまた邪道扱いになるのである。
力の競い合いにかけて専らであろうとすることこそは、世俗の汚濁にまみれきる原因となる一方、
そんなことに専らでなけれはこそ、多少なりとも世俗の汚濁から離縁していくことができるようになる。
相撲のように、むしろ力の競い合いを定型化して興行化してしまうことで、観衆たち自身が腕力を蓄えようとする
気概を萎えさせてしまう神事などもあるわけだが、その目的はやはり「力の適切な扱い」にこそ集約されていて、
適切に扱おうとするからには、腕力中毒による濁世へのしがらみなどを脱却する目的もまたあるのだといえる。
戦史上に名のある猪武者といえども、まだ力の扱いが適切なほうだったといえる。古今東西史上でも最大級の
猪武者だった西楚の覇王項羽も、自らが俗世の汚濁にまみれていることを否定したりまでしているのではなかった。
むしろ、そのやり過ぎな戦いぶりが、対抗馬であり漢帝国の祖となった劉邦に「あれほどにも強大な相手を
屈服させて天下を取った」という箔を付ける助けにもなったのだった。
「腕力こそは神の域にすら達する」という倒錯、これこそは力の不適切な扱いの最たるものである。
そこまで倒錯が深刻化しきったままの状態では、もはや本物の神仏の域に触れることはおろか、目に見える範囲に
近づくことすらも叶いはしない。失神状態仏滅状態でただただ俗世の汚濁にまみれきることしかできなくなってしまう。
出家でもしない限りは世俗に生きる常人として、「腕力こそは神の域にすら達する」という倒錯にまでは及ばない
でいること、これだけは必須条件である。ただただそれなりの力比べに乗ずることは、許容範囲内だったり、
ちょっと問題的だったりする。力の適切な扱いを旨として、柔よく剛を制することの合理性にまで配慮が
及ぶのならそれに越したことはなく、それでこそ自分自身が神仏の域にすら触れることができるようにもなる。
鬼畜の領域、修羅の領域、神仏の領域。人間が進取することまでもが可とされ得るのは、後二つのみである。
気概を萎えさせてしまう神事などもあるわけだが、その目的はやはり「力の適切な扱い」にこそ集約されていて、
適切に扱おうとするからには、腕力中毒による濁世へのしがらみなどを脱却する目的もまたあるのだといえる。
戦史上に名のある猪武者といえども、まだ力の扱いが適切なほうだったといえる。古今東西史上でも最大級の
猪武者だった西楚の覇王項羽も、自らが俗世の汚濁にまみれていることを否定したりまでしているのではなかった。
むしろ、そのやり過ぎな戦いぶりが、対抗馬であり漢帝国の祖となった劉邦に「あれほどにも強大な相手を
屈服させて天下を取った」という箔を付ける助けにもなったのだった。
「腕力こそは神の域にすら達する」という倒錯、これこそは力の不適切な扱いの最たるものである。
そこまで倒錯が深刻化しきったままの状態では、もはや本物の神仏の域に触れることはおろか、目に見える範囲に
近づくことすらも叶いはしない。失神状態仏滅状態でただただ俗世の汚濁にまみれきることしかできなくなってしまう。
出家でもしない限りは世俗に生きる常人として、「腕力こそは神の域にすら達する」という倒錯にまでは及ばない
でいること、これだけは必須条件である。ただただそれなりの力比べに乗ずることは、許容範囲内だったり、
ちょっと問題的だったりする。力の適切な扱いを旨として、柔よく剛を制することの合理性にまで配慮が
及ぶのならそれに越したことはなく、それでこそ自分自身が神仏の域にすら触れることができるようにもなる。
鬼畜の領域、修羅の領域、神仏の領域。人間が進取することまでもが可とされ得るのは、後二つのみである。
「此こに人有りて、力は一匹の雛に勝うることも能わずといわば、則ち力無き人と為すも、
今百鈞を挙ぐると曰わば、則ち力有る人と為さんや。然れば則ち烏獲の任を挙ぐれば、是れ亦た烏獲と為すのみ。
夫れ人豈に勝えざるを以って患いと為さんや。為さざるのみ。徐行して長者に後る、之れを弟と謂い、
疾行して長者に先んずる、之れを不弟と謂う。夫れ徐行は、豈に人の能わざる所たらんや。為さぬ所なり」
「ここに一人の人間がいて、アヒルの雛一羽も持ち上げることができないというなら、みな彼を力のない人間だ
と見なすだろうが、もし百鈞(約1.8トン)のものすら持ち上げられるというなら、誰しもが力ある人間だと
見なすだろう。(伝説上の力士である)烏獲が持ち上げられたものを自分も持ち上げられるというのなら、
その人間もまた烏獲並みだと見なされるだろう。ただそれだけのことなのであり、どうして力がないことなどを
憂いとする必要があるだろうか。自分がゆっくり歩いて年長者の後ろを行くのは悌順なことだが、さっさと
走り去って年長者の先を行くようならこれは不悌である。どうして力がないからといって、徐行して年長者の
後を行くことができなかったりするだろう。ただそうあろうとする心がけがないだけのことだろう。
(儒家の司る人道もまた、力の有無ではなく、真心の有無こそを第一の問題としている)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・告子章句下・二より)
今百鈞を挙ぐると曰わば、則ち力有る人と為さんや。然れば則ち烏獲の任を挙ぐれば、是れ亦た烏獲と為すのみ。
夫れ人豈に勝えざるを以って患いと為さんや。為さざるのみ。徐行して長者に後る、之れを弟と謂い、
疾行して長者に先んずる、之れを不弟と謂う。夫れ徐行は、豈に人の能わざる所たらんや。為さぬ所なり」
「ここに一人の人間がいて、アヒルの雛一羽も持ち上げることができないというなら、みな彼を力のない人間だ
と見なすだろうが、もし百鈞(約1.8トン)のものすら持ち上げられるというなら、誰しもが力ある人間だと
見なすだろう。(伝説上の力士である)烏獲が持ち上げられたものを自分も持ち上げられるというのなら、
その人間もまた烏獲並みだと見なされるだろう。ただそれだけのことなのであり、どうして力がないことなどを
憂いとする必要があるだろうか。自分がゆっくり歩いて年長者の後ろを行くのは悌順なことだが、さっさと
走り去って年長者の先を行くようならこれは不悌である。どうして力がないからといって、徐行して年長者の
後を行くことができなかったりするだろう。ただそうあろうとする心がけがないだけのことだろう。
(儒家の司る人道もまた、力の有無ではなく、真心の有無こそを第一の問題としている)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・告子章句下・二より)
とりあえず板だとたたかれるのでこちらに書きます。
ほぼ毎日読ませてもらってるぜ。ではもう寝ますお休み。
ほぼ毎日読ませてもらってるぜ。ではもう寝ますお休み。
人間はその本性が善だから、外物に囚われることなく己れの本性に立ち返ることでこそ、
善思善言善行を為すことができる。その逆に、外物に囚われて己れの本性を見失うことでこそ、
悪思悪言悪行に走ってしまう。故に、自力作善を基本として行くことこそは真に善徳の推進とも
なる一方、他力本願でいることはそれだけでも罪悪の積み重ねになってしまいがちなのである。
一時的に人に頼るとか頼らないとかいった段階の話ではなく、己れの心持ちが常日頃から
自律的であるか他律的であるかということこそが問題である。人に頼るか頼らないかでいえば、
人間は誰しもがお互いに頼り合うことでしかやっていけない生き物なのだから、頼るしかない。
そうであってなお、自らの心持ちが本質的に独立的であることが善徳の推進につながって行く一方、
本当に心持ちから完全に頼りきり、依存第一な状態でしかいられないことが罪悪に繋がるのである。
依存第一の状態を極大化させたところにこそあるのが、自分の見失いである。
自らの心を完全に失って、単なる情報処理機械も同然な脳内状態でしかいられなくなる状態、
そこでこそ、人は絶対に善行を為すことも、善徳の実在を計り知ることすらも適わなくなる。
確信犯の罪人や悪人はおおむねそういった精神状態であり、サイコパスともなれば確実にそうである。
そこに至る過程は人さまざまであり、あからさまな罪悪に手を染めることでそうなるとも限らない。
人の真心を蔑ろにするような世知辛い世の中の荒波にもまれることでそうなってしまうこともある。
ただ、そうなってしまうほどにも世の中が世知辛いのは、やっぱり世の中のどこかで致命的な
罪悪が積み重ねられてもいるからであり、自分が知らず知らずのうちからその従犯と化せられて
しまう過程として、殺伐とした世の中に嫌らしく順応させられてしまうようなことがあるのである。
一時的な頼り合いではなく、恒久的な心持ちからの依存状態を促すもの——そんなものが
あるとすれば、これこそは人々に罪悪の積み重ねをけしかける元凶の最たるものだといえる。
少なくとも、人々から善思善言善行といった選択肢を完全に奪い去るものであり、どんなに無害な
教条に止め置かれた所で、所詮は不善を最小限に抑える程度の効果しか期待できないものである。
善思善言善行を為すことができる。その逆に、外物に囚われて己れの本性を見失うことでこそ、
悪思悪言悪行に走ってしまう。故に、自力作善を基本として行くことこそは真に善徳の推進とも
なる一方、他力本願でいることはそれだけでも罪悪の積み重ねになってしまいがちなのである。
一時的に人に頼るとか頼らないとかいった段階の話ではなく、己れの心持ちが常日頃から
自律的であるか他律的であるかということこそが問題である。人に頼るか頼らないかでいえば、
人間は誰しもがお互いに頼り合うことでしかやっていけない生き物なのだから、頼るしかない。
そうであってなお、自らの心持ちが本質的に独立的であることが善徳の推進につながって行く一方、
本当に心持ちから完全に頼りきり、依存第一な状態でしかいられないことが罪悪に繋がるのである。
依存第一の状態を極大化させたところにこそあるのが、自分の見失いである。
自らの心を完全に失って、単なる情報処理機械も同然な脳内状態でしかいられなくなる状態、
そこでこそ、人は絶対に善行を為すことも、善徳の実在を計り知ることすらも適わなくなる。
確信犯の罪人や悪人はおおむねそういった精神状態であり、サイコパスともなれば確実にそうである。
そこに至る過程は人さまざまであり、あからさまな罪悪に手を染めることでそうなるとも限らない。
人の真心を蔑ろにするような世知辛い世の中の荒波にもまれることでそうなってしまうこともある。
ただ、そうなってしまうほどにも世の中が世知辛いのは、やっぱり世の中のどこかで致命的な
罪悪が積み重ねられてもいるからであり、自分が知らず知らずのうちからその従犯と化せられて
しまう過程として、殺伐とした世の中に嫌らしく順応させられてしまうようなことがあるのである。
一時的な頼り合いではなく、恒久的な心持ちからの依存状態を促すもの——そんなものが
あるとすれば、これこそは人々に罪悪の積み重ねをけしかける元凶の最たるものだといえる。
少なくとも、人々から善思善言善行といった選択肢を完全に奪い去るものであり、どんなに無害な
教条に止め置かれた所で、所詮は不善を最小限に抑える程度の効果しか期待できないものである。
そんなものの享受が横行してしまっているせいで、人々がみな善性を湛えた己れの心を
見失ってしまっているような状況において、人々をその心から正して行ってやるなどというのも、
順序の取り違えになるといえる。自らの本然からの善性を完全に見失わせてしまうような諸々の
外物の除去だとか、善性を見失った状態での人々の妄動の制限だとかの、外的な措置をそれなりに
講じてから、その後に己れの本性たる善性に気づかせて行くほうが、順序としても正しいといえる。
最悪の濁世における、実力行使による矯正の優先、それぐらいは確かに許容せざるを得ないことでも
あるらしい。だからといって「誠意正心修身斉家治国平天下(大学)」といった、人々の心からの
成長やそれに基づく治世などが全く蔑ろにされたりしてもならない。実力での矯正は、せいぜい
最悪の乱世の収拾のめどが立つあたりまで。そこから先は、人々の善性を養生することでの
低コスト高パフォーマンスかつ堅実な統治こそを主体として行くべきである。
どこまでも実力支配一辺倒でい続けるというのなら、せいぜい独裁主義支配や共産主義支配の
レベルに止まるばかり。平安時代の日本のような理想的な文治はおろか、それなりに人々の善性をも
重んじていた武家時代の実力支配にすら、為政の健全度で及ぶことはない。未だ実力支配が旺盛で
ある時期からでも、人々の本性からの善性への尊重ぐらいはあるべきであり、それに基づいて、
己れの心を見失ってしまっている愚人たちへの相応な扱いにも及んで行くべきなのである。
心ないものたちの非道が横行する世の中と、それをただ実力で押さえつけるだけ世の中と、
どちらのほうがよりマシかすら判別のしようもない。どちらも最悪にろくでもないという他はなく、
そのような両極端への振り切れから脱却して行くことこそをマシ以上の指針とすべきである。
人間の本性からの善性を蔑ろにしたままでいるような状態全般からの脱却のあらんことを。
見失ってしまっているような状況において、人々をその心から正して行ってやるなどというのも、
順序の取り違えになるといえる。自らの本然からの善性を完全に見失わせてしまうような諸々の
外物の除去だとか、善性を見失った状態での人々の妄動の制限だとかの、外的な措置をそれなりに
講じてから、その後に己れの本性たる善性に気づかせて行くほうが、順序としても正しいといえる。
最悪の濁世における、実力行使による矯正の優先、それぐらいは確かに許容せざるを得ないことでも
あるらしい。だからといって「誠意正心修身斉家治国平天下(大学)」といった、人々の心からの
成長やそれに基づく治世などが全く蔑ろにされたりしてもならない。実力での矯正は、せいぜい
最悪の乱世の収拾のめどが立つあたりまで。そこから先は、人々の善性を養生することでの
低コスト高パフォーマンスかつ堅実な統治こそを主体として行くべきである。
どこまでも実力支配一辺倒でい続けるというのなら、せいぜい独裁主義支配や共産主義支配の
レベルに止まるばかり。平安時代の日本のような理想的な文治はおろか、それなりに人々の善性をも
重んじていた武家時代の実力支配にすら、為政の健全度で及ぶことはない。未だ実力支配が旺盛で
ある時期からでも、人々の本性からの善性への尊重ぐらいはあるべきであり、それに基づいて、
己れの心を見失ってしまっている愚人たちへの相応な扱いにも及んで行くべきなのである。
心ないものたちの非道が横行する世の中と、それをただ実力で押さえつけるだけ世の中と、
どちらのほうがよりマシかすら判別のしようもない。どちらも最悪にろくでもないという他はなく、
そのような両極端への振り切れから脱却して行くことこそをマシ以上の指針とすべきである。
人間の本性からの善性を蔑ろにしたままでいるような状態全般からの脱却のあらんことを。
「昊天を瞻卬するも、嘒たる其の星の有るのみ。大夫君子よ、昭め仮みて贏る無かれ。
大命も止みて近くも、爾じが成イサオを棄つる無かれ。何をか求めて我が為めにせん、
以て庶正を戻せんとて。昊天を瞻卬するにも、曷しか恵みて其れ寧からん」
「天上を見上げてもまたたく星があるばかりで、天の助けなどを期待すべくもない。
君子大夫たちよ、だからといって怠るようなこともせず、よく謹んで勤めに励むがよい。
大いなる天命に与ることもできなくなって久しいが、だからといって己れの功業を軽んじてもならない。
どうして自分のためなどであろうか、ただ正しき民たちに利するため。天上を見上げれば、
いつかは天もまた恵みを施してこの世を安んじてくれるかもしれぬ。(天からの恵みなど全く
当てにせず修善に励み、恵みがあるとてそれは衆生のためにとする。徹底した自力作善志向)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・大雅・蕩之什・雲漢より)
大命も止みて近くも、爾じが成イサオを棄つる無かれ。何をか求めて我が為めにせん、
以て庶正を戻せんとて。昊天を瞻卬するにも、曷しか恵みて其れ寧からん」
「天上を見上げてもまたたく星があるばかりで、天の助けなどを期待すべくもない。
君子大夫たちよ、だからといって怠るようなこともせず、よく謹んで勤めに励むがよい。
大いなる天命に与ることもできなくなって久しいが、だからといって己れの功業を軽んじてもならない。
どうして自分のためなどであろうか、ただ正しき民たちに利するため。天上を見上げれば、
いつかは天もまた恵みを施してこの世を安んじてくれるかもしれぬ。(天からの恵みなど全く
当てにせず修善に励み、恵みがあるとてそれは衆生のためにとする。徹底した自力作善志向)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・大雅・蕩之什・雲漢より)
悪党をその心から正してやるなんてことも、もう望むべきでもない。
それこそ、心から正されることが最も困難な類いの人種であるのだから。
悪党を常人並みの心境にまで持って行ってやるぐらいまでは、
武力制圧だとか刑罰だとか禁治産だとかの実力行使にも頼らねばならない。
ただ、頼るのはそこまでであって、治世のための統治手段はあくまで、
「誠意正心修身斉家治国平天下」といった順序に則って行かねばならない。
心田の耕しを十八番としているのは何といっても仏門だから、
武力以上にも仏教に頼るぐらいのつもりでなければならない。
それこそ、心から正されることが最も困難な類いの人種であるのだから。
悪党を常人並みの心境にまで持って行ってやるぐらいまでは、
武力制圧だとか刑罰だとか禁治産だとかの実力行使にも頼らねばならない。
ただ、頼るのはそこまでであって、治世のための統治手段はあくまで、
「誠意正心修身斉家治国平天下」といった順序に則って行かねばならない。
心田の耕しを十八番としているのは何といっても仏門だから、
武力以上にも仏教に頼るぐらいのつもりでなければならない。
http://bbs0.meiwasuisan.com/bbs/bin/read/toriaezu/13594671...
「人間は本性が善だから、悪党を心から正せはしない。」
大したことないようでいて、実は重大な発見になっている。
ここんとこすらちゃんとわきまえとけば、独裁制の到来も防げる。
実力行使による悪党の摘発があまって、いつまでも世の中を
腕力によって支配し続けるようなことも防げるから。
「人間は本性が善だから、悪党を心から正せはしない。」
大したことないようでいて、実は重大な発見になっている。
ここんとこすらちゃんとわきまえとけば、独裁制の到来も防げる。
実力行使による悪党の摘発があまって、いつまでも世の中を
腕力によって支配し続けるようなことも防げるから。
つまり、逆に言えば、
そこんとこすらわきまえとけば、やり過ぎなども気にせずに、
心置きなく悪党どもを取り締まって行けるということでもある。
悪党を裁きにかけることと、無辜の市民を支配下に置くこととは、
全く別の性格を帯びたものとして捉えねばならなくなるから。
そこんとこすらわきまえとけば、やり過ぎなども気にせずに、
心置きなく悪党どもを取り締まって行けるということでもある。
悪党を裁きにかけることと、無辜の市民を支配下に置くこととは、
全く別の性格を帯びたものとして捉えねばならなくなるから。
邪教信仰はえてして、信者に自己を偽る迫真の演技を促すものである。
旧約信仰の肝要は、信者たるユダヤ人が政商犯としての横暴を深刻化させていくことを促すものであるし、
新約信仰の肝要も、信者に政商犯の横行を許容させたり、犯行の被害者となることを容認させたりする所にある。
真実のところを正しく指摘すれば上のようだけれども、自分が新旧約の信者となるためには、
むしろそんなことに気づいてはならないのである。ただ「神の物語」を享受するだけの盲目な子羊で
いられればこそ、内実がそれほどにも悪辣な犯罪寓意の教条を信仰対象にすらして行けるのである。
邪教にとって、真実を悟ることは信仰に結び付かず、真実から目を背けることこそは信仰に結び付く。
他人に信仰を促す邪教信者なども、「真実こそは直視しがたいもの」であるかのようにあえて触れ回ったりも
するけれども、(たとえば、ドストエフスキーが「カラマーゾフの兄弟」でイワンに語らせている現実描写など)
そのような直視しがたい現実を到来させているものこそは、邪教信仰に基づく政商の横行だったりするのであり、
現実が直視しがたいからといって盲目な信仰を促すこと自体、1セットのマッチポンプ戦略になっているのである。
新旧約信仰の内実という真実から目を背けさせて、ただただ神に帰依する、神の愛に服するなどという怠慢に
陥れるものこそは真性の信仰にも溺れてしまう。それこそ、邪教の側にとっての絶好のカモともなるわけだが、
そうならないためには、現実をよく直視して、決して見失ったりすることのない強靭な精神力こそが必要である。
すでに政商犯の暴慢が肥大化してしまっているようならば、邪教信仰を排した所にある現実社会の実情なども、
それはそれは見るに耐えない惨状と化してしまっていたりするわけだが、それでもなお現実を直視することを
やめないでいられるだけの胆力と、そこから着実に回復して行こうと志せるだけの大勇こそが必要となるのである。
邪教信仰自体は、精神の薄弱な女子供や小人男こそが享受しやすいものである。しかし、
邪教信仰がこの世にもたらす惨暴たるや、大の大人の男でも直視しがたい程のものであったりする。
旧約信仰の肝要は、信者たるユダヤ人が政商犯としての横暴を深刻化させていくことを促すものであるし、
新約信仰の肝要も、信者に政商犯の横行を許容させたり、犯行の被害者となることを容認させたりする所にある。
真実のところを正しく指摘すれば上のようだけれども、自分が新旧約の信者となるためには、
むしろそんなことに気づいてはならないのである。ただ「神の物語」を享受するだけの盲目な子羊で
いられればこそ、内実がそれほどにも悪辣な犯罪寓意の教条を信仰対象にすらして行けるのである。
邪教にとって、真実を悟ることは信仰に結び付かず、真実から目を背けることこそは信仰に結び付く。
他人に信仰を促す邪教信者なども、「真実こそは直視しがたいもの」であるかのようにあえて触れ回ったりも
するけれども、(たとえば、ドストエフスキーが「カラマーゾフの兄弟」でイワンに語らせている現実描写など)
そのような直視しがたい現実を到来させているものこそは、邪教信仰に基づく政商の横行だったりするのであり、
現実が直視しがたいからといって盲目な信仰を促すこと自体、1セットのマッチポンプ戦略になっているのである。
新旧約信仰の内実という真実から目を背けさせて、ただただ神に帰依する、神の愛に服するなどという怠慢に
陥れるものこそは真性の信仰にも溺れてしまう。それこそ、邪教の側にとっての絶好のカモともなるわけだが、
そうならないためには、現実をよく直視して、決して見失ったりすることのない強靭な精神力こそが必要である。
すでに政商犯の暴慢が肥大化してしまっているようならば、邪教信仰を排した所にある現実社会の実情なども、
それはそれは見るに耐えない惨状と化してしまっていたりするわけだが、それでもなお現実を直視することを
やめないでいられるだけの胆力と、そこから着実に回復して行こうと志せるだけの大勇こそが必要となるのである。
邪教信仰自体は、精神の薄弱な女子供や小人男こそが享受しやすいものである。しかし、
邪教信仰がこの世にもたらす惨暴たるや、大の大人の男でも直視しがたい程のものであったりする。
メディア戦略などの洗脳支配で、人々の精神力の平均値から大幅に引き下げられているような世の中で、
まともに政商犯の暴慢込みの世の中の実情と向き合って行けるような人間なども、そんなに多くいる
などとは期待できない。仮にいたとした所で、その人間が惨憺たる世の中の実情を着実に改善して
いけるだけの事務的な能力を持ち合わせているとも限らない。人々の文科系と体育会系への大別によって、
無知な蛮勇の持ち主と文弱の徒とにばかり、ほとんどの人間が枝分かれしてしまっていたりもするから、
智勇兼ね備えた真の壮士というものを期待すること自体、ほとんど望みのないことともなってしまっている。
——というような、現実との対峙者の側の不遇自体、すでに惨憺たる実情の一環ともなっている。
智勇兼備の英雄たち自身がほとんどこの世から絶やされてしまっているような最悪の状況において、
なおのこと着実な起死回生を目指して行ける指針があるとすれば、それはもはや真理の悟りでしかあるまい。
真理真実を悟った先にこそ、盲目な狂信に溺れている状態以上もの爽快さすらもがあるのだという
確信のみが、最悪の事態すらをも正善へと反して行けるだけの気概のよりどころともなるであろう。
真理に即してしか物事を改善して行く目処も立たないことを、今一度、真理の大切さを見直す機会と
することによって、このこの最悪の事態をも、一つのめでたい機縁に変えてしまえばいいのである。
「鳲鳩桑に在り、其の子は七つ。淑人君子、其の儀一なり。其の儀一なりて、心も結ばるるが如し」
「カッコウの親鳥が桑の木に止まり、その子供も七羽にまで至っている。仁徳ある君子もまた、
(多くの民を養って行くための)儀を一にする。ただ一つの儀にのみ、その心も結ばれている。
(むしろ、民を統治下に置く君子こそは民の化育に心を結ぶ。君子の志しとサービス精神の相違)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・曹風・鳲鳩より)
まともに政商犯の暴慢込みの世の中の実情と向き合って行けるような人間なども、そんなに多くいる
などとは期待できない。仮にいたとした所で、その人間が惨憺たる世の中の実情を着実に改善して
いけるだけの事務的な能力を持ち合わせているとも限らない。人々の文科系と体育会系への大別によって、
無知な蛮勇の持ち主と文弱の徒とにばかり、ほとんどの人間が枝分かれしてしまっていたりもするから、
智勇兼ね備えた真の壮士というものを期待すること自体、ほとんど望みのないことともなってしまっている。
——というような、現実との対峙者の側の不遇自体、すでに惨憺たる実情の一環ともなっている。
智勇兼備の英雄たち自身がほとんどこの世から絶やされてしまっているような最悪の状況において、
なおのこと着実な起死回生を目指して行ける指針があるとすれば、それはもはや真理の悟りでしかあるまい。
真理真実を悟った先にこそ、盲目な狂信に溺れている状態以上もの爽快さすらもがあるのだという
確信のみが、最悪の事態すらをも正善へと反して行けるだけの気概のよりどころともなるであろう。
真理に即してしか物事を改善して行く目処も立たないことを、今一度、真理の大切さを見直す機会と
することによって、このこの最悪の事態をも、一つのめでたい機縁に変えてしまえばいいのである。
「鳲鳩桑に在り、其の子は七つ。淑人君子、其の儀一なり。其の儀一なりて、心も結ばるるが如し」
「カッコウの親鳥が桑の木に止まり、その子供も七羽にまで至っている。仁徳ある君子もまた、
(多くの民を養って行くための)儀を一にする。ただ一つの儀にのみ、その心も結ばれている。
(むしろ、民を統治下に置く君子こそは民の化育に心を結ぶ。君子の志しとサービス精神の相違)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・曹風・鳲鳩より)
精子 Part9wwww
自らが社会的な弱者であることを認めるというのなら、
なぜ正規の王侯将相に統治されることを認められないのだろうか。
王侯のごとき封建社会の統治者こそは、弱者としての民たちの保護に務めることを本分としている。
民主主義社会の為政者のように民の強壮化を促したりするのでもなく、純粋な弱者としての民を保護下
に置き、その安全や福利厚生を保証するのと引き換えに、自分たちが「人の上に立つ人」たろうともする。
封建社会において為政者が上位の存在として扱われるのも、それによって相対的な弱者としての
扱いが確立される民たちを保護下に置くためでこそある。にもかかわらず、王侯や士大夫に見下される
ことに反感を抱いて体制の転覆を企てたり、士民全人の平等を謳うような信教を好んだりするのは、
「自分たち民こそは強者である」というような思い込みと共にであればまだ話が通るが、
「自分たちこそは弱者である」という自認と共にであるのなら、完全に矛盾している。
実際のところ、為政者こそは極大級の軍事力すらをも保持することが公的に認められる存在だから、
公人と民間人とでどちらのほうが普遍的に強者であるのかといえば、それは公人のほうだといえる。
「軍事力も民を守るためにこそ存在する」、理念としてはそうであるが、民同士が大規模な詐欺行為
などによって利権の共食い争いを繰り広げていたりするようならば、一時的に民間社会こそを
軍事的な制圧下に置いて事態の沈静化を図ったりすることも一種の民の保護になるといえる。
一方で、民間人が民間人であるままに国家規模の軍事力を私有したりすることはできない。軍需産業
を牛耳って陰ながらの軍部支配を試みたりすることはできても、「これこそは俺を守るための私兵だ」
などと公言しつつ民間人が私有できる軍事力なんてのは、せいぜいテロ組織レベルに止まり続ける。
故に、コソコソと陰ながらに済ますこともできないような極大級、大局規模の領域において、
民間人が正規の公人に実力行使の能力面で勝るようなことも決してありはしないのである。
なぜ正規の王侯将相に統治されることを認められないのだろうか。
王侯のごとき封建社会の統治者こそは、弱者としての民たちの保護に務めることを本分としている。
民主主義社会の為政者のように民の強壮化を促したりするのでもなく、純粋な弱者としての民を保護下
に置き、その安全や福利厚生を保証するのと引き換えに、自分たちが「人の上に立つ人」たろうともする。
封建社会において為政者が上位の存在として扱われるのも、それによって相対的な弱者としての
扱いが確立される民たちを保護下に置くためでこそある。にもかかわらず、王侯や士大夫に見下される
ことに反感を抱いて体制の転覆を企てたり、士民全人の平等を謳うような信教を好んだりするのは、
「自分たち民こそは強者である」というような思い込みと共にであればまだ話が通るが、
「自分たちこそは弱者である」という自認と共にであるのなら、完全に矛盾している。
実際のところ、為政者こそは極大級の軍事力すらをも保持することが公的に認められる存在だから、
公人と民間人とでどちらのほうが普遍的に強者であるのかといえば、それは公人のほうだといえる。
「軍事力も民を守るためにこそ存在する」、理念としてはそうであるが、民同士が大規模な詐欺行為
などによって利権の共食い争いを繰り広げていたりするようならば、一時的に民間社会こそを
軍事的な制圧下に置いて事態の沈静化を図ったりすることも一種の民の保護になるといえる。
一方で、民間人が民間人であるままに国家規模の軍事力を私有したりすることはできない。軍需産業
を牛耳って陰ながらの軍部支配を試みたりすることはできても、「これこそは俺を守るための私兵だ」
などと公言しつつ民間人が私有できる軍事力なんてのは、せいぜいテロ組織レベルに止まり続ける。
故に、コソコソと陰ながらに済ますこともできないような極大級、大局規模の領域において、
民間人が正規の公人に実力行使の能力面で勝るようなことも決してありはしないのである。
実際のところ、民間人は公人以上の強者たり得ないし、民間人も「自分たちこそは強者である」
などとまで開き直るようなこともほとんどない。いくら女が男に対してえらそうな顔をしようとも、
実際のところの能力面でまで男に敵わないのは、女もまた認めざるを得ないでいるのと同じように、
民間人もまた自分たちが本質的な弱者であることを大前提としながら、それなりに従順でいたり、
逆にルサンチマンを抱いて官民上下の序列の転覆をも図ったりする。とはいえ、後者によって
実現されるのもあくまで「カカア天下」止まりであり、そのせいで公人の側が天下国家の
総裁としての責任を放棄しての、世相の乱脈ばかりを招いたりすることともなるのである。
公人こそは強者であり、民間人こそは弱者である。その普遍的な前提に即して公人が民を保護
するというのなら、ある程度は官民上下の序列もまたわきまえられてしかるべきである。もちろん
強い者が弱い者を虐げるためではなく、強い者が弱い者を守ってやることを磐石化するためでこそある。
それを健全に実現して行くためには、官民上下の序列を否定したり蔑ろにしたりするような
思想信条をよしとしたりもしないことである。虚構の超越神への浮気によって実際の君子階級への
崇敬が疎かになったりするようならば、そのような神格信仰も害あるものとしていかねばならない。
あくまで、実際の君子士人への崇敬を助成するような神仏への信仰に限って正統とする。
ただ、それは世界中のほとんどの神仏が満たしている条件であり、それに即して邪神と見なされて
排されるような神のほうがむしろ少ない。実際の為政者への崇敬を損なわせるような邪神こそは、
八百万の神なり毛穴の数ほどの仏なりとの並存を禁止してまで、自らへの絶対的帰依を信者に強制
したりするものでもあるから、世界中の数多の神仏信仰系の信教にとっても、上のような正統異端の
条件付けが興隆の助けになることこそあれど、妨げになるようなことは決してないのである。
などとまで開き直るようなこともほとんどない。いくら女が男に対してえらそうな顔をしようとも、
実際のところの能力面でまで男に敵わないのは、女もまた認めざるを得ないでいるのと同じように、
民間人もまた自分たちが本質的な弱者であることを大前提としながら、それなりに従順でいたり、
逆にルサンチマンを抱いて官民上下の序列の転覆をも図ったりする。とはいえ、後者によって
実現されるのもあくまで「カカア天下」止まりであり、そのせいで公人の側が天下国家の
総裁としての責任を放棄しての、世相の乱脈ばかりを招いたりすることともなるのである。
公人こそは強者であり、民間人こそは弱者である。その普遍的な前提に即して公人が民を保護
するというのなら、ある程度は官民上下の序列もまたわきまえられてしかるべきである。もちろん
強い者が弱い者を虐げるためではなく、強い者が弱い者を守ってやることを磐石化するためでこそある。
それを健全に実現して行くためには、官民上下の序列を否定したり蔑ろにしたりするような
思想信条をよしとしたりもしないことである。虚構の超越神への浮気によって実際の君子階級への
崇敬が疎かになったりするようならば、そのような神格信仰も害あるものとしていかねばならない。
あくまで、実際の君子士人への崇敬を助成するような神仏への信仰に限って正統とする。
ただ、それは世界中のほとんどの神仏が満たしている条件であり、それに即して邪神と見なされて
排されるような神のほうがむしろ少ない。実際の為政者への崇敬を損なわせるような邪神こそは、
八百万の神なり毛穴の数ほどの仏なりとの並存を禁止してまで、自らへの絶対的帰依を信者に強制
したりするものでもあるから、世界中の数多の神仏信仰系の信教にとっても、上のような正統異端の
条件付けが興隆の助けになることこそあれど、妨げになるようなことは決してないのである。
「三老五更を大学に食うときは、天子も袒ぎて牲を割き、醤を執りて饋り、
爵を執りて酳い、冕して干を總る。諸侯の弟を教える所以なり。是の故に、
郷里に齒有りて、老窮を遺さず、強は弱を犯さず、衆は寡を暴かず、此れ大学由り来たる者なり」
「旧公卿で孤独の引退者たちを大学に招いた時は、天子も肩脱ぎして生贄を割き、
ひしおの料理でもてなし、名誉の爵位を送り、冕服に干という尊者に対する装束で舞いを踊る。
この大学での天子の振る舞いによる教化によって、方々の地域でも年長者を困窮させたままで
いるようなことがなくなり、強者が弱者を犯すことも、多数派が少数派を脅かすこともなくなる。
(天子が弱者を憐れみ尊ぶことでこそ、誰しもが自分以上の弱者を哀れむようになれるのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・祭義第二十四より)
爵を執りて酳い、冕して干を總る。諸侯の弟を教える所以なり。是の故に、
郷里に齒有りて、老窮を遺さず、強は弱を犯さず、衆は寡を暴かず、此れ大学由り来たる者なり」
「旧公卿で孤独の引退者たちを大学に招いた時は、天子も肩脱ぎして生贄を割き、
ひしおの料理でもてなし、名誉の爵位を送り、冕服に干という尊者に対する装束で舞いを踊る。
この大学での天子の振る舞いによる教化によって、方々の地域でも年長者を困窮させたままで
いるようなことがなくなり、強者が弱者を犯すことも、多数派が少数派を脅かすこともなくなる。
(天子が弱者を憐れみ尊ぶことでこそ、誰しもが自分以上の弱者を哀れむようになれるのである)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・祭義第二十四より)
人間にとってのあらゆる救いのなさは、全て生への執着を元凶としている。
生々流転、諸行無常の実世界において、個人の生存ばかりに専らであろうとすることが、
人間にとってのあらゆる苦しみの源となる。他人の命を重んずることではなく、
自分の命を偏重しようとすることこそは致命的な救いのなさの原因となり、
そのような傾向を人々に植え付けようとするような教条こそは、
人々に救いようのないほどもの苦しみをもたらすことともなる。
他人の命はむしろ重んずるべきであり、そのために自分の命をなげうつぐらいであるべきである。
しかも、そのような心情を一般化して世間に広く通用すらさせれば、個人個人はむしろ
自らの命を惜しみもしないにもかかわらず、お互いがお互いの命を尊重し合うことで
奪い合い殺し合いなども横行しない福利厚生の万全な世の中が形成されて行くこととなる。
しかもそれでこそ、人々が個人的な生への執着からなる苦悩を脱却して、わさわざ救いを
求めねばならなくなるような濁悪な思考や言行を帯びなくても済むようになるのである。
そのような世の中の実現を直接的に企図しているのが仏教であり、生への執着を
捨て去らせようとするその教条が個人の救いになるばかりでなく、上記のような
実利面からの福利厚生に満ち足りた世の中の到来をも実現して行けるのである。
儒学や神道やヒンズー教などはそこまでは行かず、生への執着を家の尊重などに善用することで
適正化して行こうとする。自分自身の生存もそれなりに重要なものとするが、それはあくまで
世のため人のため自分の家のための生であるとし、私的な生存欲などはやはり捨て去るのである。
長らく仏教振興に与ってきた日本人の感覚などからすれば、もはや生への執着など完全に
捨て去ってもいいぐらいの心持ちでいられもする。その上で、自分が大切な家の嫡子で
あったりする場合に限って、相応の世俗的な人生を営んで行くぐらいでちょうどだと思える。
これは、仏教も儒学も神道もという風に、世界中の教学のいいとこばかりを選別して
凝縮的に享受して来た、この日本ならではの恵まれた境遇に基づく心持ちだともいえる。
生々流転、諸行無常の実世界において、個人の生存ばかりに専らであろうとすることが、
人間にとってのあらゆる苦しみの源となる。他人の命を重んずることではなく、
自分の命を偏重しようとすることこそは致命的な救いのなさの原因となり、
そのような傾向を人々に植え付けようとするような教条こそは、
人々に救いようのないほどもの苦しみをもたらすことともなる。
他人の命はむしろ重んずるべきであり、そのために自分の命をなげうつぐらいであるべきである。
しかも、そのような心情を一般化して世間に広く通用すらさせれば、個人個人はむしろ
自らの命を惜しみもしないにもかかわらず、お互いがお互いの命を尊重し合うことで
奪い合い殺し合いなども横行しない福利厚生の万全な世の中が形成されて行くこととなる。
しかもそれでこそ、人々が個人的な生への執着からなる苦悩を脱却して、わさわざ救いを
求めねばならなくなるような濁悪な思考や言行を帯びなくても済むようになるのである。
そのような世の中の実現を直接的に企図しているのが仏教であり、生への執着を
捨て去らせようとするその教条が個人の救いになるばかりでなく、上記のような
実利面からの福利厚生に満ち足りた世の中の到来をも実現して行けるのである。
儒学や神道やヒンズー教などはそこまでは行かず、生への執着を家の尊重などに善用することで
適正化して行こうとする。自分自身の生存もそれなりに重要なものとするが、それはあくまで
世のため人のため自分の家のための生であるとし、私的な生存欲などはやはり捨て去るのである。
長らく仏教振興に与ってきた日本人の感覚などからすれば、もはや生への執着など完全に
捨て去ってもいいぐらいの心持ちでいられもする。その上で、自分が大切な家の嫡子で
あったりする場合に限って、相応の世俗的な人生を営んで行くぐらいでちょうどだと思える。
これは、仏教も儒学も神道もという風に、世界中の教学のいいとこばかりを選別して
凝縮的に享受して来た、この日本ならではの恵まれた境遇に基づく心持ちだともいえる。
そのような恵まれた環境下に与れなかったような人々が、まずどうすべきかを考えてみるに、
それは、「どういう風に恵まれていなかったか」によって対処法が変わるものだといえる。
欧米のように生への執着ばかりに専らでい過ぎた地域では、生への執着こそを捨てさせる
仏教のような教学の受容が推奨できるし、アフリカのようにむしろ個人個人の生命を蔑ろに
し過ぎているような地域では、古来からの民俗文化に神道や儒学の文化的手法を兼ね合わさせる
などして、家族単位での人々の生活をより尊重させて行くなどすればいいのではないかと思う。
今の人類社会は、総体的に生への執着が過剰化してしまっている状態である。
だからといって人々が不老不死の命を手に入れたりできるわけでもないから、
苦悩のはけ口を性向に追い求めて、世界人口を爆発的に増大させるまでに至っている。
人々に過剰な生への執着を捨てさせることこそは、人類にとっての急務である。
そのために第一に必要となるのは、人々の生への執着を極大化させる例の邪教の根絶である
けれども、ただ根絶するだけでその後に何らの精神的ケアも行わないままでいるのであれば、
邪教によって植えつけられた執着を持ち越して問題を引き起こし続けることにもなりかねない。
だからこそ、邪教を根絶した後の穴の埋め合わせにもまた勤しんで行かねばならないのである。
「我れ生の初め、庸き無きを尚いしに、我れ生の後、此の百凶に逢えり。尚くば寐ねて聡むる無からん」
「まだ生まれ付いて間もない頃から、私はただ無事な人生を送れたならばと思っていたのに、
しばらく生きてみれば、ただただ百千万の凶事に見舞われるばかり。願わくばずっと寝たままで
人の言うことも聞きたくはない。(人生の就寝以上ものつまらなさ。乱世を嘆く君子の歌でもある)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・王風・兔爰より)
それは、「どういう風に恵まれていなかったか」によって対処法が変わるものだといえる。
欧米のように生への執着ばかりに専らでい過ぎた地域では、生への執着こそを捨てさせる
仏教のような教学の受容が推奨できるし、アフリカのようにむしろ個人個人の生命を蔑ろに
し過ぎているような地域では、古来からの民俗文化に神道や儒学の文化的手法を兼ね合わさせる
などして、家族単位での人々の生活をより尊重させて行くなどすればいいのではないかと思う。
今の人類社会は、総体的に生への執着が過剰化してしまっている状態である。
だからといって人々が不老不死の命を手に入れたりできるわけでもないから、
苦悩のはけ口を性向に追い求めて、世界人口を爆発的に増大させるまでに至っている。
人々に過剰な生への執着を捨てさせることこそは、人類にとっての急務である。
そのために第一に必要となるのは、人々の生への執着を極大化させる例の邪教の根絶である
けれども、ただ根絶するだけでその後に何らの精神的ケアも行わないままでいるのであれば、
邪教によって植えつけられた執着を持ち越して問題を引き起こし続けることにもなりかねない。
だからこそ、邪教を根絶した後の穴の埋め合わせにもまた勤しんで行かねばならないのである。
「我れ生の初め、庸き無きを尚いしに、我れ生の後、此の百凶に逢えり。尚くば寐ねて聡むる無からん」
「まだ生まれ付いて間もない頃から、私はただ無事な人生を送れたならばと思っていたのに、
しばらく生きてみれば、ただただ百千万の凶事に見舞われるばかり。願わくばずっと寝たままで
人の言うことも聞きたくはない。(人生の就寝以上ものつまらなさ。乱世を嘆く君子の歌でもある)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——詩経・国風・王風・兔爰より)
Out of Base.^^;;
この世には、陰陽法則に即して日向者(ひたなもの)として扱うべきものと、日陰者
として扱うべきものとの両方がある。男か女かでいえば、男を日向者、女を日陰者として
扱うべきだし、官か民かでいえば、官職者を日向者、民間人を日陰者として扱うべきである。
民間人同士のうちでも、農業や必需産業に従事するものを日向者として扱い、ガラクタ産業や
商業に従事するものを日陰者として扱うべきである。以上のような扱いを講じることでこそ、
陰陽法則に司られているこの世の中もまた、最善級にうまくいくようになるのである。
日陰者だからといって完全な排斥対象になるのではなく、日向者に順ずるものとしてこそ
模範的であるべきである。女が夫や子に尽くす良妻賢母たれば、それが女としての誉れ
ともなる。本家の嫡子の長男などと比べれば日陰者であるべき分家の庶子や次男三男、
さらには妾腹の私生児なども、学者や僧侶や、養子先での孝子などとしての精進に励めば、
孔子や一休和尚や鬼平のような高名を後世にまで轟かすことだってできなくはないのである。
一概な日向者でいることと、多少は日陰者に甘んずることと、どちらのほうがより
個人的な幸福に与れる可能性があるかといって、それはむしろ日陰者のほうである。
偉大な王侯将相の跡取りなどのほうが、もはや個人的な栄達などを追い求めて行ける
余地もほとんどないのに対し、劉邦や羽柴秀吉のような卑賤の身分の出身者であればこそ、
そこからどこまでも上を目指して行ける余地があるために、それに基づく僥倖をも
期待して行けるのである。(ただしこの場合にも高転びなどへの注意が必要である)
ただ日陰者であるべきような立場の人間が、そこからの栄達を目指して行くためには、
相当な苦労が必要ともなる。妾腹の私生児から大学者へと大成した孔子の血のにじむような
その努力具合も、本人が体系化した五経の記録内容の精緻さなどからも伺えることである。
として扱うべきものとの両方がある。男か女かでいえば、男を日向者、女を日陰者として
扱うべきだし、官か民かでいえば、官職者を日向者、民間人を日陰者として扱うべきである。
民間人同士のうちでも、農業や必需産業に従事するものを日向者として扱い、ガラクタ産業や
商業に従事するものを日陰者として扱うべきである。以上のような扱いを講じることでこそ、
陰陽法則に司られているこの世の中もまた、最善級にうまくいくようになるのである。
日陰者だからといって完全な排斥対象になるのではなく、日向者に順ずるものとしてこそ
模範的であるべきである。女が夫や子に尽くす良妻賢母たれば、それが女としての誉れ
ともなる。本家の嫡子の長男などと比べれば日陰者であるべき分家の庶子や次男三男、
さらには妾腹の私生児なども、学者や僧侶や、養子先での孝子などとしての精進に励めば、
孔子や一休和尚や鬼平のような高名を後世にまで轟かすことだってできなくはないのである。
一概な日向者でいることと、多少は日陰者に甘んずることと、どちらのほうがより
個人的な幸福に与れる可能性があるかといって、それはむしろ日陰者のほうである。
偉大な王侯将相の跡取りなどのほうが、もはや個人的な栄達などを追い求めて行ける
余地もほとんどないのに対し、劉邦や羽柴秀吉のような卑賤の身分の出身者であればこそ、
そこからどこまでも上を目指して行ける余地があるために、それに基づく僥倖をも
期待して行けるのである。(ただしこの場合にも高転びなどへの注意が必要である)
ただ日陰者であるべきような立場の人間が、そこからの栄達を目指して行くためには、
相当な苦労が必要ともなる。妾腹の私生児から大学者へと大成した孔子の血のにじむような
その努力具合も、本人が体系化した五経の記録内容の精緻さなどからも伺えることである。
ただ勉強に励んでいただけでなく、卑賤の身分からなる劣等感との葛藤に孔子も苛まれていた
はずである。その劣等感に取り込まれて非道な邪義を触れ回ったのがイエスだったりするわけで、
妾腹の私生児級の不遇者の大半はそのような暴発に陥るか、もしくは日陰者としての苦しみの中に
一生を尽くすかのいずれかに終わるものである。そのようなあり方では「やっぱり日陰者止まり」
という謗りを免れ得ないのはもちろんのこと、日陰者としての不遇を克服した先にこそある幸福に
与るような醍醐味をも得られはしない。日陰者が日陰者なりに大成して行くという選択肢は確かに
拓けているが、その道は大変細く険しく、生半な努力などでは到底踏破できないようになっている。
以上のような論及は、もちろん先天的な不遇を克服して行く場合にこそ言えることである。
自分から好き好んで悪徳商売のような賤業に従事したりするようなら、もはや自力で不遇を克服
して行く選択肢すらをもかなぐり捨てているといえる。先天的な日陰者扱いの不遇を克服して
行くために必須となるのは、何といっても自助努力であり、自助努力こそは人並み以上でなければ
何も務まらない。自分から不遇の限りを尽くした挙句に誰かからの救いを期待するなんていう
選択肢こそはなく、それこそ誰からの同情も受けるに値しない道化としての自滅を招くのみである。
「王憂いに宅り、陰に亮すこと三祀。既に喪を免るるも、其れ惟れ言うこと弗し。(中略)曰く、
台れ四方に正たるを以って、惟れ徳の類からざるを恐る、茲の故に言わず。恭みて黙して道を思う」
「殷の王(武丁)は先代の死後、常に憂いの中にあり、三年もの間影ながらの生活に順じていた。
すでに服喪期間を過ぎてからも、ほとんどものを言わなかった。(これでは仕事にならないと憂えた
臣下が催促すると)王は言われた。『私は自分が四方の国々に対して正大な存在たるに相応しい
だけの徳を具えていないことを恐れている。そのためほとんどものも言わず、慎み黙って道を
懐い続けているのである』(影ながらの生活の中に慎み黙する中にこそ、徳を得るための道を
思うこともまたある。『伝道の書』の著者はそんなことは思いもよらなかったのだろう)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・商書・説命上より)
はずである。その劣等感に取り込まれて非道な邪義を触れ回ったのがイエスだったりするわけで、
妾腹の私生児級の不遇者の大半はそのような暴発に陥るか、もしくは日陰者としての苦しみの中に
一生を尽くすかのいずれかに終わるものである。そのようなあり方では「やっぱり日陰者止まり」
という謗りを免れ得ないのはもちろんのこと、日陰者としての不遇を克服した先にこそある幸福に
与るような醍醐味をも得られはしない。日陰者が日陰者なりに大成して行くという選択肢は確かに
拓けているが、その道は大変細く険しく、生半な努力などでは到底踏破できないようになっている。
以上のような論及は、もちろん先天的な不遇を克服して行く場合にこそ言えることである。
自分から好き好んで悪徳商売のような賤業に従事したりするようなら、もはや自力で不遇を克服
して行く選択肢すらをもかなぐり捨てているといえる。先天的な日陰者扱いの不遇を克服して
行くために必須となるのは、何といっても自助努力であり、自助努力こそは人並み以上でなければ
何も務まらない。自分から不遇の限りを尽くした挙句に誰かからの救いを期待するなんていう
選択肢こそはなく、それこそ誰からの同情も受けるに値しない道化としての自滅を招くのみである。
「王憂いに宅り、陰に亮すこと三祀。既に喪を免るるも、其れ惟れ言うこと弗し。(中略)曰く、
台れ四方に正たるを以って、惟れ徳の類からざるを恐る、茲の故に言わず。恭みて黙して道を思う」
「殷の王(武丁)は先代の死後、常に憂いの中にあり、三年もの間影ながらの生活に順じていた。
すでに服喪期間を過ぎてからも、ほとんどものを言わなかった。(これでは仕事にならないと憂えた
臣下が催促すると)王は言われた。『私は自分が四方の国々に対して正大な存在たるに相応しい
だけの徳を具えていないことを恐れている。そのためほとんどものも言わず、慎み黙って道を
懐い続けているのである』(影ながらの生活の中に慎み黙する中にこそ、徳を得るための道を
思うこともまたある。『伝道の書』の著者はそんなことは思いもよらなかったのだろう)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・商書・説命上より)
「泰山其れ頽れんか、梁木其れ壊れんか、哲人其れ萎まんか」
「泰山ですらもが崩れ落ちるのか、巨木すらもが折れ去るのか、哲人も衰え死ぬのか」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・檀弓上第三より)
孔子が晩年に死期を悟ったときに詠ったとされる歌。半ば尊大なようにも受け止められかねないが、
孔子自身の生まれの不遇さだとか、それをバネにしての努力研鑽による大成だとかをよく
慮ってみたならば、この歌も決して誇張表現などではなかったことが計り知れるのである。
母子家庭育ちの妾腹の私生児から、世界で最も子孫の多い偉人へと上り詰めたその由緒も、
決してまがい物だったりするのではなく、宇宙の真理にすら半ば合致しているものであった。
それでいて孔子は出家者や隠遁者などとは違って、旺盛な活動意欲や生存欲の持ち主でもあった。
ただそうであるというだけなら、生きる価値の無さにすらさいなまれることになりかねないような
「妾腹の私生児」という極度の逆境をはねのけて大成すればこそ、人一倍自尊心も強かったのである。
それも、根拠のない自尊心などではなく、磐石な根拠にこそ根ざした、きわめて安定的な自尊心。
妾腹の私生児にもかかわらずではなくだからこそ、それが得られた。純粋な自力作善のみによって
勝ち得た、磐石な根拠と共なる自尊心であればこそ、泰山ほどにも揺らぐことがなかったのだった。
確かにそれはきわめて困難なことであり、妾腹の私生児に生まれついたからといって誰しもが
それほどもの大成を実現できるなどとは決して言えないことである。ただ、上に書いたような
孔子の事績などもあればこそ、「妾腹の私生児=決して救われることのない不遇」などと開き直って、
不遇を極めることに陶酔したり、そのような状態の人間に同情したりすることも許されないのである。
自分が妾腹の私生児だからといって、孔子ほどもの大成はとうてい見込めない。
だとすれば隠遁者なり出家者なりとして日陰者の人生に徹すればいいのであり、
不遇に呑み込まれた自己こそをひけらかして同情を買うなんてことだけは自制すべきである。
「泰山ですらもが崩れ落ちるのか、巨木すらもが折れ去るのか、哲人も衰え死ぬのか」
(権力道徳聖書——通称四書五経——礼記・檀弓上第三より)
孔子が晩年に死期を悟ったときに詠ったとされる歌。半ば尊大なようにも受け止められかねないが、
孔子自身の生まれの不遇さだとか、それをバネにしての努力研鑽による大成だとかをよく
慮ってみたならば、この歌も決して誇張表現などではなかったことが計り知れるのである。
母子家庭育ちの妾腹の私生児から、世界で最も子孫の多い偉人へと上り詰めたその由緒も、
決してまがい物だったりするのではなく、宇宙の真理にすら半ば合致しているものであった。
それでいて孔子は出家者や隠遁者などとは違って、旺盛な活動意欲や生存欲の持ち主でもあった。
ただそうであるというだけなら、生きる価値の無さにすらさいなまれることになりかねないような
「妾腹の私生児」という極度の逆境をはねのけて大成すればこそ、人一倍自尊心も強かったのである。
それも、根拠のない自尊心などではなく、磐石な根拠にこそ根ざした、きわめて安定的な自尊心。
妾腹の私生児にもかかわらずではなくだからこそ、それが得られた。純粋な自力作善のみによって
勝ち得た、磐石な根拠と共なる自尊心であればこそ、泰山ほどにも揺らぐことがなかったのだった。
確かにそれはきわめて困難なことであり、妾腹の私生児に生まれついたからといって誰しもが
それほどもの大成を実現できるなどとは決して言えないことである。ただ、上に書いたような
孔子の事績などもあればこそ、「妾腹の私生児=決して救われることのない不遇」などと開き直って、
不遇を極めることに陶酔したり、そのような状態の人間に同情したりすることも許されないのである。
自分が妾腹の私生児だからといって、孔子ほどもの大成はとうてい見込めない。
だとすれば隠遁者なり出家者なりとして日陰者の人生に徹すればいいのであり、
不遇に呑み込まれた自己こそをひけらかして同情を買うなんてことだけは自制すべきである。
実際、孔子のような極度の不遇からの大成者が実在していればこそ、東洋社会においては不遇を
ひけらかしての人気取りなどは非とされて来た。特に、妾腹の私生児のような克服のしようの
ある不遇で同情を買おうなどとする人間には「甘ったれんな」という冷たい視線が注がれた。
それは別に間違ったことでもない、世界的に通用させても何ら問題のない常識的措置なのであり、
それにすら耐えられないなんていう薄弱者こそは社会的立場を追われたとしても仕方がないのである。
それが「ガサツ」だったりするのでもない。どちらかといえば、己れの精神の薄弱さのあまり
私利私益ばかりをむさぼって、遠方の他人を困窮や餓死にまで追い込んでおきながら、一向に意に
介さないでいたりすることのほうがよっぽどガサツである。そんなガサツさよりは、社会人として
最低限必要な厳しさとしての、克服可能な不遇に対する同情の抑制のほうを講じて行くべきである。
接ぎ木ではなく、種から生えた芽としてこれから育って行かねばならないものがあったとして、
「まだまだこれからだ」というような叱咤激励をかけてやるのが水遣りに相当するとすれば、
「大変だねえ」などと同情ばかりをかけるのは芽を無理に伸ばしたりすることに相当するといえる。
前者は成長を促す一方、後者はかえって芽を立ち枯れにさせる原因にすらなってしまう。これから
育って行こうとする芽に対する適切な助成のためにも、不埒な同情などは禁物なのである。
「災いを救いて鄰りを恤れむは道なり。道を行えば福有り」
「災いからの救いを企図し、隣りの被害者を憐れむのは道である。道を行えば福徳にも与れる。
(災いへの救助支援や憐憫は確かに人道に適っている。人道に適わなければこそ福もない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・僖公十三年より)
ひけらかしての人気取りなどは非とされて来た。特に、妾腹の私生児のような克服のしようの
ある不遇で同情を買おうなどとする人間には「甘ったれんな」という冷たい視線が注がれた。
それは別に間違ったことでもない、世界的に通用させても何ら問題のない常識的措置なのであり、
それにすら耐えられないなんていう薄弱者こそは社会的立場を追われたとしても仕方がないのである。
それが「ガサツ」だったりするのでもない。どちらかといえば、己れの精神の薄弱さのあまり
私利私益ばかりをむさぼって、遠方の他人を困窮や餓死にまで追い込んでおきながら、一向に意に
介さないでいたりすることのほうがよっぽどガサツである。そんなガサツさよりは、社会人として
最低限必要な厳しさとしての、克服可能な不遇に対する同情の抑制のほうを講じて行くべきである。
接ぎ木ではなく、種から生えた芽としてこれから育って行かねばならないものがあったとして、
「まだまだこれからだ」というような叱咤激励をかけてやるのが水遣りに相当するとすれば、
「大変だねえ」などと同情ばかりをかけるのは芽を無理に伸ばしたりすることに相当するといえる。
前者は成長を促す一方、後者はかえって芽を立ち枯れにさせる原因にすらなってしまう。これから
育って行こうとする芽に対する適切な助成のためにも、不埒な同情などは禁物なのである。
「災いを救いて鄰りを恤れむは道なり。道を行えば福有り」
「災いからの救いを企図し、隣りの被害者を憐れむのは道である。道を行えば福徳にも与れる。
(災いへの救助支援や憐憫は確かに人道に適っている。人道に適わなければこそ福もない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——春秋左氏伝・僖公十三年より)
妾腹の私生児程度の不遇は、実際に孔子のように克服ができるものでもあるわけだから、
その不遇からなる悲哀にかられての暴発に及んで、非業の最期を辿ったことなどに
「聖性」を見出せたりするようなことも、決してないわけである。
そんなものに聖性を見出すような界隈があったとすれば、そんな界隈全体が一人前の
社会人としてやっていくにも値しない重度の精神薄弱者の集いであることが確かである。
実際、そのような持て囃すべきでないものを持て囃す慣習を持つ薄弱者の界隈である
キリスト教圏こそは、世界中にガン細胞並みの有害無益な悪影響ばかりを撒き散らし続けてもいる。
他者の不運や危難を憐れむ心、いわゆる「惻隠の情」それ自体は道理に適ったものである。(>>264の引用参照)
ただ、同情をかけるべき相手とそうでない相手とを分別するのもまた、一つの道理である。
人間の心に内在する本性としての善性を完全に見失っての悪逆非道に及んだ挙句、自業自得の
自滅に見舞われてしまったような人間にまで同情をかけたりはしないのも、一つの道義的措置である。
そんな人間に同情をかけて救ってやったりした所で、何も懲りることなしにまた同じ過ちを
繰り返すことになるだけなのだから、あえて同情もかけず、救いも講じないでいるべきなのである。
己れの善性ごと心を見失っているような人間を心から矯正して行くのも不可能なことであり、
常人並みの品性に立ち戻るまでは実力での矯正が必要となることもまた、すでに述べた通りである。
(>>245-251あたりの論議を参照)
故に、「地獄」と表現されるような状況もまた、必要悪たり得ることがあるわけである。
仏教などでは、地獄をあくまで心象の一つとして捉えているけれども、実際に社会上で酷烈な処罰だとか
社会的制限だとかを講じることがあるとすれば、そのような実力行使が処理対象となる人間にとっての
「地獄」となったりもするわけである。そのような地獄こそは、やはりどうしても必要となる場合がある。
その不遇からなる悲哀にかられての暴発に及んで、非業の最期を辿ったことなどに
「聖性」を見出せたりするようなことも、決してないわけである。
そんなものに聖性を見出すような界隈があったとすれば、そんな界隈全体が一人前の
社会人としてやっていくにも値しない重度の精神薄弱者の集いであることが確かである。
実際、そのような持て囃すべきでないものを持て囃す慣習を持つ薄弱者の界隈である
キリスト教圏こそは、世界中にガン細胞並みの有害無益な悪影響ばかりを撒き散らし続けてもいる。
他者の不運や危難を憐れむ心、いわゆる「惻隠の情」それ自体は道理に適ったものである。(>>264の引用参照)
ただ、同情をかけるべき相手とそうでない相手とを分別するのもまた、一つの道理である。
人間の心に内在する本性としての善性を完全に見失っての悪逆非道に及んだ挙句、自業自得の
自滅に見舞われてしまったような人間にまで同情をかけたりはしないのも、一つの道義的措置である。
そんな人間に同情をかけて救ってやったりした所で、何も懲りることなしにまた同じ過ちを
繰り返すことになるだけなのだから、あえて同情もかけず、救いも講じないでいるべきなのである。
己れの善性ごと心を見失っているような人間を心から矯正して行くのも不可能なことであり、
常人並みの品性に立ち戻るまでは実力での矯正が必要となることもまた、すでに述べた通りである。
(>>245-251あたりの論議を参照)
故に、「地獄」と表現されるような状況もまた、必要悪たり得ることがあるわけである。
仏教などでは、地獄をあくまで心象の一つとして捉えているけれども、実際に社会上で酷烈な処罰だとか
社会的制限だとかを講じることがあるとすれば、そのような実力行使が処理対象となる人間にとっての
「地獄」となったりもするわけである。そのような地獄こそは、やはりどうしても必要となる場合がある。
己れの心を見失ってまでの悪逆非道に走っているような人間がいれば、そのような人間に対して
特定的に施すべきものとしての酷烈な刑罰などが必要となるし、妾腹の私生児の暴発死ごときに同情を
抱いてしまうような精神縛弱者がいたとすれば、これまたそのような人間に特定的に施すべきものとしての
行為能力制限だとかが必要ともなる。これらこそは、実社会に到来する必要悪としての地獄だといえる。
地獄自体は必要悪であり、地獄を招かざるを得なくなるようなならず者の悪逆非道こそは不必要悪である。
そのようなならず者の活動を活発化させる教条などがあったとすれば、これこそは地獄の到来以上にも
不必要で有害無益な邪教であったことが確実であり、地獄の仕打ちを怨むとしても、地獄そのものではなく
そのような邪教こそを怨まねばならない。むしろそのような邪教こそは、言葉巧みに信者をたぶらかして
一時的にいい思いをさせてやったりもしたわけだが、それでも、そこにこそ地獄を招く元凶があったのだ
ということをわきまえて、全ての罪責はそこにばかりあったのだということを承っていかねばならない。
そんなものに依存してしまった自分こそは、救いようのない馬鹿だったことを認めねばならない。
「一隅を挙げるに三隅を以って反さざれば、則ち復せざるなり」
「一つの物事を挙げれば、それに三つの答えを返してくるぐらいの者でなければ、繰り返し物事を
教えてやるには値しない。(一度きりで満足という慢心の非。新井白石もキリシタンの形而上学が
一世代上止まりで、二世代や三世代上の形而上への想定を全く欠いていることを非難した)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・述而第七・八より)
特定的に施すべきものとしての酷烈な刑罰などが必要となるし、妾腹の私生児の暴発死ごときに同情を
抱いてしまうような精神縛弱者がいたとすれば、これまたそのような人間に特定的に施すべきものとしての
行為能力制限だとかが必要ともなる。これらこそは、実社会に到来する必要悪としての地獄だといえる。
地獄自体は必要悪であり、地獄を招かざるを得なくなるようなならず者の悪逆非道こそは不必要悪である。
そのようなならず者の活動を活発化させる教条などがあったとすれば、これこそは地獄の到来以上にも
不必要で有害無益な邪教であったことが確実であり、地獄の仕打ちを怨むとしても、地獄そのものではなく
そのような邪教こそを怨まねばならない。むしろそのような邪教こそは、言葉巧みに信者をたぶらかして
一時的にいい思いをさせてやったりもしたわけだが、それでも、そこにこそ地獄を招く元凶があったのだ
ということをわきまえて、全ての罪責はそこにばかりあったのだということを承っていかねばならない。
そんなものに依存してしまった自分こそは、救いようのない馬鹿だったことを認めねばならない。
「一隅を挙げるに三隅を以って反さざれば、則ち復せざるなり」
「一つの物事を挙げれば、それに三つの答えを返してくるぐらいの者でなければ、繰り返し物事を
教えてやるには値しない。(一度きりで満足という慢心の非。新井白石もキリシタンの形而上学が
一世代上止まりで、二世代や三世代上の形而上への想定を全く欠いていることを非難した)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・述而第七・八より)
イエスも甘ったれだし、そこに付いて行こうとした信者も甘ったれでしかない。
一人前の社会人としてやって行く上での、最低限の厳しさも受け付けられなかった甘ったれ。
地球規模での大罪を犯したのも、あくまでその結果に過ぎないであって、本質的な問題は、
社会人としてやって行くにも値しない甘ったれにすら権能を与えようとした所にこそある。
一人前の社会人としてやって行く上での、最低限の厳しさも受け付けられなかった甘ったれ。
地球規模での大罪を犯したのも、あくまでその結果に過ぎないであって、本質的な問題は、
社会人としてやって行くにも値しない甘ったれにすら権能を与えようとした所にこそある。
「願わくは善を伐ることなく、労を施すこと無けん(既出)」
「願わくは自らの善行を誇ることなく、他人に労役を課すようなこともないようにしたい」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・公冶長第五・二六より)
「勲労有るを挾みて問うは、〜皆な答えざる所なり」
「自分の仕事の功労を鼻にかけるような無礼者は、その質問に答えてやるにも値しない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句上・四三より)
俺も皮肉で自分の無為自然を誇ったりしてるがな。
いずれも今の世の中では全くわきまえられていない道徳的教条だといえる。
働いてなんぼ、働かせてなんぼなんてのは、道家思想だけでなく、
人間道徳上の勧善懲悪志向にも完全にもとっているのだ。
「願わくは自らの善行を誇ることなく、他人に労役を課すようなこともないようにしたい」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・公冶長第五・二六より)
「勲労有るを挾みて問うは、〜皆な答えざる所なり」
「自分の仕事の功労を鼻にかけるような無礼者は、その質問に答えてやるにも値しない」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句上・四三より)
俺も皮肉で自分の無為自然を誇ったりしてるがな。
いずれも今の世の中では全くわきまえられていない道徳的教条だといえる。
働いてなんぼ、働かせてなんぼなんてのは、道家思想だけでなく、
人間道徳上の勧善懲悪志向にも完全にもとっているのだ。
聖書圏には、仁義道徳と、あと無為自然の徳に対する察知や理解が全く存在しない。
どちらかといえば、無為自然の徳に対する了解こそが全く欠けている。だからこそ、
人々が絶え間ない焦燥やルサンチマンにまみれた状態とも化してしまっている。
妾腹の私生児といえども、孔子のように社会的な大成を果たすことができる。
そこまでいかずとも、卑賤の身の上を恥じて安静を決め込んですらいたならば、暴発して
邪教を触れ回ったりするよりは、よっぽどマシな存在でいられるとはすでに述べたことである。
(道家の見地からすれば、そのほうが社会的大成以上にも上等なこととすらされる)
無為自然の徳を解さないことが、無根拠な劣等意識や嫉妬の原因ともなる。
「悪いことをするぐらいなら何もしないでいたほうがマシ」という事実関係をわきまえられて
すらいたなら、悪逆非道な犯罪稼業によって暴利を巻き上げてやりたい放題でいるような
畜生野郎などに対しては、当たり前なこととしての侮蔑意識を抱いたりするものである。
しかし、上記のような事実関係へのわきまえを欠いていたならば、なりふり構わぬ稼ぎで
富裕となっているような者に対する劣等感や羨望すらをも抱いてしまいかねないのである。
世界中の億万長者を「世界の偉人ランキング」の上位に並べ立ている欧米の経済誌なども、
無為自然の徳を全く解さない聖書信仰的な価値観に即して発行されているものである。
そんな連中はむしろ「世界の賤人ランキング」の上位にこそはべらせなければならないと、
無為自然の徳を解するものであれば考える。ただそう考えるだけでなく、それによって
賤人ランキングの上位者を心からの笑いものの対象として行きもする。
小百姓の末子や下級役人だった頃の高祖劉邦なども、そのような「いるよりも
いないほうがマシな権力者に対する心からの侮蔑意識」を抱いていたのである。
だからこそ、当時すでに相当な富豪でもあった呂氏のVIP御用達の宴会などにも
無一文で乗り込んで、好き勝手に飲食するなどの豪快な振る舞いにも及んでいたのだった。
そして、その豪放さをそのまま押し通した挙句に中華皇帝にまでのし上がった。
画像削除(by投稿者)
どちらかといえば、無為自然の徳に対する了解こそが全く欠けている。だからこそ、
人々が絶え間ない焦燥やルサンチマンにまみれた状態とも化してしまっている。
妾腹の私生児といえども、孔子のように社会的な大成を果たすことができる。
そこまでいかずとも、卑賤の身の上を恥じて安静を決め込んですらいたならば、暴発して
邪教を触れ回ったりするよりは、よっぽどマシな存在でいられるとはすでに述べたことである。
(道家の見地からすれば、そのほうが社会的大成以上にも上等なこととすらされる)
無為自然の徳を解さないことが、無根拠な劣等意識や嫉妬の原因ともなる。
「悪いことをするぐらいなら何もしないでいたほうがマシ」という事実関係をわきまえられて
すらいたなら、悪逆非道な犯罪稼業によって暴利を巻き上げてやりたい放題でいるような
畜生野郎などに対しては、当たり前なこととしての侮蔑意識を抱いたりするものである。
しかし、上記のような事実関係へのわきまえを欠いていたならば、なりふり構わぬ稼ぎで
富裕となっているような者に対する劣等感や羨望すらをも抱いてしまいかねないのである。
世界中の億万長者を「世界の偉人ランキング」の上位に並べ立ている欧米の経済誌なども、
無為自然の徳を全く解さない聖書信仰的な価値観に即して発行されているものである。
そんな連中はむしろ「世界の賤人ランキング」の上位にこそはべらせなければならないと、
無為自然の徳を解するものであれば考える。ただそう考えるだけでなく、それによって
賤人ランキングの上位者を心からの笑いものの対象として行きもする。
小百姓の末子や下級役人だった頃の高祖劉邦なども、そのような「いるよりも
いないほうがマシな権力者に対する心からの侮蔑意識」を抱いていたのである。
だからこそ、当時すでに相当な富豪でもあった呂氏のVIP御用達の宴会などにも
無一文で乗り込んで、好き勝手に飲食するなどの豪快な振る舞いにも及んでいたのだった。
そして、その豪放さをそのまま押し通した挙句に中華皇帝にまでのし上がった。
画像削除(by投稿者)
▲ページ最上部
ログサイズ:696 KB 有効レス数:321 削除レス数:0
不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。
思想・哲学掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
スレッドタイトル:聖書 Part9
