サイズが 480KB を超えています。500KB を超えると書きこめなくなるよ。
聖書 Part9
▼ページ最下部
地球人類社会において、四書五経こそは、ここ2500年の長きにわたって、わざわざ
特筆するまでもないほどに標準的な聖書としての、その地位を守り続けてきている。
その理由は、四書五経が「社会統治の聖書」であるからで、その他の用途に
用いられる諸々の聖書一般と比べれば、書物活用の場でもある世の中全体を司る
聖書である点において、やはり別格級の存在意義を持っているからでこそある。
夏・殷・周の三代に渡る古代中国の治世のあり方を、春秋時代に孔子が五経として体系化し、
その孔子自身や弟子や亦弟子(孟子含む)の言説を取りまとめた四書がさらに朱子に
よって権威化された。両者を合わせて「四書五経」というが、四書五経は宋代に定型化された
儒学正典の代表書というまでのことで、これに漏れた「孝経」「周礼」「儀礼」「大載礼記」「国語」
などの儒書も、四書五経に勝るとも劣らない聖書として扱ってもまったく差し支えないもの
となっており、四書五経を含むこれら全ての聖書が、実際に天下国家全土における治世を
実現していく上でのマニュアルとなるに相応しいだけの、十分な度量を備えている。
実際に、当時世界最大規模の国力を誇った漢帝国や唐帝国や宋帝国、
死刑一つない治世を実験した平安朝や、識字率世界最高を誇った江戸の日本
などにおいて、四書五経に代表される儒学の聖書こそは、権力者から庶民に
至るまでの、「必須の教養」としての扱いを受け続けていたのだった。
四書五経の記述に基づくような治世が実現されて後に初めて興隆する、儒学以外の高度な文化
というものもまた別に多くあり、むしろそちらのほうが治世実現後の世の中における「花形」
としての扱いを受けたりもする。唐代における詩文芸の興隆や、宋代における禅仏教の興隆、
平安時代における密教文化や女流文芸の興隆、江戸時代における武芸文化や演劇文化の興隆などが
その好例であり、そのような人々を楽しませることにかけてより秀でている文化の興隆を実現する
「縁の下の力持ち」としての役割をも儒学は担って来たから、必ずしも目立つ存在ではなかった
せいで、あまり人々にその偉大さを意識されることすらないままでいることが多かったのだ。
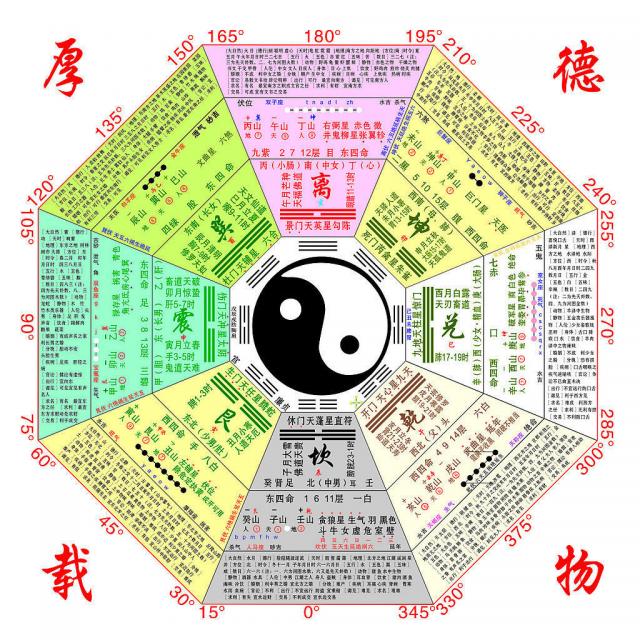
特筆するまでもないほどに標準的な聖書としての、その地位を守り続けてきている。
その理由は、四書五経が「社会統治の聖書」であるからで、その他の用途に
用いられる諸々の聖書一般と比べれば、書物活用の場でもある世の中全体を司る
聖書である点において、やはり別格級の存在意義を持っているからでこそある。
夏・殷・周の三代に渡る古代中国の治世のあり方を、春秋時代に孔子が五経として体系化し、
その孔子自身や弟子や亦弟子(孟子含む)の言説を取りまとめた四書がさらに朱子に
よって権威化された。両者を合わせて「四書五経」というが、四書五経は宋代に定型化された
儒学正典の代表書というまでのことで、これに漏れた「孝経」「周礼」「儀礼」「大載礼記」「国語」
などの儒書も、四書五経に勝るとも劣らない聖書として扱ってもまったく差し支えないもの
となっており、四書五経を含むこれら全ての聖書が、実際に天下国家全土における治世を
実現していく上でのマニュアルとなるに相応しいだけの、十分な度量を備えている。
実際に、当時世界最大規模の国力を誇った漢帝国や唐帝国や宋帝国、
死刑一つない治世を実験した平安朝や、識字率世界最高を誇った江戸の日本
などにおいて、四書五経に代表される儒学の聖書こそは、権力者から庶民に
至るまでの、「必須の教養」としての扱いを受け続けていたのだった。
四書五経の記述に基づくような治世が実現されて後に初めて興隆する、儒学以外の高度な文化
というものもまた別に多くあり、むしろそちらのほうが治世実現後の世の中における「花形」
としての扱いを受けたりもする。唐代における詩文芸の興隆や、宋代における禅仏教の興隆、
平安時代における密教文化や女流文芸の興隆、江戸時代における武芸文化や演劇文化の興隆などが
その好例であり、そのような人々を楽しませることにかけてより秀でている文化の興隆を実現する
「縁の下の力持ち」としての役割をも儒学は担って来たから、必ずしも目立つ存在ではなかった
せいで、あまり人々にその偉大さを意識されることすらないままでいることが多かったのだ。
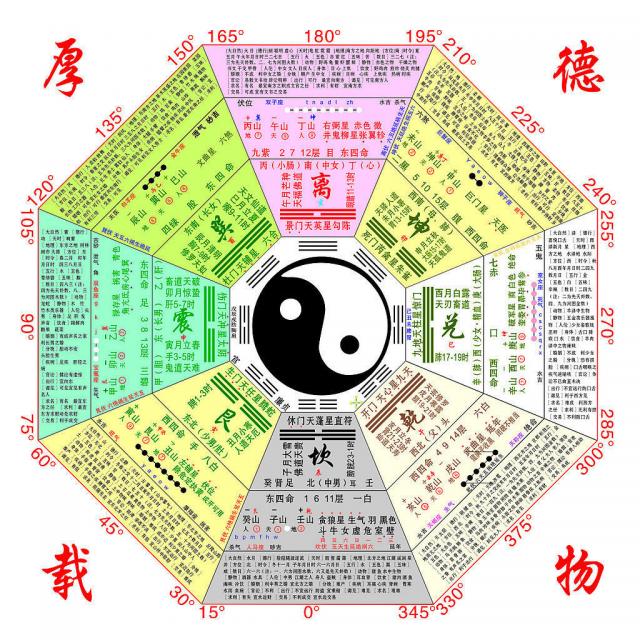
実際に、全世界を穏便に統治できる程もの度量があればこそ、儒学は治世実現後の世の中においてまで
そんなに自己主張に専らであったりしない。キリスト教なんざは、ただ世界征服を目指すだけで、
征服後の世の中はかえって最悪の争乱や破滅に陥れてばかりだから、そんな度量は一切持てず、
「征服したことに意義があった」みたいながなり立てを行うことで、自分たちの有害無益さ
に対する文句を騒音によって打ち消すことを、延々と試み続けていかなければならない。
儒学は決してそんなことはなく、その教学の優良さによって、着実に世の中をマシ以上な
治世へと導いて行くから、治世実現後には殊更な自己主張も控えて、乱世再来を防ぎ止める
ための義務的な儒学の勉強を人々に促す程度の粛々とした態度でいるようになるのである。
自分たちが縁の下からクリエートする世の中こそは最大級の治世をも獲得できるのだから、
儒者が自分たちから理念面での社会統治者としての立場を譲ったりすることを是とするわけもない。
法家心酔者の始皇帝に生き埋めにされた儒者や、乱世の荒波に飲まれて打ち首にされた吉田松陰などが、
儒学による社会統治の譲渡などを進んで容認していたような事実も当然ないわけで、儒学に基づく
統治が叶わない世の中において、仕方なく外野に甘んじるということはあっても、決して好き好んで
治世の企画者としての自分たちの立場が追われることなどを欲していたりはしないのである。
「滅国を興し、絶世を継ぎ、逸民を挙げれば、天下の民、心を帰せん」
「すでに滅びたような国も興し、絶えた家も受け継がせて、世捨て人も取り上げるようにすれば、
天下の人々もみな心から帰服するだろう。(乱世の支配者としての立場を受け継いだりするよりは、
乱世のせいで絶えてしまったような家を受け継いで復興させていくほうが、遥かに重要であろう。
ちなみにこれは周代の言葉であり、この直前に乱世をもたらしてしまった殷朝が滅亡している)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・堯曰第二十・二より)
そんなに自己主張に専らであったりしない。キリスト教なんざは、ただ世界征服を目指すだけで、
征服後の世の中はかえって最悪の争乱や破滅に陥れてばかりだから、そんな度量は一切持てず、
「征服したことに意義があった」みたいながなり立てを行うことで、自分たちの有害無益さ
に対する文句を騒音によって打ち消すことを、延々と試み続けていかなければならない。
儒学は決してそんなことはなく、その教学の優良さによって、着実に世の中をマシ以上な
治世へと導いて行くから、治世実現後には殊更な自己主張も控えて、乱世再来を防ぎ止める
ための義務的な儒学の勉強を人々に促す程度の粛々とした態度でいるようになるのである。
自分たちが縁の下からクリエートする世の中こそは最大級の治世をも獲得できるのだから、
儒者が自分たちから理念面での社会統治者としての立場を譲ったりすることを是とするわけもない。
法家心酔者の始皇帝に生き埋めにされた儒者や、乱世の荒波に飲まれて打ち首にされた吉田松陰などが、
儒学による社会統治の譲渡などを進んで容認していたような事実も当然ないわけで、儒学に基づく
統治が叶わない世の中において、仕方なく外野に甘んじるということはあっても、決して好き好んで
治世の企画者としての自分たちの立場が追われることなどを欲していたりはしないのである。
「滅国を興し、絶世を継ぎ、逸民を挙げれば、天下の民、心を帰せん」
「すでに滅びたような国も興し、絶えた家も受け継がせて、世捨て人も取り上げるようにすれば、
天下の人々もみな心から帰服するだろう。(乱世の支配者としての立場を受け継いだりするよりは、
乱世のせいで絶えてしまったような家を受け継いで復興させていくほうが、遥かに重要であろう。
ちなみにこれは周代の言葉であり、この直前に乱世をもたらしてしまった殷朝が滅亡している)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——論語・堯曰第二十・二より)
えらく高評価だけど、本家である中国がなぜこの体たらく?
ヴァカにかまうと。。。><
「体たらく」も何も、完全に実力で世界を席巻しにかかってんじゃねえか。
ただ、そのあり方が今の日本などにとっては好ましくないだけで。
「国際協調」なんてものが単なる偽善に過ぎないことも、
中国人は長年の実地経験から知り抜いている。
諸国を統べる帝王を立てないことには、国同士での仲良しや仲違いが、
政商や縦横家にとっての格好の餌食になるだけでしかないとも知っている。
そうとも知らず、日米安保なんかに頼りきりでいる今の日本のほうが、
現実の外交セオリーを全く解さない愚か者の集まりとなっている。
ただ、そのあり方が今の日本などにとっては好ましくないだけで。
「国際協調」なんてものが単なる偽善に過ぎないことも、
中国人は長年の実地経験から知り抜いている。
諸国を統べる帝王を立てないことには、国同士での仲良しや仲違いが、
政商や縦横家にとっての格好の餌食になるだけでしかないとも知っている。
そうとも知らず、日米安保なんかに頼りきりでいる今の日本のほうが、
現実の外交セオリーを全く解さない愚か者の集まりとなっている。
職種別の社会的な害益の度合いでいえば、
君子士人(権力道徳者)>農業従事者≧必需工業従事者>無職≒0>ガラクタ工業従事者≧商業従事者>犯罪者>権力犯罪者
(0以上は世の中にとって有益無害、0以下は世の中にとって有害無益)
で、人としての貴さについても、この不等号に基づく順列が当てはまる。
社会的な常駐が倫理的に許されないのは犯罪者と権力犯罪者で、これらは一方的な撲滅の対象となる。
常駐が禁止まではされないが、色々と社会的な制限を受けなければならないのがガラクタ工業従事者と商業従事者で、
これらも放任が過ぎると犯罪者並みの害悪をもたらす場合がある(特に商売人が政商として権力犯罪に走る場合が多い)。
社会的な制限どころか、保護すらされて然るべきなのが農業従事者や必需工業従事者で、国を挙げてのそれらの
事業の振興が、着実な国力の発達にも結び付く。古来から重農主義であり続けてきた日本や中国などの東洋諸国が、
重商主義であり続けてきた西洋との経済競争で優位に立てたのも、そのような根本からの国力の養生があったればこそ。
君子士人は、上記のような措置を講ずる世の中の統治者たち自身のことであり、その働きが見事で
あったからには、それこそ神さま仏さまに準ずるほどもの畏敬の対象とされていかなければならない。
社会的に言って、有益無害の極致と有害無益の極致に該当するのが、権力道徳者(君子士人)と権力犯罪者であり、
片や神仏にも準ずる尊重の対象とされるべきである一方、片や最底辺の下流(子張第十九・二〇)として賤しむべき存在である。
全くの即物的な概算に基づいて生ずる貴賤の隔絶なのだから、これを迷信的な判断などとして退ける余地も、どこにもないといえる。
君子士人(権力道徳者)>農業従事者≧必需工業従事者>無職≒0>ガラクタ工業従事者≧商業従事者>犯罪者>権力犯罪者
(0以上は世の中にとって有益無害、0以下は世の中にとって有害無益)
で、人としての貴さについても、この不等号に基づく順列が当てはまる。
社会的な常駐が倫理的に許されないのは犯罪者と権力犯罪者で、これらは一方的な撲滅の対象となる。
常駐が禁止まではされないが、色々と社会的な制限を受けなければならないのがガラクタ工業従事者と商業従事者で、
これらも放任が過ぎると犯罪者並みの害悪をもたらす場合がある(特に商売人が政商として権力犯罪に走る場合が多い)。
社会的な制限どころか、保護すらされて然るべきなのが農業従事者や必需工業従事者で、国を挙げてのそれらの
事業の振興が、着実な国力の発達にも結び付く。古来から重農主義であり続けてきた日本や中国などの東洋諸国が、
重商主義であり続けてきた西洋との経済競争で優位に立てたのも、そのような根本からの国力の養生があったればこそ。
君子士人は、上記のような措置を講ずる世の中の統治者たち自身のことであり、その働きが見事で
あったからには、それこそ神さま仏さまに準ずるほどもの畏敬の対象とされていかなければならない。
社会的に言って、有益無害の極致と有害無益の極致に該当するのが、権力道徳者(君子士人)と権力犯罪者であり、
片や神仏にも準ずる尊重の対象とされるべきである一方、片や最底辺の下流(子張第十九・二〇)として賤しむべき存在である。
全くの即物的な概算に基づいて生ずる貴賤の隔絶なのだから、これを迷信的な判断などとして退ける余地も、どこにもないといえる。
聖書信仰はこの、即物的な観点に即して最悪級の賤しさを帯びる「権力犯罪」という所業の推進を企図したもので、
それにより「ただの犯罪者は救われないが、自分たちに限っては救われる」という事態の実現を目指した。
権力犯罪を推し進めることでこそ、ただの犯罪者のような断罪の対象にはさせないという暴挙の押し通し、
それも確かに多少は通じることもあったが、最終的には絶対に通じなくなる。そして本当に通じなくなったのが、今。
この頃まで権力道徳の認知も覚束ないでいた極西の部落社会で、権力道徳の対極であるが故に劣悪な所業の極みでもあることが
明らかとなる、権力犯罪の存在性もまた即物的には察知されることがなかった。その故に、そこに宗教的な幻想までをも抱いて、
権力犯罪を推進すればこそ、ただの犯罪者は罪になっても、自分たちは罪を免れられるかのような妄想にも陥ってしまった。
そのような連中によってこそ捏造されたのが新旧約聖書で、即物的な観点に基づけば、それは「権力犯罪聖書」だとも言える。
民間犯罪以上にも害悪度の極まる権力犯罪を推進するための聖書だったのだから、当然それが免罪の対象となるわけもない。
そうだと知ってて信仰や実践したのなら極刑の対象にすらなるし、そうとも知らず信仰や実践をしてしまったのだとしても、
十分な反省や活動自粛などが必須となる。幻想を晴らして即物性に帰ればこそ、そうせざるを得ないと断じるほかはない。
「即物性に過ぎる宗教こそはカルト」みたいな物言いがされることもあるが、むしろ即物的な観点に即して不正である
宗教こそが特筆してカルトであり、即物的に見て問題がない宗教こそは正統である。宗教と即物性を乖離させようとするのも
カルトの策謀であり、むしろ正統な宗教こそは、カネやモノへの取り扱いに対する監査を恐れたりする必要もないのである。
それにより「ただの犯罪者は救われないが、自分たちに限っては救われる」という事態の実現を目指した。
権力犯罪を推し進めることでこそ、ただの犯罪者のような断罪の対象にはさせないという暴挙の押し通し、
それも確かに多少は通じることもあったが、最終的には絶対に通じなくなる。そして本当に通じなくなったのが、今。
この頃まで権力道徳の認知も覚束ないでいた極西の部落社会で、権力道徳の対極であるが故に劣悪な所業の極みでもあることが
明らかとなる、権力犯罪の存在性もまた即物的には察知されることがなかった。その故に、そこに宗教的な幻想までをも抱いて、
権力犯罪を推進すればこそ、ただの犯罪者は罪になっても、自分たちは罪を免れられるかのような妄想にも陥ってしまった。
そのような連中によってこそ捏造されたのが新旧約聖書で、即物的な観点に基づけば、それは「権力犯罪聖書」だとも言える。
民間犯罪以上にも害悪度の極まる権力犯罪を推進するための聖書だったのだから、当然それが免罪の対象となるわけもない。
そうだと知ってて信仰や実践したのなら極刑の対象にすらなるし、そうとも知らず信仰や実践をしてしまったのだとしても、
十分な反省や活動自粛などが必須となる。幻想を晴らして即物性に帰ればこそ、そうせざるを得ないと断じるほかはない。
「即物性に過ぎる宗教こそはカルト」みたいな物言いがされることもあるが、むしろ即物的な観点に即して不正である
宗教こそが特筆してカルトであり、即物的に見て問題がない宗教こそは正統である。宗教と即物性を乖離させようとするのも
カルトの策謀であり、むしろ正統な宗教こそは、カネやモノへの取り扱いに対する監査を恐れたりする必要もないのである。
「殷民に辟在りて、予れを辟せよと曰うも、爾じ惟れを辟する勿れ。予れを宥せと曰うも、爾じ惟れを宥す勿れ、
惟れ厥の中をせよ。汝の政に若わず、汝の訓えに化せざること有らば、辟して以て止めよ。辟あらば乃ち辟せよ」
「民の内に罪を犯した者が有った場合、本人が有罪を認めたからといって重罰を科すのでも、無罪を主張するから
といって罰を科さないのでもいけない。常に中正を心がけ、おまえ自身の為政に従わず、教化に服さないことが
あれば、それこそを罰して過ちを未然に食い止めよ。それでも罪を犯した者がいれば、厳酷な罰を科すがいい。
(罪の有無や科刑の軽重は正式な為政者こそが自主性を以って判断すべきことであり、干渉の余地はどこにもない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・君陳より)
惟れ厥の中をせよ。汝の政に若わず、汝の訓えに化せざること有らば、辟して以て止めよ。辟あらば乃ち辟せよ」
「民の内に罪を犯した者が有った場合、本人が有罪を認めたからといって重罰を科すのでも、無罪を主張するから
といって罰を科さないのでもいけない。常に中正を心がけ、おまえ自身の為政に従わず、教化に服さないことが
あれば、それこそを罰して過ちを未然に食い止めよ。それでも罪を犯した者がいれば、厳酷な罰を科すがいい。
(罪の有無や科刑の軽重は正式な為政者こそが自主性を以って判断すべきことであり、干渉の余地はどこにもない)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——書経・周書・君陳より)
男女関係でいえば、夫唱婦随であるほうが子宝にも恵まれて家庭円満でもいられたりする一方、
カカア天下のほうは女が多産を嫌がったり、家族関係が険悪化したりと色々な問題を生じさせてしまう。
それは、本質的な自律者である男が、依存者である女を十分な主導下に置くことが本末の正立となる一方、
依存者である女が主導的となることが本末の転倒になってしまうからで、それ以上に不思議な理由などはない。
車にしろ船にしろ、一方向に前進しやすいように作られるのが基本で、バックも一応はできるにしても、
一時的な後退だけを念頭に置いていて、常にバック走行し続けることなどを念頭においてはいない。
特殊な構造でもない自転車やバイクなどは、足をつかなければバックはできないようになっているし、
飛行機にいたっては飛行中のバックからして不可能で、エンジンの逆回転なども着陸時のブレーキなどと
してのみ用いられる。そして、こんな乗り物の例などを挙げるまでもなく、人間自身の身体構造からして
眼前に向かって前進していくことが歩行の基本となるようにできている。身体構造がクラゲやウニのような
全方向的な構造にはなっていないから、その人間が乗用することを目的とした乗り物なども自然と、
一方向に向かって進むことが便利となるように設計されていくようになっている。
夫唱婦随が人間自身や乗り物の前進であるなら、カカア天下は後退であるといえ、飛行機でもない限りは
後退だってできなくはないが、常に後退し続ける状態でいたのでは、人間や車や船といえども無理を来たすもの。
男女関係に限らずとも、一方が自律者でもう一方が依存者であるような関係が本末正立的であったり本末転倒的で
あったりすることは、人間や乗り物の前進や後退に譬えられるもので、後退が絶対に不可能なことでまであるとは
限らないにしても、常に後退をし続けるのでは無理を来たすという法則もまた、そのまま当てはまるのである。
カカア天下のほうは女が多産を嫌がったり、家族関係が険悪化したりと色々な問題を生じさせてしまう。
それは、本質的な自律者である男が、依存者である女を十分な主導下に置くことが本末の正立となる一方、
依存者である女が主導的となることが本末の転倒になってしまうからで、それ以上に不思議な理由などはない。
車にしろ船にしろ、一方向に前進しやすいように作られるのが基本で、バックも一応はできるにしても、
一時的な後退だけを念頭に置いていて、常にバック走行し続けることなどを念頭においてはいない。
特殊な構造でもない自転車やバイクなどは、足をつかなければバックはできないようになっているし、
飛行機にいたっては飛行中のバックからして不可能で、エンジンの逆回転なども着陸時のブレーキなどと
してのみ用いられる。そして、こんな乗り物の例などを挙げるまでもなく、人間自身の身体構造からして
眼前に向かって前進していくことが歩行の基本となるようにできている。身体構造がクラゲやウニのような
全方向的な構造にはなっていないから、その人間が乗用することを目的とした乗り物なども自然と、
一方向に向かって進むことが便利となるように設計されていくようになっている。
夫唱婦随が人間自身や乗り物の前進であるなら、カカア天下は後退であるといえ、飛行機でもない限りは
後退だってできなくはないが、常に後退し続ける状態でいたのでは、人間や車や船といえども無理を来たすもの。
男女関係に限らずとも、一方が自律者でもう一方が依存者であるような関係が本末正立的であったり本末転倒的で
あったりすることは、人間や乗り物の前進や後退に譬えられるもので、後退が絶対に不可能なことでまであるとは
限らないにしても、常に後退をし続けるのでは無理を来たすという法則もまた、そのまま当てはまるのである。
自律的な者と依存的な者との関係を、夫唱婦随のような良好な関係とするための道具となるのが上下の序列で、
上位に置かれた自律者が下位に置かれた依存者を一方的な統制の対象とする上での、増強剤的な役割を果たす。
別に、車をバックで走行させ続けるようなほどものカカア天下的な悪癖が根付いてしまっている
のでもない限りは、上下関係のあてがいによる夫唱婦随への矯正までをも必要とはしないわけで、
むしろ依存者こそが自意識過剰によってわがままを甚大化させてしまっているような所でこそ、
自律者と依存者との間に上下関係をあてがうことまでもが必要となってしまうのである。
無闇に上下関係をあてがったりするよりも、「自律者と依存者の関係は夫唱婦随が正則、カカア天下が逆則」
という認識を広めていくことのほうがあって然るべきで、それにより、車を前進させること程にも夫唱婦随を
当たり前なこととして受け止め、延々とバックさせ続けること程にもカカア天下を異常なこととして受け止める
ようになれば、わざわざ上下関係を徹底してまで夫唱婦随を強制したりする必要もなくなるのである。
「自律者と依存者の関係は夫唱婦随が正則、カカア天下が逆則」
これは、ただそうであるというまでのことで、そこにまで疑問を唱えたとしても仕方のないこと。
それはあたかも、「なぜ車はバックし続けるように作られていないのか」という疑問を抱くことに
大した意味がないのと同じようなもので、夫唱婦随であるべき人間関係も、丸ごと一つの車であるようなもの。
男女関係も一つの車、父子関係や君臣関係、官民関係なども一つの車。そこに主従の転倒をあてがったりするのは、
前進する目的で作られている車にバックを強要し続けるような暴挙になってしまうと考えたならば、
いかにそのような試みが不毛なものでしかないことかもまた、明らかになるだろう。
「所謂西伯善く老を養うとは、其の田里を制して之れに樹畜を教え、其の妻子を導きて其の老を養わしむればなり」
「『文王はよく老人を養った』とあるが、これは文王が田地を整理して人々に植樹や牧畜の行い方まで教え、
それぞれの妻子までをも老人への養護に務めるように導いたからである。(本人の優遇ではなく、善行へと導いた)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句上・二二より)
上位に置かれた自律者が下位に置かれた依存者を一方的な統制の対象とする上での、増強剤的な役割を果たす。
別に、車をバックで走行させ続けるようなほどものカカア天下的な悪癖が根付いてしまっている
のでもない限りは、上下関係のあてがいによる夫唱婦随への矯正までをも必要とはしないわけで、
むしろ依存者こそが自意識過剰によってわがままを甚大化させてしまっているような所でこそ、
自律者と依存者との間に上下関係をあてがうことまでもが必要となってしまうのである。
無闇に上下関係をあてがったりするよりも、「自律者と依存者の関係は夫唱婦随が正則、カカア天下が逆則」
という認識を広めていくことのほうがあって然るべきで、それにより、車を前進させること程にも夫唱婦随を
当たり前なこととして受け止め、延々とバックさせ続けること程にもカカア天下を異常なこととして受け止める
ようになれば、わざわざ上下関係を徹底してまで夫唱婦随を強制したりする必要もなくなるのである。
「自律者と依存者の関係は夫唱婦随が正則、カカア天下が逆則」
これは、ただそうであるというまでのことで、そこにまで疑問を唱えたとしても仕方のないこと。
それはあたかも、「なぜ車はバックし続けるように作られていないのか」という疑問を抱くことに
大した意味がないのと同じようなもので、夫唱婦随であるべき人間関係も、丸ごと一つの車であるようなもの。
男女関係も一つの車、父子関係や君臣関係、官民関係なども一つの車。そこに主従の転倒をあてがったりするのは、
前進する目的で作られている車にバックを強要し続けるような暴挙になってしまうと考えたならば、
いかにそのような試みが不毛なものでしかないことかもまた、明らかになるだろう。
「所謂西伯善く老を養うとは、其の田里を制して之れに樹畜を教え、其の妻子を導きて其の老を養わしむればなり」
「『文王はよく老人を養った』とあるが、これは文王が田地を整理して人々に植樹や牧畜の行い方まで教え、
それぞれの妻子までをも老人への養護に務めるように導いたからである。(本人の優遇ではなく、善行へと導いた)」
(権力道徳聖書——通称四書五経——孟子・尽心章句上・二二より)
▲ページ最上部
ログサイズ:696 KB 有効レス数:321 削除レス数:0
不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。
思想・哲学掲示板に戻る 全部 次100 最新50
スレッドタイトル:聖書 Part9
