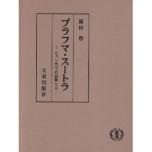まるで当たり前の事実であるかのように、「哲学発祥の地はギリシャ」だの、
「詩文学の発祥地もギリシャ」だのの、全くの思い違いが公然とまかり通り続けているが、
世界最古の本格的な詩文学は、ギリシャのホメロスなどではなく、インドのヴェーダであり、
そのヴェーダに注解を施す形式で編み出された「ウパニシャッド」こそは、
ギリシャ哲学よりも数百年程度は先んじて発祥した、世界最古の哲学にあたる。
古代中国の諸子百家が、政治行為などに関連する実際論に終始した素朴な「思想」止まりで
あったのに対し、ウパニシャッドは、理念に昇華された思索を重んじる純粋な「哲学」であり、
その内容も、「人類哲学の先駆け」としての存在性にも見合った、極めて上質なものとなっている。
その、哲学的根幹に値する「梵我一如」は、日本人などには、密教や禅などの仏教哲学を通じて
知られている場合が多いが、元はといえば、ヴェーダの解釈学でもあるウパニシャッドの根本教理であり、
ヴェーダの絶対的権威を否定した釈迦が説いた「諸法無我」とも決定的な相違を伴っている。
思索が「ネーティ、ネーティ(〜ではない、〜ではない)」と、否定を重畳していくことによって
アートマン(真我)を把捉し、そのアートマンこそは最高真理ブラフマン(梵)とも同一であるとみなす
ところなどは、「思索の構造が真我であったり梵であったりすることはない」ということを定立しているわけで、
思考が自我であることはウパニシャッドによっては否定されるため、「我れ思う、ゆえに我れあり」の
デカルトのコギト論も、ウパニシャッドによってとっくの昔に完全否定されていることになる。
ヘーゲルが、インド哲学批判の論拠とした「構造体系の欠如」も、「思考それ自体が真我であったり
梵であったりすることはない」という、明確な理念に即して徹底されていることであり、批判材料にはあたらない。
もちろん、思考の絶対性を否定するインド哲学の姿勢が、思考を絶対化する西洋哲学の価値を一切合切無効化
してしまうものだから、西洋哲学者などにとっては特に受け入れがたいものでもあるのだろうが、思考の絶対性を
否定するインドのウパニシャッド哲学こそは、全地球人類にとっての、哲学の源流であると共に本流でもある。

返信する