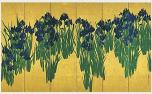地の利というのは、為政者が徳治を目的として考慮する場合もあり、それでこそ、
易学にも根ざした地相判断などによって、真に大局に根ざした地の利までもが考慮される。
古都京都の碁盤目状の街並みなどは、あらかじめ朝廷によって区画整理が行われたことで
成立したもので、よく整理が行き届いているものだから、商売人が目先の利益に
駆られて非効率な土地利用を企む余地なども予め絶やされている。
しかし、今の東京のように無秩序な街並みのままで置かれた都市もあるわけで、
このような都市構造では土地利権の吹き溜まりも発生しやすく、
商売人がこぞって出店争いを繰り広げるようなことにもなってしまう。
しかし、地方で区画整理や道路整備などの公共事業を推進する知事や市長などが当選しただけでも、
地元の商工組合が雇った(もしくは組合員自身が変装した)街宣右翼が官公庁に攻撃を仕掛けたりする。
商業権力からの報復を恐れて、今のほとんどの自治体の政治家も、商工組合の犬も同然の存在と
化しているが、土地利権で膨れ上がった商業権力の横暴を叩き伏せるのは生半なことではいかず、
江戸時代の武士ように、公権力者が武装によって商売人を制圧する必要までもが出てくる。
封建社会で、諸侯や大名が各種の商工業種を領有するのではなく、封土を領有するのも、
商工会が公権力の完全な制御下に置かれることで、「角を矯めて牛を殺す」ようなことになってしまうのを
防ぐためである一方で、商売人が目先の利益にかられて、非効率な土地利用を目論んだりすることまでは
許さないために、諸侯や大名による全土の領有を大義として、公権力による土地整理を必ず、
商売人の土地利用よりも優先させるためであったのだといえる。
封建社会の公権力者は、「小人こそは土地利権を私利私欲のために濫用する」という小人の性分をよく
見抜いた上で、その性分の許容による濁世の激化をも防止する目的で、封土を拝領していたのだいえる。
返信する